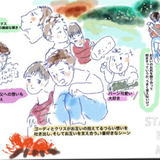コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全732件中、361~380件目を表示
邦題の大事さ❗️ジュニアさんありがとう🙏
ずっと気にはなっていたのに、中々劇場に足が向かなかった作品。たまたま「にけつッ‼︎」という地上波のバラエティ番組を観ていたら、千原ジュニアさんが洋画の邦題の付け方が変だ!という回でこの作品も話題にだしてました。それを機に、劇場公開中に絶対に観に行くぞという気になり観に行きました。結果は大成功❣️
原作は「Coda」のみで邦題では「あいのうた」がつきますが、この作品でいうとこれ以上にない絶妙な表現の邦題だと思う。
主人公の高校生ルビーが家族のなかで、唯一の健聴者。家族の仕事、生活に幼い頃から通訳として欠かせない存在。差別も受けながらも、歌が好きで家族思いの本当に心の強い良い子に成長していく。そんな時に学校の合唱サークルで顧問の先生に歌の才能を見出される。この先生役の演技がまた良いんです❣️しかし、ルビー以外の家族3人はろうあ者でもちろん歌を聴くことが出来ません。歌うことと家業の板挟みになるルビー。諦めて家業に専念する道を選ぼうとするが、家族が徐々に彼女の歌の才能に気付き始める。合唱部のコンサート。1分間くらいの無音のシーンがこの作品のなかでの最高インパクト。ろうあ者の家族がこんなふうに無音で我が娘の歌を聴いてるのかと思うと切なくなった。それでも、家族はまわりの反応を見て娘の歌の才能を確信する。兄の言葉「家族の犠牲になるんじゃない」というセリフが頭に残る。ラスト、家族全員で向かった音大のオーディション。合唱部の顧問の先生のピアノ伴奏で歌うルビー。途中から家族に向けて手話付で堂々と歌う姿、家族の笑顔😃泣けましたよ本当に!ろうあ者を演じた3人は本当に凄い!手話も含めて相当な難易度な役を見事に演じました。最高に愛があふれる家族を表現するのに「あいのうた」の邦題はなくてはならない。今後は邦題を少し気にして映画を観ていきたい。最後にルビーの彼氏役が音大に落ちたのは、良い落ちでした。🤣
身障者を扱ってる映画とか、そんなの関係ない!最高の青春映画✨
とにかくルビーがいい!大好き!全力で応援したくなる。彼女が船の上で歌いながら漁をするファーストシーンから彼女の歌声、立ち振る舞いに魅了されました。
コンサートの無音の時間、あれは絶対映画館で味わってほしい。あんな体験初めて。
そして出てくる人みんな大好きになる。赤いほっぺのボーイフレンドもヤリマンな親友もクセ強すぎな先生もクソ兄貴もルビーに依存しまくってるけどルビーのことを愛して離したくないママもパパもみんな大好きー!!
アカデミー作品賞ってウソやろ?
大泣きするって、なんて気持ちいい‼︎
約2年にわたる世界的なコロナ禍の影響からか、"家族“にフォーカスした優秀な映画が最近多いような気がする。
CODAとは"Child of Deaf Adults"の略語で、聾唖者の親を持つ健聴者の子供という意味。
それともう一つ、楽曲の終わりを表す音楽記号のことでもあり、この作品の重要なファクターである"歌"によって、ずっと一心同体のように生きてきた家族の人生が大きな転機を迎える意味にも捉えられる。
主人公の高校生ルビーは両親と兄の4人家族でひとりだけ耳が聞こえるため、家族の通訳係として学校が始まる早朝から漁師である父と兄と共に海に出て彼らの仕事を手伝っているが、密かに恋心を抱く同級生のマイルズを追って合唱クラブに入部し、そこで類まれな歌の才能を見出される。
顧問の先生の薦めで音大へ進む夢を持ち始めた彼女だが、歌声を聞くことができない家族はその才能を理解することができず、通訳する彼女がいないと家業が成り立たないと猛反対。
夢か、家族か。
葛藤の中で彼女、そして家族が辿り着いた答えとはー。
実は元々弱っちい涙腺なんですが…途中から何度も何度も熱く込み上げてくるものがこぼれ落ちないよう、大きめの眼球と長めの睫毛で必死に堰き止めていたものの、もはや最後は年甲斐もなく人に見せたらいけないレベルで止めどもなく涙が溢れ出てガッツリ大号泣。
かといって決して暗く悲しい物語ではなく、笑いと愛情と希望、そして素晴らしい歌に満ちあふれた傑作。
作品中はひたすら手話で会話したり、音も会話も歌声もない聾唖の人々の視点で描かれるシーンなども多く登場する。
どこか空虚で、身体とは切り離されたような言葉がネット上を飛び交い、音でなく文字として発言する場面が多い今の時代に、手話にこそ生命と心の叫び、コミュニケーションの本質が宿ることを思い知らされる気がする。
耳で聞く言葉と、目で見る言葉。
表現の方法は違えど、それは外国語と日本語の違いとさして変わらないし、ボディランゲージで何かを伝えた経験と同じことだ。そこに壁を作ったり差別意識を持ったりせず、心を通わせ言葉を届け合うことは簡単なこと。
ネタバレになるので詳しくは語らないが、ルビーが頑固者の父、どこかいい加減な母、喧嘩ばかりしてる兄とそれぞれ二人きりで向き合うシーン。
そんな家族に自分の歌を届けようとするシーン。
そして喋ることのできない父が振り絞る"言葉"と、彼女からの手話のメッセージ。
数え切れないほどある印象深いシーンのどれもが堪らなく愛おしく、思い出してもまだ泣けてくる…(涙腺のネジがバカになったかも)
ルビーを演じたエミリア・ジョーンズの美しく心に迫る歌声も必見必聴。
その家族を演じた3人の役者陣は、実際にも聾唖者である。
この作品の余りある魅力を語り尽くせるほどの言葉を私は持たないので、ぜひ実際観てもらって"目で"感じてほしい。
A love song. 予告編通り感動できます
もう予告を観た時点で泣けるファミリー映画っぽいなっと思ってたのですが、本当にドストレートな泣けるファミリー映画でした。いやー、良かったです。
主演のエミリア・ジョーンズは海外ドラマの「ロック&キー」を観てて上手い女の子だなぁっと思っていたのですが、本作でもお見事でしたね。手話の表現もバッチリだし、思春期の将来に悩める若者を体現しています。甘酸っぱい恋の始まりとか青春だなぁ。
でも、あの両親は破天荒過ぎて自分の親だったら嫌だなっと思ってしまいました。観てる分には楽しいですけどね。特にあの親父‼️娘は思春期っちゅーねん‼️ちったぁ気を使えや‼️まぁ、何だかんだ言っても喧嘩してても深い繋がりのある家族は観てて良いもんなんですけどね。親父の為に歌ってあげたり。ルビーはホントいい娘さんや😢
そして、V先生。厳しいながらもちゃんとルビーの事を見ててくれて。試験の時に伴奏を買って出ただけじゃなくルビーのフォローもしっかりしてくれる。正しく教師の鏡ですね。
デュエットシーンで無音になる演出には何だかグッと来ました。耳が聞こえないとああいう状態なんだなっと印象に残るシーンでした。んで、試験の時に手話交えながら歌うシーンもジーンときます。演出が上手いですね。
しかし、こういう作品こそアカデミー賞取って欲しいもんですよね。批評家の方にはストレート過ぎるのかもしれませんが、何年経って観ても、どんな世代が観ても共感できる良い作品だと思います。
ずばりアカデミー賞これで決まりでしょう!
頼むよー。この年で暗闇でしゃくり上げるわけにいかんのよー。我慢するのが大変すぎるのよー。
序盤から主人公の澄み切った歌声で涙腺が刺激され出すのだが、クライマックスの手話付き「青春の光と影」で大決壊。
自然に出そうになる嗚咽を我慢するのに本当に苦労した。「心が震える』ってこういうことなのだな。
障害の為とはいえ子供依存が過ぎる幾分毒親ぎみの両親が終盤娘と向き合う時に見せる表情の変化。父は逞しく、母は慈愛に満ちて序盤とは別人かと思うほど美しい。
また娘の晴れ舞台、その才能を体感するべきシーンで他の聴衆と同じ感動が得られない、この歯痒さ、寂しさ。
でも音で伝えられないからラストのハンドサインが強烈に胸に響く(真似すると指攣りそうだけど)
いやー会員のお好きなダイバーシティも100%カバーしてるし、もう絶対「…and Oskar goes to “Coda!”」で決まりでしょう!(あくまで俺評価)
全体的に明るいストーリー展開
なんか心が洗われた(笑)
「腫れ物」にさわらない聴覚障害者の映画
すべてが予定調和で、たぶん、こうなるんだろうなぁと思った通りに物語が進んでいくが、それは決して悪いことではなく、逆に、心地よいし、暖かい。聴覚障害者の家族を、変な配慮や忖度を排して、きれいごとではなく、生々しく、それでいて、前向きに、明るく、賑やかに描いているのが良い。
当初、娘が自分たちを手伝うのは当たり前と思っているかのような両親のエゴには違和感を感じたが、家族というのは、そういうものなのかもしれないとも考えさせられる。なによりも、そうした家族のエゴは、終盤、両親が娘を送り出すにあたっての感動を増幅させる装置としても機能している。
ただ、一点、腑に落ちなかったのは、母親が、娘に、産まれて来る時に聴覚障害があるように願ったと心情を吐露する場面。本当にそんなことがあるのだろうかと疑問に思ったが、実際に聴覚障害がある俳優が演じている以上、ある程度のリアリティーはあるのだろう。健常者には知り得ない、聴覚障害者の特別な世界を垣間見たような気がした。
泣けます、いい映画!
最近いい映画に出会えてない。と、思ったら(コーダあいのうた)は所謂、いい映画。夢を諦めない主人公ルビーと障害を持っている家族の愛溢れる物語。昨年夏、最近の冬パラリンピックで障害を持っている方々の素晴らしいプレイを見た後では、エーッ?今でも聾唖ってだけでこんなに差別するかな?と、思うが魚臭いだけでも学校でイジメに確かに合うよね、しかも、ちょっと変な家族だし。うんうん。大海原に向かって唄うルビーの歌声は素敵。夢を諦めるなって云う兄貴もカッコいいし、ママは少し毒親っぽい。パパも口ばっかり。何処にでもいそうな家族。実は家族離れ出来てないと悟る主人公も日本の家庭でよくあるようなお話。毎日悲惨なニュースばかりで夢が無い昨今だから観て、泣いて欲しい。世界中の人々が普通に夢をみられる世界が来て欲しい。
家族愛を感じたい人に観てほしい
家族の中でひとり健聴者だからこそ、耳の聞こえない家族から頼りにされてきた事もあるだろうけれど、それ以上に家族が仲良くユーモアたっぷりで、愛情深く育てられたからこそ、家族が大好きで、自分の夢より家族のサポートを選択したのかな。
責任感が強く、自分の夢をあきらめる決心をする主人公の気持ちを考えると切ない。
母親が、娘を反抗期だといって、親が耳が聞こえないから(当てつけに)合唱を始めたんだと喧嘩をふっかけるシーン、今まで耳の聞こえない両親+兄の通訳者となり、家業を支えてきた主人公の気持ちを考えると腹立たしく感じた。
と同時に、母親の気持ちを考えてみると、耳が聞こえないハンデを娘がサポートしてきてくれて、そのサポートが減ったり、なくなってしまうかもしれない不安、子供が自分の手の中から離れてしまう寂しさなんかがあったのだろうか。
子供のやりたいことや自立を応援したい気持ちと、これからの自分達の仕事や生活、将来の不安と入り混じった複雑な親の気持ちも分かる。
ハンデがあり、生計を立てるにも誰かのサポートが必要で、そんな状況で、私だったら、素直に子供の夢を応援してあげられるだろうか。
最終的にお互いを愛しているからこそ、認め合い、親も子供も自立していく。
主人公の歌のデュエットの相手の家族はそれほど仲が良さそうではない描写もあり、対比となってより家族愛について考える事ができた。
人生を両側から見てきた
ふだん、SFとファンタジー以外はあまり観ないのだが、「すごく良い」とすすめられて観たところ、すごく良かった! 映画で涙を流したのはだいぶ久しぶりだ。
CODAというのは、Children of Deaf Adultsのことで、聾唖者の親を持つ健聴者の子供のこと。主人公は聾唖者の家庭に生まれた唯一の健聴者で、家族の通訳として幼いころから家族を助けてきた。
障害者や多様性がテーマの映画だが、障害者が主人公なのではなく、健常者が主人公であることがこの映画のポイントで、とても重要な問題提起がされていると思った。それは、障害者や介護が必要な者などの家庭における、健常者の問題だ。
これは最近、ヤングケアラーや、障害者のきょうだいの問題として注目されるようになってきた。
障害者には社会的な支援があるのが当然である、という認識はずいぶん浸透したが、実際にはその理想通りには全くなっていない。その理想と現実のギャップの犠牲になるのが、障害者と直接接する立場にいる者だ。
そういった者は、障害者をサポートするのが当然という、本人にとっては理不尽な「常識」を受け入れざるを得なくて、自分自身の人生を選択する権利を奪われている場合も多いだろう。
障害者の家庭に生まれた主人公は家族を愛しながらも、家族の中では逆にマイノリティであり、ある種の孤独を抱えていたり、家族の犠牲になることを当然のように強いられることもある。
聾唖者の描き方もリアリティがある。障害者を理想的な性格の天使のように描く映画もあるが、この映画では人間としての障害者を描いている。障害を持っているがゆえに一人前の人間として扱われないことに強い苛立ちをもっており、過剰なプライドを持ち、そのために合理的な判断ができなかったり、社会との軋轢を生んでいたりする場面がある。
理想的な性格どころか、粗野で下品、反社会的な面もある。しかし、それを「障害者のくせにけしからん」と思う人がいるとすれば、それは「障害者は清く正しく慎ましく、できるだけ社会に迷惑をかけないように生きねばならないのだ」というひどく傲慢な差別思想を差別と自覚せずもっているということだ。
この映画が本当に優れていると思うのは、「歌」ということを軸にして、さまざまな角度から聾唖者と健聴者とのコンフリクト(対立・軋轢)を描いている、ということだ。
印象的なシーンがいくつもあるが、そのほとんどは「歌」に関係する。物語の背景で示されたさまざまな不調和(もやもや)が「フリ」となり、「オチ」として歌が関係するシーンが出てくる。
先生から、「歌うとはどんな感じか?」と問われたとき、主人公は言葉では表現できなかったが、「手話的には」表現することができた。適当にその場をつくろう言葉を言ってもよさそうなものだが、それを言えなかったことから、主人公の「言葉」に対する誠実さを感じることができる。そして、主人公はその特殊な家庭環境によって備えた特殊な感性をもっている、ということを示したシーンだと思う。
主人公が発表会で歌を披露しているとき、突然主人公の父親主観のシーンに切り替わり、場面から音が消えていく…。鳥肌が立つほど素晴らしい表現方法だと思った。
このシーンになる直前、我々は健聴者の視点から映画を観ている。父親の歌に興味を持たない態度、娘の発表会に似つかわしくない無礼な態度に、少し腹を立てさえする。しかし、場面から音が消えていくとき、我々は聾者がどんな風に世界を見ているのか、少しだけ想像できるようになる。音は聞こえないが、人々の喜ぶ顔、感動する顔を見て、娘の歌声がどんなに素晴らしいか、知る。そして、歓び、誇りに思うと同時に、寂しさ、悲しさも感じる。そんな素晴らしい歌声を、私は聴くことはできないのだ、という。音が聞こえる、聞こえない、ということが、2人を断絶してしまっている、2人は違う世界に住んでいるのだ、ということを。
そしてこの問題提起のあと、この問題に対する回答もやはり歌だ。喉に直接手を当て、振動で歌を感じることや、手話をしながら歌を歌うことなど。
ぼくはこの映画を観るまで、手話をしながら歌を歌うこと(手話歌)など、意味がないのではないか、と内心思っていた。正直言えば、健聴者の自己満足ではないか、とさえ思っていた。でも、考え方が浅かったなあと思う。
歌とは、単に「音」なのではない。歌う表情や、身振り手振り、歌い手のすべてが歌なのだ。木々が揺れる様子でそこに激しい風が吹いているのが分かるように、歌う姿から、その音を想像することができる。それは心に奏でられる想像の歌であるがゆえに、もしかしたらリアルな音よりもより心に響くものになる可能性すらある。
また、この映画では聾唖者の「孤独」が多く描かれている。手話歌は、聾唖者と健聴者が同じ歌(表現)について感動を共有できることに価値があるのだと思う。もちろん、同じ体験をしたわけではないが、それはつきつめれば健聴者どうしであっても同様だと思う。
映画に出てくる、「青春の光と影(Both sides now)」という謎めいた歌詞の歌。「人生を両側から見てきた」というフレーズがくり返し出てくる。これは、主人公が聾唖者の視点と健聴者の視点の両側から人生を見てきた、ということを象徴しているのだと思うけど、もっといろいろな意味を含んでいるんじゃないか、と思ったので、歌詞を探してみた。
I've looked at life from both sides now
From win and lose
And still somehow
It's life's illusions I recall
I really don't know life at all
この歌詞が意味するのは、「人生の様々な出来事」、この映画のテーマ的には、「障害」「家族」「環境」「愛情」といったものに対して、ときに「良かった(win)」と思ったり、ときに「悪かった(lose)」と思ったりするものだけど、いろいろなことが過ぎて、ふり返ってみると、何が良くて何が悪かったのかなんて、よく分からないものだ、人生とは玄妙なものよ…。そんな感じの歌なんじゃないかと思った。
主人公はCODAだけど、だから不幸というわけではない。家族は不自由に生きているからこそ、お互いに切実に助け合う必要があり、その中で深い愛情が醸成されてきた、という面もある。また、主人公の特異な歌声と感性は、CODAでなかったら身につかなかったかもしれない。
自分の環境であるとか、自分の人生について考えるとき、こういう考え方ってすごく重要だなあ、と思う。「足りないものを数えるより、持ってるものを数えろよ」みたいな話ではあるが、「自分に才能が無い」とか、「環境が悪い」と考えることは無意味というか…
一見「悪い」ことだと思えるようなこと(例えば障害とか)でも、それが良いことの原因になるようなことだってある。何が良いことだとか、何が悪いことだとか、固定されているわけじゃない。人生はそんな単純なものじゃない。
恐れずに一歩踏み出してみる
聾唖の両親と兄と暮らしている健聴者の高校生ルビーは、自分の生活より家族を優先するのを当たり前として生きてきました。けれど、唯一の愉しみの歌の才能を教師に認められると、だんだんその生活に疑問を感じます。でも自分の夢を実現すると大好きな家族の側にいて助ける事が出来ない・・・
聞こえない父と兄が漁師というのは無理があるのでは?と思っていたら、免許を取り消されたりしていました。アメリカの漁業従事者の問題点を監督が取り上げたかったのでしょうか。
自分と違う者への不寛容や偏見、ヤングケアラーなど様々なテーマがあり、演出に多少のわざとらしさはありましたが、家族の明るさと、初めは大きい声を出すのをためらっていたルビーが次第に自信に満ちてのびやかに歌う姿が爽やかで好感が持てました。
障害者の親や家族が健常者の子を抑圧するというストーリーの難しさ。そ...
障害者の親や家族が健常者の子を抑圧するというストーリーの難しさ。それを扱った素晴らしさ。娘の葛藤も描かれていた。親からすれば子どもがむしろ聾唖者であってほしいと願うようなエゴ。母親はエゴ丸出し。コンサートでの両親の無関心さ。
素晴らしきは役者としても合唱部の先生。
うまく喋れなかったからこそ、歌が彼女にとっては重要で、感動的なのは試験で手話付きで歌う場面。それまでは、恥ずかしくて親の感情表現をちゃんと訳さなかった彼女が、歌に自分をぶつけるようになってから、交渉場面でその感情を伝える。
彼女の歌う喉に手を当てて父親が聞くシーンも感動する。
健常者と障害者のはざまにいる少女の苦悩をこんなに素晴らしく表現したものがあっただろうか。
歌超えも素晴らしかった。
障害者たからこその家族の結束の大きさも感じる。そこを離れて生きてこなかったとする彼女の言葉は重い。
「必見!」とは言えないなぁ
家族愛をテーマとし、自分の夢と現実生活のあいだで揺れ動く高校生の苦悩や奮闘を描いた作品。
いい話です。
いくつか印象的な場面がありましたが、とくにクライマックスの音楽学校の入試のシーンはよかったです。
ルビーが、もう試験のことなんか忘れて、家族のために歌う。そして家族がひとつになる。その光景は感動的でした。
この試験のシーンから結末にかけての流れもなかなか見事だった。試験会場で歌うルビーの『青春の光と影』が続いたまま、途中で場面が変わっていき、ルビーとその家族に希望の光が射してきたことを、説明的にならずに簡潔に示しています。
でも正直言って僕はあんまりこのファミリーに感情移入できなかったです。お母さんが妙にオシャレだったり、お父さんのかなりクセの強いキャラにもちょっと抵抗感がありました。それから「これ必要なのかな?」と思う性描写があったりで(「PG12」の理由が分かりました)。どれも聾者を変に美化しない、彼らも健常者と同じ人間なんだということを表現したかったのだろうけれど……。
あと、「V先生」がルビーの才能を見出す過程にもう少しインパクトと説得力が欲しかったようにも思います。ただ歌が上手なだけじゃなく、名門バークリーに推薦するだけの突出した才能に出会ったわけだから。ついでに言うと、先生のレッスンもなんかちょっと抽象的な感じがしました。これも理論的で、「なるほど!」と納得させるような演出があればもっとワクワクしたような気がします。
それにしても『青春の光と影』は名曲中の名曲ですね。この作品の成功の半分くらいは、この曲のおかげ、ジョニ・ミッチェルのおかげなんじゃないかという気もしないでもないですが、やはりこの曲を上手に使った監督の手腕を讃えるべきでしょうね。
確かにいい映画です。それは認めます。でも、忙しい中、時間を割いて観にいくほどの作品ではなかった、というのが僕の感想です。本作の公式サイトには、「必見の1本!」と書いてありますが、そこまでの作品ではないと思いました。まあ好みと相性の問題ですが……。
フィクションが描く鮮やかさと限界
コーダである主人公の彼女の物語としては、感動的。
上映中、何度も涙した。
終映直後の快感のあとに残ったのは、主人公の周りにいたひとびとの存在…
主人公の父は、母は、兄は、恋人は、一体どんな葛藤を抱えていたのだろう?
主人公の葛藤は、コーダの少女の生きざまが見事に描かれていたように思う。
一方で、主人公の夢を送り出す、周りのひとびとの葛藤については解像度が粗く、一見めでたしめでたしのようだが、モヤモヤが残る。
性生活を主人公である娘にオープンな両親、マリファナを吸う父、娘の都合を鑑みずに何度も手話通訳を頼む母、キレやすい兄。
学校のクラスメイトたちの主人公へのいじめ紛いないじり、疲れ切っている彼女の居眠りへの教師の嫌味、学校全体の彼女への差別的な空気、家庭環境が良いとは言えない恋人(ここは気になったが、あまり描かれていない)。
ろう者であるとか障碍の以前に、全体的に難ありな環境下にいる主人公。
そんな状況の中、主人公だけが清潔に描かれる。
家族の通訳を生まれてからずっと担い続け、家業の漁もし、自分の学校生活や私生活の多くを犠牲にして、ろう者である家族のために尽くす娘。
そんな悲惨な状況にある彼女には、歌の才能がある。
障碍を才能で乗りこえるパターンの物語をみると、いつもなんだかな〜という気持ちになってしまう。
全732件中、361~380件目を表示