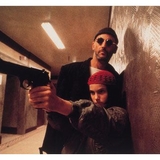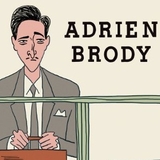ナイトメア・アリーのレビュー・感想・評価
全286件中、1~20件目を表示
面妖で絢爛、デルトロ印の大人向け寓話
邦題のカタカナタイトルだけ見て、アリーという魔性の女が出てくるんだと漠然と思っていたアホな私ですが、alleyなんですね。原作の日本語タイトルは「悪夢小路」。確かにこれは、主人公のスタンが欲と悪事の危険な小路に迷い込んでいく話。
第二次大戦が始まった1939年、人権的にアウトな獣人(ギーク)の見せ物をやる怪しげなカーニバル一座にもぐりこんだスタンは、そこで出会った老人と彼の持つ一冊の本から、読心術とそのからくりを知る。恋人モリーと独立してオカルティックなショーで売れるが、心理学博士のリリスとの出会いから、一線を超えた霊媒師詐欺に手を染める。
デルトロ監督らしい、暗く怪しい華やかさに満ちた映像に終始圧倒される。序盤のギークと鶏のシーンは、世界観の宣言であり、とびきり辛いスパイスだ。「シェイプ・オブ・ウォーター」で半魚人が猫を食べたシーンを思い出した。鶏さんには申し訳ないが(というかもちろん本物ではないが)、こういう容赦ないアクセントは、本来のグリム童話のように人間の本質に蓋をしてない感じがあって結構好みだ。
(あのカーニバルは昔縁日で見た見世物小屋を思い出した。ダミ声のおじさんがさあさあ怖いよ怖いよと呼び込みをやってて、蛇女や火のついた蝋燭の束を飲み込む芸を見せる。氷点下の世界とかいう、中が冷凍庫状態の小屋もあった。平成の話です)
中盤から出てくるリリスの執務室兼カウンセリングルームの豪華すぎるしつらえ。アールデコで隙がなくかっこいいが、彼女の金銭欲の象徴のようにも見える。とはいえ、その舞台に負けないケイト・ブランシェットのこの世ならぬ美しさに目が眩んで、これはもうスタンと組めば面白い、いや組んだらやばい、とアンビバレントな気持ちになった。
疑い深いグリンドルとのやり取りは、終始緊迫感があった。見破られるかとはらはらさせてからの全幅の信頼関係、でもやっぱモリーを幽霊がわりに立たせて(これがまた絵になる)ってのは案の定無理があった。バレるや否や殴り殺す……あーあやっちゃったよ。人生がまさに暗転する。
配役は全員適材適所だが、個人的にはウィレム・デフォーのハマり具合が好きだ。悪い生業に就く小汚い脇役でものすごく光る、というと失礼な響きだが、本当に上手いなあ、こなれているなあと思う。
酒は、身を滅ぼす欲と悪意の象徴なのだろうか。断片的に描写されたスタンの父親への憎しみが飲酒に絡むものなのかははっきり分からないが、当初の彼は憎んだはずの父の形見の腕時計を身に着け、頑なに飲酒を拒んでいた。その頃の彼は、野心はあるがギークにかすかな優しさを見せる一面も持っていた。クレムからギークの”作り方”を聞いた時も、こちらが共感できる範囲の嫌悪感を見せた。
そんな彼が、リリスの持つ情報を利用することで、同じ手練手管で金持ちから桁違いの利益を得られることを知った頃から酒を拒まなくなり、人の孤独や悲しみに深く立ち入り、付け入ることをいとわなくなる。悪事の泥沼にはまるにつれ進んで酒を口にするようになり、最後は酒を求めて腕時計を差し出し、ギークへいざなう酒も飲み干した。
スタンがギークへの道をたどることはラスト手前からうっすら見えてくるのだが、”一時的な仕事”への誘いと酒で暗示してストンと切る終わり方がいさぎよく、美しい。彼の未来の姿が、序盤に出てきたギークへループする。ありきたりというマイナスイメージではなく、昔話の因果応報エンドのような様式美を感じた。彼が踏み込んだ悪の道は、ギーク候補が拾われる悪夢小路にそのまま繋がっていたのだ。
そしてブラッドリー・クーパーの、さまざまな解釈を喚起する最後の笑い。私的オスカー候補に推したい。
余談だが、パンフレットに坂本眞一とヒグチユウコの書き下ろしイラストが掲載されている。まさにこの二人しかいないだろうという絶妙なチョイス。
映像の素晴らしさと安定のタイプキャスト。
ギレルモ・デル・トロが描くサーカスや読心術ショーのいかがわしくて禍々しい世界観は、かつてティム・バートンに期待されていたがもはや観られなくなった(もしくはセルフパロディぽく見えてしまう)ものを正面から引き受けてくれていて、目のご馳走だと思う。古い映画のリメイクというより原作小説に忠実という触れ込みだが、ギークの看板なのは旧作のものをほぼそのまま再現していたし、冒頭のシーンはアンドリュー・ワイエスの印象であるし、たぶん自分なんかでは気づけないほどオマージュが詰まっていそう。全部わかる必要もないと思うが、豊潤な映画や文化や芸術をふまえて出来上がったリッチが映像が美しい(個人的には『パンズ・ラビリンス』のゴシック感の方が好みではあるが)。
物足りないと思うのは、もうこの顔を出しておけば間違いなしくらいの、鉄板のくせ者たちが揃っていて、ロン・パールマンやウィレム・デフォーやケイト・ブランシェットは笑うくらいパールマンでありデフォーでありブランシェットだし、デヴィッド・ストラザーンとリチャード・ジェンキンスはお互いの役を入れ替えても気づかないかもと思うくらいポジションが似ている。キャスティングがイメージそのままの安心感が、いささか物足りなさにつながっている部分はある。あと情念みたいなものが、あまり迫ってこないのはデル・トロの作家性なのかも知れないなと思うようになってきたが、今度はいかに?
巨匠デル・トロが描く心の闇と運命の螺旋
人間の心というものを実に艶かしく幻想的に描いた作品だ。秘密を抱えた男が怪しげなカーニバルの一団に身を隠す。このマトリョーシカのような二重構造によって、主人公は一方で俗世から守られつつも、他方では抜け出すことのできない迷宮に囚われていくかのよう。かと思えば、本作は醜く禍々しい存在であるほど親しみと安らぎをもたらし、ノーマルに見えるものほど異常性をむき出しにするという、極めてデル・トロらしいモチーフも見え隠れする。そこでフィーチャーされる”読心術”という要素がまた面白い。誰もが人の心を知りたい、読み解きたいと願うもの。でもひとたびその安易な麻薬を手に入れると、うっかり人生を転がり落ちてしまいかねない。さらにそこへケイト・ブランシェット演じるファムファタールの司る精神分析という闇までもが口を開けて待つ。この心をめぐる攻防のなんとも魅惑的なこと。いつも以上にデル・トロの語り口と人間描写を堪能した。
ブラッドリー・クーパーのラストショットは強烈過ぎる
流れ者のスタンは獣人や芸人たちによる怪しげなショーを売り物にしている見せ物小屋に潜り込み、そこで読心術を学んで、感電ショーの人気者、モリーと2人で一座を抜け出し、都会で一旗上げようとする。時代は大恐慌時代のアメリカ。人々の顔には覇気がなく、彼らが一瞬の驚きを求めて集まってくる見せ物小屋はまるで、そんな時代の縮図のようだ。絶望感。それは映画全体に充満していて、明るい兆しがないことは最初から分かっている。ブラッドリー・クーパーがどれだけ足掻いても救われない運命にある主人公の、訳も分からず破滅に向かって突き進む道程を演じて、物凄い説得力がある。
なぜ、スタンは端から救われない運命を背負っているのか?そして、彼が悪事の限りを尽くした挙句、人生の墓場に辿り着いた時に見せる、奇妙な笑顔が意味するものは何なのか?物語の鍵になる?が、クーパーの端正な表情と熱演によって具現化されるラストショットは強烈過ぎて、しばらく席から立てなくなった。人には決して侵してはならない境界線があり、それを超えると人間ですらなくなるという恐怖が背筋を凍り付かせるのだ。
今回も凝ったセットデザインを作り上げ、俳優たちから最高の演技を引き出しているギレルモ・デル・トロだが、人間の本質を見据える鋭い観察眼は、本作でさらに磨きがかかった気がする。
ギレルモ・デル・トロ監督らしさ満載だがダーク・ファンタジーではない、運命と人間性を軸に描いたダークなサスペンス・スリラー映画。
「シェイプ・オブ・ウォーター」が第90回アカデミー賞で作品賞、監督賞、作曲賞、美術賞と最多4冠に輝いたギレルモ・デル・トロ監督の最新作。
本作でも第94回アカデミー賞で作品賞に加え撮影賞、美術賞、衣装デザイン賞の計4部門にノミネートされています。
本作は「パンズ・ラビリンス」や「シェイプ・オブ・ウォーター」のような❝ファンタジー要素❞を出来るだけ排して、1940年前後の現実世界を舞台に、運命と人間性を軸に描いているデル・トロ監督の新境地的な作品となっていました。
そして、その難しい世界観を映像化すべくブラッドリー・クーパー、ケイト・ブランシェット、ルーニー・マーラなどの演技派俳優陣が脇を固めていて彼らの演技力にも引き付けられます。
物語自体は良くも悪くもデル・トロ監督風味が満載の「ダークさ」が根底にありながら、淡々と進んでいきます。
とは言え、華やかなショービズ界が舞台になっているため、トリックの心理戦やウラ話などがあり、興味を引き続ける手法は流石でした。
映画の完成度は高いものの題材等も含め、割と好みが分かれる作品でしょう。
デル・トロ監督の新境地として見ておきたい作品だと思います。
権力を争奪する大人だらけのダークが1番怖い。
本作は、あまり情報を調べずに鑑賞するほうがいいと思える作品の部類。
ショービジネスに魅せられた野望ある青年の物語と思って見ていくと、どんどん先が気になって仕方ない。
鬼才ギレルモ・デル・トロ監督と豪華な俳優陣のセッションで、読み聞かせてはいけない「大人向けの童話」が立体的に色を放ったような不思議な感覚に陥った。
ストーリーは日本昔話に似た説得力があるが、仕事に没頭していくスタン(ブラッドリー・クーパー)の姿は見ていられなくなる。
美しくて豪華なホテル暮らしが幸せそうに見えなかったところは監督の思惑通りなのだろう。
予想外の展開にドキドキさせられたが、華やかな悪夢に酔いしれるよりも、教訓という意味合いもあり、何とも複雑な気持ちになってしまう「大人向けの童話」だった。
物語のいかがわしさは僕自身
脚本良いが、結構暗い。
違法なサーカス団でペテンの技術を極めて、独立して頂点まで登りつめた男が、一線を越えて、人生崩壊してしまう物語。崩壊する主人公はブラッドリー・クーパーが演じ、ヒロインはルーニー・マーラが演じる。他、違法なサーカス団員にウィレム・デフォー、トニ・コレット、ロン・パールマン、主人公と組む悪女にケイト・ブランシェット、ヤバい大富豪にリチャード・ジェンキンスと豪華キャストだった。
どの役者も演技が良すぎた!
主人公と大富豪の結末は、デミアン・チャゼル監督の『バビロン』のトビー・マグワイアとのシーンをなんか思い出してしまった。予想できた展開だったが、やはり怖すぎる…💦
最後まで見たら、最初と最後が繋がる凄い脚本だなと思った。獣人を憐れんでいた主人公だが、最後には自分が獣人になってしまうという…
(この監督の作品はインパクトのある怪物が度々登場するが、今回は人=怪物だったのかな!?)
人は一線を越えてしまうと誰しも獣人になり得る可能性がある。地位や名声を手に入れるとどんどん欲が出るが、どっかでブレーキかけないと取り返しのつかないことになるぞという痛烈なメッセージを感じた。地位、名声、愛する人とすべて失った果て、自分が獣人になるのは宿命だと受け入れる主人公が何とも悲しかった。何気ない小さなことに幸せを見いだし、ひっそりやることも良いかもしれない。
宿命ではなく、宿業?
『宿命』は、その人に生まれながらに与えられたものだと定義すると、
同じ宿命を持っていても、そこから這い上がる人と
流される人に別けられる
その宿命に翻弄されるのも、踏み台にして行くのも本人の努力次第
でも、この映画でテーマにしているのは『宿業』のような気がする
単なる努力では、変えられないもっと深いもの・・・
アル中の父親を蔑み、あんな男にだけはならないと決心したスタン
そのためにも「絶対に飲まない!」と頑なにずっと飲まずにいたのに、
とうとう手を出した時から、壊れていく
次々と人を56し、冷酷に正当化していく性(さが)
「獣人(ギーク)」の哀れさを見て、途中その場を離れるも
人生の最後には、自身がその「獣人」に落ちぶれていく
好きになった女性モリーが
「電気人間として芸が出来たのは、自分の限界を知っていたから。
無理だと思ったらすぐやめるの」と意味深な発言をしても、
それを自分への啓示だとは気がつかずにスルーし
転落していく
でも1番ヤバいのは、精神科医リリスだと思う
研究対象としてスタンを利用したのも彼女
患者の秘密の情報を漏らしたのも彼女
スタンがお酒を飲むように仕向けていったのも彼女
完全犯罪をもくろみ、警察にスタンを追わせたのも彼女
セラピストや精神科医なんて、個人的に(怪しい存在)としか
思っていなかったけど、やはりね
手を抜かない見世物小屋等のセットや衣装は必見の価値あり
そして、3人の女優の演技力と妖艶さに拍手
メリーゴーランドや観覧車的な大規模な見世物小屋が各地を転々と移動しながら
警察の眼を縫って営業していたことに驚いた
木下サーカスもビックリだよね
悪夢の袋小路。見せかけの千里眼では己の運命までは見通すことは出来なかった。
舞台は第二次大戦開戦時のアメリカ。人々が皆不安に苛まれたそんな時代につけこみ、のし上がろうとした男がいた。
近親憎悪により父親を殺害した過去を持つスタンは唯一の財産であるラジオを携えて行くあてもなく彷徨っていた。そんなある日、彼は見世物小屋の一座に紛れ込む。
手に職があるわけでもなく学もない彼だが、野心だけは人一倍あった。この一座の中で抜け目なくスキルを身に着けた彼は飲んだくれのピートの読心術に目をつける。ピートを殺害し、そのノウハウを奪った彼は一座のモリーと駆け落ちし、ショウビジネスの世界へとのし上がってゆく。
彼の読心術ショウはたちまち成功し羽振りはよくなったが、それでも彼の野心は飽き足らず、次第に危険な領域へ。
人々が不安に苛まれていた時代、どんなに社会的地位が高く、富に恵まれた人間でもその空虚な心までは満たすことは出来ない。そんなセレブたちの心の隙間につけいったスタン。
ピートやジーナたちの警告を無視して、心理学者のリリスと組んでセレブリティに取り入り大金を手にしてゆくが、その行いはもはやショウの域を超えていた。
影の権力者グリンドルをだましたことから追われる身となった彼は妻も財産も全てを失ってしまう。
結局、ピートの忠告通り自ら作り上げた噓で人々を不幸に誘い、自身も破滅に向かってゆく。
逃亡生活の果てにたどり着いたのはかつて彼が這い上がってきたはずの見世物小屋と同様の一座だった。そこにはエノクの標本と彼のラジオが。
思えば、スタンの運命は初めからこのエノクに見透かされていたのかもしれない。
誰もが忠告した危険な幽霊ショウはセレブたちの心の隙間につけいりうまくいったかに見えた。しかしそれは破滅とも紙一重。
そんな危険なショウに身を投じてしまったスタンはすでに悪夢の袋小路に足を踏み入れてしまっていたのだ。抜け出したと思った悪夢の小路から悪夢の袋小路へと。
もはや彼はそこからは抜け出せない。そう悟った彼は獣人になることを受け入れるのだった。
見せかけだけの千里眼、読心術でかりそめの富を築いたところで、それは元いた見世物小屋での日々と何ら変わらぬもの。
未来を見透せるはずの千里眼を持ったエノクが母の胎内で暴れ命を失ったように、自らの野心で自らの身を亡ぼしてゆく男の様を描いたデルトロ面目躍如の作品。
再投稿
悪夢の人生回転木馬
ウィリアム・リンゼイ・グレシャムの同名小説の二度目の映画化。意味は「悪夢小路」で、人生どん詰まりの浮浪者、アル中、ヤク中の吹き溜まりのこと。そこからうまく連れ出し、野人(ギーク)と称してフリークショーに出演させるくだりが、この作品の屋台骨となっている。
今回はギレルモ・デル・トロが監督/脚本だが、皮肉なストーリー回しと悪趣味な設定や美術装飾が、いかにも彼らしくファン心をくすぐる。
舞台は一九四〇年代のアメリカ。行き場をなくした孤児のスタン(ブラッドリー・クーパー)は、移動式遊園地に併設された数々の見世物に魅せられ、興行主クレム(ウィレム・デフォー)に誘われるまま下働きを始める。したたかで如才ないスタンは、タロット占いと読心術がウリのジーナ(トニ・コレット)&ピート(デヴィッド・ストラザーン)コンビにうまく取り入り、その技を盗んでいく。そして電流娘モリー(ルーニー・マーラ)に心惹かれ、一緒に独立して、ヴォードヴィルでのショーマンとなる。ここまでが第一部たる立志篇で、艱難辛苦や忍び寄る闇があるとはいえ希望もある。
第二部は、ショーの最中に「スタンの読心術は単なるトリックであって、超能力なんかじゃない」と、心療医リリス博士(ケイト・ブランシェット)に喝破される背筋も凍る場面から始まる。ところがスタンはあらゆる手段を駆使し、この難局を乗りきった上に博士をやりこめる。そこから更に上を狙うスタンに、あらゆる方向から、眩ゆすぎる光と漆黒の闇が襲いかかり包囲する。因果応報。終わらない循環する悪夢。怖いのは結局人間なのだ。
清々しいほどスタンの転落ぶりがエゲツない
2時間30分あっという間だった。全く苦じゃない。もっとこの世界に浸ってたかった。サーカスの雰囲気と、スタンの転落ぶりが面白い。
ちょっぴりダークなサーカスの雰囲気が好き。見せ物、読心術という馴染みのない要素が刺激的で、冒頭から引き込まれた。
子供の頃、遊園地の見せ物ショーで蛇を食いちぎる女を見て楽しんだ記憶が蘇る。
清々しいほどスタンの転落ぶりがエゲツない。分かりやすい成功からの失敗ぶり。いるよね、天狗になって調子乗って破綻する奴。スタンは典型的なそれだから反面教師として見習いたい。
まあでもイケメンで人の心読めてモテモテだったら、天狗になっちゃうのは分からなくもない。
やってることは悪人なんだけど、なぜだが応援しちゃうのはスタンのカリスマ性ゆえか。あそこまでやったら、最後は逃げ切って欲しかったかも。
最後自分が獣人になっちゃうエンドはキツかった...笑ってるのか泣いてるのか、分からない笑い声が切ない。「一時的に」と言われ、全てを悟った時の心境はどんな感じなんだろ。
電気女
大人のおとぎ話を期待していたが…
タイトルなし
飲んべえピートが主人公の過去を読み解くシーン、何か良からぬ物が視えてしまい怖じけてやめる姿が、ピートは本当に過去の視える人で、冒頭の放火シーンを視てしまったのかと勘ぐってしまった。観終わってみればファンタジー要素は無かったと思うが、ギレルモ作品らしく何かとファンタジー要素を思わせる独特の雰囲気は漂っていた。
中盤以降は殺された飲んべえピートの敵討ち映画だと勝手に予想してしまったものだから、心理学者リッターの復讐対象者は主人公だと思って観ていた。予想は間違っていたが彼女の罠にはまって主人公が落ちていく展開に変わりなく命を落とす事なく逃亡生活に移っていった辺りで獣人の話に繋がっていくのだなと感心した。
全286件中、1~20件目を表示