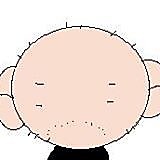ベネデッタのレビュー・感想・評価
全107件中、1~20件目を表示
The Anti-Nun Horror Film
Paul Veerhoven does what he does best in a sacrilegous plot with gratuitous lesbian nun sex scenes. Inspired by a true tale in a convent in central Italy, with demons, in French. True to the era it portrays as a costume drama, the film is a punk look at gender roles developing in the Catholic European Renaissance. Basically a pink eiga with a high IQ, fans of the director shouldn't miss it.
映画とエロスと宗教と
ポール・バーホーベン監督といえば、娯楽大作の大枠のなかで「ロボコップ」「トータル・リコール」「スターシップ・トゥルーパーズ」などのSFアクションがある一方、「氷の微笑」「ショーガール」「エル ELLE」といったヌードや性的な描写を多く含む問題作により、それまでの映画におけるエロス表現の基準を刷新してきた鬼才という印象も強い。
そのバーホーベン監督の最新作は、実在した修道女ベネデッタを題材にしていて、大まかに史実に基づく点では「ブラックブック」に共通する。レズビアンの要素、R18+指定という情報も前宣伝で強調されていた。
ベネデッタは本当にキリストの声を聞き奇蹟を起こしたのか。それとも聖痕などを自作自演ででっちあげて教会関係者や民衆を欺いたのか。バーホーベンが共同脚本も務めた本作のストーリーはその辺を巧みにぼかして描いており、判断は委ねられる。エロス要素を男性目線で期待すると、あるいは物足りないかもしれない。それでも、ヴィルジニー・エフィラが演じるベネデッタのパワフルな女性像はきっと多くの観客を勇気づけるだろうし、宗教という伝統が重視される保守的な世界で周囲を翻弄しながら我が道を行く姿には、ある種ピカレスクロマンのような痛快さがある。
呪いの伝染病
極道以下の教会
女性や末端の人間を拷問や虐待、脅しで服従させるの、日本の極道でも普通は女・子供には手を出さないです。まるで反社の様な教会でしたが、植民地時代に列強がやったことや世界大戦の非道(原爆投下など)も元を辿ればこの信仰に繋がるのかと思って、納得しました。もちろん今も最大の暴力である戦争は継続中ですし、他の宗教でも国家でも同じことをやってます。だから、私は信仰に救いを見いだせないし権力も信用できないですね。
ベネデッタは被支配層の象徴なので、ベネデッタ個人というよりも、教会の権力構造にフォーカスして観てしまいました。あと、ベネデッタは日本でいうイタコ的な、今は統合失調症という病名が付いた人だったのでは?と思いました。バーホーベンらしい作品でしたが、色々とエグくて観ているのが辛かった。歳を取るとエログロをみるのがきつくなります。
タイトルなし
卑弥呼(真説・邪馬台国伝…の)!?
R18+だけあって、表現は非常にエッジが効いていますので、
観る方を選ぶ映画でもあります。
映像が抜群に美しいです。
私が中世ヨーロッパの設定が好き・・という贔屓目もあるかもしれませんが、
衣装・建物・風景・人(特に主人公まわりの女性陣)の美しさが際立ちます。
音楽も映像にさらに彩りを与えるような良い雰囲気を醸し出す役割を
充分に発揮しています。
冒頭からベネデッタの人となりをつくりあげていく要素を
積み重ねていきながら、神格化していく彼女の土台を視聴者に理解させる
流れとなっていて、私は好感が持てました。
ただ、ベネデッタが計算しつくした"演技"をしているのか、マジなのか、
これはわからないつくりになっているのが上手い。
ただ、私は"演技"だと思って観ており(その証拠も映画では表現されます)、
というのも、原作:リチャード・ウー、画:中村真理子によるマンガ
『卑弥呼』の卑弥呼にそっくりなんですよね。ベネデッタが。
このマンガの卑弥呼は、計算しつくして卑弥呼を演じながら、
自身の人生のVisonも成し遂げようとするわけですが、
まさにベネデッタもそうなのではないか?と感じたわけです。
でも、ラストは計算高いベネデッタではなかった。
だからホンモノかもと思うところもあり、実に深い作品になっていますね。
※キリストの扱いがちょっとチャラいなぁ・・とも。
中世ヨーロッパって残酷。宗教もこの頃はどうなの!?と思います。
平気で人を拷問したり殺害していいの!?と。
そして、ペスト。
これはコロナにも通じるものがあり、意図的に扱っているように思います。
決して誉められる表現ではないし、万人にオススメもできませんが、
なんせ実在の人物を扱っているのが興味深いです。
そして、ファッションとしても見応えがある作品です。
ポール・ヴァーホーベン監督はとても80歳とは思えないくらい
エネルギッシュ。そして主演のビルジニー・エフィラの体当たりの演技も
最高でした。きっと今後も活躍されることと思います。
宗教の本質を突いてるよね
狂ったキリスト教。
難解
壮絶
ベネデッタ、真実は?
ポールバーホーベンは揺るがない
ポールバーボーベンの嗜好は揺るぎがない
ベネデッタが
ほんとうにイエスとつながり言葉を受け取って聖痕を与えられたか、
修道女としての行いを続け院長として修道院に恩恵を与えたか、
は日常としては描かれるが問題ではなく、彼女がどういう嗜好性でこの閉ざされた世界で生きているかをポールバーホーベンの側からの視点を強調して物語る。
ベネデッタが恣意的にふるまうように見えてとてもしたたかで柔らかく強い。
ビルジニーエフィラのベネデッタは象徴的に金髪だし、これまでのポールバーホーベンの女性と同様周囲に溶け込まない強さを持ち、クラッシックな画面構成の中でとても際立っている。
この拘束的な(それはとてもわかりやすい)修道院の中で異なるルックスと、その馴染むことのない行動言動は他の作品より、よりポールバーホーベンが如何にベネデッタが特異な存在であったかを強調している
(わたしの数十年来の映画的ミューズである)シャーロットランプリングは、いつもとは違いとても感情的に演技している、そこに驚いた。
若かりし美しきシャーロットランプリングの「さらば美しき人」とは対照的に静かな眼と感情が溢れる演技。
これもポールバーホーベンのなせる映画か。
バーホーベン最新作はやっぱり一筋縄ではいかなかった
YouTubeビデオで鑑賞。
みんな大好きポール・バーホーベン監督最新作。
一応ジャンル的にはナンスプロイテーション(尼僧や女子修道院を題材にしたエッチな映画)って事になると思うけど、内容は大変な時代や状況の中でも“強か”に生きぬく女性の生きざまを描いた「ショーガール」「ブラックブック」「エル ELLE」に連なる最新作。
17世紀イタリアに実在し、同性愛の罪によって70歳で死を迎えるまでの間、修道院に隔離された修道女ベネデッタ・カルリーニの伝記を原作にした作品で、その身に聖痕が現れたことで、聖女として村の中で権力を得ていく様子が描かれていく。
そんな彼女の聖痕や信仰が本物だったかどうかは観客に判断を委ねる作りになってるんだけど、監督的にはそれよりも17世紀という時代を生きぬいたベネデッタの強かさを描くことが重要だったんだと思う。
ちなみに、本作の撮影時バーホーベンは80歳なんだけど、とても80歳のお爺ちゃんが撮ったとは思えない力強く瑞々しい作品だった。
宗教、そして修道院の闇を描いた作品。
史実に基づいた映画であり、実在の修道女が主人公。
エロさとグロさが溢れた作品です。
宗教色の強いストーリーなので、序盤は入り込めなかったのですが、
中盤以降グイグイ引き込まれていきました。
修道院というのは、行き場を失った
女性を救済する聖地のようなイメージがあったんですが、
金がなければ入れてもらえない、ドロドロとした場所なんですね。
神が乗り移ったようなあのシーン。声が男性のように
なってましたが、あの憑依は真実?演技?
全107件中、1~20件目を表示