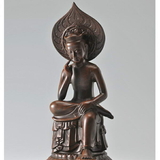2人のローマ教皇のレビュー・感想・評価
全53件中、1~20件目を表示
ローマ教皇たちの秘密が今明らかに。
様々なスキャンダルを抱えるカトリック教会の運営に限界を感じた現ローマ教皇が、革新派の枢機卿をわざわざバチカンに呼び寄せて、徹底的に腹を割って話し合う。この実際にあったエピソードを、実物の1/3大のシスティナ礼拝堂をチネチッタに建造する等、舞台の精密な再構築を用いて観客に知らしめていく。背景のリアリズムが、ドイツ人独特の無骨さで教皇を演じるアンソニー・ホプキンスと、方や、やがて、南米初のローマ教皇となるホルヘ・マリオ・ベルゴリオを、巧みなスペイン語とスペイン語訛りの英語と、実物そっくりの外見と(今年来日したので分かりやすい)、まろやかな人物の造形によって具現化するジョナサン・プライスによって、さらにリアリティを増していく。やがて浮かび上がるのは、教皇となる人間にも深い悩みと矛盾を抱え、孤独に苛まれることもあるという、とても普遍的な現実。人は何と愛おしい生き物か!?そんな後味が残る実録ヒューマンドラマだ。
会話してる話し
対話
対話劇である。
ほとんどベネディクト16世とベルゴリオ枢機卿2人の対話の話。
事実に基づく話かどうかはわからない。本人達に取材なんてできるわけないから、状況証拠からの推測に基づき創られた創作物であろう。しかし、まるでドキュメンタリーを観ているかのように、リアリティと説得力がある作品である。
人間、話せば分かるというほど簡単ではない。
教義の捉え方、教会運営の方針の異なるベネディクト16世とベルゴリオ枢機卿は、最後までその信念で折り合うことはなかったのだろう。
しかし、対話を重ねる中で、2人の間には信頼関係が構築された。孤独であったベネディクト16世にとって、心を開ける相手は対立する者。彼は、最初から後継候補として目を付けていたとしか思えない。ベルゴリオ枢機卿の過去を調べ、バチカンに呼び寄せた。自分の目で確かめるために。
対話によって相手を知る。思想信条という軸ではない、別の軸で人を見極める。
人の上に立つ者に必要な資質とは何か。
危機を救う者に必要な資質とは何か。
世界的宗教教団トップという特異な役割に纏わる話だが、その本質は、宗教教団でなくても企業でも当てはまる話のように思える。
どちらも人間がつくった組織だ。大きくなれば、派閥ができる。権力闘争がおきる。駆け引きが発生する。それらを乗り越えてまとめていくことは並大抵のことではない。
権力者は孤独だ。権力者は弱音を吐けない。権力者は完全ではない。
ワールドカップのサッカーシーンはよかった。
お互いが母国を応援して戦う。しかし、楽しそうだ。同じ土俵で楽しんでいる。
違いを認める。相手をリスペクトする。方法論は違っても大きな目標は一緒であることを確認する。そして解決策を模索する。
本当の対話とはかくあるべし、を教えられたような気持ちになった。
アンソニー・ホプキンスとジョナサン・プライスの名演が光る。
亡くなられた教皇様にご冥福を
言いにくいことはラテン語で
色んなことを考えて久し振りに鑑賞。忘れていたシーンが山ほどあった。こんなに深くて辛いシーンもあったのか。ベネディクト16世とベルゴリオ枢機卿が互いに告解する箇所では涙が溢れた(若いときのベルゴリオを演じたフアン・ミヌヒン、とてもよかった)。ホプキンスとプライスの二人ともが主役の映画だ。真逆の二人が出会い話し一緒に時を過ごし、それぞれが相手の思いや言動から反射を受ける。プライス演じるベルゴリオ=フランチェスコは本当にチャーミングで優しく強い。フランチェスコのジョークはツッコミ、ホプキンス=ベネディクトはボケだ。ベネディクトの左目が殆ど見えていないのがメイクと表情で上手く演じられていた。音楽と食事とサッカーとタンゴがいいスパイスになっていた。最後の方で本物のベネディクト16世とフランチェスコがお友達みたいに嬉しそうにしている場面が二つ流れる。2人のローマ教皇とも神様のお家に帰ってしまった(2025.04.23.)
.............................................................
会話劇でドキュメンタリー・タッチでアクチュアルな話で老いの話で、そして世界を守りつつ変えていこうとする。それは教皇にも私たちにも通じる話で笑いながらも深く考えさせられた。
初めはホプキンスがフランチェスコ役かと思っていたので新鮮な驚きだった。結局はとてもいいキャスティングだった。フランチェスコもラッツィンガーも過去、胸が痛む、別の言い方をすれば世間や母国から批判されることがあった。個人的にもラッツィンガーが教皇になったのには自分は批判的だったけれど、二人が真摯に語り合う場面で心動かされた。コンクラーヴェで世界中から枢機卿が集まる場面はどんな映画でも楽しい。それぞれに故郷があり母語があり大好きなお料理があり個性がある。
タンゴとサッカーとジョークが好きなアルゼンチン。ジョークが苦手でクラシック音楽好きで自分の心に誠実であることを大事にしてKnoedelが好きなドイツ(バイエルン)。例外が多すぎるから英語は疲れる!枢機卿の2割程度しかラテン語はわからないから大事な発表はラテン語で。
強大な力を持つキリスト教には思うことがあるけれどこの映画を見て良かった。そして今のパパ、フランチェスコがなぜ愛されるのか少しだけでもわかって嬉しかった。
映像が美しかった。音楽では「ベラ・チャオ」が流れたのはドキッとしながらも嬉しかった。そして冒頭と最後のランペルドゥーサへのフライト予約には笑えた。どこへでも身軽に移動して皆と一緒に食事して語り合うフランチェスコには親近感を覚える。この世に変わらないものはない。神も動く。いい言葉がたくさんの映画でした。
このテーマをここまでポップに描き切るとは
あまり馴染みのないテーマゆえ本作にはハードルの高さを感じていたが、第92回アカデミー賞3部門ノミネートとの高評価にて鑑賞。
観始めると意外や意外、本作とはオープニングからすっかり打ち解けることができた。
白と赤のコントラストが映える鮮やかな映像と、まさかの「ダンシングクイーン」まで織り交ぜてくるポップな音楽、そして全く畏まらないテンポ良い会話等々、めちゃめちゃ観やすいではないか。
ある一定のシーンが長く続いたりするのだが、色々な角度から楽しめるから全く飽きない。
本作でもアカデミー賞にノミネートされた2人の演技はもちろん観応えあるのだが、ノミネートされなかったものの脚本の力も観逃せないと思う。
そしてカジュアル度マックスのラストシーンからのエンドロールへ。
このテーマをここまでポップに描き切るとは…お見事!
神々しい
一言「勉強になるわあ」。
ローマ教皇の選出選挙(コンクラーベ)や、生前退位はないとか。
「ローマ教皇の裏側見せます」的内容が、興味深い。
まずは左のアンソニー・ホプキンスが。
もうローマ教皇にしか見えない、憑依ぶり。さすがですねえ。
左のジョナサン・プライス(今作でオスカー主演男優賞・ノミネート)は庶民的だし。
手に届くはずもない存在の2人に、息吹が含まれてたなあ。
教皇になる前の、2人の生き様。
ドイツ出身と、アルゼンチン出身。保守派と改革派。
歴史的背景も含めて対照的なのに、通じ合う物がある。
その交わり方も温かい。
宗教的要素もあるけど、全然大丈夫。むしろ身近に感じられる1作。
⭐️今日のマーカーワード⭐️
「この世に偶然はない。全ては神の手の中」
血の流れないタイマン
カトリック教会のことなどダビンチコードで得た知識
くらいしか知らなかったけど、
ローマ教皇って自分を律してお堅い人かと思ってたけど
とても人間臭く描かれてて、
全く相容れない2人が、口論と言うタイマンの後に
親友になると言う構図はまるで
不良漫画だなと思いました。
アンソニーホプキンスもジョナサンプライスも
とにかく可愛らしい。
エンドロールのサッカー観戦なんて、
はしゃぐ2人をいつまでも観たいくらい。
ドイツ人とアルゼンチン人と言う2人から始まって
素晴らしい着地点だったと思う。
ベネディクト16世が全く考えの違うベルゴリオを
バチカンに呼び寄せた事、これが全てだと思う。
人はいつでも変われる。
妥協ではなく変われるんだ。と言う素敵なメッセージも
受け取りました。
おじいちゃん版グリーンブック
ベンチャー企業の社長のイチモツ・ポプランがある日猛スピードで空を舞い逃走。ポプランを取り戻すための道中、過去の自分と向き合っていく話。
まず、こういう題材でありながらも男子校ノリの下ネタに走ることがないのがとても良い。下品そうに思えて意外とスマートなコメディだったなと思う。
そして、ポプランは男性性の最たる象徴だと思うので、それを剥ぎ取られ、もう一度男らしさを取り戻すとき主人公は完全にただの少年になっていたのが面白かった。
剥ぎ取られるのはポプランだけじゃなく、ポプラン探しの道中、殴られ、かつて捨てたはずの女性に捨てられ、顔にアレがかかりもするし、ポプランを口に含んでしまったり、精神的にも"男"を剥ぎ取られていく。そして残ったのは純粋に漫画と虫取りが大好きだった少年。
仕事相手の漫画を1巻も読めない男は、元々オールジャンルの漫画を楽しむ漫画オタク坊やだった。この少年の純粋さってこの映画の笑わせ方に似てる。男臭いゲスな下ネタじゃなく、単純にポプランが逃げて暴れたら面白い。それでいいのよ。
最後に、ポプランを元に戻すのも、自分の穴にはめ込むというまた"男"を剥ぎ取る行為(男性にとって屈辱的な行為)だけど、その行為によって男性性を取り戻すのが上手い。
今回のレビューすごい丁寧な言葉で下ネタ書いてるだけな気がしてきた〜(笑)
信じるものは一つでも歩む道は異なる
コンクラーベ
レビュー
さりげないVFX
キリスト教徒のすくない日本では法王にたいして、えらい人という以上の主体的な感想はない──と思う。ましてスポットライトを見ていれば聖職にいい印象を持っていない。わたしもそれである。
ぜんぜん知らない世界ではある。ぜんぜん知らない世界なのに、聖職者による性的虐待は、むしょうに腹の立つことだ。それは、おもてむきでは説教をたれる人が、抵抗のできない子供の性をもてあそぶことの卑劣さを思うからだろう。
聖職者と信者とその子供は、泣き寝入りや箝口に至りやすい位相構造を持っている。そもそもキリスト教が歴史からして死屍累々の宗教なのもあって、あくまで雑感ながら、いい印象はない。
これは学校と教師に対する庶民感情にも似ている。
わたしはかつてよく殴られたので教師にいい印象はなかった。ただ年を食って、同級や知友として教師を持ってみると、ほんとに彼らは苦労されている。まともな教師と話すほどに、世間の論調がうそのようだ。とうぜん今となっては、教師を教師だというだけで貶す気にはなれない。
すなわち世論によって、あるいは一部の不埒によって、もっとも迷惑を被ってしまうのは、まじめな聖職者たちだろう。もし聖職者を知っていたら、かれらの苦労を共有できると思う。
ただこれは非キリスト教の雑駁な感慨であって、信者やヨーロッパ諸国人の感じ方とは異なるであろうし、もとよりぜんぜん知らない世界ではある。
この映画の敷居が高いのは、非キリスト教であることに加えて、法王とはいえ、ひとかわ剥けばご老人の話だからでもある。よくこれを配信したなと思う。
Netflixに関する余談ながら、──わたしが設定をよく解ってないからかもしれないが──、おすすめでも新着でもない奥深くに、とんでもない良作が隠れている。これもそんな映画だった。
とはいえわたしとて見たのはふたりの法王がレクター博士とサムラウリーだったからだ。とりわけジョナサンプライスはわたしにとって未来世紀ブラジルの人で35年経てもまだそれが抜けない。
役者に演じさせているにもかかわらず、映画はドキュメンタリーの構造をしている。人物の撮り方も、エイジングを施した挿入シーンも、感情/感傷を出さない演技も、滞りなく見られるが、裏に相当な特殊技術を感じた。巷間の人々も、バチカン広場を埋め尽くす観衆も、完全にシームレスに映画と融合している。
懺悔として教区内の性的虐待を看過したという件があった。そこで倫理的に解釈が別れるかもしれないが、映画はすごく良かった。
どの世界にもある正反対の2人だが流石は司祭。
面白かった!
「テリーギリアムのドンキホーテ」のキホーテ役の俳優さんがフランシス教皇役!
さて。
謙虚で質素で親しみやすく、サッカーとジョークが好き。ダンスも踊る。
弱い立場、貧しい人たちに寄り添いながら、考えを実行する行動力と、大きな組織に対しても臆せずNOと言える人物。今までのやり方にただ従うのではなく、その体制を切り崩し、階級制度を変えようとしている。
「祈り」とは、悩みや心配ごと、喜び、悲しみをそのまま神に伝えることだ。
願わくば、涙を流すなら悲しい涙より嬉し涙がいい。
傷付いた者がこれ以上傷付かないように。傷はシミではない。癒されるべきだ。
自らの良心の声に耳を傾け、決して裏切らない姿は、カトリックという宗教を超えて人々の胸を熱くさせる。だからこそフランシス教皇は稀代のロックスターと呼ばれるのだろう。
ベネディクト16世は、自分は神学理論家にすぎず、今日のキリスト教徒の現実の生活をほとんど理解していなかったと言う。彼とフランシス教皇との間に「内なるつながり」があることが、とても嬉しかった。
アンソニーホプキンスだからこそベネディクト16世の人間臭さもまた魅力的だった。
手ぶれ風のカメラで臨場感を煽らず、固定カメラで二人の演技を観たかった気もする。
全53件中、1~20件目を表示