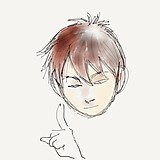世界の果ての通学路のレビュー・感想・評価
全3件を表示
ドキュメンタリーっぽくないのが凄い
日常を切り取っただけの作品。
その日常が凄い。
あーだこーだ言う以前に、生きることに一生懸命で、けどそんなこと感じさせない。象の群れからどうやって逃れるか、それだけを考えることにまっすぐで、長い距離をいかに楽できるかって純粋に考えて、タイヤがぶっ壊れても学校にいくことしか考えてない気持ちが、すごく自分自身を情けなくさせる。
いい映画。
演出感が残念でした。
これを見て単純に「日本に生まれてよかったね」とはならないでほしいなぁ…と思うこともしきり。
長時間かけて通学したら、オンボロ校舎の校庭にみんな整列して国旗掲揚してから授業開始という流れなど、おおと思います。
テーマは非常に良いと思います。
某フェスティバルで上映会があったので観賞させて頂きました。
が、最初はドキュメンタリーだと思って観賞していたのですが、途中で違和感。
歩いている子どもたちを様々なアングルで見せるのは、長時間一緒に歩いて撮った映像の編集なのでしょう。
しかし、凶暴なゾウから逃げる子どもたちを、どうやったら様々なアングルで撮って編集できるのでしょうか?
ゾウから逃げる子どもたちを背中から定点カメラで映す。逃げる最中に落とした水筒から水がこぼれる映像をアップで映す。
…私には演出されたハプニングとしか思えませんでした。
そう考えると、足を怪我してヒッチハイクというのも怪しい。
怪我をしたことは本当で、撮影者は手助けをしない条件だったのかもしれません。
ですが、あのトラックは本当に偶然そこを通りかかった善意の第三者だったのか?
トラックに乗り込む子どもたちを、外側と荷台側の両方から映し、さらに走り去るトラックを映す。
この流れを、一回でどうやって撮影したのでしょう。
カメラが複数台あったとしても、お互いが映らないようにすぐにポジショニング出来るものなのでしょうか。
そう思うと、全部「これ本当か?」になってしまう。
繰り返しますが、テーマは悪くありません。
ひょっとしたら、私自身が撮影技術に対して無知なだけなのかも知れません。
せっかく良いテーマで、色々と考えさせられる内容なだけに、そこの部分が気になってしまい、残念に思いました。
そのひたむきさに感動です
2012年のフランス映画で、ケニア、アルゼンチン、モロッコ、インドの4人の子どもたちに焦点を当てて、彼らの「通学」の様子と、彼らの学業を支える家族、授業の一コマを捉えています。
ケニアのジャクサン君11歳は、砂漠を素手で掘って水汲みをし、炭作りを手伝ったりしながら、7歳の妹サロメを連れて、毎年4~5人がゾウの襲撃にあって死亡するというサバンナの草原を通って片道15キロの道のりを2時間で毎日「通学」します。
アルゼンチンのカルロス君11歳は、山羊飼いの手伝いを終えてから6歳の妹ミカイラと共に馬に乗って、パタゴニア平原を通って片道18キロを1時間30分かけて毎日「通学」します。
3000m級の山々が連なるモロッコのアトラス山脈の辺境の村に生まれたベルベル人のザビラちゃん12歳は、家族の中で初めて学校に通える世代として、家族の期待を一身に背負い、片道22キロの山道を徒歩で4時間かけて、毎週寄宿学校まで「通学」します。
インドのベンガル湾沿いの漁村で足に障害を持って生まれたサミュエル君13歳は、車いすを2人の弟たちに押してもらい、片道4キロの悪路を1時間15分で毎日「通学」します。
どの道も、日本のアスファルト道のような道は皆無です。その道を彼や彼女は、時に命の危険を感じるほどに苦労しながらも、楽しそうに通うのです。
そして辿りついた学校で、本当に一所懸命勉学に励んでいるのです。
特に印象に残った授業はカルロス君の受けていた授業でした。
日本でいえば小学校5年生の授業で「搾乳のシステム」について教えているのです。メチャンコ実践的な授業ですよね(^^)
ジャクソン君は世界を見ることを夢見て飛行機のパイロットを、カルロス君は地元に貢献するために獣医を、ザビラちゃんは文盲の祖母や両親に支えられて医師を、サミュエル君は両親や弟たちの助けを借りながら、自分と同じような障害を持つ子どもを助けるために医師を目指し、懸命にいて気います。
本作は、その、清々しくもたくましい姿を淡々と描いた珠玉の作品といえると思います。
是非、小学生中学年以上の子どもたちに観てほしい作品です。
全3件を表示