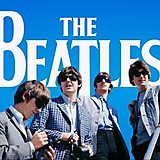遠い夜明けのレビュー・感想・評価
全17件を表示
【98.7】遠い夜明け 映画レビュー
作品の完成度
『遠い夜明け』は、その完成度において、深い考察に値する傑作である。本作は、アパルトヘイト下の南アフリカという重厚な社会問題を背景に、人間精神の尊厳と自由への希求という普遍的なテーマを、極めて高い芸術性と技術力で描き出している。その完成度は、個々の映画的要素が有機的に結びつき、観る者の心に深く、そして永続的な感動を与える点で特筆される。
物語構造における完成度は、特に際立つ点だ。白人編集者ドナルド・ウッズと黒人活動家スティーヴン・ビコという、異なる立場に立つ二人の男の絆と、彼らを取り巻く抑圧的な社会の現実を、克明かつ丁寧に描いている。ビコの思想と行動、そしてウッズの彼への共感と行動変容の過程が、非常に説得力をもって展開される。史実に基づいた物語でありながら、単なる記録映画に終わらず、登場人物の葛藤や感情の機微を深く掘り下げている点は、脚本の緻密な構成力と、物語を普遍的なヒューマンドラマへと昇華させる監督のリチャード・アッテンボローの卓越した手腕を示す。全ての要素が慎重に配置され、無駄なく、そして必然的に物語に貢献しているため、観客は寸分の疑念も抱くことなく、その世界に深く没入する。
視覚的要素、特に映像と美術衣装の統一感は、本作の完成度を最高レベルへと押し上げている主要因である。1970年代の南アフリカの風景や人々の生活が、緻密なリサーチに基づき、息をのむほどリアルに再現されている。美術は、単なる時代背景の再現に留まらず、アパルトヘイトという不当な社会構造が人々の生活に与える影響を視覚的に表現し、物語のトーンを深く強調する役割を担っている。衣装もまた、当時の社会階層や人々の心情を正確に反映し、視覚的な情報として物語に圧倒的な深みを与えている。これらの要素が、アッテンボロー監督の明確なビジョンに基づいて一貫して構築されているため、作品全体に説得力のある、そして胸を締め付けられるような世界観が確立されている。これは、単なる再現ではなく、物語に生命を吹き込む芸術的創造の極致と言える。
作品全体のテンポ配分は、熟練の技巧が光る。物語の序盤は、ビコの思想と彼が直面する現実をじっくりと描くことで、観客が彼に感情移入しやすい強固な土壌を築く。そして、ビコの死を境に、ウッズが真実を追求し、家族を連れて国外へと脱出する後半へと物語の進行が加速する。この緩急のつけ方は、物語のメッセージをより強く、より普遍的なものとして観客に訴えかけるための計算し尽くされた戦略であり、結果として完璧なバランスを生み出している。
音響設計と音楽の統合もまた、作品の完成度を語る上で不可欠な要素だ。南アフリカの民族音楽や、シーンに合わせた荘厳なオーケストラ音楽が、物語の感情的な起伏を効果的に増幅させ、観客の心に深く響き、忘れられない印象を与える。特に、アフリカの大地の音や、人々の声といった音響効果は、物語の舞台となる世界のリアリティを極限まで高め、視覚情報と相まって観客の没入感を究極のレベルへと引き上げている。
総合的に見ると、『遠い夜明け』は、その重厚なテーマと、それを具現化するための多岐にわたる映画的要素の統合において、まさに至高の完成度を誇る。物語の骨格、視覚的表現、そして音響設計のそれぞれが最高水準で結びつき、観客に深い感動と魂を揺さぶる考察を促す。この作品は、観客自身の内面と響き合うことで、その価値をさらに高め、映画芸術の到達点の一つとして永遠に語り継がれるべき傑作である。
監督・演出・編集
リチャード・アッテンボロー監督による演出は、物語の繊細な感情の機微を捉え、登場人物の内面を極限まで深く掘り下げた。特に、アパルトヘイトという不条理な社会システムの中で、人々が直面する苦悩や希望を、沈黙や視線が雄弁に語る場面を多用することで表現。これにより、観客に登場人物の苦悩や葛藤を想像させる余白を与え、感情の奥行きを無限に広げた。映像は常に詩的な美しさを湛え、広大なアフリカの風景や、抑圧された人々の日常を克明に捉え、一つ一つの絵が観る者の心に深く刻まれる。編集は、物語の複数のフェーズ、特にビコの生前の活動と、彼の死後のウッズの行動を、シームレスに繋ぐことで、複雑な時間軸を完璧にまとめ上げた。異なる時間軸のシーンを巧みに繋ぐモンタージュは、観客に一切の混乱を与えることなく、物語の多層性を際立たせる効果を最大限に引き出した。その洗練された編集は、物語の進行を加速させながらも、感情の余韻を完璧に残す、まさに職人技である。
役者の演技
主演
ケヴィン・クライン(ドナルド・ウッズ役):主人公ドナルド・ウッズが、アパルトヘイトという理不尽な現実と向き合い、友人ビコの死を通して人間としての成長を遂げる過程を、全身全霊で表現した。当初の政治的無関心から、ビコの思想に触れ、彼の死後、真実を世界に伝えるために命がけの行動に出るまでの心の変化を、非常に繊細かつ力強く演じきった。彼の表情は常に微細な変化を伴い、観客に彼の心の動きを克明に、そして生々しく伝えた。特に、ビコとの深い友情を育む過程での温かい眼差し、そして彼の死を知った時の絶望、家族を守りながら国外脱出を図る際の緊迫した面持ちは、観客の感情を強く揺さぶる。身体全体を使った演技も秀逸で、言葉にならない感情を巧みに表現し、観客を物語の世界へと完全に引き込んだ。彼の演技は、単なる役柄の再現に留まらず、普遍的な人間の心の動きと尊厳を描き出すことに成功した。
助演
デンゼル・ワシントン(スティーヴン・ビコ役):南アフリカの反アパルトヘイト活動家、スティーヴン・ビコという歴史上の重要人物を、圧倒的なカリスマ性と知性、そして静かなる情熱をもって演じきった。彼の存在は、映画全体に深い精神性と倫理的な重みを与え、観客に深い感銘を与えた。彼の演説シーンは、その力強い言葉と説得力のある眼差しによって、観客の心に直接響き、ビコの思想がいかに人々の希望であったかを雄弁に物語っていた。拷問を受けるシーンでの、決して屈しない毅然とした態度は、彼の信念の強さを際立たせ、観客に深い感動と尊敬の念を抱かせた。
ペネロープ・ウィルトン(ウェンディ・ウッズ役):ドナルド・ウッズの妻ウェンディとして、夫の危険な行動を支える妻の葛藤と愛情を繊細に演じた。彼女は、夫の安全を案じながらも、彼の信念を理解し、共に困難に立ち向かう強さを表現。特に、家族の安全が脅かされる状況下での彼女の不安と覚悟は、観客に深い共感を呼んだ。夫を支える献身的な姿勢と、自身の内に秘めた強さを見事に両立させた演技は、物語に人間的な温かみとリアリティを与えた。
ジョン・ソウ(ディオン・クロスビー役):クレジットの最後に登場するジョン・ソウは、南アフリカ警察の幹部ディオン・クロスビー役で、短い出演時間ながらも、その圧倒的な存在感で強烈なインパクトを残した。アパルトヘイト体制の冷酷さと、その中で職務を全うする人間の複雑な心理を、言葉少なに、しかし鋭い眼差しと表情の変化で表現。彼の登場は、物語の緊迫感を一層高め、主人公たちが対峙する巨大な権力の象徴として、観客に深い印象を残した。
脚本・ストーリー
ジョン・ブライリーによる脚本は、複雑な人間関係とアパルトヘイトという社会的な現実を、極めて丁寧に描き出し、観客の心を深く揺さぶった。ジャーナリストの視点から描かれることで、客観性と同時に、人道的な問題への深い洞察がもたらされる。ストーリーは、絶望的な状況下から自由と希望を見出すという普遍的なテーマを扱いながらも、安易な解決策に逃げず、人間の内面的な葛藤と尊厳をどこまでも深く掘り下げた。スティーヴン・ビコという実在の人物の思想と死、そしてその死が周囲の人々に与える影響が克明に描かれ、観客に強いメッセージを投げかける。各登場人物の背景が丁寧に描かれ、それぞれの行動原理が完全に理解できる点は、物語に説得力と真実味を与えている。その緻密な構成は、まさに完璧と呼ぶにふさわしい。
映像・美術衣装
フレディ・フランシスによる映像は、作品の世界観を構築する上で極めて重要な、いや、不可欠な役割を担った。特に、広大なアフリカの風景、抑圧された人々の生活、そして緊迫した社会情勢を、コントラストの効いた色彩と光の表現で描き出し、視覚的な情報として物語に深遠な深みを与えている。美術は、1970年代の南アフリカの街並み、家屋、そして警察の施設に至るまで、驚くほどリアルに再現し、作品に計り知れない説得力をもたらした。細部にまでこだわり抜かれた小道具やセットは、観客を物語の世界へと完全に誘い込む。衣装は、登場人物の社会階層、民族性、そして彼らが置かれた状況を的確かつ芸術的に表現し、視覚的な情報として物語を完璧に補完した。
音楽
ジョージ・フェントンとジョナス・グワングワによる音楽は、物語の感情的な起伏を効果的に増幅させ、観客の心に深く、そして永遠に響いた。特に、南アフリカの土着的な音楽と、オーケストラの壮大な調べが融合し、希望、悲しみ、そして闘争の感情を見事に表現。静かで叙情的なメロディは、登場人物の心の痛みを表現し、観客の涙腺を刺激する。緊迫したシーンでは、不安を煽るような不協和音が効果的に使用され、物語に極度の緊張感を与えた。主題歌「"Cry Freedom"」は、歌手ウィリー・ンゴマの魂のこもった歌唱により、作品全体のメッセージを集約し、観客に深い余韻を残す。その歌詞は、物語のテーマと深く結びつき、鑑賞後も長く心に残り続ける、まさに傑作である。
受賞・ノミネート
『遠い夜明け』は、その芸術性と社会的なメッセージが高く評価され、数々の映画賞で受賞・ノミネートを果たした。第60回アカデミー賞では、助演男優賞(デンゼル・ワシントン)、歌曲賞("Cry Freedom")、作曲賞の3部門にノミネートされた。また、第45回ゴールデングローブ賞では、監督賞(リチャード・アッテンボロー)、男優賞(ケヴィン・クライン)、助演男優賞(デンゼル・ワシントン)、作曲賞など、主要部門でノミネートされるなど、国内外で比類なき高い評価を獲得した。特に、デンゼル・ワシントンの演技は高い評価を受け、その後のキャリアを確固たるものにするきっかけとなった。
作品 Cry Freedom
監督 リチャード・アッテンボロー 138×0.715 98.7
編集
主演 ケビン・クラインS10×2
助演 デンゼル・ワシントン S10 ×2
脚本・ストーリー 脚本ジョン・ブライリー 原作ドナルド・ウッズ S10×7
撮影・映像 ロニー・テイラー S10
美術・衣装 美術スチュアート・クレイグ
衣裳デザインジョン・メロー A9
音楽 ジョージ・フェントン ヨナス・グワングワ A9
差別の歴史が常識である怖ろしさ
事実に基づいた作品なので背筋が凍る。身の回りにない幸福を感じる。作品中説明されるように何百年も前に移住した人々の苦労があったにせよ、近代的な軍事力で押さえつけられたら堪らない。しかし、それが正当化され自分たちに都合の良い歴史になっていく。そうなると、簡単に修正は効かない土壌ができ上る。その怖ろしさは、瀕死のビコを診断する医師が救命措置を主張しきれない場面、捻じ曲げた死亡報告に迎合する出席者の発言、に象徴される。彼らは一人一人は善良な市民のはずで、自分たちは何一つ間違ったことはしていない感覚。沁みついた文化が見ていて悲しすぎる。おそらくその感覚は、主人公のジャーナリストにもあったのではないか? だから当初はビコと距離を置いていた感じ。
後半は、真実を伝えるべく命を懸けた亡命劇で、事実だからわかっていても、緊迫したシーンの連続で手に汗握る。悲しい題材と厳しい現実の描写に留まることなく、名匠はエンタメ的な構成で良い作品に仕上げたとと思う。
重い内容ですが見応えがあって良かったです。是非観て欲しいです。
南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策に立ち向かった黒人運動家のスティーブ・ビコ。ビコを取材する内に魅了され共鳴していった新聞社の白人編集者ドナルド・ウッズの自由への闘いの壮絶な物語。 体制側の警察や政府に目をつけられた2人は弾圧を受けることになるのだがその凄まじい内容に驚きました。 映画の原作はビコの死後、アパルトヘイトの実態を国外に知らせなくてはとの思いで命がけで国外に脱出したウッズにより出版された本である。 原作はヨーロッパにアパルトヘイトの実態を知らしめヨーロッパにおける反対運動のきっかけになった。 出版から9年後に映画が制作されるがまだアパルトヘイト政策は続いていた。ウッズ夫妻は映画の監修にも参加した。 アパルトヘイトが撤廃されるのにはさらに7年の年月を要した。その間にも多くの人が犠牲となった。 重いですがとても見応えのある内容でした。非常に緊迫感があり恐かったです。是非エンドロールの最後まで観て下さい。
圧巻の154分
アパルトヘイト政策下の、黒人活動家と南アフリカの新聞記者の話。
正直な話、よく似た話は結構作品を観ているのですが。
いやいやどうして、これがどうして驚きの連続。
活動家は対話を重視し、民衆を煽るタイプじゃない。
「私達は平等に扱われたいだけ、同じ弱い人間なのです」。
そこに記者が共感し、影響を受けていく。
後半は、事実を公表するため。記者が国を脱出しようとする。
ええ〜、5人の子供と一緒にって。そっちか!。
まさかのドキドキの展開。
「ビコ(活動家)の友人は、我々の友人」。
友達の友達は、皆友達。心に訴えるものがありました。
これが全部実話なんて、全く知らなかった・・・。
⭐️今日のマーカーワード⭐️
「いつかは正義が勝つと、言ってくれ」
1970年代の南アフリカを見れて良かった。リアリティ重視の映画で内...
ハンガースト
合法な不正義を潰すのは市民運動しかない。日本はどうする?
これは、アパルトヘイト時代の南アフリカが舞台である映画です。1987 年に制作されました。南アフリカは、今でこそ BRICS の一角を占めますが、制作当時は、国際的に経済制裁を受けていて、オリンピックにも出られませんでした。その理由は、アパルトヘイトです。
アパルトヘイトとは、南アフリカの人種隔離政策のことです。政府は、白人だけから構成され、大半の黒人を狭い居住区に押し込めていました。日本では、中学校の社会の教科書にも、アパルトヘイトが紹介されていたため、当時は広く知られていました。この映画が公開された数年後に徐々に差別制度が緩和されていきました。そして、1994 年、全人種による選挙が行われ、弁護士、反アパルトヘイトの闘士で長く獄中にあった、黒人のネルソン・マンデラが大統領に就きました。現在(2023 年)、40 代以上の人は覚えている人も多いでしょう。
さて、映画に話を戻しますと、これは実話に基づく物語だそうです。登場人物はほぼ実名とのこと。
1977 年、スティーブ・ビコは、南ア政府の保安規則により、移動や面会の自由が制限されていました。彼は、黒人解放運動の指導者で、非常に知的です。ドナルド・ウッズはリベラル紙の編集長で、初めはビコを批判していましたが、次第に彼を支持するようになります。
この作品は、事実上、二部構成となっています。第一部に相当する場面では、アパルトヘイトの圧政、それにビコが反対して運動を起こし、政府はそれを弾圧し、ウッズも新聞を使って政府を批判します。第二部に相当する部分は、ここで詳細は伏せますが、打って変わってハラハラの逃避行です。それが避けられないことは第一部があるからこそ伝わるものです。是非、作品を観てください。
この作品には、正義には悖[もと]るけれど、合法な警察や裁判所が何度となく現れます。冒頭で、白人警官が何台ものトラックで黒人居住区のバラックを襲撃し、女子供の区別なく彼らに暴行し逮捕監禁します。こういうことが頻繁に起きる事が暗示されます。政府からは、この悪行が「公衆衛生上の保護」として合法だと発表されます。暴力は隠蔽され、白人の国民は差別に負い目を感じなくて済みます。こうして、不正義が適法として処理されてしまいます。
ところで、これは、遠いアフリカの昔話に過ぎないのでしょうか。僕は、そうではないと思います。例えば、公金を権力者やその縁故に流用したら、それが法的には問題なくても、不正義でしょう。罪を犯したのに、それが権力者に近いと言うだけで罰せられなければ、その手続きがいかに適法でも不道徳でしょう。こんなことが続くと、社会は壊れてしまわないでしょうか。と言うか、壊れ始めていますよね。
南アフリカでは抵抗運動が差別を終わらせました。日本はどうでしょうか。
多大な犠牲の元に独立を勝ち取ったとの想いは解るが…
随分と久しぶりになったが、
ビコが半分も経過しない中で
亡くなってしまうことなども
すっかり忘れていた中での再鑑賞となった。
また、少し前に「ソフィーの選択」を
観たばかりのだったので、
そこでのケビン・クラインとの比較も
楽しみだったが、
まるで印象の異なる演技には驚かされた。
また、アッテンボロー監督の
「素晴らしき戦争」「遠すぎた橋」「ガンジー」等
の大作感溢れる作風はここでも生きていて、
特に前半の緊迫感溢れる描写に、
作品の世界にゆったり浸ることが出来た。
ただ、終盤の逃走劇は、
地理的な浅識もあってか、
臨場感不足になってしまい、
結果、少し冗長に感じてしまったのは、
私にはマイナスの構成だった。
そして、エンディングシーン、
独立のための、
数多くの黒人指導者や住民の犠牲の元に
植民地支配的国家を勝ち得たとの描写である
ことは理解するが、
一方で、ビコが夢見て、マンデラが実現した
人種融合の国家を
勝ち得たことでもあるのだから、
その人種融合へ繋がるエピローグで
締めた方が、
よりテーマに沿ったエンディングになった
ような気はした。
勇気ある行動と尊い犠牲
ひたすら真面目な社会派
軽い気持ちで見始めたので大変だった
ちょっとこれでも見てみるか、という軽い気持ちで見始めたので大変だった。
面白いか、というとそうではない。ただ、そういう評価でやっつけるのも違う映画。基本、主観でしかないので、おもんないものはおもんないで片付けるけど、これはそれを阻む力がある。
映画、ということで言うと、長い。前半のビコと後半の亡命で流れが変わる。そこで疲れてしまう。ベタな映画でいうと、これどちらかに絞って一本作ると思う。実際そのほうが目的が鮮明になるし観る方も観やすい。
まあ、観やすい映画の見過ぎだな。そのせいで、こういうの評価できなくなるとまずい。。
ラストの暴動回想と飛び去る飛行機、死因リスト。ここに辿り着くまでの時間を省略はできない、その意図がちゃんと伝わるつくりになっている。
後半はほとんどサスペンス映画のよう。
決して悪くはないが…
映画全体として悪くはないが、ウッズの亡命後のストーリーまで描いてほしいと思った。あえて描かなかったのが、それとも描けなかったのかはわからないが、ハッピーエンドは避けたかったのだと思う。ゆえにラストの方はウッズ家族の絆的なファミリー映画感があったのは否めない。ケビン・クラインとデンゼル・ワシントンの演技は見事。
観て損はない
全17件を表示