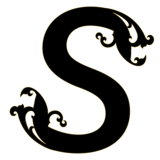さよならはスローボールでのレビュー・感想・評価
全57件中、1~20件目を表示
草野球をするおじさんたちを眺めるだけの映画なのに
この作品は、長年地元で愛されてきた野球場が中学校建設のために取り壊されることになり、そこでおじさんたちが最後の草野球をする――ただそれだけの映画。
特にドラマチックな展開も、感動的なエピソードも、手に汗握る試合シーンもない。
始終グダグダな試合運びで、決して野球がうまいとは言えず、突き出たお腹、もたついた足、空を切るバット……カッコいいシーンなんてひとつもない。
正直、途中から「私はいったい何を見せられているんだろう」と思ってしまった。
けれど、不思議なことに時間が経つほどに、胸の奥にじんわりと哀愁が広がっていく。
言葉には出さないけれど、「最後の試合が終わってほしくない」という彼らの気持ちが伝わってきて、当たり前のようにそばにあった大切な時間や関係が終わっていく寂しさが、自分の記憶とも重なって蘇ってくるのだ。
そんな彼らを見て、日常の何でもない時間の積み重ねこそが、実はかけがえのない特別なものなのだと気づかされた。
鑑賞後は、少しだけ胸にほろ苦い余韻を残しながら、自分の“今ある日常”を静かに噛みしめたくなる一作だった。
この空気感は、体験してみないと分からない
脱力系、オフビート、大人たちの放課後。本作を形容する言葉は数多くあるが、結局のところ実際にその目で体験しないとオムネス・フィルムズ一味の目指すテイストはわからない。おそらく彼らはストーリーの束縛から遠く逃れ、その瞬間に立ち現れる構造や空気感によって何か特別なものを表現しようとしている。いかに思いきって身体を預け、草野球の持つ時間軸、中年大人たちの心によぎる「今日が最後」という切なさに触れられるか。それが本作を楽しめるか否かを分けるポイントだろう。かくいう私は、放たれる心地よい映像世界が不思議な角度で自身のキャッチャーミットにズバンと収まった。一見、何もない。しかし何かがある。噛めば噛むほど味が出る。観客に委ねられているといえばそれまでだが、我々もまた仲間として球場内に立って時間と空間を共有し、この二度とは戻らない「最後」を味わっているかのよう。世界も人生も、さよならの積み重ねでできている。
休日難民たちのララバイ(からの地獄変)
スコアラーによるメジャーレジェンドの名言が秀逸
本当におっちゃんたちの草野球を観る映画だとは!
当然、野球場🏟️のワンシチュエーション。
日頃から野球をしているメンバーだから
ちゃんと試合になっていて、
彼らの会話が実にリアルでクスッと笑える面白さ。
個性もわかって、たくさん人が出ている割に
なんとなくどんなキャラなのかはわかる。
しかしながら、薄暮から夜になってのプレーが冗長すぎ
且つ厭戦ムードも伝わってきて、
これは苦痛だった。
だけど、こういうグダグダな終わり方をしたかったの
だろうな。案の定、私は数回意識が飛んだ。
それもまた良し、の作品だと思う。
セルフエコーコーコー・・・
夏の高校野球甲子園のようだ…
今年のフェイバリット3本に入る作品
空気感はおじさんとはいえまるで夏の高校野球を観ているよう
もう2度と同じ場所で同じ仲間とは野球ができないエモさが全編を支配している
この映画にスーパープレイや陳腐なストーリーなんていらないしないからいい
同じオムネスフィルムズの「クリスマスイブインミラーズポイント」と同じ人生の失われるものへの懐かしさと切なさが押し付けがましくしない感じが好きだな
ヤマなしオチなしやる気なし?だが、それがいい。
たんたんと、ただひたすらたんたんと。。。
スコアラーがジャック・レモンに似ている
何時間草野球やってんのかと
It ain’t over till it’s over. (終わるまでは終わらない) ニューヨーク•ヤンキースの名捕手ヨギ•ベラの言葉より
取り壊しの決まった野球場に男たちが集まって草野球をする、ただそれだけの映画です。タイトルにあげたヨギ•ベラの名言のように試合というのは終わるまでは終わらないので、ちゃんと終わるまでやります。試合は劇的というほどでもないけど、まあそこそこ劇的で、かつ、ありがちだよなという決着のつきかたをして終わります(今さらながら気づいたのですが、野球ってホームラン打ってもエラーしても死球を受けても、どんなプレーをしても、どこか劇的に見えてしまう競技なんですね)。試合が終わるとプレーしていた男たちは球場を去り、映画も終ります。
観ていて、これ、いつ頃を舞台にしたお話だろうか、というのが気になりました。携帯電話は登場しません。男たちが球場に乗りつけてきた車や球場の片隅に置いてあったラジカセから推測するに1980年代末から90年代半ばぐらいかなあと思いました。となると、こいつら、自分と同年代から少し上ぐらいにあたるのか、と少し嬉しくなりました。その頃、職場の仲間たちとした草野球のことを思い出しました(軟式ですけどね)。軟式のボールは時折り変なバウンドの仕方をします。私がセカンドを守っていたときに自分の前に右バッターが打った小飛球が飛んできて、前に突っ込んでダイレクト•キャッチを試みるか、ワンバウンドで処理するかで迷いました。結局、待ってワンバウンドで取って一塁に投げてアウトにしようと判断したら、そのワンバウンド目がポーンと高く跳ね上がり、私の頭上へ。私は咄嗟に両手を上げてバンザイみたいな格好で斜め後方にジャンプしたのですが(と本人は思ってるけど実際はどうだったのやら)、打球は私の頭上をこえてセンター前へ。そのときの私の格好がよほどおかしかったらしく、味方の苦笑、相手方の大爆笑を呼ぶこととなりました。他の守備機会は無難にこなして併殺に参加したりもしてたんですけどね。このワンプレーがかつての宇野選手のヘッディングほどではないにしろ、しばらく語り草になったのでございます。
閑話休題で、この映画の話。日本には「団塊の世代」という言葉があって、1947年から49年の3年間に生まれた人々を指すそうですが、アメリカの「ベビーブーマー」という言葉にはもっと幅があって、おおよそ1946年から64年ぐらいまでに生まれた人たちを指すとのこと。これ、先ほどの年代の推測があってるとすると、この映画で草野球をやってるメンバーというのはベビーブーマー•オールスターズになると思います。この草野球が醸し出す哀愁というのは、青春時代をへて社会の中心になって活躍していたベビーブーマーが絶頂期からそろそろ老境にさしかかってきたというのを示唆しているのかもしれません。
ところで、この試合にはそんな年代には当てはまらない、白髪の老左腕投手が登場します。どこからともなく現れ、リリーフ投手としてマウンドに上がり、イーファスと呼ばれるスローボールを駆使して1イニングをピシャリと押さえ、そのイニングが終わるといなくなります。あの白髪のリリーバーは誰だったのでしょう。ひょっとして、球場に住んでいた精霊だったのでしょうか。
この映画にも出てくるのですが、野球でバッテリーと呼ばれる投手、捕手のコンビの話。「お前と組めてよかったぜ」とか言ってるんですよね。この映画を観ていて、誰が言ったか忘れてしまったのですが、バッテリーに関する名言を思い出しました。「俺たちが死んだら、一緒の墓地に埋めてくれ。墓石は迎え合わせにしてな。そして墓石間の距離は60フィート6インチ」。この60フィート6インチというのはバッテリー間の距離です。
いやあ、野球って本当にいいもんですね。
さよならゲーム
さよならはベビーブーマーへの挽歌
原題は"EEPHUS"。MLB用語で山なりの超スローボールのこと。
結論から言って、私の感想としては「かなりクセは強いが、悪くはない」。
ただし、この映画は少々秘孔を突かれないと刺さらないので、恐らく大いに評価が分かれる映画だろう。
アメリカの田舎町の爺さんたちが、廃止予定の球場でドタバタと最後の草野球をするコメディだと思って映画館に行けば、間違いなく当てが外れる。
平板なストーリー展開にはうんざりして途中退席する人も居るだろう。
さりとて特別アーティスティックな香りの仕上がりでもなく、何かのファンタジーでもない。
なので、低い評価が多くなるのは無理もない。
むしろコアなミニシアターでかかりそうな、カルト的な作品とも言えるが、それでもハコ側としてはけっこう勇気の要る買い付けだろう。繁華街のミニシアターで2〜3週間で打ち切られて、しばらくしてからちょっと郊外に流れて来るようなイメージだ。それでも客席はまばらだろう。
良くもまぁ、ヒューマントラストシネマで初公開したものだと、妙な感心をしている。
この作品は、普遍的な感情を強く揺さぶらない。そういう設計もされていない。
文化や文脈を共有しないオーディエンスを端から無視しているとさえ思う。
もちろん、長年地元の草野球チームに愛されてきた場がなくなることによって、ガキの頃からここで育った中高年たちの「居場所がなくなる悲哀」を丹念に描いている、という意味では共感は(少しは)呼べるかもしれない。
ただ、それではあまりにも陳腐な、今までにさまざまな作品で語り尽くされてきた物語だ。その割には語り口に新味はない。
あるのは、ただひたすらに極私的なノスタルジーであって、その描き方が常軌を逸しているレベルでベタなのだ。
--------------------
ほとんど劇伴がない中で、ラジカセから聴こえてくるのは地元商店の宣伝と街のニュースばかり。
それだけでここが半径5km程度のスモール・タウンの世界なのだ、ということが良く分かる。
むしろ、このだらだらと鳴るラジオが作品の最初から最後まで、特定の鑑賞者にだけ刺さるように意図的に使われている。
それは試合が終わって誰も居なくなるダグアウトでも鳴り続けている(あれは誰の持ち物で、誰が持って帰るのだろう?とふと思った)。
--------------------
両チームは野次で罵りあっているけれど、全員、お互いの人柄や家族のことを骨の髄まで知っているだろう。
そこには分断すらない。
乗り付ける車に日本車など1台もない。V8の野太い咆哮を発するアメ車のセダンやピックアップ・トラックばかりだ。
それで1970年代の終わり頃か?とも思ったが、温存される隣のサッカー場で若者がプレーしているのが何度か映るので、サッカー人気の興隆と「おやじの野球」の凋落ぶりが対比されている。ということは1990年代末以降かもしれない。
その年代でこの雰囲気ということは、本当にかなりの田舎だと思う。
--------------------
季節は、ハロウィン・セールのCMが聞こえるが、別れ際に「良い感謝祭を」と言い合うような、北米では日が暮れればあれほど吐く息が白くなる晩秋だ・・・。
--------------------
こんな、極めて特殊でハイコンテクストな設定を煮詰めた作品であることを覚悟しないと、何が何だかわからない。
そういう意味では変態A24の『TVの中に入りたい』に通じるセンスがある。
ただし『TVの中に入りたい』は、現実にあったであろう一種独特なファンタジーチャンネルの番組に囚われ続けるティーンエイジャーたちとそのセクシュアル・マイノリティを重ね合わせていたので、極私的な世界線がわかりやすい。
しかしこの『スローボール』は、一見日本人にも馴染みが深い草野球がモチーフなので、実はそこに描かれた時代性やアメリカ東海岸の中~下層社会のいわば符牒のような表現が却ってわかりにくい。
われわれが感じる脱力系の笑いと、まさに当事者たちであるあちらの人びとが受け取る笑いのほろ苦さは、自ずとまったく違うはずなのである。
恐らくそれは、「アメリカ社会の最後のベビーブーマーへの挽歌」であると思う。
別のYouTubeで、昨年開催された第62回ニューヨーク・フィルム・フェスティバルでカーソン・ランド監督と”エド”役(赤チームの監督兼投手で途中で姪の洗礼式のために居なくなる人)をやったキース・ウィリアム・リチャーズを招いたトークイベント動画が見られる。ここでリチャーズは、映画でのキャラと設定はまさに自分たちのことだという前提で話している一方、自分の年令を61歳と言っているので、つまり1963年生まれだ。
アメリカの「ベビーブーマー」は一般的に生年が1946年から1964年までの幅広い世代と言われている。だからまさに彼らは「アメリカの戦後」を代表し、その世代の最後の幕引きをする役割を持っているに違いない。
また、監督のランドは、東海岸北部のニューハンプシャー州で生まれ育ったと言っている。このことも舞台となったソルジャー・フィールド球場の周囲の森や紅葉、夕方以降の冷え込みを想像させるし、両チームのメンバーの顔ぶれにも頷ける。
多くは白人だが、白人の中にも東欧系のルーツを持つ者やイタリア系らしき人、白人以外ではアフリカ系もわずかながら居る。この顔ぶれはいかにも東海岸だ。
こうした記号がいくつも散りばめられているが、ひょっとするとアメリカ国内だって極端な話、西海岸で生まれ育った人にはまったくピンとこない映画なのかもしれない。
だからこれがカンヌの監督週間部門に選出された、というのが不思議で仕方ない。コンペティション部門でもある視点部門でもないので、勝手に想像すると「かなり変わった監督」をピックアップしたとも考えられる。
最後に。
やや『フィールド・オブ・ドリームス』っぽいキャラクターが一人いた。
突然森の奥から現れた、プレイヤーたちよりちょっと年上の世代の自信満々の男性で、選手不足を嘆く青チームのワンポイント・リリーフで三者アウトを取り、いつの間にか居なくなっている。また森に消えたのか。
スコアブックを付けるのが趣味の観客、老フラニーは「ああ。確かに見たことがあるやつだった」と呟く。
それは、ひょっとするとかつてこの球場でプレーし、ベトナムから帰ってこなかった男かもしれない。
あるいは、この球場の「野球の精」かもしれない。
あるいは、歴代この球場でプレーしてきた人たちの念の化身かもしれない。
しかしそのキャラクターも特に印象付けるような演出ではなく、「あれれ、今の人、何?」と拍子抜けしてしまうような、場合によればいとも簡単に忘れてしまうような位置づけで、さらりと描かれている。
この不思議なキャラの登場のさせ方と見せ方は、『スローボール』という作品のテイストの本質を物語っているような気がする。
そして、原題がなぜ「超スローボール」なのか。
徐々に退場していく世代が、その後のGenXやZ世代にがつんと速い球を投げ込むのではなく、人を食った超スローボールで「打てるものなら打ってみろw」と表現したかったのか。
それとも、もう速球なんか投げられないぜ、勘弁してくれよ、あばよ小僧ども、という寓意か。
超スローボールのイメージと、「最後の記念すべき試合」なのにぐだぐだと終わってしまうことと、冬にはまた集まろうな、という呼びかけに生返事で「ああ」と答えるがたぶんもう絶対に集まらないだろうことと、スコアブックと折りたたみ椅子を脇に抱えて車ではなく徒歩で闇に消えていく老フラニーの後ろ姿が、全部重なってえも言われぬ余韻を残す。
そんな、ちょっと心苦しい映画だった。
さて、これからどうしようか……
草野球をするおじさんたちを淡々と描いただけの映画なの。
試合してる野球場が閉鎖されることが決まってて、最後の試合なんだよ。それを描いてんの。
ただ淡々と描いてるからね。どう観ようが観る方の自由なんだけど。
なんか置いていかれる人たちとか、かえりみられることのない人たちとか、そういう人たちの話として観たな。この人たちはトランプに投票するだろうなとか思ったの。
野球場閉鎖して中学校ができるんだよね。いまは遠くにしか中学校ないんだって。
この設定がうまいんだよ。
誰でも普通に考えて、草野球しかやってない野球場残すより、中学校つくる方がいいんだよ。文句言えない。草野球やってるおじさんたち自身も文句言えないことは知ってんの。
でもそこが、かけがえなく大事な人たちだっているんだよ。超少数だろうけど。
その人たちのことは誰か考えてくれんのかっていう。
まあ、考えないんだよ。考えてもらえないことはおじさんたちも知ってる。
どうも一方のチームの監督だかキャプテンだかの人が、中学校建てようって言っちゃったみたいなんだね。だからみんな「裏切り者が」みたいなこと言っちゃうんだけど、そう言うのは理不尽だって知ってんだけど言わずにいられないの。
この監督だかキャプテンだけが、バリッとしてんの。野球場なくなっても、仕事でバリッとやんだろうなって感じなの。居場所があるんだよ。
あとは米国の野球文化みないなのいいなと思った。
野球選手の名言をひいてくるんだけど、それがカッコいいの。
日本だと「永遠に不滅です」ぐらいから、名言がなくなっちゃてる気がするのね。知らないだけかも知れないけど。ちょっと文化の点で、米国にはかなわない。
娘さんが Take Me Out To The Ball Game 歌うけど、いいね。歌詞を始めて真剣に観た。
これ、なんとなく観てたけど、七回だから歌ったんだね。そういうところもいい。
それで原題が《EEPHUS》なんだけど、山なりのボールをこう言うんだね。
水島新司が超遅球を武器にするピッチャーの話を描いてたことあったけど、こんな感じなのか。
このEEPHUSの感じが、作品の感じに合ってて良かったな。
最初と最後に引用されるのがルー・ゲーリッグのLuckiest Man Speechなんだね。
スコアブックをつけてるお爺さんが真似するんだけど、最後に「さて、これからどうしようか……」みたいなこと言うよね。
野球がある間はLuckiest Manなんだけど、それが終わってしまうと途方に暮れるしかない。
そういうことを観ていて思ったな。
休日にこうしてスケジュールを調整して、少なくとも球場に集まって来られる程度には健康体をキープしている時点でまず偉いのである
地元で長く愛されてきた野球場<ソルジャーズ・フィールド>は、中学校建設のためもうすぐ取り壊される。毎週末のように過ごしてきたこの球場に別れを告げるべく集まった草野球チームの面々。言葉にできない様々な思いを抱えながら、男たちは“最後の試合”を始める…(公式サイトより)。
公式サイトのイントロダクション文以上でも以下でもない、特に何も起こらない映画。だが、中年になってもなお、特にチームスポーツを楽しんでいる人なら共感ポイント目白押しの作品だ。
スポーツは最終的にはどっちが強いか決める。それはメジャーリーグでもおじさん野球でも同じである。だが、おじさん野球の場合は、休日にこうしてスケジュールを調整して、少なくとも球場に集まって来られる程度には健康体をキープしている時点でまず偉いのである。次に、ビール腹だろうが、腰が痛かろうが、いま持っている技術と身体能力で、勝利に貢献しているかどうかはいったん置いておいて、とりあえずその場は一生懸命やっているのも偉い。何よりも、粗野で低俗な言葉を吐きながらも、20人近いメンバーと人間関係を良好に維持できているところも偉いのである。
試合の合間に交わされる、浅そうで深そうでやっぱりそんなに深くない科白のひとつひとつも絶妙だし、選手の散漫な集中力を示すような、野球とほとんど関係のないカットも秀逸。ピザ屋のおやじはこの仕事は好きじゃないし、ガキは隠れて煙草を吸おうとするし、球場つぶしてできる学校なんて要らないと強がる。突然、ドラマチックなBGMが流れたり、そこまで必要とは思えないスローの映像演出も妙で可笑しい。もやは勝利を決するために野球をやっているのか、野球をやっていること自体が目的なのか、よく分からなくなる展開も素敵である。後半、やや愚鈍な展開になるのは、たぶん、選手たちの「ダラダラ」を観客に追体験させるためであろう。
全57件中、1~20件目を表示