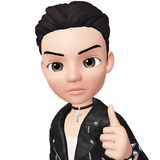ハウス・オブ・ダイナマイトのレビュー・感想・評価
全186件中、61~80件目を表示
まさに変則的『羅生門』?ではない!超リアリズム作劇!!
同一の出来事を3種の角度から描写するという、、、視点変換が、、まさに変則的「羅生門」?ではない超リアリズム?作劇です💦💦💦
キャスリン・ビグロー本領発揮の極緊迫型サスペンス、、、緊張感がスゴイ!! ノンストップでした。約2時間が一瞬という凍りつくような体感!でした。 賛否両論あるようですが、僕は角度が異なる同一突発事件への対応方法?のリサーチの徹底ぶりに感嘆しました😊
同じシチュエーションが3度くり返されますが、一体どうなるのか、だいたいは分かっていても「最後の大統領の決断」及び「シカゴへの着弾の有無」が、、、映画のラストまで分かりません。そこを分からなくして、作品は観客をグイグイと引っ張っていきます!!
ここからは予想ですが、、、
果たして大統領は全面報復したのか
シカゴは核ミサイルで壊滅したのか
これらは観客に全て委ねられます💦
しかし、ここまで緻密な事実を積み重ねた(リサーチの結果の)作品は、まさに見事です。
起こらない事が起こった場合。。人は??
独特な構成
キャサリンビグロー節!!
緊張感マシマシな作品!すごいなーこの映画、監督誰だったけと思いながらエンドロールでキャサリンビグロー!!やっぱり!そうだよねーと納得。
軍上層部、政府高官、大統領みんな一人の人間、立場上厳しい訓練、シュミレーションはこなしているが、所詮一人の人間。現実にスーパーマンはいない。歴史上、大犯罪者になる頭おかしい人はたまに出現するが、やはり何万人の命、家族、大切な人の命を割り切って行動できる人なんていないのだ。この世界がいかに異常なバランスで成り立っているか。近年戦争が身近に感じる分、まるでフィクションとは思えない。
北朝鮮のミサイルはよく日本を飛び越えるが、そのたびにいかに世界中が緊張し、対応していることを認識しなければいけない。いつ威嚇射撃ではなくなるかを。
改めて日本は被爆国として、核開発、核保有、核使用の反対を世界中に発信しなければいけない。
各国のリーダーは核使用をためらわず決断できるのか?
その時は世界が消滅する。
とても絵空事とは思えない。
レベッカファーガソン同い歳ですが、綺麗すぎ、かっこよすぎ。最高!!
いきなりネフレで観れるなんて!
見逃したなあって思いきやネットフレックスで観れるやん。恐怖のカウントダウン どこから発射されたか?対撃ミサイルが失敗 最悪やないか。都市が一つなくなる?
なんかリアルだ。まあ単品だけど怖かった。
楽しめた
訓練と実戦
嫌な緊張感
さすがに3回は飽きる
面白くはあったが同じ20分の出来事を場所を変えて3回繰り返すのはくどい。
初っ端のオリビア大佐がメインの話は緊迫感があった。
全ては司令室同士のやり取りで実際のミサイルの飛行シーンなどは一切なく、
各セクションでの人々の緊張感だけで事態の重大さを伝えるなどは演出の技だと思う。
これってすごいなあって思うんだよね。普通なら敵国の緊張感や兵器の映像を見せることで、これから恐ろしいことが起こるよってことを描くわけだけど、そう言うのを一切削除して、ことの重大さを伝えるわけだからね。
各シーンで各々のスポットを当てた人々の国防への忠誠と家族への想いなど他のアクション映画などでは見られない家族や恋人への思いの片鱗を見せたり、弱さを見せたり人間らしさを描かれている。
あの状況でパニックを起こさず半分諦めの中での任務と祖国を守らなければという思いが複雑に混じり、実際あんな空気感になるんじゃないかなとは思った。しかし大統領の決断一つで人類の運命が決まるわけであのような重大な場面を大統領とはいえだたの個人が全人類の運命を背負うとか、人間って実に愚かな生き物だなとつくづく思った。
所詮猿に毛が生えた程度で進化の終着点みたいな驕りがあるから、持て余したパワーを制御しきれはしないのだなとよくわかる。人間がこのような巨大なパワーを持つのはまだまだ早いのだなと思った。
とにかく緊張感はすごかったんだけど、やっぱり同じシーンを角度を変えて3回見せると言うのは飽きがくるよね。それにあのエンドは全く評価できないね。未消化で残念だった。
さすが、キャスリン・ビグロー!な一作。 レベッカ・ファーガソンのキ...
独特の構成
地味に怖い。 敵が誰なのか、どこから発射されたのか——それすら分か...
61%の確率で保っている世界の均衡
Netflixで、先日配信が始まり、一部劇場公開もされた、核爆弾発射に伴う、社会派のサスペンス。最近は、ロシアのウクライナ侵攻、ガザ地区とパレスチナの戦闘と、きな臭いニュースが毎日の様に、メディアで報道されている。そんな世界情勢の中での本作。決してフィクションではなく、いつか近い将来、核ミサイル発射の秒読みが来るのかもしれない怖さを感じた。
本作では、ミサイル着弾が確定してから19分間という短い時間の中を、3つの章で描いている。第1章では、国防の最前線で指令を出す人々、2章では、国家防衛式センターでの、軍のトップの官僚たち姿を、そして、第3章では状況を総括しながら最後の決断に迫られる大統領と、国防に関わる3つ立場の人々の苦悩と葛藤、恐怖そして絶望が映し出されていく。着弾の危機迫る中、秒読みでの指示や対応、言動について、緊迫感と緊張感のあるシーンが続き、女性で初のアカデミー賞受賞監督のキャスリン・ピグローが、見事に描き切った。
いつもの日常時間が過ぎるはずだったある日。突然、出所不明の核爆弾搭載のミサイルが発射された。最初は、いつもの北朝鮮辺りのミサイル発射実験と構えていたアメリカだったが、ミサイルの方向が、いつもの実験コースから外れ、アメリカ本土に着弾する可能性か高まる。どこか何の目的に発射したのか、全く情報が掴めない中、着弾場所がシカゴと断定され、アメリカ政府、国防組織は混乱に陥る。
タイムリミットが迫る中、アメリカは、迎撃ミサイルを発射した。しかし、確実と思われていた迎撃ミサイルが失敗に終わり、核ミサイルはシカゴへ向かって飛び続ける。手の打ちようがなくなる中、アメリカ国防総長が下して、大統領命令の指示を仰いだ方法とはいったい…。この中で、迎撃ミサイルの的確率は61%という低さには驚かされた。ある意味、現在の世界情勢は、この61%を頼りに均衡を保っているということだ。
出演者もなかなか豪華。大統領にはイドリス・エバンス、軍の大差にはレベッカ・ファーガソン、国防長官にはジャレッド・ハリス、大将にはトレイシー・レッツ、また、迎撃失敗の責任を感じる少佐にはアンソニー・ラモス等、他にも多くの俳優が集結して、個性豊かな俳優陣が、タイムリミットに向けての緊迫感迫る演技を見せている。
アメリカの軍人役人大統領いくら何でもメンタル弱過ぎ
表現したいことはわかる
たった一発のミサイルで簡単に、全面核戦争になるかもしれない
そうしたら人類全体で破滅するかもしれない
そんな危うい世界に私たちは生きてるんですよ わかってますか?ってこと
物語はどこの国が発射したかわからない大陸弾道ミサイルがアメリカ本土に向かって飛翔していることを、アメリカ軍やら連邦政府やらが把握してからの、軍や政府のあわて狼狽する様を延々と見せつけられる。
しかし訓練された軍人があんなにオロオロするのか、敵国からの先制攻撃の事前シミュレーションなど徹底的にやっていると想像されるアメリカ連邦政府や大統領がこんなに狼狽するものなのか。
本当のところは知る由もないので、わからないけど、登場する人物がそろいもそろってメンタル弱い。
私は疑問に感じてしまって没入出来なかった。
実際のアメリカはさすがにもうちょっとシステマチックに動くんじゃないだろうか。
結末もふわっとして解釈を観客に丸投げするタイプの映画。良くも悪くもそういう映画。
迫られる決断に
何十年も前から既視感のある内容だった💤
ミサイル迎撃にあたふたする司令部や、家族に避難を指示する様子が描かれますが、何十年も前から既視感のある進歩の無い内容だと思います。ビグロー監督が題材にすべきなのは、今現在まさに行われている戦争なのではと思います。ロシア外相との電話が何か間抜けですし、タイトルが言いたかっただけなのか最後も投げっぱなしでした。
張り詰めた緊張と未完の余韻
ガクガクブルブル🫨 観てる最中 終始マジで震えた
Netflix契約してるお方は、
今から19分以内にご鑑賞下さい(笑)
キャスリン・ビグロー監督は、
アカデミー賞受賞のイラクでの爆発物処理隊員を描く「ハート・ロッカー」と、ヴィン・ラディン殺害の秘密作戦実行の裏側を精緻に描いた「ゼロ・ダーク・サーティ」も身の毛がよだつ現実を白日の下に晒した、スンゲー作品でしたが、またしても我々が直面する核抑止戦略のヤバい現実を暴露する映画
核ミサイルが1発、極東から突如、通告も連絡も無く、国籍不明の潜水艦から発射され、迎撃に失敗🤯
わずか19分後にシカゴに着弾する状況が起こる
その時、どんなシステムが発動し、何が起き、どんな状況が出現するのか、事実に基づき、シュミュレーションした映画
どこから誰がなんて、問題にしないキレッキレな脚本が冴え渡る
観る者は唖然とする事実を突きつけられて、どんなホラー映画よりも怖くてココロの芯が凍りつくだろうね🧊
急に寒くなったこの時季に観ると風邪🤧引くかもしれないよ
邦題「ハウス オブ ダイナマイトとは、ダイナマイトで作られた家🏠🧨 世界中の人はそんな家の中で何も知らずに暮らしていることに気付かされる😳🤯🥵
地球と言う“核”家族
この映画は、日本人であるならば、唯一の被爆国であり非核保有を宣言している国の国民であるならば絶対に見なければならない傑作
いわゆるシチュエーションスリラーと言うジャンルの本作は、限りなく現実的な物語展開でありながら、フィクションをいい塩梅に溶け込ませた物語になっている
現実的な作品によくありがちな“説明臭さ”や“ダレ”が少なく、常に現場の臨場感を伝えてくれる構成になっているため、2時間があっという間だった
話しの構成としては、海洋上から発射されたICBMミサイルがアメリカに着弾するまでの18分間という同一の時間軸を[3パート]に分けて6箇所からの視点で紡ぐ
それぞれ立場の違う主要人物たちが、未曾有の事態に直面し、奮闘し、絶望する
特に自分は国防長官パートが好きだ
国防の要であり超重要人物でありながら、一人の親としての葛藤、仕事の責務がせめぎ合い、作中で一番人間的な部分を見せる
彼のパートは3話目なので、その3話目を見てから再び他パートを見ると、会議中の“違和感”に納得できてしまう
ここ最近の日本映画で例えると、シン・ゴジラからゴジラ要素を抜き、攻めてくる敵がどこかの“国”になった映画
と言うのが一番しっくり来た
核を持つ国を攻める馬鹿はいない
作中でも似たような台詞があるが、それは前提であり建前でありあくまで空論だ
どこかの馬鹿が、自爆覚悟でアメリカに報復したら
もしその“馬鹿げた”事態に直面した場合、アメリカという国がどう動くか。それをリアルに、人間味を醸し出しつつフィクションを織り交ぜた映像作りには脱帽した
作中では一切、爆弾も爆発しなければ銃も発砲されない
カースタントも無ければ感動的な再会もない
だが、下手なアクション映画よりも緊張感と緊迫感の演出はうまい
見終わって思わずため息をついてしまうほどに
最近の世界情勢的にも、知っておいて損は無い知識を得られるので、粗筋を見て気になった人は絶対見たほうが良い
全186件中、61~80件目を表示