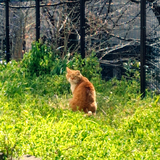ハウス・オブ・ダイナマイトのレビュー・感想・評価
全200件中、1~20件目を表示
核抑止論の欺瞞と、薄氷上の平和に麻痺した人間の無力さ
ある日突然、どこの国からかもわからない核ミサイルが今から20分後に着弾すると言われたら、アメリカの防衛の中枢はどうなるか。そのシミュレーションのような映画だ。いつも通りの穏やかな朝を迎えたアラスカの軍事基地やホワイトハウスが、謎の大陸間弾道ミサイル(ICBM)を検知したことから緊張と混乱のるつぼと化す。
本作では、ICBMの検知から着弾間際までの小一時間ほどの関係者の奮闘とパニックが、視点を変えつつ3回繰り返して描かれる。最初がアラスカの軍事基地とホワイトハウス、次が国防長官とその周辺(ペンタゴン?)、最後は出張中の大統領。1周目でリモート会議の画面の向こうにいた人間、声だけ聞こえていた大統領がその時何をしていたかを、2周目3周目で明らかにするといった構成だ。リモートの向こうから断片的に聞こえていた言葉が発された状況が、視点が変わるにつれ徐々に分かってくる仕掛けになっている。
この3周の全て、つまり映画のラストも、ミサイル着弾直前で物語は終わる。最後までICBMを発射した国はわからないし、実際に着弾し爆発したのかどうかも描かれない(物語の中では、何らかのレーダーの誤認である可能性、湖に着弾し不発となる可能性などにも言及がある)。
こうした終わり方は賛否あるかもしれないが、ラストがこの締め方だったからこそ、監督のメッセージがより鮮明に浮かび上がったと思う。
「世界は爆弾の詰まった家だ」苦悶する大統領の言葉は、現在の社会情勢を端的に表している。それは存在する核弾頭の数の多さ(2025年6月時点で、廃棄予定のものを除いて9,615発。長崎大学核兵器廃絶研究センター公式サイトより)のことを指すと同時に、どういうきっかけで核ミサイルの発射ボタンが押されるかわからない、国家間の緊張感の高まりのことを指すようにも聞こえる。
核抑止という理屈がある。だがこれは、核保有国の指導者が皆核の脅威と影響を正しく理解し、本当に核を使ってしまうようなおかしな者が出てこないという、互いの国の良識に依存したものだとも言える。
この物語のように、ひとたびどこかの国が核を使えば、抑止などというお題目は瞬時に吹き飛ぶ。抑止のたがが外れ、報復から全面核戦争にでもなれば、人類文明はあっという間に壊滅するだろう。日本が経験した広島の原子爆弾がTNT換算で15キロトン。現代の戦略核の主流は水素爆弾で、100キロトンから1メガトン級のものまであるというのだから。
そうした危険をはらんだ大量の核兵器を背景にした、抑止力という薄氷の上にかろうじて成り立つ「平穏な日常」を、私たちは無自覚に享受している。
また本作は、国防の最前線で最悪の事態に対応する組織もまた、弱い人間から成り立つものに過ぎないということも描いている。
着弾のカウントダウン開始後、寸暇を惜しんで知恵をしぼるべき立場の人間たちが事態の深刻さをなかなか認識できなかったり、認識したらしたで家族に電話したりするのは正直見ていて苛立った反面、まあ人間とはこんなものだろうとも思った。いくら国防を仕事としていても、何の前触れもなく敵国がどこかさえわからないまま、突然20分後に大都市が壊滅する攻撃を受けると言われたら、一国の防衛を担うエリートたちにもメンタルの限界が訪れるのかもしれない。
核抑止という危うい均衡がひとたび崩れたら、その崩壊を確実に押し留める仕組みや手段など結局ないに等しい。コイントスのような確率の迎撃ミサイルが外れたら、着弾までに間に合うことを願いながらシェルターに逃げ込むしかない。その後地上は、絵本「風が吹いたら」のような運命を辿るだろう。
核抑止論の欺瞞と、その危ういバランスが崩れたときの人間の無力さ、それをビグロー監督は3回のリフレインで描き尽くした。結果的にミサイルが爆発したか否か、それがどこの国からのものだったかは、この主題にとっては蛇足だから省いた。潔い判断だ。
最後に、ビグロー監督のインタビューでの言葉を引用する。
「複数の国々が、文明社会を数分で終わらせられるほどの核兵器を保有しているにもかかわらず、一種の集団的な麻痺状態、つまり”想像もできない事態の静かな正常化”が起きているのです。 破滅という結末が待っているというのに、どうしてこれを”防衛”と呼べるのでしょうか。 私はこの矛盾に正面から切り込む映画を作りたかったのです。絶滅の影の下で生きながら、それについてほとんど語らない世界の狂気に深く迫るために。」(2025.10.5 BANGER!!! 記事より)
圧倒的なリアリティに満ちた緊迫ドラマ
爆発という要素はビグロー作品の一つの大きなテーマだが、吹き荒れる炎や爆風よりもその直前の一瞬の静寂こそ、彼女が醸し出す緊張感が最高潮に達する見せ場だ。太平洋上で発射された核ミサイルがアメリカへ向けて飛来する。そんな緊迫したシチュエーションを描く本作も、やはり爆発前の一瞬を描いた群像ドラマと言える。いたずらに破壊のカタルシスを求めるのではなく、この映画が描くのはあくまで「現実に直面する政府要人やスタッフたち」。それも彼らの過去や未来ではなく、あくまで焦点が当たるのはごく限られた数十分の「現在」の枠内だけ。そこでの行為や発言、表情を通じて、人の生き様を力強く炙り出す。もちろん、徹底した取材力はこれまで同様。登場人物や関連機関のディテール、さらにはこの最悪の事態に伴うシナリオも、我々に圧倒的リアリティを突きつける。世界は逃げ場なき火薬庫。綱渡りのような状況に手に汗握りつつ、背筋が寒くなる一作だ。
緊張感の作り方がパーフェクト👌💯
あ〜疲れた😮💨ジャックバウアーの居ない24🥶
怪物みたいな構成なのよね👍
下手なホラー映画より怖い話だし🇺🇸🚀💥🥶
日本映画だったらおそらく無駄に叫びまくるシーンとオーバー過剰演出だらけで逆にドン引きになる場面を(最後どうなったか全て見せるか説明するんだろうね🇯🇵🤮)この作品はしっかり顔演技で絶望的な状況なのを伝えるのが見事でした🫡
ある一定の過剰演出で面白くしてると勘違いしてる日本映画を作る人達にこれを観せて改心させてやりたいですよ(裁判モノだと更に裁判長〜って叫びまくるから悪質なんですよね🤮)
19分しか無いタイムリミットモノなのも緊張感を作るのに上手く作用してるし最後の大統領の決断と核爆弾が落ちるのを見せない事によって観た人たち同士で話が盛り上がるし上手いオチのつけ方よね🤠(大統領の選択と核爆弾がシカゴに着弾する場面が無いので全てを描いて無いから低評価のパターンもかなりの数いるよね絶対に😉)
しかし良い作品だったからめちゃくちゃ大満足です🚀🌏💥
弾丸で弾丸を撃つ‼️
この作品はキャスリン・ビグロー監督の面目躍如たるハラハラドキドキの軍事サスペンス・スリラーですね‼️シドニー・ルメット監督の「未知への飛行」やケヴィン・コスナーの「13デイズ」を思わせる、あっという間の2時間でした‼️発射元不明の核ミサイルがアメリカに向かって発射され、刻一刻とタイムリミットが迫る・・・‼️実質、ミサイルが発射されてから数十分間の出来事を、大統領、国防長官を始めとする政府関係者それぞれの視点から描いています‼️大変面白くあったのですが、今作はヒジョーに観る者を不安にさせる作品ですね‼️ミサイルがどこから発射されたか分からない、迎撃ミサイルが何度も失敗する、某国が原潜を所有してることを大国アメリカが把握してない‼️世界一の大国であるアメリカがこの程度の対応しか出来ない現実であれば、まさに今作は「今そこにある危機」‼️映画を面白くするための脚色であれば、リアリティ皆無の大問題‼️作り手側のそういう姿勢は私を大いに不安にさせます‼️シカゴが壊滅(?)するラストも含め、ビグロー監督の演出は大変素晴らしいので、次作以降も期待なんですけど、元ダンナと同じく寡作なのがチョット気になりますね‼️
現代版「未知への飛行」
十分あり得る
結局どこから発射されたかわからないミサイルが、あと20分でアメリカ本土に着弾するという事態を受け、いくつかの立場やシチュエーションからその20分間の対応を描いた作品。通話相手が言った言葉が後になってどのシチュエーションで言ったか分かったりする。
ものすごく政治的だが、このような事態においてどうすべきかを述べる監督ではないので、だから核武装すべきなのかしてはいけないのか、見る人によって正反対の意見を持つ可能性があるなと思った。明確なのは、一旦戦争が始まってしまうと全ての人の日常生活が奪われてしまうということ。始まってしまってからロシアと交渉していたが、本来はもっと前に外交努力をすべきだった。高度な外交テクニックで不必要な摩擦は避け、撤回できないような迂闊な発言などせず、絶対こんな事態にならないようにすべき。
抑止の危うさ
とにかく時間がない
アメリカ大統領が核ミサイルのボタンを携行してる話は知ってたけど、いざって時はもっと自動的にスクリプト的なものが発動するかと思ってた。
国家の危機に備えて、予算をかけて人材を集め、体勢を整えていても、発射から着弾までの短い時間に人を招集したり情報を集めたり検討したりして、細かい判断をひとつひとつ積み上げなきゃいけない。あとはここまで大事になると身内とかにも連絡したいーーとなれば、あまりにも時間が足りない。
でもここでの判断の1コ1コがのちに検証され、結果的にまちがえてた場合、大罪人として歴史に名が刻まれたりなんかする可能性も。非常にきびしい。絶対やりたくない。
アメリカ版シン・ゴジラ的なアプローチだけど、やっぱアメリカ映画はこういう時でも家族命がリアリティなんだなー
だし、もしホントにこれが国家安全保障体制の実情に近いなら、もう機能してないに等しいと言ってるも同然。
こういうシステムの機能不全を突いて映画にする感じ、ゼロダークサーティに似てるかも。
足元がこんなにガタガタだと知ってアメリカ人ならさぞかし眠れなく……と思ったらビンラディン殺害につづくトランプ復活でまたしても世の流れに振り回されるキャスリン・ビグロー。。
今のホワイトハウスはこれが牧歌的に思えるほどガタガタになってるらしいじゃない?マジで今なにかコトが起きたら、と考えると日本人でも眠れん話。
オチはよくわからなかった。君らで考えなさいってこと?うーん…丸投げかぁ
決断の重み
レベッカ・ファーガソンの存在感が大幅に増した!
配信(ネットフリックス)で視聴。
安全保障がテーマだが、IF要素が強い内容。色々、考えさせられた作品。安全保障も今後色々あるだけにイメージとして観たらやはり怖い。レベッカ・ファーガソンの演技は素晴らしかった。貫禄が出てきた。トム・クルーズと共演した事が強味に。存在感が増した。
悔やむのは映画館で時間が合わず見逃したこと。配信で観たのは良かったが。
HAVE A NICE DAY
ビグローが描く現代のミサイル危機。今の地球の状況とは、今にも壁が壊れそうなほど爆薬がいっぱい詰まった家。世界を何度も終わらせられるほどの核兵器を、各国が競い合うように保有している"異常な現実"
今世紀に入ってから(『デトロイト』の人種差別政策含めて)戦争を描き続ける硬派な社会派監督キャスリン・ビグローの骨太な作風が、本作でも大いに生かされていた一貫した作家主義。実話モノも手がけてきただけあって、様々な視点からアンサンブルキャストが生きた心地のしない19分間を繰り返す、この同時系列多視点モノ(羅生門方式)な群像劇ポリティカルサスペンスでも見事な手腕を発揮していた。
「傾斜が水平に」
モーニングブック(朝の報告書)からブラックブック(核の手順書)へ。その後の一分一秒を争う緊急事態での混乱との振り幅を効果的に描く束の間の平和パートから、ドキュメンタリータッチなハンディによる手ブレ撮影など、ポール・グリーングラス監督作品も少し彷彿とさせるような語り口で手に汗握る。胃がキリキリと神経のすり減るような観賞体験を約束してくれる。
【デフコン2】「弾丸で弾丸を撃つ」
そりゃ自分の家族が気になるよね。混乱具合はわかるけど、緊急事態庁のメインキャラが時間無い緊急事態下にもかかわらず危機管理室側に食いかかっては、自分の仕事も避難させるべき対象である「議員たちがいい顔しない」ってすぐに折れて、無理だったことを報告しているだけに見えた。挙句COG(Continuity of Government)だから、それは仕方ないのだけど、本作のキャラクターで一番要らないムーブをして邪魔しているようで、イラっときた。
【デフコン1】「弾薬が詰まった家」
エルバの大統領役は必然、無論似合いすぎ。そして最後は観る者に委ねられている決断…。
ビグローなので期待したが…
何十年経っても変わらない
今から60年ほど前の映画があります
『未知への飛行』と言う映画です
60年も経つのです
同じように爆弾に国の上の人達が右往左往するのです
多分この作品を作った人も知っているはずだと思います
さほど有名ではないですがかなりの力作だと私は思う
と言うかあんなに昔なのに扱っている内容すら色褪せないってどうなんでしょうね
人の乗らない戦闘機もある
戦場に行かなくても戦争できちゃう
まさにそんな世の中になったのにいまだに核の脅威をこんな風に作品にして見せられると本気で心配してしまう
オムニバス形式であらゆる視点から物事を見るような仕組み
とても面白い
話が変わるごとに緊張感が増して行く
誰もが弱い一面を見せて涙する
聖書の引用がこの作品ではポッドキャストになっていたことに気がつく
苦笑いする
ずしりと残る
採点4.2
キャスリン・ビグロー監督によるパニック系ポリティカルサスペンス作品。
始まりは米に発射されたのか?といった1発のミサイル。
そこからの緊張感が凄い。
発射場所が特定できない、迎撃ミサイルが当たらない、最高レベル達するデフコン、ギリギリとなる米政府当局者達。本当脚本が良いですね。
危機管理室、国防長官、大統領と三章に区切り物語を前後させた構成。それぞれの視点や登場人物ごとにエピソードを作るなど、偶像劇な作りが本当に巧み。
大統領の暗転と共に聞こえるミサイルの飛行音、雛城の頭上に残る二つのミサイル雲、ラストの司令官の姿、エンドロールで聞こえる着弾のようなSE。
「核の抑止力」ではなく「常にある核の脅威」を描いた、ずしりと残る作品でした。
これまでの戦争映画とは一味違う
タイトルにも記した通り、本作はこれまでのハリウッド製戦争映画とは一味違う内容となっています。
まず最も特徴的なのは、戦闘シーンが一切描かれていない点です。本作は、アメリカ本土に向けて核ミサイルが発射され、それをアメリカ側が探知してから着弾予測時刻までの約20分間にわたる対応を描いています。
この「戦闘を描かない」演出が妙にリアルで、緊張感が観客へひしひしと伝わってきます。
また、従来のハリウッド映画であれば、土壇場で迎撃に成功し、作戦本部の面々が拍手喝采して「めでたしめでたし」となりがちですが、本作ではミサイルが着弾したのかどうかさえ明示されません。仮に着弾しても、不発で終わることもあるらしいのですが、その結末すら分からないままエンドロールへ突入します。そこがまた不気味で、何とも言えない後味を残します。
構成面では、探知してから着弾までの20分間をさまざまな視点から繰り返し描いている点が興味深かったです。
演技面では、レベッカ・ファーガソンの存在感が際立ちます。迎撃に失敗した後や着弾点が判明した際、セリフに頼らず、表情や仕草だけで絶望感を表現する演技は何とも言えません。
あと、本作を鑑賞して「未知への飛行」と、そのパロディ的作品である「博士の異常な愛情」を思い出しました。どちらも類似したテーマを扱っています。ネタバレになるので詳しいコメントは控えますが、特に「未知への飛行」はお勧めです、と言いたいところですが、かなり古い白黒作品なので、現在の高画質に慣れた目で観たらどうなのか不安です…
全200件中、1~20件目を表示