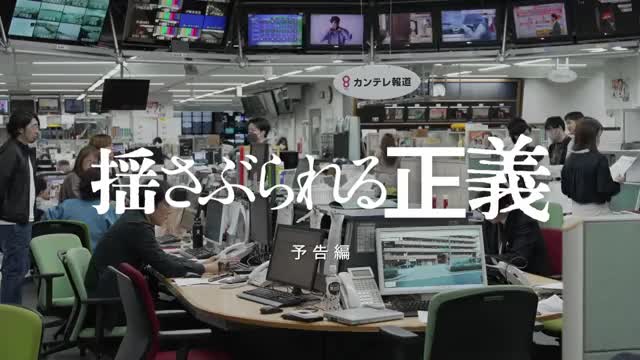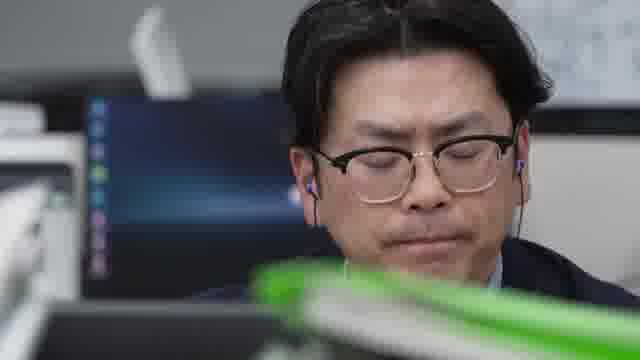「「信じること」と「疑うこと」は、本当に対立するのか」揺さぶられる正義 KaMiさんの映画レビュー(感想・評価)
「信じること」と「疑うこと」は、本当に対立するのか
揺さぶられっ子症候群については興味を持っていた。事故で頭部に衝撃を受けた可能性もあるのに、3つの症候があればただちに「大人による揺さぶり」「虐待」と疑われ、冤罪が多く生み出されたのだ。この映画は一連の報道の集大成のように見ることができた。
この3症候論を強く主張した医師のインパクトあるインタビューも、もともとは関西テレビの報道で、この映画の監督によるものだった。
対する秋田弁護士は一審で有罪とされた事件で次々と逆転無罪を勝ち取る。映画は、一種の法廷ドラマとして緊迫感をもって鑑賞することができる。
一方、ハッピーエンドで幕を閉じることを拒んでいるのが20代後半の男性被疑者のケースだ。「俺がそんなんするわけないやろ」とまくしたてる、いかにも悪質そうな義理の父。
それまで冤罪を疑われた親たち(あるいは祖母)とは違い、この人の冤罪を晴らすのは難しいのではと思わせる。
しかしこの若者は5年も収監された末、支援してくれた弁護士に感謝でいっぱいの、人懐こくて味のある人物として戻ってくるのだ。高裁で立派に無罪を勝ち取ったが、現在検察が上告中とのこと。
テレビの報道者としての監督は、当初この若者を疑ってしまった。その贖罪のように、メディアの限界を問題提起することが映画後半のテーマになっている。
ただ、映画の踏み込み方は深くない。「犯人逮捕」の瞬間だけ盛大に報道し、冤罪に加担するメディアの問題は大昔から言われてきたではないか。
「初めから君を信じていればよかった」という監督の反省は、人間ドラマとしては誠実だし、天然な人柄をうかがわせる。その分、考えるべき余白を大きく残していると思うのだ。
そもそも、「虐待を見逃さない」「冤罪を作らない」という「二つの正義」の争いとしてこの問題を描くのはちょっとズレている。
虐待発見派の医師は「子どもの立場に立つ」と言う。しかし、親の加害を立証するだけでなく、急死の原因となる病気を突き止めることも子どものためだろう。冤罪を晴らす側だって、「あなたを信じたいからこそちゃんと疑いを晴らそう」という考えも成り立つはずだ。
つまり二項対立に陥らず、多角的に真実を明らかにするという姿勢が大事ではないだろうか。被疑者と二人三脚を組む弁護士ならいざ知らず、報道や検証の仕事であるのなら。