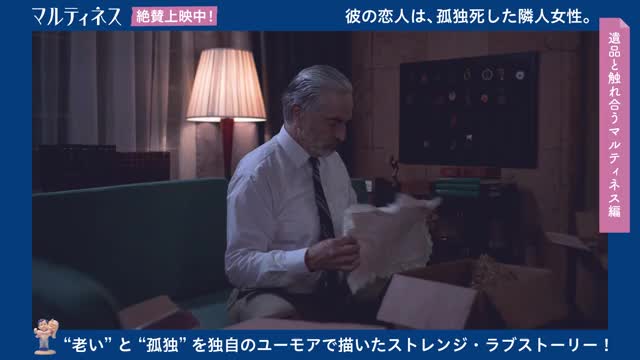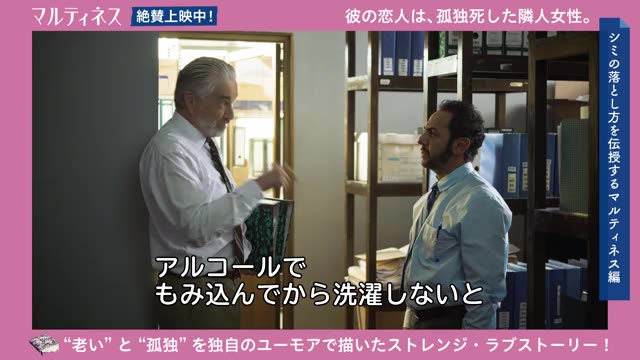「どう見ても変態なのだが、そう見えない理由が至る所に隠されていた」マルティネス Dr.Hawkさんの映画レビュー(感想・評価)
どう見ても変態なのだが、そう見えない理由が至る所に隠されていた
2025.8.27 字幕 アップリンク京都
2023年のメキシコ映画(96分、G)
顔見知り程度の孤独死した隣人からプレゼントを贈られた初老の男を描いたヒューマンドラマ
監督&脚本はロレーナ・パディーシャ
物語の舞台は、メキシコのとある町(ロケ地はグアダラハラ)
公認会計士として長年勤めてきたマルティネス(フランシスコ・レジェス)は、ルーティンな毎日を過ごし、家と職場を往復する毎日を送っていた
そのルートから逸れるときは水泳に行くか、公演の池を散歩する程度で、それ以上の行動を起こしてはいなかった
彼の住むアパートでは1階下の2Bの部屋から大音量のテレビの音が日夜鳴り響いていて、マルティネスは耳栓をせずにはいられなかった
本人に直接話しかけても無視される日々が続き、大家のベルタ(マリア・ルイーサ・モラレス)もほとほと困り果てていた
ある日のこと、60歳になったマルティネスに転機が訪れる
それは、定年退職を控え、後任の会計士パブロ(ウンベルト・ブスト)が西部支店から赴任してきたことだった
人事から何も聞かされていないマルティネスは、それを確かめてからでないと引き継ぎはできないという
だが、週明けに人事部のサンチェス(Martha Reyes Arias)から正式に聞かされ、渋々と業務を引き継ぐことになったのである
物語は、退職によって人生が揺らぎ始めたマルティネスの元に、さらに不可思議な出来事が舞い込んでくる様子が描かれていく
それは、大音量の主アマリア(メリー・マンソ)は半年前に自宅内で亡くなっていて、それが孤独死だったというものだった
さらに、顔見知り程度の関係だったのに、彼女からマルティネス宛の贈り物が残されていた
その箱にはインテリアで使うような置物がいくつか入っていて、マルティネスはどう扱って良いのか悩んでいた
大家は次の住人のためにアマリアの荷物を外に出していたが、何を思ったのか、マルティネスはそれらを自分の部屋に引き入れてしまうのである
物語は、まさかの遺品漁りからの故人の人生を準えていくという変態的な側面があり、なぜかそこまで変態行為に見えない不思議さがあった
それはマルティネスが妄想と現実をギリギリのラインで切り分けているからであり、それを象徴するのが、ランジェリーと添い寝をするシーンなのだと思う
そのシーンでは、初めはランジェリーに覆い被さる(正常位)のような体勢から、思い立ったように添い寝へと転換していた
マルティネスの中にある一線というのは、妄想を現実と結びつけてしまう即物的な行為であり、それ以外の行為は絶妙に「妄想世界でのデート」のように描かれていた
それゆえに気持ち悪さというものが際立たなかったのだが、そんな中でも「超現実に陥らせる罠がある」というのは憎い演出だと思う
アマリアはある男(Marco Aurelio Hernandez)の愛人だったという告白があって、それを知ったことによって、マルティネスはこれまでにない衝動に揺さぶられてしまう
愛人だと思われる男のところに突撃して、いきなり殴って去ったり、パブロの評価を人事に話す際にも誇張して悪い部分だけを伝えてしまう
我ここにあらず状態のまま他人に影響を与える行為を続けていて、ふと我に返った時には引き返せないところまで進んでしまう
思えば、マルティネスは自分の人生をコントロールしているようでできておらず、かなり周囲の影響を受けて路線変更をしてしまう男だった
それは、騒音が消えた後に自分で騒音を作り出したりという行為に見られ、一つの贈り物が人生を根底から覆す方向に向かわせていく下地となっていた
他人を最も嫌う男が、他人から影響を受けまくっているということ自体が人生の恥部のように感じていて、それが彼の孤独を生み出していたのだろう
理想の自分を求めた根源には、影響されやすい人柄というものがあって、その部分は最後まで変われない部分だったのかもしれません
いずれにせよ、一つのプレゼントがきっかけとなっているのだが、なぜアマリアはマルティネスにプレゼントを残したのかは不思議だった
それは劇中では描かれないのだが、マルティネスが同じことをしていることで、その理由というものが見えてくる
マルティネスは旅立つ前に同僚のコンチタ(マルタ・クラウディア・モレノ)に贈り物をするのだが、これは自分を忘れないでという意味なのだと思う
そして、贈り物をできなかったパブロに対しては、実際に彼の元を訪れて、思い出を作ろうとしていた
他人から影響を与えられる男は、他人に影響を与える人物になったことで、良くも悪くも人生の生き直しをしていく
それが正しいのかはわからないけれど、彼なりに導いた人生の結論だと考えるのならば、それを尊重してあげたいな、と感じた