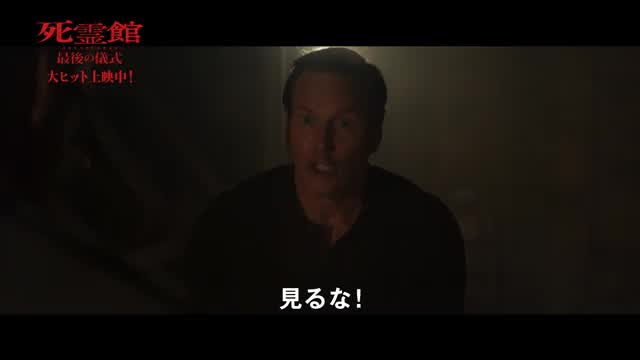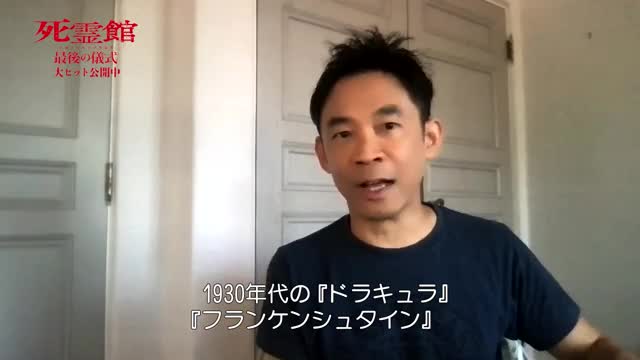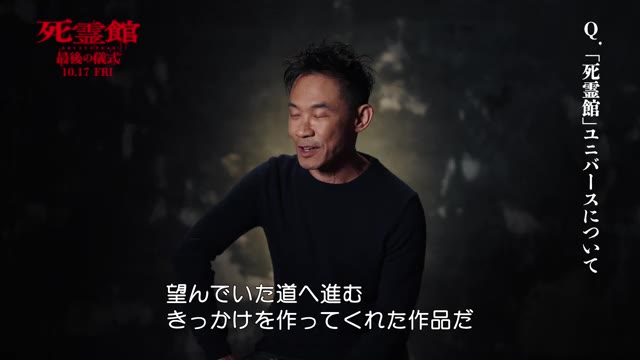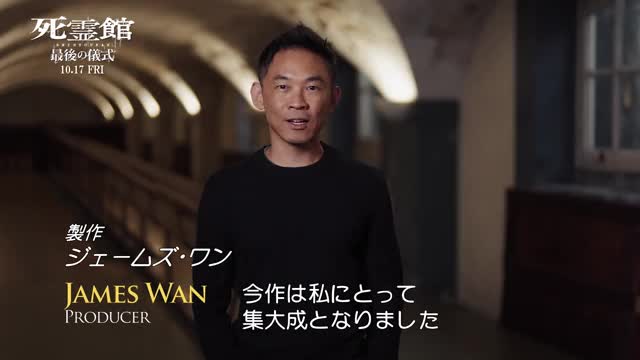死霊館 最後の儀式のレビュー・感想・評価
全115件中、61~80件目を表示
最後
このシリーズもどうやら最後らしい
主演のパトリック・ウィルソンが家族を愛する理想の夫(父親)を演じているのだが、個人的に彼の出演作で一番好きなのはドラマ版「ファーゴ シーズン2」
こちらでも妻と娘を愛する理想の父親を演じており、シリーズで一番好き(ちなみにバカ夫婦役で共演したキルスティン・ダンストとジェシー・プレモンスはその後結婚したのもシーズン2)
シーズン1も映画版と一番リンクしており、悪役のビリー・ボブ・ソーントンも気持ち悪くて最高なのだが、やっぱり2が好き(一番嫌いなのはシーズン3、悪役が嫌い…)
と、ドラマ版ファーゴのことばかり書いてきたが、本題のこの映画、最終版らしく終盤思わず笑っちゃうくらいイロイロてんこ盛り
新キャラのトニー役、「ボヘミアン・ラプソディ」のロジャー・テイラー演ったひとでした、オワリ!
サブリミナル効果で夢に出そう
ホラー映画としては一級品
死霊館 最後の儀式(映画の記憶2025/10/19)
最終作に相応しい
シリーズ1と2は怖くて大好き。でも3はジェームズ・ワンが監督から離れてしまったので未見。アナベルのスピンオフは何本かは見ているライトなファンと言ったところ。
今作は最終作という触れ込みなので観に行ったが、上映時間はホラーものとしては長尺の2時間15分!えーっ思ったが心と身体を準備して鑑賞。
その長い上映時間の理由はウォーレン夫妻の家族、そして霊に取り憑かれたペンシルベニアの一家のドラマが丹念に描かれていたから。それが並のホラーとは違う品格を作品に与えているのだけど、そのドラマが映画のテーマに結び付いて恐怖度を増しているかと言うと微妙で、あまり面白くないのである。ドマラ部分をバッサリ切るか、もっとコンパクトにして30分くらい短くした方が締まった作品になった気がします。
でもウォーレン夫妻のコンビは相変わらず息がピッタリで、この2人を見ているだけで心地良くなるし、最終作に相応しい構成も良かった。
これからは娘さん夫婦を主人公にしたスピンオフが作られそうです。
最後を飾るに相応しい
70年代はオカルトブームで、私が子供の頃はテレビは心霊現象やオカルト映画であふれていた。
妹たちとオカルト映画を観ながら留守番。そのままオカルト好きになり、今に至る。
暗がりから何かが現れそうな、正統派オカルトが好きだが、その後ブームはスプラッタやゾンビに移行。
再び、70年代オカルトに脚光を浴びせたのがこの#死霊館シリーズ 監督の#ジェームズワン 悪魔に魅入られた家族を救い、絆を取り戻すウォーレン夫妻。
怖いだけではなく、ヒューマンドラマも丁寧に描いているのが、このシリーズの魅力だと思う。
夫妻は亡くなってしまったが、呪物を収めた博物館は今も健在で、一人娘のジュディが継いでいる。
この映画は次世代への継承の物語であり、家族と愛の物語。
ラストに相応しい作品だった。
ありがとうジェームズワン。
怖い怖い怖い
ほんとに終わり?
恐怖だけではないおもしろさ
■ 作品情報
実在した心霊研究家エド&ロレイン・ウォーレンの夫妻が体験した奇怪な事件の実話をもとに描いた人気ホラー「死霊館」シリーズの最終章。監督はマイケル・チャベス。 主要キャストはヴェラ・ファーミガ、パトリック・ウィルソン、ミア・トムリンソン、ベン・ハーディなど。 脚本はイアン・ゴールドバーグ、リチャード・ナイン、デヴィッド・レスリー・ジョンソン=マクゴールドリック。 原案はデヴィッド・レスリー・ジョンソン=マクゴールドリックとジェームズ・ワン。製作国はアメリカ。
■ ストーリー
1986年、ペンシルベニア州でスマール一家が経験する謎の超常現象から物語は始まる。心霊研究家エドとロレイン・ウォーレン夫妻は、呪われたアンティークの鏡にまつわるこの事件の調査に乗り出す。邪悪な悪魔はウォーレン夫妻の愛娘ジュディを標的にし、ジュディは自身の持つ霊能力によって、恐怖の渦に巻き込まれていくことになる。夫妻は、スマール家と自分たち家族のために、邪悪な悪魔の仕掛ける謎と恐怖に立ち向かう。
■ 感想
苦手なホラーも克服すべく、少しずつ挑戦する中で、今週は本作を鑑賞してきました。シリーズものであることを事前に知ったのですが、過去作を自宅で一人で観る勇気もなく、予習なしで突撃してきました。しかし、多くの方々の高評価レビューに偽りなく、単なる恐怖にとどまらず、過去作未鑑賞でもしっかりと物語のおもしろさが感じられる作品で、とても引き込まれました。
全体を通して、これはホラーというよりも、ウォーレン夫妻の家族の物語であるという印象を受けます。序盤は意外なほど怖さがなく、むしろ温かい家族愛が丁寧に描かれており、トニーのプロポーズのシーンでは、思わず目頭が熱くなるほどです。「死霊館」なんて仰々しいタイトルのわりにはたいしたことないじゃんなんて舐めてかかっていたら、物語が終盤に進むにつれて、じわじわと、そして容赦なく恐怖度が増していき、めっちゃ怖かったです。
同シリーズの過去作やアナベルシリーズとの関連については、未鑑賞の自分には不明な点が多かったのですが、それでも本作単体として十分に楽しめる、そして怖さを味わえる内容でした。何よりも、これが実話に基づいているという事実が、恐怖心をさらに煽ります。本作のおかげで、少しだけ過去作にも興味が湧いてきました。
お化け屋敷に居るみたいな感覚
死霊館 最後の儀式 ホラーに、これ以上の何を望みますか
惜しい😓
エンディングでシリーズ長かったんだなー、しみじみ。
伏線は?ヴァラクは?
2025年劇場鑑賞286本目。
エンドロール後映像というか画像有り。
いつ終わるのかと思っていましたがとうとうこれで死霊館サーガの最終作。実話を基にしているので、これが最後の事件だから作りようがないという訳です。アナベルやラ・ヨローナ、死霊館のシスターみたいにスピンオフは作れるでしょうけど。
今まで散々黒幕として予知夢に出てきて、スピンオフ2作まで作ったヴァラクが出てきません。まぁあの時々出てくるおばぁちゃんシスターがそうなのかもしれませんが、全然黒幕感ないし、別に
「うぉぉぉ!ヴァラク!お前を倒すぜ!」みたいな感じもなかったし。あれ?この夫妻に娘いたっけ?というくらい唐突感があったのですが、よくよく思い出してみると本編には記憶になくてもアナベルシリーズ3作目でアナベル相手にお家で頑張ってた子が娘でしたね。
そのアナベル人形もちゃんと置いてあるし、今までのシリーズに出てた(はずの)人たちもたくさん出てくるし(最後らへん人が集まるシーンってこれまでの事件に関わってた人たちかな?そうだと思い込んでちょっと感動してたのですが)最終作にふさわしい面もあるのですが、やはりあのヴァラクとどう決着をつけるのかを楽しみにしていた身としては拍子抜けたと言わざるを得ませんでした。
これが実話だなんて
実話で押し切る居直りが清々しいシリーズ。
文句を言えば「空気読めよ」と叩かれそうで怖い。
いちゃもんつけるほうが野暮ってもんですよ。
心霊現象はチラリズムといいますか、はっきり見えるほど怖くはなくなりますね。
いくら見ても怖いのはエクソシストのリンダ・ブレアぐらいです。
私の最恐エンターテインメント不動のNo.1は宜保愛子さんの世界の幽霊屋敷探訪です。
もちろんブツが見えるわけではなく、宜保さんが「嫌だわ~、怖いわ~、いや~、来ないで~、ああ~」と恐怖に身悶えるだけなのに、恐ろしさに正視も出来ないほどでした。
今でも思い出しただけで、1人でトイレに行けなくなるほどです。
シリーズものとして映画化してくれないかな。
サンドラ・ブロックあたりで。
その時、ようやく私の呪いは解かれると思うのです。
大切な人の為に
心霊調査を引退したエド&ローレン夫婦だったが、ある恐ろしい超常現象の知らせが入り…。2人の最後の闘いが幕を開ける…といった物語。
お馴染み、死霊館シリーズの最新作ですね。
今回も幾度となくジャンプスケアに驚かせられるが、このシリーズの良い所は単なるビックリホラーにとどまらず、サスペンス要素も強い所!!
まぁ実話を元にしてますからね。
それに加えて今回は家族ドラマ色も。トニーの転職理由、エドには沁みただろうなぁ…。ここにはグッとくる。
何度も悪魔と対峙してきた夫婦だが、今回は実の娘がかかっているだけに、必死さも段違い!これだけ取り乱す2人の姿に焦燥感が更に募る。
ラストは激しい闘い。
ってかお父さん、あんな重たそうな鏡降ってきて無事なのかよ…!?
そしてサイモン、しれっと再合流w
上述の通り、ホラーでサスペンスで家族ドラマな本作。これで最後との事だが、アナベルやヴァラクの作品ももう観れないのだろうか?
色々と謎のまま終わるのがホラーの様式美でもあるとは思うが、まだまだ観たいなぁ。死霊館のシスターだって更なる前日譚あっても良さそうだし…。
後は…骨董市には週刊ストリーランドのおばあちゃんみたいなのが絶対いるのだろうか…?
描かれないことが多いけど、始まりは大体そこなので、そこを掘り下げた作品も観たいかも。
…とまぁとにかく、これで本当に最後ではなければ良いなぁと思わさた作品だった。
実在の悪魔祓い夫婦の話を映画化しているようですが、洋画ホラーにあり...
全115件中、61~80件目を表示