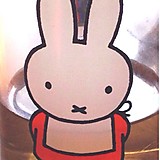黒川の女たちのレビュー・感想・評価
全37件中、1~20件目を表示
戦争はいつでも男の顔をしている
黒川開拓団のことは以前から知っていたが、当事者の方々の実際の声を聞いたことがなかったので、とても興味深かった。
戦争だから
生きるためだから
みんなを守るためだから
様々な大義名分を無理やり突きつけて、半ば強制的に犠牲にさせた乙女たち。
戦争が無ければ、青春を謳歌し、人によっては素敵な恋をして、様々な選択肢ある未来を歩めた乙女たち。
本来ならば、守ってあげなければならない立場の乙女たちに、戦争を起こさせた大人たちが、さらに地獄を味合わせた現実に反吐が出る。
そしてそれを恥ずかしいことだと隠し、そのせいで周りに歪んだ認知を引き起こし、差別や偏見を招く状況にさせたこと、彼女たちが立ち上がるまで何もしなかったことにも反吐が出る。
この事実を無かったことにしないように尽力した人々には頭が下がるし、これを記録として映像に残したことは素晴らしいことだと思った。
ただドキュメンタリー映画という視点で見ると、もう少し構成や編集はブラッシュアップできたのでは無いかと思う。
当時の様子をわかりやすいイメージ図に起こすとか、加害者の男性側のインタビューを複数入れたりだとか、もう少し作り込みや工夫が欲しかった。
なので、点数をつけるのが難しく、ドキュメンタリー映画としての観点と、映画のテーマ性やこの作品の目的の間を取り、ちょっと厳しめにつけました。すみません。
劇中でもある男性が言っていたように、なぜこんなことが起こってしまったのかを考え続けることが、今の私たちには必要だと思う。この作品はそのきっかけを与えてくれるような作品だった。
性暴力は根絶する?
世間の風当たりの情けなさ
〈映画のことば〉
「生きていてくれて、ありがとう。」
もちろん、賛否の両論はあるだろうと思います。
しかし、結果としては生きて故国の土を踏む日を再び迎えることができたことは、黒川開拓団の「この決断」にあったことは、否定しがたいこととも、評論子は思います。
令和の今ならともかく、軍人だけでなく、国民の一人ひとりまで「生きて虜囚の辱(はずかし)めを受けず」と教えられていたはずです。
現に当時の満州でも他の開拓団は集団自決自決を選んだとのことですし(中国とは別の戦いだった)沖縄戦でも、多数の現地民が、しかもアメリカ兵の目の前で、崖から海に身を投げたりして、自決という選択をしているという、その世相の中で。
仲間の命をつなぐために、黒川開拓団で「この決断」ができたことは、評論子には、奇跡的にも思われます。
そのことは、本作での「接待」に実際に従事したという女性にかけた、彼女の娘さん(お孫さん?)による、上記の映画のことばにも、如実に表れているというべきでしょう。
極限的な状況にあってもらともかくも「命を繋ぐ」という選択ができたことは、十二分に「英断」としての評価に値すると、評論子は考えます。
むしろ、評論子が気になったのは、やっとの思いで帰国した彼女らに、世間の風当たりは、決して優しくはなかったとのことでした。
脳科学者の茂木健一郎は、「挑戦できる人と、できない人の違いは?」と題して、こんな一文をものしています。[「ピンチに勝てる脳」2013年、集英社刊・集英社新書)]
「日本には、自分が日本の代表となっての中で戦おうとする人があまりに少ないのが現状です。そして、もっと悪いことには、海外で戦おうとする人の足を引っ張る日本人も少なくありません。僕が最初にアメリカに行ったときも、「日本人がアメリカに行っても通用するわけがない」といったような非難をさんざん浴びました。どういうわけか、日本人というのは、自分たちの仲間が挑戦しに行こうとするとき、必ず足を引っ張ろうとするようです。そして、失敗して帰ってきた人に対しては「それみたことか」という意地の悪い気持ちもあるかもしれません。」
「僕は今、英語のブログを毎日書いているのですが、そのブログに対してのコメントの仕方が日本人と外国人では、かなり違います。日本語で英語へのコメントを書いてくる人の中には、アメリカやイギリスに住んでいる日本人や、もしくは昔、海外に住んでいた経験のある人がいます。その中には、時折なんとも奇妙な人たちがいます。単語のスペルが間違っているとか、文法的にそういう表現はないとか、要するに、茶化すような内容か、人を貶(おとし)めることを目的として書かれたものがあるのです。ところが、外国の人が、僕の英語のブログにコメントをくれるときは、僕が書いたブログの内容の実質的なことにしか触れてきません。僕の英語のブログに対するコメントを見ていると、挑戦できる人と、できない人との違いが見えてくる気がします。」
本作での黒川開拓団の決断は、ある意味、団員の命を賭した「挑戦」でもあったのだと、評論子は思います。
その「団員たちの命を賭した挑戦」を経て、命からがら故国に帰った「接待」の女性団員に、心ない批判を浴びせかけたという当時の(令和の今も?)の「世間」という日本人たちの「足の引っ張り合い」には、失望を通り越して、情けなさを感じざるを、評論子は得ません。
作中に説明的なセリフがない(あるいは極端に少ない)ためか、あまりドキュメンタリー作品の鑑賞が得手ではなかった評論子にも、本作は、ズンと胸に迫る一本にもなりました。
そのことでも、本作は評論子の「ドキュメンタリー苦手意識」を、グッと軽くしてくれたようにも思います。
充分に佳作としての評価に値するものと、評論子には思われました。
(前記のとおり、黒川開拓団のこの「決断」には、賛否の両論があろうかと考えます。
評論子のこのレビューも、そういう多様な価値判断を否定するものではなく、レビュアーの皆さまにも、あくまでも評論子が本作を鑑賞しての一本のレビューとして受け止めていただけると、幸いです。)
(追記)
それにしても。
愛娘たちを「接待」に送り出すと決めた時の、彼女たちの親子さんの心情は、いかばかりなものだったでしょうか。
彼女らに勝るとも劣らない艱難辛苦だったことでしょう。
「戦争の不条理」というものは、こんなところにまで顔を出すものなのかと思うと、本当に胸が痛みます。
そのことを声高に訴えてはいないとしても、本作も立派な「反戦映画」だったという受
け止めをしたのは、独り評論子だけではなかったこととも思います。
【感涙】地元ミニシアターで上映される機会が来るのを待っていました。
・7月のテレビ朝日の報道ステーションで「ドキュメンタリー映画「黒川の女たち」が間もなく上映されます」というニュースが流れてから、地元ミニシアターで上映される機会が来るのを待っておりました(東京都内等の映画館まで出かけるフットワークがないため)。
・満州開拓団をはじめとした「民間人」は、ソ連国境沿いに置いてけぼりにされ、関東軍はさっさと撤退し、日ソ中立条約が破棄された後、ソ連が攻め込んできた事は、「映画ラーゲリより愛をこめて」を観るまでもなく、歴史的史実として承知しておりましたが、18才ぐらいの若い女性が「黒川開拓団」をソ連軍や満州の現地民から守るための犠牲となり、ソ連軍の性暴力に服する事実は唖然とするしかありません。映画館内の女性観客がすすり泣きをしていました。
・「なかったことにはできない」。この心の叫びは、現在90歳過ぎの女性たちが「今語っておかなければ、歴史の中に埋もれてしまう」という危機意識から、顔を出してまで映像の中に登場して告白するという行為につながったのでしょう。
・現在は「男女共同参画社会の構築」、「女性の自立」という言葉が当然のように語られますが、戦争当時は男尊女卑の社会であり、女性は男性に仕えるという社会風潮だったと思います。現代がいかに恵まれているかという事がよくわかりました。
・この映画が上映されているのは主に「ミニシアター」。黒川の女たちの事実はもっと広く世間に知られるべき事ですが、シネコンでの上映はイオンシネマなどの一部にすぎません。そのことは残念に思います。
・この映画が作成された事、黒川の地元に乙女の碑(プレート)ができたので、後世に史実が残されたのは良かったと思います。
・この映画を鑑賞できたことに感謝いたします。
黒川の女たち
終盤に登場した男性が、「あんたの母親が、そうだったら、あんた嬉しか?」的な事を言っていた。
完全に男目線の言葉が心に沁みた。
このドキュメンタリーを観ていなければ、自分もこんなだったのではないか。
そこに気付いたのは、この作品のおかげでした。
女性達が供物にされ、助けた男達に蔑まれた人生。
長かったでしょう。
敬意しかありません。
右傾化する世界、そして日本。
今だから、観るべき作品です。
これを授業に取り上げた教師の言葉。
「これを教えないと、知らないままになってしまう。」、敬意を表します。
そして、父親が行った行為に真正面から向き合った、遺族会の会長。
その勇気にも、心から頭が下がりました。
これを製作した、
TVアサヒ、ありがとうございます。
NHK、何してんの。
歴史は人
思う事が多いので、映画自体を評価するのが難しい。
こうして話してもらえる環境に至るまで80年かかった訳で、生きて歴史を聞くことのできる自分に何が出来るのかと逡巡します。
戦争でつらい体験をした誰もが、生きている間にちょっとでも救われてほしいと願います。
違う意見の人もその地域に存在する事が(私個人は彼に賛成できないが)凄いと感じました。
また、遺族会?の長の姿勢や態度が勉強になりました。
詫びるとはこういう事かと。
「太平洋戦争」の敗戦で、戦争の悲しさがとても強く長い期間伝えられてきたけれど、ちゃんと勉強して「大東亜戦争」を振り返りたい。
マスコミがそれをもっと助けてくれたらありがたい。
日本に住んでいる人全員がこの映画見たらいいのに、と思いました。
戦争の犠牲者はいつでも弱い人たち
1930~40年代に日本政府の国策のもと実施された満蒙開拓により、日本各地から中国・満州の地に渡った満蒙開拓団。日本の敗戦が濃厚になるなか、関東軍は南下し1945年8月にソ連軍が満州に侵攻してきた。開拓団の人々は守ってくれる軍が居なくなり、命の危険にさらされた。岐阜県から渡った黒川開拓団の人々は生きて日本に帰るため、数えで18歳以上の15人の女性を性の接待役として敵であるソ連軍に差し出し助けを求めた。帰国後、女性たちを待ち受けていたのは差別と偏見の目だった。心身ともに傷を負った彼女たちの声は消され、この事実は長年にわたり伏せられることになった。しかし終戦から約70年が経った2013年、ソ連将校への性接待を行った黒川の女性たちは重い口を開き事実を公の場で語りはじめた。そんなドキュメンタリー作品。
ソ連は終戦後も民間人を襲ったり、シベリアへ連れていって過酷な労働を行わせたり、卑怯なのは昔から変わらないんだな、と改めて思った。
そんな中、黒川開拓団全員が殺されるか、ソ連将校の機嫌を取って生贄的に性接待をお願いされ、断ることもできず、対応した15名の独身女性の方には頭が下がる。
自分の娘、孫まで差別を受ける事を恐れて事実を話せなかったのも凄くよくわかる。広島で原爆を受けた被爆者も同じような思いだから、自分のことのように思えた。
戦争の犠牲者はいつも弱い人たちだなぁ、という感想で、この思いはどこにぶつければ良いのだろう。
まずは、多くの人にこの作品を観てもらい、知ってもらうことからかなぁ、とも思う。
機会があったら岐阜県白川町の乙女の碑を訪ねてみたい。
人権尊重の歩みを進めてきた成果
もとになった番組は、放送時に試聴済みだったが、今作は幾重にも深まりを増したドキュメンタリーになっていたと感じた。今年観た、戦争関連の作品の中で、自分にとってはno.1。
自分が強く印象に残ったのは、「接待」の事実を証言された方の孫たちが、口を揃えて「(証言された祖母を)誇りに思う」と語っておられたことだ。
この発言こそ、戦後の日本が、人権尊重の歩みを一歩ずつ進めてきた成果だと思う。
そして、80年間に渡って平和な時代を重ねてきたことで、人としての尊厳について、私たちが想いを致せる環境にある今を、これからも決して損なってはいけないと強く思わされた。
作中、ご自分の「接待」の事実を、長い間証言できなかった方が、お孫さんに「(それを公にされてから)とてもよく笑うようになって、表情が明るくなった」と評される場面が出てくる。
そこからわかるのは、「決して口外してはいけない」というのは、一見被害者の心情を慮ったようにみえても、一貫して加害者(差別者)の論理で、それに従う被害者(被差別者)は、自分で自分を差別していることと同じになってしまうという悲しい事実だ。
差別に関わる事象の際に、よく語られる「寝た子を起こすな」は、やはり完全な誤りであることが、ここでも証明されている。
そうした点で、碑文の建立に力を注いだ、遺族会の4代目会長の尽力には、本当に頭が下がる。
多くは語られなかったが、身内の過ちに向き合わざるを得ない苦しさと格闘しながら、丹念に「接待」の犠牲になった方々を訪問されて、碑文建立を達成された姿勢(寝た子を正しく起こす姿勢)は、先の戦争との向き合い方として、私たちも忘れてはいけないと思う。
最後に、女子校の授業(多分、探究の授業と思われる)で、この問題を取り上げられている先生と生徒たちが描かれたが、こうした加害性と被害性が複雑に入り組んだ事象を、共に真っ正面から考えようとする姿勢に希望を感じた。
戦争に関してのわかりやすい語りは、得てして危うさを多分に含むことがある。そういう意味でも、今作の冒頭で満州事変や関東軍、そして開拓の実態について触れられていた意味は大きく、自分自身も、最近鑑賞した「蟻の兵隊」等とつなげて考えることができた。
戦争にとどまらず、人の尊厳について考えるきっかけになる作品なので、ぜひ多くの方が、観て考えて下さることを願っている。
いつも犠牲は民間人
あの戦争による「性接待」
希望を感じるラスト 見てよかった
戦後80年。戦前・戦中・戦後の「事実」の検証はなにも終わっていない
この映画は岐阜県黒川村の村人がなぜ満蒙開拓団員となって、満州に渡りどのような生活をしていたかを、映像で説明しているので当時の状況をよく把握できた。ことはソ連が侵攻してからおこった。関東軍は開拓団員になにも知らせず退却し、そして敗戦。開拓団員は誰の助けもなくソ連の支配下に入る。そして満州を支配していた日本人は、現地の中国人を侮蔑する扱いをしていたから、中国人から復讐を受けることになる。
黒川開拓団の上層部は、中国人から身を守るためソ連将校に協力を依頼した。その見返りは、若い女性の性接待であった。なんとか黒川村に引き上げた開拓団の上層部は、性接待をなかったこと不問にした。村では性接待した女性たちに噂をたて汚れた女として差別した。
時を経た後、当事者の老女数名が性接待の事実をありのままに話し出した。誰が呼びに来てどのように性接待したのか、詳細に。見ていて驚いたのは、自分たちの行為を堂々と話す老女らの姿だ。
老女たちの行為は、恥部ではなく、黒川開拓団員全員の身の安全を守るためだという信念からのものだった。誰に恥じることもない、自分に恥じることのない勇気は、このあった「事実」を後世に伝える、残さなくてはいけないというただ一つの思いだけだ。その気迫に圧倒されてしまうばかりだ。
松原文枝監督は「事実」を語る老女たちと真正面から向き合う。本人たちだけでなく、遺族や関係者にもカメラを回し「事実」をあぶりだす松原監督は伝承者として老女とともに存在し、特に村の「男社会の論理」が今まで不問にしてきたことに大きな疑念を持ち、問い正す強い意志を感じた。
今年は戦後八十年。戦争は本当に終わったのだろうか。今まで知らなかったことが幾多もあるのではないか。戦後八十年の「検証」は本当になされているのか。戦前・戦中・戦後におきたすべての国民の死と生きる苦しみの「事実」が、すべて伝承されていないし「検証」できていないのだ。松原監督は「事実」をフィルムに刻印し残し伝える使命感を持ち「検証」したのだ。
乙女の碑に行ってきました。
映画を観て、パンフを購入して読み、岐阜県白川町にある「乙女の碑」に行って花を手向けて来ました。「岐阜県の白川」と言っても合掌造集落で有名な白川村とは全く別の場所です。「美濃白川」と呼ばれています。静かな山村ですが極端に辺鄙な地域ではなく、名古屋や岐阜からもまずまず行きやすい場所ではあります。黒川集落の鎮守の神様である佐久良太神社の境内に「乙女の碑」はありますが、碑文は本当にぎっしり書いてあって、これをしっかり読むことによっておおよそのことが分かるようになっている丁寧でかつ学びの多い碑文だと思いました。猛暑日の午後、神社の境内に30分ぐらいはいましたが、地元の方も含めて誰もいませんでした。境内は非常に良く手入れがされていてこの場所が昔も今も村の鎮守としての役割をしっかり果たしているなあと思いました。前述の飛騨の白川村とは異なりほぼ観光色のない場所(失礼)なのでオーバーツーリズムの心配はないと思います、地元にしっかりお金を落として訪れてみてはいかがでしょうか。
別の話です。作品やパンフの中(主にパンフ)でどうしても納得できない部分があります。自分の中でまだ整理ができていません。また投稿したいと思います。
戦争と性暴力の事実
ひとつづつ明らかにされるべき満蒙開拓団の悲劇
80年前に満州で性被害にあった女性たち。これは彼女たちの証言により史実を未来に伝えんとするドキュメンタリー。
1932年(昭和7年)、中国の東北部に日本の実質的な植民地として建国された満州国。日本政府の国策のもと農業移民団である満蒙開拓団が日本各地の農村から入植した。
まずは多くの人が満州へ渡ったシステムを再認識する。
1941年から44年にかけて岐阜県黒川村(現・白川町)から渡った黒川開拓団。1945年8月にソ連軍が侵攻し、過酷な状況に追い込まれた。18歳以上の女性15人を性の相手として差し出すことでソ連軍に守ってもらう道を選択した。
帰国後の差別と偏見。
事実は長年にわたり封印されることに。
しかし終戦から68年が経った2013年、黒川の女性たちは手を携え、加害の事実を公の場で語りはじめた。女性たちの証言を松原文枝監督が丁寧に紡いだ。感動的なドキュメンタリーになった。
ただし黒川開拓団の悲劇は氷山の一角。
日本全国で約800の開拓団、27万人が満州り、8万人が犠牲になったという満蒙開拓団。困窮する農民を嘘のプロパガンダで誘導し、満州に置き去りにした日本政府が「死者の数では計り知れない悲劇」を産んだ。
哀れ棄民政策の果ての陵辱
冒頭、「満蒙開拓」の実態がいかなるものであったかが明かされる。傀儡国家・満州を実質支配する関東軍が入植者を配置したのはソ満国境沿いであり、ひとたび急あれば入植者を徴用する意図があったこと。日本各地から貧農を集め、甘言を弄してあてがった土地は、現地農民の家屋田畑を接収したものであったこと。未開の地を開拓するのではない、武力をもって収奪した農地を居抜きであてがったのだ。さらに、入植した日本人部落の人員構成など詳細な情報がソ連側に知られていたこと。
黒川開拓団の悲劇がそのあと語られるのだが、まずもって杜撰ででたらめな植民地である満州に、多くの日本人を送り込んだ政府・軍部の棄民政策にこそ原罪がある、と制作者はこの序章を忘れなかった。
戦時中の性被害というと慰安婦問題が想起されるが、これも当事者からの告発がきっかけであった。なかったことにされては2度死ぬことになる。悲痛な声に我々は耳を傾けなければならない。
全37件中、1~20件目を表示