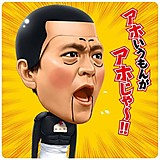大長編 タローマン 万博大爆発のレビュー・感想・評価
全173件中、1~20件目を表示
岡本太郎も大喝采!大公認!
まずここまでデタラメでふざけたものを作りきったその熱量に惜しみない賛辞を送りたい!そこまで突き抜けている。
しかも、単なるおふざけ映画ではなく、根底にはしっかりと岡本太郎のメッセージが流れている。芯があるのだ。意外にも深い映画であったことに驚かされた。
またテンポのいいこと!
でたらめ8兄弟登場シーンには不覚にもワクワクしたぞ。
なんにでも「大」をつけるぞ。「一流」も。
絶対飲みたくない「太郎汁」。
スクリーンが!おもしれえ。
(↓刺さったワード)
応援してはならない
でたらめるな
お利口さんになるな
人のことを気にするな
べらぼうな夢はあるか?
デタラメをやってごらん
好かれる奴ほどダメになる!
マイナスに飛び込め!
響くぅぅぅっ!
✳︎パンフレットは買いですよ。
変身ポーズやエランスティックの秘密、立体メガネまで「付録」が盛りだくさん^_^
いささか騙されているような、煙に巻かれる痛快さ
もともとテレビでやっていたタローマン自体、自分にとっては決して可笑しくて笑えるとかではなく、手作りのクラフトマンシップと岡本太郎というモチーフが放つキテレツでありつつ説得力のある哲学性みたいなものに幻惑されて面白いかどうか判別できないままに観てしまう奇妙な番組だった。そのノリとテンポをそのまま映画に持ち込んで、延々と100分くらい続けてみようという趣向には軽い狂気すら感じるが、だんだん観ているこちらの感覚m麻痺してきたくらいのところで、やはり哲学が思想みたいなものがじわじわと沁みてきて、気がついたら反骨と現代批判にすら取れるクライマックスにまんまといい映画だったなと思ってしまっていた。それが順当な評価なのか、いささか騙されているのではないかと疑ってしまうとこもタローマンぽくて実に良かった。
岡本太郎を軸に「1970年での世界観から2025年を想像して描く」という、思わず「何だコレは?」と言ってしまいたくなる奇抜な意欲作!
昭和45年開催の大阪万博を体験していない人でも、シンボルである「太陽の塔」は知っているでしょう。この「太陽の塔」を作ったのが芸術家である岡本太郎。
改めて「太陽の塔」という有名な造形物を眺めると、正面なのに曲がった鼻や口など、万博のシンボルとしては独創性に溢れ過ぎています。
当時の人も「何だコレは!」と衝撃を受けたでしょうが、「何だコレは!」も含め「芸術は爆発だ!」「芸術は呪術だ!」など、岡本太郎の有名なフレーズや造形物が本作で重要な骨格を形成しているのです。
1970年(昭和45年)に開催された大阪万博が、2025年(昭和100年)に再び開催された現在。
本作は、岡本太郎を軸に「1970年での世界観から2025年を想像して描く」という、思わず「何だコレは?」と言ってしまいたくなる作品なのです。
この作品が実際に1970年代に作られたのであれば、当時の映像技術では物足りなさが出たと思いますが、あくまで本作が作られたのは現代なので映像表現も見応えがあります。
岡本太郎という稀代の芸術家が遺した数々の表現も、今だからこそ刺さるものがあります。
「失われた30年」といった言葉が出ている現在の日本。
「現在の日本」と、本作で描かれる「1970年での世界観から想像された、夢と希望に満ちた2025年」を比べてみることで、「本当に現在の日本は経済がダメになっているのか?」を考えたりするのにも適した作品だと思います。
いわゆる脱力系だがNHKらしく堅実。しかしテンポが悪く冗長。
2025年公開作品
初鑑賞
U-NEXTで鑑賞
NHKで放送されたドラマ版は何度かチラッと観たことがある
監督と脚本は『セイカイはのび太?』『77部署合体ロボダイキギョー ドラマ・伝え方が9割』の藤井亮
1970年のタローマンとCBGが昭和100年の2025年にタイムスリップする話
60年代の怪獣特撮映画を彷彿させなくもないそれともまた違う独特のノリ
外国人が演じているエランの娘はともかく日本人なのに声もわざわざ別人が当てている
怪獣はこの世界では奇獣と呼ぶ
タローマンは奇獣数匹をあっさり片付け海辺でシャンソンな食事の時間
所謂デタラメである
タローマンや奇獣やエランの娘のデザインは岡本太郎作品がモチーフになっている
それが良い
たびたび岡本太郎の肉声が使用される
登場人物の会話のなかでたびたび岡本太郎の数々の名言が多用される
青春映画との二本立てで昔こういう映画あったという設定で岡本太郎好きなサカナクションの人が解説している
舞台挨拶ではNHKのスタッフたちをサイコパスと称した
TVドラマは毎回5分程度だから良い
狐につままれる感じで
「なんだこれは」も二時間弱となるときつい
そもそも藤井氏は映画監督ではない
今回長編映画は初挑戦
CMとかMVと短いやつの方が
せいぜい長くても30分
それを超えるとちょっと
映像作家として売れているようなので当然センスは感じる
ちゃっちい映像だがあえてそれをやってるわけでそれが絶妙
配役
タローマンに岡村渉
CBGの隊長に森野忠晋
CBGの紅一点のマミ隊員に小笠原皆香
CBGの隊員でサイボーグの風来坊に川端英司
CBGの中年隊員にべーやん
CBGの青年隊員に伊達要希
少年隊員に北村直大
高津博士にボブ・マーサム(村角太洋)
鷲野蛭賀社長に堀田マナブ
鷲野社長の部下に高見健
2025年からやってきたサイボーグのエランに岡村渉
声の出演
ナレーターに賢太郎
鷹野社長に賢太郎
隊長にアドレナ・リン
マミ隊員にマザえもん
少年隊員にマザえもん
タローマンマニアに山口一郎
この映画を旧万博会場で見ました。
発見された幻——万博とともに甦るタローマン
うーん
日が合わなくて、応援上映というとんでもない日にあたってしまった😅周りのノリには全くついていけず。挿入歌みたいな途中途中の歌を、なんでこの人たちは歌えるの?何回リピートしてるのって驚かされた。
万博と太陽の塔、月の石など、行きたくてしょうがなかったけど、大阪までなんか貧乏でそんな余裕のなかった小学生時代。太陽の塔は憧れで、今でもいけてないけど、あんな風に扱われて、とかは別に言わないけど。ストーリーとしては、ところどころで、昭和のニュアンスが散りばめられててクスッとしてしまったところもあったので、★1にしました。配信を待って見ようかなとも思ってましたが、配信だったら最後まで見なかったかな。
好きな人は刺さりまくると思われる(☆は付けにくい)
舞台は1970年の大阪万博で, 当時の目線で架空で作った未来像 2...
主題歌が素晴らしい
爆発だ、爆発だ、爆発だ、芸術だぁ♪
街に襲来する謎の奇獣達をでたらめ殺法で次々と撃破するヒーロー(?)タローマンのお話なのだが、先ず70年大阪万博の時代の荒っぽい映像や妙に説明臭いセリフや特撮技術が素晴らしい
そして舞台を大宇宙万博の控える2025年に移してからは秩序vsデタラメとなるのだが、まるで昭和のコンプラを無視していたバラエティ番組vs現代のコンプラ重視していたバラエティ番組みたいだった
残念なのが2025年世界でのタローマンが戦うまでが結構暇だったね
ちょいちょい場面の切れ目で登場する「タロォォウマァァァン♪」が変に癖になる
上映中ずっとスクリーンのサイズが小さい気がしていたが、まさか終盤にスクリーン上下の幕を捲り上げて敵奇獣を殴りまくるアイテムにする為にわざと小さく見せていたのはお見事!! っと岡本太郎も言っていました
とんでもなかった。
稚拙な感想ですがでたらめでべらぼうで泥臭くて真剣で、
終盤は泣いてしまいました。
今、涙がぶり返している。
きれいでないものも認めようという精神は昭和から岡本太郎さんは唱えていたのだなと思ったし、
昭和中期の映像の再現が秀逸。訂正。これは撮り直しなどはしていないようですね。
ということは映像の繋ぎ合わせ?メイキングを見てみたいです。
キセルを持った早口の博士、太っちょの子ども…
ベタでとても良い。
昨今ニセモノまがいの昭和ドラマもよく見ますが当時のブラウン管映像を彷彿される懐かしさ。
この古き良き日本を垣間見れるは語り継がなければならない。自分にとっては初見だったのだが
あと結構自分は爆笑ポイント多かったです。映画館は割と静かでしたが…
だめだこりゃ。
太郎汁のような劇薬を105分間飲まされ続ける映画
見ていて疲れるが見た後に、芸術に浸りたくなる そんな感想をこちらが持った時点でタローマンの勝利じゃなかろうか。そんな感じがした。
タローマンをご存知ない人にいえば、ある意味ボボボーボ・ボーボボのような劇物を見続けている感覚に近い。まさに劇薬だが、面白いしストーリーはちゃんとしている。
令和の技術で本気の昭和特撮に向き合っているし、円谷ウルトラマンリスペクトも忘れないし、岡本太郎の作品経歴そのものが伏線になったりもする。全部めちゃくちゃだけど筋が通る作品でした。
自分は平成産まれではあるものの、ドラえもんや鉄腕アトムを読んだことがあるので昭和の人々が未来をどう想像していたかは何となく知ってる。昭和産まれでないなら、その昭和人たちの想像を何となく覚えたうえで見るべきだとは思いました。
見るのがキツい
タローマンを知り合いから聞きノリで鑑賞。
公開が短縮され最終日で30人くらい居た。
上映は県で一館のみ。横の県の劇場を見たら0人。地域で人気が違う様。
事前情報を全く知らずに見たが、
古臭過ぎてキツい。この昔ながらのベタな昭和特撮が好きな人は良いんだろうか、良さが全然分からない。笑ってるのは50代くらいのオッサンのみ。多分好き嫌いが分かれるので
かなり好きじゃないと映画を観にこないんだと思う。
黒電話式の携帯電話を使う事にオッさんの笑いが起きていたが、ギリギリ分かるレベルなのであーなるほどくらいの感想だった。
癖が強く、多分好きな人は好きなんだろうが、
嫌いな人はとことん嫌いになる映画。
友達は途中から寝ていた。
万人受けは絶対にしなく、気軽に女性を連れていけない映画。
自分の中に毒を持て!
最高の映画
3本目にはちときつかった。
特撮作品の原点回帰であり、到達点
全173件中、1~20件目を表示