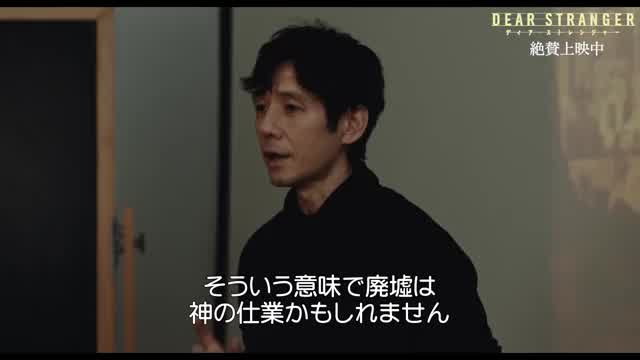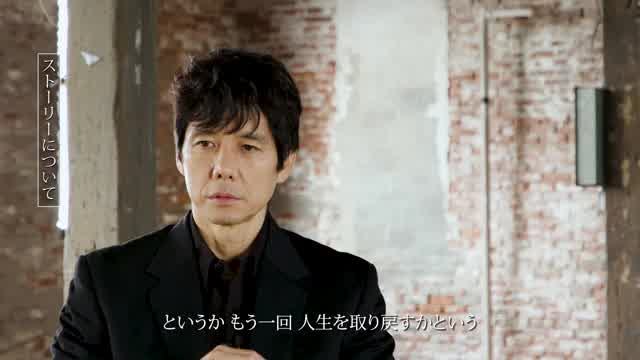「最も近しい他者――『Dear Stranger』が描く父の無力」Dear Stranger ディア・ストレンジャー 基本的に映画館でしか鑑賞しませんさんの映画レビュー(感想・評価)
最も近しい他者――『Dear Stranger』が描く父の無力
人はなぜ他人を狂わせるのか。この作品を観た後に残る問いは、単純な「犯人は誰か」ではなく、人と人の関わりが持つ暴力性そのものだった。
物語の表層はこうだ。ニューヨークで暮らす日本人研究者・賢治と台湾系アメリカ人の妻ジェーン、息子カイの一家が、強盗事件と誘拐に巻き込まれる。強盗に入った移民労働者ドニーは、貧困と孤独に追い詰められ、やがて子を人質にとり暴走する。そして最終的に彼は自殺し、無実の賢治は自首する。だが事件の細部は曖昧で、殺人の瞬間も描かれない。そこにこそ監督・真利子哲也の狙いがあると考える。
象徴的なモチーフは数多い。廃墟は「震災の記憶」と「壊れた心」を映す鏡、車の異音は「見て見ぬふりをしてきた夫婦の不和」、人形劇は「母が子に命を吹き込もうとする創造」であり、賢治の発砲は「自己崩壊と罪悪感の爆発」である。抽象的で難解に思えるが、すべては「生と死」「再生と断絶」の二項対立を際立たせる仕掛けだ。
興味深いのは、ドニーと賢治の対比である。妊娠を知って逃げたドニーと、逃げずにジェーンとカイを受け止めた賢治。社会的には同じ「Stranger=異邦人」だが、選んだ態度が正反対だった。ドニーは「なれなかった父」として賢治を鏡に見て劣等感を募らせ、羨望と嫉妬を破壊衝動へ転化する。だからこそ暴力はジェーンではなくカイ、すなわち未来の象徴へと向かう。
一方で、賢治もまた強くはない。彼は逃げなかったが、事件以前から家庭に深く関わることを避け、研究に没頭していた。ジェーンやカイに寄り添うより、自分の世界に閉じこもる時間が多かった。車の異音や夫婦の軋みを放置してきたように、日常の不和にも無関心だった。その積み重ねが、強盗に居合わせず家族を守れなかった現実と重なり、「父として無力だった」という痛切な自己認識へと結びつく。だからこそ、無実でありながら自首するという極端な自己罰を選んだのである。
ラスト、刑事がジェーンを訪ねる場面は結論を示さず余白を残す。真相は不明なまま、観客に「あなたはどう解釈するか」を問いかけて幕を閉じる。
『Dear Stranger』は、推理の答えを与えない不親切な映画だ。しかしそれは、人と人が本当には分かり合えない現実を映し出すための誠実さでもある。最も近しい家族ですら他者であり、他者との関わりが時に人を救い、時に壊す。その残酷さと、かすかな希望を同時に抱かせる映画だった。
コメントありがとうございます。
余韻がある作品は好きなのですが、文化的にも階層的にも交わらない人々を無理やり結びつけた印象がずっと残って、どうもダメでした。
せめて、テンポがよければ。