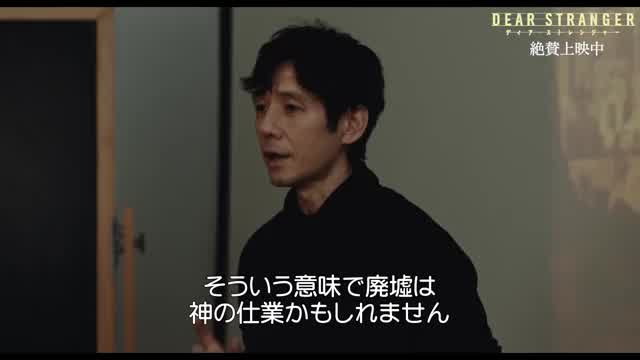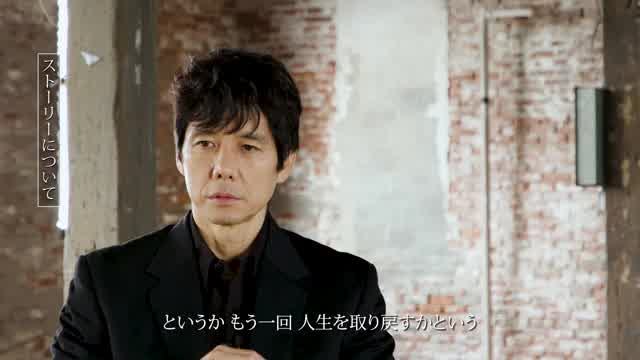Dear Stranger ディア・ストレンジャーのレビュー・感想・評価
全77件中、1~20件目を表示
ストレス耐性が強めの方なら
白状すると、真利子哲也監督の作風が苦手だ。身体的暴力や精神的圧迫の描写で鑑賞にストレスが長い時間伴うから。最新作「Dear Stranger ディア・ストレンジャー」ではもっぱら後者の精神的なストレスを観客に共有させるシーンが多い。もちろんストレスへの感受性と耐性は人によって異なるし、真利子監督の作風が大好きなファンも多かろう。ストレスへの耐性が強めの方なら、本作への評価も高くなるのでは。
グイ・ルンメイはお気に入りの女優で、日本を除くアジアの女優では一番好き。十代後半のデビュー作「藍色夏恋」(2002)を含む青春ものから、恋愛、アクション、ヒューマンドラマと、年齢に応じて出演作のジャンルと役柄も移り変わったが、ベルリンの金熊賞を受賞するなど高評価された「薄氷の殺人」(2014)のファム・ファタールが素晴らしすぎたせいか、以降は「鵞鳥湖の夜」そして本作と暗めの役柄が多い気がする。
ニューヨークで暮らす日本人助教授(西島秀俊)と台湾系アメリカ人の妻(グイ・ルンメイ)が一見愛し合っているようで互いに本音を隠している節があり、さらに幼い息子の失踪も相まって夫婦間のストレスが表面化し高まっていく。母国語がそれぞれ日本語、台湾語の夫婦は英語で会話しており、このコミュニケーション不和もストレスの一因に。私自身短期間ながらアメリカで過ごした経験があり、ストレスが限界を超えて母国語で悪態をつくシーンには大いに共感した。
直接的なバイオレンス描写はほぼないものの、グイ・ルンメイが大型の人形を操るシーンは本作随一のダイナミックなスペクタクルになっている。なお、10月24日に日本公開されるリュック・ベッソン製作アクション「ドライブ・クレイジー タイペイ・ミッション」でのグイ・ルンメイは、やはり幼い息子のいる妻だが天才的ドライブテクニックで台北の街を駆け抜けたり、元恋人の米国人捜査官と喧嘩したり甘い雰囲気になったりと、多彩な魅力で楽しませてくれる。好対照の2作の役柄を見比べるのも一興だろう。
人形の意味は?
多分混沌とした、いわゆるカオスな状態を描きたいのかな、生きているということ自体がカオスの中にいることだということが言いたいのかな?と思ったりしたのだが、脚本が曖昧過ぎるのと、ブツ切りのフィルムを繋げた感があるのと(実際映画ってそうなのだけれど)、登場人物の誰もがそこにいるようでいない人のよう、実在感が薄いのだ。
強いていえば子供の実父の彼女だけが生きている人のようだった。
かといって淡々とした中に何とも言えない味があるとも言えず、申し訳ないけれど、多分監督と私の感覚が合わないということなのだろうと思う。
刑事さんいきなり脈略なく登場とか。
突っ込みどころ満載。
にしても!
恐怖の人形w
これに何の意味があるのだろう、きっと意味があるに違いないと思って最後まで観たのだけれどわからなかった。
あれだけ人形に時間が割かれていたのに。
私の感性が鈍いのか?
そして「こんなエキセントリックな奥さん、私でも嫌だ」になってしまった。
夫の方も夫の方で「廃墟の研究者」なのだが、それも周りから理解されない。
変わり者夫婦の話だった。
タイトルなし(ネタバレ)
話の筋はとても好みだっただけに、細かな物語の展開で大きな損をしている印象。
主演が西島秀俊という共通点もあって、序盤から日常と不安が共存する部分は黒沢清監督の"クリーピー 偽りの隣人"を想起させる。しかし、サスペンスではなくヒューマンドラマとして描いた部分があり、クリーピーほど人間存在というものの不可解さ、精神分析学的な無意識とカオスを表現しきれていない。
西島秀俊演じる賢治は震災で家族を亡くしている。理不尽そのものである世界の訪れを体験したにも関わらず、それが廃墟に魅入られるキッカケとなるのみで不可解な世界存在そのものと向き合おうとしない。むしろヴェールに覆われた仮初の社会的存在であろうとする。妻の不平に対して呑気に返事をする振舞いと合わせて、この理不尽に対する無頓着さに鑑賞者は苛立ちを覚えるだろう。
ニューヨークで暮らす夫婦は共に母語の違いで言語による自己表現が困難である。だから妻は人形劇というアクティブな、一方夫は廃墟研究というパッシヴな方法で自己表現を行なう。妻がそのような不自由を夫と共有したいのは明白であるのに、あくまで一般化された生活、父性を望む夫はやはり無頓着である。思いかえせば、この家族は序盤からほとんど視線が邂逅しないではないか。賢治が自著の講演会で廃墟の必要性と不可視化の危険性を訴えながら苛立つのは、自分自身が最も身近な廃墟"Blank"から目を背けていたことに気づいてしまったからだ。結局、"Blank"の烙印が消えることはなく、車はまるで何かのアラートかのように悲鳴をあげ続ける。
こうして思い返してもやはり話の筋は良い。でも最悪なのはラストだ。賢治は結局、事件を追っていた刑事に嘘の自白をしてしまう。まるでそれで罪が償われるとでも言うかのように。結局、彼の無頓着さは物語冒頭から何一つ変わっていなかったのである。本来であれば彼は世界の理不尽を受け入れ、より辛い道を家族と共に歩まざるをえないはずであるのに。
製作の意図はともかく、ぬるい結末でこの作品の価値は大幅に損なわれてしまったといえる。
思っていたより普通
2025年劇場鑑賞283本目。
エンドロール後映像無し。
予告のイメージから人形が生きている世界に迷い込むファンタジー要素に突入すると思っていたのですが、人形はそういう劇を劇中でする、というだけで、話自体は現実的なものでした。
息子が誘拐されてからが本題という感じで、夫婦間の問題が浮き彫りにされるというもので、そこに警察が絡んできて・・・という展開です。
まぁ色々最後に繋がる原因はあると思うのですが、結局銃が全ての元凶だと思います。アメリカでの話なのですが、日本だと起こり得ない話になっています。全編アメリカの話なので洋画だと思っていたら東映のロゴが出てきたので邦画なんだ、と分かったのですが、制作はともかくアメリカでしかこの映画は作れなかったんだろうなと納得です。
後は西島秀俊が英語でも西島秀俊だなぁと感じられて良かったです。
劇中に出てくる人形劇が人形と音楽が相まって、コメディを演じているのに妙に怖かったです。人形が無表情なのはNHKの人形劇もそうだったのに、あっちは怖くなかったのは演技の違いなのか、人形の表情が絶妙だったのか・・・。
人格破綻の塀の上
「人格破綻」というキーワードが真利子哲也作品の矜持か。その塀の上を歩いていて破綻側に大きくバランスを崩す人間を描き切ったり、また堕ちた破綻者からこれでもかと被害を被る弱者を描いたり…何れにせよ、度を過ぎた表現で我々の人間性もその都度試されてきた。さて、今回は…試されるには違いないのだが、実に洗練されているようだ。
破綻を内包しながら必死にハイソな家庭を保持する夫婦にガンバレガンバレとエールを送りながら物語は進んでいく。そして作者は、我々が同化した頃を見計らって主人公夫妻に取り返しのつかない瑕疵を作らせてしまう。ほとんど同一化していた我々の良心や誠意こそがここで問われる事になるのだ。展開としてタイミングとして実に秀逸に感じた。この瑕疵を背負って以降、バランスを崩しながら塀の上を歩いているのは我等なのだから、もう眼を離す事はできない。どんな裁断が下るのか。なんだか情緒的な人形劇さえも苛々として見ていられないのは、真利子哲也監督の思う壺なのだろうか。
理解できなかった。
西島秀俊さんのの英語が、流暢だった。あと、私はジェーン(グイ・ルンメイ)が、若い頃の松雪泰子さんに見えてしまいました。作品は良く解りませんでした。ジェーンの等身大の人形劇は、何を意味してたのでしょうか?ジェーンの内面(本心)をあの人形劇を通じて表現していたのかしら?
ドニーの死因は?賢治が廃墟で拳銃を発砲するシーンの意味は?など良くわかりませんでした。ドニーはあんな落書きだらけの車で、カイ(息子)を誘拐したら目だってしょうがないでしょう…突っ込み所も多々有りでした。
賢治がカイを連れて大学へ行って、目を離した隙にカイが誘拐されてしまいますが、誘拐ではありませんが、街中でも親が連れの小さな子供に気をかけず、携帯見ながら歩いている姿をたまにみます。←「歩きスマホするんじゃねえょ、😡子供しっかり見とけ、飛び出したり何かがぶつかってきたらどうするんだ...」と心の中で怒っている自分がいます。小さな子供に気をかけず、スマホ見ている心境はなんなんでしょうかねぇ?
デカい人形がなんかすごく怖い
期待とは違う感じでした
「ディストラクション・ベイビーズ」「宮本から君へ」の真利子哲也監督作品ということで興味を持ち観に行きました。
淡々とした日常の中に不穏な空気が漂う前半は期待が高まりましたが、誘拐事件発生後は、モヤモヤする部分が多かったです。
犯人の最終的な目的がよく分からず、共犯者のモチベーションの理由もよく分からず、刑事の捜査能力もどうなのかと。
そこはあまり問題ではなく、主人公夫妻が疑心暗鬼に陥る状況、信頼関係の不安定さを描くということかも知れませんが。
構成も、あえて疑惑を高めてモヤモヤさせるものにしているのかなと思いますが、真相?の提示の仕方も唐突な印象で。
音楽についても、子供がいなくなり主人公夫が必死で探す場面など、なんだか緊迫感が感じられず、違和感があるような気がしました。
監督で興味を持ち観ましたが、個人的に夫婦の心のすれ違いというような話はあまり興味が無いということもあり、自分には合わなかったのかなと。
淡々とした不穏感のある映像などは良かったです。
夫婦の危機、あるいは父性の危機?
女は人形劇、男は廃墟研究とそれぞれオブセッション(に近い仕事)を抱え、育児に専心できないでいる。そんなところに、子の誘拐事件が起きるが、事件は意外にあっさり解決して子どもも戻ってくるが…。ミステリ、というより心理劇の要素が大きく、象徴的な表現も多用され、なかなか核心にはたどり着かない語り口。傍から見ると、ぐちゃぐちゃ悩んでないでちゃんと親をやれ、と言いたくもなるが、そうは割り切れないのもまた人間。そうしたままならなさが、人形/廃墟に象徴されている…ということだろう。NYで暮らし、非母語でコミュニケートせざるを得ない中国・日本人カップルという設定も、安易な「心の通じ合い」的解決を許さず、もどかしい。ほぼ全編英語で通すが、西島秀俊が時折切羽詰まって漏らす日本語が、とても印象的(抑制が毀れた瞬間を見てしまった、ような)。銃や車の使い方も技巧的だが、やや暗喩が渋滞気味ではある。この主題なら1時間半くらいの上映時間に収めて欲しいところ。
異邦人であり続けざるを得ないことの悲哀 設定そのものが秀逸な ある夫婦の物語
この作品は人間の心の闇とか精神の崩壊とかいった、けっこう重いテーマを扱っている感じなのですが、まずは登場人物の設定が絶妙です。
物語の中心にいるのはニューヨークで暮らす賢治(演: 西島秀俊)とジェーン(演: グイ•ルンメイ)の夫婦。ふたりの間の日常会話はどちらにとっても母語でない英語で交わされます。もうこれだけで、最近の作品だと『落下の解剖学』にあったような、互いにとっての外国語を使った夫婦間のコミュニケーションという重要な問題が提起されます。
さらにふたりとも東洋系で、いくら国際都市ニューヨークといってもどちらも異邦人的存在です。さらに妻のほうが両親が在ニューヨークでジェーンというファーストネームを名乗っていることから分かるように移民二世で義務教育レベルから英語での教育を受けてきたと推測されるのに対して、夫の賢治のほうは恐らく震災の被害者でやむを得ない事情で日本を離れてニューヨークに移ってきたと推測され、英語も第二言語として後天的に身につけたということで、ふたりの「異邦人度」に強弱がつけられていたりもします。
また、夫の賢治はテニュアトラック期間中の大学教員で、研究テーマはなんと「廃墟」です。身分としてはまだ不安定で、ひとつ間違うと人間的に廃墟みたいになってしまうかも、というあまり芳しくない比喩も浮かんできてしまいます。講演中に質問を受けた賢治は思わず日本語で「諸行無常」と独り言を口にしてしまうのですが、彼の研究の方向が東洋的無常観のほうに進めば、アメリカで研究生活を続けるとすると学問の世界でも彼の異邦人度は高まりそうです。
一方、妻のジェーンのほうは人形劇団のリーダー格の劇団員で舞台監督も兼任しているようです。この仕事は彼女の「生きがい」になっているように見えます。仕事のために、まだ幼い息子のカイを実家の両親のところに預けに行ったりもしています。そんなジェーンに対して母親は中華文化圏出身者的な家族観を持ち出して諭したりもしますが、ジェーンは聞く耳を持ちません。このあたりに移民一世と二世のジェネレーション•ギャップを感じます。あと、ジェーンの父親のほうはどうも認知症を患っているようで、またあまりよろしくない比喩を使うと人間における廃墟みたいな状態にあります。何はともあれ、ジェーンが登場人物中でいちばん「ニューヨーカー」っぽいという印象を私は持ちました。
ということで、よく人生のオブセッションの対象として、「スポーツ」「学問」「芸術」の三大領域が語られることがあるのですが、この夫婦はその内の二つ、夫が学問、妻が芸術に取り憑かれていて、これで夫婦間のコミュニケーションの手段が第三言語ともなれば、ドラマが始まる条件は整ったり、と感じられます。でも、それだけではなくて、ふたりの間の4歳の息子のカイの実の父親はジェーンが以前交際していたドニーという男ということで、この夫婦には息子の出生に関する秘密まであります。賢治はそのことを承知の上でジェーンと結婚したのでした。
で、カイが突然、行方不明になります。これでそれまでは表面上は仲のよい夫婦に見えたふたりの間に亀裂が入ります。ここらあたりから、賢治の精神状態が崩れてゆきます。彼は第二言語である英語のスキルはかなり高いと思われますが、ネイティブではないのである種「言語弱者」のような状態になって公の場で英語で話す際に声を荒げることが多くなります。
結局、カイは無事に戻ってくるわけですが、カイを一時期、誘拐していたであろうドニーの死体が発見されます。ということで物語はミステリ仕立ての展開を見せるわけですが、この映画をミステリ作品として観ると、ツッコミどころ満載、脚本は穴だらけということになります。そもそも、NYPDの刑事が大した分析結果も出てこないうちから、ある仮説を事件関係者に話したりして、けっこう間抜けです。私は、これ、文芸寄りのドラマとして観たら、そこそこ秀逸だから、まあそういう欠点は見逃してあげようよと優しい気持ちで観ておりました。終盤に出てきたシーンにあるようにドニーは自殺したと私は思っています。結局、カイも賢治も事件の被害者であるというだけで、罪に問われることはないでしょう。
とどのつまりが、賢治は正気の側から狂気の側に落ちそうになりながらも、結果的にはなりますがカイを守ったのです。それまで、賢治はジェーンとホンネで話し合ったことはないと思われますが、カイを守る気持ちに偽りはなく、そのことはジェーンに通じたと思います。
以下、私に見えたこの夫婦の未来です。結局、賢治は学問の道をあきらめ、ジェーンの実家がやっていたグロッサリー•ストアの店主になります。女房の尻に敷かれながらも賢治は幸せそうです。ジェーンの人形劇団はニューヨークではなかなか評判がいいようですが、ジェーンは少しの間、お休み取らざるを得なくなります。そう、カイに7つ年下の妹ができたのです。めでたし、めでたし(笑)
異邦人
とにかく全編重苦しい雰囲気の映画だ。暗いというより重苦しい。そして映像も暗くて一部見にくい。
舞台は全編ニューヨークで台詞もほぼ英語。西島秀俊にとってもグイ・ルンメイにとっても母語ではない言語での台詞だが、監督は登場人物の母国ではないので流暢でなくてもよいということだったらしい。実際、西島は英語のできない僕が聞いていても流暢ではないのが丸わかりだったが、グイ・ルンメイは非常に流暢にしゃべってるように聞こえ、もともと言語能力が高い人なのかもしれない。そのためもあってか西島も演技が下手な人ではないはずなのに、グイ・ルンメイのほうが圧倒的に演技が上手く感じられた。人形劇も素人目には本当に出来る人のようにしか見えず、本人はインタビューで米国に渡ってから集中的に指導を受け、かなり苦戦したと言っていたが、とてもそうは見えなかった。やっぱりグイ・ルンメイすげえ。そして相変わらずお美しい。
映画はちょっと重苦しすぎて、夫婦の亀裂とかも今ひとつ僕の趣味ではなかったんだが、監督が『ディストラクション・ベイビーズ』(未見)や『宮本から君へ』(未見)の人と聞くと、なんとなくわかるような気がする。まあ悪くはなかったです。
答えがないから探さないと
結局、どうしたらよかったんだろう‥
少しずつ分かり合えない歪みが、日常にストレスを与えていって、それがあるきっかけで露見、爆発する、というのを撮りたかったのだと思うけど、観終えたこちらに相当なストレスを残す映画。答えを教えて欲しいわけじゃないけど、しんどいなぁ。
わたしは立場的には妻側だけど、ジェーンには全く共感できず。これは国民性? それか個人的な性格の問題? 夫さんは割とよくやってたと思うけど‥
夫婦のなんやかや、って話はあんまり好みじゃなく、トム&ニコールのアイズワイドシャットとかも性に合わないんですが、ここは夫婦だということを置いておいて、人種間、または超個人間の話と考えると、やはり分かり合えないんだ‥という結果になるのは切ないですね。戦争のニュースを見てるみたい。
不協和音みたいなBGMも、車のキュルキュルも、洗わないままのBLANKも、暗くてよく見えない演出も、もうずっとストレス。
人形も廃墟も、どっちもなかみはがらんどう。がらんどう同志が家族を作ろうとしてるんだから、うまくいかなさそうだけれど、どういうふうに惹かれあったんでしょう。
ところで、人種や言語の違いをあらわす為に日本人と中国人夫婦にしたのだと思いますが、同じアジア人、欧米の人からみたら違いがよく分からないかも?などと思ったりして。
正直、奥さんが
疫病神だと思う、引っかかった男含めて。人形と生身で引き裂かれたのか?こういう人、よく観るねェ遠い山なみとか。
今迄観たNINIFUNIとディストラクションベイビーズより、大分観易かった。ジャズぽいジムオルークも聴き易かったけれどキュラキュラ音・・。
最後の巨大人形にはあまり意味が?
Darknessな人間の心理
前半の幸せに見えながらもすれ違っている感がわかる
賢治(西島秀俊)とジェーン(グイ・ルンメイ)夫妻。
その子カイのおかげで何とか保ている様子。
加えて、ジェーンが父母を頼り、カイを預けたりするのもリアル。
なんかもう前半だけでモヤる。
カイが誘拐されてから、夫妻の亀裂が決定的に。
もう醜い争いは本当に見たくないくらい。
しかも誘拐犯は、賢治が車屋で会った荒くれた男。
この男が妻の元カレ。
そしてカイは、その元カレの子・・・というこれでもか!というくらい
設定が入りくんでいるし、元カレの現彼女が共犯となって誘拐。
誘拐事件は解決して無事カイは戻ってくるが、
そこからカイを守る行動で賢治はすごく悩む。
ジェーンが寄り添うも悩み続ける。腹立たしいくらいウジウジしている。
ようやく光明が見えたかと思いきや・・・
誘拐犯の彼女に復讐されるという、
なんとも人間のイヤな部分だけをこれだけ見せられると、ゲンナリしてしまう。
ラストも悲しいなあ。
ジェーンとカイが元カレの墓参りをしているのがどうにも悲しいやらせつないやら。
この後、賢治とジェーンはどうなっていくのだろう?
恐るべし真利子哲也監督。
ドスンと気分が落ち込むヘビーな作品だった。
後悔と蟠り(わだかまり)の積み上がった先にあるものWhat Lies Beyond Accumulated Regret and Unspoken Feelings
自分にとって良い映画かどうかの基準は
観る前と後で、世界が変わって見えるかどうかだ。
その意味で、良い映画だった。
日本、台湾、アメリカ、移民など
ルーツの異なる登場人物が
英語、台湾語、日本語、スペイン語(?)で
繰り広げられる。
始まって程なく、
気にならなくなる。
暮らしていれば
小さな後悔、
小さな蟠り(わだかまり)はある。
主人公の賢治は、妻のジェーンに
子供のカイに、
そして自分の過去に、積み上がったものがある。
彼の仕事は、過去に強く影響を受けている。
おそらく阪神淡路大震災と思われる。
その影響は、個人的に理解できる。
妻ジェーンも、子供のカイに、
夫の賢治に、そして自分の過去に。
二人の後悔と蟠りで、他の人々を巻き込みながら
物語が進んでいく。
正しいとか間違っているとかではなく、
それぞれの想いが交錯し、
人々を突き動かし、
エンディングを迎える。
アメリカという国の
ルーツを別に持つ人々の集合体であることも
観ているものに突きつけてくる。
ああ、だから「Dear stranger」なのか。
【ストレンジャー
〘名〙 (英stranger) 外国人。見知らぬ人。】
メインキャストは、全員
strangerだったよ。
日本人、台湾人、黒人、おそらく南米からの移民。
考え続けることを観るものに求める
そんな映画でした。
My standard for whether a film is good or not is simple: does the world look different before and after watching it?
In that sense, this was a good film.
Characters of different backgrounds—Japanese, Taiwanese, American, immigrants—interact in English, Taiwanese, Japanese, and Spanish (?). But before long, the mixture of languages no longer feels unusual.
In life, we all carry small regrets, and also small, unspoken feelings that we cannot quite put into words.
The protagonist Kenji has accumulated these—toward his wife Jane, toward his son Kai, and toward his own past. His work, too, is strongly influenced by his past—most likely the Great Hanshin-Awaji Earthquake. That influence is something I can personally relate to.
Jane, his wife, also carries regrets and unspoken feelings—toward her son Kai, toward her husband Kenji, and toward her own past.
Together, their regrets and unspoken emotions drive the story forward, pulling other people into their orbit.
It isn’t about right or wrong. Rather, their emotions intersect, push people into action, and lead to the ending.
The film also confronts the audience with the reality that America is a collective of people whose roots lie elsewhere.
Ah, so that’s why it’s called Dear Stranger.
Stranger (noun): foreigner, outsider, someone unfamiliar.
All of the main cast were, in fact, “strangers”—Japanese, Taiwanese, Black, and likely immigrants from South America.
It is a film that demands its viewers keep thinking about it long after the credits roll.
Dear Stranger(映画の記憶2025/9/25)
なんか納得できん場面もありました。(;´・ω・)
① 拳銃の必要性ですね。
② 4歳に殺人罪?? 自己防衛でしょ 誘拐だし。
③ 自首しますって どーにも意味が わからんちん。
でも グイちゃんが 昔のイメージ残していたので
良しと します。手話とかも流暢でしたね。
10年ほど前に観た「言えない秘密」が最高でした。
夫婦って....難しいよね。
全77件中、1~20件目を表示