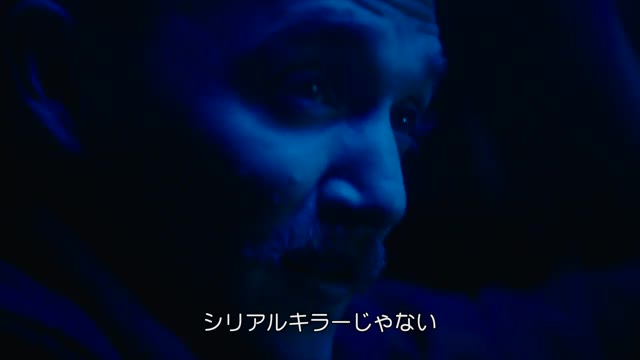ストレンジ・ダーリンのレビュー・感想・評価
全57件中、41~57件目を表示
斬新なアイデア
本作は全体を6章に分け、さらに章の順序を入れ替えて見せることにより、観客を巧みに欺く仕掛けが施されています。私はまんまとその仕掛けに引っかかり、最初は女性の方を応援していたのに、物語が進むにつれて、男性を応援することになっていました。
この構成自体は非常に面白く、これまでにも似た手法があったのかもしれませんが、私にはとても新鮮に映りました。また、メインの二人の演技も素晴らしく、特に女性役の表情の演技は真に迫るものがありました。
強いて言えば、後半になると奇抜な展開にも慣れてしまい、先が読めてしまうのが少し残念でした。
(注意)
人を殺すことに全くためらいがない描写が多いので、ある意味では清々しいとも言えますが、そういった描写が苦手な方は注意が必要です。
(追記)
うっかりして、ちゃんと字幕を観ていなかったのですが、エンドロール後に流れた音声の意味が分からなかったです。
ラストシーンの魂の顔演技に驚愕。叙述的な仕掛けも備えた深みのある「ノワール」映画。
総じて面白かったけど、個人的には冒頭の「第三章」の時点で、ネタの核心部分にほぼほぼ確信が持ててしまっていたので、そこの「びっくり」は正直あまりありませんでした。なんか、すれっからしですみません。
ただ、こういう叙述的な仕掛けや「意外な犯人」に関して、自分が気づいてしまったからといって、点数を落として評価するのはとてもアンフェアだとつねづね思っているので、ここは「その心意気や良し」ということで、大いに称揚したいと思う。
一定数の「きちんと騙された」良い観客がいて、彼らが「きちんとびっくりしてくれた」のであれば、この映画は作品としてもネタとしても成功なのだし、「気づいてしまった」側の人間が徒に評価を下げて、とやかく言う筋合いの話では全くないのだから。
おそらく誰が読んでもそのネタには気づかないのではないか? といった『十角館の殺人』(綾辻行人)のような稀有な例もないでもないが、たいていの作品の場合、早い段階で真相に気づいてしまうダメなマニアもいれば、純粋にどんでん返しや「意外な犯人」に気づくことなく作品を満喫できる多数派もいて、どちらかだけということはまずない。
あまりにバレバレすぎる場合は多少は文句をつけた方がいいかもしれないが、しっかり考えられた痕跡がある場合は、僕はたとえ自分は真相に早い段階で気づいても、「たくらみの存在」だけで高評価をつけることにしている。
そもそもミステリの場合は、きちんと伏線がはってあればあるほど、それだけ客が真相にたどり着けてしまう可能性は高まって来る。それがミステリにおけるフェアプレイの鉄則だ。
『ストレンジ・ダーリン』の場合は、きちんと小道具の伏線や行動の違和を序盤からみっちり練り込んであるぶん、気づいてしまう観客はどうしても出てしまうと思う。
むしろ、映画との「出逢い方」が、多少「不幸」だった気がしないでもない。
封切り映画として、前宣伝で「シャッフル」とか「予測不能」とかいった要素を強調されただけで、ある程度この手のジャンルが好きなファンとしては、「仕掛け」の存在とその内容の可能性について事前にどうしても考えてしまうし、そのなかからは一定数の「ネタの当たりがついてしまう人間」も出てきてしまうからだ。
同じ映画を、いきなりつけっぱなしのWOWOWとかから流れてきた状態で、タイトルすらわからないまま予備知識ゼロで観たとしたら、ものの見事に引っかかって仰天して、周り中に隠れた傑作だと喧伝して回った未来線もあったかもしれない。
そう思うと、「気づいてしまった」自分と、その視聴環境に残念な想いは少しある。
自分自身、学生時代にマジックサークルに所属して「演じる」側にいたこともあって、この手の映画ではむしろ「綺麗に騙されてあげられる」観客で居たいと思うし、それが演者(作家・監督)と観客(読者)の関係性でいえば、一番ウィンウィンの在り方なのは間違いないのだ。
きれいに騙され、きれいに驚き、そのあとのトリック解説をきちんと理解したうえで、きれいに感心できる。こういう「上品な読者(観客)」に、僕はなりたい(笑)。
一方で、ミステリを宣伝するのはとても難しい行為だ。
宣伝するときに「仕掛けがある」こと、「意外である」ことを織り込まないと、いちばん喜んでくれるお客さんを逃すことになるからだ。
よほど隠蔽工作に自信がない限り、本当は「どんでん返し」とか「意外な結末」といった煽りは入れないに越したことはなく(とにかく予備知識ゼロの無防備な状態で体験するのがいちばんなんだし)、ネタがバレたらみんなが不幸になるだけなのだが、そこに事前告知で触れないと、そもそも客が作品を手に取ってくれない。
このジレンマについても痛いほどによくわかるので、あまり映画会社を責める気にもならない。でも、やっぱり「宣伝でああいわれちゃうと」「ネタは消去法でこれしかないよな」とは思っちゃう(笑)。
― ― ― ―
蓋を開けて見れば、この話は『恐怖のメロディ』(71年、クリント・イーストウッド監督)や『危険な情事』(87年、エイドリアン・ライン監督、マイケル・ダグラス×グレン・クローズ)の流れを正統に受け継ぐ「恐怖のワンナイト・アフェア」「女はこわいぜ」系のスリラーだったわけだが、叙述的な仕掛けは抜きにして純粋にその手の映画として考えてみても、本作の完成度は結構高い気がする。
ジャンル映画らしいローコストな雰囲気はぬぐい切れないにせよ、とくに女優さんの大熱演のおかげで、この手の映画にありがちなチープさは感じられないし、なにより35ミリフィルムによる昔ながらの撮影ということもあって、映画としての「品格」がどこかしら保たれている。
何より素晴らしかったのは、ラストシーン。
最近、なにかですごく似たような演出を観た記憶があるなと思って脳内検索したら、『PERFECT DAYS』の役所広司でした(笑)。
今回のヒロイン役を務めたウィラ・フィッツジェラルドの迫真の顔演技は、しょうじき役所広司に全然負けていないどころか、いささか上回っているかもしれない。思わず息を殺して見入ってしまったよ。
いわゆる「ネタ明かし」が前の章で終わって、あとの時間で何やるつもりなんだろう? と思ってたら、これがやりたくてダラダラ引き伸ばしてたのね。
自分のなかにも悪魔を観てしまったおののき。
命が次第に喪われて、魂の抜けていく感覚。
だんだん近づいてくる死に対する恐怖心。
自分でも抑制の利かない悪行三昧に、
ようやく終止符を打てる解放感。
やがてとぎれる意識と感情。
活動をとめる生命機関。
力を喪う眼差し。
停まる呼吸。
断末魔。
息の詰まるような「悪の終焉」を、がっつり相手に目線を合わされた状態で凝視し続けることになるこのラストシーンこそ、本作において監督が「本当にやりたかったこと」だと言っていい。
叙述トリックは、仕掛けの一端に過ぎない。
この物語は、本質的には犯罪者が魂を燃やし尽くし、やがて滅び去るまでを注視しつづける筋金入りの「ノワール」であり、イーストウッド的な「女性恐怖」映画の体裁を取りながら、その実「フェミニズム的視線」をも備えた「女性映画」でもあるのだ。
エレクトリック・レディに「はまって」身を亡ぼす官憲というのは、まさに『カルメン』や『情婦マノン』と同じ、「ファム・ファタルに運命をくるわされた男」の典型例であり、いったん気づいてみれば、これほどノワールらしいノワール映画もない気もする。
― ― ― ―
●章タイトルが出て、音楽(ショパンのノクターン第1番変ロ短調)が流れるつくりは、昔の無声映画などを模している可能性もあるが、同じ趣向は『スティング』(73)などでも観られる。
各章の語られる「順序」に大きなポイントがあるという意味では、『メメント』(00)に代表されるクリストファー・ノーランの時系列シャッフル映画がまずは想起されるけれども、純粋に叙述トリックを仕掛けるためにシャッフルが用いられているという点では、どちらかといえば60年代アメリカにおけるニューロティック・スリラーや、00年代以降日本の新本格作家によって盛んに執筆された「時系列錯誤系」叙述ミステリなどの小説群に近いもののような気がする。
●ライフルを持った男に追われている割に、森で拾ったタバコや酒を嗜みながら休憩をとる様子とか、明らかにもともと着ていたとは思えない真っ赤な手術着のような変なファッションを身にまとっているとか、出だしの第三章からすでに「そこはかとない違和感」が立ち込めている。
要するに、彼女がまっとうな「被害者」ではない可能性の気配は、別段隠すことなく最初から漂っているのだ。
●ベッドにおける女と男の虚々実々の駆け引きは、「性暴力は男の意思のもと無理やり実行される」という先入観を基底に置きつつ、その「常識」を徐々に揺るがしていくというスリリングな作りになっている。
ウィグや手錠、小銃、コカイン、スタンガン、熊撃退スプレーといった小道具の出し入れも巧みで、脚本としてかなり練り込まれている印象。
男が女側の過激な提案に乗って、「これでいいのかな?」と探り探り進行しているなかで、少し図に乗った瞬間に相手に素に返られて「それは求めてない」とダメ出しされるのは、SMでなくても大いにありうるシチュエーションなわけで、かなり「プレイ」としては生々しい。基本、男性はよほどの自己中キャラでないかぎり、「そこはダメ」とか「やめて」という言葉にいつもおびえながら、ことに及んでいるとは思うんですよね(笑)。
●独特の色彩設定とクセの強いアングルの選択は、監督および撮影監督の美意識の一端を示す。パンフレットによれば、監督は大のベルイマン&フェリーニの信奉者で、監督と撮影監督は準備段階でブライアン・デ・パルマ、デイヴィッド・クローネンバーグ、デイヴィッド・リンチの映画を丹念に研究したらしい。プロダクト・デザイナーに対しては、リンチの『ブルーベルベット』(86)とヴィンセント・ギャロの『バッファロー’66』(98)を参考に進めるように示唆していたとのこと。なるほどたしかに!
二人ともきわめて良い趣味の持ち主であり、心からの共感と同胞意識を覚えざるをえない(笑)。もちろんそのセンスは、この作品の全体に十分に生かされているといってよい。
●クローネンバーグ映画としては『戦慄の絆』(88)の名がパンフでは挙げられていたが、個人的には女性の描き方や刹那的なラストも含めて、『ラビッド』(77)と共通点が多い気がする。
●序盤、森の中で展開されていた猫と鼠のゲームは、中盤に入って老夫婦の住むヴィクトリア様式のコテッジに舞台を移すが、この老夫婦のどこかうろんな気配が、作品になんともいえない奇妙なツイストを加えている。
ちょっとデイヴィッド・リンチの『ツイン・ピークス』風とでもいうのか。
とくに、あの朝ごはんのえげつなさ!(笑)
あれ、アメリカ人が観たら容易に何か思い浮かべるような、ヒッピー独特の食習慣とかあるんだろうか??
目を疑うような大量のバター。黒焦げのウインナー。投下されるホットケーキ。
大量の目玉焼き。上からかけられる尋常じゃない量のベリージャム。シロップ。
うげげげげげげげ!!! 気持ち悪いようwww(フェリーニとかブニュエルの食の悦楽を描いた作品や、『サブスタンス』の食事シーンを想起させられる)。
「『甘い』と『しょっぱい』の無限ループを!!」と高らかに歌い上げていたのは『3月のライオン』のあかりさんでしたが、これはさすがにカオスすぎんだろ(笑)。
●あと、老夫婦が「私たちはただのヒッピーでもバイカーでもない。終末論者なんだ」とかいってて草。ちょっとこのへんの話は、誰か(町山さんとか)詳しい人に説明してもらいたいなあ。アメリカにはヒッピー崩れで山奥に隠遁しながら終末に備えて準備している特定のカルト層がいるってことだよね。
●『ストレンジ・ダーリン』では、ホテルの従業員にせよ、山小屋の老夫婦にせよ、警察官にせよ、エレクトリック・レディの犠牲者には、単なる犠牲者という以上の愚かさとコミカルさと因果応報の感覚が付きまとう。そのあたり、ちょっと『シリアル・ママ』(94)と通底するコメディ感覚があるかも。
「こういうタイプの女性がそんな恐ろしいことをやるわけがない」という先入観を隠れ蓑に殺戮を繰り返すシリアル・キラーという点で、両者には深い共通点がある。
●ちょっとバングルズのヴォーカルみたいな声のシンガーソング・ライター、Z・バーグの楽曲が全編を彩り、サントラを形成している。僕にとっては未知の歌手だが、抒情的で好ましい曲を書く人だと思った。なんでも、監督が曲を使わせてほしいと連絡したら、全編で楽曲を書き下ろすという条件でOKを出したらしい。カッコいい!
●パンフで『そらのおとしもの』や『これゾン』に出ていた声優の野水伊織が、ガチ勢の映画ライターをやっていてびっくり。しかもものすごくちゃんとしたことを、ものすごくしっかりした文章で書いている! おみそれいたしました。
逃げるトランプ追うポリス
いやあ、「でっちあげ」そのものでしたね。ビックリしました。ヤク中とはいえ、モンスターでしたねこの姉ちゃん。シチュエーション、真相、シチュエーション、真相のジェットコースターでした。最後までハラハラ感が続きました。エピローグ前でこれで終わりと思いました。実際、隣の男性ここで帰りました。気持ちはわかりますが、あの男性と私とは、この作品の感想は絶対違うと思います。私は場内明るなるまで座ってます。改めて、皆さん、場内明るくなってから帰りましょう。
カラクリ以上のものはなかった
冒頭、
連続殺人がナンタラ、っていうテロップが流れた後、
運転席に座る口ひげを生やした中年の男性に、
助手席から女性の声で
「あなたはシリアルキラーなの?」
というカット。
その後、
その男性が上半身裸で、
おそらくベッドで馬乗りになっているであろう短いカット
(腰から下は映ってない)をはさんだと思ったら、
いきなり「第3章」。
これだけでもう、ミスリードを狙ってることが分かる。
女性の運転する赤いフォードを
男性の乗る黒くてゴツい車が追いかけ、
途中でライフルを取り出して撃つ。
赤いフォードは横転して停止。
負傷した女性が這い出して森へ逃げ、
最後は森の中の民家にたどり着く……
一見、男性がシリアルキラーのように見えるが、
これは逆に違いない。
男性の撃ち方が堂に入っていて、プロにしか見えないし。
続いて、4をとばして「第5章」。
民家を捜索する男性。
その仕方が、どう見ても軍か警察。
しかも、家の主の死体が転がってる。
ここで、確定。
ここまで20分ぐらいだったか。
* * *
あとは、
1章→4章→2章→6章→エピローグ
と進むにつれ、小ネタを含めて種明かし。
でもまあ、それだけ。
そうなった背景が描かれるわけでもなく、
感情移入したくなるような要素も一切ないので、
単なるクイズの答え合わせでしかない。
残念。
そして、
ひと安心かと思ったら……
というのもまあ、お約束というか。
ラスト、さらにもう一捻りあるかと思ったら、
そこまでしつこくはなくて、これまた残念。
――拳銃をもう1丁持ってたはずなので、
運転手を撃って車が事故って炎上、
みたいなラストを予想したんだけど
(ありきたり?w)
* * *
それにしても、
森の民家に住む終末論者の老夫婦の、日曜の朝食が、
異常なほど多量のバター、これまた大量のシロップとホイップクリームをのせた目玉焼きとパンケーキとソーセージ(と若干の苺)で、
しかもその作り方を真上から、料理教室よろしく撮ってたのは、
いったい何だったんだろう。
あと、
エレキベース?の爆音で
ゴォーンという子供騙しで虚仮威しの効果音を多用するのはご勘弁願いたい。
この人もやられてしまうのか???と思いつつ
まずはあれこれ考えず素直な気持ちで見ましょう。3.5.1.4.2.6.7章と繋がるわけで、最初の思い込みを次々裏切っていく展開。こういうのは好きだわ。途中でトリックに気づいてつまらんかった、という意見も多いですが、今のご時世誰にも想像つかないトリックなんてあるんですかね?
途中下着の上下の色がなんか変で気になってましたね。
しかし、何人も関係ない人達がやられていくのはなんとも切ない思いになったということは、だいぶ感情移入したようです。
そして他のみなさんも述べてたようにラストはもう1本の銃でドカン!という哀れな結末かと思ったんですけどね。
ネタバレ厳禁胸糞映画
ではありましたがチャプターを多用して前後するストーリーと俳優さん達の演技力、そして優れた演出がこの映画を面白い作品に仕上げていたと思います。実話が元になってるらしいけど警察官が囮捜査とはいえそこまでするかとか突っ込み所はあったとは思いますが先の読めない展開でグイグイ引っ張っていきました。あと女性ヴォーカルのBGMが印象的でよかった。
3→5→1→4→2→6→エピローグ
冒頭から6章で構成される物語と説明があり、変な順番で見せてくる演出だったので、3番目の5章が始まった時に、私の想像が「連続殺人鬼は、この被害者描写の女性で、ラストは殺されるな」と想像してしまったことから、全くその通りの映画だったので、私自身は全く楽しむことが出来ませんでした。残念、別の内容で驚きたかった!
ENJOY PLAY
巷を騒がせるシリアルキラーがとある田舎町でみせる鬼ごっこの話。
2018〜2020年シリアルキラーがなんちゃらかんちゃらの字幕は良かったけれど、その後の立ち上がりの空気感が異質で、なんか違う作品観に来たかの様な。
そして全6章を時系列をいじり倒してみせてエピローグという流れだけれど…
いきなりチェイスの3章
状況がわからず白々しく感じる5章
今更みせるには怠い1章
やっぱりそうだよねの4章
補完の2章
ツッコミどころ満載な6章
6章からは結構面白くなったけれど、あとの展開を先にみせられているから前半の章はただの説明になっていてスリリングじゃ無いのよね。
時系列をイジることを前提に書かれた本か、後からイジろうとして書き換えたのかわからないけれど、こういう奇をてらったみせ方をしないと厳しいのかね。
タイトルなし(ネタバレ)
※ネタバレしてる感想です
全体が6章立てでそれを時間軸をばらしたタランティーノ的な構成・演出ですが、各章に番号ふってあるせいである程度先読み出来てしまうかも。
それでも最近のアメリカ映画はインディー系低予算映画の方がハリウッド大作より面白いことが多いですがこれもそんな一本でした。
撮影監督のジョバンニ・リビシてどこかで見た名前だと思ったら『テッド』や『アバター』、『プライベート・ライアン』の衛生兵が一番馴染みあるかな、の俳優と同姓同名かなとおもったら同一人物だそうですが35㎜フィルムでの撮影はなかなかよくて今後は撮影監督としても期待出来ると思います。
未知の悪魔より身近な悪魔がいい‼️
私は近年この作品ほど映画的興奮を覚えた作品はないですね‼️ルールを無視した構成の妙がここまで映画を面白くした例は、タランティーノ監督の「パルプ・フィクション」以来でしょう‼️連続殺人鬼と、その標的(ターゲット)となった者の、息詰まる闘いを描く・・・‼️ストーリーはそれだけ‼️最初に2018年から2020年にかけて、連続殺人鬼が全米を恐怖に陥れたとの字幕が入る‼️そして6つの章の物語との説明字幕‼️するといきなり3章から物語がスタート‼️結論から言うと3→5→1→4→2→6→エピローグという構成‼️オープニングとなる3章ではカーチェイスからスタート‼️追われる女と追う男‼️この時点で男が殺人鬼、女がターゲットであると観る者は意識してしまう‼️この意識付けが今作の面白さの根源にあって、カーチェイスの果てに森の中の老夫婦が住む一軒家に逃げ込んで3章が終了‼️そして前述の通り、不規則に章が進むにつれ、1章での男と女の仲睦まじいホテルでのやりとり、3章ではブロンドだった女の髪が1章で赤毛になっていたり、3章で女が片耳を失って血まみれだったり、女が身にまとっている赤い服、熊撃退用のスプレーなど、様々な伏線や小道具が不規則な構成の中で見事に回収されていき、それがどんでん返しの連発となって見事な見せ場となるのがホントに素晴らしいですね‼️そして徐々に明らかになる男と女の真の素性‼️ホントにゾクゾクさせられる作品‼️これぞ映画ですね‼️そしてZ・バーグというアーティストによるサントラもこれまた素晴らしく、彼女の切なく哀愁のある歌声が映画を格調高くしてますね‼️ 35ミリフィルムで撮影された少しザラついた画面‼️そして「あなたはシリアル・キラーなの?」と女が男に尋ねるオープニング・カット、女が車中で静かに息絶えるラスト・カットをモノクロで描く演出も、同じく映画の格調を高めていて素晴らしい‼️海外では「秘密を知る前に観よう」とか言われてますが、今作は秘密というよりは、その構成の妙に唸らされ、楽しまされる作品だと思います‼️
ドン引きする男が面白い。
一つの話を6章に分け、3→5→1→4→2→6→エピローグ、と時系列を乱したことで、「一体誰がやばいんだ」と楽しめて良かった。
・おそらくバーかどこかで一夜の誘いを交わしてホテルに向かう男女。とにかくメイン女がヤる気を削ぐ台詞をひたすら言うため、メイン男が可哀想で途中から笑えてくる。
もう早くヤらせてやれよ!と思うくらい。以下抜粋
・ホテルに到着し、車の中で「女だって遊びたいのに簡単には遊べない。暴力をふるわない?シリアルキラーじゃない?」と尋ねる女。
・「演技でなく本気で暴力ふるって。止める合言葉を告げたときは止めて」と言い、合言葉を言った後「怖かった、最高だった!」
・いざヤろう、となっても「コカイン吸おう」など言う。それを準備する女を見る男の真顔っぷり(ここは職業柄もあるのかな)
・終末論者夫婦の朝食。
バターどさー!そこで目玉焼き作成!その後パンケーキ!
できあがった!パンケーキで目玉焼きとウインナーを挟む!ブルーベリージャムをたっぷり!メープルとかけちゃう!仕上げにホイップクリーム!
なんだこれはぁ……。
・結局やばいのは女で、男は追いかけていただけ(銃構えてKittyKittyとか言っちゃうけど)。
・実は男は保安官。女を手錠にかけて助けを呼ぶ。でも女の持つ熊撃退スプレーで返り討ち。痛みに悶え何故か女側へ。首を食い千切られ絶命。あのさぁ…。
・応援に来た保安官(ベテラン男と新米?女)。凄惨な現場に長年の勘で「現場はこのままにして応援を呼ぶぞ!」と言う保安官男に、「女の命が大事!車に乗せて連れて行く!私が女だからってそんなこと言うのか!」と保安官女。
「いや、俺はお前がオムツしてるときから現場にいるから」と返すも、メイン女が痛がったので「助ける!!」と返す保安官女。
その後は終末論者妻が現れて、終末論者妻を殺し、「良くしてくれたから」と保安官女は逃され、保安官男は殺される。
保安官女へのイライラありましたね…。
・最後はたまたま通りがかった車に助けてもらい、乗り込むもメイン女が運転手に銃を向けた瞬間に運転者に撃たれる。
「銃を向けられたので撃ってしまいました。今から向かいます」と恐らく警察に電話する運転手の横で、虫の息で胸元の銃を弄る(一丁は運転手に奪い捨てられたが、保安官から盗んだものがもう一つある)が、絶命。
最後の車のシーン、虫の息のメイン女だけ映っていて…。
突然こちら(側にいる運転手)に発砲で終わると思っていたので少し驚き。
めちゃくちゃオススメ!とはならないものの、飽きずに楽しめた。
メイン男がかっこよくて最高だったなぁ…。
純粋悪の最期
予告を見る限りでは、ふつうのシリアルキラーものだったらどうしよう?
…くらいに思っていたが、ふつうじゃなかった(笑)
チャプター仕立てではあるが、いきなり3からかよっ!と脳内でツッコミを入れたが、
3から始まることで、まんまと観客をミスリードする効果があったことが
後々わかる。
そしてチャプター5、レディがデーモンから追い詰められいよいよ殺されるのか!?
という、チャプター3からの展開を強調する見せ方。
これが秀逸。
その後も、チャプターをザッピングしながら展開するのだが、
なるほど、レディがシリアルキラーだったか!!
もうレディが異常。性癖というより、彼女は人を傷つけずにはいられないし、
殺すことも何とも思っていないし感じてもいない、まさにシリアルキラーであり、
どうしようもない存在であることが、ストーリーの展開とともに明らかになるのだ。
多くの人が彼女の手によって葬られていくのだが、ほとんどが瞬殺していて、
おそらくは考えて殺してはいない。衝動的に殺している。
もうヤバすぎる存在。
そのヤバすぎる彼女のラストも秀逸。
結局、地元民の手によって射殺される(自己防衛)のだが、
死にゆくレディの顔の演技がすごい。
『Pearl パール』のミア・ゴスのラストの顔の演技(もはや芸)以来の衝撃だった。
ふつうのシリアルキラーものじゃないよな、と予見していながらも、
この展開は予想していなかった。
またまた製作者の意図通り、面白くは観れた。
しかしこういう展開の映画は観ていてとても疲れるので、
フェイバリットかと言われると微妙である。
まんまと
騙されましょう笑
いや、実際面白い構成だし、こりゃ騙されるわ〜と。
主役2人も、観てる方とも。
思い込みを覆される痛快スリラー?
もちろんハッピーでもなんでもないけど。
こんなことが実際あったのか?
最後の、人の良さげな農家風の人。
防衛本能というのか、日本人にはないな〜と。
武器もないけど。
あっという間に終わった感じ。
しばらく赤と黒にうなされそう笑
エンドロール前に帰った人が数名。
映画はエンドロールまで観た方がいい。
トイレ我慢出来るなら(笑)
本作品も音声だけだったけど、おまけ付き。
まんまと乗せられてしまった。 観客の先入観によってミスリードさせる、脚本・構成の妙。 語る順番自体が演出になっていて素晴らしい。
自分は極力情報シャットアウトして観る派なので、、、
冒頭シリアルキラーの実話で全6章と聞いて、逃げる負傷した女、追うライフル男を観れば、誰だって普通に殺人鬼の監禁から逃げ出した女と思う。
しかも3章から。
そして既視感の嵐。
ああ、これは観なくてもよかったかなと思った素直な自分。
この時点でまんまと監督・脚本家の思うつぼにはまってました。
助けを求めた家の怪しさ。
薄気味悪いくらい平和的な老夫婦。
ここで感じた嫌な予感さえも違ってた。
この先の女の行動から、徐々におかしくなってくる。
観せる順番自体が演出になっている脚本の妙、アイディアが素晴らしい。
主演ウィラ・フィッツジェラルドによる静かな狂気。
バーバラ・ハーシー演じる終末論者の老夫人の幸福そうで穏やかな表情。
婦警の先走る正義感からの思い込み、
経験と勘から慎重になるベテラン警官。
登場人物それぞれの説得力、各俳優の仕事も的確で納得する。
最後、女を拾った中年女性のためらわない一発、にスカッとする。
撃たれた後、手を服の中でごそごそさせていたので、てっきり警官から奪った「2丁目」の銃で反撃するかと思ったら、なぜかなかった。
警官から2丁銃を奪った見事な伏線!と思ったのに残念。
みんな騙される。
全部で6章あるのに、3章から始まって、しかもいきなり犯人の男と被害者の女が分かってしまう。
「えっ、ミステリーなのに、もう犯人分かってネタバレって何?」と思ってると、次は第5章で、ライフル構えたシリアルキラーが、逃げるコネコちゃんを探す場面。なんとヒッピーのオヤジはシリアルキラーに撃たれて血を流して死んでいる。
「ええー、シリアルキラーの正体ってふつう映画の後半で判明して、まさかコイツが犯人だとは思わなかったという意外性でみんなビックラこくもんでねえの? こんなに早い段階で、ここまでハッキリと正体バレバレって何か変だなー」と思いながら鑑賞する。
ここで余りの違和感に、オヤもしかしたら、女性がシリアルキラーかもと鑑賞者に気付かせる。連続殺人の犯人なんて聞くと、みんな思い込みで勝手に犯人は男と決めつけるのを逆手に取ったんだなと観客は分かる。第4章で、誰がヒッピーのオヤジ殺るかだな。ということで第1章へGO。
しかし登場人物たちは騙される。
誰かから逃げているらしい傷を負った若い女性が「助けて」と叫んでたら、誰もそいつが殺人犯だとは思わない。
だから、みんな騙されて殺される。
第2章で下着姿の彼女を助けた2人も、第4章のヒッピーの2人も、第6章の警官2人も騙される。
ベテラン男性警官は警戒したのだが、さすがに相方の女性警官にああまで言われてしまったので渋々同意したのが命取りになった。
エピローグの女性は彼女を助けたが殺されはしななかった。
「銃を向けられたので撃ちました」なんて、さすが銃社会アメリカならではの対応だと思って驚くやら感心するやら。日本だったら相手が銃を持ってるなんて思いもしないから、絶対殺られてる。
アメリカでは小学生の子供でも銃で人を殺すことがあるから警戒はしていたのだろう。
相手が子供だろうが女性だろうが、銃を向けられたら一瞬の迷いが命取り。躊躇なくぶっ放す。お見事 。
ポスターの赤い髪の女性が気になるから鑑賞しようなどと思った僕も絶対殺られてる (-""-;)
【追記】エピローグでも思い込みで判断した (  ̄▽ ̄ ;)
エピローグで女性が騙されてシリアルキラーをトラックに乗せたとき、僕は、シリアルキラーを殺すのは(或いは捕まえるのは)いったい誰なんだろうと思った。も(ぅ)ゼッタイ、オバハンは殺されるか助けられる側で、彼女が自分の身を自分で守る側になるかもしれないという考えは、全く頭をよぎらなかった。
もしかしたら、シリアルキラーが男性警官を殺すのを、たまたま近くで目撃した警察官か一般人が、オバハンを助けるためにライフルでシリアルキラーを殺して一件落着になるのかなと思った。
シリアルキラーを成敗ずるのが、警官にしろ一般人にしろ、僕がイメージしたのは男性だった。
まったく、これじゃあ 「女性は守られ助けられるもの、男性は守り助ける側」っていうゴリゴリの昭和のオヤジの発想じゃね?。 って昭和だけどネ (^^;)
自分はそうじゃないと思っていても、刷り込み・思い込み恐るべし。最近だと認知バイアスって言うようだ。
上は黒 下は赤。
シリアルキラーによる連続殺人事件が起きてるなかBARで出会いラブホ手前で停車し、どうしようか考え中な女・レデイと男・デーモンの話。
チャプター形式全6章を3.5.1.4.2.6章エピローグの順で見せてく。
いきなり始まる逃げる女と追う男、停車中の車内とホテル内のやり取りを絡めながら…、四駆に乗りショットガン構え追う男にヤバさを感じ、逃げる女に緊迫感を感じながらも…でっ何で3章から?と観進めれば…。
ヤバイ奴はオマエかい!確かに第1章から順に見せたら普通すぎるし、この計算されたランダムに見せる順序に面白さと上手さを感じる。
コイツはヤバイ奴だから気をつけて!と駆け付けた男女2人の警官に思うものの…。ラストのウエスタンハット被ったバァさんナイス!で面白かった。
章立ての置き換えで何かやるなと思っていたら
素直に騙される
変態は際限をしらぬ
しかし何に憑かれているのか、コロスコロス
物語を作った女性警官は生涯落ち込むだろうな
戸惑い無く銃をぶっ放せるアメリカのおばちゃんに感慨
死んだようで、とりあえず良かったエンド
全57件中、41~57件目を表示