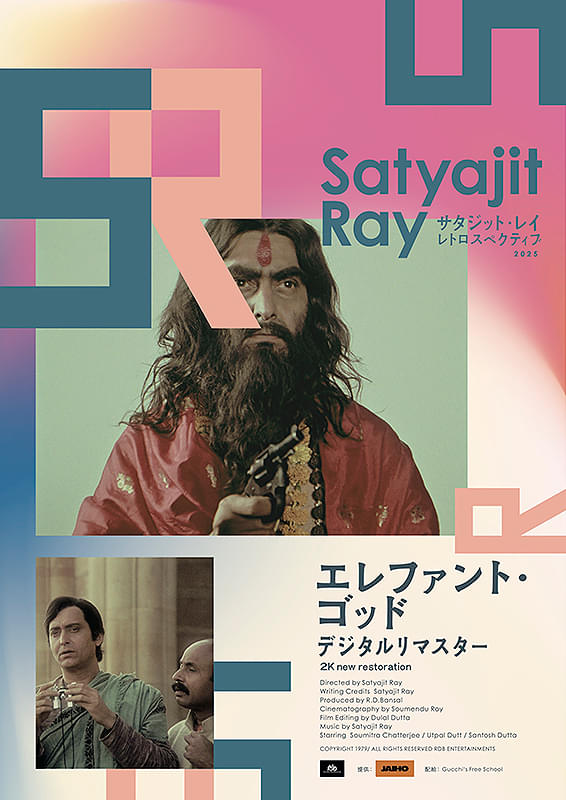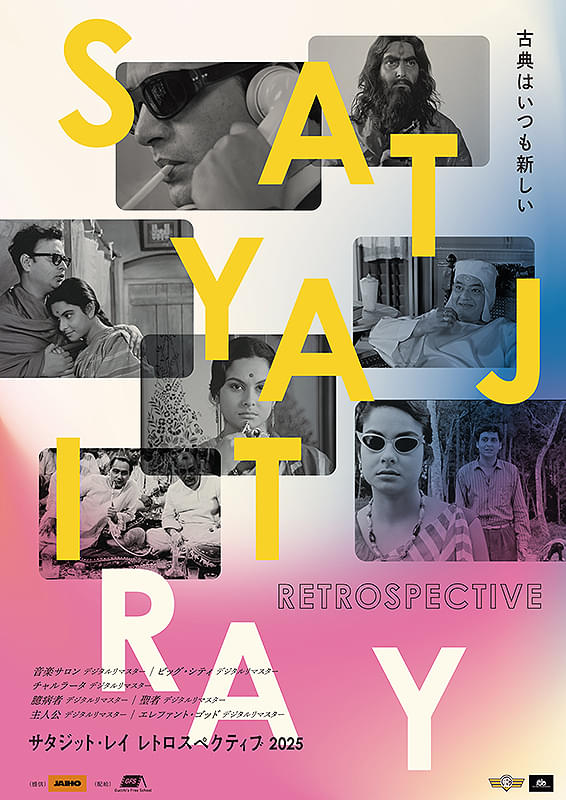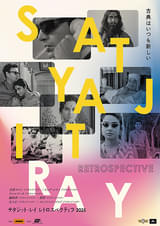エレファント・ゴッド
劇場公開日:2025年7月25日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR
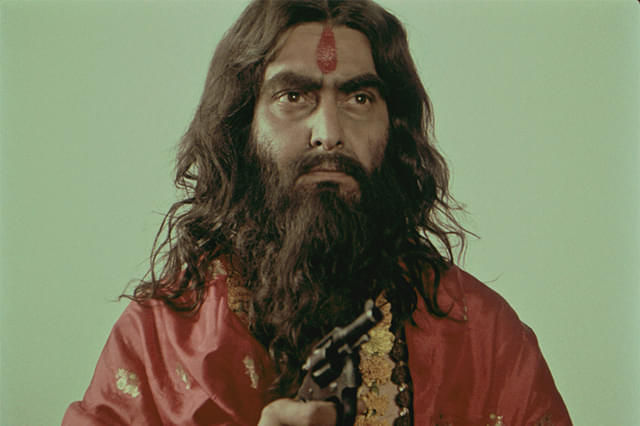
解説・あらすじ
「大地のうた」「チャルラータ」などで知られるインドの世界的映画監督サタジット・レイが執筆した全35作の児童向け人気小説「探偵フェルダーシリーズ」を、1974年の「黄金の城塞」に続いてレイ監督が自ら映画化した冒険コメディ。
聡明な私立探偵フェルーと従弟の少年トプシ、冒険小説作家のラルモハン・ガングリーは、休暇を過ごすためヒンドゥー教の聖地バラナシへやって来る。そこで彼らはある男から、事件の解決を依頼される。それは、ネパールの王子から譲り受けたという家宝の金のガネーシャ像が盗まれたというものだった。調査を進めていくなかで、フェルーは事件の重要な手がかりを知る少年ルクと親しくなる。卓越した分析力と洞察力を武器に真相へと迫るフェルーだったが、やがて事件の背後に潜む陰謀に気づく。
主人公の探偵フェルー役に、レイ監督作の常連俳優ショウミットロ・チャタルジ。日本では、レイ監督のデビュー70周年を記念した特集上映「サタジット・レイ レトロスペクティブ 2025」にて、25年7月に劇場初公開。
1979年製作/122分/G/インド
原題または英題:Joi Baba Felunath
配給:グッチーズ・フリースクール
劇場公開日:2025年7月25日
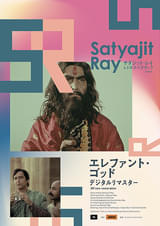

 カメラを止めるな!
カメラを止めるな! ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 インターステラー
インターステラー すずめの戸締まり
すずめの戸締まり ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ジュラシック・ワールド/炎の王国
ジュラシック・ワールド/炎の王国 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム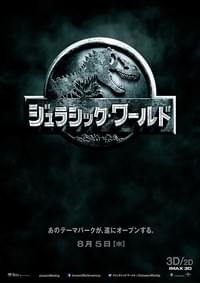 ジュラシック・ワールド
ジュラシック・ワールド キングダム
キングダム