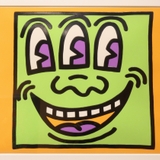ザ・ザ・コルダのフェニキア計画のレビュー・感想・評価
全170件中、1~20件目を表示
タイトルだけだとよくわからんが、近作では飛び抜けてとっつきやすいのでは?
もはやコマ撮りアニメであろうが実写映画であろうが、外に出てロケ撮影するのではなく撮影スタジオにセットを建てて一分の隙もなく映像をコントロールするようになったウェス・アンダーソン。箱庭的な美意識は揺らぐことはなく、観ていて息が詰まるような感覚に陥ることもあったが、本作はいささかネジの外れた親子の絆と冒険のお話という一本筋が通っているせいか、よりリラックスして楽しめた。妙な寄り道ばかりしているように見えるのも、人によっては退屈かも知れないが、そういうディテールにこそ神が、いやアンダーソンが宿っていたりするし、Netflixの短編以降、そういうムダなディティールに遊び心が戻ってきたように感じていて、本作の寄り道もいちいち愉快。まあこの辺の印象は観る側がアンダーソンに何を求めているかで大きく変わるとは思いますが。でもベニシオ・デル・トロ演じるザ・ザ・コルダが無茶苦茶だけど飛び抜けて魅力的なキャラであることは誰もが賛成してくれるのはないか。娘リーズル役のミア・スレアプレトンももともとウェス・アンダーソンの大ファンというだけあってどんなテンションの演技が必要なのか完璧にコントロールしていてみごと。
アンダーソン流の不意を衝くアクションに驚かされる
アンダーソン一座の巡業の季節がやってきた。近年は豪華キャストが横一列に人間模様を織りなすタイプが多かったが、本作では家族、そして傍若無人さと愛嬌を併せ持つ家長が旋風を吹かせる懐かしいスタイルへと回帰。だが、見せ方や取り扱う題材は従来とやや異なる。私が驚いたのは、その鮮烈かつ独特なアクションだった。とりわけ冒頭の飛行機爆破に至っては、いわゆる大作系のカタルシス的アクションとは次元の異なる、突然何が起こったか分からなくなるほどの瞬間的演出によって機能美と衝撃、双方の効果を提示してみせる。その後も幼子が放つ無数の矢といい、突如はじまるバスケの試合といい、アンダーソン作品に単なる精緻な構図の絵巻物とは別の、動的衝動がもたらされているのを感じる。時折、展開が速すぎたり、情報量が多すぎたりして咀嚼する時間が足りなくなるが、父娘が織りなす人生を変える旅路は味わい深く、ドタバタの先に待つ風景に心奪われる。
緊張感があるようでないようである
本作でもウェスアンダーソン節が炸裂していた。役者同士は真顔で早口で...
ウェス監督のやりたい事全部詰まってるんでしょ?という映画笑
お話の本筋はぶっとんだ父と、真面目な娘っ子の絆を深めるロードムービー的な感じなのだけど、ストーリーが難解で、理解するのにかなり時間がかってしまい途中眠くなったり笑
ストーリーに重きをおくと本当につまらない映画なので、途中から見方を、PVを見るような感覚に切り替えたら、かなり楽しめた🎶
細かいディテールや飾ってある絵画、写真集のようなパステルカラーの背景、シンメトリーな配置、家具などは、やっぱり可愛い♡
同じことをしつこく繰り返すシーンとか見ると、一見シリアスな内容にみせかけて、ウェスはコメディに全振りしたいのかなぁと思った
しかし、それがあまり面白くはなかったところが残念(>_<。)
デルトロのコメディ演技とスカーレット・ヨハンソンのホットパンツ姿は、見る価値あるのかなぁ(*´艸`)
1番良かったのはラストと、お話の本筋である親子の絆が産まれたところと、クレジット♡♡クレジットにちょこちょこ、映画のポイントとなるイラストが出てきたり、文字の配列が美しい✨おそらく映画にでてきた絵画の紹介もしていて、あのクレジットは良かったなぁ
個人的には、来年閉館してしまう、シネマカリテで、ウェス・アンダーソンを見れた♡というところに行く価値はあったのでした♡♡
敷居が高そう...と恐る恐る観ましたが、コメディとして面白い!
ウェス・アンダーソン監督作品を初鑑賞。
アート作品と思いきや、がっつりコメディでした笑
至る所に小ボケが敷き詰められており、(元ネタは分かりませんでしたが)最後まで楽しく見れました!
個人的には、火矢にボーガンで応戦するシーンと、いきなりバスケを始めるシーン、散々殴り合った後に話し合おうとするシーンがお気に入りです笑
画作りは凄まじく、どの瞬間を切り取っても写真集の表紙になるのでは?というくらい整っていました。
かと言って見ていて胸焼けすることが無いのは、無駄をできるだけ排除したシンプルなデザインになっていることや、カメラワークと映像の切り替えが小気味良いからでしょうか?
先に撮りたい画を決めて、現実をそれに近づけて撮影しているように感じました。
「写実主義の真逆をやってみた」と言うのは簡単ですが、映画1本分の画を先に決めるのは尋常じゃない労力と発想の引き出しが必要だと思います。それをやってしまうのが才能なのだろうな~としみじみ感じました。
ストーリーは2/3くらいまで見てやっと何となく理解できるくらいなので、ストーリー重視の人には合わないかも?
登場人物は何を考えているのかいまいち分からないのですが、なぜだか、みんな活き活きして見えました。
作り手のこだわりが光る作品ゆえに、「自分のプロジェクトを破産してでも成し遂げる意地」「どちらが強いかをハッキリさせたい意地」に執着する姿、つまり、ある人から見たらくだらないと思われるようなことに価値を見出して命をかける姿に、アートやものづくりの行動原理を見た気がします。
ひとつ不満なのは邦題。
本編通りの発音の「ジャージャーコルダ」の方がリズミカルで気持ち良いのに、なぜひっかかりのある「ザ・ザ・コルダ」にしたのでしょうか。あえて違和感を残したんですかね?
(え、そんなこと気にならない?これは失礼しました)
観る前は難解な作品かと身構えていましたが、最初にいきなりグロシーンが来て度肝を抜かれた以外は、肩肘張らずに楽しく見れる作品でした。
(いつビョルン先生が吹き飛ぶのか、中盤は冷や冷やしながら見ていました笑)
なんとも言えぬ解放感があった。
「グランド・ブダペスト・ホテル」ほどの快活さや「アステロイド・シティ」のような唐突さはないが、多数の芸達者たちによって演じられたコメディー。
タイトルにあるフェニキアは、地中海の貿易で活躍し、現在のアルファベットの元になる文字を見出したことで知られている。この映画で目指しているのは、ヨーロッパの基軸になるような経済圏を打ち立てることか。地図は、どうみてもフランスだったが。そう言えば、東洋人は目立たなかった。
1950年代、莫大な財産を持つザ・ザ・コルダは、血脈を中心に、鉄道、トンネル、発電など産業のインフラを整備し、一族の150年にわたる繁栄を夢みる。自分の後継者として、9人いる男の子ではなく、修道院に入っている(本当に自分の子供かどうかもわからない)ただ一人の女の子、リーズルを指名する。しかし、国際シンジケートによる資材の価格釣り上げ、襲撃などが次々と押し寄せ、分担金の調整に追われる。西洋音楽でも、150年を一区切りにすると判りやすいと昔、習ったっけ。
途中かなり寝たのかもしれないが、それでも楽しめたのには、二つの理由がある。なんと言っても、主人公が浴槽に浸かりながらオムレツを食べるところからはじまり、最後は自分で調理し、達者に皿を洗うところで終わること。もう一つは、絵画と音楽だろう。
邸宅の部屋、特に寝室にルノワールの「青い服の子供(エドモン・ルノワール)」やルネ・マルグリットの「The equator(赤道)」などの実物が飾られ、スペインの大物が「マハ作品」などを隠し持っていたことが思い出される。秘匿していた秘本なども出てくる。音楽では、最後にIgor Stravinskyの名前が大きく出るが、前半のバレエ音楽「ペトルーシュカ」、最後を飾ったバレエ音楽「火の鳥」の終曲、中盤ではバッハの「主よ、人の望みの喜びよ」の合唱ヴァージョンがよかった。観客を飽きさせないヴェス・アンダーソン監督のマジックに魅せられる。
たくさんボケてくれてありがとう
守銭奴の悪人が地獄行きの恐怖と娘への愛情によって生き方を変えるまで。
ずっと真顔でボケ倒している所が好み。面白い画も豊富。目が喜ぶ。OPの風呂俯瞰シーンだけでも料金の元はとれた満足😊
平面愛
炸裂!予告篇からそれは解っていた、今回は上からの画も。エンドクレジットに出て来る絵が止めか。
ストーリーは他愛なく、PVみたいに観るのがいいかも。娘がカワイく救われた、スカヨハもああいう格好がイイネ♥ベニチオ似てないよ!特に目が!
今回のイメージカラーは白ですかね。
今度は、ほぼミッションインポッシブルw
シニカルで知性を感じる台詞回し、能面演技、明度の高い色彩描写、幾何学的な画面内配置。One and Only のウエス・アンダーソン ワールド全開。個人的には好きな監督のトップ10には入るウエス・アンダーソンなんですが、コレは彼の作品の中でも上位に入るんじゃないかと。
およそ、人間的な部分が、ガッサリ切り落とされてるのではないかと思われるザ・ザ・コルダが、内面に隠し持っていた信念を実現する過程で、実の娘じゃない娘への愛で人間性をも取り戻す。フェニキア計画とは、彼の人間回帰の計画であった、と言うのが物語の建て付け。
なんですが。ですが。
能面演技なんですよね。セリフは一見難解、って言うほど難しくも無いけど、直接的表現は取らず、シニカル。なんで、物語のシリアス度は戯曲的に婉曲化されていて、リアリズムはほぼゼロな訳ですよ。
ここのところが、ウエス・アンダーソン作品の好き嫌いを分けてるのは間違いなく。独特の彩色表現で、今風の人や若い人の人気は高いと思われますし、業界内、特に役者さんからは絶大な支持を受ける彼。契約の場面に卓についてる面々の豪華さには、思わずニヤついてしまいました。
面白かった。
とっても。
ウエス・アンダーソンとベニシオ・デル・トロで寝てしまうとは!
ウエス・アンダーソンもベニシオ・デル・トロも好きなので軽く楽しみにしていました。
プライベート・ジェットの最初の墜落まではいつものウエス・アンダーソンでわくわく見ていたが、その先急失速。
一風変わったシチュエーションと人、そのやりとりと間となんとも言えない笑いの空気と、さくっと入れ込まれた風刺を楽しむ、のがウエス・アンダーソンの持ち味で、作りこみありありのパステルカラーの背景も好きなんだけど、今回は奇抜が過ぎてスベった模様。訳が分からず気持ちが付いていかない。
同じことをしつこく繰り返す(バスケットボールのシーンとか)、そもそもプライベートジェットが墜落するパターンも繰り返しで、墜落と墜落の間の話は突飛すぎるのに平板で間延びしており、飽きてしまった。
常連も新顔も俳優さんの顔ぶれは豪華なのに、宝の持ち腐れ(腐ってはいませんが)でいまいち活かされず。紅塩出るさんはさすがにまあ良しとして、スカヨハは特に彼女じゃなくても良いし、カンバーバッチの奇妙奇天烈な役はもはや無残の域で気の毒になった。なんじゃああれは。
私の誕生日でしたのに。。。
それでもやっぱり唯一無二
独自性がありすぎて評価がしづらい
ウェス・アンダーソン監督の作品は今まで何となく好みではない気がして、足が遠のいていたのだが、今回はそこそこ評価が高く、ベニチオ・デル・トロが主演ということで鑑賞。
結論としてはやはり好みではなかった。
コメディとしての独自の世界観は確立されていて、好きな人は待ちに待った作品。そうでない人は全く興味なし。そういう作品なのではないか。
ただ、根底にあるのは家族のつながり、父と娘のつながりの話でそのあたりは分かりやすかったのではないか。
そして、収穫は修道女見習いの娘、リーズル役のミア・スレアプトン。父親ザ・ザ・コルダとリーズルの掛け合いは映画を引っ張っていく役割を果たしていた。
終幕に向けてどんどん父親に似ていく娘。ラストは何と微笑ましい。
最近のアンダーソンはビジュアルでしか楽しめない。
驚きが減ってきたけどまあ、
ウェス・アンダーソンはムーンライズ・キングダム以外全部観ていますが、個人的にはグランドブタベスト〜フレンチディスパッチまでがピークだったかな…
(ダージリン急行までのストーリーの有耶無耶さがちゃんと起承転結な話を作るようになったというか…アステロイドシティからまた初期化された気がする)
めっちゃ好きだけど信者にはなれないんだよね
万人受けをハナから狙ってないのに、誰にも作れない映画を作るから本当に鬼才なんだけど
とはいえタイトルロールの映像には感嘆したし、現実には重い題材(インフラ整備に搾取される現地の人とか意図的に操作される物価とか遺産は渡さないけど才能があれば利用するであろう養子とか)をとぼけた台詞とキュートな映像でフラットに挟んでくるのは相変わらず可笑しいし
資金提供のパーセンテージがどんどん無理になっていくのに笑ったし
主人公と娘?と秘書?のリズミカルなセリフのバレーボールが軽快だった
今までマイケル・セラがこの監督に起用されてなかったのが不思議
あの世のシーンの役者さん全員認識できなかったけど、もう一度見て確認したいと思うほどではなかったのよね…ネトフリとかて配信で見られるようになったら確認してみます
芸術とファッションと、少し哲学
この作品は、ファッション系の雑誌で多く取り上げられていて知りました。
ウェス・アンダーソン監督は、名前も知らなかった素人です。
作品のサイトにも、本物のルノワールを美術館から借りていたり、カルティエやプラダが協賛しているとあったので、ほとんど美術目的で鑑賞しました。
予告編で「ファミリーコメディ!」と紹介されていましたが、コメディというほどポピュラーな感じはありません。
自家用飛行機で資金集めに奔走し、飛行機が墜落しても撃たれても全然死なない、商談も何故かバスケの勝負で交渉をまとめるなど、ツッコミどころは確かにありますが。
むしろ、チェ・ゲバラ似の共産革命家が登場して協働したり、修道女が持つ宝石付きの十字架のネックレスは果たして神の意に沿うのか、など宗教・思想に絡めたエピソードで、ストーリーに深みを持たせていると思います。
ザザコルダが新たな人生へ進む結末も、哲学的。
気楽に見れるオシャレ映画と思っていましたが、予想外に深い内容で、ウェス・アンダーソン監督は鬼才だと感じました。
※※※※※※※※
後日談。
ウィキペディアでウェス・アンダーソン監督のプロフィールを見たら、『ダージリン急行』の監督だったとは。
テキサス大学で哲学を学んだ、とあり、なるほどと思った。
アメリカでは映画は開始5分で意味が伝わらないと売れない、と聞いたことがあるが、本作もどちらかと言うと、商業的成功と言うよりは、ミニシアターに馴染む作品ような気がする。
滅多に行く機会のないシネコンの大スクリーンで見れたことは幸い。
全170件中、1~20件目を表示