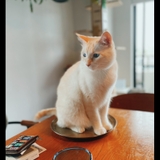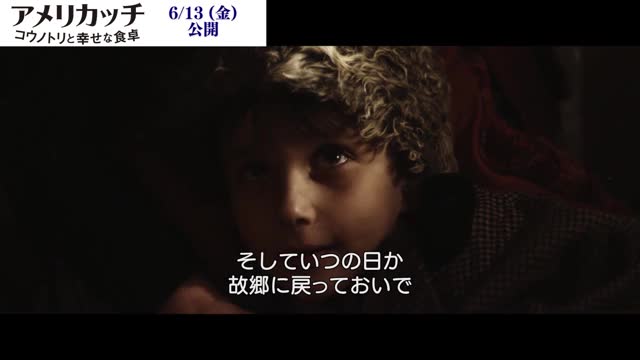アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓のレビュー・感想・評価
全32件中、1~20件目を表示
この映画は時に言葉を超越して愛と尊厳を伝える
タイトルの語感から生じる可愛らしくコミカルな響きと、それとは真逆の悲痛なまでの歴史の重みや爪痕を併せ持つ稀有な作品だ。それゆえこの映画の笑いには涙がにじむ。言うなれば『ライフ・イズ・ビューティフル』的な喜劇の感動とでも言うべきか。自らのルーツを求めてアルメニアに舞い戻った主人公を待ち構える運命はあまりに不運で、過酷だ。しかし彼が独房の鉄格子ごしに誰かの暮らしを覗き見るとき、広い窓はワイドスクリーンとなり、見ず知らずの男はサイレント映画の花形スターとなる。この思いがけなく生じる唯一無二の劇場的状況が実に見事。絶望のふちで咲くイマジネーションが胸を揺さぶってやまない。そしていつしか互いを鏡面的に意識し合うようになってからは、彼らがまるで引き裂かれた分身のようにも思えてくる。それは主演、監督、脚本を務めたグールジャンが、祖父を始め故郷の人々を追想し、心を重ねようとする姿そのものなのかもしれない。
【”アルメニア人のアララト山の絆。そして怒りに呑まれるな!”今作は無実の罪でソ連の獄に入れられた男が格子から見えたアルメニア人元画家で現看守と交流し、自由を勝ち取る様を描いたヒューマンドラマである。】
■1915年。オスマン帝国によるアルメニアジェノサイドで祖母を失った幼きチャーリー。祖母は銃殺される前に”笑顔を忘れないで。”と彼に言葉を遺す。その後、幾星霜。
ソ連統治下の祖国・アルメニアに帰還したチャーリー(マイケル・グールジャン)は、刑務所長ジャン(ジャン=ピエール・ンシャニアン)とその妻ソナ(ネリ・ウヴァロワ)の息子を事故から防ぐが、ジャンによりスパイ容疑で逮捕されてしまう。
だが、めげずにチャーリーは牢獄の小窓から隣のアパートに住む夫婦を観察するのが日課となる。彼らが生活する姿を見て楽しんでいたが、或る日夫婦は喧嘩別れをしてしまう。チャーリーは男が刑務所の監視役である事を洗濯物から知り、夫婦仲を戻そうと奮闘するのである。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・ストーリー構成、演出とも秀でた作品である。何よりも刑務所内のチャーリーを始めとしたアルメニア人囚人たちが、アルメニア文化を誇っているのが良いのである。
■ご存じの通り、アルメニア人は長年虐げられてきた人種である。今作の冒頭で描かれるオスマン帝国によるアルメニアジェノサイドなどである。
故に、チャーリーの様に世界各国でアルメニア人は暮らしている。旧ソ連崩壊によりアルメニア共和国が出来てからもその状況には変わらない。今作の監督・脚本・主演のハリウッドのベテラン俳優であるマイケル・グールジャンもその一人である。
だが、彼らはアルメニア文化を忘れない。今作はその思いに満ちた作品でもあるのである。
・アルメニア文化と言えば、アルメニアの民族の象徴とも言われるアララト山がその代表格であろう。ノアの箱舟が流れ着いたとされる山である。
今作ではそのアララト山が重要なモチーフになっている。看守の男(後半に明らかになるが、高名な画家であったアルメニア人のティグラン(ホヴィク・ケウチケリアン)。彼は教会を描いた事で、画家を止めさせられ刑務所の看守になっており、画家の夢を断ち切れなったために妻と口論になっていたのである。)の家での宴会を見ていたチャーリーが自分もアルメニア人と伝える為にタバコと引き換えに描いて渡したアララト山や、ラストのシーンでも効果的に使われているのである。
■今作の演出で上手いのは、ティグラン夫婦の会話が字幕でも出ない所である。観る側は夫婦の会話や、仕草や室内の状況で夫婦関係の状況を推測するのであるが、これが良いのだな。
・今作では、チャーリーは無実の罪で獄に繋がれても決して諦めない。彼はティグラン夫婦の家を観るために独房を快適なカラクリに満ちた部屋に変え、ベッドを椅子にしてティグラン夫婦の家を眺めながら食事を摂るシーンなどとても良いのである。
・そして、彼の想いが通じてティグランは出て行ってしまった妻を迎える為に、酒も止め部屋も綺麗にするのである。そこに漸く戻って来た妻(ナリーヌ・グリゴリアン)。
そして、ティグランはお礼にバターを差し入れしたりするのである。壁が有っても二人の友情は成り立ったのである。
ー このシーンで、チャーリーがティグラン家のパーティに参加している夢想シーンも良いのだな。-
・だが、或る日、チャーリーたちはシベリア送りを命じられる。だが、偶々刑務所に訪ねて来たソナは、チャーリーが獄の中にいる所を見てしまい、夫である刑務所長に激しく詰め寄るのである。
そして、チャーリーは意地の悪い看守によりティグランにボンチク(ベルトで鞭うたれる事。)をされながらも刑務所から釈放されるのである。
・彼が自由の身になって行った場所は、長年観て来たティグラン夫婦が住んでいたアパートなのである。そして、そこの棚に挟まれていた布に見事に描かれていたのは、アララト山だったのである。
そして、チャーリーは老いるまでその部屋で、楽しく仲間達と宴会などをして暮らすのである。
<今作は無実の罪でソ連の獄に入れられた男が格子から見えたアルメニア人看守と交流し、自由を勝ち取る様を描いたハートフルなヒューマンドラマなのである。>
アルメニアと北朝鮮
第一次世界大戦時にトルコがアルメニア人を100万人単位で虐殺していたと言うとんでもない歴史的事実を知ったのは映画「消えた声が、その名を呼ぶ」(2015)を観た時でした。ナチによるユダヤ人虐殺と同様のホロコーストがあった事をジイサンになるまで知りもしなかったのです。学ぶべき歴史はまだまだ沢山。
さて本作は、そのホロコーストを逃れてアメリカに移住していた男が、ソ連治世下で落ち着いた社会になったと思われた祖国に戻ったところ、いきなりスパイ容疑で逮捕され監獄に放り込まれるというお話です。しかし、物語は決して暗くはならず、監獄の窓から見える近所のアパートに暮らす夫婦を静かに励まし続けるという予想外の展開を見せます。男が置かれた状況は不条理で厳しいのに、夫婦を見守る眼差しは妙に可笑しく、心温まります。観る者は自分の心を一体どこに置けばよいのか戸惑ってしまうのでした。これは上手い造りだなぁ。
ところが、更に引いた視線で見ると、彼の境遇が全く別の歴史的事項に重なって見えます。それが、「地上の楽園」の宣伝文句に夢を託した在日コリアンの人々が北朝鮮に帰った途端に厳しい現実に晒されたという「帰国事業」です。僕の身の回りでこの事業に加わった人は居ませんが、日本人としてはかなり身近な問題に感じます。それだけに、本作の舞台が北朝鮮であったなら「悲惨な現実をこんなにホッコリ物語に描いてしまっていいのかな」と感じていたのではないでしょうか。それは考え過ぎなのかな。
其れよりも何よりも宗教って必要ないよな。
ワンブロック先の同居人
アルメニア---1915年のオスマン帝国によるジェノサイドはアトム・エゴヤン監督の「アララトの聖母」やファティ・アキン監督の「消えた声が、その名を呼ぶ」でも描かれてきましたが、過去から他国に蹂躙されてきた歴史を持つ国。最近まで隣国とのナゴルノ=カラバフ紛争が続いていたことも記憶に新しいです。
個人的には私の敬愛するショーン・ベイカー監督の常連俳優で、お気に入りでもあるカレン・カラグリアンの出身地でもあります。
主人公チャーリーは極めて理不尽な状況でも絶望せずに、少しでも興味を持てることを見つけ、器用な手先を駆使してポジティブに生きようとします。その姿勢に純粋に感動させられます。
作業場の石をズボンの裾に隠して持ち帰るシーンや刑務所内に仲間を増やしていくくだりは「ショーシャンクの空に」を想起させます。
看守夫婦とまるで同居人のように共に食事をし、洗濯をし、夫婦の不和には心を痛め、それをとりなし、子供の誕生を祝う。小窓を通しての生き生きした描写に我々観客もいつしか巻き込まれ、共感を覚えます。
釈放後は嫌な思い出から逃れるために、すぐにでもアメリカに帰国しても良さそうなのですが、アルメニアに留まる決心をしたチャーリー。この国の過酷な歴史が自身の体験と重なり、神聖なるアララト山の霊性が民族の矜持を呼び覚ましたのかもしれません。
笑顔を忘れないチャーリーの生き様に感服
冒頭に母親から言われた「笑顔を忘れずに」は、
チャリーの人生における矜持だと感じた。
それは刑務所送りにされてからも、
格子窓から見える真向かいの家の中の風景に
楽しみを見出したり、刑務所の中でも
看守との関係性が徐々に変わっていく様から
そう感じるのだ。
真向かいに住んでいるのが、
チャリーが助けた子どもの母親の妹の夫であり、
チャーリーのいる刑務所の見張り台で働くティグラン。
もうこの設定が全てだと思うし、
だからこそ、ほぼワンシチュエーションにもかかわらず
ドラマが生まれるのだと思った。
チャーリーは不運だが、実は幸運でもある。
幸運を引き寄せたのは、
子どもを助けたという善行があったから。
だから、運なのではなく、因果応報なのだろうか。
ラストショットのチャーリーも印象的。
チャーリーの苦労は想像を絶するほど過酷だが、
そこにチャーリーの笑顔と創意工夫に
観客として助けられた。
じんわり心に沁みた。
力なき者の処世術
子供がたったひとり、衣装箱に入れられ船積みされて、よくぞアメリカまで行きつけたものだ。その後どうやって生き延びたのか。チャーリーは運がいいのか悪いのか。
個人がどうあがこうとびくともしない大きな力に翻弄され続け、せっかく移住できたアメリカから希望を抱いて故郷のアルメニアに戻ってきたと思ったら、たった一度の「親切」がとんでもない不幸を招くおそろしく理不尽な目に遭わされるが、チャーリーはあまり抵抗しないし嘆いたりもせず、なすがままに流れに身を任せ周囲に逆らわず生きていく。抵抗も嘆きも無駄だと知っているからか。
逆らわずその場になじんで何かしら「楽しみ」を見つけて生きていく。
それが、チャーリーが身に着けた、力なき者の処世術なんだろう。
当初チャーリーに意地悪してサンドバックにして楽しんでいた職員たちもいつの間にか親しくなって、刑務所なのにその辺の職場のよう。
チャーリーが房の中でいろいろ仕掛けを施して住みやすく改善、向かいの夫婦観察を楽しむあれこれを整えているところはたくましくて笑ってしまった。
踏みつける人がいれば、助けてくれる人がいて、それが人生。
でも、助けてくれる人がいないかタイミングが悪いかで、終わってしまう人生もいくつもある。
覗かれていた側が、カギのありかを教えてくれたことに感謝するか、覗かれていたことに嫌悪感を持つかで、チャーリーの運命は変わったはず。
しょせん、人生は運なのだろうか
「運」のように見えるが、チャーリーの日ごろの行いが引き寄せた、めぐりあわせのように思える。
刑務所の所長ドミトリーは妻のソナに頭が上がらないが、彼女はどういう立場なんだろう。
いい人でよかった。
チャーリーは結局アメリカには戻らず、故郷アルメニアに留まり、家族、同胞に囲まれてにぎやかな食卓を囲むという、夢に見た幸せを手にしたようで、彼の幸せが心から嬉しかった。
アルメニアという国の複雑な事情とソ連によるでたらめな統治を描きつつ、コウノトリのように、自由に空を飛んで自身の居場所を決められたら、という願望と、高いところなら呆れるくらいどこにでも巣を作り居場所にしてしまうコウノトリのように、どこであろうと自分なりの居場所と楽しみを見つけてそこで生きていける人が幸せに近いという、シンプルかつ普遍的なことが描かれていた映画だったと思います。
コウノトリには、私が知らない宗教的な意味合いもあるのかも。当時のソ連では宗教は禁じられていたことでもあるし。
エンドタイトルで流れていた曲がとてもよかった。
インドの楽曲のようであり、バラライカのような楽器も聞こえる、独特で耳に残る曲調と、民族衣装に身を包んだ演奏者たちがとても良く、アルメニア音楽をもっと聴いてみたいと思いました。
アルメニア
アララト山をバックにしたラストの曲で泣けそう
アルメニア・米国の合作だそうだ。米国が絡んでいるにしては良い映画だな。もちろんハリウッドは全く無関係だろう。監督・脚本・主演がマイケル・グールジャン。どうやら映画の主人公は彼の身内がモデルらしい。
第一次大戦中にオスマン帝国内で起きたアルメニア人虐殺を逃れ、米国に渡った少年が、1948年ソ連邦内のアルメニア共和国へ戻り、そこで身に覚えのない政治犯として投獄される。
独房の窓からは隣のアパートの様子が見え、そこで暮らす夫婦に強い思い入れを持つ。刑務所の監視係でもある夫には絵を描く趣味があり、その点が主人公と共通するだけになおさら気持ちが入り込む。そのままでは一方的な覗き魔のようなものだが、二人はある事件で接点を持つにいたる。
今まで実際にアルメニア人には幾度か会ったこともあるが、とても良い経験だった。それだけに彼らを襲った悲劇と、それを無視し続けた周辺国・大国のエゴに対して憤りを感じていた。エンドロールの最後で、アララト山を背景にして民族衣装をまとったアルメニア人たちの歌曲が流れると、じわっときてしまった。今のところ今年観た外国映画のベストワンだな。
中盤までは退屈。
私にとってアルメニアと言えば、作曲家アラム・ハチャトゥリアンの母国である。たしか、アメリカの小説家ウィリアム・サローヤンもアルメニアからの移民のはず。知らない国ではないが、アルメニア語を始めて聞いた。また、アルメニアはトルコ?から大量虐殺を受けたことは、漠然と知っていた。
物語は第二次世界大戦後、祖国再建というスターリンの口車に騙されて、強制収容所に収監されたアルメニア系アメリカ人の苦難の話。絶望的環境の中で、人はいかにして生きていけるかを訴える映画だ。
中盤までは本当に退屈だった。牢獄の窓から見える収容所監視人と通じあえた所から、やっと面白くなる。が、現実はやはり過酷だ。明るい結末にしたい気持ちは分かるが、私には疑問だ。
アルメニアのように、戦後日本でも北朝鮮出身者の祖国帰還運動があった。帰国者は劣悪な環境に置かされた。知っているだけに、結末は納得がいかない。
アルメニア音楽も素敵。
アルメニアの映画です。歴史的に不安定なこの地域の映画大好物ですわ。地続きは本当にいつも武装してないとウクライナ見たく難癖つけられてあっという間に国土取られちゃうんで心落ち付かないですね、日本に生まれてよかったです。この地域の歴史も上記の理由で複雑で日本ではあまり紹介されないのもあり、必ずパンフ買ってその国の背景歴史少し知るのも楽しみの一つです。
バラバラに世界に散っていたアルメニア人が大戦後、国の再建のために母国に集められ(実はソビエト連邦の陰謀)、アメリカに居た主人公がいきなりスパイ容疑で投獄される所からはじまる獄中記です。ライフイズビューティフルみたくどんな辛い状況でも笑顔で生きる事の重要さ、ユーモア(humor)とは人間らしさなんだよと、どんな状況でも楽しみ方を見つける事が重要なのだと教えてくれる映画です。かれの場合は窓から見える元画家の看守の家庭だったりするのがなかなか話を面白くしてくれてます。
アルメニアといへば私は
映画だとパラジャーノフですかね。
音楽だとJazz系ティグランハマシャン最高です。
アルメニアじゃないけど「コシュバコシュ」とか、「葬送のカーネーション」とかも素敵ですよ。
sprite survive
映画を見終わって、すぐ思ったことは主人公Charlie Bakhchinyan(監督脚本、主人公Michael A. Goorjian )の想像力・創造力などが、現在人である我々が投獄されたら残るだろうか?
当時を計算すると、1922年(アルメニア・ソビエト連邦)からスターリンの死、1953年まで約31年主人公(チャーリーorカロ)は獄中にいたわけだが、この間、主人公は砂、石、そして、口をきくことは看守やソ連軍や同胞とだけである。この中で、画家Tigranの差し入れて、絵を描きはじめた。それに独演をしたりしたわけだ。また、Tigran(Hovik Keuchkerian )や奥さんのマネごともした。二人の気持ちになって、アドバイスを与えたりした。その、アドバイスが絵だったり、黙示力もあった。エンターテーメントスキルもあるわけだが。体罰を受けても、食事が粗末でも、乾杯したり、アルメニア語を生活の中に入れて、一人芝居をした。獄中の環境が最悪でも、彼はこのクリエイティビティがあったからこそ、ここまで生きられたと思う。
たとえば、Z世代のある青年が投獄したとすると、まず、使えなくなるものはスマホである。膨大なインフォが隠されていると思うし、どの組織や仲間にもコンタクトされたくないから。これなしに、紙と鉛筆の世界に戻るわけだ。スマホに汚染されているとしよう。そうすると、鉛筆での動きはキツい。我々は主人公のようなクリエイティビティーをどう確保できるのだろう。明らかにサバイバルスキルである。肉体的にもメンタルも弱くならないためにも。生き抜くためにも。
まず映画の冒頭に字幕でアルメニアの歴史が説明される。『第二次大戦のあと30年世界に散って行ったアルメニア人がソ連政権の元に戻ってきた。スターリンはアルメニア人虐殺の生き残りの人々に、お金を出した。10万人のRepatrates (この場合アルメニアに戻ってきたアルメニア人)の中に三百十三人の米国アルメニア人がいたと。米国の市民権を拒否して、自国に戻って、自分のアイデンティティと文化をとり戻した。この物語はその中の一人の話である』と。映画の最後に、この映画は監督の祖父に捧げると。多分だが、これは監督の祖父の経験に脚色を加えて制作したもか?と思った。なぜかというと、1915年にアルメニアの主人公の家族がオスマン帝国の虐待に遭い、米国に難民化した。それは監督の祖父も同じであり、祖父は(主人公も)アルメニアのソ連体制に(Repatrates )戻ってきたから。
序幕で主人公のお婆さんが『Caro,Never lose your smile』と。おばあさんのいうことをよく聞いたね。大変だったのに。それに、この時、すでに主人公はイマジネーションのある子供だったんだね。
メインストーリーは1948年、アルメニア・ソ連の時代から始まる。第2次大戦後、妻を失った主人公は、故郷アルメニアに帰ってきたが(Repatrates )ソ連連邦から信用されず、スパイだと思われてしまう。ソ連は米国が反革命プロパガンダを広めるために送り込んだと思っている。事態をのみこめていない主人公とソ連側の軍人の会話は質の悪いコメディのようだった。たとえば、十本のネクタイをある軍人は欲しがっていると思ってる主人公。しかし、軍人は主人公に10年のシベリア行きを与えると。また、数人の同胞が刑罰を受けるんだが、その順番を先にさせてくれと頼む主人公。主人公はアメリカ英語でとても丁寧に頼むんだよね。おかしくて、おかしくて!
主人公は独房に押し込められるが、その生活で、小窓から 自分をエンターテインする方法を見つけたようだ。 Tigran(Hovik Keuchkerian )と奥さんの演劇を遠くから観賞している。会話の続きが毎日あり、遠くから見ているだけで、十分理解できるようだ。最初は演劇の観衆になったように振る舞うけど、その後は家族の一員になって、食事も一人で食べず、窓向こうの夫婦と一緒に食べるようになる。たのしそうだ。ター(Ta)という楽器を Tigran?が弾き始めた時、主人公はほとんど聞こえていないと思うが、目を閉じて聞いているのが良かった。こんなとこで生活しているけど、感慨深い顔つきをして聞いていたよ。食事にしろ音楽にしろ独房にいて一般人のアルメニア人の文化との接点を見出したんだね。文化を体験して、自分をその文化に置いてみるのもアルメニア文化を知る最高の方法だからね。コメディのようだけど、悲劇で、おばあさんの言った、微笑みを忘れないね。主人公のポジティブなスピリットが苦境を乗り越えたね。主人公はシベリアに流刑されずにアルメニアに残ることができたが、30年もの間、監獄の中で刑罰を受けた。
主人公のおばあさんが冒頭で歌っていた「gorani」の意味が『鳥』だと、ソナから教わったシーンもいいねえ。この歌はアルメニアのフォークソングだけど、Taronという地域の曲だと。これで、主人公が鳥に注目したり、地震でも鳥の卵を助けようとしたりした行動に伏線を貼ってるね。
この地域を検索する(私の検索が間違いなければ)と、現在はトルコだ。巨大な文明の発祥地、アルメニアの現在は小さな国になったけど、近隣の地域は過去にはアルメニアだったようだね。
ここで、おかしいと思ったシーンをいくつか書いてみる。
1)自分のことを正当?のアルメニア人だと思っている年配の刑務所仲間がいるが、彼はTrigonのことを身売りをしたスターリン派だという。Trigonこそ反スターリン派だと思うが。なぜなら、彼の芸術に理解を示さない、スターリンの独裁に対して、画家としての仕事を奪われ、監視塔で働いているから。そして、主人公のチャーリーにこっそり画材を送ったり、食べ物を届けたりして主人公の立場を理解してくれてる。でも、主人公チャーリーを命令で、殴らなければならなかった。その心の呵責で彼は、監視塔での仕事を辞めたように思う。ソ連体制で、果たしてそれができたかどうか知らないが。少なくても、ソ連のコマンダー、ドミトリー(Mikhail Trukin )の奥さんのソナ(Nelli Uvarova )とTigranの奥さんは姉妹だから。コネはあるよね。
2)自分のことを正当な?アルメニア人だと思っている男は刑務所の中で最高に引き立つし、監督はアルメニアの知名度を上げるためにも面白い存在を映画に入れたね。自分の国を誇りにしているのいいことだ。アルメニア人がワインを発明したとかいうが、検索してみたら、ジョージア人の説もあるようだ。古代文明の発祥地、メソポタミア文明(チグリス・ユーフラテス)の土地だから、はっきりアルメニア人と言い切れないものがあると思う。しかし、キリスト教を国教として最初に受け入れたのはアルメニア人だというのは史実となっている。エルサレムにも(モスリム、ユダヤ、クリスチャン、アルメニア使徒教会)があるからねえ。
3)ソ連のボス、ドミトリーのダブルスタンダードと権力の横暴には笑っちゃうね。西洋の物質への憧れ、それを持てない僻みや英語が少し話せる妻ソナから味わう屈辱。ソナの主人公に対する言動を伺っているのを知ってか、その嫉妬深さ。スターリンが死んでから、ニキータ・フルシチョフの大きな写真が飾られたが、ドミトリーの家族はその後どうなちゃうんだろうと思った。スターリン派の人の将来はフルシチョフの政策には結びつかないからね。
最後に、監督はなぜこの作品を作ったのか見当がつかない。パンデミック中の作品のようだ。勝手に考察すると、一つにはアルメニアの知名度の低さにアルメニア人だったら驚くと思う。ダイアスポラはユダヤ人や中国人のように世界中に散らばっているが、アルメニア人はおとなしい人々だ(偏見?)。そして、アルメニアというと主に、オスマン帝国の虐殺を思い出すし、その映画やドキュメンタリーは数ある。それに、メソポタミア文明。三代文明の一つだと言っても、イラン、シリア、トルコ、イラクなどと現在では幅広い国にまたがっている。文化のいいところだけを海外に出す(偏見?)、イスラエルや日本と違って、もっと幅広くアルメニア文化を啓蒙したいのではないかと思う。それを深くするには人間の喜怒哀楽がつきものだからこの映画をこのように、アルメニアで作ったと思う。-私見
すごく良かった こんな状況下でも、 こんなに素直で前向きで、人を信...
すごく良かった
こんな状況下でも、
こんなに素直で前向きで、人を信じて疑わず
どうしたらこんな人ができるんだろう、
そう思いながら何度も泣いてしまった
監督のおじいさんに捧げられてたようだけど、
まさか、おじいさんの体験談?
ヴァーニャを助けただけなのに
お互いカタコトな上に、ちょっとした発音の違いで全く意味が変わってくるからややこしい。
過酷であるはずの状況をユーモアを交えて描くというストーリーは、なんとなく『ライフ・イズ・ビューティフル』や『ジョジョ・ラビット』を彷彿とさせる。
戦後だからユダヤ人の迫害のような事は起こらないとはいえ、理不尽じゃないか。
ずっと、あの時ヴァーニャを助けてなければ...というのが心の片隅に残る。
しかしチャーリーの前向きで気丈なキャラクターと、ティグランへの想いが届かない「志村うしろうしろー」的なもどかしさが微笑ましく思えるのが救い。
と同時に、ドミトリーをぶん殴ってやりたいもどかしさもあり。
終盤のチャーリーの、なんとも言えない寂しげな表情がすごく印象的。
なんか幸せになってほしい。
希望
牢獄の小さな窓から見える故郷
「飛んでお行き、小さなコウノトリ」それは息子の幸せを願う母の思い。
アルメニア人版「ライフイズビューティフル」と呼べるような作品。ホロコースト、いわゆるジェノサイドと聞くと、どうしてもユダヤ人を先に思い浮かべるけどアルメニア人も同じく受難の民であり、ユダヤ人同様ディアスポラを経験している。
本作も「LIB」同様に主人公はどんな苦境に立たされても決して笑顔を忘れずに希望を抱き続けた。
オスマン帝国によるアルメニア人虐殺を逃れた幼き日のチャーリー。彼を命がけで守った母は銃殺される間際まで彼を笑顔で見送った。「人生これから苦しい時もあるだろうけど、どんな時でも笑顔を忘れてはいけないよ。飛んでお行き、小さなコウノトリ」それは母が息子に込めた思い。息子を思い最後まで笑顔でい続けた母。
これはアウシュビッツに収容されながらも息子を思い、怖がらせないよう噓をつき通したあの父親の姿と被った。彼も銃殺刑に処せられる直前まで隠れてる息子の目の前でおどけて息子を笑わせた。生涯忘れられないシーンだ。
母の思いが通じたのか、大戦が終結し故郷に戻ってきたチャーリーは笑顔を絶やさない紳士となり、子供を助けたことから同じアルメニア人のソナと親しくなる。
しかし、彼女の夫のちょっとした嫌がらせと当時のずさんなソ連の体制も合わさり、チャーリーはスパイとして逮捕されてしまう。
暗い独房に収容されたチャーリー。幼いころに虐殺により唯一の肉親の母を失い、見知らぬ土地で生き抜いてようやく帰ってこれた故郷の地でスパイと疑われてよもやのシベリア送りになる直前まで。
このような悲惨な体験をしてきたなら、人間はへこたれてもおかしくはない。実際に彼の独房での所業に看守たちは彼が頭がおかしくなったのではと疑う瞬間もあった。
しかし、彼は狂ってはいなかった。彼はこんな絶望的な状況の中で小さな幸せを見つけていた。
暗闇が暗ければ暗いほど微かな光でも見つけやすくなるように、彼は絶望的な状況下で微かな幸せを見つけていた。それは独房の小さな窓から見える景色だった。
それは同じアルメニア人で看守のティグランが夫婦で暮らすアパートの部屋。長く故郷を離れていた彼にとってその光景は忘れていた故郷を思い出させてくれる光景だった。
そこで繰り広げられる夫婦の何気ない日々の暮らしを見つめていつしか彼は彼ら夫婦と同じ時間を過ごす。冷たい牢獄にいるはずの彼が暖かい空気に包まれ幸せな時を過ごせた。
仲睦まじい二人と自分とを重ね合わせ彼らの幸せがまるで自分の幸せのように感じられた。大勢の来客を招いた際にはアルメニア人の伝統的な食事の作法なども学ぶことができた。
彼は日々の強制労働や粛正による拷問のつらい日々でもその窓から見える景色のおかげで幸せを感じることができた。
夫婦が離婚の危機には彼が何とかして彼らをつなぎとめようとキューピットの役割まで果たした。文字通り地面にスノーエンジェルを描いて。
彼の存在に気付いたディクランは彼に感謝して、それから彼らの窓越しの交流が続いた。やがて夫婦に子供が出来てそれを自分のことのように喜ぶチャーリー。
しかし運命は彼らにさらなる試練を与える。粛清の拷問担当にティグランが選ばれたのだ。初めて言葉を交わせるほどに近づけた二人だったが、それは言葉ではなく暴力を浴びせる場面であった。
スターリン体制のソ連で逆らうことは死を意味する。チャーリーもそれを理解していた。殴られた方のチャーリー、殴らされた方のティグラン、二人は共に同じ痛みを受けた。
彼らはともに傷ついていた。同じ民族同士で傷つけ合わねばならなかった彼らのその姿こそソ連統一の名のもとに行われたスターリンの民族政策に翻弄された少数民族の姿だった。
同じ受難の民のアルメニア人同士、ようやく祖国に戻った彼らにとってソ連のスターリン体制は残酷であった。
しかし二人の絆は壊れることはなかった。ともに描いたアララト山の絵を見せ合う二人。それはまさに彼らアルメニア人の祖国の象徴でありアイデンティティの源。それが彼らの絆をより強いものとしていた。
ノアの箱舟が大洪水を逃れて辿り着いたとされるアララト山。ジェノサイドを経験しディアスボラを経験してやっと祖国にたどり着いた彼らも同じだった。
やがて別れの時が訪れる。ディクランたち家族は転居してしまう。そしてチャーリーもソナの計らいで釈放されることに。
故郷を探すつもりで祖国へ戻ってきたチャーリーだったが、彼はある部屋を借りてそこで暮らし始める。
その部屋の窓からはチャーリーが閉じ込められていた独房の窓が見えた。この部屋こそディクランたちが暮らしていたあの部屋だった。
チャーリーはここに故郷を見出していた。だから故郷を探す必要はもうなかったのだ。彼はここで家庭を築き幸せに暮らした。カーテンを閉めることはけしてなかった。
独裁者たちがいくら物理的に人の命を奪おうとも彼らの魂までは奪うことはできない。彼らの思いは受け継がれていく。たとえその人間が死のうとも失われず受け継がれていく彼らの意志。死んでも失われないものを魂というのならその受け継がれていく意志こそ魂と呼ぶんだろう。母の魂は息子に受け継がれ、彼は幸せを運ぶコウノトリとなった。
人生で忘れられない映画のワンシーン、「ライフイズビューティフル」の一場面を思い出させてくれた。
「過酷な状況でも希望を失わず」
全32件中、1~20件目を表示