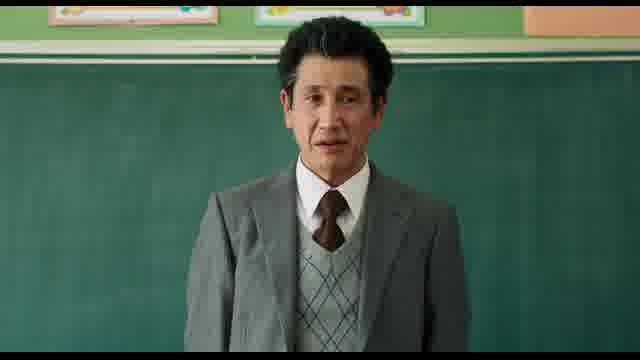中山教頭の人生テストのレビュー・感想・評価
全19件を表示
そういえば最近の渋川のアニキはゆるキャラかも
話の内容は、私の中ではあり。 いつの時代もイジメはあるし、嫌な先生...
人間は本当に面倒な生きもの
【”先生や大人が言う事なんて全部間違っている。ゴールなんて目指さなくていい。”と教頭先生は最後の挨拶で生徒達に言った。今作は全国のお堅い教育委員会に喧嘩を吹っ掛ける如き、教育ヒューマンドラマである。】
■山梨県の小学校で教頭を務める中山(渋川清彦)は、教育生活30年のベテラン。昔は熱血教師だったが数年前に、自分が授業中に妻が事故に遭い、それでも授業を止めなかったために死に目に会えず、中学生の娘に責められ自分も後悔を抱いて生きている。
娘の進学を控え、一応校長昇進試験にも挑戦するが、ナカナカ合格できない。
校内では、近隣のクレーム爺さんの対応や電球の交換など雑用担当だが、いつも笑顔を浮かべている。
そんな時に、校長に逆らった女性教師の代わりに来たマアマアパワハラの男性教師も、学校に来なくなり、急遽中山は教頭兼、久しぶりの担任になる。だが、そのクラスは表面上は問題が無く見えたが、様々な問題を抱えるクラスであった。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・いつものように、フライヤーをロクに読まずに観に行ったので、”善良な教頭先生が、問題ある生徒達を矯正させ、良かった、良かったじゃないの、”などと思いながら鑑賞開始。
・だーが、この映画が色んな意味で凄かった。
笑顔一切なしの男性教師の生徒に対するパワハラの接し方に始まり、生徒間でも関係性が複雑に入り組み、モンスターペアレンツは出て来るわで、そこを教頭が”ビシッと”締めるかと思いきや、教頭もグダグダなのである。
で、思ったのだが”あ、この映画は先生は万能の神などではなくって、普通の過ちを犯す人間であり、教頭先生の成長物語だな。”と思ったのである。
・スンゴイ、優しい笑顔の女の子が、モンスター級のサイコ苛めっ子であったり、不登校の女子や、苛められている男子と、苛めっ子の女子の関係など、大人社会もビックリであるが、少し前に見た学校のドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会」を思い出し、”この映画は、そのブラックバージョンでもあるな。”と思いながら観賞を続行する。
・中山教頭は教育長(風間杜夫)で、女性校長(石田えり)を激しく糾弾する夜の酒の場では(というか、夜の酒の場、ムッチャ多し。教育長、仕事しろ、仕事!)へこへこ、教育長のいう事を聞き、校長の前では自分の意見を言い出せない。
果ては、校長が下した不登校女子に対する処分の厳しさを糾弾される場で、自分の昇進を考え、校長の擁護に回る始末である。
・だが、教頭はそんな日々を送る中で、少しづつ、生徒達に望むことを学んでいくのである。この辺りの教頭を演じた名俳優渋川清彦の、媚びたような笑顔を浮かべながら生きる姿は絶品である。
・中山教頭は更に、校長昇進試験でカンニングまでするのである。”あーあ。この映画、全国の教育委員会に更に喧嘩を売っているよ。”と思いつつ、試験後に若い試験官から呼び止められた教頭は、存外の”この間の会見での毅然とした態度が立派でした!”などと言われる握手を求められるも、当然それに応えずに、悄然とした顔で、会場を去るのである。
・そして、或る晩。中山の携帯に電話が入る。それは、彼が校長の試験に不合格になった連絡だった。だが、彼はそれを聞いて、何故か笑顔になるのである。
・だーが、その後、ナント女性校長の使い込み(たった、8万円。せこいなあ。けれども、彼女には日の当たらない女子重量挙げ選手を指導する立場にもあったのである。)が発覚し、繰り上げ式に中山は工長になるのである。
<ラスト、学期末の挨拶で中山が生徒達に、少し涙を浮かべて言った言葉が良かったなあ。彼はこう言ったのである。
”先生や大人がこうしなさいって言う事なんて、全部間違っている。ゴールなんて目指さなくていい。”
そして、その言葉の後に駆け寄って来たモンスター級のサイコ苛めっ子の女の子が心配そうに”何か分かったんですか。”と言った時に、中山が彼女に向けた笑みなき真面目な眼が良かったのである。
今作は、一人の過ちの多い教頭先生が、様々な経験をする中で、生徒と共に成長し、真の教育者になって行く姿を描いた作品なのである。>
<2025年6月29日 刈谷日劇にて鑑賞>
教室の解像度が高い
己の職業柄、こういう作品のリアリティーラインにはうるさいタイプですが、これはかなりリアルだと断言できます。教室内ヒエラルキー、表には見えてこない陰湿さ、決めつけたことによる子どもや親のトラブル、保護者説明会のヒリヒリ感、そして何より教頭先生の何でも屋加減。お見事でした。強いて言うなら教頭先生が代わりに担任に入るんだから、名前覚えてもらえるように学校内では名札してあげて〜って感じ。
教頭=中間管理職とはまさにこのこと。校長の窓口も平教員の窓口もPTAの窓口も。家に帰れば思春期の娘の感情に左右され、妻への悔恨。とことん挟まれる境遇を渋川清彦が見事に演じきってたと思う。
教員を志す場合、対子どもに何かをしてあげたいからがほとんどなわけで。管理職は対大人になるので、強烈な出世欲がないとなり手が少ないのが現状。この主人公は教頭より校長のほうが仕事の融通が効くからというのは、家庭への罪悪感が大きいとは思うけれど、それでは貪欲にはなれないよなーとは思う。
映画でスローモーションになる数少ないシーンが効果的。妻に会えるシーンもフィクションならではの面白さ。後半のネタバラシパートの痛快さ。大人は間違えるからの道間違いのきれいさ。
良いお話で終わりきれない『死ね』の連呼も、この監督らしいなと。
教頭の思い出なんて普通はない
渋川清彦の演技が見事❗️
中山教頭の人生テストを観たが、予想以上に良かった。椎名先生の代役で中山教頭が臨時担任を担当したが、大変な業務の中生徒と向き合う姿勢は失わなかった。中山教頭の思いが生徒に伝わった。校長試験も同時進行。改めて、学校の大変さを痛感。渋川清彦の演技は素晴らしかった❗️夜明けのすべて、箱男の演技が物凄く良かっただけに今回も見事。
とにかく教頭は大変だ
舞台は山梨県の田舎の小学校。何でもかんでも雑用を押し付けられる教頭の中山先生は、ひょんなことから5年生の臨時担任を持たされることになり、校長試験の勉強もままならなず……。
校長、教員、生徒、教育委員会、そして保護者や近隣住民といった諸々のステークホルダーたち、そして家庭内では娘との関わりの中で葛藤する中山先生の姿はおかしくもあり、哀しくもある。
学校の現場としては、それはありな得ないだろうと思える話と、よくありそうと思う場面が交錯して描かれる。
中盤過ぎまで、こんな話を若い連中が観ていたら、そりゃあ教職に就こうなんて考える大学生は激減して、教員不足はますます加速されるだろうな、と思いながら観ていたのだが、最終的にはわりといい話に着地していた。
ただ、そんな感じに着地させてしまって良いのだろうか?という懸念も拭えない。学校の問題は社会全体が抱えている問題であり、それを学校に押し付けて自分は知らんぷりみたいな人間が多いことが最大の問題なのではないか。教師であろうがなかろうが、あるいは大人だろうが子どもだろうが、一人ひとりが抱える自分の弱点や苦悩、問題点にもっと対峙してもいいのかも知れない。
ルールに従ってさえいれば人生を間違えないという訳ではない。ポスターにある「先生や大人がこうしなさいって言うことは全部まちがってる」というセリフには劇中では「君がやりたいと思うことは全て正しい」という続きがある。先生が生徒に言うセリフではあるが、ちょっとするとこれは中山先生が自分自身に語りかける言葉だったのではないだろうか。そして、自分のやりたいと思うように行動することが正解なのかこそが彼の人生テストなのだろう。
で、プロテインシェイカーはどうなった?
ルールに頼るということ
前日に同じ11歳を扱った「ルノワール」を観たばかりなので印象を引きずってしまうのだが、本作でもこの年齢の女子が男子を置き去りにして大人になり始め、少女と女性、天使と悪魔が同居している感じをうまく捉えていた。
諦めずに夢を追い続けることが大切、みたいな思考停止に堕する事なく、世の中に不合理や不正義が蔓延しているのを認める所から始めよう、という終業式スピーチは、子供達が社会に出た時に過剰に絶望して折れてしまうのを防ぐためのメッセージで、漫画「夢なし先生の進路指導」を思い出させる。
色々ベタな演出があったり娘との関係描写もイマイチだったものの、スーパー熱血教師を描いて教育現場への過度な期待を煽るようなしょーもない作品でない事だけは確かだろう。
渋川清彦の自信なさそうな演技はなかなかよかったけど、光石研だったらどんな感じだろうと想像してしまった。
ゆるキャラ校長
校長職を目指す頼りない小学校の教頭先生の話。
妻を亡くし中学生の娘との2人暮らしで、娘の為に今より時間を作れるようにと校長職を目指す中山教頭が、休職した先生のフォローの為に5年1組の臨時担任まで務めることになり、様々な問題に直面して行く。
何があったのか良くわからないけれど、元々の5年1組の担任が降ろされて、後任となった先生のちょっとヤバい感じをみせていく始まりから、生徒の中にも問題が…まあ結構黒幕はわかりやすいけれど、散々広げて振りまくって、ほとんどのネタが実はこうでしたで終わりなのはちょっとね。
先生が題材の話しなんだから、そこへの対応がキモだと思うのだけれど。
優しくマジメで、少しどころかかなり頼りない教頭の、変化とかトラブル対応とか向き合う姿とか、面白くはあったけれど、口下手なのはやっぱり損だよね…。
それにしても、何でもかんでも説明会とか、怖いですーとか、今時はこれが普通なんでしょうけど、アホクサ&メンドクサ。
金八先生シリーズのように、、、
「中山教頭の人生テスト」は、
まさにタイトルが示す通り、
一人の教頭が直面する様々な試練を通して、
現代社会における教育現場の厳しさ、
そして一人の人間としての生き方を深く問いかける作品だ。
本作が描くのは、
理想と現実の狭間で奮闘する中山教頭の日常と、
その真摯な姿だ。
学級崩壊の危機、
モンスターペアレントからの理不尽な要求、
そして学校組織内部の人間関係といった、
教育現場が抱える生々しい諸問題は、
映画でも既視感のある内容だ、
しかし、本作はそれらを単なる社会派ドラマとして消費しない、
中山教頭は独特のスタンスで対応していく。
そして、
その「独特の展開」をみせるストーリーテリングだけではない、
映像表現の力が、物語のリアリティと深みを格段に高めている。
カメラは、
学校という閉鎖的な空間の中にある「豊かな空間」を巧みに捉える。
手前、中景、奥、さらに「奥の奥まで、丁寧に作られている灯り」は、
単に画角やアングルだけを美しく見せるだけでなく、
登場人物たちの心理的な距離感や、
学校という場所が持つ多層的な人間関係を、
視覚的に表現しているかのようだ。
光と影のコントラストが、教頭の内面の葛藤や、
彼が置かれている状況の複雑さを暗示する。
特に印象的なのは、
学校の撮影という高い難易度に真正面から挑んでいる点だ。
日本の多くの小中学校の校舎は、
学習環境を考慮して、
子どもたち自身の左側から太陽が広く差し込むように設計されており、
撮影には残念ながら様々な制約が伴う。
金八先生シリーズのように左側の窓が無いようにセットをつくると、
多くの問題は解決可能だ。
しかし、
本作はあえて「カメラを窓に向ける」
これは単なる技術的な挑戦ではないと推察される。
窓から差し込む自然光や、
移りゆく天候は、
子どもたちの心境の変化や、
物語のターニングポイントを象徴しているように感じられる。
撮影スケジュールやキャストの芝居が、
天候に左右されることを承知の上で、
この表現を選んだ製作陣の意気込みが伝わってくる。
それはまさに、「中山教頭の人生テスト」という作品の核、
つまり不確実で予測不能な人生そのものを描くために必要なリスクであり、
その挑戦が成功しているからこそ、
本作は観る者に強い印象を残すのだ。
文字数は増えてしまうが、
印象的な撮り方として、
「道の駅までの中山教頭の車のロングショット」も、
彼の孤独な決意や、
一人の人間として歩む道のりを物語るような引き絵だ。
こうした細部にまで宿る映像表現は、
中山教頭という人物への深い共感と、
「全方位で、中山教頭を応援する仕事ぶり」に裏打ちされていると感じる。
スタッフ・キャストが一丸となって、
彼の人生、彼のテストを見守り、
子どもたち、先生たちを、
支えているような温かい眼差しが、作品全体から感じられるのだ。
全19件を表示