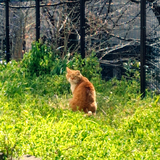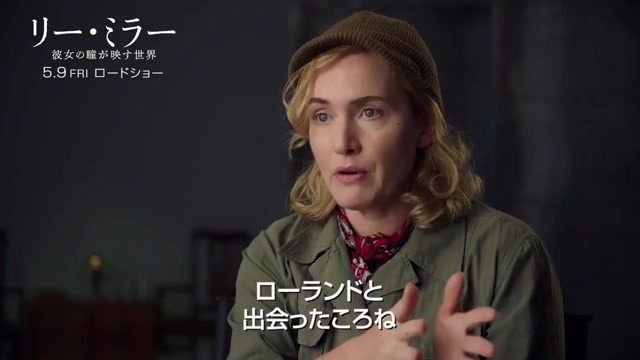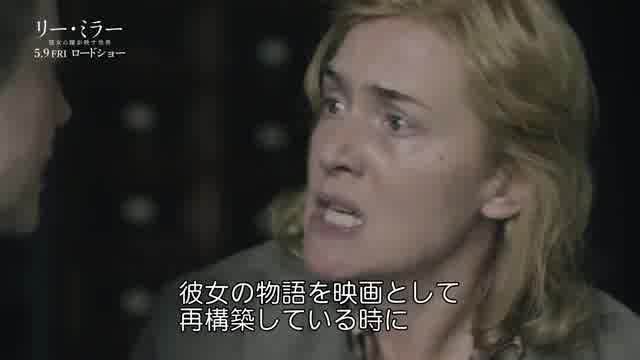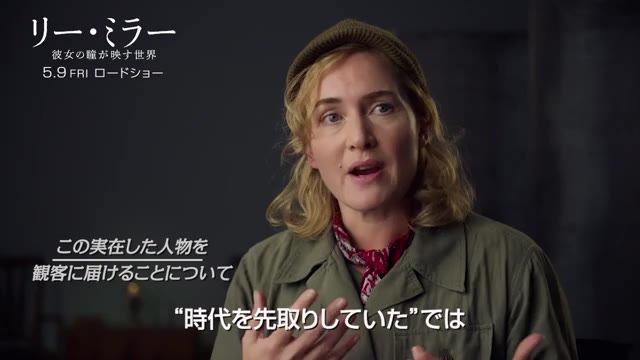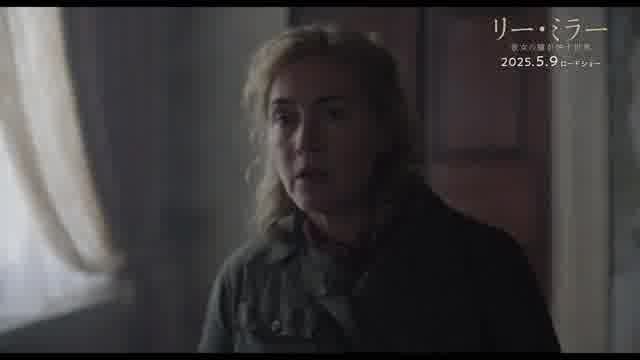リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界のレビュー・感想・評価
全127件中、1~20件目を表示
リリーの瞳から見る世界の残酷さ
見えない傷をつけられた彼女、彼らはこれからどうやって前に進んでいけばいいのか。
サブタイトルの通り、リーを通して見た世界から、人間の残酷さや非道さが否応なく突きつけられた。彼女が気付き、写しだす世界の多くは搾取され傷つけられた弱者たち。特に女性や子供が多いのが印象的だった。
最初は彼女の行動を見て、なんて正義感溢れる強い女性なんだろうと思ったけれど、見ていくうちに、ただの正義感や使命感での行動ではないんだろうなと感じられた。きっと彼女自身も搾取されてきた側で、前に進みたかったんだと気づいた。
よく実在の人物を描いた作品だと、生まれから晩年まで描いている作品が多いけれど、この作品では意図してリーのモデル時代や、戦後は描かず、彼女が従軍記者兼写真家をしていた次期のみに焦点を当てて描かれている。個人的には焦点を絞ったからこそ、彼女が伝えたかった想いを感じ取りやすく、始終心打たれた。
ひとつネガティブな意見を言うとしたら、レビューでもちらほら見かけたが、リーを演じたケイト・ウェンスレットの体型について。
確かに実在のリーを見たらもう少し細身だし、従軍記者にはリアリティに欠ける体型に思えた。華やかなモデル時代と切り離して見てもらえるように、という意図とかがあったのかもしれないけれど、もう少し絞った方が作品のノイズにならなかったように思う。
ただ、魂がこもったケイト・ウェンスレットの演技は本当に素晴らしかった!!!!まさに熱演だった。
個人的には大満足な作品で、ホロコースト・戦争映画として見応えがあったし、女性としての生き方としても考えさせられた。
多くの方にオススメしたい作品。
彼女の行動原理
リー・ミラーは「シビル・ウォー アメリカ最後の日」でキルステン・ダンストが演じたリー・スミスのモデルとなった人物だが、それ以外のことは正直よく知らなかった。
ニューヨークのファッションモデルからファインアートの写真家、転じて戦場カメラマン。写真家時代のマン・レイとの恋愛関係、ピカソやジャン・コクトー、ポール・エリュアールとの交流など。箇条書きで見れば、精力的で華やかな人生、という印象だ。
だが彼女の心の奥深くには、幼い頃受けた性的虐待の記憶が横たわっていた。また、リー本人がどう評価しているかは不明だが、10代の頃から結婚後まで彼女のヌード写真を撮り続けたという特殊な父親の存在もあった。
戦争、そしてホロコーストという、究極的に個人の尊厳を破壊する蛮行から彼女が目を逸せなくなっていった、他人事としておけなかったのは、そういった体験に根ざす部分があるのだろうか。
本作で描かれるのは、上に書いたリーの目まぐるしい人生の中で、のちに夫になるローランド・ペンローズとの出会いから戦場カメラマンとして終戦を迎える頃までのおよそ10年ほどだ。作品の製作に自ら奔走したケイト・ウィンスレットは、「モデルとしての彼女に対する先入観を捨てるため」「リー自身がもっとも誇りに思っていたであろう時期」だからと述べている。
それは、彼女が受動的な被写体、マン・レイのミューズという男の付属物のような二つ名から脱して真に能動的に生きた時期とも言える。また、終盤に77年パートのインタビュアーが息子のアントニーであることが明らかになるが、ペンローズとの出会い以降10年という区切り方は、実はリーの死後屋根裏から出てきた写真をもとに彼が両親の出会い以降の母親の軌跡をたどっていたという物語の構造とも辻褄が合うようになっている。
己の目指す道を突き進むリーだが、時代の風潮でただ女であるということが様々な場面でハードルになる。ただ、各ハードルは映画の尺的には割と素早く解決されてゆき、なんだかんだリーは最前線で撮影出来るようになる。
そして彼女はドイツの敗戦とホロコーストの痕跡に行き着く。ライプツィヒ市長の家族の遺体、収容所の屍の山。このシークエンスの映像的インパクトが頭ひとつ抜きん出ていて、リーの伝記というよりホロコースト映画なのではという錯覚さえ覚えた。
リーの人生は何故そこへ流れていったのだろう。あくまで本作から受けた印象のみでの推測だが、彼女を動かしていたのは例えば反戦とか世界平和とか、そういう抽象的なお題目ではない。
7歳の時レイプの被害を周囲に黙殺されたという体験を持つ彼女は、戦争の犠牲者を襲った悲劇が自身の受難と同様に、誰にも知られずやがて忘れられてゆくことが我慢ならなかったのではないだろうか。
写真家としての行動原理が観念的な正義感よりも個人的なトラウマに直結しているからこそ、VOGUEが自分の写真を載せないことに、預けた写真を切り裂くほど激昂した、そんな気がする。
一般的な写真家なら、命懸けで撮ったからこそ作品の破壊などせず、時間がかかっても作品を世に問う方法を探すだろう。だが彼女にとっては、犠牲の証が日の目を見ることがトラウマの癒しであり、その逆はトラウマの再現でしかなく、その状態には耐えられなかったということなのかもしれない。
収容所の死屍累々を見た直後にヒトラー家のバスタブで咄嗟に服を脱いで自撮りをするという心理は個人的には理解出来ないのだが、彼女の行動が頭で考えた理念よりもトラウマを背景にした直感と衝動に基づくものだと仮定すれば、漠然と納得してしまうのだ。
ところでこれは非常に言いづらい感想なのだが、観ている間ずっとケイト・ウィンスレットの骨太な体型が気になってしまった。ごめんなさい。
77年パート(リー70歳)は全く違和感がないし、70歳のリーを演じる49歳のウィンスレットに凄みさえ感じた。
だが序盤の1937年、マネの草上の昼食よろしく上半身をはだけて友人とピクニックをしている場面では、肩の肉が盛り上がった貫禄ボディに違和感を覚えた。この時リーは30歳、マン・レイとの活動を経て実業家アジズ・エルイ・ベイと結婚して3年ほどカイロで暮らし、ベイを置いてパリに戻ってきたばかりの時期だ(ベイとはペンローズとの子をみごもってから離婚)。
その後6年ほど戦場カメラマンとして活動するのだが、ずっと貫禄ボディのままだ。これは完全に私の先入観なのだが、最前線で命懸けの取材活動をするリーにそぐわないように見えた(筋肉でガッチリしているならまだ分かるが)。当時の実際のリーの写真を探してみたが、私が見つけた範囲でのリー本人は人気モデルだった頃の面影が残るどこかシュッとした佇まいで、細身とまでは言わないがそこまでガッチリしていない。
弁解すると、これはルッキズム的なものとは違う。デニーロ・アプローチ並にやれとまでは言わないが、ビジュアルでの役の表現も観る側にとっては大事な情報だ。途中でマリオン・コティヤールがきちんとげっそりした姿(元々痩せているからメイクでの演出だろうが)で出てきた時は、ビジュアルの「それっぽさ」に少し安堵した。
ウィンスレットの演技自体は素晴らしいし、そもそも本作は彼女が発起人となって作られたのだから、そういう意味では彼女が主役を張るのは自然なことだ。
ただ、戦場カメラマン時代からインタビュー(もとい息子の空想)までは3〜40年経過しているのだから、役者を分けてもよかったんじゃないかなあ、とは思う。申し訳ありません。
WWII through the Lens of a Fashion Photographer
The film Lee presents Lee Miller as a woman ahead of the curve. The city slicker Vogue photographer was one of the first women in Western society to walk into the battlefield in uniform. She faces resistance from fellow soldiers but also some unanticipated support. I wasn't aware of her famous photo in Hitler's bathtub on the day of his downfall, but is an interesting story. A historically accurate pairing to last year's war photographer doc, Civil War.
ウィンスレットだから描けたこと、描けなかったこと
本作を観ながら、共通点のある比較的最近の伝記(的)映画を2本思い浮かべていた。1本目は、浅野忠信主演で写真家・深瀬昌久の生涯を描いた「レイブンズ」。写真が人物や出来事などの一瞬を切り取って提示する作品形式だからこそ、作品から切り離された前後の文脈を補ってストーリーを構成する伝記映画と写真家の人生は相性がよいと改めて感じる。
もう1本はティモシー・シャラメが若き日のボブ・ディランに扮した「名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN」。長年にわたり活躍した才人の人生を要約して丸ごと見せるのではなく、(作り手にとって)最も重要と思われる一時代に焦点を絞って映画のストーリーを構成した点が共通する。
「リー・ミラー――ファッションモデル、写真家、従軍記者、雑誌記者、クラシックミュージック愛好家、一流料理家、旅行家。さまざまな世界を常に自由に生きた女。さまざまな顔を持ちながら常に自分自身であり続けた女」。リーの息子アントニー・ペンローズが著した伝記「リー・ミラー 自分を愛したヴィーナス」(松本淳訳・パルコ刊)の冒頭でそう紹介されている。リーが撮影した写真、そしてリー自身をとらえた写真を多数含むこの伝記本を原作としつつも、映画「リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界」が描くのは、1937年にリー(当時30歳頃)がフランスでローランド・ペンローズと出会ってからの約10年間。2人で移住したイギリスでヴォーグ英国版の写真家兼記者となり、第二次世界大戦が始まるとドイツ軍空襲下の英国人を撮影、さらに1941年の米国参戦後は米軍の従軍ジャーナリストとして欧州戦線を取材して終戦を迎えるまでの年月にほぼ絞られている。
この時代設定は、ケイト・ウィンスレットがプロデューサーとして本作の成立に大きな役割を担ったことも関係していると思われる。過去にもリー・ミラーの人生を映画化する企画は、息子で伝記著者でもあるアントニーに何度か持ち込まれたが、いずれも合意に至らず流れていたという。だがウィンスレット主演作の「エターナル・サンシャイン」で撮影監督を務めたエレン・クラスがウィンスレットに企画を提案し、ウィンスレットが製作兼主演、クラスが監督の座組でアントニー側に交渉した結果了承され、リーが遺した資料すべてにアクセスすることを許可されるほどの信頼を得た。ウィンスレットの知名度に加え、彼女が「タイタニック」や「愛を読むひと」など歴史大作で演じてきた女性像の印象もプラスに働いたろう。
そしてもう1つ重要なのが、リー・ミラーの容姿、特に後半生の外見が近年のウィンスレットにかなり似ていること。映画のキービジュアルでも使われている、ヒトラーのアパートの浴室で自身を同僚に撮影させた代表的な1枚などは、驚くほどの再現度だ。リーがファッションモデルから写真家にキャリアを移していった20代の頃は、残っている写真を見ると比較的痩身で顔もよりシャープな印象だが、30代以降は加齢のせいもあってか肉付きがよくなったように見える。
その点もおそらくは、ウィンスレットら製作チームがリーの30代以降をメインにした大きな理由の1つだったはずだ。もしも19歳でモデルとしてキャリアをスタートさせ22歳のときにアート写真家マン・レイの弟子兼恋人になり写真術を身につけていった時期も映画に含めるとしたら、撮影時46歳のウィンスレットが自ら演じるのは無理があっただろう。また、2時間程度の本編で若い時期まで描くなら、波乱万丈の数十年を駆け足で紹介するだけで深みに欠ける映画になりかねない。そうしたもろもろの判断から、従軍ジャーナリストとしての活躍をメインとする30代の約10年間を描くことに決めたのだと思われる。
カメラマンに限らずさまざまな職業で男女格差、女性差別が根強い時代、自らの才能とバイタリティで活路を見出し、男性ジャーナリストにも引けを取らない勇気と機動力で前線に赴きスクープを連発したリー。彼女の生き様を描くことは、今の時代にも女性をエンパワーするという点で、大いに意義と価値が認められる。また、「シビル・ウォー アメリカ最後の日」(2024年10月日本公開)でキルステン・ダンストが演じた戦場カメラマンのモデルとなった人物として紹介されることも多いリー・ミラーだが、この「リー・ミラー」が2023年秋に北米の映画祭で上映、24年9月には英米を含む主要国で劇場公開されていたことを考え合わせると、「シビル・ウォー」が日本でも公開週1位の大ヒットを記録したことが「リー・ミラー」の日本公開を後押しした可能性がある(逆に「シビル・ウォー」が不入りだったら、「リー・ミラー」も配信スルーになっていたかも)。
だが一方で、ウィンスレットら製作陣の判断で割愛されたリーの若き日々も、できることなら映像で描いてほしかったというのも偽らざる本音だ。リーが幼少期に経験しトラウマとなった出来事は映画の後半で触れられているが、アマチュア写真家だった父親から10代の頃にヌードモデルとして撮影されるなど、持って生まれた美しさゆえに性的搾取や性的虐待にさらされる理不尽さも経験した。だが彼女は自らの美貌を呪うことなく逆に武器として使い、モデルになって自分の世界を広げ、さらには写真家になって見られる側から見る側へと立場を変える。マン・レイに師事し、その頃にピカソやマックス・エルンスト、ジャン・コクトーといった芸術家らとの交流を通じて、芸術とは何か、美しさとは何かについて考えを深め、自らの表現を確立すべく励んだ。そうして培ったアーティストとしてのセンスがあるからこそ、彼女の報道写真がドラマやストーリーを感じさせ、現代の私たちが見ても心を動かされるのだろう。つまりは若き日々もまた描かれるべき魅力的な要素に満ちた年月だったはずで、ウィンスレット主演作であるがゆえに描かれなかった時期のリーも、将来のいつか、配信ドラマでもドキュメンタリーでも映像化されるといいなと、望み薄と思いつつ気長に待つことにする。
彼女が観たもの、感じたことを追体験する
ミラーという人物について伝記的、網羅的に描くという選択肢もあったはず。だが、企画を長年、大切に温めてきたケイト・ウィンスレットら製作陣は、ミラーが多くの芸術家たちを魅了したモデル時代を潔く切り捨て、その後、戦場写真家となって直面する言い知れぬ試練や心の動きにこそ肉薄する。意を決して乗り込んだ戦場で、彼女はどう駆け巡り、何を感じ、何を見たのか。それは同時に、我々が未曾有の世界大戦を「女性の視点」で目撃する、貴重な映像体験をもたらしてくれる。何より役柄に魂を注いだウィンスレットの「この人物について世界に伝えねば」という使命感が伝わるし、主人公が降伏後のドイツへ踏み入ってからの光景には息を呑むばかり。そこで撮影される歴史的な一枚。ミラーが何を思い、どんな意図があったのかをセリフではなく、ただ我々に”衝動”として突きつける。観賞後、彼女についてより深く知りたくなる、大きなきっかけをもたらす作品だ。
「リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界」モデルから従軍写真家へ転身した...
ヒトラーのバスタブに浸かった女性戦場カメラマン
リー・ミラーが歴史的写真の被写体として、
もっとも有名にした一枚の写真。
それは映画のジャケットにも映り込んでいる
「ヒトラーの浴室」で入浴しているリー・ミラーの写真です。
1945年4月30日~ヒトラーが自殺したその当日の撮影です。
この写真を撮影したのはコンビを組んで戦場カメラマンとして助け合っていた
デヴィッド・シャーマンがシャッターを押しましたから、
デヴィッド・シャーマンの写真であり、シャーマンの功績なのは当然ですが、
アイデアはリーが出した。
しかしながら、リーミラーが裸になり、お湯を張り、湯船に浸かり、
傍にあったヒトラーのポートレート写真の写りを良くするために、
写真枠からガラスを外して叩き割り、昔のカメラの解像度低さを
カバーして
「胸はうつしてはダメ!!」とポーズを決めた。
シャッターを押したのはデヴィッドだけれど殆どの功績は
【リーミラーのもんじゃ‼️】
そう思いますね。
リーミラーの人生は幼い日から、男性に搾取され続けた歴史でした。
7歳で仮住まいをしていた親戚の家で、家人の留守中に性被害を受けた
幼い日の傷。
カメラマンだった父親に10代の頃からヌード写真を撮られた傷。
ヴォーグのファッションモデルに飽き足らず、フランスに渡り、
当時大流行したシュールレアリズムの画家マン・レイの
弟子兼愛人兼モデルだったのに、
制作を手伝った作品の名義は全てマン・レイが独り占めした。
リー・ミラーは性的にも名誉的にも金銭的にも搾取され続けて来たのです。
フランスがナチスから解放された時。
★ナチスの将校の妻となったり愛人になった女性たちが、
槍玉に上がり、髪を切られて丸刈りにされる写真。
(リーの心には女たちへの同情があった筈です)
当時、ナチスがユダヤ人を大量にガス室に送り大量殺戮が行われていた事を
庶民たちは知りませんでした。
【どんどん消えていく人たちがいる】
そんな認識でした。
しかしリーはフランス国内にナチスが作ったアルザス地方の
ナッツヴァイラー強制収容所が解放された時、いち早く死体の山を
撮影しています。
そんなリーも戦後は夫のローランドの元に帰り、息子のアントニーを
出産します。
1947年のことでした。
それからの30年は表舞台から退き、良き妻・良き母として生きて行く
選択をしたようです。
母親の死後にアントニーが屋根裏部屋にある大量の写真を見つけるまでは。
女性として歴史に埋もれその功績を知られずにいたリー・ミラー。
その実像が明らかになる映画でした。
「シビル・ウォー アメリカ最後の日」で、キリステン・ダンストが
演じる戦場写真家のリーは彼女がモデルですね。
壮絶な人生
とにかくびっくりした。戦場カメラマンという人達の考えてる事が全然わからない。なぜあの人たちは命をはって、あんな危険な場所に自ら身を投じていくのか?確かに戦争の現実を記録に残す事が大切なのはわかる!彼女たちがした事の功績、誰にも出来ることじゃないし、立派な事だと思う。ただ、彼女たちは何に突き動かされているのか?全く理解できない。当時の時代の流れや現地の様子をリアルに描き出す。そしてこれは映画だ。実際はもっと壮絶だと思うと…現在の彼女が過去を語るような形のストーリーテリング。現在の彼女はなかなか話そうとしないし、とにかく口が重い。内容が内容なだけになかなかキツイ映画だった。途中消したり見るのやめたり出来ない映画館で鑑賞して良かった。気になる人は御自宅で鑑賞してみてください。
戦後80年だからか…
目を逸らしたいけど 出来なかった 〜 真実を切り取る
「 VOGUE 」トップモデルから報道写真家となり、「 VOGUE 」のヨーロッパ特派員として戦地に赴いた女性写真家リー・ミラーをケイト・ウィンスレットが熱演。
南フランスの友人宅で、後の夫となる美術家ローランド・ペンローズ( アレクサンダー・スカルスガルド )と出逢う。
戦地で行動を共にする米「 LIFE 」誌の従軍記者デイヴィッド・E・シャーマンをアンディ・サムバーグが、リーの伝記「 The Lives of Lee Miller 」の著者でもあるリーの愛息子アントニー・ペンローズをジョシュ・オコナーが演じる。
豪放磊落なリーが報道写真家となり、自らを奮い立たせ戦地に赴き、強制収容所の凄惨な人々の姿をカメラに収め続ける姿が痛ましい。
記事によると、主演のケイト・ウィンスレットが、ローランド・ペンローズの義妹の持ち物であった8人掛けのテーブルと出逢ったことが、本作制作のきっかけとなったらしい。
ー「 Believe it. 」
映画館での鑑賞
女性に観て欲しい作品
リー ミラー 彼女の瞳が映す世界
もの言う写真たち
インタビュアーがやけに偉そうで、なんだか変だと思っていたら、そういうことでしたか。
でも、もしかしたらあのインタビューは、母の死後、残された膨大な「母の仕事」を整理しながら、脳内で交わした母との対話だったのかも。
彼女は抑圧に対して敏感で、是正に向けて抑圧者(男社会)に噛みつき立ち向かう闘魂に満ちたひと。自己主張が強い、結構なエゴイスト。だが、親しい人や弱いもの(特に女性)への共感は強く、人類愛のような広い愛を示す、激しい人。
幼いころに性的虐待を受け、実の父親にヌード写真を撮られ続けたような、生い立ちが大きく影響しているのだろう。トラウマだらけだったと思う。
飛び抜けた美貌で周囲を魅力し、マン・レイのミューズとして名を知られても、思考や発言が尊重される訳でなく、男社会の徒花でしかない。
リーがトップモデルの座を捨て写真家に転身したのは、自己主張の場を求めたのではないか。
写真なら言葉は要らない。発言をマトモに聞いてもらい難い立場のものには、うってつけの意思表示媒体だ。
せっかく公認戦場カメラマンになれても、男社会の壁に阻まれ、現場には入れない。ならば、と誰も思いつかなかった後方の、従軍の女性達を撮ってみせる。彼女のスタイルは、戦争そのものというより、そこにいる「人」にフォーカスするもののようにみえるが、それはこの経験で確信を得たのでは。そして、人がいることで、見るひとに背景に広がるストーリーをも想像させることも、知ったかも。
解放直後の強制収容所の、貨車の死体とそれに遭遇した米兵の、一瞬の表情を切り取る。その場の空気も一緒に閉じ込めたようで、見る者は一目でその場を共有した気持ちになる。
ヒトラーの邸宅の豪華なバスタブで数週間分の汗と溜まった垢を落とす、パフォーマンス写真の時代性は無二のものだ。
そして、戦争の影で泣く女性達、ナチの協力者として引き出され丸坊主にされる若い女性、ナチ高官の父親に強要され自害させられた少女など、無知だったり立場が弱かったり、女性であるが故に翻弄されるしか無かった人達を、告発者のように撮り続ける。
そうやって撮った写真を没にされたら、それはキレるだろう。
告発が握りつぶされた、上げかけた声を押さえつけられた、幼いころからのトラウマが襲ってきて絶望感が増し、我を忘れるような激昂になったかも
ケイト・ウィンスレットがリーに思い入れたのはとても良く分かる。意思が強く、堂々として貫禄があるところはとても良かったが、もう少し本人に寄せられなかったか。
そういうのはケイトの美学に反するのかもだが、作中のケイトのリーは、30歳そこそこの若さの、元カリスマモデルには見えない。キルスティン・ダンストみたいなら違和感なしに受け入れられたのに。(有り体に言えばカラダ絞って欲しかった、俳優なんだから)
リーには、オードリーとデイヴィッドという二人の「戦友」がいる。
女性の、バイアスが掛かっていない対等で自然な戦友関係を描いた作品は初めて見た気がする。
デイヴィッドは、一目でユダヤ人と分かる。その彼が、嗚咽する。それを黙って抱きしめるリー、この二人の心の通じようが、実はこの映画で一番感動的で印象に残った場面だった。
彼女から見える真実を切り取りたい本能
冒頭、昼下がりの屋外のパーティの短い会話シーンから、
当時の不穏な時代状況、主人公リーのウィットに富んだ魅力的なキャラクター、
周囲の主な登場人物たちの性格、関係性をさらっと描き出す。
見事に要約された導入から物語に引き込まれる。
その後、戦争の時代に突入し、
とくに戦争に翻弄される一般市民をカメラに収めようとする主人公リーの姿を中心に、
実際の写真の撮影現場や前後の背景、経緯を肉付けする形で話が展開していく。
ケイトウィンスレットは意志の強い眼差し、がっしりした体格など
主人公のイメージにぴったりはまっていて、
使命感、意志だけでなく、本能に突き動かされて撮影を重ねていくような姿が印象的。
改めて想像を掻き立てる瞬間芸術としての写真の凄さも感じた。
アメリカ人だったから女性でも従軍できたというのも面白い事実。
報道写真家リー・ミラーの激動の生涯を演じたケイト・ウィンスレットが渾身のパフォーマンスを見せている。自ら製作も兼ねた意欲作だ。
戦場でカメラを構える動的なシーンもあるが、全体的には淡白に語りで進んでいくのが物足りない。
しかし、そこに描かれる彼女のヒステリックなまでの信念と情熱には感服する。
彼女自身の少女時代の出来事が、誰かにとっては見たくない事実であっても、誰かにとっては知られたくない事実であっても、何が起きているのかを世間に知らせなければならないという信念につながっていた。
そこも台詞で説明されるのだが、語るケイト・ウィンスレットと、聞き役のアンドレア・ライズボローの丁寧な演技が胸に訴えてくる。
年老いたリー・ミラーがジャーナリストのインタビューに応える形で語りはじめ、物語は回想録として展開していく。
このジャーナリストが誰だったのか、この語りは本当は誰によるものだったのか、映画の結末で言葉ではなく映像でそれを説明するところは見事だった。
リー・ミラー知らんかった
サブタイがダサい。
ミリタリに興味があり少しは人より知ってるつもりだったが彼女の事は知らなかった。当時のアメリカで前線に女性が行く事はかなり稀であるはずで、リーの経歴あってこその特例だと思う。作品の制作もやってるし、監督女性だしケイトウィンスレットもガチで演じ切ったのであろう、どのシーンも迫力説得力あった。
リーミラーの波瀾万丈の経歴の前半はぶっ飛ばし後半の戦場カメラマンとしてのキャリアにフォーカスした作品です。彼女が戦場で見た物と作品を順番に見せていく趣向で、戦場に取り憑かれていく過程を追っていめす。結構エグい描写、リアル彼女の撮った写真など多いから要注意、気がつくと私も口で息をしてた。PTSD(いや出版に関するストレスも大きいかも)に苦るしんだ晩年、最後の締めも気が利いていて、この辺が息子さんが持ってる映画化権の獲得に寄与した気もするな。
全127件中、1~20件目を表示