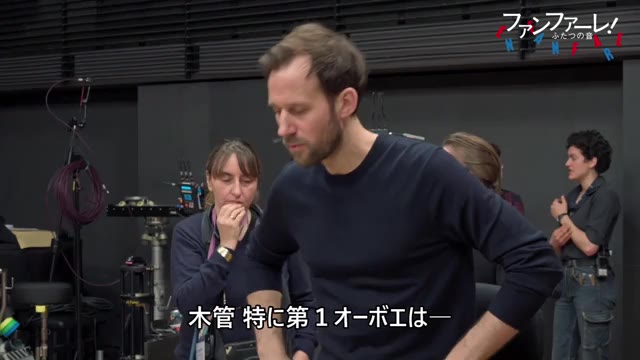「セ・ラ・ヴィ」ファンファーレ!ふたつの音 LukeRacewalkerさんの映画レビュー(感想・評価)
セ・ラ・ヴィ
お約束ですよね…
総じて辛口に言えばベタですよね…
泣かせに来てませんか…
映画・ドラマ擦れっ枯らしの「詰まんねえヤツ」としての内なる自分は、いっぱしの素人評論家みたいにポジショントークしようとする。
いや、ホントにそれでいいのか?ともう一人の内なる自分が首を傾げ、余韻の直感に素直に従えと言う。
それは、血を分けた兄弟でありながら異なった人生を歩んで永く離ればなれだったがために、再会してもこじらせまくったティボとジミーのようだな。
私は、そんな内なる二つの自分を和解させ、シンプルに統合させなければならない。
-----------------------
この映画の最も優れた美点は、脚本とともに、圧倒的に編集でしょう。
冗長な背景説明や経過を潔く削ぎ落としながら、それでいて鑑賞者の受容を妨げないスピード感とペーソスの深みを保っているのは、とてもクォリティが高いと感じた。
そして余計な「伏線」やら「回収」やらが無い。
優れた「物語」というのは、「ありふれた人生」、つまり「誰にでもある人生」という普遍性を、多様なエピソードでフィクションに変換して届けてくる。
この作品のエピソードとは、生き別れた兄弟が経済的にも文化的にも社会的地位でも真逆の育ち方をしたこと、その兄弟を結びつけたのは骨髄移植であること、そして弟も生来的に持っていた絶対音感という絆が判明すること、などだ。
それを田舎の炭鉱楽団の仲間たちが遠景で際立たせてくれる。
しかし、創作者のそのようなエピソード設定に惑わされてはいけない(決して惑わすつもりではないにしても)。
その普遍性たる「骨」は、こう言ってしまえば平板過ぎておもしろくも何ともないのだが、人生に勝ち組も負け組もない。希望と絶望、期待と失望が等しくやってくる。禍福は糾える縄の如し。
それが人生さ。
って、フランスが時折り見事にみせるまさにセ・ラ・ヴィだ。
だから、寿命の折り返し点はとっくに過ぎた小生のような年頃の人間には、やたらと「身につまされる」。
そう言えば、昨年末の『ネネ エトワールに憧れて』にも通ずる。主人公のアフリカ系の少女のほうではなく、才能あふれるその子を排除していくバレエ団の女性年配ディレクターのほうに深い哀しみがあった。
『クレオの夏休み』もそうだ。アフリカに帰った乳母を夏休みに訪ねたフランス人の幼児が主人公のようであって、実は乳母の哀しみが深く描かれていた。
昨今のフランス映画って、こんな感じなのでしょうか? 好ましいという意味で。
佳い映画を観た、という余韻に浸りながら席を立つことができたのは、幸福である。