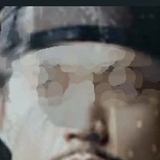長崎 閃光の影でのレビュー・感想・評価
全129件中、1~20件目を表示
彼女たちが捧げた青春と命を見て私たちにできること
原爆投下直後の長崎で、命を救おうと奔走していた日本赤十字社の看護師たちによる手記「閃光の影で-原爆被爆者救護赤十字看護婦の手記―」を原案に、当時看護学生だった少女たちの視点から原爆投下という悲劇を描いた作品。
映画のクオリティという点を見れば、とても粗が目立つ。
予算の少なさからか、2時間ドラマのようなCGや、作り物とわかるようなリアリティのないセット、様々な手記のエピソードを繋ぎ合わせたからか、とっ散らかった印象のある脚本。
正直先週公開となった戦争映画の「木の上の軍隊」を先に見ているだけに、どうしても比べてしまう。
しかし、戦後80年経った今、当時10歳だった人も今では90歳。この先いつか訪れる、戦争経験者がいない世の中になったとき、代わりに語ってくれるような映像作品はたくさんあるに越したことはないと思う。
どうしても原爆といったら広島の方が大きく捉えられがちになってしまうが、あと1週間降伏が早ければ多くの命が助かったと思わずにはいられない、長崎の原爆に対してのやり場のない気持ちに胸が締め付けられる。
なぜもっと早く降伏できなかったのか。
なぜこれほどまで国民の命を犠牲にする道を突き進んでしまったのか。
彼女たちが捧げた青春や命の分、現代の私たちはこの「なぜ」を考え続けなければいけないと思った。
不安、痛み、勇気、献身。被爆者を救護した彼女らの魂が80年後の私たちに届く
少ない予算ながら、高く尊い志が伝わる力作だ。
被爆直後の長崎で救護にあたった女性たちの証言をまとめた「閃光の影で 原爆被爆者救護 赤十字看護婦の手記」を原案とし、やはり長崎の被爆を題材にした劇映画「TOMORROW 明日」(1988年)の製作を担った鍋島壽夫、長崎出身の被爆三世である松本准平が監督と共同脚本、さらに保木本佳子も脚本に参加。看護学生3人の視点で、原子爆弾が投下され爆発した瞬間の衝撃や、直後の状況、次々に運び込まれる重傷者たちの救護に献身する姿を描き出す。
愛国少女的なアツ子(小野花梨)、カトリック信者のミサヲ(川床明日香)、純朴なスミ(菊池日菜子)という具合に、主要キャラクター3人の背景や言動の傾向に差異を出すことで、限られた本編尺の中でさまざまな視点からのエピソードのバリエーションが生まれている。証言のすべての要素を盛り込むことは不可能で、取捨選択は当然ながら、たとえば敗戦後も民間人を見下して威張り散らす軍人に言い返したり、助けを求める朝鮮出身者を拒絶したりといった短い描写に、美談にするのではなくネガティブな面も避けずに語り継ぐ姿勢がうかがえるのもいい。
まだ原爆そのものが一般に知られていない時代、誰も経験したことのない市街の壊滅と膨大な死傷者に直面した彼女たち。恐怖や不安、痛みと喪失を抱えながらも、懸命に勇気を振り絞って救護にあたる姿、その心持ち、魂が80年の時を経て私たち観客に確かに伝わってくる。とくに若い世代に届くといいなと願う。
不穏さを増すこの現代世界に伝えるべき記憶
80年前の記憶を伝える本作は、言うなれば正解のない映画だ。あの日の惨状をどれだけ詳述しても十分過ぎることはなく、かと言って、それだけに留まると観客の胸に届くべきドラマ性が薄まってしまう。おそらく題材を掘り下げれば掘り下げるほど描くべき要素は増えるばかりで、何をどう削ぎ落として作品を紡ぎ上げるかは葛藤の連続だったに違いない。その末に生まれた、3人の新米看護師を視座に据えた物語構造を私は評価したい。10代の少女にとって現実は過酷だ。あの日あの時、彼女らは何を見て、何を感じたのか。私の祖母も当時ほぼ同齢だったことに鑑賞中ふと気づき、胸に込み上げるものがあった。また、本作は惨状を描くだけでない。生き残った者が明日を生きようとする。そうやってこの広い空を繋いでいく映画でもあるのだと感じた。日々、不確実性を増す世界で、本作が心と理性の防波堤となって、人々に何かを感じるきっかけをもたし続けることを願う。
不幸も平等では無い
哲学のマイケル・サンデル教授の本「実力も運のうち 能力主義は正義か?」(ハヤカワ文庫)をゆっくり読んでいるのですが、中に気になる記述がありました。
キリスト教世界で摂理主義に基づくと、自然災害やテロリズム(欧米社会で異教徒が加えたもの)による被害ですら、神が人間に与えた懲罰であると考える向きもあるそうです。
主人公と友達ふたりは、いずれも長崎で原子爆弾の爆発に巻き込まれましたが、自身や家族の被害の重さは大きく異なるものになりました。
主人公の友達のうちひとりは、運の良し悪しでは片付けられない被害の不公平さ、不条理を訴え、自身が長崎の地でキリスト教徒でありながら、神の加護が無いことに憤ります。
このあたりはやり切れない思いが残りました。
長崎、広島の原爆は歴史の一部になりましたが、被害を受けた方たちの想いを、これからもそれぞれ受け止めていかなければならないのでしょうね。
水崎綾女さんが難しい役どころで魅力的でした。
ん〜…(これ↓)?…嫉暴露(ネタバレ)?????…。
前評判と違い、むっちゃよかった
映画の意味は?
内容は舞台劇レベル。原作が複数の人の話をまとめたモノなのでちょっとバラバラ感があった。映画のうれしさが無かった。一つ気になったのは原作にもない朝鮮人迫害のシーンがあるのだが事実ではないとエンドテロップで入るのは意味が解らない。だったら最初から入れたらあかんでしょ。
バチカンで10月上映予定。バチカンからの「核の脅威」の世界発信の一助になれば幸いです。
・長崎原爆投下直後から、看護活動に従事した若い看護学生3名の1か月間の物語。
・命を救うはずが、被曝により「見取り」となってしまう患者がどんどん増えていくなか、それにもめげず懸命に看護する姿を丁寧に描いています。
・「はだしのゲン」のように目を覆いたくなるような被害者の状況を描くのではなく、抑えめに描いており、若い方や高齢の方まで見やすいように配慮・工夫がされています。
・予算の制約上、被爆地の描き方を高度なCGを多用するような描き方は出来ませんが、それでも「原爆の悲劇」を伝えたいという製作サイドの心意気はスクリーンから感じ取れます。
・「被団協」がノーベル平和賞を受賞するなど、核抑止の必要性が叫ばれる中で、逆にロシアが戦争に「核を用いる」可能性をほのめかすなど、核の脅威はますます高まっています。
・被爆地にある「浦上カトリック教会」(浦上天主堂)の建物が爆風で吹き飛ばされ、その様子に呆然とするカトリック信者の様子も描かれており、本作は10月にバチカンで上映される予定となっています。
・日頃、世界平和を唱える「バチカン」でも、この映画を実際に観ることにより、改めて「核の脅威」について世界発信する一助になれば幸いに存じます。
一本の映画として本当にいい映画だった。
とても誠実な映画だった。
起こったこと、その中にいた人たちをそのまま、余さずに映画に刻みつけるのだという気概を感じた。
それだけに、見ている間は辛かったけど。
ああ、こんなことどうか起きませんように、と願うようなことが、次から次に起こる。
家族は真っ黒になって死に、恋人や同僚は正体不明の病に冒されて死ぬ。
あの爆弾のおぞましさをあらためて思った。
当たり前だがスクリーンに映されているような事態が、何万通りも起きていたのだ。実際に。
これは既に起こった事実なのだから。
年齢を重ねるにつれて、映画や資料映像とかで原爆の投下シーンを見ることが、本当に怖くなってきた。
その向こうで生きていた人々の営みが、日々本当にそれぞれ大変で、それぞれに意味のあるものであったということが、実感としてわかってきたからかと思う。
そしてそれを無惨に蹂躙する戦争行為が、何某かの理屈や事情を盾に、人間が意図してやるものなんだだということも。
この映画でも投下前のシーンがあったけど、ああ、止まってくれ、誰か止めて、と思ってしまう。
あと一週間で戦争は終わるのに。
人間がやってることなんだから、止まる道筋はあったはずなのだ。
「あと一週間早かったらみんな生きとったのに」ってセリフにもあったけど、終戦まで広島からは10日、長崎からは一週間もたっていなかったんだとあらためて思った。
何十万人が死に、突然戦争が終わり、一週間前に落ちた爆弾にやられて地獄のようになった街が残る。
一体何なのだろう、これは。
よく戦争を二度と繰り返さないように、とか、そのために記憶を語り継ぐ、とか言うけど、それはほんとに、お為ごかしや綺麗事ではなしに、ほんとに絶対的に必要なことなのだ。
それを確かな実感をもって、思い出させてくれる映画だった。
ただ、そういう、感じるメッセージとかではなしに、単純に映画としても掛け値なしに素晴らしい映画だったというのは、声を大にして言いたい。
臨場感のあるセット、美しい映像、俳優陣の誠実で確かな演技とそれを引き出す演出。
今年見るべき一本の映画があるとしたらこれだったんだと思った。
もう上映終わり間際だと思うけど、自分はこれ映画館で見れてにほんとに良かったです。
「死んでもいいから水を一杯くれ」
原爆の憎さ
助けても助けても死んでいく… そんな中で生きるとは…
タイトルなし(ネタバレ)
昭和20年8月の長崎。
日本赤十字社の看護学校に通う女子学生3人は、故郷長崎に戻っていた。
3人とは、田中スミ(菊池日菜子)、大野アツ子(小野花梨)、岩永ミサヲ(川床明日香)。
スミには、造船所で働く勝(田中偉登)という幼馴染の恋人がいた。
そんな勝にも召集令状が届いた。
9日、長崎の空が閃光に包まれた。
原爆である。
スミ、アツ子、ミサヲの3人もそれぞれ看護婦として被爆者の看護にあたるが、現場は壮烈なものだった・・・
といったところからはじまる物語。
終戦80年ということで今年は戦争ものをよく観ている。
原爆投下直前から描かれる長崎。
3人の看護学生を通して描かれる戦争の悲惨さと不条理さ。
心が痛む描写も多々あり、不条理さに対する怒りも深く描かれている。
正直、観る前は「綺麗事として描かれているとイヤだなぁ」という危惧はあった。
が、そんなことはなかった。
「力作」かつ、既に「名作」の雰囲気すら感じました。
主役3人、いずれも好演。
ここで描かれる彼女たちは、犠牲者でありながらも献身する。
英雄といえる。
戦後のわが国の礎・・・
しかし、そんな英雄を生み出す必要など、戦争がなければ、生み出す必要などないのだ。
忌避すべきもの。
そんな戦争に対する怒りが本作には詰まっています。
一見の価値あり
戦後80年にふさわしい作品
戦後80年は若い世代に語り継ぐ最後の年代と言われています。その中にあって、赤十字の救護に当たられた方たちの生の声を集められ、作品に仕立てられたことに本当に敬意を表します。お金さえあれは欲しいものが手に入る、ますます物質的に豊富になっていくいま、この時代の大変さが身につまされます。
若い俳優の皆さんの熱演に感謝。
アメリカの2つの大罪
戦争末期、戦後の日本の社会背景や国民の気持ちがよく分かる。「原爆は地獄だ」アメリカが憎くて憎くて仕様がない。英語を勉強したい、アメリカの本を読みたい、なんて絶対に言えない。そんな空気がこの国にあったのだ。僕は大学で英米文学を学んだ。でもこの映画をみたら英米文学を学んだこと、これから学ぶことに罪悪感を持ってしまう。もし出来ることなら戦争の記憶を忘れてしまいたい。もちろんそうすべきではないことは承知だが、そう思わずにはいられない。
アメリカには2つの大罪があります。1つは広島に原爆を落としたこと。もう1つは長崎に原爆を落としたことだ。たとえ日本の侵略戦争だったとしても、その2つの過ちは消えません。
この先、永遠に原爆が使われないように祈ります。
80年前に終わった戦争のことを忘れないで。戦後を戦前にしないためにも覚えていて。当時を生きた人たちからの、そんなメッセージが込められた作品です。
毎年八月の風物詩。・_・
夏祭。七夕。打ち上げ花火。
お盆。日航機墜落。終戦の日。
原爆。ヒロシマ。そしてナガサキ。
この時期、戦争を描いた作品の上映が増えます。
今年も何本か、当時を振り返る作品がありました。
その中の一本としてこの作品を鑑賞することに。
重い内容なのかなぁ …と身構えながら
鑑賞開始。
実際に看護に従事した看護婦たちの声を集めた「閃光の影で」と
いう資料を元にしているそうです。
その混乱の中で、原爆が落ちた日に爆心地付近に居合わせた看護
学生の少女3人の行動を中心に、どんなことが起きていたのかを
描いた、ドキュメンタリーに基づいて後世されたとの事なのです
が、所々に創作を埋め込んだノン・フィクション風の作品なのか
な との印象を持ちました。
少女役3名の演技(セリフ・行動)を中心に捉えて観ていたので
すが(それはまあ、当然のことですが)、違和感を感じてしまった
箇所もそれなりにあった気が、しなくもないです… ・_・;
けれども
実際にその場で行動した方々の記憶と記録を元にしている という
その一点において、この作品が世に出た意味・意義は大きい。
そう思わずにはいられません。
80年前の戦争の記憶。戦争があったという事実。
それを風化させないためにも、後世に残すべき作品かと思います。
鑑賞して良かった。…とは思います。
見た方が良いか尋ねられたら、是非一度は、とお薦めします。
(二度観たいかと問われると、うーん …というのも本音)
※ 不意打ち気味に、グロい場面や血の気が引く場面が出てきます。
ガーゼ交換とか麻酔注射直後に足を●●…とか …@▲@~;;
その手のシーンの耐性が低い方はご注意くださいませ。(自分だ)
◇
■不自然に感じた場面
セリフによる会話に、真実味に欠けると感じる部分がありました。
瓦礫の下で父を見つけた少女が、やたら「大丈夫?」と声をかけて
助け出そうとする場面なのですが…
※どうにも 創作感を感じてしまいました。
そのセリフを含んだ箇所の演技も、ぎこちなく感じられ
不自然さが拭えない感じがしました。
記録されているセリフがそうなのか?と
最初は思っていたのですが、鑑賞後しばらくして思ったのは
# 当時の記録とはいえ、記録にそこまでのセリフまでは
残ってはいないのでは? #
ということ。
# そういった場面でのセリフはライターによる創作では? #
ということ。
そこに思い至り、なんとなく納得した次第です。
「人が 呆然とした」時、意味のある言葉は口をついて出ず
「 言葉を失う」状態になるような そんな気がしました。
■リアルに感じた場面
一方で、人力車を引く場面での3人娘の会話のシーン。
この部分にはリアルさを感じました。
それぞれが、相手の勝手な(と思える)行動を非難します。
ついにはこんなセリフまで。
「神はこの爆弾を落とした相手の事も許すの?」
信じていたことは、所詮は綺麗事なのだろうか。 と
理想と本音が混じり合った本心のぶつけ合いの場面。
だからこそリアルに感じられた場面です。
※ 今起きている戦争・紛争の当事者に対する問いかけ
にもなっているように感じます。
人類に与えられた永遠のテーマなのかもしれません
◇最後に
今年は戦後80年。
戦争を体験した世代もどんどん少なくなってます。
戦争がどれだけの物を破壊したのか
記憶の彼方に埋もれさせてしまわないように と
この時期に振り返ることには、意味があると改めて思います。
「戦後」が続きますように。
「戦前」になりませんように。
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
涙ぐんでしまいました…
ぼんやりと受身で鑑賞してはいけない作品。
頭をフル回転させて、想像力を働かせながら鑑賞しなければならない作品である。
抑えた映像と演出が心に刺さるのである。
原爆の悲惨さは筆舌に尽くせないこととは思う。でも、はだしのゲンのような、作者の気持ちが入りすぎた、過剰な演出や表現は、逆にこころがひいてしまう。
わたしの祖母、母はいわゆる戦争体験者であるが、その体験談は意外に地味なものである。それは、自分が見たもの体験したものがすべてであるからだろう。当時に戦争被害の全体を知るすべはないし、本当の悲惨さを経験した人びとは、命を落とされた方々だろう。だから、その後の情報で、自分の体験を脚色することなどはできないのである。それが同じ時代を生き、そして命を落とした人びとへの鎮魂であると思う。
この作品は、祖母や母の体験談を聞いているような感じがするのである。
未熟な見習看護婦に、ヒーロー的な活躍もできるはずもなく、自分の無力さに揺れる心が痛々しい。
戦後80年過ぎても、戦争体験者の話というのを聞く。本当だろうかと思ってしまうのは余りに不謹慎なのだろうか?
祖母は20年以上前に他界、母は85を過ぎ、静かな余生をおくっている。
たった80年前の真実
たった80年前の事。自分は戦争を知らない。けど両親、祖父母、知人から生々しい体験は聞けた。
後何十年かすればこの戦争も、関ヶ原等の様に歴史の中に埋もれて、物語になるのだろうか?
観てる間、そんな事を考えていた。
きれいな映画館で、良い環境で。片手にドリンク、自由に飲める。
そんな自分に少し罪悪感を抱く。
原作は当時の看護師達の手記を纏めた本。その為、映画も散文的で、出来がいいとは言えない。
また、予算がなかったのだろう、CGやセットはショボい。
戦時中にしてはみな綺麗すぎるし、特に野戦病院での彼女らの日々、汚れていく感じは表現されていない。
悔しかったろうな。予算さえあれば…そう思っただろう。
そこは批判しても仕方ない。
そして戦後80年目の夏。
「鬼滅の刃」がスクリーンを席巻している為、この映画は朝7時台の、誰が見るんだという、ひじょうに鑑賞しにくい上映時間に追いやられている。それが現実。
しかし、それで良いのか!?
興行側には、今、見せなくてはいけない映画を観てもらうようにしなくてはいけないのではないのか!?
この夏に!
シネコンはすごく見易すく、綺麗で便利な環境を作った。しかし、大切な物を無くしてないか!?
そして、それは自分自身にも言えるのではないか⁉️
#長崎閃光の後で
全129件中、1~20件目を表示