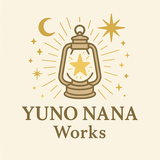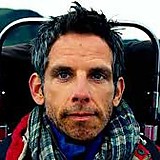8番出口のレビュー・感想・評価
全1070件中、1~20件目を表示
相手は小松菜奈さんで間違いないですか?
日本ではトップクラスのヒットプロデューサーである川村元気氏と、これまた才能あふれる脚本家平瀬謙太朗氏が仕掛けた「ヒット」間違いなしの企画からの映画。初日から長蛇の列のがあったとの報告と受け、実際公開3日間で興収9.5億円を突破、2025年公開の実写映画で1位を獲得。
原作ゲームはやったことはなく、本作の「説明がしっかりされている」らしいノベライズも手にすることなく、「ヒット」しているということだけだと、全く興味のないタイプの作品だが、割とうるさ型の有名評論家、youtuberが絶賛している。
ゲームの世界観とそこに迷い込んだ男の人生の「選択と決意、父になる」の物語らしく、ノベライズもはっきり言語化しているらしい。
8番出口
・
・
・
主人公二宮はオープニングで、スマホで戦争か災害のニュースをザザっとスワイプし、ちゃんと読んでるのか、ふりをしているのか、よくある車両入り口に陣取る。
直接経験したことはないが、サラリーマン退勤時のラッシュアワーの地下鉄に、乳児を抱いた母親が乗っており、赤子がギャンギャン泣く。それをうるさいから何とかしろと母親にキレまくるサラリーマン。あるかもしれない、あった話も聞くこのシチュエーション。残念?ながらこのシチュエーションにオレ自身はあまりリアルを感じない。
想定通り何か行動を起こせるはずもなく、というか、起こす必要がない二宮は電車を降り、その後別れた彼女から「電話」がかかる。二宮は、(過去のことは分からないが、)電話の画面に見える(超美人の)小松菜奈と別れており、明らかにうだつが上がらない二宮にどうしようかと相談するのである。そうして彼は「8番出口」の世界に迷い込む流れ。
8番出口の異変については、彼の小松菜奈からの相談をどう受け止めるか、の選択および決意と全く関係のない異変ばかり。ゲームのことは知らないで話を進めるが、そこに登場するオジサンの一幕は全く二宮の脱出劇には関係がない。とこの辺はゲームファンへのサービスなのだろうということで納得はしている。
だが、彼が脱出し、「病院へすぐ行く」と言って乗った電車は、物語最初と同じ電車、シチュエーションなのである。そこで彼は、オレたち観客の方を見据え、その騒ぎの方へ顔を向けて閉幕する。「騒ぎの方へ顔を向けて」なので、二宮がその騒ぎに対して「父親になるには良しとする行動」に出た、という解釈が強いようだが、果たしてそんな行動は存在するだろうか。
この映画は、初めから二宮の妄想で、不快とされる「赤子のギャン泣き」と「他人の止まない咳」を浴びせて、やかましい音響とともに、こちらの神経を触って観客を試す。赤子と喘息といった当人にはどうしようもないことを、観客のオレたちにはことごとく不快に感じさせる確信犯。これはなかなかに上手いと思った。
また本当に小松菜奈(のような女性)に子供ができたのなら、こんな話にはならないだろ、という突っ込みも作り手側には十分承知の上だと思う。
となると、そもそも子供ができたというのが、妄想。あるいは、相手は「小松菜奈」であるはずがない。
そして同じ電車(シチュエーション)に戻った、ということは、彼は映画のはじめから勝手に妄想し、結局答えを出せずにループしている。つまり騒ぎのほうを向いたが、そのまま電車を降りた、というほうが正しく観える。初めから何も起こっていないということ。(消えたカバン、収まった咳、「ボレロ」で挟む)
つまり、登場人物はすべて主人公の持っている顔、一面。電車でキレる男ですら、主人公の顔と思ってもいいかもしれない。
今回の「不快」の演出および演技が確信犯であること。クリアしたかに見えてそうではない、という解釈も可能である点。ヒットメイカーだけど、浅い、と言われてきた川村氏の一撃。それがこの違和感、異変探しのゲームと「合っている」と思わせた点がとても素晴らしい。観客を試す、といった実験もそれなりに成果があったようだ。
そして、「意を決した」とも「また逃げた」「そもそも現実に向き合っていない」ともとれる、二宮氏の風貌(と役作り)が素晴らしい。
だけど、オレ個人はすっごい長い90分だったので、この評価。
追記
このポスター、実は二宮氏の鼻先口先のほんの少しだけ8の字から出ているんだよね。ちょっとだけ、ループから抜けている、すこしだけ「前に出る」ということなんだろうけど。
オジさんGJ!
いや、オジさんが素晴らしい。聴くところ、演じたのはベテランの舞台俳優さんみたい。私が言うことじゃないけど、よくぞご出演いただきました。不気味で鉄壁の演技力、ありがとうございます。
ゲームの映画化と云うことで、非常に限られた世界観ではあるものの、その再現度が素晴らしい。そもそも、元のゲームが素晴らしかった。実写にしか見えない映像感覚で(オジさんは流石にCG感は拭えない)続編の8番乗り場のリアリズムも、もはや異常。開発者さんはその手の専門家なんでしょうか。
映画化のテーマとしては「心の迷いが生んだ時空の歪み」→「迷いから決断する勇気」ということでしょうか。「満員電車で泣く子供」「キレた他人から怒鳴られる」「それを助ける勇気が無かった」「彼女から身ごもったとの電話」「迷ってる。どうしようか決められない(泣」、そして主人公は地下に迷う。この流れ、設定付けからゲームの舞台に突入するまで、淀みなく素晴らしい。
そして進むか戻るか、このシンプルで純粋にプレイヤーの判断力が試されるゲーム性、そして決断する力は「勇気」、見知らぬ人でも助ける「勇気」、ゲーム性と主人公の設定を重ね合わせた、「ゲームの映画化」としては予測を超えて「甘さ」「脳天気さ」もない渋くて好印象だと感じました。
細かいことを云えば、「観に来た人はみんなゲームをプレイ済みでしょう?」という感じが拭いされない。プレイヤーが間違い探しに入るのが早すぎる気がする。「異変の有無」と云われて、指さし確認で間違いを探すのは、ゲームプレイの再現に入るのがちょっと早い気がした。そして迷いだしたら、まずスマホを取り出すと思う。地下で何も判らなくとも、チラ見ぐらいするのが現代人。
また、オジさんに設定付けされたのには驚いた。成る程、元はオジさんもプレイヤーで闇堕ちしたという設定ですか。元のゲームでは8番じゃない出口から出ると単なるリスタートだけど、NPCに墜とされるのは映画ならではの面白いアイデア。あの女性が歩いてくるバージョンも遊んで見たいな。自分が一通りプレイしてからも、映画化を記念してでしょうか。いくつか異変が増えていたので、女性の方もお願いします。
あと、(説明はなかったけど、ミスリードではないと思いますが)自分の未来の子供の出現も面白い。異空間での現象なら有りかと思う。ただ、最後にあの子とはぐれて、なにか思ったりしなかったのでしょうか。何か一言あるべきだったでしょうか。それとも自分の未来の子供と判ったから、もう振り返る必要はなかったのか。
結論的に自分の迷いと迷宮のサスペンスを重ねた良作だと思います。「見つけてほしいから迷子になった」「道に迷う→心の迷い」「結論を出す勇気が出せず、自分から道に迷っている」等々、迷いに関する哲学めいたものがあるような気がして実に有意義だったかと。
あと、付け加えるなら、如何に映画の中の話といえど、あんなに可愛い彼女がいるんだから、二宮さんには頑張って欲しいものです。
(追記)
付け加えで、映画版固有の異変で興味深いものが幾つか。
「電話をかけてきた自分の彼女(同じ地下道にいた)」
「通路のど真ん中で待ち構えている少年の母親」
「開いた扉の向こうで見て見ぬふりをする自分自身」
これら自分自身や自分の味方のようで、「異変」という自分の「敵」なんですよね。自分の大切なものやトラウマが自分を惑わし襲ってくる自分自身にしか通用しない罠。
似たようなエピソードが他の映画にもあったのを思い出しました。うろ覚えですが、攻殻機動隊シリーズ劇場版「イノセンス」で、手榴弾に殺されかけたトグサが「自分の妻と娘の姿が脳裏に浮かんだ」というと、バドー「気を付けな、そいつらは死神だ」という――ちょっと理屈が掴みかねますが。その他、グインサーガという小説では主人公グインのトラウマとなる人物が自分を責め立てる、自分の心を鏡映しにした罠。
小説にして映画化もされている「1984」では、これは具体的な調査の上での拷問でしょう。どうやって調べたのか自分だけが苦手なネズミで根を上げさせたり。
「鬼滅の刃」などでも最終的には自分のトラウマと対峙することはよくありますが、故意に仕掛けられる場合もあれば、見るもの触れるもの全て自分のトラウマを連想し恐怖する場合も有り、前述3つの異変を説明するとしたら、そういうことかもしれません。よくある言い回し、「自分との戦い」と言ってしまうと、ちょっとチープになっちゃうんですけどね。
映画に何を求めるかで評価が変わりそう
元のストーリーがあるわけではない単調なゲームから、よくここまでストーリーを作りあげ、映画的なエンタメ性を組み込んだなと、監督の発想力がすごいと思った。
始終不気味な雰囲気を視覚的にも聴覚的にも感じさせ、地下鉄通路という閉塞感と、主人公が喘息もちという設定からの息苦しさで、見ているこちら側も呼吸が浅くなり息苦しさを感じる。この没入感はとてもおもしろい。
しかし映画が進むにつれて、主人公はどんどん焦ってパニックになったり、無気力になったりしていくのに対して、見ている自分はどんどんハラハラ感が薄まり、息苦しさも無くなり、むしろ変わらない環境に慣れてしまい冷静になっていってしまった。なんなら、わかりやすい異変なのにも関わらず、鈍感に動く主人公たちにモヤモヤしてしまった。
メッセージ性もわかる。主人公の人生の迷いを無限の地下鉄通路と合わさっているのもわかる。
しかし私は主人公の悩みがどうも個人的に共感ができなかった。共感できる人も多いとは思うけど、あの彼女との短い電話のやりとりだけでは、主人公の悩みや葛藤に寄り添って見ることができなかった。なんだかすごく男性的な視点だなと感じてしまった。
全体的にシチュエーションパニックに少し繊細さとドラマチックさをを入れましたみたいな感じなのだが、なんとなく日本より海外の方がウケが良さそうな作品だと思う。
ゲームが人気なこともあり、小さな子供たちも何人も見にきていたけれど、一応ジャンルはホラーなので、大きな音や、驚かしてくる系が苦手な方、途中津波の描写もあるので津波にトラウマがある方は注意が必要。
また冒頭は主人公の視界で進むので、三半規管が弱い人は見ていて多少酔ってしまうかも。
ゲームから広げた世界観という点は大変興味深くおもしろいと思ったけれど、ゲームからということがなかったら映画的には面白かったかと考えると今ひとつという、評価がなかなか難しい作品だった。
日常に潜む“異常”を歩く。心理を抉る90分🎬
見慣れた街の風景に、ひとつだけ違う“何か”がある。その違和感は、歩を進めるほどに膨らみ、やがて世界そのものが崩れ始める。
本作品は派手な恐怖ではなく、心理をえぐる静かな狂気に満ちている。まるで都市伝説のような不気味さに、最後まで目が離せない。
SNSで広がった“間違い探し”の感覚が、ここまで映画的に仕上がるとは正直驚き🧐
最後には、登場人物が逃れられない状況に追い込まれるシーンで息が詰まる😱
伏線の配置と不安の演出が見事としか言いようがない👏
いやはや、川村元気作品は、受け取る側に“人生観や人間心理への覚悟”を少し要求してくるのも面白い🤫
音響、カメラワーク、エンドロールまで、違和感に満ちた徹底ぶりも是非お見逃しなく。
見応えのある一本を、是非映画館で♪
深呼吸をお忘れなくね🤫
明るい画面のホラー
明るいホラー映画だった。アリ・アスター監督の『ミッドサマー』も明るいホラー映画だったことを思い出した。あれは、青空の太陽の下で異様な奇祭が繰り広げられる内容だったが、こちらは明るいLEDライトの下で心理の迷宮に迷い込む作品として作られている。(主要なレファレンスになっているであろうキューブリックの『シャイニング』もその名の通り明るいホラーだった)
舞台となる地下通路のセットも綺麗だ。不自然なほどに。使用感がないというか、開通してまもない地下通路のようだ。
典型的なホラー映画なら、セットをもっと汚しをいれて、古ぼけた感じを出して、電球も切れかかってたりして、恐ろしい雰囲気を出そうとするパターンが多いけど、本作の作り方はその真逆。しかし、くっきりと何もかも見えているはずなのに、出口は一向に見えてこないことの恐怖がある。異変探しに観客を参加させるために明るいという理由もあるだろう(原作ゲームも明るいし)。
キャラクターの匿名性も作品の面白さに一役買っている。固有の名前を持たない本作のキャラクター、必要以上に描かれないバックグラウンド、その方が現代の観客が自分を投影しやすいと考えたかもしれない。
原作の雰囲気そのままに、分かりきらない不安感が良い
原作ファンとしては、「人気になったから映画化したのか」「これをどう映像化できるのか」と正直、期待値はあまり高くありませんでした。
ですが、原作の雰囲気をそのまま残したまま、オリジナリティもしっかり含まれていて、面白い作品でした。
冒頭の1人称視点で主人公の視覚・聴覚を共有する演出で一気に物語に引き込まれました。原作も1人称視点なので、繋がるものを感じました。
(イヤホンをつけたら環境音が音楽に切り替わったところが面白かったです。)
「異変」は原作と同じものももちろんあって、見つける楽しみもありましたし、映画オリジナルのものもあって、角を曲がるたびに新鮮な気持ちで見れました。
まさかおじさん視点もあると思わず、予想外の展開に「そうきたか」と驚きました!
ルールを破ったおじさんの末路が……なんともゾワッとしましたね。まるで、この世界のシステムに組み込まれ、ただの歯車と化したような……
(直前で人間らしく感情的になる描写があったので、余計に「差」に恐怖を感じました)
しかも、原作と同じ「異変」なのでソレが駄目なのもすぐ観客がわかるのも良いなと思いました。
結末はどうなるのかと思っていたら、「えっ、ここで終わり!?」ってところで終わりました。「答え合わせは!?」とスッキリしない感じで終わりましたが、想像の余地があって「これはこれでいいか。原作も結末があるわけではないし」とわからないまま終わるのも原作に対してリスペクトを感じて、私は好きでした。
登場人物に名前がないのも好感度高かったです。
おもしろかったよ!
少し解釈違い。クオリティは高い
演技はとても良かった。(特に迷う男の二宮さん、歩く男の河内さん)
ただジャンプスケアのような、音を使ったびっくり演出が多く、原作ゲームをプレイした時に感じた怖さ、(じっとりと潜むような恐怖)と映画の解釈が合わないと感じてしまいました。ここは個人の感覚ですが…。
原作にストーリーがほとんどない中、映画化できたのは凄いと思いました。
生きている空間
8番出口自体、ゲームが気になっているくらいで実況動画や実際にプレイなどはしていませんが、私の映画的価値観が合う方のレビュー動画を見て、公開から少し経った頃に見ることにしました
その方いわく、ファン映画的な部分があるため必ず実況動画や実際にプレイをしてから行くべき、実況動画やプレイが気にいればきっとハマるとのことで有名YouTuberの実況動画をみてなかなか面白そうなゲームだと思ったので少し期待値高めに設定して見ましたが、結果的にやはりプレイ映像を見ていてよかったと心の底から思います。
長尺で回す撮影手法で終わりないループを演出するのはなかなか考えられていて見ごたえがありました
二宮さんの実際に8番出口に迷い込んだときの緊迫感と喘息による閉塞感。喘息の友人がいるのですが発作がそのまま当事者のようでとてもドキドキしました
ビックリ要素はあるにはありますがわかりやすいですし、少ないです。少し身構えるくらいで十分です
人間的なストーリーは最低限。
でもそれが8番出口の異界感を生み出す絶妙な加減で素晴らしかった
ゲーム勢からするとびっくりなおじさんの正体と設定もあって原作知っている人でも8番出口を映画の1つの作品として記憶に残していくのは見事だと思いました
一番良かったのは、流行りの歌手や尖った新人を使わず、世界一有名なループ曲のボレロを使用したこと
最後の二宮さんの涙ぐみながら何かを決意した顔から一転、真っ黄色な8番出口のロゴが全面に出され、ボレロが大音量で流れる展開は、思わず「お見事!」と叫んでしまいそうでした
さて、この作品に向く人と向かない人ですが、私が考えるに向く人は
・情報量の少ないメタファーを感じ取れる人
・概念的な恐怖を感じ取れる人
・8番出口というゲーム性やゲーム空間が合う、好きな人
は特に刺さるのではないかと思います
逆に向かない人は
・恐怖対象が人や幽霊など具体的でないと怖く感じない人
・メタファーが苦手、感じにくい人
・映像的な部分でいろんな変化を楽しみたい人
・津波や濁流の映像を見ても平気な方
はあまり見ても刺さらないのではないかと思います。
他にも色々喋りたいですがひとまずこのあたりで気になった方は是非ゲームを見たりプレイしてから映画を見ることをおすすめします
説教臭さ感じて興ざめ
惜しい。個人的には海での家族シーンも濁流から子供を救うニノも要らなかった。無責任男が親になる覚悟を決める成長ストーリーを見せられ、スマホばかり見てる日本人とか赤ちゃんに怒鳴るオジとか、説教くささが鼻についてしまった。イイ話狙ってます?需要が違うのでは?謎解きメインにするとかホラー要素大切にしたらより良かったのに。
とは言え、すれ違うオジサンもニノの演技も良かったし眠くならず楽しめたので及第点の星3つ。いろいろ勿体ない。
王道ホラー
設定の限界か
間違い探しに正解し続けないと出られない通路に閉じ込められる。ただそれだけの設定を、よくここまで膨らませたと思いました。ホラー、ドラマ、ストーリー、どこをとっても、8番出口を映画化するならこれ以上ないと言えるものができていると思います。原作ゲームに真摯に向き合い作られた作品であるのだと思います。
ただ、面白いとは思えませんでした。何が悪かったかと問われれば、明確なタイムリミットもなく、同じ通路を彷徨い続けるという危機感の薄い設定。間違い探しという地味な作業。これらだとは思うのですが、これらは8番出口の根幹にあるものなので、変える訳にはいかなかった部分でしょう。
8番出口という限られた材料の中で作られたものとしてのクオリティは高かったので、この制作陣の次作に期待したいところです。
そこにいる錯覚——無限回廊の迷宮
途中の展開が面白かった
20分で終わるジャンプスケア・ループ系ホラーゲーム、それを90分の映画に。
ゲーム内容、世界観、登場人物を脚本家なりに解釈し表現しているのでとても見ごたえがあるし、作者の思いも見て取れてよかった。
同じ場所をひたすらループする恐怖、焦燥をBGM、カメラワーク、人物で表現できている。見ているこちらも心臓が締め付けられるような気分、凄みがある。またゲームに負けず劣らずのジャンプスケア要素が多い、予備の心臓が必要かも。
不快なトラウマ表現もあり、お化け屋敷レベルでも本当に無理な人は映画館では視聴できないと思ったほうがいい。
♦良いと思ったところ①最初と最後
「走行する地下鉄車内、子供の泣き声にキレるサラリーマンとひたすら謝り、赤ん坊をあやす母親。周りの人は気が付かないフリをして誰も母親を助けない。」しかし主人公もその一人、結局大音量のボレロを流すイヤホンでサラリーマンの怒号に蓋をして気が付かないフリ。彼には母親を助ける勇気はなかった。
上記がプロローグの内容、これは後々地下通路をループする一因となった。
そしてラストシーン、主人公はプロローグと全く同じ状況に遭遇する。「地下鉄車内、サラリーマンに怒鳴られる赤ん坊の母親を誰も助けようとしない。」
徐々に音量が大きくなるBGMボレロ、主人公である迷う男の顔に真正面から徐々にズームが入る。迷っている様子。どうなるか。
迷う男、意を決して母親とサラリーマンがいる方向へ動き出す。タイトル「8番出口」が大きく出て終幕。ボレロに合わせて流れるエンドロール。
ループものの最後にふさわしい終わり方、最後の最後に主人公は迷いを振り払い、母親を助けた。人間としての成長と真のループからの脱出が同時に描かれていて圧巻。これが見たかった。
♦良いと思ったところ②キャスティング
本当にゲームから出てきたような風貌の河内大和、「歩く男」はこの人にしかできない。
物語の構成から必要な主人公「迷う男」、冴えないフリーター役は二宮和也ピッタリ。
ほかの出演者も全員実力派で演技も自然、映画の雰囲気に自然と引き込まれた。もう少し下手な人を出演させておけば心臓が擦り減らずに済んだかもしれない...
所感
なぜ地下鉄通路のループにハマってしまったのか、通路をNPCのように歩いているおじさんは何なのか、後々繋がってくるので納得。主人公はプロローグの出来事がずっと気がかりであることを、彼女との電話や、異変の描写でしっかり示されてるし。
ダメ出しするとすれば「よし怖がらせちゃうぞ~ホラホラホラ~」感が一部ある。ジャンプスケア・ホラーだから当たり前ではあるけどもう少し巧妙にできたところもある。ねずみのシーンとか。
全1070件中、1~20件目を表示