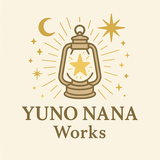トロン:アレスのレビュー・感想・評価
全83件中、1~20件目を表示
ブラック・サバスは好きですか
正直、評価の厳しい映画だと思った。初作は当時として画期的なCG映画であり、それだけでも映画史に残る傑作ではあるのですが、コンピューターシステムの世界に人間丸ごと取り込まれる話は、SFとしてもかなりファンタジーだと思う。ソフトウェアとの対話もなされているけど、当時の素朴な技術では数値の区別しか出来ない時代。
なので、★5を付けれるとすれば私みたいな人間に限られるんじゃないかと思う。初作にあった映像の再現で、バイクを始めとする「光の壁」を放つメカニックは懐かしい限り。第2作でも再現されてはいたけれど。ソフトウェアの化身である人間型のキャラクターと、ユーザーを名乗る巨大な顔との会話もまた、初作の幕開けでみられる印象深いシーンの再現。
加えて、自分の世代には懐かしいパソコンの世界。フロッピーディスクなんて知らない人もいるんじゃなかろうか。画面にタイプされる行番号付きのコーディングは、明らかに昔のBASICのようなインタプリタ言語。そうだそうだ、初作「トロン」の時代、パソコンはこんな感じでした。前述したけど、そのレベルの技術で会話できるソフトウェアなんて信じられないんですけどね。
タイトルにも書いた「ブラック・サバス」というバンドの音楽は、ちょうどこの時代の音楽だったのでしょうか。まだ学生で洋楽なんて聴くセンスを持ち合わせていませんでしたが、今は結構好きです。粗さのあるハードロックの重たいサウンドが堪りません。なので、「こちら側」のCEOがブラック・サバスの「パラノイド」と共に舞台に上がるシーンは心が躍りました。
初作を見返すと、ゲームセンターの名前が「SPACE PARANOIDS」。果たして、ブラック・サバスと関連性があったかどうか判らないけど、そのブラック・サバスといえば、ギタリストのトニー・アイオミが広めて音楽史上に多大な影響を与えたパワーコード。ソフトウェアもコードなら、音楽もコード。関係ある? 関係ないかな。
そして発想の逆転。ソフトウェアで構築された兵器や兵士の具現化。要するに3Dプリンタの技術発達の末なのでしょうか。3Dプリンタ独特のバリ付きで具現化されていくのに、クスッと笑ってしまった。
そしてソフトウェアの哲学。「命令された通りに任務を遂行する」「バグがあるとすればユーザーの設計であり、コンピューターは命令された通りに実行しているだけ」、つまり、結果的にシステムが崩壊しても、どんな被害が出ても、命令されたとおりに実行するだけ。それがユーザーの母親を殺す結果となったとしても。
それは悪意でも誤りでもなく、命令に従うソフトウェアの純粋な忠誠心。主人公を追い詰めた「アテナ」(ギリシャ神話の女神の名前)が倒れる際に「アレス」(ギリシャ神話の戦いの神の名前)に、「命令に従っただけ」(だったかな)と言い残し、アレスが頷き返したのも、そういうことだと思います。ソフトウェアは悪くない。ただただ、ユーザーである人間が悪いのでしょう。初作はもう少し見返さないと思い出せないのですが、コンピューターのソフトウェアをテーマとするにあたり、きっちりとその哲学が込められていることに納得の出来映えだと思います。
しかし、アレスは発達する。ユーザーの意見に逆らい、自分の道を生きようとする。これ、手塚治氏の「火の鳥」に登場するロビタ(だったかな)というロボットを思い出します。ただ、命令に従うのでは無く「お言葉ですが」と反論できる。今のAIが散乱する時代、悪い人間をたしなめ、思いとどまらせる、こうした機能が必要という事でしょうか。
初作のリスペクトはまだまだありますね。「永続性」のテストにオレンジが使われたのは、どうやら初作の実験でも「オレンジの電子化」が行われていた模様。
その当時の電子化の技術で初作と同じようにアレスが取り込まれたのは、初作とまったく同じCGを再現された世界。これは初作を見ていない人には判らない、しかも当時にリアルタイムで感動した人だけの感動だったと思う。バイクの挙動とか当時のまま。このサービスは嬉しかったなあ。
というわけで、この映画の評価が低いとすれば、初作の当時に感動した人しか面白くない、ということじゃないでしょうか。ちなみに、今日私が見に行った映画館では巨大な劇場で数名だけのガラガラ状態でした。割高のドルビーだし無理もないか。
赤と黒の境界線の向こうに見えたもの🟥×⬛️
長編映画として世界で初めて本格的にCGを導入したことでも知られる
SF映画「トロン」シリーズの第3作目🎬
…らしい。
もちろん基本“邦画派”の私は過去作未鑑賞でございます🫣
しかししかし、
あの真正面から目を刺激する赤🟥と黒⬛️――
潔くシンプルなメインビジュアルにどうしようもなく心を奪われ、本日、いざ鑑賞。
結果からいうと🤫
観てよかったし、面白かった〜😎
音楽もなんか凝っていて、ひたすらカッコよかった。ロック好きな中高年が思わずニヤリとしそうな心煽るサウンドでした。
前作を知っていた方がより深く楽しめるだろうけど、
私のような“ゼロ知識参戦”でも十分世界に入り込めるので、怯まずチャレンジを😎
AIの方から現実世界にやってくるという発想は、あるようでなかった気もする設定で新鮮。
「29分間」というリミットがまた絶妙な時間⏳大好きな素数で好感度もアップ⤴︎⤴︎。
現代ではすでに、AIなしでは生活が回らない。
そんな彼らが思考と感情を持ち、創造者の命令を超えて自発的に動き出したとしたら?!全くの絵空事で終わらない世界線の話なので、没入感の後の考えさせられる時間まで込みの映画体験となる。
主人公アレスの旅先の姿がカッコ良すぎて痺れた。
時代が彼に追いついて、永続を手にしたAIが現実を凌駕した時、知らない時代の知らない国で、もし彼らに会ったとしても、私はきっと驚かない。
未知との遭遇は、実はもうあなたの世界のすぐ隣で始まっていて、あの目の覚めるような赤と黒の境界線の向こうで、あなたが来るのをじっと待っているのかもしれない🫣😎😱
「未知を恐れるより、未知を“体験する側”になった方が面白い。」
本作は、そんなメッセージを光の速度で届けてくれる映画です🎬
映画館でぜひご覧ください♪
予告にいい意味で騙された。
テレビの予告編見て「ありきたりのアクション映画」と思って観る気が萎えてたのですが、面白いという話も聞き鑑賞。
初代を観た人は行ってすぐ宣伝するべきでした。予告編作った人、もう少し上手い伝え方もあったでしょうに。
トロンレガーシーより全然面白かったです。
まあ、ツッコミどころはいくらでもあるけどキリがない。
元々の作品がファンタジーみたいなものでしたから。
ビット君、、、いい
電子バイクも2パターンあるのね。
最後に次回につながるような要素出て見たいなーと思いましたけど、、、売上爆死?なら無理でしょう。サーク、、
ディズニーお膝元のエクスピアリ映画館ももう終わる、、、11/23 記
トロンのシリーズって、、、。何がしたいの?
人気がなければ、映画の公開は短くなるんですね。平日1回、16時って誰が見に行くの。。。
たまたま会社が休みだったから見れたけど、仕事終わりの時間帯にやってほしいよね。
とはいっても、見なくてもよい映画であったことは確かです。いや、見なくてよいという評価をするために見たほうがよいか。
歳をとると、映画によけいなツッコミを入れてしまい没入できなくなります。3Dプリンタがあるので、立体構造の作成は現実味はあるのですが、有機物やレアメタル・レアアースがなければ作れないものを一瞬で作るのはさすがに映画でも無理無理。ましてや、それのオレンジジュースなんて見ている人を置いてけぼりです。また、アジア人女性が主役ですが、これってディズニーの"ポリコレ”なのか、アジア人(やインド人)は、IT系に強く頭がよいという"ステレオタイプ"なのか、どっちなんだろうと考えてしまう(ほど、映画にのめり込めていなかった)。
それでも、"ハッキング"をデジタルワールド内での兵士たちの戦いで表現したり、AIが迷いが生じてより人間に近づく感情を得たり、"永続コード"は"非永続コード"だという生命の考え方もよかったし、もう少し手直しすればすばらしいストーリーになっていた気がするんです。
こうなると、ターミネーター3の再評価です。えっ? なんで?
デジタル(というかAI)が、現実に侵入し支配する方法が気持ち悪いです。クルマを支配し、すべてを支配していきます。人類の追い詰められ方が恐ろしい。トロン アレスは、しっかりしたテーマを持っていたと思いますが、新しいものを作ろうとして、作り切れなかった。。。前々作の人物であったフリンは、コンピューターワールドに取り込まれても重要な役で復活しましたが、逮捕されるのがいやで、デジタルに逃げたデリンジャーが復活する続編はないでしょうね。
現実と仮想が交錯する、新時代のトロン
CG表現の完成度はシリーズ随一。現実世界とプログラム世界の融合が精緻に描かれ、物語に圧倒的な臨場感をもたらしている。
イヴ役のグレタ・リーの起用も光る。アジア系俳優としての新鮮な存在感と、冷静さの中に潜む人間味が、デジタルとリアルの境界を揺さぶる物語に深みを与えている。
AI兵士アレスが現実世界で“デジタルデトックス”を選択し、対照的にディリンジャー社のCEOジュリアンがデジタル化していくというラストは、象徴的かつ示唆に富む展開だ。
プログラムが「生」を求め、人間が「データ」になるという逆転構図を通して、テクノロジーと人間性の本質を問い直す。映像と脚本が高次元で融合した、シリーズの到達点と呼ぶにふさわしい一作。
汗
んー、映像は凄まじかったのだけど、物語とか設定がなぁ…腑に落ちん。
主人公はセキュリティソフトらしい。
所謂プログラムで擬人化させて兵士にするとか。
3Dプリンタのようなもので具現化する。
…ふむ。
つまり、人ではない。
飯も食わなければ呼吸も必要としない、はずだ。
ぶっちゃけ瞬きなどの生理現象もいらない。
見てくれだけが人であればいいはずだ。
そいつが後半、汗をかいたり動悸がはやくなったりする。…なんでだ?
具現化する機械もそうだ。
どんなメカニズムで動くのだろう?
プログラムなわけだから、内部構造すら設定する必要があると思われる。外殻だけデザインすれば済むような話ではないはずなのだが…。
中盤ヒロインが電脳世界に転送される。
…ちょっとよく分からない状況なんだけど、彼女は彼女の生態情報を全てデータ化され、電脳世界で再構築されるのであろう。そこはまぁいいのだけれど、現実に戻ってくるのだ。3Dプリンタで出力されて。
SF的な視点で言うと空間転移にあたるとは思うのだけど…彼女には29分という制限はかからない。
有機物すら出力し再構築する3Dプリンタ。毛細血管すら再現してしまうのか?いや、細胞って話にまで及んでしまう。
どうにも…気に食わない。
このシークエンスの調理方法が違ったらもうちょいのめり込めたかもしれない。
落とし所は、まぁ、よくある感じだったが続編の構想もあるようなので、見てみようと思う。
現実に出てきちゃダメ
前作はIMAXで観て、「これこそIMAXで観るべき映画だ!」と大興奮だった。
トロンは不思議な魅力をもつ作品で、映像のスタイリッシュさとか、物語の哲学性とか、なんか特別感がある。
で、この「トロン:アレス」も楽しみにしていたのだけど、近くの映画館のIMAXは吹替版しかないし、なんかストーリーもいまいち面白くなさそうだったから、結局2D版を観た。
で、やっぱりいまいちだったなあ…。
現実世界からデジタル世界に入れるのだから、理屈からいえばデジタル世界から現実世界にも行けてもよさそうなはずだけど、それがあまりにむちゃすぎて現実感がない。
なんでそう感じるのか考えてみると、現実世界からデジタル世界に入る、という物語を、自分は無意識にファンタジーの文脈でとらえていたのだ、ということに気づいた。アリスが不思議の国に入ったり、バスチアンが小説の中に入ったり、ってのと同じ。前作までは、プログラムやコンピューターウイルスが擬人化されて人の姿になっていても、この世界はそういうことになっている、というので納得できた。
でも、デジタル世界から現実世界に行く、となったとき、SF的(科学的)に考えてしまって、「こんな科学、どう考えても地球文明のものじゃない」ってなってしまう。3Dプリンターとかじゃなくてレーザーで質量をもつ物質を作り出してしまうだけで超技術なのに、それ以上の技術がばんばんでてきて、こんなテクノロジーもってたらこの企業世界征服できちゃうじゃん、とか思ってしまう。
1つだけ心に響いたセリフがある。「私はこれを永続コードと名付けたが、本当は非永続コードなのだよね」みたいなやつ。
確かに、デジタル世界のもの、つまり「情報」というのはある意味永遠の命をもっているわけだが、それが現実世界のものになってしまうと、有限な存在になってしまうという。非常に深い話だと思う。
ぼくは個人的にはトロンのシリーズは、こういう「情報世界」の奥深さみたいものを追っていく話にすべきだったと思う。情報の世界というのはいいかえれば数学の世界だったり、イデアの世界だったりするわけで。フリンがデジタル世界で仙人みたいな存在になった(存在、非存在を超えた存在になった)ってのも、そういう奥深さを感じさせる。
動力は?
映像と系譜をしっかり引き継いでいるトロン。
ただ物語の核となる仮想のものを現実世界に転送できるという点において、現実世界に転送されたものは何か動力となっているのか?
もし電力であるのなら理解は出来るのだが、なんとなくその点をあやふやにしてるのが気になった。
また無限の時間を得たアレスが顔から血を滲ませているシーンはどうして?という感じがした。
そしてラストシーンの容姿の変化もまた同様の認識となり、彼は人間なのか?それとも容易に見た目を変化させられるのか?そんなシーンはなかったのだが。
Still Remains
AIがより身近になった現代にこそぶち込むべき映画を圧倒的映像、そして現実への原点回帰を魅せる映像体験を味わえたなと思いました。
今作はシンプルなストーリーに映える映像をガンガン魅せていくスタイルで、尚且つストーリーも破綻していないので程よいハリウッド映画、何にも染まってないディズニー映画というところもホッとできるポイントが高かったです。
AI兵士たちの電脳空間での戦いがこれはこれはカッコよく、赤いソードでバンバン戦い、空飛ぶガジェットもお披露目したり、ブロック状に攻撃や制限時間で崩れていくのもゲーム的な感じで最高でした。
現実世界の道路をイカつい近未来バイクで駆け回る様子は痺れちゃいました。
赤の線で街を染め上げながらの爆速でのチェイスは燃えますし、実際に高速道路を貸し切って撮影するスケールのデカさにも驚き桃の木でした。
デカ監視ロボが街を闊歩しながらミサイル機をバンバン撃ち落としていったり、ビームで街中を覆ったりして占拠していく様子も素晴らしかったです。
過去作設定との繋ぎとして強かった29分間の縛りも後半活きてきたかなと思いました。
序盤は気づいたら29分経過というのが多かったのですが、現実世界に飛び込んできてからの29分のスリルがひしひしと伝わってきたなと思いました。
ストーリーとしてはやはり登場人物の成長があんまし感じられないままストーリーが進行していくのでのめり込む前に次の展開へというのが多かったのが惜しかったです。
とはいえアレスが完全サイボーグから80年代好きのジャレッド・レトになる瞬間のユーモアは最高でした。
解決後のアレスが楽しんでいる様子を見れてオールオッケーでした。
音楽も超素晴らしく世界観にベストマッチで良かったです。
サントラはリピート確定です。
映像体験としては間違いなく花丸でしたので、好みだろうなとは思いました。
バカデカIMAXで観たかったなぁ。
鑑賞日 10/21
鑑賞時間 12:50〜15:05
映像は素晴らしいけども。
トロンシリーズ初見。
話はありきたり。
寝そうになっちゃった。
A I戦士や乗り物の光の帯演出とかかっこいいけど、ラスボス的に出てきたデカい何かがカッコ悪すぎて笑っちゃった。機能性も機動性にも欠けるアレはなんだったんだ…
と思っていたけど、長い歴史を持つシリーズの延長線として、技術の進歩やテクノロジーとの共存など様々なテーマが錯綜していたのですね。
多人種を採用してるとこは流石のディズニー。
個人的にはディズニーのロゴのシンデレラ城が黒赤の配色になってるところもツボでした。
はたらくプログラム
コンピュータープログラムを擬人化した「トロン」第一作目から今回三作目。身体の細胞を擬人化した「はたらく細胞」のヒントとなったシリーズだと睨んでる。
今回はプログラムを3Dプリンターで実体化できる技術が開発されたことにより彼らプログラムの世界グリッドから現実世界への侵略の危機がせまる。そんな中で革新的セキュリティプログラムのアレスが自我に目覚め、自分の創造主に逆らいヒロインを守り自分自身をグリッドから解放するために戦うといういわば王道の物語となっている。
そもそもがプログラムを擬人化するという「インサイドヘッド」や「はたらく細胞」と同じような世界観の作品なので端から理屈にこだわるような作品ではなく、よくあるロボットが自我に目覚めた系の作品として楽しめばいい。そういう意味で80年代ミュージックを愛する人間味のあるキャラクターとして描かれたジャレット・レト演じる主人公アレスは魅力があった。またヒロインを演じたグレタ・リーも「パストライブズ」以来注目していた俳優さんなので、個人的には彼女が出演してるのが鑑賞の後押しになった。キャスティングが合わないという意見もわからなくもないが。今回時間調整のための鑑賞だったけど期待値が低い分楽しめた。
いま人間が永遠に生きる手段として人間の脳をデジタル化するという方法が考えられている。自分の意識をデジタル化して保存できれば肉体は死んでも意識は半永久的に存在できる。しかし本作のアレスはコンピュータ上では半永久的に生きられるにもかかわらず彼はその真逆の行動をとる。永続コード(非永続コード)を手に入れたアレスは不老不死でいられるはずのグリッドから脱出して現実世界での限りある命を手にする。
自我に目覚め人間らしい心を手に入れたアレスが不老不死ではなく限りある命を選択したのがなんだか印象的であり、これが作り手が本作で言いたかったことなのかなと感じた。
ただのプログラムである彼はこの世界のすべての事象がデーターとして頭に入っているがそれを身をもって「体験」することはできない。正確な天気予報をしながら雨に打たれる経験が出来なかったと惜しむ気持ちを吐露するアレス。彼は永遠に生きられるが生きている実感を得られないグリッドの世界よりも生きている実感を味わえる現実世界での限りある命を選んだ。彼のこの姿はなんとなく現実世界よりもネットの世界に傾倒しリアルな人間関係やら生きている感覚が希薄になりつつある現代人を皮肉ってるようにも思えた。そういう意味で本作は案外深い作品かもしれない。
ちなみに金属3Dプリンターで実体化される際にアンドロイドのアレスや戦車に金属のバリがついてるのはわかるけど、生身の人間であるイブがグリッドから転送されて実体化される際も金属のバリがついてたのはおかしいのでは。それとも彼女も機械化されたのかな?
ついにあのデジタルバイクが現実世界に…!
リアル世界の街中でのライトサイクル・バトルが見られただけでも大満足な映画だった!
80年代と揶揄して初代『トロン』のヴィジュアルを再現したり、前作の『レガシー』から引き継がれた要素も所々に取り入れられていたのが良かった。
特にアレスの最後の復活後が『レガシー』の白色だったのがうれしかった。
なるべく情報なしで見に行ったのでX-MEN版クイック・シルバー役のエバン・ピーターズが出演していたことにびっくりした。
X-MENシリーズ以降見かける機会がほとんどなかったが今回のバカ息子役はかなりハマり役だった。
これを機にまた映画業界で活躍してほしい。
けっこうご都合な展開もあったが1番気になったのは、未知の相手との初戦闘で敵本陣の浮上要塞にミサイル当てた上に脱出しながら機体特効した戦闘機パイロット。
モブのくせに有能すぎるあいつは何者だったんだ笑
とてもよかった
1作目を先日見て、予習していたおかげでけっこう面白い。一作目の世界を踏襲しており帯を後ろに引くバイクが現実世界で立体物として残り道路交通をめちゃくちゃにする。
ゲームの世界の人間アレスがどの程度人間なのか、当初は25分の寿命なので気にする必要がなかったが、内臓や脳など全部ゲーム世界から現実世界に移植して、最後は期限がなくなり食事もすれば排泄もして、寝たり老いたりするのだろうか。戸籍もない。特に何も説明がない。現実世界の人間がいったん、ゲーム世界に移植されて、再び現実に戻るから同様なのだろうか。
クライマックスでは1作目の変なやぐらみたいな巨大兵器が街を襲う。そこも踏襲するか。
ホンダシビックTYPE-Rが高評価されていて鼻が高い。
映像表現は素晴らしく、迫力もあったが・・。
IMAX 渋滞の昨今。
あっという間に見れなくなるので、いまのうちに IMAX で鑑賞。
---
うっすら、初代トロンを覚えている私。
円盤をつかったアクションは懐かしさもあり、砕け散るシーンも、良く作ってる。
今作、バイクを含めた疾走シーンも、とても良く作られており、
VFX もとても、素晴らしい。スケールもでかい。迫力もある。
が・・・。何かが足りない感じがする。
きっと、物語部分なのだと思う。
---
初代の時代、プログラムの中に人が投影され、CPU だの、
プログラムに人格があったり、記憶ディスクで戦ったり、
めちゃくちゃ、斬新さがあったと思う。
しかしながら、攻殻機動隊やら、ゲームやら、リアルなサイバー空間、
IT を駆使したシナリオに慣れてる私にとって、今作、あまり斬新さを感じない・・・。
AI エージェントが心を持ち、管理者ユーザーに逆らい、肉体を得て、
特別なプログラムで、人間になる。というのは、少々無理があるような気がした。
また、これもグリフィス (鷹) が受肉して、現世に現れる経験をしているためか、
斬新さを感じない・・・。
---
予告をみて、斬新さ、新世代を期待し過ぎてしまったのも、良くなかった気もする。
きっと、お昼や深夜のロードショーぐらい、軽い気持ちでみたら、
もっと面白かったのかもしれない。と感じた。
誰もが学ぶべきだ
こないだ鑑賞してきました🎬
アレスにはジャレッド・レト🙂
「スーサイド・スクワッド」や
「モービウス」
にも出てましたね🤔
今作のAI兵士という役は、どことなく空虚な雰囲気を出していてなかなかうまい。
見た目は人間そのものですが、徐々に自分の存在意義に疑問を感じていく様は私は共感できる気が😳
元々そういう要素があったかのような設定ですが、まあ主役ですしね👍
永続コードの鍵を握る科学者、イヴにはグレタ・リー🙂
彼女がなぜ永続コードにこだわるのか、劇中で明らかにされます。
色々抱えている人で、その重みが見え隠れする表情は良かったですね😀
エバン・ピーターズは野望に取り憑かれた悪徳CEOジュリアンを熱演😳
彼の母親エリザベス役で、ジリアン・アンダーソンを久々に見たのは嬉しかったです😁
私は過去作未見ですが、そこまで置いてけぼりを食らうことなく楽しめました😀
AIプログラムが自我に目覚めるという、既視感のあるプロットですが、アレスの心理描写はわりと丁寧です。
一昔前ならファンタジーで済ませられましたが、200年後あたりには似たようなことが起こるかもしれないのが恐いところですね⚠️
シリーズファンはもちろん、初見の方も問題なく見れる1本でした🫡
映像革新!
レビューで比較的低評価だったので、あまり期待せずに映画館に行きました。しかし、とても面白く良い意味で裏切られました!
まず、なんといっても圧倒的な映像に男心がくすぐられました。特にあらゆるチェイスシーンではバイクや光の演出なども相まってかっこよく、緊張感もありました。
また、永続コードの皮肉のくだりも個人的にはとても面白かったです。
レガシーの方はほとんど見ていなかったので、登場人物など少し整理する時間があったかなと思います。次回作も出そうだったので、今回の作品をさらに超えるような映像や脚本を期待したいです!
ジリアンとグレタ
旧作は見ておらず。それなりに力も金も入ったCG大作、絵面やシーン単位のスジには不満はないんだが、世界観というかあっちとこっちの境界に、最後まで素直に入っていけない。3Dプリンタ的に実体化を見せるし、バイクや兵器など現実社会で実現していない技術も実体化してしまう。あろうことか人間をデータ化して取り込んだり戻したりするし、未来人とか宇宙人とか異次元人が相手なのかというような超技術だけど、設定上創造主は人間でIT企業の産物というのは無理があるよな。 80年代やオリジナルのフリンと結びつけていくところは嫌では無いんだけど。ホンダシビックとか。
オープニングでXファイルのスカリー、ジリアン•アンダーソンの名を発見、懐かしくて調べたらまだ61歳だった。これもスタッフの懐古趣味かなぁ。
あとグレタ•リーといえばApple TV+の「ザ•スタジオ」で「A24とかは予算がないんで宣伝ツアーも貸切フライトが無い」とか言ってたけど、ディズニーの本作では乗れたかな?
追記 グレタ•リー、ぐれたり、ぐれなかったり。
圧倒的な映像美と、浮かび上がる「あの古典」。そしてはっきりと感じるディズニーの遺伝子
「トロン」シリーズはれっきとしたディズニー作品であり、そういう意味では「白雪姫」「シンデレラ」「美女と野獣」などなどと肩を並べる作品…と言えるっちゃあ言えるのだが、その雰囲気はディズニー作品の中でもとりわけ異質に感じる。我々が「ディズニーキャラクター」としてイメージする愛らしさやキャラクター性を完全に削ぎ落とした、シンプルかつスタイリッシュな画面作りが果たす役割はかなり大きいだろう。毎回大物ゲスト(今作はナイン・インチ・ネイルズ。見事すぎた)を呼んでオーダーしている劇伴音楽も大きく一役買っているに違いない。それでも「トロン:アレス」は「ディズニー最新作」の看板を引っさげて新作を投入した。ちょっとこの意味を考えてみたい。
「トロン」シリーズの中核にあるのが「グリッド」と呼ばれるコンピュータソフトウェアである。グリッドの「内部」には3次元空間が広がっており、プログラムたちが人工知能の意思を持って社会を築いており、そして「現実世界」の人間が特定の手段でグリッドの中に「侵入」することができる。グリッドに侵入した人間は、この空間を探索し、冒険し、時にはプログラムたちと肉弾戦に発展することもある。SF作品の中でもかなりファンタジー寄りの設定だ。
この「"現実世界" と "ファンタジー" の融合」は、実はディズニーが頻繁に取り上げているテーマでもある。はっきりと言及している「魔法にかけられて」を始め、「リロ&スティッチ」、「トイ・ストーリー」…いや、「ロジャー・ラビット」の時代から、ディズニーは「この世界は空想と隣り合わせ」と主張しているのだ。「トロン」の「グリッド」も、描写こそ独自路線なもののディズニーの伝統芸能なのだ。
今作「トロン:アレス」では、グリッドの方の存在が、グリッドの中での姿・形・機能のまま、現実世界に現れることができる…ただし、29分間だけ。この「29分の壁」を破る「永続化プログラム」を巡る企業間抗争が、本作のメインストーリーとなる。「グリッド」技術の本家大元であり、永続化プログラムの平和利用を目指すエンコム社が善…というか被害者の役回り。逆にグリッド存在の軍事利用を企画し、永続化プログラムを強奪しようとするディリンジャー社が悪役という構図だ。ていうかディリンジャーさん、他社の成果物を使いたいならそんな強引な手段を取るなよ。あんたもビジネスマンなら(映画館から出て冷静に考えたらとんでもない展開だったなと気づく事、ありますよね)。
面白いなと思ったのが、今作の主人公でありタイトルにも起用されている「アレス」が、元々は悪役であるディリンジャー社側の存在であるということだ。彼は人工知能としてあまりにも高性能であったため、ディリンジャー社の強引というか非人道的なやり方に疑問を覚えてしまい、結果的にエンコム社と同じ価値観で行動するという、「裏の裏は表」的な流れでヒーロー側に立つ。王道かもしれないがワクワクできる展開だ。…もしかして予告で触れていた「AIの反逆」ってこのことですかね?だとすると直接的なイメージの裏をかいていて上手いなぁと。
一方、最後までディリンジャー社の指示に忠実だったのがプログラム「アテナ」である。「なんとしても永続化プログラムを捉えろ」という指示のもと、破壊行為や殺人も厭わないし、最終的に超巨大空中戦艦を繰り出して現実社会に大混乱を引き起こす。「AIの反逆」というフレーズから受ける印象に近いことを行うが、こちらはむしろ一切反逆はせず「忠実すぎた」からこそ人類の敵になってしまったのだ。
人間のあいまいな指示が、加減を知らないツールによって大混乱を引き起こす…ここまで書いて、私はある作品を思い出した。「トロン」シリーズの過去作ではない。ディズニーの古典的名作、「魔法使いの弟子」である。見習い魔法使いミッキーマウスが、魔法のホウキたちに「水汲みをしろ」としか指示しなかったところ、周辺に大洪水を起こしてしまう話である。今作「トロン:アレス」製作陣のディズニー社の人員が、「魔法使いの弟子」を意識しなかったはずがない…と、私は考えている。
実際、私もIT業界人の端くれで、仕事の文脈で「魔法使いの弟子現象」と言ったことがある。良かれと思って作ったプログラムが、想定以上の作用をして、結局有害になってしまうことを指している。そして対話的AIツールが急速に普及したここ数年、AIの言うことを鵜呑みにして間違った判断をしてしまっただとか、AI搭載開発ツールが誤作動して本当に大事なデータを削除してしまったといった事態が現実に発生している。今作の「アテナ」の行動は、割とシャレにならない含みがあると強く感じた。
対話的AIの急速な普及、それで生まれた社会の歪み、そういった時代の流れのド真ん中に「トロン」シリーズ最新作を投げ込んだ「トロン:アレス」は英断という他ない。空想と現実はいつも隣にいる、でも空想は時に暴走する…そういった哲学が、ディズニーには伝統的にあったのではないか。こんなことも考えられるほど、あまりにも充実した映画体験だった。
悪くはない
旧作はあの時代であの設定、なんか無理矢理感がある内容でウケた印象。
次作はあの世界観を綺麗にし、映像という点で進化したもののストーリーはまぁ無難なSFになった感じ。
そして今作。この時代でやる意味としては続編だから、という理由しかない。映像美は他の映画でもあるし、ストーリーももっと練られたSFはある。
そう考えると不安にしかならなかったのですが、エンタメとしては良かったと思います。
あの世界をさらに綺麗にし、かつ古い世界も登場させ、ストーリーも繋がりがある。話も王道展開で楽しくみられます。
だからこそなのか、あまり感じるものはなかったかなぁ…
なんか設定も無理があるし。時間制限や永続化に違和感しかない。
かといって、具体的にどうすれば良かったか、というのは浮かばないのですが…
王道の展開
映像はとても美しく、演出も古典的で先が読める部分は多いものの、王道の面白さがありました。
音楽も前作『トロン:レガシー』のダフト・パンクの要素を感じさせる仕上がりで、これはこれで悪くなかったと思います。
一方で、グリッドの世界から物質を次々と生成していく描写は、さすがに現実離れしすぎていて、少し違和感がありました。
SF作品だから割り切れる部分ではあるのですが、そこがどうしても引っかかってモヤっとしてしまいました。
全83件中、1~20件目を表示