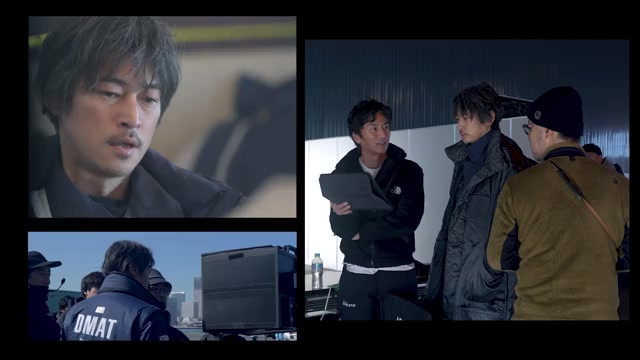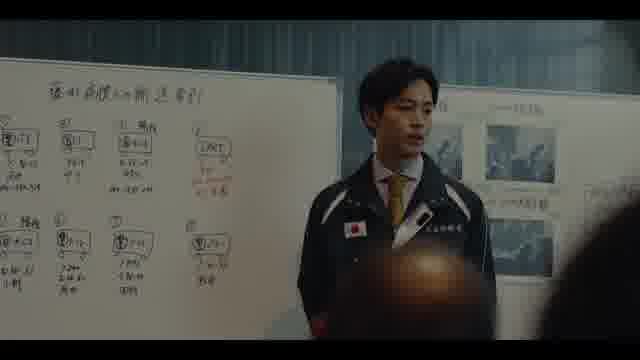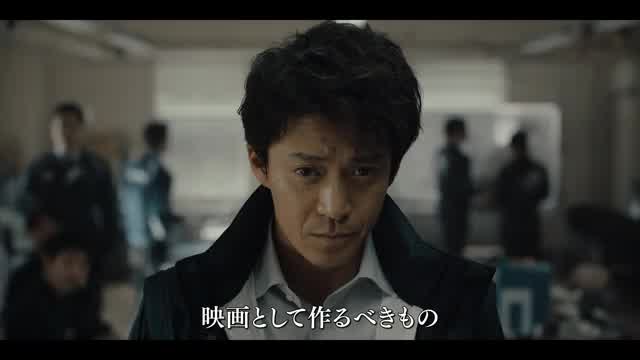「観客を煽らない映画」フロントライン TUMSATさんの映画レビュー(感想・評価)
観客を煽らない映画
あのときどういうことになっていたかの勉強に、長男長女と3人で鑑賞。パニックが引き起こすスリリングな展開を想定したのが間違いで、そのせいか、かなり淡々としていた印象。もっとシリアスに重く、報道に踊らされる国民の理解のなさを訴えるようにも、あるいはもっとドラマティックにしてあっちとこっちの言い分でバチバチさせて観る側がハラハラドキドキ、とできる題材のはずだが、飄飄とした作品で、何かを突きつけられる、考えさせられるのではなく、最後の窪塚の電話のように、むしろ爽快な気分にさせられる。映画でマスコミを批判することが難しいのだろうが、それにしてもキレがない、とでもいえばよいのだろうか。朗読+映像でも伝わるものは同じではないかと思う。むしろ河内大和が劇団でしているように彼が一人で全台詞のほうが見ごたえ/聞きごたえがあったのでは。あちらこちら(役所、報道メディア、医療機関、学会)への忖度が見え隠れして、あれこれ不満を抱えて映画館を出た。
そう感じたのは、誰目線で語られるか、がはっきりしないからなのかな、と思った。何かしらの立場で語ると別の何かの立場が見えなくなるので仕方がないのだが、しかしそのせいで葛藤が薄っぺらくなっている。報じるか報じないか、どのように報じるか。船にいくかいかないか。水のために離岸するかしないか。家族の辛さの解消を優先するか、患者の治療を優先するか。決まり事を守るか、逸脱するか。感染を怖れて患者の受け入れに反対する医療従事者は小栗が言うように辞めるべきなのか。世間を振り回した暴露動画は削除された、で済まされるのか。検疫官の責任転嫁、乗組員の献身と苦しみ、いいかげんな識者をもっと取り上げてほしかった。
足りない部分は想像力で補えばよいが、想像のほうが実際の映画より魅力的では仕方がない。実際に怒鳴り合い、殴り合いがなかったのかもしれない(最後、滝藤に熱量を感じて映画を観たなと思えた)が、どうにもわたしの日常のほうが盤根錯節しているのでは、と思えるほど物足りなかった。つまり、非日常の世界がそこにはなかった。
松坂の台詞が的を得ていて0.5点。曰く、この映画自体が実話を笠に着て、鑑賞者の「善意や良心につけこんで」表現者としての「責任を回避」しているように感じた。