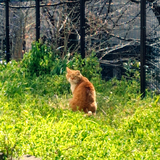シンシン SING SINGのレビュー・感想・評価
全136件中、1~20件目を表示
ラストシーンのその先で生まれた映画
コールマン・ドミンゴがオスカーにノミネートされていたから観てみようかくらいのノリで予備知識を入れずに鑑賞したので、エンドロールで驚かされた。
主要キャストのうち、3名(C・ドミンゴ、マイク・マイク役のショーン・サン・ホセ、演出家ブレント役のポール・レイシー)以外は一般的なプロの俳優ではなく収監された過去を持つ人たちで、その多くは物語に出てきたRTA(Rehabilitation Through the Arts)の経験者だという。ディヴァイン・アイ役のクラレンス・マクリンは、元々は実際にシンシン刑務所で恐れられる荒くれ者だったところRTAで更生し、ディヴァインGのモデルであるジョン・ウィットフィールド(作中、Gにサインをもらう役でカメオ出演)と共に本作の原案・製作総指揮を担っている。
刑務所という殺風景な舞台には不似合いなほど穏やかに進んでゆく物語を追ううち、ドキュメンタリーを観ている感覚に陥る瞬間があったが、それは彼らの実体験が作品の空気に反映されていたからかもしれない。
結果的に先入観なしで彼らの演技を観ることが出来たという意味では、事前リサーチ不足でよかった気がした。
刑務所の演劇グループに、所内一番のワルがやってくる。本作を紹介するそんな短文から、私はほぼ無意識に安直な「暴力や絶望を物語の推進力とする、ありがちな刑務所ドラマ」(パンフレットより。なお作品の背景を詳述したパンフは必読)を連想していた。思えばそれもある種の偏見だったのだろう。
しかし蓋を開けてみると、そこにあったのは人間らしい感情への回帰と癒しの物語だった。RTAのミーティングで次回作の打ち合わせをし、ブレントから演技の手ほどきを受ける中で、収監者たちは自分の内面と向き合う。最初は反発していたディヴァイン・アイも、自分の態度について仲間から忌憚のない指摘を受けたりするうちに徐々に変わってゆく。
ブレントの導きで自分たちが完璧だった時のことを各々が言葉にする場面などは、つい私もその問いを自分自身に投げかけてみたりした。演劇によって自分の感情との付き合い方を学ぶことは、人生経験を通してそれを学ぶことに近い気がし、彼らの体験を不思議なほど身近に感じた。
本作は収監者たちが人間性を取り戻す話にとどまらず、人の心についての普遍的な物語でもあるように思う。
ディヴァインGが冤罪で投獄されていることは中盤でさりげなく明かされるが、その冤罪を晴らす闘いそのものがドラマチックにクローズアップされることはない。一方、彼の減刑嘆願の却下は、親友マイク・マイクの病死という不幸と重なり、彼の心に抱えきれないほどの苦悩をもたらした。
彼が力を貸したディヴァイン・アイの減刑が先に叶ったことは本来Gにとっても喜ばしいはずだが、そのことさえもこの時の彼にとっては孤独と絶望を際立たせる出来事に見えたことだろう。ディノが言った「何かを気にかけると心が開く、そこから痛みが入ってくる」という言葉がGの姿に重なる。
「マミーの掟破り」本公演の前に、「心が抱えきれない時がある」と荒れた態度をメンバーたちに謝ったG。遥か遠いニューヨーク州の刑務所で私とは全く違う世界を生きる彼だが、彼の心のあたたかさ、彼を襲った失望や喪失を知った上で聞いたこの言葉から伝わる感情には垣根など全くなかった。
そして、出所が叶ったGが迎えにきたアイと抱擁する姿に胸を熱くせずにいられない。この短く美しいシーンは、解放、更生、絆、さまざまな意味を感じさせるものだった。
プロではない当事者が演者として参加した作品と言えば近年では「ノマドランド」が記憶に新しい。だが、本作では企画の考案段階からメインキャストに至るまで、当事者たちがより深く関わっているという点が特徴的だ。
シンシン刑務所での演劇プロジェクトに触発された映画が生まれ、それを私たちが鑑賞する、この構造自体がRTAの延長線上にある気さえしてくる。
彼らの実体験が結実したのがこの作品であり、私たちは映画館へ行くことによって、ある意味物語の先にある彼らの実人生、すなわち本作の製作に参加したという人生の軌跡にも触れることが出来る。作品の存在自体が実話と地続きになっている、かつ物語として高いクオリティを実現している、なかなか稀有な映画ではないだろうか。
Unapologetically Intellectual
A heavy prison drama about inmates rehabilitating through theater, Sing Sing was one of the Best Picture snubs at the Oscars. Colman Domingo is well-deserving of his acting nomination. As the story centers around auditions for Hamlet, the Shakespearian energy pervades the narrative, reflecting the characters' struggles as if they are manifested from the scripts in their hands. Such is the power of acting.
やはり(刑務所は良くないけど)刑務所映画は良いものが多い。 しっか...
シンシンの舞台に
NYに実在するシンシン刑務所。警備レベルは最厳重で、収監されている囚人たちも重罪者ばかり。
そこで行われている更正プログラム。その一つに、演劇。
長らく収監されているジョン・ウィットフィールド、通称“ディヴァイン・G”は、このプログラムの中心人物。
同グループの仲間と日々稽古などに打ち込む彼は、無実で投獄された身であった…。
穏やかな性格と台本も書く賢さで仲間から慕われる一方で、自分の境遇に苦悩も抱え…。コールマン・ドミンゴが今の絶好調ぶりも分かる巧演。
新作舞台の為に新たな“キャスト”を探す。スカウトしたのは最も恐れられている囚人。クラレンス・マクリン、通称“ディヴァイン・アイ”。
彼や他の囚人たちも知らない役者ばかり…と思ったら、それもその筈。囚人たちのほとんどは、実際に収監されプログラムに取り組んでいた元受刑者たち。
ディヴァイン・アイは本人。ドミンゴが演じたディヴァイン・Gも別役で出演。皆が驚くほどのナチュラルな演技。これもプログラムの賜物だろう。
実際の刑務所を舞台に、実際の元受刑者たちによる、実際の演劇プログラム。
稽古シーンなどはドキュメンタリーのよう。劇映画を見ているのか、ドキュメンタリーを見ているのか、不思議な錯覚。
勿論、ドラマ仕立ての劇映画である。無実で…とか囚人たちの交流など、同じく刑務所を舞台にしたあの名作を彷彿。
それと同様に、サスペンス仕立てで刑務所から脱獄…なんて展開になったら何だか趣旨が違くて嫌だなぁと思っていたので、地味だが終始プログラムと囚人たちのドラマに一貫していたのは好感。
苦悩や不条理は募る。
特に親しかった隣の房の囚人。ついさっきまで話していたと思ったら…。
自殺や刑務所内のいざこざで殺されるならまだ分かるが、あまりにも突然の病死…。
仮釈放申請の聴聞会。演劇プログラムが如何に自分の為になったか、真摯に訴えたのだが…、審査役の態度はシビアで素っ気ない。
結果は通知されなくても分かる。どうせ…。
さすがに自暴自棄になり、最終リハーサルで大声で我慢の限界をぶちまけてしまう。さらには、プログラムを下らないとまで…。
受刑者たちが刑に服すのは当然。許されぬ罪を犯した。
だが、それが間違いの時だってある。その不条理…。
俺たちに自由は無い。
…いや、たった一つある。それまで束縛されたりしない。
自由意思。演劇をやろう!
当初新作舞台は、ディヴァイン・Gが構想していたいつもながらのシリアス劇の予定だったが、ディヴァイン・アイの笑えるのをやりたいという意見と多数決で喜劇に変更。
皆の意見やアイデアを募ったその内容は、ハムレットやらリア王やらグラディエーターやら海賊やらロビン・フッドやらガンマンやら『エルム街の悪夢』のフレディまで登場する、奇想天外なタイムトラベル・コメディ。
この劇、見てみたかった気もする。残念ながらそのシーンは丸々カット…。
EDには実際の演劇の映像。
この演劇のみならず、様々な更正プログラムを聞いた事がある。もの作りや犬の飼育など。
釈放された受刑者たちがまた刑務所に戻ってくる率は深刻なほど高い。が、何かプログラムに携わった者は率が低いとの検証結果もある。
何か、生きがいを。
それによって見出だし、本当の自由へ希望を繋ぐ事も出来る…。
開かれた刑務所
主役のディヴァインGを演じたゴールドマン・ドミンゴは
役所広司とそっくりの演技巧者であり、
人間味溢れるリアリティある存在感。
彼は凸凹した長方形の顔形含めて役所広司でした。
2人に特に共通するのはペーソス溢れる哲学者の姿。
シンシン/SINGSING刑務所の演劇を使った刑務所での
【更正プログラム=RTA】って、
これは刑務所受刑者の再犯率を調べる上での
モデルケース・・・だったのでは?と思います。
どこの刑務所でもこのPTAを実施予算はない筈だし、
トランプ政権のような政府機関も封鎖してしまうような政権では
まず一番にコストカットされること間違いないでしょう。
でもシンシン刑務所では行われたこのプログラムの
その効果は抜群のようですね。
事実このRTA之を受講した刑務所受刑者の再犯率は3%以下と、
信じられない数字です。
犯罪者の多くは演劇の恩恵を受けるような環境に生まれてない
思われます。
しかし演じることは心を開放すること。
そして怒りや悲しみ、喜びを表現することで、
感情のコントロールを会得し、そして他者を思い遣る気持ちが
芽生え始める。
他者を愛することは、心の余裕がなくては生まれない気がします。
ディヴァインGの勧めで仮釈放の申請をしたハムレット役のクラレンス。
クラレンスの心は捻くれ、ささくれ立っていました。
人間不信も大きい。
しかし申請は認められて出所が叶います。
演じたのは実際に刑務所に服役して演劇更正プログラムを受けた本人の
クラレンス・マクリンが演じているのは驚きでした。
無実で何十年も服役しているディヴァン・Gの仮釈放の申請は
却下され続けて、ディヴァインGの心は折れてしまいます。
しかし演劇仲間たちが、彼の復帰を誰よりも望んでいました。
ハドソン川の岸辺にあるシンシン刑務所。
窓から見える景色や、自由時間に歩く散策路など、
いかにもゆとりのある開かれた刑務所って感じですね。
多くのプリズンものの映画とは大違い。
プリズンものではない名作の「ジーシャンクの空」や
「パピオン」での極悪刑務所長は全くでてきませんし、
よく見かけるお決まりの新入り之受刑者への通過儀礼とも言える
性加害も見受けられません。
窓ひとつない暗闇の懲罰房や、水圧をマックスに上げた水攻めも
皆無です。
遂に出所のかなったディヴァインGを出迎えるクラレンス。
どんな開かれた刑務所であっても、自由と希望の新生活は
彼が夢見た夢そのものである筈です。
映画館で見た
U-NEXTのポイントで映画館で見た。
3ヶ月に1回2人分のチケット買って映画館に行くのが恒例になっている。
教皇選挙かアノーラ、ブルータリスト、プロフェッショナル、アマチュア、ゲッベルスで悩んだ。この時期めちゃくちゃいい映画ばっかり。
教皇選挙行こうとしたら満員でNG、彼氏と行くからアノーラは興味無いとのことでNG、ゲッベルスは時間が合わずNG、実話ということで次点のシンシンを見た。
見てから半年くらい経ってしまったから細かいところは覚えていない、、俳優たちが本人ということでその点も楽しめた。エンドロールのas himselfはテンション上がる。普通に違和感ないくらい上手かったと思う。
あまりストーリーとしては面白くはなかったかな。実話が好きだからそこは良かったが、あまり盛り上がりや落ちるところがなくスーッと終わってしまった感がある。
エンドロールが1番感動したかも。
何十年も懲役くらって、出所した頃には身内がいないとか、子供たちが巣立っているとか、どんな気持ちなんだろう。自分は捕まるようなことはしないけど、本当に冤罪だけが怖い。しかも海外で勘違いで捕まったら最悪。
面白くなかった訳じゃないけど、映画館で見るような映画ではなかったかも。あとキノシネマ初めて行ったが、自宅のシアタールーム(プロジェクターとソファ置いただけ)並にスクリーンが小さかった。キノシネマだけで放映しているマイナーなやつとかあるから、結構この映画館は気になっていたがあまり好きではなかった。
観てよかった
好き嫌いが分かれる作品かもしれません。
「観てよかった。この映画に出会えてよかった」と思える作品でした。
スニークプレビューで、家人が見せてくれた作品だったのですが、「実話」だというし、
アメリカの重刑専門の刑務所の更生プログラムの<舞台演劇>のグループの人たち本人が本人役として、演劇グループのメンバーとして出演していて、びっくり!
主役の冤罪で刑務所に入れられてしまった黒人ディビアンGを演じたドミンゴさんは、ベテラン俳優さんで味の演技をされており、それは彼のキャリアからすれば当然なんです。が、後に相棒になる黒人服役囚ディビアンIを演じたクラレンス・マクリンさん、(なんて凄みのある、哀愁のある演技をする俳優さんだろう)と感嘆していたのですが、HIPHOPのキングのように存在感もあり、韻をふくんで唄うようにワードが出てくるアーチスティックな俳優さんで、(ハリウッドはすごい役者さんが次から次へと出てくるなあ)と思ったら、その方もこの刑務所の<舞台演劇>のグループの人(本人)だというので、本当にびっくり!!
後で公式HPを観たら、刑務所の<舞台芸術>グループメンバーとして出演していた役者さんのほとんどが<本人>だったんです。すごい!! 演技プロ! 最高にイカした人たち!
演劇は「他人の人生を演じる」ことで、人生というものや、人の心の動きを客観視する訓練ができるんだそうで、それを繰り返していると、自分の心の動きも客観的にみられるようになって、心の自己管理が出来るようになって、役作りのために「沈思黙考」する習慣や、南幅して人の人生について考えるようになって、それで、やがて自分のことも客観視できるようになって、やがて更生の道を歩みだす…ということのようです。
こんなに、心理描写が丁寧に描かれた映画、久しぶりに見ました。
私は、この映画と出会えてよかったです。
塀の外と内を隔てる鉄製の網
公開時、どうしてもタイミングが合わず、断念した作品を、u-nextの残ポイントで鑑賞。
はじめ、吹き替えで流れはじめたのだが、これは絶対字幕で見るべきやつと直感し、開始1分で、冒頭から字幕で観直したら、やっぱり届く深さが違った。
初っ端からディヴァインGを演じるコールマン・ドミンゴが醸し出す、複雑な感情の入り組んだ芳醇な演技に対して、ディヴァイン・アイの薄味加減に、最初は嫌な予感しかなかったのだが、終わってみると、それすらも演技だったのかとわかる。
折々の場面で、その時の心の動きを一番知るのは本人なわけで、本人たちが、本人たち役を演じることの意味に気付かされる思いだった。
無罪による投獄といった形で、いわゆる人種差別に起因した偏見の問題は、今作の中でも存在しているのだが、あえてそこをクローズアップせずに、「塀の外と中」の対比に特化して、「自由はあるけれども、生きづらい外界」と「制限はあるけれども、理解してくれる仲間のいる監獄」の間で揺れる登場人物たちの、立ち直りの物語にスポットを当てた展開にうなったし、作者や監督たちの秘めたメッセージの強さを感じた。
隔てているのは、向こうがはっきり見えて、外気だって変わらないはずの鉄製の網一枚なのに、なんとその先の遠いことか。
とある人物がその場から去った後、固定されたままのカメラの映像が流れ続ける数秒間も、その絶望的な遠さを見事に描き出していた。
<ここから内容に触れて書き残したいこと>
・演劇プログラムの教育的価値が、よく伝わってきた。演じるということは、他者の気持ちになって考えてみるということに他ならないし、そのためには、自分のこれまでの心の体験を掘り起こすことが必要になる。自ずと、自己の中にメタな視点が生まれ、また「脱獄しなくても外に出られる」心の自由さも獲得して、より不幸な選択肢を選ばずに済むことにつながるのだろう。そうしたことを出演者たちの姿から感じとって、「RTA受講者の再犯率は3%(公式サイトの猿渡由紀のコメントより)」いう驚くほどの数字も納得できた。
・助ける、助けられるという関係についてもディヴァインGと、ディヴァイン・アイのやり取りから考えさせられた。助けた者たちに助けられるというストーリーは、テンプレかもしれないが、やっぱり沁みてしまうし、涙腺が緩む。
このプログラム自体が、そうしたつながりを自然とつくり出していると思うし、そこへのリスペクトが感じられるエンドロールのテロップは、熱かった。
・「ここではniggaではなく、brotherと呼ぶんだ」というセリフにグッときた。
自嘲的な物言いは、それを乗り越えた強さの表れにも見えるし、自分でもそう思って使っているのだろうが、やっぱり自他を傷つけるナイフなんだと思う。
全ての出発点は、相手へのリスペクト。
・「フェーム」と「アイリーン・キャラ」という言葉に反応してしまった。懐かしい…。
感じたことメモ
最初からこんな自分になりたかったわけじゃなくて。
抜け出そうともがいたり、諦めたり。
相手を思ってやっていても、いつまで人の背中を見送る自分を保てるのか。納得させられるのか。
私なら腐ってしまいそう…
楽しみたい自分がいる一方で、そんな自分を客観的に見て疑問を抱く部分とかも良かったな。
生か?死か?ソレが問題だ。
ムショ慣れしていく中で、心を鈍らせて生きる屍と化すか?
演劇を通して、
《自分ではない誰かになりきる》事で、否が応でも己と向き合い、苦しみながら《人間》を取り戻す道を選ぶか?
万雷の拍手を獲て感じてしまった刹那の自由、心の解放。
馴れきって当たり前になっていた刑務所の臭いや雰囲気に違和を感じる…
手に入れた鈍感を捨てるのは辛いだろう。
然し、冒した罪を贖いたいのなら、向き合う苦しみを対価にせねば、本当の反省なんて心の内から滲み出る訳ない。
苦しいからこそ喜劇を!
諦めってのは………未練を残すんだよ
悪くはないけど・・・。
本物は迫力が半端ない💦
登場人物たちが、実際の囚人を起用とは
2018年「暁に祈れ」を思い出させます。
罪を背負った囚人たちが
少しでも外界との繋がりに思いを馳せ
別人を演じる事で、一時的に心は解放され
母のもと、子供たちのもとに飛んでいける
その時だけは自由に思想を馳せることが出来る喜び。
無実の罪で収監されているディヴァインG が
いつか無実を証明できる
善良でありさえすれば、誰かの手本になるような
存在であり続ければ、いつかは仮釈放が
認められると信じていた彼の
それが叶わなかった時の
絶望感と虚無感に苛まれる姿は痛々しい。
ぶつかり合いながらも、いつしか深い絆で
結ばれていた仲間との友情はこれからの人生の宝物
シンシン SING SING
全136件中、1~20件目を表示