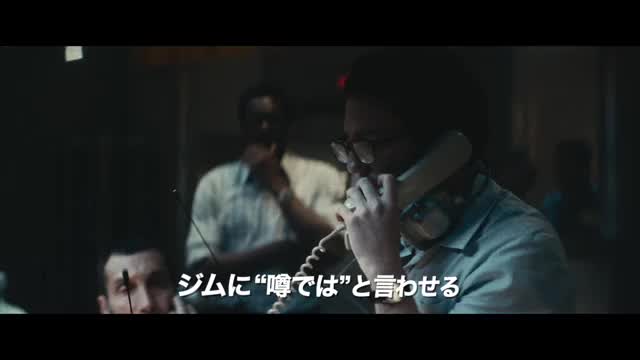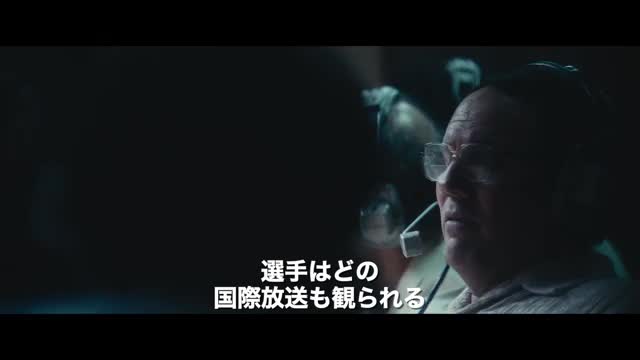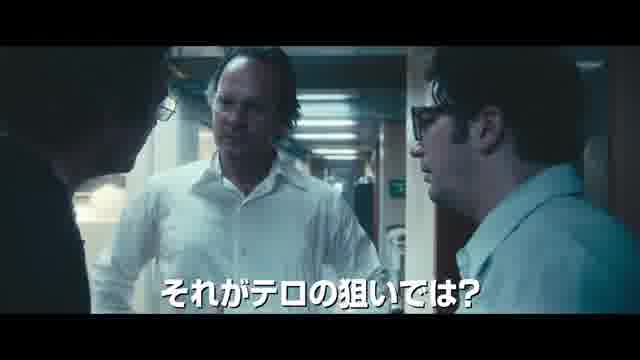セプテンバー5のレビュー・感想・評価
全197件中、161~180件目を表示
薄味で物足りない密室劇
これまた予告篇との落差の大きい作品だった…。
予告篇には「今年最高の緊迫感」とあるけど全然緊迫感がなくて寝落ちしてしまいそうになる。
まあ自分たちに危険が迫ってるわけじゃないし、人質を助けるために奮闘するわけでもないので仕方ないけど。
スポーツ局のスタッフが予想外の出来事にバタバタしてるだけの90分。
テロが起きても隣で試合を続行してる70年代の危機意識の低さを確認した映画でした。
コンパクトな脚本の見事さ
ミュンヘンオリンピックの時、小学2年生だった私も、選手村での人質事件は何となく覚えている。また、同じような時期にあった浅間山荘事件の生中継も、楽しみにしていた番組が潰れてガッカリした記憶と共によく覚えている。
どちらも半世紀以上たったが、今も記憶に残っているのは、事件の大きさもさることながら、テレビでの中継映像の衝撃があったからだろう。
本作は、そうした、急速に普及が進んだテレビメディアが与えた影響と、何をどこまで伝えればよいのかという現場の模索について、当時の映像の手触りそのままに描き出すというスタイルを取りながら、実は今も答えの出ていない問題を私たちに投げかけてくる。(それも、スリリングなエンタメ作品として)
自社内でのイニシアチブ争い、警察との攻防、他局との駆け引き、スクープとファクトチェックとの葛藤などの他にも、ジェンダー差別や他宗教他民族へのマイクロアグレッションなどを織り込み、加えて、西ドイツという国家が、ナチスへの反省という点から、どれだけイスラエルに気を使ってきたのかまでもが、コンパクトに95分で描かれる脚本の見事さは、アカデミー賞ノミネートも納得。
今はやっと停戦しているが、ガザでの民族浄化とも思えるイスラエルの過剰な攻撃が報道されてきた中にあって、どうしてドイツはあんなに強固にイスラエル支持を貫くのかが個人的にはとても疑問だったが、ホロコーストだけでなく、こうしたパレスチナのテロ組織に起因した政府の失敗の記憶の累積も影響しているのかと思ったら、肯定はできないが少し納得した。
それにしても、テレビがオールドメディアと呼ばれ、個人のネット配信が当たり前になってきている中で、報道規範という部分は、これから更に大きな課題になると思う。でもそれは、視聴率や閲覧数などで利益が発生する仕組みの中では、作り手側の問題というより、受け手側の私たちが何を選んで何を観るかという問題なんだろうけれど…。
重い…
メディアの本質は『ショウタイムセブン』にも通ずる・・・と思いました
事実の事件の顛末を描いた作品ですが、
メディアの在り方については、『ショウタイムセブン』を思い出してしまいました。
やはり、スクープは独占したいのかな・・・とか、
「噂」でもいいから報道してしまうあたり、ちょっとどうなの!?と考えた次第です。
残念な結末に至った事件自体にもスポットは当たっているものの、
なぜ解決できなかったのか、ということよりも、私はやはり報道の是非が
本質的に伝えたかったことなのかなと感じました。
事実に基づきテロ事件を追うので、90分くらいの長さの映画とはいえ、
結構疲れてしまいます。それだけ緊迫感がありますし、遊びがないと言いましょうか、
ずっとシリアスなんですよね。当たり前ですがそれが疲れたりするんですよ。
主要キャラクターも最初は見分けがつきずらく、誰が誰なんだか頭の整理をつけるのに
時間がかかりました(笑)
その中でも通訳マリアンネがカッコよかったですね。
演じたレオニー・ベネシュは『ありふれた教室』で主演でしたね。
さすがの演技でした。
というわけで、エンターテインメントというよりも、実にシリアスなドキュメンタリータッチの
作品で、私は期待通りでした。
限られたステージの中でこれだけの緊張感を出すのは見事
糠喜び
評判が良いのと事件発生当時、私自身小学生でした。子どもごころにオリンピックで何故?と思っていたのでその当時の様子のことを知りたくて11:00から観ました。なかなかの作品です。1972年ミュンヘンオリンピック開催中に発生したパレスチナの過激派によるイスラエル選手団の人質事件を題材としたドラマ。オリンピックの衛星中継を担っていたアメリカABCテレビが、テロ事件の推移を全世界に実況中継する。ドキュメンタリーのような地味なつくりがリアリティを増していた。ニュース報道の専門家ではないアメリカ人スタッフ、責任者は視聴率、特ダネという誘惑と人命がかかっているという経験したことのない深刻な状況下で瞬時の判断を迫られ、緊迫感を持ってカメラを切り替え映像が繋がれる。迫害されたユダヤ人側から描かれることが多かったホロコーストがドイツの一般の人々の心に残した傷跡を伺わせる言動がストーリーに重みを加えている。ダイヤル式電話機、チャンネル型テレビ、無線機、喫煙…当時を彷彿させるアイテムが印象に残った。ドイツ人女優レオニー・ベネシュがテレビ局の現地ドイツ人スタッフとして活躍する演技が良かった。結果は…。当時のことに興味がある方は、観て損しない作品です。
正直辛い
ジャーナリストとしての功名とすり減った倫理観
ジャーナリズムの本質は変わらない。それをまざまざと感じてしまう。
人質事件を知った放送クルーがとった行動というのが、スクープ(報道の一番乗り)への体制作りと情報の独占化。
彼らが商業メディアである以上、その行動は至極当然だと思うが、報道の使命というキレイな服をまとって自身の行動を正当化するプロセスが、描かれる。
独断でスクープを放ったスタッフは、結果オーライでお咎めなし。史上稀に見る視聴率ということでトップもご満悦。
その後の検証は、するわけないよね。当時だし。
彼らが良心を全部捨てているわけではなく、大学で学んだであろうジャーナリズム論を頭の片隅に置いて行動している。
ジャーナリストとしての功名とすり減った倫理観を天秤にかけながら事件と対峙する様子が、客観的に描かれている。
週刊文春と望月記者の言説が象徴的で、訂正はするが謝罪はしない。
結局のところ、いろんな報道を自分の頭で再構築して理解するしかないよね。
サンシャイン作戦
視聴率と人命
1972年ミュンヘンオリンピック開催中に発生した、パレスチナの過激派によるイスラエル選手団の人質事件を題材としたドラマです。
オリンピックの衛星中継を担っていたアメリカのテレビ局が、テロ事件の推移を全世界に実況中継することになります。
まるでドキュメンタリーのように、音楽なども最低限に抑えられた地味なつくりがリアリティを増していました。
ニュース報道の専門家ではないアメリカ人のスタッフたち、責任者たちは視聴率、特ダネという甘い誘惑と、人の命がかかっているという今まで経験したことのない深刻な状況の中で瞬時の判断を迫られて揺れ動きながら、さながら「カメラを止めるな!」のごとき緊迫感を持って次々とカメラを切り替えながら映像が繋がれてゆきます。
また、これまでは迫害されたユダヤ人側から描かれることが多かったホロコーストがドイツの一般の人々の心に残した傷跡を伺わせる言動の数々がストーリーに重みを加えています。
ダイヤル式の電話機、チャンネルを回すテレビ、携帯無線、喫煙…1972年当時を彷彿とさせる、もはや博物館級となってしまったアイテムが印象に残りました。
若い世代の人は「これは何?」という印象を持たれるかもしれません。
映像にキャプションを入れる方法のアナログさ加減ときたら仰天ものです。
「ありふれた教室」で主役の女性教師を演じたドイツ人女優、レオニー・ベネシュがテレビ局の現地ドイツ人スタッフとして熱演。素敵でした。
事実を知る事は大切 噂は・・・
1972年9月5日、ミュンヘンオリンピックでパレスチナのテロリスト集団・黒い九月がイスラエルの選手村を襲撃して2人を殺害、9人を人質にとって宿舎に籠城し、イスラエルに拘束されていたパレスチナ人や囚人など、300人以上の解放を要求した。やがて交渉は決裂して空港で西ドイツ警察による救出作戦が行われ、銃撃戦や犯人の自爆攻撃が起き、噂によると、人質全員無事解放された、とABCは放送したが、実は・・・そんな史実に基づく話。
ミュンヘンオリンピックは、水泳のマーク・スピッツの活躍を当時のテレビで映していたが、日本も平泳ぎの田口や体操、バレーボールなどで盛り上がったと記憶している。
その裏で、テロ事件があった事は日本で報道されたのか、あまり覚えていない。ミュンヘンの前、同年冬の札幌オリンピックが有り、スキージャンプやフィギュアのジャネット・リンで盛り上がった直後に日本赤軍によるあさま山荘事件が起きたが、あの時の鉄の玉で山荘を壊す映像が印象に残っている。
前置きが長くなったが、本事件はそんな時代の話で、世界中が注目する平和の祭典オリンピックを利用した卑劣なテロで、結果として合計17人(人質9人含む選手とコーチ11人、警察官1人、犯人5人)が死亡する大惨事となった。
それをABCの報道クルーじゃなくスポーツクルーが中継した。そのためか、情報は錯綜し、一旦は人質全員無事解放との噂が流れ、それを報道したが、誤報で、事実は人質全員死亡だった。
これを事件として知るのは良いが、ほとんどオリンピックの報道センターのようなところだけで、視聴率や、情報の裏どり、といった放送局目線での進行であり、デジャブ感で先週観たショウタイムセブンの阿部寛を思い出した。
途中眠くなったし、個人的にはあまり刺さらなかったが、これはこれでいいんでしょうね、くらいの感想。
イスラエルとパレスチナの争いはガザでみられるように現在も続いていて、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、と宗教絡みの憎しみは根が深いのだろうと、改めて思った。
9月5日
この時期に突きつけられる
メディアリテラシーについて
緊張感が凄かった
だれの事件
だれの責任?報道の功罪。緊迫の映像と、1時間半の短い尺を無駄にすることなく濃密な時間で駆け抜ける編集で、報道の義務と責任を描く実話モノの報道スリラー。"実話"モノとは言っても、例えば『大統領の陰謀』や『ペンタゴン・ペーパーズ』のように報道のあるべき姿(可能性)と格好良く英雄(ヒロイズム)的な面を映し出したタイプの作品ではない。無論、事件の顛末的にそうなるわけないのだが…。
本作はむしろ最前線の事件の周りであれこれ動き回って余計なことをして"遊んだ"結果、事件の展開を悪くさせることこそすれど、良い方向への影響は決して及ぼしていない報道の功罪についてだ。そんな、テレビ史上に残る悲劇・惨劇を驚くべき再現度とリアリティで再訪・追体験する1日。よく書かれた脚本と恐ろしく手際のいいストーリーテリングで、舞台劇・密室モノ的に報道室で繰り広げられる手に汗握る展開に釘付け!
「事件は現場(選手村)で起きてるんじゃない、ニュースルームで起きてるんだ!」的な驕り・思い上がり(?)から、それがどういう結果を招くかという職業倫理的な部分や後先のことは考えず(無視して)、自分の仕事をしているだけと飛びついたがための結果。ジョン・マガロがそんなニュースルームを瞬時の判断を迫られる切迫した状況の中で統率し、『ニュースの天才』がどうしても頭をよぎるピーター・サースガードが喝と指示を飛ばす。
初めてのことをやり遂げた人々へのリスペクトが感じられない
人質事件の現場や、それを取材するテレビクルーの様子などは一切映されず、テレビ中継の調整室と、それがある建物から画面が離れることはない。
そのため、まるで、スタッフの一員になったかのような臨場感と緊迫感が味わえるし、密室での閉塞感もひしひしと伝わってきて、観ているだけで息苦しくなってくる。
それに加えて、外部との連絡手段が、トランシーバーと有線電話と電報しかなく、おまけに、ドイツ語が分かる通訳が1人だけという状況で、欲しい情報が手に入らないもどかしさと、焦燥感も追い打ちをかけてくる。
人質が処刑される瞬間を放送しても良いのかと悩んだり、テロリストに警察の情報を与えてしまっていることに気付かなかったりと、史上初めてテロを生中継することになったスタッフたちの葛藤や失敗も生々しい。
極めつけは、事件の結末に関する「誤報」で、スクープをものにするための迅速性の追求と、複数の情報源による信憑性の確認という、ジャーナリズムの永遠の課題が、ここでも胸に突き刺さってくる。
エンディングでは、登場人物たちの疲労感と暗澹たる気持ちが痛いほど実感できるのだが、その一方で、仮に、事件が無事に解決されていたならば、彼らもこれほど落ち込むことはなく、むしろ、初めてのことをやり遂げたという達成感を得たのではないかと思われる。
その点、せっかくテレビマンたちの奮闘ぶりを描いておきながら、テロの生中継のマイナス面ばかりが印象に残り、その意義や功績がほとんど感じられなかったことには、やや釈然としないものが残った。
インターネットが普及した今の時代にも通じるマスメディアの問題点を、批判的に描くのは大いに結構だが、史上初の難題に取り組んだ先人たちに対するリスペクトが、もう少しあっても良かったのではないだろうか?
25-023
オリンピックのはずが
事件については全く知らない、親から聞いたこともない
特殊部隊か報道スペシャリストが5人?と思ったら日付
TV局生中継の慌ただしさ、事件の成り行き終始ヒリヒリしたムードで見るというか、見守っていた 現場の皆さん臨機応変でその場その場で判断下すの難しかっただろうな
報道に関する問題だけじゃなく?過去の事件、メガネの渋いおじさん達が奮闘するお堅い雰囲気でしたが、ユダヤとドイツとかイスラエルとパレスチナとか今尚起こっている問題にも触れてるようにも感じました
しかしあんな凄い灼光でその情報、えーっと思っていたら...
全197件中、161~180件目を表示