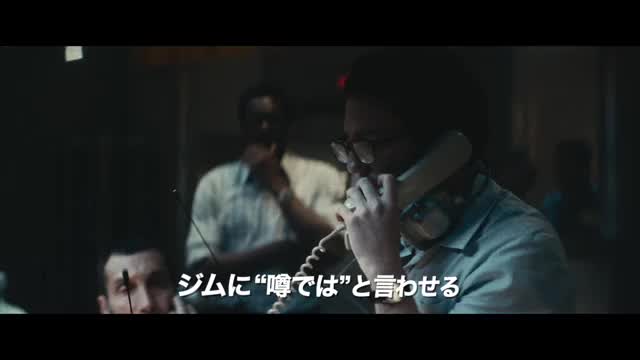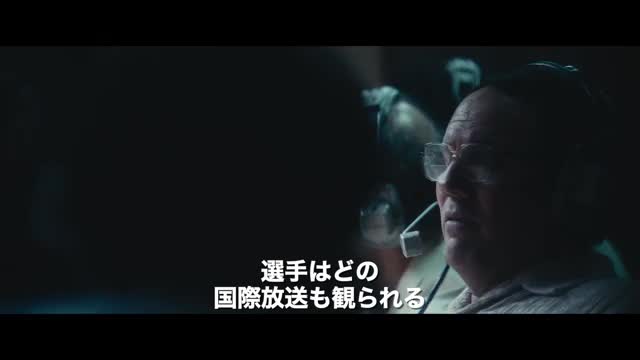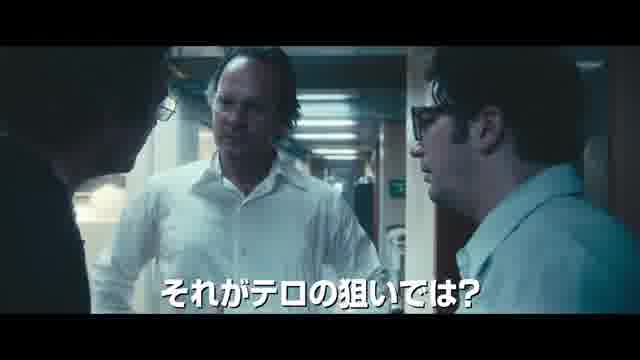セプテンバー5のレビュー・感想・評価
全197件中、141~160件目を表示
実話ベースだからなのか、期待通りに展開しない
ミュンヘンオリンピック、日本男子バレーが8年計画?で金メダルを目指し宣言通りに世界一に輝いた熱狂の舞台で、こんなことが繰り広げられ、しかも協議は中止せず、まるで平穏無事化の如く「平和の祭典」が幕を閉じたとは……
キャストには「ありふれた教室」の先生が通訳役で出ているじゃない!製作にはショーン・ペンが名を連ねている。
対テロの収束方法の是非はさておき、局面局面における瞬時の決断を迫られる面々の葛藤はよく描き出されていたと思うし、まだまだ戦後・分断されたままのドイツの世界へ向けての「見栄」、そしてアナログな時代での通信方法など、観ている最中にいろんなところに感情移入できてモヤモヤしたり憤怒したり、悲嘆にくれたり、緊迫感が持続する作品でした。
分断が進む今の世の中に不安を強くもしました。
その日、二十時間の顛末
尺が共に百分弱との共通項を始めとし、
一週前に公開の邦画〔ショウタイムセブン〕と
かなり重なる部分が。
勿論、先の作品は{フィクション}、
こちらは{ノンフィクション}との違いはあれど。
放送の現場で
突然訪れたまたとない機会に
臨機応変に対処する中で、
数字や栄達を求める態度や、
事実を報道することに向き合う姿勢が
独特のスピード感で描かれる。
とりわけここでは、
制作陣がワンチームとなり
以心伝心で一つの有機体のように機能し事に当たる。
観ていて胸のすく思い。
1972年は、
イスラエルに対するパレスチナの武装組織による抗争が
とりわけ多くあった年との記憶。
5月8日には「黒い九月」による
「サベナ航空572便ハイジャック事件」。
その失敗を受け5月30日には
「日本赤軍」による「テルアビブ空港乱射事件」。
そして9月5日の、やはり「黒い九月」による
「ミュンヘンオリンピック事件」へと繋がる。
それを衛星中継で全世界に配信したのが
アメリカ「ABC」のスポーツ番組制作クルー。
まるっきり畑違いのフィールドも、
目の前の好餌は逃さずとの
ジャーナリストの本分を剝き出しに、
知恵と駆け引き、コネクションを駆使し
放送を継続。
人質が中継中に射殺されたらどうするのか、や
テロリストも自分たちの映像を見て情報収集しているのではとの、
生放送故の葛藤のエピソードも挟み込まれる。
その時の緊張感に満ちた副調整室でのスタッフの表情は
ドキュメンタリータッチの本作の中でも白眉。
一方で眉を顰めるのは、
政治や組織が絡むうさん臭さ。
テロ事件が起きても、当時のIOC会長『ブランデージ』は
オリンピックの継続を指示。
方や、命の危険が迫るイスラエル選手団をよそに
非日常の祝祭が何事も無かったように同衾する。
『マーク・スピッツ』は七つの金メダルを獲りながら、
身の危険を感じいち早くアメリカへ帰国したというのに。
そして最終盤での、人質全員解放との噂や広報発表。
当然、悲劇的な結末を我々は知っているのだが、
何故にこうした情報が流されたか。
現代にも繋がる、情報操作のテクニックを見る。
報道する際に、複数のソースに当たる必要性は
メディアには当然求められるも、
受け取る側もリテラシーを高く持たねばならぬことを改めて認識する。
最後の場面での、えも言われぬ余韻も
やはり近似さを感じさせる要素。
一つの事件が終わっても、
明日はまた異なる報道に当たらねばならぬ。
耳目を集める、
新たな出来事が画面を席捲するかもしれないのだ。
怒涛の90分、疲れた。
映画館で見る「娯楽か」というと微妙だが、観る価値はある作品
今年55本目(合計1,597本目/今月(2025年2月度)18本目)。
この映画のストーリーの大半は実史にとったものであり、何ならこのときの報道はギリギリNHK他でもドキュメンタリー番組でも見ることができるし(いわゆるNHKプラスのお話(権利の関係で放送から1週間まで)。静止画像ならいつでも見られる)、一定年齢以上の方は「そういう事件もあったっけ」で知っている方も多いと思いますが、この問題の背景は宗教論も絡んでおり、一般の民放が扱うことが少ないため、実質的に「お堅いNHK」しか扱わず、よって知らない、あるいはそもそも論で「NHKを見ない」人も一定数いますので、それをまたまとめなおして映画館で流す意味はあるんだろうな、といったところです。
結局のところ、安全を重視した体制にするのか(日本では、いわゆる立てこもり等は、犯人がテレビを見ていることも想定できるため、これらは強くは報道しない)、あるいは、憲法のいう「取材・報道の自由」を優先するのか(他国においても同趣旨の規定は、通常、憲法典の中にはあります)という2択論の話であることは誰でもわかるとして、映画内で描かれていたこともまた理解できるし、逆の考えも一つまた理解できるし、「あなたならどうする?」タイプの問題提起型の映画と解することも可能です(ただ、日本において、NHKなり民放なりのそこそこ「放送にかかわれるレベルの社員」になれるほどの人が、毎年何人就職しているのか、という実際問題はありましょうが)。
特に他の方も描かれていた通り、何をもって悪として善とするかという善悪論には基本触れず、ただ単に当時の事情を描くということに徹した点は、悪く言えば「眠いタイプの映画」ではありますが、問題提起型の映画とも解するなら一定の思想を強制するのも問題で、あえてここをぼかした本映画はやはり広い意味での問題提起型の映画というところで、決して「楽しい」映画ではないでしょうが、「教養アップには」良いのかな、といったところです。
採点上特に気になる点までないのでフルスコアにしています。
--------------------------------------
(減点なし/参考(映画館帰責事由)/menuクーポンをひたすら渡されるのが謎すぎる)
まぁ、ここに投稿される方は多かれ少なかれこの点は気にされているのではと思いますが(中には、地方でアプリ(というより、menuのサービス)の提供サービス外でも配っている模様。よって、もらって帰って何か頼もうとすると「エリア外です」と言われたりする模様)、まぁ、2本映画を見て、一度出てまた入るとき、また配るの??っていうのもアレですが、最近はいわゆる入場者配布特典が週替わりするなど色々ありますが(最近の例だと「メイクアガール」)、その中に「忍び込ませてでも」渡そうというのは、それもそれでどうなのか…といったところです(ゴミ箱に、ポップコーン等以上にそれらが捨てられている光景を見るにつけ、紙資源の無駄遣いなのでは…といったところ)。
--------------------------------------
世界がそれを目撃した日。
映画「ゾディアック」を観たときと、非常に似た気持ち、感触。
これから観る方は、事実に基づくドキュメンタリーとして、観てほしいと思う。
-----
当時の技術、仕事ぶりの再現は、素晴らしいものがあった。
半田付けして、その場で、線をつなげちゃう。とか
写真を新たに撮影して、拡大した写真にする。とか
テロップ入れがアナログ。スロー映像もアナログ。等々
主にキャスター、レポーターに光があたるが常だが、
技術スタッフ、管理職、裏方に光があたっているのが良い。
また個人的に、音楽表現も凄いと感じた。
------
私は、恥ずかしながら、この事件を知らなかった。
鑑賞後、某国で飛行機テロが起こった際、
テレビをずっと観ていた自分のことを、ふと思い出した。
世界がそれを初めて目撃した日。
その日を境に、多くのことが変わっていく世界。その後の追及と、復讐。
この 9/5 も、きっと、そういう瞬間だったと想像する。
「生放送するべきだったか!?」という問いにも、賛否はありそうだ・・。
現在の世界情勢を考えると宣伝しづらいのか目立っていませんが、イスラ...
報道の責任
ABC対CBS
その後の報復合戦が終わらない
セプテンバー5
事件が現在進行形の中で、
場面が変わるたびに、ジャーナリストとしてのコンプライアンスと被害者関係者の人権や会社関係者との調整を配慮しなが実況中継を継続していく執念と機転が、スタッフ全員が見事に展開していく様は見ていて爽快だった。
ただ、全員死亡という現実を1人帰宅する車の中で、
ルーンはどの様に走馬灯を振り返っていたのだろうか?
そして、この事件以降もそれらの報復合戦が今も繰り返されている今を思うと9月はやばい月かな?
黒い9月
若い頃、事件の数年後に期せずしてミュンヘン空港内を乗換移動したこたとがある。
事件のことなどすっかり忘れていたが、空港ロビーを一歩出るとそこは戦場の様な機関銃を肩から下げた兵士が幾重にもいて、何度も検閲を受けた記憶がある。
それは、ミュンヘンオリンピックテロ事件によるものだと直ぐに分かった。
その後も報復合戦は繰り返されて、
9月11日に繋がったのか?
(^ω^)
1972年のミュンヘンオリンピックで起きたパレスチナ武装組織によるイスラエル選手団の人質テロ事件の顛末を、
事件を生中継したテレビクルーたちの視点から映画化したサスペンスドラマ。
「HELL」のティム・フェールバウムが監督・脚本を手がけ、報道の自由、事件当事者の人権、報道がもたらす結果の責任など現代社会にも通じる問題提起を盛り込みながら緊迫感たっぷりに描く。
1972年9月5日。
ミュンヘンオリンピックの選手村で、パレスチナ武装組織「黒い九月」がイスラエル選手団を人質に立てこもる事件が発生した。
そのテレビ中継を担ったのは、ニュース番組とは無縁であるスポーツ番組の放送クルーたちだった。
エスカレートするテロリストの要求、錯綜する情報、機能しない現地警察。全世界が固唾を飲んで事件の行方を見守るなか、テロリストが定めた交渉期限は刻一刻と近づき、中継チームは極限状況で選択を迫られる。
出演は「ニュースの天才」のピーター・サースガード、
「パスト ライブス 再会」のジョン・マガロ、「ありふれた教室」のレオニー・ベネシュ。
第82回ゴールデングローブ賞の作品賞(ドラマ部門)ノミネート、
第97回アカデミー賞の脚本賞ノミネート。
セプテンバー5
September 5
オリンピックでテロ事件が起こっただなんて…この事実を知らなかったの...
1972
スポーツ番組のスタッフ達が、ミュンヘンオリンピックで実際に起きたテロ事件に遭遇し、選手村で人質を取ったテロリストの報道に奔走する姿を描いた作品。 本年度ベスト!
冒頭はミュンヘンオリンピックの中継の様子が描かれ、お仕事映画のような雰囲気。
それが銃声が聞こえた瞬間、空気が一変!
背筋が凍り付くような緊張感で息つく暇もない展開に釘付け(笑)
テレビ局のディレクター、ジェフを中心に展開するストーリー。
テロリストが選手村で人質を取り立て籠る中、ジェフは中継を報道番組のスタッフに引き継がず、自ら陣頭指揮を執り、生放送で世界に情報を発信しようする展開。
「そこにカメラを!」「この角度から狙え!」 ジェフが的確に指示を出す姿は、緊迫感の中でも冷静にプロとしての誇りを感じた(笑)
通訳の女性も、人質となった選手たちの情報を迅速に収集し、スタッフと連携する姿が印象的。
受話器と無線を両手に持ち、情報を収集するジェフの姿が熱い!
情報が錯綜する中、視聴者に一早く真実を伝えたいジェフと、真実のみを伝えようとするプロデューサーとの間で激しいやり取りが繰り広げられるシーンが印象に残る。
報道の使命と倫理の間で葛藤する彼らの姿が心に深く突き刺さる。
先の読めない展開に引き込まれ、息を呑む衝撃的な結末を迎えた時は最近観た映画の中でも群を抜いていた感じだった!
テレビ画面に映し出されたテロップは、現代のデジタル社会からは想像もできないほど原始的な方法に驚きました( ´∀`)
デマが蔓延る現代人から見れば、ある意味「牧歌的」「良心的」な時代
本作のテーマは明確。
「マスコミの役割とは」だろう。
でも「答え」が提示されるワケではなく、彼らの葛藤描くことで、観客一人ひとりがそれについて考えることになる。
本作が現代に作られた意味、意図とは?
例えば20年前なら?
単なる「昔話」で終わってしまったのではないだろうか?
20年前との違いは「SNS」と「デマが蔓延る」こと。
本作の葛藤は現代のSNSではあり得ない。(現代のマスコミもないかも)
「良心」と「報道」の葛藤があった、
そして事件の結果に責任を感じる、という両方の意味で「牧歌的」だと思う。
あとは当日は中継するには機材と衛星の枠が必要で、だからこそ「本気度」が違ったのかな、と。
「俺達が撮って世界に届けるんだ」っていう気概があった。
今のSNSにそんなモノがあるだろうか?
葛藤も気概もないよね。
「報道」(SNS含む)の価値を見つめ直す作品だと思う。
マスコミが ますゴミ🗑️で無かった時代。
俺もこの時代ギリ覚えてる
NHKは 商品表示に巻紙をして隠し
特定の 私大の宣伝 コメンテーター 特定の私大の字幕はなかった。プロデューサー等の出身校
学歴番組もなかった。
先週Q9様マジ酷かった ふかわの背景に物凄くデッカく ・・・・大学 ダヨ 恥しれよ❗️東大特集なのに
そして な・ツネみたいな勘違い政治野郎もいたけど
基本的に 特定与党の 提灯持ち🏮報道は少なかったと思う なんで 選挙で惨敗負けた敗軍の将 持ち上げる❓
そう あくまでも今のますゴミ🗑️と比べれば
皆 情報の最先端を行っている 矜持があったように思う
権力への批判精神あったと思う
そんな古き良き時代のマスコミ作品。
全てが全て真実では無いだろうけど 美化もあるだろうけど
骨格は真実だと思う。
刻々と迫る状況に 真摯に対応するテレビ局マン に共感
ミュンヘン五輪での事件 と言えば
スピルバーグのメジャーな作品 タイトルそのまま 007ダニエル・クレイグの出世一歩手前 ホップ・ステップ作
があって 俺も勿論 観てるが
そもそも 作品の作風の前に 時系列が違う記憶が
🈶有料パンフは 制作無し
確かに 繊細な重いテーマ事実だから 意図的に制作しなかったのが理解できる。
まあ 俺は結果知ってるし ウイキペディア見れば結果は誰でもわかるから
『でも リアルタイムではどうなんだ❓』的な緊迫感のある作品 手に汗握る💦
後半の方は たぶん 報道陣厳重に規制されてて 撮れなかった部分 ということかもな
報道のあり方 というより 報道の原点を観た。今のますゴミ🗑️なら 陰で笑って放送してるだろなぁ
観客 上映回数絞ってるから 超🈵満員 隣の人の息吐く音がうるさかった でも 吐くなとは絶対言えないから
じっと我慢の子 😣 の俺だった。 スリリング作品 良い点は一回の鑑賞で済むこと
ちなみに 俺は 結構 学歴だけはあるけど 今の 放送姿勢は不満😑です 要するに 上から目線
人質救出作戦を米国テレビ局が生中継でテロリストに見せて死なせた‼️❓
全197件中、141~160件目を表示