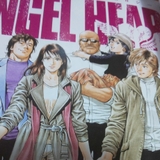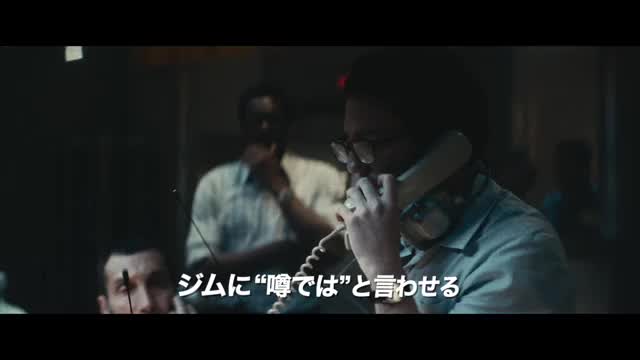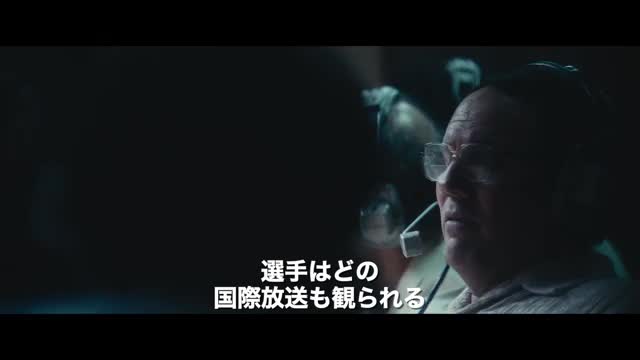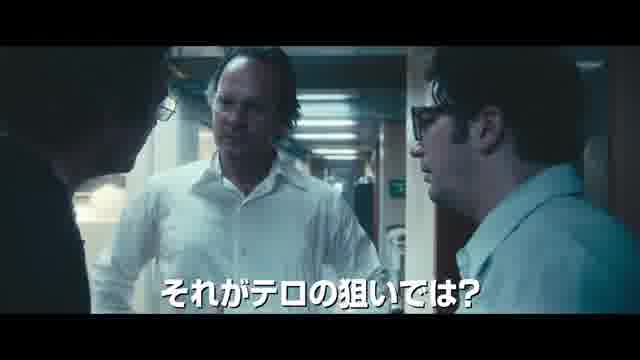セプテンバー5のレビュー・感想・評価
全197件中、181~197件目を表示
構成の妙
物語の最初から最後までオリンピックの生放送の中継基地の視点のみで話が進むのに中弛みせず飽きさせない構成は見事
恐らく当時の実際の報道の素材も使ったであろう映像も良かった
当時の番組製作の裏側っぽいモノも垣間見えてそこも良かった
テレビマン全員がプロ意識もった職人集団みたいでかっこよかった
でも名前と顔が一致しないまま声だけの出演になるキャラがいたり
視点は中継基地で固定なのにキャラは事件現場各地に行ったり来たりするから
全体像が若干わかりにくい部分もあった
それから1972年当時の世界とドイツを取り巻く環境をあらかじめ理解してないとピンと来ないやり取りが多少あって
人によっては物語に入り込む妨げになるような気もした
さらに今では当たり前の報道協定だとかも当時はなかった事を理解しておく必要がある
躊躇、葛藤、達成感、後悔……
当時の緊張感を再現した、フィルムの作り方がすごかった。
中継スタッフによる、「これを放送していいのか?」とか、「死人が出た責任は我々にないのか?」という躊躇、葛藤、達成感、後悔……ドロドロした感情が次々に描写されて、引き込まれました。
まだ世界がテロに初心(うぶ)で、西ドイツは第二次世界大戦の反省から極度の平和主義を定めた憲法で他国の軍や警察を受け入れないことを定めていたため、訓練されていない町の警察官たちが対応し大惨事へ発展って展開だった模様。
もちろん、報道管制とか、犯人の立てこもるビルの電気を落としてTV中継を犯人に見せないなどのノウハウもなく。
各国の警察にテロ対策チームが作られ、オリンピックや各国際イベントでのテロ含めた警備体制が構築され、選手村や施設には関係者以外立ち入り禁止となった今に至る、きっかけの事件だったらしいですので、その歴史を知るという側面でも有意義な作品でした。
裏はしっかり取ろう
とにかく地味、ひたすら地味な作品。でも、『スポットライト』や『記者たち~衝撃と畏怖の真実~』といった報道メディアの実録もの映画が大好きな者としては大好物。知る権利、報道のモラル、被写体の人権など、テーマの切り口はさまざまなこの手のジャンルは普遍ゆえに現在でも通じる。折しも本作で扱われる人質テロ事件も、終わりの見えないパレスチナ・イスラエル紛争とリンクしているわけだし。
この事件が複雑なのは、発生地がドイツのミュンヘンという点。ナチスの影を払拭すべく、人質となったイスラエル選手団救出を半ば“贖罪”とイコールにしたドイツ。ところがその結末があまりにも皮肉。
「裏を取る」のはマスメディアに携わる者としては怠ってはならない作業。しかし昨今はフェイクニュースという言葉が独り立ちしてしまうほどになっている。一応メディアに属する者として、本作のABCスポーツ番組クルーは他人事としては見られない。
ただ残念なのは劇場用パンフレットが作られなかった事。前述したようにこの事件は今のパレスチナ・イスラエル紛争ともつながっているのだから、事件が起きた背景を網羅したパンフはあっても良かったのでは。
【”リアル、テロ・ライブ”ミュンヘン五輪で起きたイスラエル選手人質事件を生中継するアメリカABCクルーの、視聴率か人命かを問いながら放送する臨場感が凄く、ジャーナリズムの在り方を問う重き作品。】
■1972年9月5日。西ドイツ、ミュンヘン五輪の開催中、選手村でパレスチナ武装組織”黒い九月”は、パレスチナ人テロリスト500人の解放を要求し、選手・コーチ二人を殺害し、残り9人を人質として立てこもる。
その様を、アメリカABCスポーツクルーは、世界に向け生中継するのである。
◆感想
・中継を担当したのは、報道クルーではなくスポーツクルーである。専門ではない彼らはそれでも、報道する責務と他局との視聴率争いとの狭間で揺れて行く。
・西ドイツ警察は中々機能しないし、苛苛する中、彼らはドイツ人女性スタッフを通訳にし、更にはスタッフを選手村に潜入させスクープを撮影しようとする。
■だが、スポーツクルーたちは、途中で自分達が映しているTVが、選手村の部屋でも観れることに気付き、西ドイツ警察が放送を止めようとしても、彼らは一時は放送を中断するが直ぐに再開するのである。
選手たちが、テロリストたちと空港に向かい、銃撃戦になった時に、彼らはスタッフを空港に向かわせる。
そして、選手たちが救出されたという連絡が入り歓喜するが、それがあやふやな情報だと分かり翻弄される姿が、生生しい。
<ラストは、異様に重い。結局人質は全員死亡という連絡が入るのである。本作は、ミュンヘン五輪で起きたイスラエル選手人質事件を生中継するアメリカABCクルーの、視聴率か人命かを問いながら放送する臨場感が凄く、ジャーナリズムの在り方を問う重き作品なのである。>
■尚、この事件後、イスラエルの諜報機関モサドが、パレスチナに行った苛烈なる復讐劇はスティーブン・スピルバーグ監督の逸品「ミュンヘン」で描かれている事を、敢えて記す。
ものすごい緊迫感だけど
オリンピック開催中に発生したテロ事件を、警察でも、犯人でもなく、報道目線で描いています。
スマホもない、デジカメもない、ネット回線もない時代。情報も限られているが、事件は目の前で起きている。なんとしても報道したいという思いと、かたや、報道すべきか?という葛藤も含めて、緊迫感がひしひしと伝わってきます。
一方で、事件が最悪の結果を迎えた中、現場を仕切っていた人たちが、どんな気持ちだったのか、特に、現場を任されていた主人公の心情も、もう少し描いて欲しかったと思います。皆さん、報道の現場の人間とはいえ、元々、スポーツを担当するクルーだったわけだし、悲しい結果に、尋常な精神状態ではなかったと思います。
ドイツ人のスタッフは、最後に、大丈夫か?と尋ねられて、気持ちを語る場面がありましたが、それを尋ねていた責任者も、上司から、明日も頼むと言われて、はい、わかりました・・・だけではない、ものすごく複雑な気持ちがあったと思うのですが、どうなんでしょうね?
リアルタイム中継放送の是非を報道する側の視点で描く
誤報(ぬか喜び)の後の結果に青ざめるアメリカABC放送の
クルー‼️たち・・・
その姿ががとても印象的でした。
人質全員解放から、人質全員死亡‼️
この落差は人命尊重する重大なスクープに暗い影を落としました。
人質の家族は、解放無事の報から、その直後には
奈落の底へ突き落とされたのですから、
《報道の重み》《報道の責任》
それは計り知れないですね。
【ストーリーは実話】
1972年9月7日(=題名)のミュンヘン・オリンピック選手村で起きた、
パレスチナの武装派集団(黒い九月)による、
イスラエル選手団の人質テロ事件。
それをアメリカABCテレビのスポーツ担当のクルーが、
寄りによって報道knowhowのないスポーツクルーによって、
衛生放送で世界に同時生中継をしてしまったのです。
視聴したのは9億人。
日本でもテレビや新聞で見聞きしましたが、リアルタイムの
衛星中継はなかったと思います(家族に確かめたのですが、)
リアルタイム中継。
①その是非と、功罪。
②ABCにあったCBSへのライバル心と焦り。
③ドイツにとっての、このオリンピックの持つ意味。
③は特に重要な気がします。
ナチスドイツに恨みを持つイスラエル人が、
ドイツで開かれる戦後初のオリンピックに参加したこと。
【平和の祭典=オリンピック】で、
イスラエル選手団の全員11名が
今度はパレスチナ人に殺されたことの意味。
人質を連れたパレスチナのテロリスト集団(黒い九月)は、
空港で人質が全員解放された・・・との偽情報が、
ドイツ側広報、ドイツ高官から流される。
その誤報の原因は、映画を観ても私には分からなかった。
❹人質のイスラエル選手の部屋では、ABC放送の映る
カラーテレビがあり、
テロリストには警察の動きが筒抜けになっていた。
・・・では何故?
❺選手村の電源をシャットアウトなかったのか?
競技の中断はすぐに終わり、またすぐにはじまったのか?
この事をABCクルーは悔いて責任を感じているが、
気づかない警察と、オリンピック事務局にも疑問を感じる。
撮影したクルーでただ1人のドイツ人として生放送に貢献した
通訳を兼ねたマリアンヌ(レオニー・ベネシュ)、
そのマリアンヌの立場も微妙だった。
イスラエルへのドイツ人として複雑な感情を込めつつ、
職場ではアメリカ人にドイツ語を訳して、
警察無線の傍受やら、そしてドイツラジオ局の情報も
同時通訳する。
(これはある意味スパイ的立場に似ている)
ABCスポーツクルーは、特に撮影責任者のジョン(ジョン・マガロ)、
そして番組責任者のスポーツ担当デスクのルーン
(ピーター・サースガード)が仕切った。
ここの2人が、事態が変わるたびに、何度も重要な決断を迫られる。
特にルーンはアメリカにいる報道スタッフにスクープを
横取りされないために、
必死で、喧嘩腰でアメリカにいる報道チームと電話でやり合う。
(実際問題としてニューヨークから来たって間に合わないのだ、
(たった一日に起こって終わった顛末なのだから、)
撮影は1972年を実に詳細に再現、
その場にいたスタッフそしてカメラマン、
機材(望遠カメラの大きさと重さ)
テレビ局のモニター画面も本当に小さくて、
覆面を被ったテロ犯は窓辺に何度となく姿を現すやら、
ドイツの警官が屋上から人質の部屋に侵入計画も、
犯人たちにバレバレだったのだ。
それほどに警察にもテレビクルーにも判断の時間が持てないほどの
スピードで進んだ奇襲作戦のテロだった気がします。
ジョンはトップを切って“人質の無事“を報道したくて、
“多分“を付ければ、良いか!?
「多分人質は全員解放された」との一報を流す。
それは瞬く間に世界中に流れる。
しかし実際には空港での地獄の銃撃戦の末に、
イスラエル選手団の11人全員と警官、パレスチナ人5人が
全部で17人が死亡したのです。
世紀の誤報・・はあっという間に塗りかえられて、しまったわけですが
ジョンの青ざめた顔、そしてABCスポーツ担当責任者のウィアーに
とっても苦渋の選択だった。
咄嗟の判断を迫られるリアルタイム放送の難しさを、
思い知らされました。
この映画を観る前に「ミュンヘン」2005年を観たのですが、
「ミュンヘン」はこの映画の「黒い九月事件」とその後、
その後のイスラエルの報復とパレスチナの報復への報復・・・に、
重きを置いた映画でした。
そしてパレスチナとイスラエルの問題は、50年後の今もなお
報復の連鎖は続いているのです。
余談ですが、調べたら1972年は私の住む「札幌冬季オリンピッ」が
2月にあって、その秋の9月がミュンヘンオリンピックだったのです。
ドイツが戦後の復興の象徴的立ち位置がミュンヘンオリンピックで、
札幌冬季オリンピックは“札幌に地下鉄が通って便利になったよー“
そんな楽しいお祭りだったのに、ミュンヘンでは今も歴史に禍根を残す、
“血塗られた平和の祭典“だったとは!!
報道する側の伝え方、倫理観を、
今改めて問いかけたい・・・
ティム・フェールバウム監督はそう語っています。
メディアの意義
ジェフの知り得る内容で画面が展開するのだが、彼が事前に知っている情報(内部の人間関係)が語られないので、内容把握はかなり難しい
2025.2.24 字幕 イオンシネマ京都桂川
2024年のドイツ&アメリカ合作の映画(95分、G)
実際に起きたミュンヘン五輪テロ事件を放映局目線で描いた伝記映画
監督はティム・フェールバウム
脚本はモリッツ・ビンダー&ティム・フェールバウム&アレックス・デビッド
物語の舞台は、1972年9月5日のドイツのミュンヘン
五輪中継を行なっていたアメリカの放送局ABCのスポーツ局は、スポーツ運営局長のマーヴ(ベン・チャップリン)の指揮の下、管制室長のジェフ(ジョン・マガロ)を中心としたチームでライヴ中継を行なっていた
その日は男子水泳の決勝戦が行われていて、ジェフは冷静に試合を見つめ、的確なカメラワークを指示していた
そして、朝の4時40分頃、「黒い九月」のメンバーが選手村に侵入し、イスラエル選手団の宿舎へと突入した
その後、AK-47による銃撃が起こり、ABCのスタジオでは複数の人間がその音を聞くことになった
ジェフたちは事実確認を行うために各方面から情報を募ると、どうやら選手村にて何かが起こっているらしいということがわかった
その情報は即座にラジオ放送やドイツの公共放送などを通じて流れるようになり、ジェフは通訳のマリアンネ(レオニー・ベネシュ)に翻訳をさせて、事態の進展を見守った
オリンピックタワーから選手村は一望できたが、そこを移すためのカメラはなく、そこでスタジオカメラを1台外に出して撮影を試みることになった
また、現地に16ミリを持たせたカメラマンを配することになり、カメラアシスタントのゲイリー(Daniel Adeosun)、カーター(Marcus Rutherford)とマリアンネを派遣していく
マーヴは社長のルーン(ピーター・サースガード)に伺いを立てて許可をもらい、方々から情報の裏どりを始めて、他局との番組枠の争奪合戦を繰り広げていく
現場はジェフに一任され、アンカーのピーター(ベンジャミン・ウォーカー)に指示を出して原稿を読ませ、ジャック(Zinedine Souailem)はカメラワークをコントロールしていくことになった
状況が全く掴めないまま、ようやくイスラエル選手団のいる場所がわかり、その窓からテロリストたちの様子も見られるようになった
イスラエルの内相も現地に赴き、料理人のふりをして中に入ろうと試みたりするものの、なかなかうまくはいかない
そんな折、警察のサンシャイン作戦が動き出し、外壁や屋上に警察が配備されるのだが、その様子をABCのカメラが捉え、放送に乗せてしまったのである
警官隊が放送を止めるようにと乱入し放送は一時中断するものの、結局は追い返して放送を続けることになった
そして、そうこうしている内に犯人グループが移動するという情報が流れ出す
マリアンネたちも動き出し、移送するためのヘリも到着してしまう
行き先は近くの空軍基地だと推測され、スタッフもそこに向かう
だが、なかなか中の様子を捉えることができず、マリアンネの叫びだけがスタジオ内に響きわたるのである
映画は、テロをライヴ中継してしまったABCの顛末を描き、ドイツが軍隊を突入させられなかった実情などが飛び交っていく
マリアンネが超有能キャラなので何が起こっているのかが手に取るようにわかるのだが、実際にはここまではっきりしたことはわからなかったと思う
事件の概要がわからないために「テロリスト」とも呼べず、選手のふりをして選手村にスタッフを突入させるなどの無茶もやっていく
そんな中、ドイツの報道官が「人質は無事に解放された」と発したことから、ABCもそれを信じて流してしまう
だが、その言葉の端々に違和感を感じたマーヴは裏どりのない情報は流すなと忠告する
それでもルーンの命令によって、ジェフは「噂では」という言葉を付加して、アンカーに話させてしまうのである
その後、現場にいたマリアンネからの一報が入り、まだ銃撃戦が続いていることが知らされる
祝杯ムードのスタジオの空気は一変し、そして、公式的な発表として「人質は全員死亡」という事実が突きつけられるのである
映画は、ジャーナリズムの裏側を追いながら、リアルタイムに感じるような構成になっていた
実際の事件は、午前4時40分に始まり、午後11時30分頃に応援部隊が到着して、全てが終わっていたことがわかっている
人質9名、警察官1名が死亡し、犯人側はリーダーを含む5名が死亡し、3人が逃走を図った
その3人も後に逮捕されることになるが、同年10月20日に起きたルフトハンザ航空615便ハイジャック事件にて解放されている
また、オリンピック自体は、9月6日の午前10時に再開し、中断していたのはわずか34時間だった
いずれにせよ、約18時間ほどの出来事なのだが、ほぼリアルタイムに感じられるほどに濃厚な凝縮がなされていた
無駄なシーンもほとんどないのだが、あまり説明がないので、放送局内部の人間関係というものがほとんどわからないまま話が進んでいく
なんとなく雰囲気で掴んでいくしかないのだが、この内容ならパンフレットを作って解説してくれないと厳しい
あの現場には約15人ほどいて、1カメにピーター、2カメにジム・マッケイが別スタジオでゲストを招いて放送を切り替えていたが、それ以上を把握するのは難しい
また、外に出たマリアンネたちを追う映像がなく、ジェフを中心として、外の音と見える範囲の映像だけを使っている
俯瞰するショットがほぼゼロなので、それが没入感を生んでいるのだが、画面が暗く、かなり疲れる映画なので、覚悟して臨んだ方が良い作品であると思う
まあまあだった
ミュンヘンオリンピックの事件を報道するテレビ局のお話で、ほぼスタジオの調整室内で物語が進む。調整室がやたらと薄暗くて閉塞感がずっと続く。短いわりに退屈で眠くなる。『ミュンヘン』などを見てなかったらあんまり意味が分からないかもしれない。衛星中継のテレビの放送枠を局どうしで交換したり奪い合うのがどういうことなのだろう。ABCでずっと放送しないのだろうか。
人質のことを本気で心配する人たちばかりなのも違和感がある。もし自分があそこにいたら、もちろん死ねばいいとは思わないし、助かって欲しいとは思うけどあそこまで親身になれない。所詮他人ごとだ。家族か友達、知人でもなければあんな気持ちにならない。全員が悲痛な面持ちで、一人くらいオレみたいな人物がいないものだろうか。
1972年に本当に撮影しているかのような表現がすごい。
報道の矜持を感じました。
全くスリル、臨場感なし。
制作者側にマドンナの元ダンナ!
1972年ミュンヘン五輪といえば、バレー好きの私からしたら、全日本男子バレーが唯一の金メダルを取ったオリンピックとして語り継がれている程度の知識しかなく、裏でこんな悲惨な事件があったとは…。
今は亡き松平康隆監督の元、クイック、時間差攻撃、ジャンプサーブ、天井サーブ…今の速攻コンビバレーの原型を産んだ伝説の12人の印象しかないほど、日本は男子バレー初の金メダルに浮き足だってた印象しかありませんでした(いえ、直接当時の試合を見てたわけではなく、よく秘蔵映像として以前のバレー経験者なら繰り返し見ていました)。
その時起きた人質テロ――五輪史上最悪の事件として、今もなお語り継がれている歴史的な1日を基に描かれている作品が本日昼の回でバンクーバー公開が最後ということで、雪がチラつく中観に行きました。
日本人選手のメダルラッシュに沸いた夏が記憶に新しいオリンピック。その長い歴史の中で今なお大会史上最悪の事件として語られるのが、1972年9月5日、ミュンヘンオリンピック開催中に起きた、パレスチナ武装組織「黒い九月」によるイスラエル選手団の人質事件。本作は、突然世界が注目する事件を中継する事になったTVクルーたちの視点で、事件の発生から終結までの1日を90分間ノンストップで描いています。
第82回ゴールデングローブ賞では作品賞(ドラマ部門)、第97回アカデミー賞では脚本賞にそれぞれノミネートされていますので、ご興味のある方はぜひ。
主人公を演じたジョン・マガロが「(1972年)9月5日(セプテンバー5)にニュースの歴史が変わった」と語る本作は、1972年のミュンヘンオリンピック開催中、パレスチナ武装組織「黒い九月」に襲撃されたイスラエル選手団11人が犠牲になったテロ事件を題材に、緻密な脚本と重厚な映像で圧倒的な緊迫感を描き出した社会派映画となっていて、このイスラエル選手団人質事件は、選手団11人の他に、警察官1人と犯人5人の合計17人が死亡しました。
「脚本を読んですぐにやると決めた」と脚本に惚れ込んだショーン・ペン。「全員のエネルギーが生み出した至極の作品だ」と本作の完成度に自信を見せているとのことでした。ピーター・サースガードもまた「見事な脚本で、物語の伝え方を熟考してある」と、ティム・フェールバウム監督自身が執筆した緻密な脚本を絶賛しています。
フェールバウム監督とともに脚本を書き上げたモリツ・バインダーは「1972年の事件を新しい視点で届ける。現代に生きる人にこそ見てほしい」と熱く語り、本作ではプロデューサーに徹したペンも「最高の美術チームが作り上げたセットが、俳優の魅力を引き上げると証明した」とセットデザインにも凝っていることを語りました。
1972年当時の中継スタジオを徹底的に再現するため、製作チームは個人収集家や博物館、放送局の倉庫に至るまで調査。フェールバウム監督やキャストたちも、セットの隅々に置かれた実際に動く1972年当時の機材に「(本作が描く1972年当時の)世界に入り込める」と口を揃える。CG合成のブルーバックの前で演技するのではなく、セットにある実物に触れて体感でき、半世紀もの時間を自然にタイムスリップできる撮影現場に感動しきり。
本作の大部分は、事件が起きたミュンヘンで撮影されていて、今回撮影された映像と1972年当時の映像を組み合わせて、色合いなんかもかなりリアリティを感じましたし、編集のハンスヨルク・バイスブリッヒは「観客が物語に没頭できるようにテンポの速い作品にしたかった」と、本編を96分に凝縮し圧倒的なスピード感で観客をエンディングまで誘う編集の意図を語っています。
ドキュメンタリー作品ながら、特にリアルなドンパチシーンもなく、全体的には静かな作品ですが(後ろの席からイビキが聞こえましたw)、オリンピックがビジネスだけでなく政治的にも利用される所以はこの事件だったのかと思わされましたし、国際関係、警察の対応、テロ対策、マスコミの報道のあり方など、多面的に考えさせられました。
多少退屈に思われるかもしれませんが、エンディングロールの後、制作、俳優陣へのインタビュー動画がありますので、ぜひ最後まで席を立たずにご覧下さい。
忘れてはならない
放送は二度と同じではなくなった。
まだテロが始まっていない時、ABCスポーツのチーフプロデューサーは、競技での勝者ではなく敗者を先に写すように指示をする... これはモチーフとしての意味なのか?
そしてその事の回答のメタファーがドイツ人臨時通訳に対しての言葉なのかもしれない。この話は、ドイツのチーフプロデューサーが会見で述べた言葉に対して放送責任者ベーダーに彼女が説明しているシーンより。
Gipa: He's saying that the games are an opportunity to
welcome the world to a new Germany to move on
from the past.
Bader: Yeah, sure.
Gipa: I mean it's what we all hope for, but as can we do,
but move on. Try to be better.
Bader: Are your parents still around?
Gipa: Yes.
Bader: Let me guess. They didn't know either, right?
Gipa: But I'm not them.
Bader: No, no, you're, you're not. I'm sorry.
I'm Marvin Bader.
当時、駆け出しで未熟だったプロデューサー・ジェフリー・メイソンはプッシュ式の電話の幕開けと共に世界的テロリズム、開催国の躍進と不安定さ、CBSとの衛星放送権の争いと衝突、そこには、ただ単に自尊心を含んだ報道の取り組み方を映像化している... それは以下のセリフより
テロ行為が目の前で起こっている緊張が張り詰めているスポーツクルーに電話口でニュース班からこんな事を言われている。
No offense guys, but you're Sports. You're in way over
your head. News should take over.
ABCスポーツの社長ルーン・アーリッジがそれに対して、クルーにゲキを飛ばす(※彼は後にABCニュースの社長に就任している。)
Okay, look, I know this isn't a responsibility that everyone wants.
But does it make more sense to have a talking head from News
take over from halfway across the fuc*ing world? Our job is to tell
the stories of these individuals, whose lives are at stake, 100 yards
away. And our job is really straightforward. We put the camera in
the right place, and we follow the story as it unfolds in real time.
News can tell us what it all meant after it's over. And I'm sure they're
gonna try. But this is our story. And we're keeping it.
もちろん、この前半のセリフで見ている側にも緊張感が伝わってくる。来るが、この作品『セプテンバー5』が今この瞬間にぞっとするような衝撃をもたらしているとは思わないし、言えない。それはサブ・コントロール・ルームというワンシチュエーションであり、時代が半世紀前の事でもあり、現実味がなく、そこには隔たりが第四の壁のように強く意識させ悲しいことに常に存在するイスラエルとパレスチナの緊張をアナログ的に思い出させるものと個人的には捉えているために... だから決してそれに対する過剰な反応は起きやしない。
2年前のハマスの襲撃が起こったとき、この映画はポストプロダクション中だったそうで、いずれにせよ、この映画のメインプロットは襲撃やそれに対する治安部隊の対応や制圧、あるいは襲撃が何故、起こった理由などを表してはいない。つまり『セプテンバー5』は主に、襲撃がどのように報道されたかについて焦点を当てている。
Bader: Black September, they know the whole world
is watching. If- I'm saying if- they kill a hostage
on live television, whose story is it? Is it ours, or
is it theirs?
ドキュメンタリー風映画が「真実の映画」との差とはどのようなものなのか?
アーカイブス映像と撮影された映像をシームレスに繋ぎ合わせることで映画から虚構上のトリックを排除し インタビューや録音の肉声などを多用するのことで、作り手の存在を意識させるとともに、ダイナミズムを感じさせないカメラワーク、編集技術 、当時のプッシュ式電話や持ち運びの不便なカメラなどの小道具などと組み合わせて、プレッシャーにさらされているニュースルームの混乱を強調するはずが、 16 mm スタイル映像が落ち着いて見えさえする。従来のニュースルームのドラマのような言葉による派手さは排除され、その慎重なセットアップによるペース配分が、リアルタイムでの意思決定の断片化と不確実性が強調されたことで、より真実味が生み出されそうに見えたが...しかしながら
機械のボタンのように、意識的または無意識的に、道徳や感情を簡単にオン・オフにすることもできないのは、そのような事が映画に限らず芸術において非政治的産物ではないと言い切れる夢遊病者が抱く幻想なのかもしれない。だから本作のような映画はこうした概念が真実味を見失ったために空虚化を招いている。
先ほど登場した Gipa こと雑用係のような通訳のマリアンヌがこのように語っている。
No... Innocent people died in Germany again. We failed.
Germany failed.
(※ "again" この言葉が何時の事を指しているのかで作品の重みが変わってくる。この言葉を発したマリアンヌを演じた女優さんは非常に評価が高い。)
3大ネットワーク、全盛時代。視聴率や宣伝効果というお下劣な勝者がいるとするなら... 多くの方が犠牲になっているのを知ったうえで、 その事を踏まえて不謹慎でもいえるのは、勝者は彼らパレスチナ武装組織「黒い九月」なのかもしれない!?
全197件中、181~197件目を表示