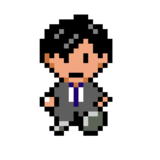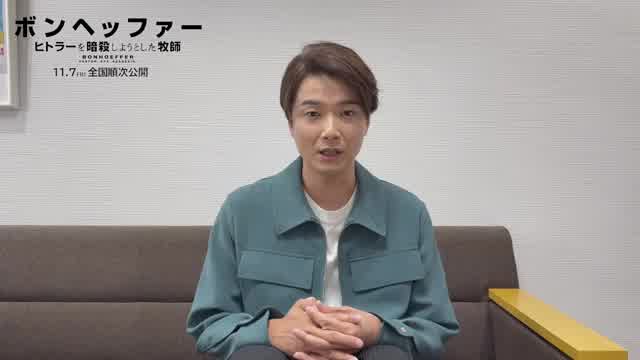ボンヘッファー ヒトラーを暗殺しようとした牧師のレビュー・感想・評価
全63件中、21~40件目を表示
ヒトラーに屈しなかった牧師
拘束されている状態と過去の明るく過ごした時期とが交互に出てくるので、戸惑いがあった。会議でも、楽団で自らピアノに興じたり、教会学校の授業を抜け出して聖歌隊の聴衆に加わったりしたかと思ったら、ホテルに友人の黒人を連れてはいろうとして白人でさえ命の危険を強烈に感じる罵倒を受けていた。
「ヒトラーに屈しなかった牧師」でも良いのではないかと思った。主役は、『ぼくたちは希望という名の列車に乗った』その他の作品にも出ている俳優で、雰囲気に既視感がある。
観なければよかった
エピソードがバラバラで理解しにくい
宗教と政治
留学したNYでジャズやゴスペルを
肌で感じ楽しむが黒人差別にも
目の当たりにする。
自国に帰国したがナチスが台頭。
そしてナチスが書き換えた聖書なる。
酷くて非人道的。
反ナチとして弾圧されながらも
命をかけて抵抗して行く姿は勇ましい。
『悪を前にして沈黙するのは悪であり
沈黙する教会は罪である』を唱え
貫く姿勢は凄まじい。真摯な言葉だ。
宗教と政治を巻き込み、戦争になって
いく緊張感が常にあった。
戦争への狂乱は恐ろしい。
最後は神のような目と表情だった。
ラストは切ない………。
悲しい歴史
歴史は繰り返すというけれど、こんな時代は繰り返してもらいたくないな。映画『ボンフェッファー ヒトラーを暗殺しようとした牧師』をみながら呪文のようにそんな言葉が、頭の中を駆け巡った。
日本だってあの時代のクリスチャンはどうだったのか
日本政府により、一つの団体に統合された上、メッセージや信者は監視されていた。
唯一反抗して投獄されたのは、ホーリネス教団だったはず。
ただ、日本ではあまりあの時代を検証する動きはない。
いくつかの団体は、戦争に加担したことを反省する声明をだしてはいるが。
現在でも、日本のクリスチャン人口は、せいぜい1%ぐらい。
まあ、あまり影響力はないので、話題にもならないけど。
ドイツとなるとそうもいかないですよね。
映画にあるように、ナチスは自分たちの正当性を誇示するために、聖書の書き換えもしているし。
第一次世界大戦後のハイパーインフレ
ドイツ経済は、どん底で、人々は疲弊し誰かこの窮地を打破してくれないか。
そんな空気が、蔓延していたころ、アーリア人種の優位性を全面に上げるナチスの出現。
人々は、熱狂して支持。
この人たちならなんとかしてくれるのではないか。
だから、多少都合の悪いことには、目をつぶって。
そんな空気が、伝わってきます。
どこか、現在の日本の状況にもにてるところが。
ヒトラーに標的にされたのが、ユダヤ人。
これも突然ではなくて、ヨーロッパには反ユダヤ主義が根強くあり
いまでも。
教育水準が高く、金持ちが多く、妬まれやすい。
それに、キリスト・イエスを処刑台に送ったのは、ユダヤ人。
標的にされやすいんだけど、恐ろしい時代ですね。
牧師が殺人を犯してもいいのという疑問
「汝の敵を愛せ」聖書の言葉ですが。
ボンフェファーは、相反する選択しますよね。
ただこれは、聖書解釈にふた通りあって。
文字どうり、どんな場合でも状況でも相手を許す。
もう一つは、キリスト・イエスにあってという前段がつく解釈。
となると、ナチス・ヒットラーは許容できるはずもなく。
だからといって、暗殺に加担してもいいのかという疑問が。
あとの時代なれば、あれだけの悪行が露わになると、致し方なしという解釈もなりたつのですが。
あくまでも、牧師ですからね。
かなりの葛藤が、あったはずで。
しかし、もう済んだことなので。
ただ、そんな葛藤をしなければらない時代にならないでほしいと、切に願います。
肩透かし
屋根裏の殺人鬼を快演したヨナス•ダスラーも演技に困ったのではないか。 ボンヘッファーを通じてナチス時代のドイツ宗教界の罪を描こうとしたのか、宗教者としてのボンヘッファーを描こうとしたのか、どっちつかずであった。どちらにしてもドラマに不可欠な葛藤が描かれておらず感情移入しにくいし、いたずらに時系列をいじっているため、史実さえつながらない。最大の欠陥はサブタイトルにある「ヒトラーを暗殺しようとした」ことが、ウソではないにしても本人が直接手を下しておらず肩透かしに終わっていることだ。残念な映画だった。
名前が難しい
テーマとしては非常に良かった
喪失と再建
時は第二次世界大戦、ナチスの台頭に危機感を覚えた牧師が、ヒトラー暗殺を企てた作戦に身を投じようとし…といった物語。
第一次世界大戦における最愛の兄の死、アメリカ留学先での人種差別…目の当たりにしたいくつもの経験が彼の思想を育て上げていくが、祖国はナチスがどんどんと大きくなり、まさかの教会までもが…。
成程、いくらナチスが支持されようとも、当時のドイツ=100%ナチスと言うわけでは当然ありませんからね。こういった人々もいたんだなぁ。あの状況での説教、どれだけ勇気のいったことか。
それでも、信仰と現実の狭間で苦しむボンヘッファー氏だが、とうとう暗殺と言う本来であれば忌憚とも言える手を打つことに。う~ん、こんなこと言ったら怒られてしまいそうですが、こんな状況で、敵を愛することで勝利を…なんて言ってもねぇ。祈るより決死の行動が求められる場面ですよね。
そんな彼らの勇気に感嘆させられる作品ではあるが、ちょっとワタクシには難しかったというか、話を見失いがちになってしまったかも。7人のユダヤ人を…の件、ゲシュタポの指示の意味がよくわからんかった。因みにあそこにいた兵達はスイス兵って理解であってるのかな?
そして、手を汚さない…か。
キレイな言葉に思えるけど、自分の手を汚さずに事を運ぼうとするヤツが一番信用ならんけどな…汗
さておき、あと2週間…にはタメ息が出そうになったし、危険すぎる悪を相手に命を懸けた人々の想いを無駄にしてはならないと思う今日この頃、と感じさせられた作品だった。
なぜ英語?
ヒトラー暗殺未遂の顛末を描いたサスペンスではなく、ボンヘッファーという殉教者の信念を貫いたものがたり。
最初のうちは、アメリカに留学してジャズに触れ、黒人の差別を目の当たりにした主人公だけがまとも、他のドイツ人はみなおかしいみたいな感じで違和感を覚えたが、途中からは教会や兵士の中でさえナチスに抵抗した者がいたので少し安心?した。それにしてもあの時代のドイツには生まれたくなかったとつくづく思う。
キリスト教徒ではないが終盤にパンを分け与えるところは少し感動した。
平和で豊かなこの国では、キリスト教があまり浸透しないのがわかる気がする。
言葉に重みのある内容なのに何故英語なのか、会話だけでなく壁の落書きやメモまで。
ドイツ兵士がソノバビッチ!って叫ぶの、なんだかなぁ。
not to speak is to speak, not to act is to actとか良い台詞がたくさんあったから脚本かノベライズがあれば読みたい。あ、英語や。
この時代の、ドイツの、ボンヘッファーだけではないが、国家の未来のために力になったであろう人たちが終戦間際に命を絶たれたのは実に悔やまれる。もう少し戦争が早く終わっていれば、そして戦争さえなければ。
今現在も失われている命がある。
この時代のこの国で暮らしていることに感謝しなければならない。
邦画によくあるエンディングの台無しソング🎵
ジャズとゴスペルだけでよかったのに。
関係ないけど、
サッチモ本人が出てるダニー・ケイの「5つの銅貨」は泣ける。
ボンヘッファー理解には全く役に立たない
ボンヘッファーの伝記映画ではなく、ボンヘッファーの人生におけるいくつかの出来事から想像を膨らませた完全なるフィクション映画でした。
それならそれでもいいともいえますが、この映画にはそれゆえに相当問題を抱えていますので記します。
まず背景として。ここ何年かアメリカではトランプ支持者がボンヘッファーの言葉を「悪用」し、自らの暴力行為などを正当化しようとする動きがあり、国際ボンヘッファー協会や遺族らがこれに対する警鐘を鳴らす声明等を発表しています。
この映画もまたそうした流れの中でかつがれ、主演俳優らがそうした動きへの反対声明を発表しています。
つまりまず、この映画が受容される状況が非常に問題含みなのですが、この映画は内容にも問題があります。
試写で観た知り合いのボンヘッファー研究関係者が、みなさん難色を示しており、戦々恐々と観に行き、難色を示していたわけがよくわかりました。
この映画はドラマチックに、わかりやすく、そしてボンヘッファーではなく製作陣のしたい話に沿わせるために、ボンヘッファーの人生史、人となり、なにより思想を理解するにあたって、誤解を招くような表現、あるいは「嘘」ともいえるレベルのものが大量に含まれています。
ドキュメンタリー映画ではないのですから、面白くするためにある程度脚色をするだとか、話を「盛る」だとかが全て悪いとは言いません。
ただこの映画は、ボンヘッファーを描きたいように描くために、ボンヘッファーの人生を理解するにあたって重要な人物や出来事、著作、情報を大量にオミットし、逆に映画自身が描きたかった(伝記には記されていないような)オリジナルの会話やシーンなどを盛り込んでおり、その結果、時系列などのおかしさだけに限らず、ボンヘッファーや周辺の人間の行動や発言がかなりおかしいことになっています。
何より、ボンヘッファーの反ナチ抵抗運動とそこに関連する神学的思索について不正確な理解・知識のもと進行していきます。
ボンヘッファーにそれなりに詳しい人間として、正直観ていて大変苦痛でした。おそらくボンヘッファーに詳しい人に限らず、ナチス・ドイツやドイツキリスト教史に詳しい人も苦痛なのではないでしょうか。
しかもその割に知識がないとなぜこのような流れになるのかわからないところがしばしばあるように思います。
細かい描写の不正確さは枚挙にいとまがありませんので全てを指摘することはしません。
アメリカ製作だからかアメリカ留学時代の経験による影響を強く描きたいというもくろみによってアメリカとの関係が多分に「盛られて」いるのももうこの際おいておきます。ナチス台頭直後にヒトラー批判がこめられたラジオ講演をおこなったことも全く言及されてませんがもうそれもおいといて。ボンヘッファーがいかに検閲逃れに様々な表現を駆使していたのかも気にしていないようだったのもおいておいて。あぁ、獄中での描写もおかしかったですね。(あまりにありすぎる!)
しかしボンヘッファーにとっても、当時のキリスト教界にとっても、非常に重要な人物であったカール・バルトが影も形もないのはなぜ?
ボンヘッファーは21歳で博士号を授与され、24歳で大学教授資格を認められた、若き天才「神学者」であったわけですが、ボンヘッファーの研究についてやドイツの大学関連のことを完全にオミットしているのはなぜ?
婚約者マリーアが全く出てこないのはなぜ?
こうした重要な出来事や背景情報、周辺の神学者・哲学者は、若く熱く反骨精神に満ちた孤独な抵抗者像に押し込めるために完全に切り捨てられています。それゆえにボンヘッファーの思想についてもろくに描かれないという仕様になっているわけです。
盛るのも、尺の都合もあるでしょうし登場人物を減らすのも一概に悪いとは言いませんが、描きたいボンヘッファー像に沿わせているだけなので、伝記とも著作とも乖離した行動や発言、演出を繰り返すのは流石に問題でしょう。
ボンヘッファーの人生を、親友でありボンヘッファー研究の第一人者であるエーバハルト・ベートゲ(非常に重要な人物であるにもかかわらず一瞬の登場でしたね)は、第一期神学者・第二期キリスト者・第三期同時代人と区分しました。この区分をどこまで念頭に置くべきかは後世の研究上議論がないでもありませんが、ボンヘッファー研究としては非常に重要な区分であり、つまりボンヘッファーの関心や立場は時代によって様々であったのです。この映画は描きたいボンヘッファー像に押し込めるために、そうした時代的変遷も完全に無視しています。(後期に初めて確立する思索を若きボンヘッファーに喋らせているところもあったなぁ)
ひとり若く反骨精神のある若者を描きたかったので、「告白教会」の名前がでてきて牧師研修所のことはでてきても、「告白教会」という組織がどういうものであったのか、どういう人たちであったのかは全く描かないところに全てがあらわれています。そうした他者との交わりや組織の中での役割を描いてしまうと、描きたい像からズレますものね。でもボンヘッファーは非常に他者との交わりも重視した人でしたよ。
ニーメラーの描写も本当に雑。
そもそもナチス・ドイツとキリスト教との関わりについての描写自体が大層雑ですね。
ボンヘッファーの反ナチ抵抗運動に関しては、草稿集『倫理』で示された「罪の引き受け」が非常に重要なわけですが、そこらへんもオミットです。神学や学問の話は多分製作陣はあまりしたくないから。
そもそもどういう著作を書いていたのかはほぼオミット。
ボンヘッファーは暗殺や暴力行為を全面的に肯定した人でもないし、敵を愛するとか愛さないとか、そういう話より踏み込んだところを問題にしていたわけですが、そこらへんを描く気もありませんでしたね。
行動、あるいは行為はボンヘッファーにとってはもちろん重要でしたが、とにかく何かしろということではなく、ボンヘッファーは考えに考え自身のキリスト教倫理を構築したわけですが、製作陣はそういうことにも関心がないみたいですね。
書いているとあまりに長くなってしまうのでそろそろ切り上げますが、題の通り、この映画はボンヘッファーの人生史、人となり、思想を理解するにあたっては全く役に立ちません。
知られざるナチ政権下のドイツ宗教界
プロットに多少の違和感はあるものの、実在の人物と史実にそこそこ沿っているリアリティがどすんと胸に響く。
何よりも「ナチスが権力を握って行く過程でのドイツ宗教界(キリスト教)の不作為とナチへの加担」という日本ではあまり知られていない事実に震撼する。
そもそもナチスが聖書そのものを書き換えていたなんて強烈すぎる。
(イエスをアーリア人に、モーセの十戒を「十二戒律」にして「総統を愛せ」「純血を維持せよ」を付け加えていたとは)
宗教界に限らず、当時のドイツ社会ではヒトラー/ナチスに対する反感や嫌悪が当たり前のようにあったにも拘らず、徐々に人心を侵食していったプロセスが家族や宗教家たちの会話で表されていて、なかなか巧みな脚本だった。
ボンヘッファーはそんな空気の中で「教会で語られる言葉は神の言葉のみであって、人間(ヒトラー)を称賛する言葉ではない」という宗教的ド正論を曲げない。
ただし、彼自身は直接的に暗殺の実行部隊には関わっていないのだが。
ドイツ国内レジスタンスやドイツ国防軍内部での反ヒトラー活動、英国との関係なども描かれていて、情報量は多い。
ただ、一つだけ難点(というより私の感じ方なのだが)ドイツ国内のドイツ人ネイティブ同士の会話が流暢な英語、というのがどうしても引っかかる。そこは徹底的にドイツ語の会話にして、字幕にして欲しい。
英語ネイティブの人たちはそれが嫌なのかな?
殉教者の人生ダイジェスト
ロンドン・ウェストミンスター寺院の「20世紀の10人の殉教者」のレリーフになっているボンヘッファー牧師。
ナチス統治下のドイツで、彼の反ナチス・反ヒトラー活動がどのようなものだったのかを、ダイジェストドラマ的にまとめていました。
第一世界大戦で亡くなった兄の形見の聖書を受け取ったのがきっかけで牧師になる道を選んだり、黒人の牧師仲間がアメリカで白人からの仕打ち受けるのを見て人種差別への反発を覚えるようになったり、細かいエピソードを積み上げ、人物像を浮かび上がらせる作り。
ボンヘッファーは、キリストの再来みたいな、我が身より信仰をという姿勢を貫く殉教者キャラとして描かれる。
正直、キリスト教徒ならぬ我が身には共感できないものの、神のもとでの平等の意味と、ナチスの「ヒトラーが神と同じか神より上の存在」とする考えの下で聖書を改竄する様がいかに酷いかは、理解できた。
歴史や考え方などを学ぶという点では良い作品ですが、芸術や娯楽という面での、映画としての出来は微妙かな。
彼と、彼の友人であるニーメラー牧師など、反ナチス活動を行った聖職者たちの名言集みたいな側面もあり、私程度でも知る言葉が次々と出てきましたよ。
「悪に直面して黙ること自体が、悪である」(ボンヘッファー)
「ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった。
私は共産主義者ではなかったからだ。
ナチスが社会⺠主主義者を牢獄に入れたとき、私は声をあげなかった。
私は社会⺠主主義者ではなかったからだ。
ナチスが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった。
私は労働組合員ではなかったから。
それから学校が、新聞が、ユダヤ人がとなり、私はそのたびに不安になったが、やはり何もしなかった。
そして、ナチスが私を攻撃したとき、私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった」(ニーメラー)
このヒトラー暗殺は、何分の誤算だったのか?
ナチス関連の映画は何作も観てきたけれど、ユダヤ人迫害に関するものや、戦後の残党を描いたものしか観たことなかったかも。
同じドイツ人も対象だったことは知らなかった。
どうして教会が標的になったのか不思議だったけど、なるほどイエス・キリストがユダヤ人だったからなのか。
そしてヒトラーを暗殺しようとしていたのは、家具職人だけではなかったのですね。
またしても何かを察して暗殺を免れた、ヒトラーの悪運たるや。
ボンヘッファーのことは初めて知ったけど、一手間違えれば命が危ない、綱渡りのような極限状態でも我が身を顧みず、人々を救おうと奮闘する姿にハラハラした。
アメリカのホテルで経験した、人種差別も関係しているのかな?
絞首台で空を仰ぐ表情が、聖職者と呼ぶに相応しい人生を象徴するかのようなシーンだった。
現在と過去が行き来するので、はじめは少し混乱したけど、アメリカ時代のジャズシーンも素晴らしかったし、今まで観たことのなかった題材が新鮮で良かった。
しかしながら、よくもまあ毎度毎度、憎たらしい風貌のナチス親衛隊役を見つけてくるものだ。
今回の面長シャクレも腹立つ。
“神に喜ばれる生き方とはどういうことか!?”
日本のクリスチャンでない方がこの映画を観ると、宗教色が強く押し出されたチープな映画だと批判的に感じる方がいたり、単にヒトラーや戦争の悲惨さは伝わったとしても、作者が観てる側に何を訴えかけたいのかの真理が余り伝わらないかもしれないが、これはクリスチャンには是非観て頂きたい作品の1つであり、今の日本は当時のドイツのような宗教的迫害はないにせよ、今を生きるクリスチャンにとって、“神に喜ばれる生き方とはどういうことか!?”を考えさせられる良い作品だと思う!
ゲシュタポの指示は何だった?
WW2下、神より上のヒトラーとナチスを阻止する為に、手を汚そうとしたキリスト信者の話。
ゲシュタポに捕まって、移送、収容されるボンヘッファーが、幼少期の兄との思い出や米国の神学校への留学のことなどから回想する体で展開して行く。
ドイツに帰り、ナチスとヒトラーの台頭を知り、阻止するべく牧師として行動する姿や、葛藤する姿をみせていくけれど、ちょっと信仰に寄り過ぎな感じが。
ヒトラーも、えっとこれヒトラーですよね?なクオリティだし。
とはいえ、この方の存在は知らなかったし、正に暗躍しスパイやレジスタントの様に振る舞う様や覚悟はなかなか良かったけれど、エンドロール中の名言テロップラッシュで、またしても宗教プロパガンダを感じてしまった。
真髄
ボンヘッファーの事前知識は、神学者でありながらヒトラー暗殺未遂事件に加担した人やったかな?というくらいの浅い知識。
ヒトラーは邪悪な存在であろう。ただ、戦争中ユダヤ人を殺害した人々は?なにも行動を起こさずじっとしていた人々は?ボンヘッファーは「悪の前の沈黙はそれも悪。行動しないこともまた行動であり、悪である」と訴えた。
兄の葬式後に、僕のピアノなんて誰も聞いていないと母に訴えたボンヘッファー。時は流れ自国が危機的な状況に瀕し自らの大切にしている教会までが侵されようとしている。国、教会を守ろうとするその過程が淡々と描かれている。
ドキュメンタリーのようであるが、説教だけでは限界があると察するボンヘッファーの苦悩が伝わってくる。戦争で兄を亡くしたこと、アメリカに留学し差別を目の当たりにしたこと…それらの出来事がこのままではいけないという信念につながったのかもしれない。あの幼き日の誰も演奏を聴いていない状況から、ボンヘッファーの当時の言葉が今もなお語り継がれるのは多くの人々が共感し、勇気をもらい救われたからなのかなと。
処刑されることは知っていたため、祈るような気持ちで見ており途中からとても感情移入してしまい涙が溢れた。アメリに残れば命は助かった。やけど、自分の何かが死んでしまうと思ったんやろうなあと。
この時代のドイツが題材となる映画は数多くある。関心領域、小さな独裁者…個人的には悪意に無関心の人々、はたまた見ないようにしようとする人が描かれた作品を観ることがおおかったが、この人のように命懸けで国と戦った人もいることを忘れてはいけない。
「これが最期です。私にとっては生命のはじまりです」
【”悪の前の沈黙は悪である。”今作は実在のドイツ人牧師、ディートリヒ・ボンヘッファーがナチス思想に抗い、暗殺を企てるも終戦直前に殉教する様と、彼が後世に与えた影響の大きさを明示した作品なのである。】
ー 敢えて冒頭に記すが、今作は多数の人物が次々に登場し、物語も時系列を行き来しながらが展開していくので、可なり脳内フル回転で鑑賞する。
少し、脚本が粗い気がしないでもないが、主人公が実在のドイツ人牧師であり、ナチス崩壊の最後の最後まで抵抗を止めずに、ドイツの教会を想うが故に殉教する様や、彼が遺した多くの著作が、第二次世界大戦後にキリスト教会に大きな影響を与えた事を鑑み、その人物像を描いた作品として、評点を4にした次第である。
そして、彼が絞首刑に処せられたシーンが、笑顔を浮かべ神の下に旅立つがごとく描かれていたが故に、嗚咽が漏れた所為もある事も付け加える。ー
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・物語は、ディートリヒ・ボンヘッファー(ヨナス。ダラー)が第一次世界大戦で戦死した兄の形見である聖書に影響を受け、牧師になるシーンから始まる。
若き彼が神学生だった時代のアメリカで黒人の親友が居り、当時の黒人への偏見にめげずにその友を同じ宿に泊めようとしたり、ジャズに薫陶を得ていく様が、後年の彼の思想の背景になっている事を示唆する序盤の展開が良い。
・時代は、極悪レイシストであるヒトラー台頭によりドイツ国内で勢力を増すナチスへ忖度する教会内部の動きに敏感に反応し、仲間を作り、教会での説話の際に多くの親衛隊が着席する中で”教会は聖域であり、権力の場ではない!”と決然と言いきる姿は、可なり沁みる。
・だが、ナチスの弾圧は激しく彼はスパイとなり英国に渡り、非合法活動を牽引せざるを得なくなっていくのである。
冒頭に書いたように、”この辺りの描き方をもう少し、整理してくれたらなあ。”と思いつつも、彼がユダヤ人たち7名を10万マルク支払いながら、中立国スイスに逃がすシーンなどは、初めて知った事であり、興味深く鑑賞したのである。
■ラストシーンも、上記に記したように哀しいが、ボンヘッファーが笑顔で絞首台に上がる様が神々しく、可なり沁みてしまったのである。
そして、エンドロールで流れる、彼が遺した多くの著作がその後のキリスト教会に多大なる影響を与えた事を語るテロップを読み、感慨深く感じたのである。
<今作は実在のドイツ人牧師、ディートリヒ・ボンヘッファーがナチス思想に抗い、暗殺を企てるも終戦直前に殉教する様と、彼が後世に与えた影響の大きさを明示した作品なのである。>
全63件中、21~40件目を表示