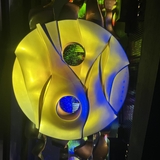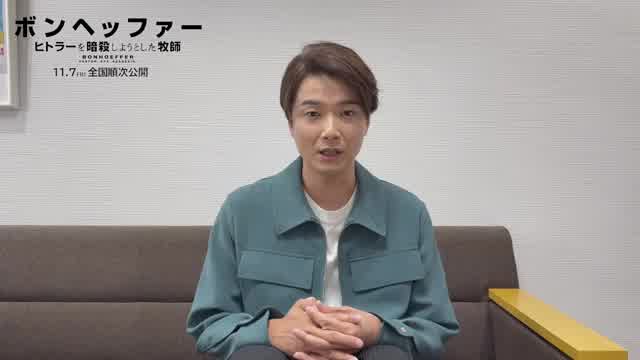ボンヘッファー ヒトラーを暗殺しようとした牧師のレビュー・感想・評価
全65件中、1~20件目を表示
悪の前の沈黙は悪であり、神の前に罪である
生徒による生徒への暴行動画がネット上で拡散されて、隠れていた事実が晒されています。ネット上で晒すことの是非は様々な場で議論がなされています。その前に、いじめも含め、このような場面に出くわしてしまった若者がどのように向き合うか、学校だけでなく青少年に関わる全ての人々の中で語られ、未来に希望と生きる勇気を与えられる世界であるよう、この映画が観て、そう強く願いました。
神への冒涜許すまじ -ある神学者の葛藤-
かなりインパクトのある特殊メイクで、第二次大戦後のドイツのシリアルキラー、ブリッツ·ホンカを演じたヨナスダウナーが、今度はナチ政権下のドイツ人神学者ボンフェッファーを演じた反戦映画。
第一次世界大戦で兄を失った6人兄弟の三男。子役の弟妹たちがとても可愛いかった。
1930年代にニューヨークの神学校に留学し、ハーレムの黒人教会を体験する場面は聖歌隊のゴスペルシーンがミュージカル仕立てのようで、楽しかったのだが····
ナチスはキリストではなくヒトラーを崇拝せよと教会に鉤十字を掲げ、説教の内容を検閲してくる。神への冒涜に対して真っ向から逆らうことは叶わず、隠れキリシタンよろしく、森の中で若い聖職者の養成を続けたり、先輩司教がナチに潜入しながら、他国からの支援を画策し、中立国スイスの警察に高い対価を渡してユダヤ人を逃がしたり、ヒトラー暗殺を計画するのだが、ドイツ人牧師を支援してくれる連合国側の団体はいない。チャーチルのそっくりさんみたいな俳優が出てきた。からだに爆薬を巻きつけた自爆テロ実行係の牧師が遂行できずに、計画は未遂に終わり、ボンフェッハーたちは小さい教会の収容所に捕らえられて、ヒトラーが自殺する3週間前に絞首刑に処されてしまう。
特殊な環境下において、教義との矛盾に苦しみながらも行動に出る勇気をもって指導し続けたドイツ人神学者の映画。彼はガンジー思想にも強く影響されていたので、その葛藤はいかばかりだったかと。
ナチスが共産主義者を連れさったとき、私は声をあげなかった
ナチスが勢力を拡大し、教会内部ですらヒトラーの神格化が進みつつあった時代に、教会の神聖化を説いてヒトラー暗殺計画にまで加わった実在の牧師のお話です。
ヒトラーを暗殺していれば戦争とホロコーストで死ぬ人は確かにもっと少なかったろう。ただし、聖職者がその企みに加担する悩みはもっと掘り下げるべきだったと思います。正義を貫こうとしたこんな人が本当に居たと初めて知る事ができたのは収穫でした。鑑賞後に調べてみると、彼に関する様々な本が日本でも既に出版されています。
作中で、以下の有名な警句がボンヘッファーの説教中で述べられます。これは実際には彼の言葉ではなく、本作中にも登場するマルティン・二―メラの言葉です。独裁者による全体主義は、ヒトラーだけで広がった訳ではなくそれを無批判に支持し煽った国民の選択でもあったのです。まさしく現在のこの国の姿ではないでしょうか。手遅れになる前に。
ナチスが共産主義者を連れさったとき、私は声をあげなかった。私は共産主義者ではなかったから。
彼らが社会民主主義者を牢獄に入れたとき、私は声をあげなかった。私は社会民主主義者ではなかったから。
彼らが労働組合員らを連れさったとき、私は声をあげなかった。私は、労働組合員ではなかったから。
彼らが私を連れさったとき、私のために声をあげる者は誰一人残っていなかった。
政治と宗教
戦後の世界が変わっていたかも?
現代の日本に生かされている意味
ウエストミンスター寺院 西門「20世紀の殉教者像」に並ぶ10人の殉教者。
その1人、ディートリヒ・ボンヘッファーを描いた映画です。
いつも通り、映画館の紹介文以上の知識を頭に入れずに鑑賞しました。子供時代から始り、時間軸をあちこち移動しまくる煩わしい構成で、しかも、主人公は眼鏡をかけてたり、
かけていなかったりするので軽く混乱し、前半では、うたた寝する瞬間が多くて
弱っちまいました。
でも、後半に近づくにつれ時間軸移動も少なくなったしドラマチックな要素が
増加したので、もう睡魔に襲われることはなくなりました。
ずっと眼鏡をかけてましたしね。
でも、そのドラマチックな部分には、調べた限りでは多くのフィクションが含まれて
いたようです。ボンヘッファーが絞首刑に処された場所も寒々しい郊外の一軒家の
前ではなくフロッセンビュルク強制収容所だし、スイスにユダヤ人数人を引き渡す
劇的なシーンも、どう考えてもフィクションくさい。だからといって多くの人が
知ることがなかったボンヘッファーという人を広く世界に紹介したという意味で
この映画は価値あるものだしドキュメンタリーではなく伝記というものは本来
そういうものであっても良いのかもしれないと今は思っています。
アメリカ・ベルギー・アイルランド合作ということにはなっていますが、まあ、
良くも悪くもアメリカ映画ってことでしょうか。
わずか、39歳で亡くなったボンヘッファーなのに、そんじょそこらの宗教家
(神学者と言うべきか?)では達し得ない高みに到達した人だと私は思います。
同時に私なそ自分のブログで言いたい放題を書き殴っていますが、お咎めを受ける
わけでもなく、こうして好き放題を書ける今の日本って長い歴史の中でも広い
世界の中でも、すごく貴重な時と場所だと、心底、思います。
キリスト者として
クリスチャンとして見ました。神への信仰を第一とし、ユダヤ人を助けた牧師 ボンフェッファーのことはこの映画で初めて知りました。聖書に ユダヤ人を呪うもには呪われ、ユダヤ人を祝福するものは祝福される、とありますが、映画の中でも アブラハム、イサク、ヤコブの神よ と祈るシーンは印象的でした。恐怖政治に怯えて権力におもねってしまう当時の教会の有り様もまた戦争中に政府公認のキリスト教団におもねった日本の教会とオーバーラップします。地上での最後は絞首台の露と消えるボンフェッファーですが、天では主の慰め癒しそして祝福が大いに注がれていることはクリスチャンなら充分に理解できることです。まさにキリストに倣うものとして人生でした。途中、画面がくらいのと、難解なシーンもあり幾度か気を失いました。
まさに不屈の闘志
カナリス提督のことを想い出す。
ヒトラーと戦った比類なき聖職者、ディートリッヒ・ボンヘッファーの一生を描く。
彼が、他の牧師と違っていたことの一つは、若い頃、米国に留学した経験があり、その時、ゴスペルに触れていること。その後も、ロンドンのドイツ人教会の牧師として赴任し、世界教会会議議長と知り合うなど、幅広い視野を持つ聖職者であるが、国際性があった。
神学者として高い評価を得る一方で、牧師として周囲の支持を得てゆく過程で、ヒトラーが首相に就任し、ユダヤ人の追放を打ち出す。ドイツのプロテスタントの多くがそれに追随したが、彼は同志と共に、別派の「告白教会」を結成する。
ここまで見た時、彼には、政府内、特に国防軍の高官に強い支持者がいたに違いないと思った。ラジオ放送でナチの批判をしても逮捕されなかったのだから。
しかし、彼は、そのさらに上を目指す。ナチの内部に入り込んででも、ヒトラー体制の転覆を図ったのだ。映画では、43年3月の暗殺未遂が描かれているが、より重要であったのは、44年7月20日「ワルキューレ」として別の映画でも描かれた暗殺計画の方だろう。ただし、彼はすでに43年4月、ユダヤ人の亡命を幇助した罪により逮捕されていた。したがって、彼は暗殺計画の当事者というよりは「黒いオーケストラ」と呼ばれる反ヒトラー・グループの精神的な支柱だったのだろう。しかし、この計画に関与したことにより、終戦間際に、国防軍情報部(通称アプヴェーア)におけるバックボーンであったと思われる(逢坂剛さんの小説によく出てくる)カナリス提督と共に、罪に問われる。映画では、時間軸を行ったり来たりしながら描かれるため、こうした筋道は、必ずしも明らかではなかった。
一つの疑問は、当時のドイツを舞台にしたドイツ人中心の物語なのに、全編英語であったこと。資本は、米国、ベルギー、アイルランド。何よりも、米国人に見てもらいたいと制作者たちが考えたのだろう。おそらく、彼が英国国教会のメンバーと交渉を進める間、何度もチャーチルの名前が出てきたことからも、昔も今も世界の情報と金融を握っている英国人はユダヤ人迫害について知りながら、何もできなかったことを後悔していたに違いない。それで、英国の実効支配していたパレスチナの地に、隣国のレバノンを支配していたフランスの同意もあって、イスラエルを建国できたのだろう。ただし、その地の住民たちを追い出す形で。そういえば、映画の途中で、ウクライナのことも出てきた。ただ、あのキーウの谷で行われたユダヤ人虐殺には、ウクライナ警察が関与していて、それがプーチンのウクライナ侵攻の口実の一つとなっているのだが。
少々拍子抜けします
信仰のために行動をもって立ち上がった人
この映画の公開を長く待ちわびていましたから、非常に楽しみにして観に行きました。
ボンヘッファーの物語は、「軽く理解して流す」なんてとてもできない、心の深いところを揺さぶる重さがあります。
歴史も文化も日本と全然違うし、キリスト教文化が深く根付いたヨーロッパの物語は、どうしても理解しづらい部分も多い。映画なので、史実と違う部分も多分にあると思いますが、いろんな意味で距離があるのにそれでも心に響くのは、彼が「信仰のために行動をもって立ち向かった人」であるからだと思います。
もし今、戦争や迫害があったら?
自分ならどうするのか?
・・・考えさせられます。
ボンヘッファーはまさに「行動する神学」を生きた人ですね。
この映画は万人向けではないし、レビューも高くはならないでしょう。でも、「理解される人数は少なくても、深く届く人がいる」そのような作品なのでしょうね。私にも心の深いところに希望の灯がともりました。楽しみにして観に行けて、とても感謝です。
この作品の制作はもとより、日本上映のために力を注いでくださったすべての方に感謝しています。
彼の書いた詩でできた賛美歌「善き力にわれ囲まれ 来るべき朝を待とう」の歌詞のとおり、やがて御国に入る朝が来たときには、会ってみたい人物のひとりになりました。楽しみにしておきます。
生き様
クリスチャン映画ですね
どこまでも神を信じて教義に突き進む彼の姿は殉教者ですね
ストーリー展開のためなのか「まだホロコーストは起きてないのでは?」「チャーチルはもう首相だっけ?」とかちょっと史実と食い違うような気がします。
クリスチャンの方はきっと楽しめると思いますが僕は違うのですいませんでした。
彼の取った行動は正しかったのだろうか
あんな方法で暗殺出来るわけない
第2次世界大戦下のドイツで、牧師でありながらスパイ活動に身を投じた実在の人物ディートリヒ・ボンヘッファーを描いた伝記。
ナチスが台頭してきたドイツでは、独裁者ヒトラーを神のように崇拝する聖職者たちにより教会が支配されていた。この状況に危機感を抱いた牧師のボンヘッファーは、教会は聖域であり、権力の場ではない、と反発し、ヒトラーを全人類の脅威と見なした。ドイツ教会を守るべく国内外の協力を求め、スパイとなった彼は、ナチス政権を崩壊させるため、ヒトラー暗殺計画、に加担したが・・・そんな話。
教会の牧師が主人公だから、キリスト教に詳しくないと深くは楽しめない感じがした。
殺されるとわかっていてベルリンに戻ったのは、命よりも大切な事が有る、からなのだろうが、生きていてこそ、という面もあると思うのだが。
それと、あんな簡単な方法でヒットラーの暗殺なんか出来るわけない。もう少し入念に練った作戦かと思ったら、拍子抜けだった。
日本も他人事ではない歴史
私は牧師ですが、牧師になるための勉強ではほぼ触れるであろうボンヘッファー。映画化するのを知って、楽しみにしていました。映画としては、キリスト教的な素地がないと理解が難しいのではないかな?と思いましたが。キリスト者としてはすごく深い映画でした。一貫して、虐げられているものの側に立つことを描いているんだなと思いました。
ここで思うのが、ナチスの時代にドイツに起きていたこと。ヒトラーの神格化でドイツは戦争に国として参加しました。そして、当時日本は天皇を神格化して戦争に参加しました。ドイツにも日本にもキリスト者はいました。全く違うのは日本のキリスト者はドイツのキリスト者とは異なる対応に出たことです。それによって、日本のキリスト者は朝鮮のキリスト者を殉教にまで追いやっていますし、偶像崇拝の罪を犯しました。見ていてものすごく考えさせられます。
憎悪に人種は問わない…
全65件中、1~20件目を表示