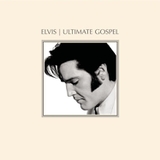光る川のレビュー・感想・評価
全39件中、21~39件目を表示
ユーロスペース最終日
「光る川」の引き込まれていく物語の始まり方がとても好きです。
私の中でこの物語は3度のはじまりがあると思っていて、その3度に水が落ちて丸く円になる映像が映し出されている。
それぞれ生活や時代は違えど、確かに同じ場所でおきた出来事が、静かな川の流れから激しい流れへと変わっていく。
川の流れだけでなく、人の心や思いも変わっていくのもリンクしていておもしろかったし、じわじわと心に残った。
町娘のお葉が朔に出会う前と出会ったあとの顔の表情が違うのも印象的だった。
恋をする女性の顔つき、目がふわっとしていたものが、目に色が濃く、美しさが増してほんと素敵に見えました。
ユウチャが紙芝居を観たあとに、川の上流から器が流れてきて、バッチャに昔話を聞き、ユウチャが青い淵を目指し進んでいく姿はまるで、ジブリの映画を想像させられるように、まっすぐで勇敢で、だけどなんだか可愛くて、2人を惹き合わせる瞬間は感動的でもありました。
ちゃんと草笛を持ち帰らず捨てている姿、だけどまだ子供らしく、お父さんに最後はおんぶされていて、すべてがキレイに終わる本当に素敵な映画だった。
また好きな映画が増えました。
華村推し。
前作ワンダリングを観て印象良かったし、華村あすかのスチールがかっこ良くて見に来た。
オーディションで選ばれたらしいが手足長くて、小顔であどけなく、あごも小さい現代的な美しさの子で山里の娘役大丈夫か?と思ったが演技もなかなかしっかりしてて、透明感あり破綻なく見れた。
顔の形が良いので髪アップが大変似合うなぁ。
今後の成長が楽しみ、新規推し決定である。
さて話はいつもの日本民俗学的ファンタジーで良いのだが、会話というか脚本というかどうもしっくり来ない。常連の役者達なのに何処か現代的、しかも説明的に感じてしまった。絵が美しいし話もシンプルだからもっと絵の力を信じたら良いと思う。言わずに感じる方が深く刺さるよ。終わり方も少々安っぽい感じがしてしまった。
タイトルバックの木版画調のアニメが素晴らしい。
岐阜県の川が舞台
美しい横顔のチラシだったが、金子雅和の第1作、第2作のレビューを見て、難解な作風なのかなと思い、最初は見ないつもりだった。ただし、この光る川のレビューは高評価が多く、あわてて映画館に駆け込む。結果は私の見込み違いで、素晴らしい映画だった。観客はいないわけではないが、少な目でシニアのみ、若い人がいないのは残念。シニアの人たちはどこでこの映画の評判を聞きつけて見に来るのかと思った。中部圏です。昨年の「重ねる」も岐阜県の自然が舞台で良作だったが、本作の自然描写は神秘的で、さも何かを物語るような深遠な川の美しさに引き込まれる。さらにストーリーは昔話と現代とを見事に融合させ、わかりやすく、時間を飛躍させている。古い日本の田舎暮らし、その厳しい環境でたくましく生きる人々。一方、現代でも厳しい現実はある。痛切ながらも強く心に訴えかける物語である。
華村あすかさん
チラシや予告編で華村さんの美しさに惹かれて観に行こうと思いました。
本当に美しかった。
失礼ながらあまり存じ上げませんでしたが、ネットで拝見した現実の華村さんよりもむしろ今作のこの役の方がまとめ髪や着物が似合っていて、所作もお芝居も良かったです。
こんな素晴らしい女優さんがいたのか、これからの活躍を期待したい、活動情報を見たいと思って検索しましたが、SNS等では見られず、どういう感じなのでしょうか。
舞台挨拶にも出ておられないですし、本当にいる人なのか。
役柄同様、神秘的で幻を見るようです。
作品は、過酷な撮影で蜂やヒルの被害もあって大変だったとのことですが、そういうことが分からないくらいの俳優さんの演技、素晴らしい、美しい作品でした。
美しく高品質の絵が印象的
美しい日本を情景を世界に伝える金子雅和監督待望の新作!
過渡期の想像力の現代的な意味について
2024年。金子雅和監督。1958年の岐阜県長良川の上流域。さびれゆく集落の再生のために、人々は神聖な山を切り開こうとしている。しかし、そこにある青い池には古くからの言い伝えがあった。紙芝居でそれを知った少年はその物語にのめり込んでいき、という話。
1950年代はある意味現代社会とはいえ、田舎では言い伝えがリアリティをもっているという前提がある(日本はまだ第一次産業従事者が多数だったはず)。青い池の悲劇やそれを元にした伝説はまだ生きている(祖母の世界)。しかし、近代的な懐疑もお金儲けのために仕方がないという資本主義優先の思考も一般化している(父の世界)。そのうえで、少年はフィクションを通して、フィクションを信じる力を梃子にして、伝説の世界へ飛び込んでいくことで、現実の世界を変えていく。この全体が1950年代という過渡期の物語だ。
2025年の現在、そもそも言い伝えがリアリティをもって受け入れられる素地はない。だから、それへの懐疑もないし、資本主義的思考は当たり前すぎて取り上げられることさえない。この世界では、劇中の少年のように、フィクションを信じる力を梃子にするだけでは伝説の世界に飛び込んでいくことはできないし、現実の世界を変えることはできない。では、この映画はなにをしているのか。
グローバルな価値観が隅々までいきわたった現代社会における文化相対主義的な抵抗、とひとまずはいえそうだ。文化相対主義が持っているアイデンティティ政治の危うさも含めて。相対化の度合いが増えると普遍化の度合いが減る。この映画では「愛」が普遍的なものとして追及されていないのもそのせいかもしれない。
水と緑に癒されてきました
安田顕さん目当てで見に行きました。
勝手に、カメオ出演的なあまり出番のない役かと思い込んでたんですけど、予想外に出番が多くて満喫。情の深い父親として、娘や息子に向ける優しい顔、娘の幸せを願う思いのあまり大声で怒鳴りつける炉端のシーン、地に這いつくばって懇願する木地師たちとの直談判、どの場面でも声の緩急の迫力がすばらしくって観に行った甲斐がありました。
ストーリー自体は、嵐の中子ども一人を滝に行かせてしまうお祖母ちゃんは幼児虐待だと思うし、悲恋伝承のふたりが実は結ばれて現代(というには昔ですが)でも嵐が収まって山が開発から守られるというオチはちょっと安易な気がしてしまうのですけど、日本昔話の世界はまあ理不尽で不可解なものですものね…。
川や風の音、山の中の踏み分け道、滝と鵜の目の淵、と自然の風景がなつかしくも美しくて観ているだけで森林浴気分で、小学生のころの金剛山遠足を思い出していました…。
土地の伝承
「こんな美しい映画があるんだ」
もはや映画自体が伝承だ
アルビノ現象を山神と祀る村人の不変の作法を描いた「アルビノの木」。
絶滅したニホンオオカミの軌跡を探し求めているうちに、かつて、そこに住んでいた人たちの想いとリンクし、時を共有するという不思議な体験の「リング・ワンダリング」。
そして、ネイチャー三部作として「光る川」。
三本ともに、ストーリーはいたってシンプル。
しかし、セリフを少なめにし、川のせせらぎの音や木々の風に揺れる音、鳥の声、自然気象の音などを印象深くすると、とても奥行きが感じられた。
過去の人と時を共有するとは、流行りのタイムリープなどのSFとは違い、そこにはもう存在しなくなっても、その想いがそこに残り、それが霊的に同期する事であって、いかにも日本的なネイチャー作品なのだ。
それを象徴しているのは滝だ。
いつも滝が作品の鍵を握っており、そのパワーを伝える撮影に感服する。
監督は日本を良くわかっておられる。
生活のすぐそばに霊的なものがあり、それは想いであって、それこそが伝承なのだと思います。
没入新体験ー時空を超えて
旅をしてきました。岐阜の深い緑の山々。青々した清らかな川や滝。その大自然の中で出会い恋に落ちる山の民の若者と里の娘と。大きな使命を背負い山奥の道なき道を行く幼いユウチャと。彼らとともにに歩き、川のせせらぎの音、鳥たちのさえずりを聞き、轟く滝の水しぶきを浴び、木々のむせる匂い、穢れを浄化する空気の中にいたんです。そして、草笛が響く。その音色に鷲掴みされ。。。
原作小説がすごく好きで(自分的には副題の本家の上をいく)映画期待してみました。
松田悠八著『長良川 スタンドバイミー1950』にインスパイアされた金子監督の映画は、小説とはまた違うストーリーでしたが、作者へと、描かれた岐阜の自然と営む人々へのリスペクトとオマージュは、損なうことはなく、むしろより深まり神々しいほどでした。オールロケの圧倒的な映像美は、パンフにはー ロケ地を1か月ほど監督自ら探し歩き、その土地に息づく気配を感じ、民話や伝承から選んだーとあり納得しました。だからこそでしょう。客をスクリーンに引き込む装置が映画にセットされているに違いないと思うほど。これはですね、絶対に自宅のテレビではできない新たな体験だと言えます。映画館で見るべき映画だと実感しました。それにしても、美しく哀しい。そして優しさにあふれていました。
近年のマイベスト。お薦めします。
自然に宿るもの
アンビバレントな映画か
マルチエンディング紙芝居
日本的自然観と霊性の視座から創造秩序と人間性回帰を問う
金子雅和監督が長良川流域を遡り自然光の中で撮影した映画「光る川」は、現代人が忘れかけている自然への畏怖や人間の根源にある生命力を、岐阜県内をロケーションした圧倒的な実景撮影と民俗学・美術に裏打ちされた世界観で描き出す作品として国内外から注目を集めている。この映画は、無垢な少年の眼差しを通して、現代化への分岐点となる高度経済成長期と、人々が自然への畏怖を抱いていた300年前の時代とが邂逅する物語。
現地撮影による川面の煌めきなどの映像美、高木正勝による自然音を活かした音楽性もすばらしい。ローマ・カトリック系メディア「オッセルヴァトーレ・ロマーノ」は、2015年に刊行されたフランシスコ教皇の回勅「ラウダート・シ――ともに暮らす家を大切に」との思想的親和性を論じられている。キリスト教も含め海外からの高い関心が寄せられていることが興味深い。
監督:金子雅和 2024年/108分/日本/英題:River Returns/ 配給:カルチュア・パブリッシャーズ 2025年3月22日[土]よりユーロスペースほか全国順次公開。
全39件中、21~39件目を表示