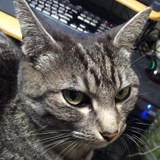「JRの広報映画―脱線しない物語と、再構成される安全神話」新幹線大爆破 ぐにゅうさんの映画レビュー(感想・評価)
JRの広報映画―脱線しない物語と、再構成される安全神話
1. 存在しない社会批判
かつて1975年版の『新幹線大爆破』は、国家に振り落とされた人間の、静かで必然的な怒りを描いた作品だった。あの列車が象徴していたのは、高度経済成長という名のレールの上を疾走する「豊かさ」であり、その影に取り残された者たちの無言の抵抗だった。
だが、今回のリメイク作品には、そうした社会構造への批判性は決定的に欠けている。表層的には“何かが起こっている”ように見せながら、その実、観客に差し出されるのは「事件」と「対応」のマニュアル的な展開に過ぎない。誰が怒り、なぜ列車を止めようとするのか──その問いに対する答えは、最初から用意されていない。
物語の核にあるべき「なぜ今、この物語を語るのか」という問題意識が欠落しており、その代わりにあるのは、ただ整った演出と速いテンポ、そして緊急事態対応の様式美である。
結果として、この映画は“何かを描こうとしていない”というよりも、“最初から描くつもりがなかった”とすら思える。それでも列車は走る。映画の中でも、現実の興行的戦略としても。
2. JR東日本のコマーシャルとして
この映画を見終えたとき、真っ先に思い浮かんだのは「これはJR東日本のブランドムービーだった」という一言に尽きる。映像は端正で、車両の描写は美しく、司令室の緊張感や乗務員の冷静な対応は、まさに企業が社会に向けて打ち出す「安全神話」の再構築である。
その中で、あからさまに“物語的な存在”として置かれているのが総理補佐官のキャラクターだ。
彼は最初、現場を無視して強権的に介入し、明らかにわかりやすいビランとして振る舞う。観客はすぐに、「ああ、こういう人が混乱を招くんだ」と理解する。
しかし後半になると、人命を優先する姿勢に“突然”転じ、最後には神妙な顔で頭を下げる。展開としては丁寧に伏線を張っていたわけでもなく、単に予定された感動を生むための“更生型キャラクター”に過ぎない。
さらにこの人物にはもう一つ、演技面での問題がある。現場のリアリティを体現するJR職員たちの抑制された演技と比べ、補佐官だけが過剰に芝居がかっており、映画のトーンから浮いている。このギャップが悪目立ちし、「ドラマ」と「広報映像」が並走してしまう違和感を生む。
つまりこの作品は、最初から“緊張”を物語に埋め込むのではなく、“混乱しても最後はうまくいく”という結末を予定したうえで、必要な対立構造を後付けしているように見える。そしてそれこそが、企業PR的構造の典型だ。
列車は止まらない。誰もが職責を全うする。そして最後には“誰かが”謝って物語が閉じる──
これはエンタメの形式を借りた、極めてよくできた広報映像である。
3. 犯人
本作における犯人は女子高生であり、後半でその正体が明かされる。
彼女は確かに観客の視線を引きつける存在だ。犯人と判明したあとの表情の変化には息を呑むほどの迫力があり、若手俳優としての力量をまざまざと見せつけた。
だが、それにもかかわらず、彼女は物語を成立させるための舞台装置として扱われている。
設定そのものはよく練られている。彼女の父親は1975年の“旧事件”で、犯人を銃殺した「英雄」とされていた人物である。その栄光は実は演出であり、父はその嘘に囚われることで支配的な人格となり、娘である彼女に虐待を繰り返していた。
その結果、彼女は“父の栄光の舞台”である新幹線を自らの手で破壊しようとする──動機の連関には一定の説得力がある。
だが、この構造は物語の進行上、単に「納得できる設定」として使われるだけで、彼女自身が“人間”として描かれることはない。
彼女がなぜそうせざるを得なかったのか。彼女がどのように日々を生き、どんなふうに壊れていったのか。そうした内面への想像を脚本は促さない。
あくまで彼女は、「このタイミングで事件が起こる」ために、そこにいる。
そのため観客が感じるのは、彼女への共感や葛藤ではなく、「ああ、このために仕込まれていたんだな」という構造への納得である。
そしてそれは、犯人が象徴でもメタファーでもなく、「事件を起こすための役割」としてのみ存在していることの証左に他ならない。
ここには、人物の生きた痛みではなく、整えられた物語の“運行”がある。
その意味で、彼女の存在すらまた、列車と同じく脱線しない設計のもとに動かされているのである。
4. 動機
本作における犯人の動機は、父への復讐である。
1975年の旧事件において、父は犯人を銃殺したとされ、「英雄」として称えられた。だがその神話は演出によって作られたものであり、父はその虚構の中で自尊心を肥大させ、娘である犯人に対して日常的に暴力を振るうようになる。
犯人は、自らを苦しめた“父の栄光の舞台”である新幹線を標的とする。
この動機は、個人的な恨みという次元を超えて、国家が作り出す虚像、そしてその影で繰り返される家庭内暴力という社会的構造を内包し得た。
加えて物語の中には、この動機をさらに深く読み解くための要素がいくつも配置されている。
彼女は修学旅行中の生徒であり、教育制度に包摂されながらもそこから逸脱しようとする存在である。
乗客には国会議員という政治的象徴が同乗しており、鉄道・教育・国家という、日本社会の制度的三位一体が偶然にも同じ空間に収められている。
また、車内で暴力沙汰が発生するシーンでは、彼女自身が非常ボタンを押すという行動を見せる。
だが、列車は止まらない。
その場を静めたのは、車掌としてその場を制圧しようとしていた主人公の社用電話であり、極めて制度的な「上からの声」によって事態が制圧されるという構図になっている。
その直後、犯人は車掌に問う──「守りたくない人を、なぜ守るのか?」
それに対して車掌は、「そんなことは考えていない。ただ、お客様を安全にお届けするのが私の仕事です。」と答える。
ここには明らかに、倫理の裂け目が見える。
誰を守るべきか? なぜ守るのか?
制度の内側にいる者たちは、個人の良心ではなく“職務”としてしか行動できないのか?
しかしこうした問いは、脚本の中で掘り下げられることなく、そのままスルーされる。
犯人が発する問いには、確かに物語の核心を揺さぶる可能性があった。
だがその問いは、観客に引き渡されることなく、その場限りの“いいセリフ”として消費される。
彼女の行動は、構造の暴露であり、制度批判として成立し得た。
だが映画は、それを“感情的な背景”にとどめてしまう。
そのために、観客は「理解」はしても「共振」はしない。怒りは連鎖しない。問いは拡がらない。
この動機は、構造として描かれたのではなく、構造から意図的に切り離された。
その選択が、映画の射程を決定づけてしまった。
5. 総括―疾走する映像、思考を置き去りにして
本作は、エンタメ映画として驚異的な完成度を誇る。
映像、編集、音響、演出、俳優の演技──どれを取ってもハイレベルで、ハリウッドのスリラーと比べても遜色はない。
観客を引き込み、緊張感を持続させ、最後まで駆け抜けるその構成力は見事であり、商業作品としては大成功と言えるだろう。
しかし、それほどの完成度を誇るがゆえに、ある種の“空白”が際立って見えてしまう。
それは、ドラマの不在である。
1975年版『新幹線大爆破』は、国家の成長からこぼれ落ちた一人の男を中心に据え、社会の歪みと、社会に無視された者の怒りを静かに、しかし確かに描き出した作品だった。
爆破そのものが目的ではなく、「叫び」であり、「存在の証明」だった。
あの作品には、時代とぶつかりながら生きる人間の“切実さ”が、確かに映っていた。
一方で本作は、すべてが整いすぎている。
怒りは背景に閉じ込められ、動機は説明され、衝突はすみやかに処理されていく。
事件が起こっても、新幹線は最後まで止まらず、事件は解決され、すべての秩序が回復される。
まるで、新幹線が運転を再開するように。
ここには、観客の感情を揺さぶる葛藤も、物語の終着点としての変化もない。
物語が疾走する一方で、思考は車外に置き去りにされたままである。
本作が手にしたのは、「傷つけずに消費される怒り」と「脱線しない物語」だった。
あまりにうまくできているがゆえに、映画がかつて持っていたはずのざらつきや痛み、そして語られるべき“不安”が、どこにも残されていない。
その無傷さこそが、本作がJR東日本のコマーシャルであるという私の評価の核心だ。
新幹線は予定通りに破壊され、予定通りに人が死に、すべては正確に元のダイヤへと戻っていく──怒りも祈りも、そこには乗っていない。