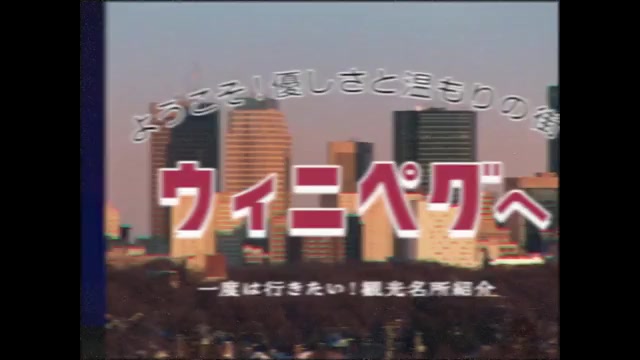「始まりは終わり、終わりは始まり」ユニバーサル・ランゲージ ジュン一さんの映画レビュー(感想・評価)
始まりは終わり、終わりは始まり
物語りの舞台はカナダ。
公用語は英語とフランス語のハズも、
本作で使われているのは主にペルシャ語とフランス語。
主要な登場人物たちの肌の色も浅黒く
どうやら「メタ世界」の設定。
一方で、ケベック州独立問題など、実際の事柄は、
会話の節々に上がっている。
タイトルの「ユニバーサル・ランゲージ」を最初に聞いたときは、
『ザメンホフ』による人工言語「エスペラント」を想起した。
が、「エスペラント」は「ユニバーサル・ランゲージ」と表現されることは無いらしく、
どうやら異なる意図で使われているよう。
もっとも劇中では、「ザメンホフ通り」との、
(おそらく架空の)地名により、ふれられてはいる。
地方都市ウィニペグの小学校。
フランス語教師から嫌われている『オミッド』は
黒板の文字が読めない理由を、
駐車場で七面鳥に眼鏡を盗まれたからと話す。
当然、教師には信用されぬも、
不憫に思った同級生の『ラギン』は眼鏡を探しに行く中途で
氷に埋もれた高額紙幣を見つけ、
これを掘り出せば『オミッド』に新しい眼鏡を買ってあげられると、
姉と共に奮闘する。
他方で、モントリオールでの生活に疲れ、
母親が独り住む故郷のウィニペグに戻ろうとしている『マシュー』がいる。
久し振りに実家に電話を架けると『マスード』と名乗る見知らぬ男が出、
今夜会おうとだけ伝えられる。
母が住むハズの実家に向かえば、
そこには見知らぬ家族が暮らしており、
狐につままれたような思いも湧き上がる。
この二つの挿話が、終盤
絶妙に交錯する。
意表を突く人物の繋がりが明らかになり、
胸に刺さる団円を迎える。
そこに流れるのは、人々の溢れる善意と、
取り返せね過去への喪失感。
とりわけ後者は、
『マシュー』と『マスード』が入れ替わることで
より強く観る者に印象づけ、
戻らぬ時間を巻き戻そうとするかのような
記憶に残るラストシーンへと繋がる。
『マシュー』役は監督本人(『マシュー・ランキン』)が演じており、
出身地もウィニペグとのこと。
一種の{私小説}に近しい作品のようで、
彼の故郷に対する偏愛とも取れる表現やエピソードが頻出する
(故郷以外でも『グルーチョ・マルクス』への思いも随所に見られる)。
もっとも、とりわけ街の変化は、地域住民にとっては理解の範疇も、
背景を知らむ地球の裏側に住む我々には埒外。
薄っすらと伝わりがするが、隔靴掻痒さを覚えるのは否めない。
要は、あまり普遍さを感じさせない要素になっている。
〔ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ(2019年)〕鑑賞時と
近似の感情がわだかまる。