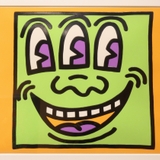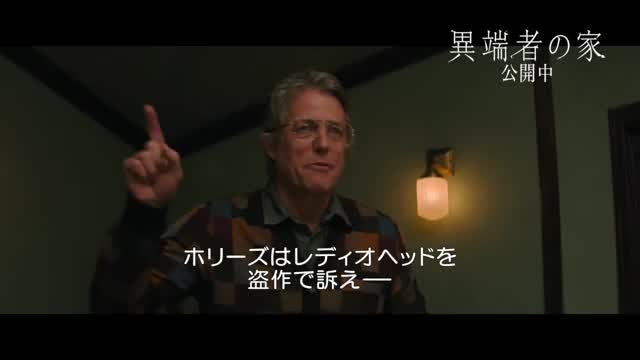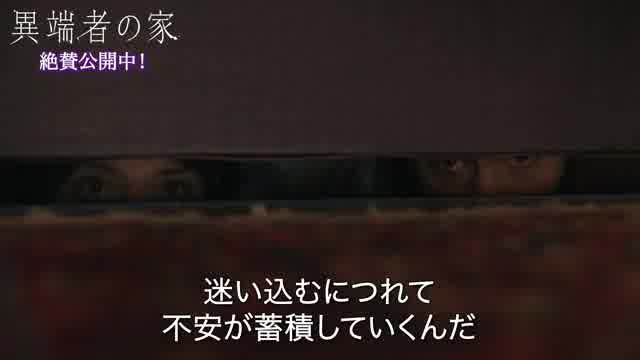異端者の家のレビュー・感想・評価
全93件中、41~60件目を表示
異端者はどっち?
予告編からは、布教に行った先がたまたまサイコパス男だった、くらいのお話かと思っていましたが、もっとヘビーなやつでした。
あらゆる宗教に疑問を抱く男、Mr.リード(ヒュー・グラント)が、自分が信じる「唯一神」を証明するため、他宗教を布教してくる輩を論破してやろうと待ち構えており、モルモン教の布教に訪れた若いシスター2人に宗教観の揺さぶりをこれでもかとかけていきます。
否が応でも、観客も自分にとって「宗教」とは何か?という問題と向き合わさせられる羽目に。
※モルモン教はキリスト教を源流とする新興宗教で、立ち位置的には日本でいうところの統一○会、エ○バの証人、みたいなものですね(教義は全く違いますが)。劇中に出てくる「魔法の下着」はモルモン教徒が身につける特殊な下着です。
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は劇中では「ビッグ3」と揶揄されていますが、どれも同じ「神」(ヤハウェ、父なる神、アッラーなど、それぞれ呼び名は違いますが)を崇める一神教です。同じ神様を祀るなら仲良くすればいいのに、互いに「他宗教の神は神にあらず」と異教徒を敵視しているのが傲慢だなーと常々思っていました。
Mr.リードのやり方は過激ですが、自分の意に沿わない出来事に対して「神様の与えた試練」「全ては神の御心のまま」などとこじつけのようなことを言って思考停止しているように見える人々をネチネチいたぶりたくなる気持ちも…わかる。
(私は中高6年間たまたまミッションスクールに通っていましたが、キリスト教について知れば知るほど偽善的な部分が目につき、絶対に信者にはならん!と固く誓ったひねくれ者です)
ちなみに、キリスト教の「神」とは「三位一体」の「父なる神、イエス・キリスト、精霊」があわさったものです。
イエス・キリストは、人間の原罪を贖わせるために「父なる神」が地上につかわせた「神の独り子」で、奇跡を起こし、十字架にかけられて死に、40日目に復活しました。イエス・キリストの復活を信じること=神の御業信じること、ひいては「父なる神」を信じることに他ならぬことで、この映画でもリード氏が「復活」にこだわっていたのはそのあたりの感覚が染み付いているのかなと。
キリスト教圏の人間にとって、復活の奇跡を信じることは信仰の証明につながるんでしょうね。
終盤になって判明するリード氏の信じる唯一神に私は妙に納得してしまいました。
宗教って言ってしまえばそのためにあるものでは、と前々から思っていたので。
(その文脈でいえば、仏教は宗教ではなく哲学ですね)
異端者なのは彼とシスターたちのどちらなのか?という目線で見ておりましたが、原題は「HERETIC」(異端者)、かつ、ラストに出てくるタイトルがぼやけていて見えない…ということは?
…と、色々と考えさせられる映画でした。
映画的な側面に目を留めると、ヒュー・グラントの巧みな話術を交えた悪魔的な演技がすばらしく、恐怖演出も相まって本当に怖かったです。
モノポリーの話の最中に、ボブ・ロス版のモノポリーが出てきて、くすっと笑ってしまいました。
「ボブの絵画教室」、懐かしすぎる。
あんなのあるんですね〜。
他のミームに関してはわからない物もあり、かつとても情報量の多い映画で一度では理解できず。
これから、ネタバレサイトやここのレビューで勉強させていただきます。
信仰者から観る「Heretic(異端者)」
予告編からは、何か脱出ゲームのような物語を想像していましたが、実際には宗教色が非常に強く、予想とは大きく異なっていたが、タイトルである「異端者」のテーマに非常に的を射ており、エンタメとしても宗教の観点からも興味深かったです。物語は大きく分けて、前半の会話中心のパートと、後半のホラー気味のミステリーパートという二部構成になっていて、それぞれ異なる面白さがありました。
人によっては前半の会話パートが退屈に感じるかもしれませんが、信仰を持つ者として、普段から似たような感じで他人と語り合ったり議論したりしているので、3人の会話は非常に面白く感じました。途中で男性は「これは不快に思わせるかも」「怖い話になるかも」と、世の中の宗教に対して挑戦的な姿勢が出てきますが、信仰心が強い者にとっては、日頃から学び続けているので、そうした問いに対し説明する機会を与えられるから、むしろ歓迎すべきだと感じます。正直、議論をしたいだけでしたら、扉が開く朝まで全然付き合いますよ(笑)。もちろん、あんな不気味な状況でなければ、ですが。
後半からは、本当の恐怖が始まります。途中まではスピリチュアルな物語なのか、それとも何か仕掛けがあるのか分からないように物語が発展し、3人の対峙を通して少しずつ真相が明らかになり、ややグロテスクな描写もありますが、巧妙な洗脳の過程と心理戦は非常に興味深く感じました。最終的に全員を救うことはできませんでしたが、1人だけでも救えたことにより、監禁されていた女性たちの救いに繋がったと、完全にバッドエンドではなかったのが救いです。
個人的な考察になりますが、異端者として描かれた男性は、「人間の傲慢」の象徴だと思います。彼は非常に頭の切れる人物であり、同じ手法で人を洗脳するたびに「自分こそが正しい」と確信し、それを繰り返すことで自分の欲望を満たしていました。ただ、彼が狙ったのは信仰心がまだ確立されていない、そして布教経験が浅い若い女性ばかり。本当は、自分と同等かそれ以上の相手に挑む勇気は持ち合わせていないのに、弱い者に勝つことで「自分は他人より優れている」と思い込む――まさにそれこそが「傲慢」であり、タイトルの『Heretic(異端者)』が示す意味だと感じました。実際、こうした極端な手段を使うわけではないにせよ、宗教者にわざと難解な質問を投げかけて、うまく答えられなかったことを理由に、自分の正しさを証明しようとする傲慢な“異端者”は、世の中に少なからず存在しています。
本作は最終的にスピリチュアル系の話ではありませんが、確かに「奇跡」が起きたと感じさせる展開でした。しかし、その奇跡を過剰に神聖化せず、控えめに描いている点は、個人的には好感を持てるポイントです。
PS:祈りには効果があります。しかし、それが人間の欲望を満たすためのものであれば、効果はありません。だからこそ、作中に登場する「祈りの実験」には本質的な意味はないです。
異端 vs 異常
「脱出サイコスリラー」って書いてあったけど、メインは宗教論争じゃないですか…
シスターが猥談を繰り広げる導入にまず驚いた。
リードとの対話は背景説明や伏線なども入っているので有意義ではあるが、なんだか冗長。
自分が無学で、何がどれだけ異端か分からないってのもあるんだけど。
このテの作品ってなんで最初から不穏な空気出すんだろ。
粗筋で分かってるとはいえ、朗らかな雰囲気から豹変って方が個人的には楽しめるのだが。
その後も期待した脱出ゲーム的な展開にはならず。
モノポリーやパクり問題の喩えは面白かったが、語ってる内容としては別に新しくもない。
結局は、宗教すべてを信じられなくなった男が、マンスプレイニングからの支配を試みる話。
でも、そんなことのためにここまでやるかね。
“復活”の(有り触れた)トリックも“仕込み”が大変なもので、更に一件につき一人“使い捨て”るんでしょ。
その“処分”も含めると、難易度高過ぎでは。
パクストンが急にしっかりしだすのはまだしも、バーンズ復活はあまりにご都合主義。
直前に開閉があった“床下収納扉”が隠れてるのもおかしい。
「祈りは無意味だが、誰かを想って祈ることは尊い」という、宗教を否定も肯定もしない結論はよかった。
主役2人が正教から異端扱いされてるモルモン教、という構図も興味深い。
でもこの設定との食い合わせは好みではなかった。
最後のアレにはちゃんと意味がある
ネタバレ無しで感想を書くつもりだったが、最後に出てきた蝶を見て理解していない人が多いのでビックリした。バタフライ効果ではない。この映画は信仰と否定の戦いのものだ。途中でシスター・パクストン(金髪)が「私は蝶に生まれ変わって指先に止まる。それが私の証だと分かるように」と言っていた。つまり最後の現れた蝶はそれを連想させるものであり、もしかしたらそれを一緒に聞いていたバーンズ(黒髪)が真似(信仰)したのかもしれないし、幻かのような表現があったので未来の自分自身かもしれない(信仰を否定しかけたのにコレを切欠に本心から信仰に目覚めた可能性)、そういう奇跡の誕生だったという話しだ。またバーンズが復活したのもキリストの信仰(恨み、支配、憎しみ)そのものであった、という話しで、犯人は幸せの中で死んだのだろうし、何度でも深読みしようと思ったら見返すことができる構成になっている。これは明らかにソウのように意図的に考えられた物しか写っていない。お客とはいえ、なぜ偉そうに映画を見下そうとするのだろうか……。
脱出迷路ではなく、討論と推理ゲーム
予告を見る限りだと複雑な仕掛けがある家からの脱出を目指すような内容だと思っていましたが、蓋を開けてみれば全然違う内容であった。宗教布教のためにある男の家に訪れた女二人と宗教についての会話が繰り広げられるが、なんだろう、この常にまとわりつく恐怖感は。。。その恐怖感の正体は男のちらつく独自の思想か。。。予想と違った内容であったが、2時間退屈する事はなく楽しむ事ができた。支配こそ絶対の宗教と考えていた男であるが、死への恐怖から結局、女に祈りを捧げることを求めていたいたのがなんとも人間らしいなと感じた。
宗教バトルしようぜ!お前モルモン教代表な!
俺?俺は「支配」教!👐
宗教について研究し尽くした結果こじりに拗らせた感じですか?
色々知りすぎたり勉強しすぎたりした結果、うがった見方しか出来ない人は研究職向いてませんよ。
素直にまっすぐ見ようという姿勢も必要なのに斜め方向からしか見れてないってことじゃないですか。
常に第三者視点、俯瞰して見れない人は止めといた方がいいですよ。
こうなりますから。
って教訓ですかね?
いやまあ深いこと考えずとにかく祈れよってことかも。
序盤の論争というか講義、面白かったですよ。
有識者ならすごく白熱するんでしょうね。
宗教講義を2時間聞いてたらいつの間にかスリラーになってたという映画でした。
その内助けが来るってわかってるなら地下に降りるなや地上で粘れよとか無粋な突っ込みはなしで…
まあまあスリルとちょいグロと女の子頑張れ💪を楽しめましたよ!
まあ、別に、特筆すべき箇所もありませんけどね…
Go to sleepな世界の始まり。
宗教オタクの預言者ごっこ。
自らの意思で彼の箱庭に迷い込んだ、若く熱心なモルモン教徒2人もここでは異端者である。
偏屈な年寄りvs今時珍しい若者。
オモテナシも早々に、照明ギミック発動後はウラアリ説教地獄の反復なのだが、若者も稚拙ながら強気に反論していく。
これは割と健全な「世代間ギャップ解消策」だ。
トム・ヨークのモノマネで滑っても我慢。私も、オセロと言ったら、リバーシですね?と返された事がある。
肝心なオチはあっけないもの。
すり鉢状に積み重なったノンストップ宗教蘊蓄合戦が効果的だったとは思えないが、
信仰心が、コンドーム談義に花を咲かせていた乙女2人の魂を救えなかった事だけは事実。
言語のニュアンスを忠実に知りたい作品
まず宗教モノということで、その手の基礎知識が薄い日本人との親和性はあまり高くない作品だが、多少の知識があったので一応ついていけた(まぁうっすい知識だけど)
そのうえで、大前提として男がたどり着いた結論がいまいち明確な答えになってないのが気にかかるところ。基本的に神なんてものは存在しないし、宗教なんて所詮人心を掌握・支配するためのものに過ぎないってことではあるんだろう。言わば男との宗教レスバに負けた女達が地下に閉じ込められていたということで、生殺与奪の権を握られていたから素直に言うことを聞くしか無かったと言うことなのだろうか。とにかくヒュー・グラントが強烈な圧をかけてくる議論パートが重苦しくて息苦しくて大変。
地下室の噴霧器から放出されていたものは何だったのかもよく分からない。大変おもろかったが、消化不良な部分も少なからずあったという作品でした。
ヤマなし、オチなし(加筆してます)
残酷で目を背ける場面が多かったが、特にヤマもなく。オチもなし。
ヒュー・グラントはラブコメに出ているときと全く同じ雰囲気で、サイコパスの不気味さなし。
見知らぬ女性の二人組が家を訪ねてきたら99%宗教の勧誘なので、映画を見ながらつい嫌な顔してしまった。最初から彼女たちにあまり同情的になれない。
ヒュー・グラントが長々と理屈を並べている間にいつの間にか寝てしまって気が付いたらすでにふたりが監禁されていました。
「宗教」というものに、反射的に胡散臭さを感じてしまうので、リード氏の言う事のほうが「正論」に聞こえてしまう。「宗教は『支配』だ」というのには共感するものがある。
それから、「布教者はセールスマンのようなもの」も、良くも悪くもその通りだと思うし、個人的には宗教組織は、優れた集金システムだと思っている。
(私の「信仰」は日本の八百万の神をなんとなく信じていて、若干の縁起を担ぎ、お正月には初詣をして神社で100円硬貨でお賽銭を納めて守護やご利益を祈るようなものなので、そう感じてしまうのかも。)
多分ですが、日本人はそう思っている人が多いんじゃないだろうか。
リード氏は持論として宗教=支配にたどり着き、それを証明するため、試験的に囚えた女性を恐怖で支配し、「宗教」を作ってみたのよ、どうよ、とわざわざモルモンの宣教師に見せつける。
リード氏はぷち宗教を地下室で作り上げて、自身の宗教論議に拮抗できる相手を待っているのかも、と思いました。
専門家と思しき宣教師を呼び寄せて議論をふっかけて、不合格なら実験対象として地下に監禁、そして次を待つ、という感じだったのかも。
覚醒したシスター・パクストンには、自身の箱庭宗教を見せてみて、モルモンとして議論相手となれるかもな段階に至ったような。
宗教にはこだわるが倫理には微塵もこだわらないのがアタオカで怖い。
そしてリード氏は小難しいことをファーストフードやモノポリーなど、身近なものに例えるのが上手。コドモニュースの解説者のようです。
囚えられて檻に入れられていた女性たちは、リード氏に呼ばれて宗教団体から派遣されてきた布教者たちではと思うが、あの付近で行方不明になった女性が多いということでもっと騒がれていそうなものです。
恐ろしいけれど滑稽
シンプルなワンシチュエーションスリラーで主人公たちがどうなるのかと先が気になり、信仰に対する視点なども面白かったです。
個人的に宗教勧誘などは胡散臭いと考えているものですが、主人公たちの普通の若者らしさや真面目さ、偏見に晒されている様子などが冒頭に描かれ、主人公たち個人には好感を持つことが出来たのでスリラー要素にも引き込まれました。
年長男性と若い女性という年齢差や性差など、何気にパワーバランスを見せつける会話の不穏さも印象的です。
この閉じ込められた状況では聞かされる方は恐怖でしかないでしょうし、若い女性を狙って仕掛けている家主はやはりクズだなと。
宗教等に関する家主の理屈には結構同意できますが、その上で人のために祈ることの尊さが示されるのは良かったと思います。
ラストの蝶は、彼女の魂かと思いグッときましたが、このラストが夢という解釈もできそうで。
脱出できたという方を信じたいですが。
家主の行為は恐ろしいものですが、基本的には若い女性にマンスプレイニングをして悦に入っているだけのおじさんのようで、滑稽さもあり見ているこっちがこっぱずかしい気持ちにもなりました。
昔、路上で幸せお祈り宗教に声をかけられた時、「他人の幸せを祈って意味があるのか」「他人を祈ることで自分も幸せになるとか、自分の幸せのために他人を利用しているということだろう」などと言って論破した気になっていた若い頃の自分を思い出したりもしてしまい、こっぱずかしいです。
やり尽くされたフォーマットでも、プラスアルファでマル
やり尽くされたフォーマットでも、プラスアルファがあることで映画として成立する好例。
若い女性が不気味な館を訪れてサイコパスに解禁されるという何度も見た光景。ただ、そのサイコパスはヒュー・グラントであり、若くて少々現代的なシスター、そして宗教や信仰心について語り合うというプラスのプロットによって、「もう、見飽きた」から「興味がそそられる」に変わる。
モノポリーや音楽を例にした説明。まさかのファントムメナスネタ。
そして、最強?の宗教=支配という結論。
特に悪魔ネタのホラーでは、信仰心によって主人公側が勝利という筋書きが多い中、
今回の切り口はよかった。
首を切られた女の子の謎の一時復活はあったけど。
ゾンビのような女性やサイコパスの登場場面(振り返ったらいるとか)を必要以上に観客にビビらせない、
音でビビらせない、様子を見に来た関係者を殺さない点なども
安易な方向に走らなかった結果として好印象。
名作とまでは言えないけど、
満面の笑顔からイカれ顔に変化するグラント、同系映画スプリットのアニャのような存在感のソフィー・サッチャーの演技でサクッと観るホラー映画としては満足でした。
鑑賞動機:あらすじ8割、ヒュー・グラントがおかしい2割
オースン・スコット・カードをふと思い出す。
『ブギー・マン』に出てた目力強めのサッチャーさんですね。パッとしない弱腰の相方とで、海千山千のヒュー・グラントにどこまで立ち向かえるのか。完敗の予感しかしない。
慇懃無礼というか、論破することそのものよりも、相手を不快にさせた上で優位に立ちたい感じがする。
おそらく常日頃から準備(!)してるのか。まああんな家作ってる時点でアレレな人なのだろうけど。
前半の緊張感がうすれそうになったけど終盤持ち直した感じ。ギリギリセーフ。胡蝶の夢と邯鄲の夢をごっちゃにしてたわあ。
無宗教教にとっての神は…推し?
タイトルなし(ネタバレ)
布教活動のため森の中の一軒家を訪れたモルモン教女子ふたり、シスター・パクストン(クロエ・イースト)とシスター・バーンズ(ソフィー・サッチャー)。
中から出てきたのは、気のいい初老の男性リード(ヒュー・グラント)。
モルモン教の戒律に則り、女性同席でないと家の中に入れないから、玄関先で・・・と告げるふたりに、リード氏は「妻は奥でパイを焼いている」からと答え、二人を招き入れる。
リード氏は、モルモン教の教義・戒律についての矛盾点などを披歴し、ふたりを辟易させるが、リード氏の妻はなかなか姿を現さない・・・
といったところからはじまる物語は、超面倒くさい論破男vs.純粋無垢な乙女の対決映画という、まぁジャンル映画かなぁ。
自己の価値観を脅かされることが「恐怖」の源、リード氏の論説によって自身の信仰心が揺らいでいくという前半が面白い。
が、ダンジョン的邸内で生命の危機に陥る中盤以降はフツーの怖い映画。
(ということで、少々退屈)
蝶のエピソードがいくつか登場するが、終盤、虚実を弄って観る側を混乱させようというのは、劇中登場する「胡蝶の夢」のモチーフか。
ただし、あまり感心せず。
ラストの蝶はリインカーネーションのものだろうねぇ、と。
なお、「バタフライ・エフェクト」は劇中、台詞で語られるのみ。
ヒュー・グラントの超面倒くさい男のリード氏役、これまでの役柄からかけ離れているようにみえるけれど、ロマコメの帝王だったころの延長線上にあるような気がして、妙絶なキャスティングだと思いました。
信じるのも自由。信じないのも自由。
神様も色々。祈り方も色々。唱える言葉も色々。
宗教に支配されるのか信者に支配されるのか。
目の前の迷える子羊に迷わされるとは、修行が足らん証拠の女子2人。
追い詰め方がエグいイケおじの対決。
この作品はみたらし団子の餡のように見た目よりもねっとりとそしてノドが乾くしつこさ。
ちょっといろんな知識を持つと勝手に恐怖を構築し増大させてしまう人には背筋がゾクゾクするね。
ヒュー・グラントの良さが満遍なく際立つ、そして節々に『クスッ』とさせてくれる台詞回しが良かったです。
Butterfly Effect
家ホラーや家スリラーが大好物なので今作も喜んで鑑賞。
めっちゃ家の中が迷宮なのか、トラップまみれなのか、静けさの中に迫る恐怖なのか、色々と想像が膨らんでいきました。
宗教勧誘のために伺った家の住人がどう考えてもヤバいやつで…という感じの作品で
日本に住んでいるとどうにも宗教には疎くなってしまい、宗教トークをかましている時ははて?となりながら観ていましたが、楽しそうに喋っているので愛想笑いしながら観ることができました。
宗教の本職に対して、培った知識でレスバしまくるおっちゃんがなんだか面白く見えてきて、思っていた方向とは違うけどこれはこれで…って感じでした。
制作チームの過去作的に「ホーンテッド」に近しいスタンスのイかれた家を期待していたんですが、ギミックはほとんど無しで、おっちゃんが色々なものに例えて宗教についてドヤっていき、気に入らなかったり少しでも琴線に触れたらブチギレ大爆発と思っていたより脳筋でした。
部屋のトリックとかもサクッとバレたり、行動の怪しさも全部指摘されたりとで、この人そもそも隠し事しながらの行動向いてないんじゃ?と何度思わされた事か。
家を上から見た構図なんかもお出しされるんですが、基本的にそこまで凝った作りではなく、なんなら地下室の方が凝った作りだったり真相が隠されていたりとで、もう隠し部屋作りたがりのおっちゃんじゃんとクスクスするしかなかったです。
R15+か?って聞かれると微妙なラインで、欠損描写だったりグロさはあれどそこまで刺激強めではなく、コンドームトークも別に直接的なシーンがある訳でもないので規制するほどでもないですし、別にPG12でも良かったのでは?とは思ってしまいました。
終盤の展開はかなーり無理のある展開で…映画なので多少のご都合展開は許容できる方だと思っていたんですが、祈ったらシスターが復活したり、首に思いっきり刃物を刺したはずのおっちゃんが普通に動いていたり、バタフライエフェクトの伏線回収だったりと家の構造の巧みさとかガン無視で突き進んで終わっていくのでなんだかなぁって気分になりました。
ヒュー・グラント、クロエ・イースト、ソフィー・タッチャーの3人で引っ張ってくれたおかげでレスバ合戦がなんとか観れたかなって感じです。
優しそうだけど気味の悪さを纏っていたヒュー・グラントは不気味で最高です。
ここ最近のA24は良くも悪くも尖った作品多めなのでバチっと自分にハマる作品が出てくることを願っています。
鑑賞日 4/27
鑑賞時間 18:55〜20:50
座席 A-4
ヘレテックって原題は残してほしかった
ヘレテックって原題は残してほしかった・・サブタイトルで異端者の家はありだけど
テーマが割と壮大なだけにもったいない
プロローグの若い女の子のリアルな会話からの宗教勧誘先の宗教問答はストレートに面白い
宗教についてさほど縁のない自分にとっても興味深い内容でこれがホラーかどうか関係なく引き込まれるものがあった
完全に罠に気が付いてからの緊張感はまさにホラー
ここから先はネタバレ
個人的にこちらが生き残りそうと思った人が先にやられてそのあとの怒涛の展開はテンポも速くもっと早く覚醒してれば二人とも助かったんじゃないの?と思ってしまった
いろんな伏線も回収されているようでしたが、一度では読み取りできない描写もあったみたいで他の人のレビューをみるのもこの映画の醍醐味かも
宗教は支配、祈りには力はないが人のために祈る行為は美しい
この言葉に出会えただけでこの映画を見たかいがありました
A24がクレジットされてなかったら…
A24製作といえば「ミッドサマー」、「X」、「MEN 同じ顔の男たち」など一癖も二癖もある作品が多い中、この「異端者の家」はA24がクレジットされていなかったら観賞しなかったと思います。
期待して観賞しましたが『なんだ、フツーじゃん』と期待ハズレだったのはいがめない感じでした。
ただ、あのヒュー・グラントがなかなかのはまり役でビックリしました。
そういう意味では「A24ありがとう!」と言いたいですね。
でも、死んだはずのシスターバーンズがあのような形でシスターバクストンを助けるのであればもう少し伏線がほしかったです。
家に着く前から
良かった。
予想していた迷宮脱出ではなかったがこの感じもなかなか良かった。
まずヒュー・グラントもそうだが女優2人もめちゃくちゃ顔がいい。ああやっぱり女優は美人だわと思った。
ということ以上に脚本が結構よくできていたように思う。
リードおじさんがモノポリーで宗教を表現する演出は面白かった。
モノポリーを調べたら本当に原型になるエリザベス・マギーの地主ゲームが出てきた。
まあ作中でもツッコミがあったように地主ゲーム、モノポリー、モノポリー別バージョンがユダヤ教、キリスト教、イスラム教というのはだいぶ大雑把過ぎではある。けれどもなるほど感はあった。うわ、自分支配されちまうわ。
ショートのバーンズの方が抗っていて一見強そうに見えるが、であるがゆえに退場が思いの外早かった。
ロングのパクストンの方が流されやすい雰囲気を醸し出しつつバーンズ死後は戦う決意をするのは成長物語感があって良かったと思う。
序盤に写真撮る女の子達に騙されてマジックパンツさらされたのすら後半の伏線になっていた。
バーンズを刺す合言葉をマジックパンツにしている。
マジックパンツの合図でバーンズが刺すかと思いきや逆に刃物を隠し持っていたリードに刺される、という悲しい展開になるも。
終盤でリードが調子こいて「お前は周りから言うなりだ。例えば下着のマジックパンツですら!」みたいな発言をしたらパクストンがキーでリードをブッ刺すという綺麗な伏線回収。
ここら辺の脚本は本当にうまかったと思う。
思えば冒頭で自転車を持ち上げて階段を上がっていたのも「リードの家が普通では行きにくい高い場所にある」という伏線になっていたんだな。
家に入った最初の方で窓に蝶がとまる演出があり、中盤で胡蝶の夢の話が出て、ラストに脱出したパクストンの元に蝶がくる。これは死んだバーンズの生まれ変わりなのではと思わせてエンドロールに入る回収の綺麗さ。
毒入りパイを食べ死んだ女が生き返る奇跡を見せたかったリードおじさん。しかしそれは死体隠し入れ替わりトリックだと見破られた。
にも関わらず、終盤にパクストンが刺されて大ピンチ!なところを死んだはずのバーンズが立ち上がってリードにとどめの一撃をくらわす!という「死んだ人間が生き返る」奇跡展開をわざとやる対比のうまさ。しかもとどめの釘ついた板は前半でバーンズが柱にさりげなく立てかけていたモノの伏線回収でもある。
この映画はこういった伏線回収がとても綺麗。
「これ2人がかりなら結構前半で脱出できたんじゃない?なんなら他にも逃げるチャンスは割とあったような」感もあるはあるが、それを補う脚本と演出のうまさがある。
宗教は支配だ、と終盤でマイナスな雰囲気を示しつつも、でも相手のことを想って祈るのは美しいよね、というプラスの感情も忘れない。
どっちの扉選んだところで結局出れねえじゃねえかというリードの小狡さ含め。
とにかく本作はよくできた少人数サイコサスペンスの家になっている。
面白いのもわかる。面白くないのもわかる。
鑑賞した後、タイトルにある「異端者」の意味をしばらく考えていた。ヒュー・グラント演じる悪役が「宗教的な異端者」という意味ではなく、「思想的な異端者(危険思想者)」という意味だったのかと思う。原題の「HERETIC」も異端者って意味だし。
序盤は主人公二人と宗教論争をしていたり宗教的な問いかけを続けているから、この悪役も何かの派閥に属しているのかと思いきや、突き詰めると(宗教ではなく)危険思想にのめり込んでいる人物だった。
モルモン教の事は詳しくないですが、アメリカ国内でも「変わった教義を持つマイナーな分派」くらいのイメージ。つまり、彼らの論争部分の大半は理解しきれなかった。避妊インプラントを摘出するシーンも「わからんが、たぶん婚前性交渉の否定との矛盾を指摘しているんだろうな?」と思った。多分、日本人の大半が理解できない。
ただ、そういう不明な部分はあっても観客を引っ張り込む力があるのも感じた。序盤はジリジリした違和感に始まって家の奥に進む度に違和感が恐怖に増幅していく流れは非常に良かった。この手映画だと犯人の正体が暴かれると途端に萎えるものが多いが、悪役の正体を暴いた後もしっかり仕掛けを残していた点はいい感じ。
よく喋るのに本心や思想の根幹を見事に隠している悪役、「舌戦の攻防が巧み」でありながら、(最終的には負けなければならないために)ある程度弱い、といういい塩梅が出来ていたと思う。「よく考えたらあのトリックを全部独りでやって、独りで〇〇の世話とかやってるんだよな……」と思うと中々の努力家だ。あと、主役二人を閉じ込めるための仕掛けを操作するシーン、音とスピード感が合ってて好き。
良い意味でも悪い意味でも「きちんと閉じこもっている映画」だった。例えば死んだと思われていたシスターが起き上がって悪役にトドメを刺すのも、予め「復活」というキーワードが出ていて伏線になっている。
主人公二人が外の人間に助けを求めている間は家の外のシーンもあったが、二人が外を意識せずに目の前の悪役に相対するようになるとそれも無くなる、というように観客の意識の向け方が上手かった。
個人的には良し悪しありつつの良作、という感じ。ただ、ホラーシーンがちょっと少ない気もする、もっとビックリさせるカットを入れても良かったのではなかろうか。
邪悪なカルト宗教に追い詰められた女子大学生。
キリスト教の布教活動をする二人の女子大学生。
カルト宗教と、神学論争。。。
最後に、脱出した場面で、蝶が手に止まり、飛んでいく。
いろいろな意味に取れる
良いラストシーンだった。
全93件中、41~60件目を表示