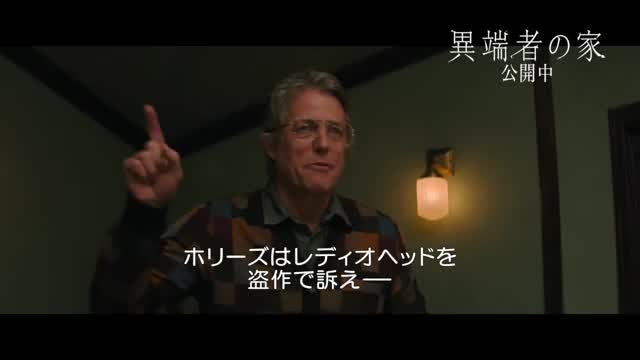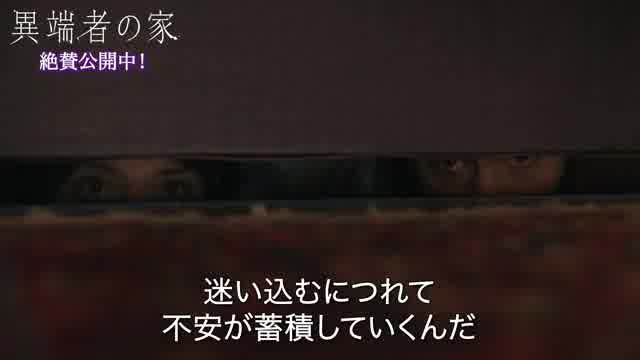異端者の家のレビュー・感想・評価
全94件中、1~20件目を表示
宗教マニアをぢ vs モルモン布教女子のアンフェアファイト
すっかり性格俳優にシフトしたヒュー・グラントを楽しめる映画。「ジェントルメン」での癖つよ探偵役を見たあたりから、もっとそっち方面を演ってほしいと思っていた私はそれだけでプラス評価。
彼のキラースマイルの威力はまだ健在で、玄関のドアを開けた時に彼が見せた微笑みには、悪役だとわかって見ているこちらの気持ちさえ一瞬油断させる力があった。話が進むにつれ、その笑顔や愛嬌ある笑い皺がリードの不気味さに似合って見えてくるところはさすがだ。
サイコスリラー映画としては、うーんどうだろう。怖い映画苦手の私でもあまり怖くなかったから、このジャンルが好きな人には物足りないかも。
(二の腕の傷をほじくるシーンだけはギエエエエとなった、怖いというより痛そうで)
前半、リードが宗教や信仰心の本質(彼の持論)についてシスターたちに滔々と語るくだりは興味深かった。(「ボブの絵画教室」バージョンモノポリーには笑ってしまった)
八百万の神の国に生まれ育った消極的無宗教の私にとっては、正直なところ物語の前半においてはリードの主張の方が、モルモン教より首肯できる部分が多かった(ただし、パンフレット掲載の寄稿によると各宗教についてのリードの説明は所々嘘を含んでいるそうなので、鵜呑みにするわけにもいかないが)。
アメリカ国民にはキリスト教信者(もちろん宗派は分かれているが)が多いというイメージがあるが、イエス・キリストの逸話への冒涜とも取れそうなリードの主張は批判を招かないのだろうか。Rotten Tomatoesでの評価は比較的高く、社会問題化するほどの反発を受けてはいないように見える。
末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教の教団)は本作を非難する声明を出しているそうだが、作品を鑑賞したモルモン教徒当事者にとって、序盤に描写された宣教師の日常は結構リアルなものだったようだ(The Guardian、2024年11月の記事より)。
本作の2人の監督、スコット・ベックとブライアン・ウッズはモルモン教徒の友人らに脚本について相談し、彼らの日常会話をもとに台詞を創造したという。
そのリアリティと、キリスト神話説的な主張をしているのがサイコパスな悪役、という設定であること、そして最後には「誰かのために祈ることは素晴らしい」と信仰を肯定するパクストンがリードを倒す展開。これらがあるから、前半のキリストに対する冒涜的なリードの主張も、キリスト教徒から見れば「迫害者の間違った考えの描写」として消化されているのかもしれない。
前半のマンスプレイニング的宗教論破がそのまま続くのもまた一興だが、それではスリラーというよりめんどくさいおじさんの話だ。ここからどうサイコスリラーに持っていくのか、と思っていたら、後半での怖がらせ方自体は結構ありきたりな感じでちょっと気分が盛り下がった。暗い地下、唐突に出現する貞子みたいな女。ジャンプスケアと流血。
宗教マニアを極めた結果無神論者になったのかと思いきや、宗教の本質は支配であるという結論に至りそれを実践したリード。結局、支配行為という邪教の信者になったということか。
悪役の背景をどこまで描くべきかは作風や好みによって分かれるだろうが、リードについては個人的には、あのような考えに至った理由や彼のヒストリーが見えた方が面白くなりそうな気がした。パクストンが地下でいくつかの部屋を通った時、そこに雑然と置いてあった色々なグッズにヒントがあるのかなと思ったが残念ながら分からず。キリスト教圏の人が見たらピンとくるのだろうか。
「胡蝶の夢」の話をどう効かせたいのかよく分からなかった。脱出後のパクストンの手に蝶がとまった時、まさか夢オチなのか?という安直な不安がよぎったが、さすがにそれはなかった(笑)。
ところで、合言葉として出てきた「魔法の下着」だが、モルモン教に入信した人が一生身に着ける、上は半袖アンダーシャツ下は膝丈ステテコみたいな衣服のことだそうだ。神との聖約の象徴であり、下着の上から着る服で完全に覆わないといけないので、自然と露出の少ない服装になるという。その名称を合言葉として使うのは、魔除け的なニュアンスがあったのかもしれない。
頭脳を刺激する宗教談義スリラー
思っていた以上に本気の宗教談義が続く。たまたま中学生のときにモルモン教の経典を読んだことがあり、そのときに抱いた疑問を思い出したりして、ついヒュー・グラント側に肩入れしそうになるのだが、いやいやコイツも大概というか絶対アウトな人でしょう!と思いなおしたりして情緒的に忙しいのも、結果的に地味シブジェットコースタームービーとして機能してくれて得をした気分。
ヒュー・グラントの怪演が話題になるのは当然として、対する小娘ふたりに一筋縄ではいかない顔をもたらしたソフィー・サッチャーとクロエ・イーストも素晴らしかった。日本はわりと信仰心と縁の薄いお国柄だと思うが、他人の信仰心を無碍にするわけにもいかないので、役に立つ知的な遊びという面でも楽しめる。とはいえヒュー・グラントの言うことをまんま鵜呑みにするとたやすく陰謀論者の落とし穴に落ちるんでしょうけども。
その異端はペテン。別の異端は奇跡を起こす…
よく町中なんかで宗教の勧誘に声を掛けられると、ウザッ!…と思う。私はあまり宗教が好きじゃない。母の死にも関連するので。
だからこうして若いシスター2人の視点から描くと、大変やな…とも思う。
布教活動で町を回るシスター・バーンズとシスター・パクストン。
何人か勧誘した事あるシスター・バーンズはポジティブな性格だが、勧誘ゼロのシスター・パクストンはネガティブ。話を聞いてくれる人はほとんどおらず、心無い悪戯も…。
そんな時、森の中の一軒家でもいいから話を聞いてくれる人に会うと、救われた思いになる。主のお導き!
応対してくれた中年男性リードはあの“ロマコメ王子”。にこやか朗らか気さくな性格で、そりゃ警戒心も薄れる。
宗教にも関心ありで話をしていると、突然雨が降ってくる。リードは家の中へ招く。
これにはさすがに警戒。中年男性の家に若い女性が2人…。規則で同伴の女性が居ないと家の中に入れない事になっている。
奧でパイを焼いてる妻ならいる。その言葉をすっかり信じ、2人は家の中へ。
ネズミやカエルが天敵のいるカゴの中に入ったようなもの…。
妻特製のパイが焼き上がるのを待ちながら、温かいティーを飲んでくつろぎ、話の続きを。
リードは頭が良さそうなのは話していて分かる。お喋り上手で話に引き込まれる。
話が弾んでいたが、ある質問から雲行きが怪しくなってくる。一夫多妻制についてどう思うか、キリスト教会設立者ジョセフ・スミスについてどう思うか…?
リードは宗教を否定するような事を…。それでも2人は対応していたが…。
父を亡くした経験のあるシスター・バーンズ。ちょっと無礼な話をしてしまった事から居心地が悪くなる。
パイがまだ焼き上がらない。奥さんも一向に姿を現さない。
様子を見てくる…と、奧に引っ込むリード。その隙に、帰るか否か迷う2人。
帰る事に決まったが…、玄関ドアが開かない。と言うかドアノブが無く、開けられない。
スマホを掛けるが、電波が入らない。
閉じ込められた…?
警戒心はとっくに通り越し、恐怖。
その時、奧へ続くドアが静かに開く。誘うように。
恐る恐る奧へ入っていく。そこで待ち受けていたのは、恐怖と試練であった…。
リードはどうやら豹変して性的に襲い掛かったり、殺そうという気はないようだ。
寧ろ、それが怖い。一体、何が目的なのか…?
2人は現状の事や帰らせて欲しい事を懇願する。すると、
家に招き入れた時、家のあちこちに金属が埋め込まれてあり、スマホは使えない事を暗示したのに、何故教会から連絡が…と嘘を付く?
妻がいると何故易々と信じた?
リードの言い分はサイコな男のキチ○イな言動というより、頭のいい男が若い迷える子羊を翻弄しているようだ。
リードだけが楽しいトークは尚も続く。独自の宗教論を展開。
どの宗教も真実とは思えない。世界三大宗教を例に出す。
原点はユダヤ教。これをリメイクしたのがキリスト教。ニューバージョンがイスラム教。いずれも信仰対象や物語など似通っている。
これをモノポリーに例える。元々は名もなき女性が発案したボードゲーム。それを基にアメリカが“盗作”したのがモノポリー。以後、類似品が氾濫。
誰も元祖や原点を知らない。世の全てが反復。それの何処に真実がある?
これを私なりに映画に置き換えると…、第1作目の『ゴジラ』がある。ハリウッド版がある。近年の『−1.0』がある。TV放送や最近の人が見るのはハリウッド版や『−1.0』ばかり。原点をきちんと見た事あるのか…?
あくまでリードの持論だが、何だか説得力あり。ついつい話に引き込まれた。
しかし、シスター・バーンズは反論。各宗教宗派それぞれの主の姿、教え、歴史がある。決して反復なんかじゃない!
この意見にも同感。初代もハリウッド版も『−1.0』もそれぞれの面白さと魅力がある。
2人はモルモン教。現在正式には“末日聖徒イエス・キリスト教会”。ジョセフ・スミスが設立したキリスト教の新派で、異端の一つ。最大の特異は主流キリスト教の三位一体(父・子・聖霊)否定。それぞれ別個であるとの考え。禁止されているものも多く、カフェイン、アルコール、煙草。婚前の性交渉も。厳しいが、教徒は幸せを感じている者も多いという。
リードからすれば亜流の亜流の異端かもしれないが、それでも2人は信じている。
それを試されているのか…?
前半は見る者の価値観を揺さぶる会話劇がメインだが、後半は動きがある。
帰らせて欲しいと頼む2人。が、玄関ドアはタイマーでロックされ開かない。帰るなら、強制も、引き留めようと無理強いもしない。ご自由に。
しかし、裏口から。2つの扉のどちらかを。“信仰”と“不信仰”。
一体この男は何を示そうとしているのか…?
2人が選んだのは“信仰”の扉。
地下へと降りる。
行き止まり、地の底のような密室空間。唯一の出入り口は下ってきた扉だが、言うまでもなくリードが見張り、鍵を掛けられた。
不穏な会話劇から息詰まる密室スリラー。ここでも変化球。
2人だけかと思いきや、浮浪者のような老婆が。
老婆は置かれたパイを食べる。その直後、息絶える。毒入りのパイ。
リードの声が響く。2人に息絶えた事を確認させる。
リードが驚くべき事を。もし、この老婆が“復活”したら…? その“奇跡”を信じるか…?
モルモン教もキリストの復活を信じている。しかし、リードが言う“復活”や“奇跡”はキリストのそれではなく、我が手によるもの。
そんな事はあり得ないと思っていたが、老婆は復活。恐れおののく2人。
リードの信仰や宗教は、絶対的な“支配”。
“支配者の家”で絶対的な支配の下、2人は成す術もないのか…?
が、遂に突破口を見出だす。2人揃って無事の脱出を試みるが…。
これまでにも『パディントン2』や『ダンジョンズ&ドラゴンズ』で悪役を演じた事はあるが、いずれもユーモラスだった。
これほどの恐ろしさ、不気味さは初めて。
ラブストーリーやコメディが多いが、実際は実力巧者。
ヒュー・グラント、圧巻の新境地!
対する若手2人、ソフィー・サッチャーとクロエ・イーストも負けていない。
監督のスコット・ベックとブライアン・ウッズは『クワイエット・プレイス』の脚本コンビ。監督作は『ホーンテッド 世界一怖いお化け屋敷』『65/シックスティ・ファイブ』などB級作品が続いていたが、急にどうした?!…ってくらいレベルアップ。
確かに独自論や哲学的な会話、特に日本人には宗教観は小難しい。が、不穏なサスペンス、リードのキャラに不気味さと共にユーモア孕み、ホラーとしても震え上がらせる。
突然の来訪者。2人を心配する牧師が訪ねてきたようだ。
が、地下から声は届かない。存在を気付かせようとするが、その時復活した老婆が2人に迫る。
襲い掛かるのかと思いきや、意味深な言葉を…。
2人はリードが地下に下りてきた時、合言葉を決めて殺してでも逃げようとする。シスター・バーンズはシスター・パクストンにナイフを託す。
リードが下りてきた。合言葉を発した時、凶刃が首を。首を切られたのはリードではなく、リードが隠し持っていたナイフでシスター・バーンズが…。
パートナーが殺され、絶体絶命の状況。どちらかと言うと弱い心のシスター・パクストン一人になり、このまま絶望するかと思ったが、それが彼女を奮い立たせた。
老婆復活のからくりを見破る。牧師が来て2人が扉に張り付いていた時、身を潜めていた別の老婆と入れ替わっただけ。シスター・パクストンはちょっとした違和感を感じていた。
違和感はリードにも。一見完璧に支配しているように思えるが、その端々で綻び。内心、リードは焦っている。
リードはシスター・バーンズの腕を切り、金属片を取り出す。それはマイクロチップで世の陰謀をまた得意気に話すが、それはただの避妊器具。
イカれた陰謀論まで抜かす始末。復活もただのトリック。何て事はない。
真実を見つけ、勇気を出したシスター・パクストンにとって、リードは支配者ではなかった。異端は異端でも、ペテンであった。異端者ならぬ“ペテン師の家”。
代わりの老婆が出てきたハッチを見つけ、そこを抜ける。先はまた別室で、多くの女性が囚われていた。老婆はこの事を示していた。
ペテン師で、もう完全なる異常者で犯罪者。
遂にリードはシスター・パクストンに襲い掛かる。
そこで奇跡を見た。リードを食い止め、息の根を止めたのは、殺されたと思われたシスター・バーンズであった…。
ご都合主義を感じるかもしれない。
実は瀕死の重傷を負っただけで死んではおらず、最後の力を振り絞って…。実際、シスター・バーンズは…。
敬虔な布教活動が、最悪の結末に…。
友を失い、一人になってしまったシスター・パクストン。
だが彼女は、教えや書ではない奇跡や復活をその目で見たのだ。誰かを助ける為に。
奇跡がもう一つ。
シスター・パクストンは自分が死んだら蝶になって、愛した人の手に止まりたい。
ラストシーン。シスター・パクストンの手に蝶が止まる。
友愛という奇跡を見た。
信仰を“操作”することの恐怖
宗教ホラーの皮を被りながら、実は“信仰とは何か”を問う知的スリラー。モルモン教の若いシスター2人が、森の奥の屋敷を訪ねる。信仰の言葉を携え、真理を語るはずが、待っていたのは理屈と論理で信仰を分解してくる男、リード。彼の家は、信仰の構造そのものを模した迷宮であり、彼女たちは信仰そのものを“試される”側に転じていく。
この作品の主題は、“信仰を支配する者”と“信仰に支配される者”の入れ替わりだ。リードは宗教を否定しながら、その仕組みを精緻に理解している。だからこそ、信者を「試す」ことで信仰の脆さを暴く。彼にとって信仰は救いではなく、支配の装置であり、他者の自由意思を奪うための構造。
この知的暴力こそが、映画の根幹にある恐怖だ。
――信仰を操作する者は、神を装うことができる。
物語の中盤、シスターの右腕に一瞬だけ映る手術痕。説明は一切ない。私は何かの怪我かと思い、そのまま見過ごした。ところが後で調べて驚いた――あれは「避妊インプラント」の痕だったのだ。知らんがな、そんなもん。宗教ホラーを観に行って避妊医療の知識を試されるとは思わなかった。だが、それこそがこの映画の巧妙な罠だった。
モルモン教では避妊は神の意志に反するとされる。つまり、その痕跡があるということは、彼女が信仰の枠を越えて“自らの身体を自分の意志で選んだ”証。リードが見抜いたその傷は、信仰的には“異端”だが、人間的には“自由”の痕でもある。
この一瞬の映像が、宗教的純潔の崩壊と、自律への目覚めを同時に描いていた。
監督のスコット・ベックとブライアン・ウッズは、『クワイエット・プレイス』でも顕著だった“説明の削除”をさらに徹底した。セリフを削ぎ、沈黙と痕跡で語る。確かに美学としては成立している。だが、本作では観客を置き去りにしている側面もある。説明の欠如が宗教の不透明性と重なり、「理解できないことこそが信仰である」とでも言いたげだ。だが、それは映画としての誠実さと紙一重だ。観客が気づかない伏線を「理解の遅れ」として処理する態度には、わずかな傲慢さすら感じる。
それでも、ヒュー・グラントの演技は圧巻。温厚な笑みの裏で他者を心理的に解体していく知的サディズム。彼の言葉は宗教を否定するようでいて、実際には“信仰を再設計して支配する者”の言葉。信仰とは、人を救う装置であると同時に、人を縛るプログラムでもある。リードの屋敷はそのシステムの縮図だ。見えない境界、強制的な選択、そして「自由」を装う支配。観客もまた、彼の信仰装置の中に閉じ込められている。
終盤、シスター・パクストンが雪原で手を差し出すと、蝶がとまる。かつて彼女が語った「死んだら蝶になって戻りたい」という言葉の再現だ。現実か幻覚かは分からない。だが、その曖昧さこそが信仰の本質を映す。信仰とは、証拠を求めれば失われ、疑えば崩れる不確かなもの。それでも私たちは、何かを信じることでしか生きられない。だからこそ、誰かがその“信じる力”を利用すること――それこそが最大の恐怖である。
本作は信仰の名を借りて人間の自由意志を奪うメカニズムを冷静に解剖する作品であると理解した。信仰を操作することの恐怖とは、すなわち「信じたい」と願う心を誰かが支配すること。そして、その誰かはいつだって、神ではなく人間である。
神がいなければすべてが許される
コンビクリエーター、スコットベック&ブライアンウッズの、Heretic以前のもっとも大きな成果はクワイエットプレイスのライターだった。監督業では好評を得たHaunt(2019)があるが、アダムドライバーの華々しい映画出演歴に泥を塗る怪作65(2023)も彼らが書いて演出した。
そんな来歴を見る限りこのコンビクリエイターがHereticをつくったのは意外だった。意外と同時に、映画クオリティについての考え方が調節された。
映画のクオリティは監督の力量や才能によるが、動機やアイデアもクオリティに作用することがhereticを見て解った。
それを解っていなかったわけではないが才能という礎石に動機やアイデアを載せることで映画クオリティが形成されることを、65からHereticへの変化があらわしている気がした。
成熟した映画製作環境があり、そこに集うクリエーターの技量or能力が横並びのような状況ではむしろ動機やアイデアこそが傑出の条件になる。当たり前のことでもある。
かえりみればアリアスターもジョーダンピールもダニー&マイケルフィリッポウも、タイウェストやロバートエガースやマットベティネッリオルピンやデヴィッドロバートミッチェルも斬新なホラーアイデアによって頭角を露わしたわけである。
業界も観衆も黒澤明やキューブリックやタルコフスキーのような天才の出現を待っているわけではなく、新しいアイデアの顕現を待っているのだ。
映画を見慣れている方ならご同意いただけると思うが、映画を見始めて10分ぐらいは、たいていその映画世界にじぶんの感性を慣らしている時間帯であろうかと思う。
ゲームならチュートリアル、仕事ならオリエンテーション、まだ面白いのか面白くないのかが解らず、楽しむためにじぶんを映画側の歩調に合わせている時宜がある。
一方で、最初からスッと引き込まれてしまう映画もある。Hereticは冒頭のマグナムコンドームの会話からスッと引き込まれ終いまで夢中になった。
見終えて、これがあの65と同じスコットベック&ブライアンウッズ監督だと知り、映画クオリティの考え方の調節を余儀なくされた。65は退屈で見ていられなかったからだ。65からHereticに至る1年のあいだにスコットベック&ブライアンウッズ監督の映画製作能力が向上したのか?そうでないなら何が違うのか。動機とアイデアが違う、という結論になった。
Hereticの動機となったのはブライアンウッズの父親が食道がんにより死去したことだという。そこから死後の世界に関する疑問がストーリーを形成していった。
伝道者のキャラクターを可能な限り本物らしくステレオタイプにならないようにするため、様々なモルモン教徒から取材し、且つ元モルモン教徒である女優二人(Sophie ThatcherとChloe East)を主演に据えた。
宗教を真剣に扱いながら、あくまでエンタメの文脈で書き、大まかなアイデアは風と共に去りぬ(1960)とコンタクト(1997)から得たという。
いったい誰がHereticを見て風と共に去りぬやコンタクトを思い浮かべるだろう?すなわちHereticは身内の死という強い動機から突飛なアイデアを経由し元モルモン教徒を揃えてつくられた。だからクオリティが上がったわけである。
Hereticの核心、リード氏(ヒューグラント)の主張は、宗教とはユダヤ教が時代や地域によって形を変えながら存在しているに過ぎないという観点から、すべてが焼き回しのような事象で世界が構成されていることへの嘲笑である。ボードゲームのモノポリーも楽曲のCreepも焼き回しで、もしモノポリーの発案者が権利を主張すれば、あるいはThe HolliesがRadioheadを訴えれば、類似品は存在できない。ユダヤ教が類似を許さなければ宗教は生まれない。であるなら他者を支配することが宗教をも超えたすべての欲望の根源だという理屈である。モルモン教分派の一夫多妻を実現し女たちを支配監禁するうちに邪曲、変節していったと思われる。
理屈はともかくとして、映画Hereticを貫く緊張は、監禁状態に陥った二人の女性の凄まじいまでのストレスが怒濤のようにこっちへ伝播してくることに他ならない。初見では常人気配のあるリード氏が妻がパイをごちそうすると言うので入って会話するあいだに、違和感が不安に変わり、不安が怪しさに変わり、怪しさが確信に変わり、確信が恐怖に変わり、恐怖が逃走や闘争の本能を目覚めさせる、その過程がマジ険悪で、グラントはノッティングヒルと同一人物とは思えないほど怖かった。
死の淵から最後の力を振り絞ってリード氏を倒したシスターバーンズ(Sophie Thatcher)を預言者と見なし、結局シスターパクストン(Chloe East)が論理的にも肉体的にもリード氏を凌駕して、幻影に蝶を見るところで映画は幕を閉じる。
モルモン信徒は、アルコール煙草コーヒーお茶薬物が禁じられ、婚外性交渉もポルノも自慰も避妊も禁忌とされている。すなわち映画Hereticは、ダサい聖徒の神殿下着を履き、一般社会から嘲弄されるような世間知らずの新米モルモン信徒が、勇気と知恵をもって異端者に抗い、最終的にそれを凌駕する様を描いた映画、と言える。
隠喩や小道具や仕掛けも多くとうてい恐竜とアダムドライバーが追いかけっこする映画をつくった監督と同じ監督がつくった映画とは思えない。
雰囲気はアスターのHereditary(2018)、ストレスはLenny Abrahamson監督のRoom(2015)、宗教的筋書きを差し引いても、Hotel Coolgardie(2016)のように男が女に与えるハラスメントの恐怖の本質を描いていると思う。
imdb7.0、RottenTomatoes91%と76%。
私的好みではない表現でしたが、一方で見事に深さある秀作だと思われました
(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
結論から言うと、今作の映画『異端者の家』を、正直に言うと表現されている内容は好みではなかったのですが、一方で見事に深さある秀作になっていると思われ、大変面白く観ました。
個人的な関心に引き寄せると、今作は、「奇跡」と「信仰」について描かれた映画だと思われました。
すると、ではその「奇跡」と「信仰」とは何なのか?との設問が現れると思われます。
先回りして個人的な答えを示すとすれば、哺乳類である人間は生まれた後に親などの庇護や養育が必要になるのですが、「奇跡」とは、生まれ落ちた赤ん坊が親などの取り上げや庇護や養育によって生き延びることが出来た、その事に当たると思われます。
そして「信仰」とは、赤ん坊が生き延びる事が出来た「奇跡」を生み出した、親などの周りとの関係性をしっかりと感受して抱きしめる、実感のようなものとして信じる事に当たると、個人的には思われます。
すると、この映画の異端者の家の主人である、ミスター・リード(ヒュー・グラントさん)は、自身が生まれ落ちて生き延びることが出来た、親などとの周りの庇護や養育の記憶が、体感されずに破壊されている(「奇跡」も「信仰」も破壊されている)人物として存在していると解釈されると思われます。
ミスター・リードは、自身の異端者の家の家にやって来たモルモン教の宣教師のシスター・バーンズ(ソフィー・サッチャーさん)とシスター・パクストン(クロエ・イースト)を家に閉じ込め、2人に宗教問答を仕掛けます。
しかしミスター・リードの話は、理屈が通っている部分はあるかもしれませんが、観客である私達を含めて、大半の人間に、彼の理屈は根本的におかしい間違っている、と感じさせます。
なぜなら、ミスター・リードは、自身が生まれた後に親や周りから受けた庇護や養育によって生き延びたという実感の「奇跡」も「信仰」も根源的に破壊されているので、他者に対する信頼の根源である思いやりや共感と言った、心が破壊されていると伝わるからです。
他者との信頼の基盤である思いやりや共感と言った心が破壊されている人物の理屈は、信頼の基盤が壊れている為に、どこまで行っても本当の意味で正しいと他者に伝わる事は不可能なのです。
そしてミスター・リードは、生まれ落ちた後の周りとの関係性における「奇跡」も「信仰」も破壊されているので、心が基盤から溶解して、他者との区別を失くしていると感じさせます。
それが、モノポリーを例に使った、各宗教の違いを溶解させ、一体化させようとする論理の披露になります。
この全ての差異を溶解させようとするミスター・リードの理屈に、毅然と反論するのがシスター・バーンズです。
シスター・バーンズは、それぞれの宗教の違いを具体的に述べ、ミスター・リードの全ての差異を溶解させ一体化させようとする理屈が、間違いであることを示します。
これは、シスター・バーンズが、生まれ落ちた後の周りとの関係性における「奇跡」や「信仰」をしっかりと体感しているからこそ、他者との関係性の基盤の強さから、他者と自身や様々な差異を、しっかりと認識出来ているから成し得た主張だと思われました。
多くの観客も、シスター・バーンズの「奇跡」や「信仰」に裏打ちされた毅然とした態度に、静かな勇気づけをもらったのではと推察します。
ただ、この映画が凄いのは、この毅然とした魅力あるシスター・バーンズが、首をミスター・リードに切られて、命を落とすところにあると思われました。
そして、最後に異端者の家から脱出し、生き残ったのは、ポルノビデオにも興味を示す、「信仰」の意味から言うと中途半端にも思えたシスター・パクストンの方だったのです。
この中途半端にも思えたシスター・パクストンが生き残った意味は、以下だと解釈されると思われます。
実は、ミスター・リードの「信仰」の破壊(「不信仰」)も、シスター・バーンズの「信仰」の強さも、どちらも多くの私達はグラデーションの中で持っていると思われるのです。
なので、私達は、ミスター・リードの「信仰」の破壊(「不信仰」)も失笑して退けることも出来なければ、シスター・バーンズの「信仰」の強さにも惹かれ重要だと思われています。
そして、シスター・バーンズが首を切られて命を落としたように、「信仰」の強さが、特に現在では、破壊された「信仰」(「不信仰」)を救うことは出来ない、というのも真理として伝わるのです。
私達は現在、「信仰」と「不信仰」とに(あるいは、生まれ落ちた後の親や周りからの庇護や養育を、実感として持っている人物や思想と、破壊されている人物や思想とに)、分断されている時代に生きていると思われます。
そして多くの私達は「信仰」と「不信仰」との間のグラデーションの中の中途半端な人物として生きていると思われるのです。
その意味で、中途半端にも思えたシスター・パクストンが最後に生き残った事は、双方が両極端で分かり合えない分断の現在の中で生き延びなければならない、双方のグラデーションの中にいる多くの中途半端な私達への、勇気づけの表現になっていると思われました。
今作の映画『異端者の家』を、以上の点から深い秀作に思われ、ただ一方でスリラー的な描写は好みではない点もあって、僭越、今回の点数となりました。
先が見えない面白さ
あらすじ
地域の子供にもバカにされるモルモン教。宣教を担当するシスター二人は、パンフレットを請求した人物を訪ねるよう教会から指示を受ける。
訪問するとそこは郊外の一軒家。住人の中年男性は二人を家の中へと招き入れるのだった。
前提として「ヒュー・グラントが悪役のホラー」という情報だけ入れて鑑賞に臨んだ。
ところが、冒頭のA24のロゴで嫌な予感。また「一体何を見せられてるんだ」的な作品なのかと。(アリ・アスター関係映画に懲りた)
しかし、見進めていくと、物語展開が見えない序盤、トラブルに巻き込まれていく中盤は惹き込まれる感覚に久々にゾクゾクした。実に面白い。
ホラーの文脈・お約束は守られ、伏線らしきものもしっかり提示。
実に王道なホラーに仕上がっているため、ストーリーに集中でき安心して鑑賞できた。
音によるびっくり演出はほとんどないものの、後半・終盤でグロ演出はあるので、耐性ない方はご注意を。
宗教の成り立ち、モルモン教とは、スパイダーマン(1作目orアメスパ)、スターウォーズEP1などの
知識があるとより楽しめると思う。(劇中で説明されるので無くても大丈夫。)
以下ネタバレ
第一印象としては、「これユタ州で流せるんかいな?」というもの。
そのくらいモルモン教をディスりまくっている。(案の定猛抗議があったそう。)
でも、よく見ていくと、特定の宗教をディスっているのでは無く、「大体の宗教は模倣である」っていうのが
ヒュー・グラントの表向きの主張なので、日本の某巨大新興宗教も当てはまるなあ、と思って見ていた。
ヒューグラントはノリノリで悪役を演じている。決して暴力的では無く(序盤・中盤)、
理路整然(かなり自分勝手な解釈を下敷きにしてるが)と主人公達を追い詰めていくところがまた一段と恐怖を生む仕掛けになっていた。
先へ先へと変化していくトリッキーな屋敷の作りも良い。
途中で主役が交代するのも、予想していた展開が裏切られた感じでよかった。
黒髪の比較的世慣れした主人公だと、単純に力で反抗して脱出だと思っていたが、物語の「先が読めない感」が加速した。
最後は奇跡をひとつまみ、という演出も憎らしいがストーリーにスパイスを効かせていて合っていると思った。
屋敷からの脱出も、何故か出れた!ではなくちゃんと理由づけしているところも良かった。
ただ、終盤にかけてのヒュー・グラントの目的の陳腐さの開示や普通の暴力に訴えるホラーに成り下がったのは非常に残念だった。
信仰心と呼ばれるものとは
信仰心と言うものは、我々日本人には少し馴染みがないかも知れない。
それ故にこの映画の本当の恐怖や不快感は想像でしかわからない。
それでも、その「信仰心」を「大切な誰か」や「譲れない信念」に置き換えるとわかりやすい。
冒頭の会話シーンから二人のシスターの立ち位置や性格がわかりやすく、すんなり頭に入ってくるのが良い。
冷静で判断能力に長け、頭の回転も早く知識豊富なシスター・バーンズと、どこか俗世への憧れのようなものを捨てきれず、年齢よりも幼さを感じさせるシスター・パクストン。
この二人との何気ない会話から「より自分が操りやすい方」を最初から選んでいたミスター・リードの異常性と知能の高さにはゾッとさせられた。
ミスター・リードの語る「宗教」のそれは、まるで大学の講義のような説得力があった。
特に「宗教のファストフード」のくだりはとても興味深いとすら思えた。
言葉だけではなく、時に視覚や聴覚からも強いストレスを与え、更に絶望的な状況へと追い込んで行く。
特に地下室に降りてからの密室での恐怖と悪夢のような奇跡を見せつけられる展開には「自分ならどうするのだろう」と言う考えが止まらなかった。
あの状況で自我を保っていられたのは「二人だったから」ではないか。
それと同時に「二人でなくなったから」こそ強くなったシスター・パクストンの覚醒は痺れる展開だった。
「支配」と言うひどく身勝手なそれは、宗教における「信仰」とも似てるとも言える。
では何がそれをわけるのであろうか。
自分自身で選択し、進んだと思っていた道が全て誰かの思い通りだったなら?
自分の信念と思っていたものが全て誰かのシナリオだとしたら?
今ここに立っている事すら自分ではなく、誰かの意思だとしたら?
そんな身勝手でただの屁理屈でしかないミスター・リードの言い分を、跳ね除ける勇気も打ち勝つ強さも持てず、ただ受け入れる事でしか生きる事の出来なかった人々の成れの果てが「彼女達」だったのだろう。
綺麗事のようにまとめられた美しいラストシーンは、あれこそ奇跡とも言えるのかも知れない。
二人のシスターの信仰心が起こした、本当の奇跡。
神などいないのかも知れない。
それでも、自分が信仰するものは自分自身で選んでいいのだ。
祈りは、誰の為でも美しいのだから。
信仰とは?という異常なまでの問いかけ
(※以下、宗教、信仰について自分の感想を書いていますが、あくまで個人的な思いなのであしからず!)
面白かった!
予告を観て、ヤバいおじさんによる女性の監禁、そして家に隠された危険な仕掛けの数々、この家から脱出することはできるのか?といったアクションスリラーを想像していたのですが、公開後に宗教に関する話が主題だという口コミを読んで「なるほどそっち系か」と想像を改めていました。
しかし、今回本編を観て、宗教・信仰というテーマ性のあまりの濃度とグロさ・怖さが想像以上で驚いた!
そのサプライズがとても興味深く、自分は楽しむことが出来た。
自分だったらあの地下への階段降りれないかもしれないなぁ。
朝扉があくまで待ちます、ここで話しましょうとか言うかも。
あそこを降りる覚悟はないな。
預言者には心底ビビりました。
私は特定の宗教を信仰していないので、この映画の主軸である「信仰とは何なのか?」「絶対の宗教とは何か」「何が真実なのか?」といった部分への理解度は十分と言えない。
理解しきれないところがとても残念で、ここの知識や接してきた経験があるともっとこの作品の核を味わえたのだろうと思う。
ただそれでも、映画を観終わったとき、「現代の宗教という“システム”はあまりにも不完全で支配的、ただし信仰は極個人的なものであり、きっかけや始まり、目的が何であれそれは誰にも否定できないものなんじゃないか」という自分なりの解釈をした。
自分で考えたのか?自分で本当に選んだのか?そこにもしかしたら不正解はあるのかもしれないけど、正されるべきは都合良く人々を搾取する宗教という器で、信仰はただそこにあることが全て、間違いも正解もないというか。
だから、そういう意味で言えばあの男の個人的な信仰も誰にも否定できるものではないのではないか。彼こそ信仰というものを突き詰めた結果、あの形をとるまでに狂ってしまったのかなとか。
最期、祈るシスターに息も絶え絶えに近づいたとき、彼女を殺そうとしていた行動ではあるんだけれどもどこかすがるような、祈りの力を信じたいような、そんな姿にも見えて、彼がここまでくる過程に何があったのか、何を知ったのか、何に絶望したのか想像をめぐらせたりした。
ふたりのシスターを探しに来た教会の男がついでに冊子を渡そうとしたとき、何とも皮肉を感じて、その時のヒュー・グラントの表情も含め印象に残ったワンシーンだった。
また、宗教をモノポリーで例えるところも好き。深い歴史と精神世界をもつ宗教のはずが、商業的なひとつのゲームで例えられる。「なんなんだろうな、この世界も人間も」と思ってしまった。
ヒュー・グラントがこういう役をやってくれることが嬉しいし、これからも色んな姿を見せてほしい。
少し頼りなく世間知らずだったシスターが最初と最後では別人のように変わったことも、彼女の表情、演技ともに素晴らしかった。
映画を観終わった後にちょうどネットニュースで「新教皇が“家族は男と女の結びつきに基づいている”と宣言した。」という記事を読んで、そこについた様々なコメントを読み、またこの映画について考え込んだりなどした。
その宣言の内容がどうこうという話ではなく、神への信仰とまでいかずとも、何を信じてどう行動するのか、常々自分で決めることが大切なのだろうなと。
話は簡潔にお願いします
職場でさも重要なことですという顔をしながら全く中身のない話をする人がいた。不思議なことに堂々とした態度もあってその人の話をみんな聞いてしまう。やけど最後まで聞いても中身がなく、5分で終わる話を20分もかけてはて?何を聞かされてたんや…と内心腹立たしくなる。特に私のようなせっかち人間は🤨
この映画のヒューグラントがまさにそれ。意味があるようでない。聞いたところで解決のヒントにもならない。やけど、追い込まれた極限の状況では冷静にはなかなか判断できない。自分と考えが違うからといってなぜあそこまで過激な行動に出るのか?そしてたまたまあの家を訪れた2人を監禁する。あの2人にそれをしたところで何の意味があるのか。?がたくさんやった。そして痛々しいシーンが多く終始眉間に皺を寄せて観ていた。
ヒューグラントはいいひと役のイメージが強いけれどこういう悪役もやるんやなあ。新鮮やった。最後の蝶は夢か現実か…
信仰と脱出
宗教勧誘に来たシスターが議論好き
サイコパスおじさんの家に閉じ込められ
追い込まれていく。
紳士的なヒューグラントの笑顔が怖い。
信仰心をぶちのめしにかかり、理詰めで
攻める。怪しい家には必ず地下室が存在する。
あの階段降りるだけで死を予測してしまう。
宗教者を嫌らしく追い詰める良質な
サスペンス。大切な人の為に祈る事は
美しくもあるなぁとも思った。
サイコスリラーは前半だけ
前半はセリフに引き込まれてなかなか面白いが、後半急にゾンビ映画風でつまらなくなる。捜索に来た男性信者が活躍すると期待させるわりには、何の役割も果たさないし。色々もったいない。
タイトルなし(ネタバレ)
猟奇ホラー系好きなのだが、私の好み的には少し微妙。
色々理屈捏ねているが、結局女性にマンスプレーニングかまして支配したいキモおじな感じが嫌。(突き詰めると性癖っぽい感じとしか思えない感じがする)
宗教、信仰に対する思考実験みたいな雰囲気やミニチュアハウスに閉じ込められてる映像演出などは面白いけど、革新的な感じはない。
個人的にはハウスジャックビルトの様な、全然共感できないが
こいつの体内にはこいつの神話や哲学があってこいつなりの倫理があるが、社会的倫理とまったく噛み合ってないから社会悪とゆう猟奇犯とかの方が好み。
この作品は、それっぽい感じの結局キモいおっさんなのが不快感強めに感じた。
アメリカなのに
アメリカなのにって感じ。
日本なら無宗教的な感じは受け入れられやすいのだけど、これをアメリカで映像化するあたり良い意味でアメリカの自由さを感じさせてくれた。
このホラー、驚かせる的な怖さも少しはあるが宗教的な要素を色濃くしその言葉により相手を論破することで得られる優越感を楽しむ奇人要素をホラーに転換した部分は見応えがあった。
ただ2人対1人(初老)の構図であれば、もう少し直接的な対決部分を絡めて描いた方が、より怖さも増すのではないかと思われた。
また自分にこの物語のキモとなる宗教的な知識が足りない点は評価を下げてるかもしれません。
宗教についての議論会
神学家のおじさんがモルモン教徒の2人に説教する話
支配が唯一無二の宗教であると気付いたおじさんが支配を教えようとするが復活の奇跡により釘板で殴られるEND
部屋脱出デスゲームかと思ったら、宗教問答映画だった。宗教に明るくないためか、人物の背景が薄く感じて、そこまでしてやることなのかなぁと疑問に思った。
ヒュー・グラントが怪演
コロナ禍前までは、たまに土日に宗教の布教活動の来訪者がありましたが、コロナ禍を境に無くなりました。私はいつも「実家が○○宗のお寺です←嘘も方便」と言っていました。すぐに帰られましたね。
モルモン教の若い2人の女性の宣教師が、郊外の一軒家に布教活動で訪れたところ監禁されてしまうというお話し。一軒家の主リード役のヒュー・グラントが、怪演でした。紳士的な振る舞いとサイコに満ちた振る舞いの落差が大きく、そこを上手く表現していたと思う。神学論戦には、若いシスターもタジタジでしたね。また当初は弱々しかったシスターパクストン(クロエ・イスト)が、段々と力強くリードと対決するようになる変化は見応えがありましたね。
余談ですが、信仰は大切かもしれませんが、あまりにも極端すぎると人が変わってしまいます。人を変えるのは、愛(←いい意味での)とお金と宗教にはまってしまうことだと思います。
支配のからくり
末日聖徒イエスキリスト教の勧誘に訪れた二人の若きシスター、バーンズとパクストンがその家で恐怖の体験をする物語。
その家の主リードは宗教に関する知識が豊富で勧誘に来た若い二人を容易く論破してしまう。初めから彼には勧誘に乗るつもりはなかった。それを感じた二人は辞去を申し入れるが玄関ドアは閉ざされ半ば監禁状態に置かれる。
家を出たいのなら裏口の扉のどちらかを選べというリード。右の扉には信仰の文字、左の扉には不信仰の文字が。あくまでも強制ではなく自分の意思で選択させる。
しかしどちらを選んでも行き着く場所は同じ地下室。そこで彼女らは死者の復活の奇跡を見せられる。
すべての既存の宗教を信じないリードはこうして訪れた女性たちに奇跡を見せては己の創造した新たな宗教を信じ込ませようとしたのか。しかし仕込みの女性の言葉をヒントにトリックだと見破られてしまう。
バーンズの避妊インプラントの傷跡にあらかじめ目をつけていたリードがそれが彼女の復活を妨げているなどというこじつけにも騙されなかったパクストンは地下の部屋を見つけて脱出を試みる。しかし出口だと思った先には女性たちを監禁する檻が並べられていた。
すべては自分の意思による選択、自分の意思による判断でたどり着いた先が出口ではなく逃れられない監禁場所と知り愕然とするパクストン。
ここまで自分はすごろくの駒のようにリードの思惑通り操られていたに過ぎなかった。自分の意思で行動しているつもりがすべて彼の支配下にあったことを知り愕然とする。
この家の構造自体がまさに洗脳のための装置だった。第一段階で奇跡を見せることで洗脳を試みる、もしそれが失敗しても誘導により監禁部屋にたどり着かせることで敗北感を味わせ屈服させることにより洗脳するという二段構えの周到な支配のからくり。
思えばそれは宗教が辿ってきた歴史でもあった。奇跡をその教典で知らしめて信じ込ませ信者を募る。教典を信じようとしない異教徒たちに対しては十字軍のように武力で圧倒する。
信じ込ませて支配するか屈服させて支配するか。リードのしていることはそのような宗教の歴史を実践してるだけであった。
今までの成功体験からリードが油断して墓穴を掘ったことに加えて死の間際、死力を振り絞ったバーンズのおかげでパクストンは脱出に成功する。
彼女の手に止まった蝶の幻は胡蝶の夢のごとくシスターバーンズが見ている夢なのか、それとも蝶がシスターパクストンの姿になって解放された夢を見ているだけなのだろうか。
直接的に映像で怖がらせるのではなく、周到に精神を支配してゆくそのマインドコントロールの過程を見せられてなかなか興味深く最後まで見れた。
暇人の家
お仕置きするためにそこまでやるなんて、暇人としか思えない。
固定電話が無いのにケータイの電波つながらない家に住むなんて暇人としか思えない。
セリフの8割が何を言っているか分からない。
ㇾディオヘッドをパクりと言いながら、今さらやりつくされた脱出系映画やるのも反復性なんでしょうね。
ただいたずらに怖がらせるだけの映画だと思った。
怖ぇ~けど面白かった!この悪魔に神の一撃を下す!
やっぱ洋画はこうでなくっちゃ(*´ω`*)
最近洋画見る機会がめっきり減って、たまに封切来たと思ったら
MCUとかコミカルアクション系。はたまた歌ってるとか、ミュ-ジカル系。
なんか昔はバランス良く 恋愛物とか裁判物とかヒュ-マンドラマ、サスペンスとか、そしてカルト系が順番に巡っていたのだがな。
昨今アメリカではサスペンス・ホラ-系がブームな様で。
配信作の煽りで劇場はお化け屋敷状態にしないと客が来ないのか何とも情けない景況ですわ。
そんな中 チョイ遅れたけど今日は「異端者の家」見たんよね。
この作品 中々面白かったよ。マジ評価★4程は有ると思うのだが。
まぁカルト物なんだけどね。A24らしいド真ん中な作品ですね。
そんでもって見応えは有ったわさ。
最後まで見てて、信仰者が必死に祈り、神の鉄槌が下されるって言う場面ね。
それを感じたよ。あの”ジョ-ズ”の最後、アゴを圧搾ボンベ爆破破壊と同じ位、スキッとしたわ。
場面は暗いし、キモイし、怖いの嫌いな人にはオススメしないけども、
そんなにグロくは無いし、ひぇ~と一度は驚くと思う。(;^ω^)
------
監督・脚本:スコット・ベック氏、ブライアン・ウッズ氏
(クワイエット・プレイス作品のタッグ)
----MC-----
ミスター・リード(やべぇ奴・異端者):ヒュー・グラントさん
シスター・バーンズ(布教活動シスタ―・しっかり者):ソフィー・サッチャーさん
シスター・パクストン(布教活動シスタ-・スカ-トまくられる):クロエ・イーストさん
------------
とにかく、こんな深い森中の家に 異端者が居たんしゃ~ (#^.^#)
(チョイボケさせてくれ~ た、頼む m(_ _)m)
( ̄д ̄)それは置いといて・・・
(話展開)
急斜面なメッチャ階段上って、森の中の一軒家へ チャリンコで辿り着く。
天気崩れて雨降りだす夕方。シスタ-二人、ドアチャイム押す!
(;´・ω・) キリスト冊子持ってきたよ ⇒ (-_-メ) ムムム・・・
(-_-メ) ちょっと待ってて・・・ ⇒ (;´・ω・) おっさん遅せ―な
(-_-メ) お前さん達 どうぞ中へ。
(;´・ω・) ウチら直ぐ帰らな~。冊子はこれっすわ。
(-_-メ) 今妻がパイ焼いてる。雨降って来たし中で茶でも飲んで行けば?!
(;´・ω・) あ!いい匂いする。 (外野聲:ホンマけ?ホンマにこの時したんけ?)
じゃ~ ちょっとお邪魔しま~す。入ったシスタ-二人。
((( ドア ガッシャン ロック )))
ゴキブリホイホイに 入った シスタ-達!!
さぁ大変の始まり・・・
(-_-メ) 色んな宗教の アーダ・コーダ 君らが知らん事を俺は知ってるぞぉ。
モノポリ-の俺様のうんちくを聴くんだ~ オメ-ラよ~
(;´・ω・) も-やだ-。テンション下げ下げぇ。
奥様は何処?パイ無いやん、もう帰りたい~ 玄関開いてへんやん。
(-_-メ) そやったかな?玄関カギ硬いネン。
帰りたかったら そこの左右のドア どっちか選べ。信じた方が外に通じてる。
(;´・ω・) コイツ!マジ キメ-ヤヴァイ奴じゃんか。何とか脱出せねば・・・
アハハハ、左側ドアから・・・へ??? 地下階段じゃん。
絶対に外になんかに通じてない。( 確信 (@_@;) )
(-_-メ) ココ来るまでにどんな所に家建ってるか知ってるでそ。
地下に降りて行ったら出られるんだよぉ~ ( ̄д ̄)
== ココから 二人と おっさん異端者との心理バトル戦が始まる ===
という訳で、暗い地下部屋で、異端宗教の奇跡を見せられる二人だが。
・老婆が毒食って死す。確かめさせられる二人。だが 死体が復活して蘇る。
(ここ 度肝抜いたわ (@_@;) )
・”下着”言葉で反撃作戦~ だが敢え無く 返り討ちに・・・ひえ~!!
しかも左の二の腕部分を (@_@;) (@_@;) (@_@;) 何すんだぁ~
ぎぃゃぁぁ ~ ~ ~ (アカン 吐きそう!)
・もう ダメだ・・・ し、死ぬ。きっとぉ。
冷静に、とにかく冷静に成れ。 考えろ。考えるんだ。
これは 神の奇跡なんかじゃ xxxxxxxx。きっとxxxxx。
そして xxxxxx、xxxxxx、xxxxx となって xxxxxxとしてる。(#^.^#)
・(;´・ω・) あ~ぁ神様、私を どうか私をお助け下さいぃ・ぃ・ぃ...。
(-_-メ) お前の命は神に捧げられるんだぁ~ぅぅ・ぅっ
((((( どっひゃ ~ ~ (@_@;) ))))
---------- と言う さすがの展開ね!!-------
ひとつ ひとつ ドアを開けて行くドキドキ感。
歩く物音。出来そうで出来ない、できないけど 出来る・・・
そう言う所が 面白かったですね。
ヒュー・グラントさんが中々の役処でして、
今上映中の”ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今”の彼とを
はしごで観たら きっと情緒オカシク成るのは必至かもw。 (●´ω`●)
興味ある方は
是非 今の内に
劇場へ!!
蝶に想う
面白かった。ただし、この映画は宗教にあまり関心のない人にとっては、完成度の高くないサイコスリラーのように思えただろうと思う。
実在の宗教団体である末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)を出しているのは、監督が「そうでなければ描けないテーマ」のためだと思う。
モルモン教というのはキリスト教系の新宗教の1つで、創始者であるジョセフ・スミス・ジュニアが1820年ごろに起こした宗派。独特なのは、カトリックなどが用いている聖書のほかに、ジョセフが神の啓示により発見したとされるモルモン書を使用している点。日本でも二人組で自転車に乗って布教活動している姿をよく見る。
宗派の特徴として、排他性が強い(自分たち以外の宗教を間違っているという信念を持つ)、根本主義的である(モルモン書を神の言葉とし、真実のよりどころとする)、伝道活動に熱心である、という点がある。キリスト教の各宗派はそもそもこれらの性格が強い宗教だが、モルモン教は特にこれらの傾向が強いと思う。
wikipediaによると、全世界で1700万人の会員がおり、キリスト教の教派としては米国で4番目に大きいらしい。政治にも大きな影響力を持つ。
映画の冒頭の「飲み物」「一夫多妻制」「モルモン教の由来」のやりとりは、たぶんアメリカでは「あるある」の議論で面白く観れるところなんだろう。
リードがねちっこく、やや茶化してモルモン教の奇異に見える点、教義の矛盾点を遠回しに指摘するのに対して、バーンズが(相手への嫌悪をおさえつつ)できるだけ誠実に答えようとする、というやりとりは、実際の伝道の現場でよくある光景なのだろうな、と想像できる。
この映画の登場人物である3人はそれぞれ異なる信仰への背景を持つ。
シスター・パクストン
いわゆる宗教二世で、信仰にさほど疑問を持たず、無邪気に布教活動を行っている。良くも悪くも信仰に対する葛藤がなく、深く考えていない。布教活動をまさにセールスのように考えている。
リードの示す「信仰」「不信仰」の扉で、安易に「不信仰」を選んでしまったのは、信仰に対する自分自身の信念を持っていないことを表している。
終盤では、自分の意志で選択したように見えて、実は他人の意志で選択させられている(自分は信仰によって支配されていた)、ということを自覚する。
シスター・バーンズ
親の改宗により信仰の道に入った。熱心で真面目な信仰者だが、その裏には信仰への葛藤があった。信仰への迷いがあったからこそ、それを打ち消すために熱心だった、ともいえる。
リードがトリックによって死者の復活の奇跡を見せたとき、バーンズは「これは単なる臨死体験であり、奇跡とは違う」と反論した。この反論は実は彼女自身の不信心を告白した(自覚した)瞬間でもあった。
彼女が冒頭のリードの宗教批判に対して論理の穴を指摘できたのも、彼女自身がそうした信仰への疑いに対して、以前から自問自答していたから、とも考えられる。
ミスター・リード
おそらくはもともとは熱心な信仰者で、「真実」をクソ真面目に追ううちに、「神はいない」「宗教は単なる支配のシステムに過ぎない」という結論に至り、闇落ちした。神に反抗して地獄に落ちた堕天使の絵が彼を象徴的に表している。神を熱烈に求めながらも、神はいないと絶望している、というゆがんだ精神をもっている。
「信仰」「不信仰」の扉は、どちらも正解ではない。これは、「信仰」の道に進んでも、「不信仰」の道に進んでも、どちらも地獄だと彼が考えている、ということ。
彼は、「熱心な信仰者」を支配することで、「神はいない」こ証明しようとすると同時に、その試みを打ち砕いてほしい(神がいると証明してほしい)と考えているのではないか。
映画の最後で、シスター・パクストンは祈りの効果は無い、と分かっていながら、祈りをささげる。この彼女の態度こそが信仰の本質ではないかと思わされる。
パクストンの手にとまった蝶が、次の瞬間に消えたのは、いろいろな解釈がありうる。蝶は、バーンズが「死んだあと蝶として戻ったとき、自分だと分かるように手に止まる」と語っていたこともあるが、リードの語っていた「胡蝶の夢」も連想させる。
この映画では、リードによって何度も「二者択一」の選択を要求される。「信仰」「不信仰」の扉もそうだが、シスターたちがリードに会った瞬間から、常にリードに「どちらを選ぶ?」と聞かれている。「胡蝶の夢」の話も、「現実」か「非現実」か?
リードは、「どちらを選ぶか人間にゆだねられていること」が自由意志ということだが、実は真の自由意志というものは存在せず、「どちらを選んでも実はそれは選ばされている」、という主張なのだと思う。
蝶がバーンズの魂か、そうでないか。それを考えるとき、はっと気づく。それをはっきりさせる必要があるのだろうか?ということに。二者択一を考えることが無意味なこともあるし、ときに有害なこともある。
全94件中、1~20件目を表示