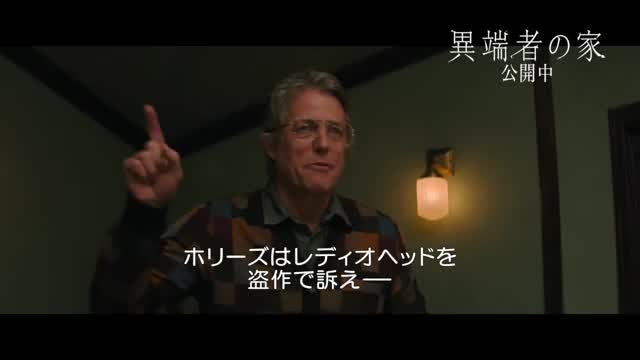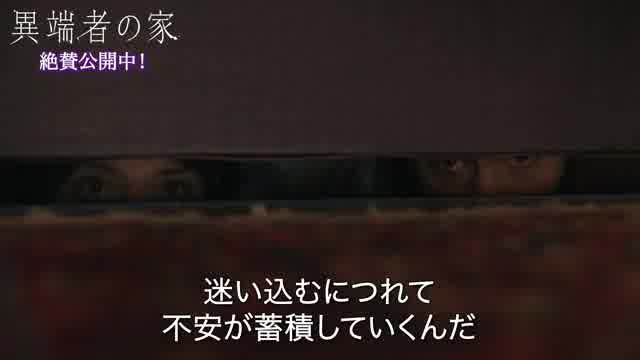「信仰を“操作”することの恐怖」異端者の家 こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)
信仰を“操作”することの恐怖
宗教ホラーの皮を被りながら、実は“信仰とは何か”を問う知的スリラー。モルモン教の若いシスター2人が、森の奥の屋敷を訪ねる。信仰の言葉を携え、真理を語るはずが、待っていたのは理屈と論理で信仰を分解してくる男、リード。彼の家は、信仰の構造そのものを模した迷宮であり、彼女たちは信仰そのものを“試される”側に転じていく。
この作品の主題は、“信仰を支配する者”と“信仰に支配される者”の入れ替わりだ。リードは宗教を否定しながら、その仕組みを精緻に理解している。だからこそ、信者を「試す」ことで信仰の脆さを暴く。彼にとって信仰は救いではなく、支配の装置であり、他者の自由意思を奪うための構造。
この知的暴力こそが、映画の根幹にある恐怖だ。
――信仰を操作する者は、神を装うことができる。
物語の中盤、シスターの右腕に一瞬だけ映る手術痕。説明は一切ない。私は何かの怪我かと思い、そのまま見過ごした。ところが後で調べて驚いた――あれは「避妊インプラント」の痕だったのだ。知らんがな、そんなもん。宗教ホラーを観に行って避妊医療の知識を試されるとは思わなかった。だが、それこそがこの映画の巧妙な罠だった。
モルモン教では避妊は神の意志に反するとされる。つまり、その痕跡があるということは、彼女が信仰の枠を越えて“自らの身体を自分の意志で選んだ”証。リードが見抜いたその傷は、信仰的には“異端”だが、人間的には“自由”の痕でもある。
この一瞬の映像が、宗教的純潔の崩壊と、自律への目覚めを同時に描いていた。
監督のスコット・ベックとブライアン・ウッズは、『クワイエット・プレイス』でも顕著だった“説明の削除”をさらに徹底した。セリフを削ぎ、沈黙と痕跡で語る。確かに美学としては成立している。だが、本作では観客を置き去りにしている側面もある。説明の欠如が宗教の不透明性と重なり、「理解できないことこそが信仰である」とでも言いたげだ。だが、それは映画としての誠実さと紙一重だ。観客が気づかない伏線を「理解の遅れ」として処理する態度には、わずかな傲慢さすら感じる。
それでも、ヒュー・グラントの演技は圧巻。温厚な笑みの裏で他者を心理的に解体していく知的サディズム。彼の言葉は宗教を否定するようでいて、実際には“信仰を再設計して支配する者”の言葉。信仰とは、人を救う装置であると同時に、人を縛るプログラムでもある。リードの屋敷はそのシステムの縮図だ。見えない境界、強制的な選択、そして「自由」を装う支配。観客もまた、彼の信仰装置の中に閉じ込められている。
終盤、シスター・パクストンが雪原で手を差し出すと、蝶がとまる。かつて彼女が語った「死んだら蝶になって戻りたい」という言葉の再現だ。現実か幻覚かは分からない。だが、その曖昧さこそが信仰の本質を映す。信仰とは、証拠を求めれば失われ、疑えば崩れる不確かなもの。それでも私たちは、何かを信じることでしか生きられない。だからこそ、誰かがその“信じる力”を利用すること――それこそが最大の恐怖である。
本作は信仰の名を借りて人間の自由意志を奪うメカニズムを冷静に解剖する作品であると理解した。信仰を操作することの恐怖とは、すなわち「信じたい」と願う心を誰かが支配すること。そして、その誰かはいつだって、神ではなく人間である。
共感ありがとうございました。
モ教の知り合い(全員女子)が多く、話をよく聞きます。9種類ある天国の最高峰目指して、毎年、年収の10%を払い、子供は5~6人つくり、男子は皆、宣教のため世界中に派遣される………厳しいですね。(>_<)