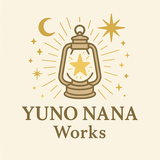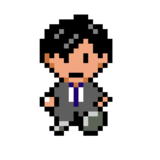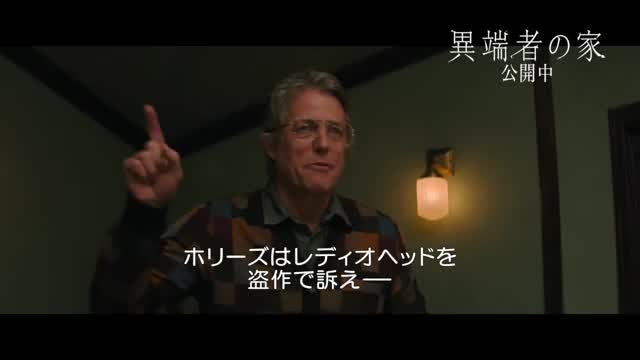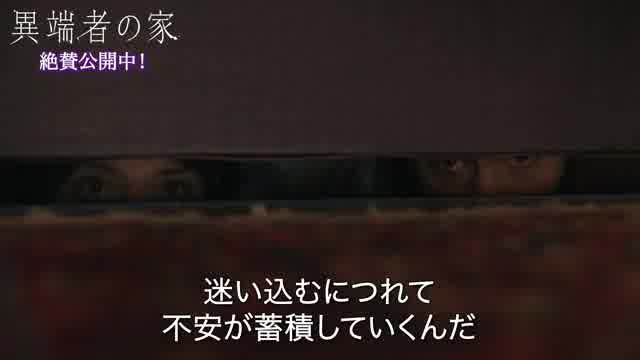異端者の家のレビュー・感想・評価
全303件中、1~20件目を表示
たとえ美味しそうなパイの匂いがしても知らない他人の家には絶対に上がらないでおこうと心に誓う
一切の前情報なしでの鑑賞。知っていたのは、タイトルとメインビジュアルのイメージのみ。まさかこんなに恐ろしいサイコスリラー映画だったとは…😱聞いてないよ〜🤫知ってたら絶対観なかったかもしれない。だってホラー映画嫌いだもの🙄
私の知っているヒュー・グラントは「ノッティングヒルの恋人」など甘いマスクで惑わすラブコメ作品のイメージですが、本作ではその彼のイメージを根本から覆されます。いつもの甘い笑顔は封印され、不気味なうすら笑いで追い詰めてくる奇人を好演。またそれがうまくマッチしているんだな🙄 でも男前ってのは、歳をとってシワが刻まれても、どんなに恐ろしい役を演じても、やっぱり根底にあるカッコ良さは隠せないよね。キムタクがいつもキムタクなのと同じ🧐ヒュー・グラントにこの役をキャスティングした人は素晴らしいですね、ほんまハマり役です🤫
私の中のホラー映画ってこういう映画なのです。お化けとか出てくる必要ないのよ👻 いつも思う「普通の優しげな人の豹変」がいっちゃん怖いからね🧐「ブルーベリーパイ食べてく?」からの「なんかこれおかしいんじゃね?」と2人のシスターが徐々に気がつくまでの間合いが絶妙。ちゃんと、段々、少しづつ、レベルアップしていく「怖さ」で心震える😱これってよくありがちなホラー展開なんですか?ホラー初心者すぎてわからん🔰わからんけど、私には十分過ぎるほど怖かった〜。密室で出られないというだけでもう絶望だよね。私があのシスターたちの立場だったらどうするんだろう?と常に考えながら観てるから、もっと怖くなるよね。シスターたちは、偉いよね👏恐怖に怯えながらもちゃんと選択してるんだから。私だったら絶望を通り越してもう号泣してるよね😭チョロいのよ、わたしホラー初心者🔰だから。いや、どうだろう?逆に火事場の馬鹿力みたいなのが湧いてきて勇ましく戦ってみたりする自分に出会えたりするんかな?絶対に体験したくはないけど、ほんとにそんな場面に出会した時に自分がどんな「選択」をするのかは興味はあるよね🧐
正直、宗教的なことはよく分かりません。けれどもミスター・リードの言い分にも半分くらい理解できる部分はありました。しかし「支配」こそが宗教なのだといった彼の考えとは異なり、私の中の宗教的なものは「自分の信念」みたいなものに置き換えられるかもしれません。
そんな私の信念から導き出した本日の教訓はコチラ
「たとえ美味しそうなパイの匂いがしても知らない他人の家には絶対に上がらない」
追伸
しばらくパイと扉がトラウマになりそうなくらい度直球に恐怖を喰らい夜道を帰るのが怖くなる🥲😭
5分後に始まった映画「たべっ子どうぶつ」に幸い心癒され無事帰宅♪
宗教マニアをぢ vs モルモン布教女子のアンフェアファイト
すっかり性格俳優にシフトしたヒュー・グラントを楽しめる映画。「ジェントルメン」での癖つよ探偵役を見たあたりから、もっとそっち方面を演ってほしいと思っていた私はそれだけでプラス評価。
彼のキラースマイルの威力はまだ健在で、玄関のドアを開けた時に彼が見せた微笑みには、悪役だとわかって見ているこちらの気持ちさえ一瞬油断させる力があった。話が進むにつれ、その笑顔や愛嬌ある笑い皺がリードの不気味さに似合って見えてくるところはさすがだ。
サイコスリラー映画としては、うーんどうだろう。怖い映画苦手の私でもあまり怖くなかったから、このジャンルが好きな人には物足りないかも。
(二の腕の傷をほじくるシーンだけはギエエエエとなった、怖いというより痛そうで)
前半、リードが宗教や信仰心の本質(彼の持論)についてシスターたちに滔々と語るくだりは興味深かった。(「ボブの絵画教室」バージョンモノポリーには笑ってしまった)
八百万の神の国に生まれ育った消極的無宗教の私にとっては、正直なところ物語の前半においてはリードの主張の方が、モルモン教より首肯できる部分が多かった(ただし、パンフレット掲載の寄稿によると各宗教についてのリードの説明は所々嘘を含んでいるそうなので、鵜呑みにするわけにもいかないが)。
アメリカ国民にはキリスト教信者(もちろん宗派は分かれているが)が多いというイメージがあるが、イエス・キリストの逸話への冒涜とも取れそうなリードの主張は批判を招かないのだろうか。Rotten Tomatoesでの評価は比較的高く、社会問題化するほどの反発を受けてはいないように見える。
末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教の教団)は本作を非難する声明を出しているそうだが、作品を鑑賞したモルモン教徒当事者にとって、序盤に描写された宣教師の日常は結構リアルなものだったようだ(The Guardian、2024年11月の記事より)。
本作の2人の監督、スコット・ベックとブライアン・ウッズはモルモン教徒の友人らに脚本について相談し、彼らの日常会話をもとに台詞を創造したという。
そのリアリティと、キリスト神話説的な主張をしているのがサイコパスな悪役、という設定であること、そして最後には「誰かのために祈ることは素晴らしい」と信仰を肯定するパクストンがリードを倒す展開。これらがあるから、前半のキリストに対する冒涜的なリードの主張も、キリスト教徒から見れば「迫害者の間違った考えの描写」として消化されているのかもしれない。
前半のマンスプレイニング的宗教論破がそのまま続くのもまた一興だが、それではスリラーというよりめんどくさいおじさんの話だ。ここからどうサイコスリラーに持っていくのか、と思っていたら、後半での怖がらせ方自体は結構ありきたりな感じでちょっと気分が盛り下がった。暗い地下、唐突に出現する貞子みたいな女。ジャンプスケアと流血。
宗教マニアを極めた結果無神論者になったのかと思いきや、宗教の本質は支配であるという結論に至りそれを実践したリード。結局、支配行為という邪教の信者になったということか。
悪役の背景をどこまで描くべきかは作風や好みによって分かれるだろうが、リードについては個人的には、あのような考えに至った理由や彼のヒストリーが見えた方が面白くなりそうな気がした。パクストンが地下でいくつかの部屋を通った時、そこに雑然と置いてあった色々なグッズにヒントがあるのかなと思ったが残念ながら分からず。キリスト教圏の人が見たらピンとくるのだろうか。
「胡蝶の夢」の話をどう効かせたいのかよく分からなかった。脱出後のパクストンの手に蝶がとまった時、まさか夢オチなのか?という安直な不安がよぎったが、さすがにそれはなかった(笑)。
ところで、合言葉として出てきた「魔法の下着」だが、モルモン教に入信した人が一生身に着ける、上は半袖アンダーシャツ下は膝丈ステテコみたいな衣服のことだそうだ。神との聖約の象徴であり、下着の上から着る服で完全に覆わないといけないので、自然と露出の少ない服装になるという。その名称を合言葉として使うのは、魔除け的なニュアンスがあったのかもしれない。
頭脳を刺激する宗教談義スリラー
思っていた以上に本気の宗教談義が続く。たまたま中学生のときにモルモン教の経典を読んだことがあり、そのときに抱いた疑問を思い出したりして、ついヒュー・グラント側に肩入れしそうになるのだが、いやいやコイツも大概というか絶対アウトな人でしょう!と思いなおしたりして情緒的に忙しいのも、結果的に地味シブジェットコースタームービーとして機能してくれて得をした気分。
ヒュー・グラントの怪演が話題になるのは当然として、対する小娘ふたりに一筋縄ではいかない顔をもたらしたソフィー・サッチャーとクロエ・イーストも素晴らしかった。日本はわりと信仰心と縁の薄いお国柄だと思うが、他人の信仰心を無碍にするわけにもいかないので、役に立つ知的な遊びという面でも楽しめる。とはいえヒュー・グラントの言うことをまんま鵜呑みにするとたやすく陰謀論者の落とし穴に落ちるんでしょうけども。
ヒュー・グラントの妙味を研究し尽くした唯一無二のホラー
かつてヒュー・グラントがロマコメ帝王だったことが都市伝説に思えるほど、ここ最近の彼は変幻自在だ。たとえ陰湿でナルシストな”嫌な奴”に振り切れたとしても、観客は苦笑いしながら、でもやっぱり彼の個性に魅了されてしまう。そんな彼が行きついたホラーの新境地。今回のキャラを構成するのはやはり”喋り”だ。ほぼ全編が彼のセリフ回しで占められていると言っていい。通常なら一人の俳優がこれほど喋り続けると観客も早々に飽きるものだが、相変わらずの甘いマスクで、まるで歌うように知的で優雅で緩急タイミングの絶妙な演技をやられると、この出口なき家さながらにもう止められないし、出られない。私自身、鑑賞中の自分が果たして恐怖しているのか、それとも魅了されているのか、最後まで分からなかったほど。どんな役でもグラントはグラント。これは他のキャストでは置き換え不可能な、もはや彼のために仕立てられたホラー。だからこそ最高なのだ。
サイコパスなのにいつものヒュー・グラント!?
宗教の布教活動をしている2人の若い女性がドアをノックすると、目の前にリードと名乗る気さくな中年男性が現れて、家の裏で妻がブルーベリーパイを焼いているから一休みして行かないかと提案する。女性たちはその誘いを受け入れる。
しかし、男は2人の話に耳を傾ける気などさらさらなく、宗教に関する持論を展開し始める。同時に、その家は脱出不可能な設えになっていて。という密室サイコパスホラー。
これまでも、入ってはいけない家に入ってしまった訪問者たちが死ぬほど怖い思いをする同じジャンルに属する傑作が何本かあった。しかし本作の場合、宗教にまつわる(まつわらなくても)持論というものが他者にとっていかに不快か!?というテーマが観客を苛立たせるところが異色と言える。そして、この世界のどこかでは閉ざされた家の中であらゆる異端者が息を殺して獲物が引っ掛かるのを待っているというリアリティが、異色に拍車をかける。
最大の見どころは多少既視感がある物語を独特の個性で牽引していくリード役のヒュー・グラントだと言って過言ではない。英国が生んだ世紀のチャラ男から、最近は軽妙や悪役までカバーするグラントが、ここではなんと、いつも通りのグラントを演じることで恐ろしいサイコパスになりきっていることに驚く。いう言われれば、グラントの目はいつも危険な光を放っていたことに気づく人は多いかも知れない。異なる役に挑戦し、都度変身するのではなく、役を自分に引き寄せてきたということに。改めてヒュー・グラント、凄い俳優である。
宗教論破合戦
いまいちよくわかんなかった。
リード氏は何かしらを経験して宗教にのめり込んだが自分の納得のいく宗教が見つからず、
宗教を突き詰めた結果、支配であるということに行きついた。
そこで自分の信者を作るために訪れる女性を様々な言葉で信仰を論破してMY宗教に入らないか?と勧誘してたって事なのかな?だけどシスターバーンズに逆論破されてこいつは信者にならないと見て殺害してしまった。みたいな事なのかな?と思った。
僕は宗教に興味がないので神の行いについて深く考えたことはないので、信者たちが持つであろう神や宗教への矛盾などの会話にイマイチついて行けなかった。これ迷路に入り込むまで信仰について110分中半分もかかっている。これを楽しむにはそれなりに宗教の矛盾について考えたことがないとなかなか退屈だったと思う。
また予告ではあたかも巨大迷路に迷い込むようなイメージで伝えていたが全く大きくもなく、CUBEのような罠があるわけでもない。迷路というか地下通路に入ってからもひたすらリード氏の宗教論やMY宗教への勧誘がされて、なんか女性二人がかりで行けばやれ倒せるんじゃないかという感じだったのでそんな緊迫感もなかった。
最終的にシスターパックストンと相打ちになってどっちも死ぬかもってなった時に、彼女の信仰への揺らぎを持ちつつも、それでも人のために祈ることは美しいことだと言って迫る死を前にしてなおもリード氏のために祈ることでリード氏は結局最後にシスターパックストンに信仰を見つけたが、、、、その瞬間、、。という皮肉なことが起こり、シスターパックストンは信仰を取り戻すという皮肉な結果となったということなのかな?
ただずっと宗教なんて嘘さ!みたいな論破が続いてて流石に110分も聞いてるとちょっとそろそろダンジョンで罠と戦えよって思ってしまった。まあそれは最後までないんだけど。
そんなこんなで全体的にダルダルな感じで話が進むので多分みんな期待していたものとは違うじゃんって思ってるんじゃないか?
シスターバーンズはブギーマンで注目してたんだけど、シスターパックストンは初だったけど、随分可愛い人だなって思って今後もきっと出てくるだろうなと思っている。これからいい作品に恵まれれば二人ともスターになるんじゃないかな?それはよかった。
ヒューグラントはラブコメが多いせいかUNCLEしか見たことないので然程この役回りに驚きはなかったなあ。まあキモい役の割にはイケメンすぎじゃないかなとは思ったけど。
興味深い話もあるが2時間弱あったわりには薄味なような…
笑えるしスリリングな良作
布教に訪れた若い女をオッサンが理論でやり込めて、あろうことか宗教についてのマンスプレイニングを始めるという導入部がとにかく面白い。
わが家も布教で突然ピンポンを鳴らされることがあるため、最初はちょっとこのオジサンに肩入れしてしまったくらいだ。
また、何とも粘着質でくどいオッサンをあの美青年でならしたヒュー・グラントが演じるというのも味わい深い。
昨今、悪役を演じることも多く、楽しそうに演じているのがとても良い。
前半の軽妙で皮肉の効いた展開から、後半はガチのホラー展開になるのだが、このトーンの転換が少し唐突だと感じた。
ただおしゃべりしてるだけのシチュエーションの方がずっとスリリングだったからだ。
とはいえ、後半はこういうマンスプレイニングジジイをぶっ倒すというフェミニズム的な爽快感もあり、実に現代的でユーモアの効いた作品だと思う。
楽しみにしていたので初日に映画館へ
ストーリーがしっかりしていて奥が深い。グロで怖がらせるホラーとは一線を画す。ヒュー・グラントの演技が秀逸でリビングで穏やかに話してる時からゾクゾク、ザワザワしてきて、途中からずっと気を張り詰めて見入ってしまった。効果音の使い方もさすがA24。何度も驚かされ心臓に悪いなと。笑
宗教絡め具合が欧米人に受けそうと思ったらかなり賞も取ってる。モルモン教やキリスト教の信仰の厚いアメリカ人の友達(映画に出てくる二人のシスターみたいな)がいるので宗教の話はよく理解できた。そのあたりは欧米と日本で評価が分かれるかもしれない。
イケオジによる怪演!
その異端はペテン。別の異端は奇跡を起こす…
よく町中なんかで宗教の勧誘に声を掛けられると、ウザッ!…と思う。私はあまり宗教が好きじゃない。母の死にも関連するので。
だからこうして若いシスター2人の視点から描くと、大変やな…とも思う。
布教活動で町を回るシスター・バーンズとシスター・パクストン。
何人か勧誘した事あるシスター・バーンズはポジティブな性格だが、勧誘ゼロのシスター・パクストンはネガティブ。話を聞いてくれる人はほとんどおらず、心無い悪戯も…。
そんな時、森の中の一軒家でもいいから話を聞いてくれる人に会うと、救われた思いになる。主のお導き!
応対してくれた中年男性リードはあの“ロマコメ王子”。にこやか朗らか気さくな性格で、そりゃ警戒心も薄れる。
宗教にも関心ありで話をしていると、突然雨が降ってくる。リードは家の中へ招く。
これにはさすがに警戒。中年男性の家に若い女性が2人…。規則で同伴の女性が居ないと家の中に入れない事になっている。
奧でパイを焼いてる妻ならいる。その言葉をすっかり信じ、2人は家の中へ。
ネズミやカエルが天敵のいるカゴの中に入ったようなもの…。
妻特製のパイが焼き上がるのを待ちながら、温かいティーを飲んでくつろぎ、話の続きを。
リードは頭が良さそうなのは話していて分かる。お喋り上手で話に引き込まれる。
話が弾んでいたが、ある質問から雲行きが怪しくなってくる。一夫多妻制についてどう思うか、キリスト教会設立者ジョセフ・スミスについてどう思うか…?
リードは宗教を否定するような事を…。それでも2人は対応していたが…。
父を亡くした経験のあるシスター・バーンズ。ちょっと無礼な話をしてしまった事から居心地が悪くなる。
パイがまだ焼き上がらない。奥さんも一向に姿を現さない。
様子を見てくる…と、奧に引っ込むリード。その隙に、帰るか否か迷う2人。
帰る事に決まったが…、玄関ドアが開かない。と言うかドアノブが無く、開けられない。
スマホを掛けるが、電波が入らない。
閉じ込められた…?
警戒心はとっくに通り越し、恐怖。
その時、奧へ続くドアが静かに開く。誘うように。
恐る恐る奧へ入っていく。そこで待ち受けていたのは、恐怖と試練であった…。
リードはどうやら豹変して性的に襲い掛かったり、殺そうという気はないようだ。
寧ろ、それが怖い。一体、何が目的なのか…?
2人は現状の事や帰らせて欲しい事を懇願する。すると、
家に招き入れた時、家のあちこちに金属が埋め込まれてあり、スマホは使えない事を暗示したのに、何故教会から連絡が…と嘘を付く?
妻がいると何故易々と信じた?
リードの言い分はサイコな男のキチ○イな言動というより、頭のいい男が若い迷える子羊を翻弄しているようだ。
リードだけが楽しいトークは尚も続く。独自の宗教論を展開。
どの宗教も真実とは思えない。世界三大宗教を例に出す。
原点はユダヤ教。これをリメイクしたのがキリスト教。ニューバージョンがイスラム教。いずれも信仰対象や物語など似通っている。
これをモノポリーに例える。元々は名もなき女性が発案したボードゲーム。それを基にアメリカが“盗作”したのがモノポリー。以後、類似品が氾濫。
誰も元祖や原点を知らない。世の全てが反復。それの何処に真実がある?
これを私なりに映画に置き換えると…、第1作目の『ゴジラ』がある。ハリウッド版がある。近年の『−1.0』がある。TV放送や最近の人が見るのはハリウッド版や『−1.0』ばかり。原点をきちんと見た事あるのか…?
あくまでリードの持論だが、何だか説得力あり。ついつい話に引き込まれた。
しかし、シスター・バーンズは反論。各宗教宗派それぞれの主の姿、教え、歴史がある。決して反復なんかじゃない!
この意見にも同感。初代もハリウッド版も『−1.0』もそれぞれの面白さと魅力がある。
2人はモルモン教。現在正式には“末日聖徒イエス・キリスト教会”。ジョセフ・スミスが設立したキリスト教の新派で、異端の一つ。最大の特異は主流キリスト教の三位一体(父・子・聖霊)否定。それぞれ別個であるとの考え。禁止されているものも多く、カフェイン、アルコール、煙草。婚前の性交渉も。厳しいが、教徒は幸せを感じている者も多いという。
リードからすれば亜流の亜流の異端かもしれないが、それでも2人は信じている。
それを試されているのか…?
前半は見る者の価値観を揺さぶる会話劇がメインだが、後半は動きがある。
帰らせて欲しいと頼む2人。が、玄関ドアはタイマーでロックされ開かない。帰るなら、強制も、引き留めようと無理強いもしない。ご自由に。
しかし、裏口から。2つの扉のどちらかを。“信仰”と“不信仰”。
一体この男は何を示そうとしているのか…?
2人が選んだのは“信仰”の扉。
地下へと降りる。
行き止まり、地の底のような密室空間。唯一の出入り口は下ってきた扉だが、言うまでもなくリードが見張り、鍵を掛けられた。
不穏な会話劇から息詰まる密室スリラー。ここでも変化球。
2人だけかと思いきや、浮浪者のような老婆が。
老婆は置かれたパイを食べる。その直後、息絶える。毒入りのパイ。
リードの声が響く。2人に息絶えた事を確認させる。
リードが驚くべき事を。もし、この老婆が“復活”したら…? その“奇跡”を信じるか…?
モルモン教もキリストの復活を信じている。しかし、リードが言う“復活”や“奇跡”はキリストのそれではなく、我が手によるもの。
そんな事はあり得ないと思っていたが、老婆は復活。恐れおののく2人。
リードの信仰や宗教は、絶対的な“支配”。
“支配者の家”で絶対的な支配の下、2人は成す術もないのか…?
が、遂に突破口を見出だす。2人揃って無事の脱出を試みるが…。
これまでにも『パディントン2』や『ダンジョンズ&ドラゴンズ』で悪役を演じた事はあるが、いずれもユーモラスだった。
これほどの恐ろしさ、不気味さは初めて。
ラブストーリーやコメディが多いが、実際は実力巧者。
ヒュー・グラント、圧巻の新境地!
対する若手2人、ソフィー・サッチャーとクロエ・イーストも負けていない。
監督のスコット・ベックとブライアン・ウッズは『クワイエット・プレイス』の脚本コンビ。監督作は『ホーンテッド 世界一怖いお化け屋敷』『65/シックスティ・ファイブ』などB級作品が続いていたが、急にどうした?!…ってくらいレベルアップ。
確かに独自論や哲学的な会話、特に日本人には宗教観は小難しい。が、不穏なサスペンス、リードのキャラに不気味さと共にユーモア孕み、ホラーとしても震え上がらせる。
突然の来訪者。2人を心配する牧師が訪ねてきたようだ。
が、地下から声は届かない。存在を気付かせようとするが、その時復活した老婆が2人に迫る。
襲い掛かるのかと思いきや、意味深な言葉を…。
2人はリードが地下に下りてきた時、合言葉を決めて殺してでも逃げようとする。シスター・バーンズはシスター・パクストンにナイフを託す。
リードが下りてきた。合言葉を発した時、凶刃が首を。首を切られたのはリードではなく、リードが隠し持っていたナイフでシスター・バーンズが…。
パートナーが殺され、絶体絶命の状況。どちらかと言うと弱い心のシスター・パクストン一人になり、このまま絶望するかと思ったが、それが彼女を奮い立たせた。
老婆復活のからくりを見破る。牧師が来て2人が扉に張り付いていた時、身を潜めていた別の老婆と入れ替わっただけ。シスター・パクストンはちょっとした違和感を感じていた。
違和感はリードにも。一見完璧に支配しているように思えるが、その端々で綻び。内心、リードは焦っている。
リードはシスター・バーンズの腕を切り、金属片を取り出す。それはマイクロチップで世の陰謀をまた得意気に話すが、それはただの避妊器具。
イカれた陰謀論まで抜かす始末。復活もただのトリック。何て事はない。
真実を見つけ、勇気を出したシスター・パクストンにとって、リードは支配者ではなかった。異端は異端でも、ペテンであった。異端者ならぬ“ペテン師の家”。
代わりの老婆が出てきたハッチを見つけ、そこを抜ける。先はまた別室で、多くの女性が囚われていた。老婆はこの事を示していた。
ペテン師で、もう完全なる異常者で犯罪者。
遂にリードはシスター・パクストンに襲い掛かる。
そこで奇跡を見た。リードを食い止め、息の根を止めたのは、殺されたと思われたシスター・バーンズであった…。
ご都合主義を感じるかもしれない。
実は瀕死の重傷を負っただけで死んではおらず、最後の力を振り絞って…。実際、シスター・バーンズは…。
敬虔な布教活動が、最悪の結末に…。
友を失い、一人になってしまったシスター・パクストン。
だが彼女は、教えや書ではない奇跡や復活をその目で見たのだ。誰かを助ける為に。
奇跡がもう一つ。
シスター・パクストンは自分が死んだら蝶になって、愛した人の手に止まりたい。
ラストシーン。シスター・パクストンの手に蝶が止まる。
友愛という奇跡を見た。
ヒュー・グラントの演技に脱帽!
配信(dmmtv)で視聴。
ハラハラドキドキするホラー・スリラー作品。更にA24。
どうなるのかわからなかったが、怖いなりに面白かった。ヒュー・グラントがまさかホラーの館の主人として出るなんて。
A24はハチャメチャの作品もあれば、びっくりするぐらい正当な作品もあるが、この作品は
ヒュー・グラントの演技が素晴らしかったしこれぞ怪演。
ただ、ストーリーはよくある設定か。宗教に関心がない人には辛い作品。
A24にしては異端な作品。
支配という暴力性。
(デビューの頃は清純派に思えたモルモン教徒である
アイドルでしたが、
でも、不倫ばかりして、色情いえ恋愛体質の)
斉藤由貴さんの感想を聞きたいなぁ〜
とボンヤリ思いました。
宗教は支配。
(なかなか適切な思想。
日本の新興宗教は暴力的な支配力で人を傷つけるのが目的のような団体もあるからねぇ〜被害者談。)
祈りは意味がない。でも他の人のことを祈ることは
美しい。
それを言いたかったんだろうね。
魅力ある作品。
計算されている作品というか。
2人の脚本監督がフルにディスカッションして練りに練られた作品にも観える。
ただ私には起承転結の転が長く、飽きた。
期待していたヒュー・グラントは、そんなに怖くなかった。
ヒュー・グラントといえば、美しい『モーリス』から
垂れ目のニヤケでラブコメを通過してコールガールを
買春。
『ウォンカと〜』のウンパルンパの怪演の方がある意味、
怖かった。
ワンコと散歩をしていると、遊んでいるの?と思えるように蝶が、僕の周りをひらひら舞う。
きっと誰かが守り祈っているんだろう、と思っている。
想像と違った。
信仰を“操作”することの恐怖
宗教ホラーの皮を被りながら、実は“信仰とは何か”を問う知的スリラー。モルモン教の若いシスター2人が、森の奥の屋敷を訪ねる。信仰の言葉を携え、真理を語るはずが、待っていたのは理屈と論理で信仰を分解してくる男、リード。彼の家は、信仰の構造そのものを模した迷宮であり、彼女たちは信仰そのものを“試される”側に転じていく。
この作品の主題は、“信仰を支配する者”と“信仰に支配される者”の入れ替わりだ。リードは宗教を否定しながら、その仕組みを精緻に理解している。だからこそ、信者を「試す」ことで信仰の脆さを暴く。彼にとって信仰は救いではなく、支配の装置であり、他者の自由意思を奪うための構造。
この知的暴力こそが、映画の根幹にある恐怖だ。
――信仰を操作する者は、神を装うことができる。
物語の中盤、シスターの右腕に一瞬だけ映る手術痕。説明は一切ない。私は何かの怪我かと思い、そのまま見過ごした。ところが後で調べて驚いた――あれは「避妊インプラント」の痕だったのだ。知らんがな、そんなもん。宗教ホラーを観に行って避妊医療の知識を試されるとは思わなかった。だが、それこそがこの映画の巧妙な罠だった。
モルモン教では避妊は神の意志に反するとされる。つまり、その痕跡があるということは、彼女が信仰の枠を越えて“自らの身体を自分の意志で選んだ”証。リードが見抜いたその傷は、信仰的には“異端”だが、人間的には“自由”の痕でもある。
この一瞬の映像が、宗教的純潔の崩壊と、自律への目覚めを同時に描いていた。
監督のスコット・ベックとブライアン・ウッズは、『クワイエット・プレイス』でも顕著だった“説明の削除”をさらに徹底した。セリフを削ぎ、沈黙と痕跡で語る。確かに美学としては成立している。だが、本作では観客を置き去りにしている側面もある。説明の欠如が宗教の不透明性と重なり、「理解できないことこそが信仰である」とでも言いたげだ。だが、それは映画としての誠実さと紙一重だ。観客が気づかない伏線を「理解の遅れ」として処理する態度には、わずかな傲慢さすら感じる。
それでも、ヒュー・グラントの演技は圧巻。温厚な笑みの裏で他者を心理的に解体していく知的サディズム。彼の言葉は宗教を否定するようでいて、実際には“信仰を再設計して支配する者”の言葉。信仰とは、人を救う装置であると同時に、人を縛るプログラムでもある。リードの屋敷はそのシステムの縮図だ。見えない境界、強制的な選択、そして「自由」を装う支配。観客もまた、彼の信仰装置の中に閉じ込められている。
終盤、シスター・パクストンが雪原で手を差し出すと、蝶がとまる。かつて彼女が語った「死んだら蝶になって戻りたい」という言葉の再現だ。現実か幻覚かは分からない。だが、その曖昧さこそが信仰の本質を映す。信仰とは、証拠を求めれば失われ、疑えば崩れる不確かなもの。それでも私たちは、何かを信じることでしか生きられない。だからこそ、誰かがその“信じる力”を利用すること――それこそが最大の恐怖である。
本作は信仰の名を借りて人間の自由意志を奪うメカニズムを冷静に解剖する作品であると理解した。信仰を操作することの恐怖とは、すなわち「信じたい」と願う心を誰かが支配すること。そして、その誰かはいつだって、神ではなく人間である。
オリジナルは模倣に塗り替えられていく📕
女子2人でモルモン教の布教に来たはずなのにヒューおじさんがジワジワと信仰心を剥がしにかかる宗教ディベートが珠玉。
この映画では、信じるもの(宗教じゃなくても、信奉してるもの、例えば推しとかでも)を引き剥がされる恐怖を描いており、その過程や、葛藤が見どころでありました。
つまりは宗教、音楽、ボードゲームなど、所詮人間の作ったものは同様に、何かしらの影響から生まれたものであり、本来大切にすべきオリジンは模倣に塗り替えられて忘れられていくという文化論を説いてるんですね。
で、そもそも映画、特にハリウッド映画こそが、どこかで聞いたことのあるような話、登場人物という風に似たような映画が多いなと感じますよね。
これはハリウッドのストーリーテクニック本「神話の法則」や新しいとこだと「SAVE THE CATの法則」の影響が大きいかなと思っています。これらのシナリオ指南本のおかげで良質なシナリオの作品が増える一方、模倣のようなシナリオでも予算がついて映画が作られるという。
これらのハリウッドのストーリーテクニック本の元になったのが、神話学者ジョーゼフ・キャンベルの「千の顔を持つ英雄」です。これは神話の中にある共通のエピソードを人間の共通課題として分析した本で、神話といいながら神話だけじゃなく、仏教とキリスト教の共通エピソードなど宗教の類似性も多く知ることができます。
この映画はこの本に大きく影響をうけた、というか脚本家は絶対読んでますよね?そういう意味でこの映画もまた、反復なのでありますね。
他の映画でも「この映画は裏側にキリスト教とか宗教とか神話が隠されてます」とか言われることがありますが、まあそうなりますよね。映画を作る方、評論家もこの本を読んでるから!😆
ラストは映画的にまあこうなるよなという着地でしたが、好みとしてはもう少し違うパターンが見たかったので⭐️4としました。
かなりの良作
ヒューグラントがうますぎ、ヤバすぎ、怖すぎ😱
女性二人がモルモン教の布教活動で訪問した家が…
と言った内容なのだが、本当に面白くて怖かった。
冒頭は本当に心優しい紳士的なおじさんかと思いきや、少しずつ宗教の話になると、その人が様々な宗教に詳しい事が分かってくる。女性二人を試すような質問をしたりちゃんと理解してるのかとか…信仰心を試したり…ヒューグラントはめちゃくちゃ宗教マニア。
もしかしたらその辺詳しいとより楽しめるのかもしれないが、なにも分からない我々日本人でも十分に楽しめる会話劇!
そして舞台はこの家の中だけなのだが、見事なカメラアングルで資格も飽きさせない。さり気ない伏線。
話がすすむに連れて家の奥へと入っていくのだが、それに連れて会話劇も激しくなり男の本性も明らかになってくが狙いが分からなくて最後までずっと楽しい。怖いのが大丈夫な人には見てほしいが覚悟して見てほしい👀
全303件中、1~20件目を表示