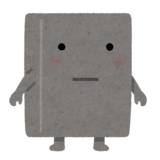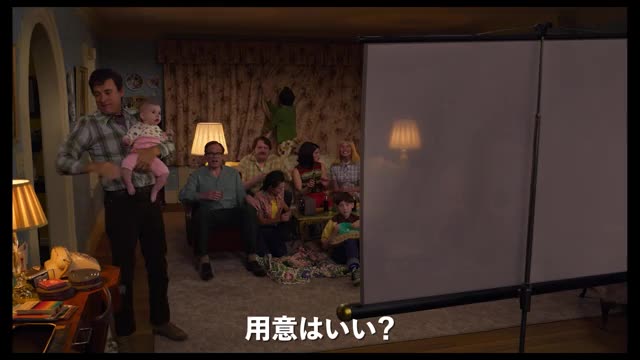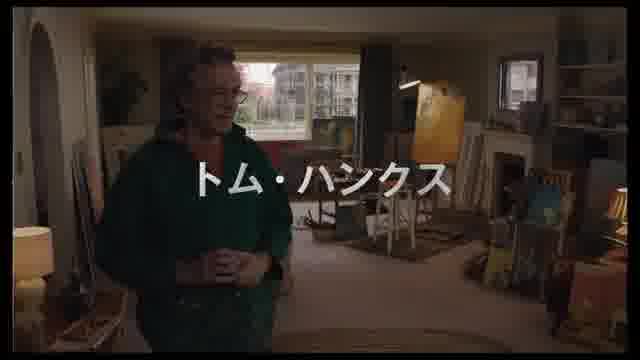HERE 時を越えてのレビュー・感想・評価
全103件中、61~80件目を表示
スクリーンで観る美しい絵本
退屈と感じられる方もいるだろう。視点を固定して人類が誕生する以前から現在まで幾つかの家族の姿を映し出す。必ずしも時系列ではなく時代が戻ったりするが抵抗はなかった。
私にも覚えがある出来事。これから起こるかもしれない出来事。つらいこともあるが最初から最後まで心地良さを感じていた。この輪の中に自分も入れたらなと憧れのような気持ちも抱いた。あの安心感がどこから来たかは文字にできない。
家を建て替えずリフォームして次の人達に渡されることが多いアメリカの話なので、日本では少し難しい感覚かも…。
技術的冒険作
セブンクラウンハイボール
アメリカのとある家がある場所で巻き起こってきた様々な出来事を、恐竜がいた時代から定点画像でみせる話。
売り文句の通り恐竜がいた様子から始まるけれど、それは最初の数分だけで、後は人が現れてからそこに住んだことがある家族たちの様子をみせて行く。
定点と言いつつワイプで少しズレた場所の様子もあったけどね。
時系列を行ったり来たりしながらみせるつくりではあるものの、プロローグを除いてはそれぞれの家族のドラマは時系列通りで、メインでみせる家族のストーリーもなんてことない普通の家族のお話しだし、時系列を弄る意味も感じられず。
この家族を山場にして全て時系列通りにして、後の家族なんか要らなかったんじゃね?
ある意味群像的な作品だけれど、これと行って刺さるような話しもなく、まあこんなものというか、ふーんという感じ。
そこには何時も一組のカップルが
トム・ハンクスとロビン・ライトの若い表情といい、貼り付けたような画面といい、何だか切り貼りして作られたようなストーリー
家族が一同に集い、新しい命が誕生していく一方呆けて老いてゆく様は寂しさと楽しさが入り混じっていた 家は縛るものでもあるのだな
もう少し伏線回収とかあればもっと面白かったような気がした 個人的には土地、家買う時に昔その土地がどのような場所だったか遡って調べた方がいいって話を思い浮かべてしまった とはいえポール・ベタニーのカメラ抱えて騒いでる喧しい親父振りは面白かったな
アメリカの嫁、姑
アメイジング!ビューティフル!
きっと凄い映画だろうが評価が難しい
ついて行ってイイですか?
試みは面白い ドラマがなぁ・・・
2025年劇場鑑賞106本目。
エンドロール後映像無し。
家の中を映している映像から始まり、そこを四角で切り取って、そこの中だけ時代が変わり、四角がなくなって時代がそちらに固定され、また四角が出てきて・・・という変わった設定の映画。家から恐竜時代にまでさかのぼって火山が出てきたのにはさすがに山はなくならんやろ、と思っていたらあっさりなくなったー!(笑)
大体6つくらいの時代がメインで、それがどんどん入れ違いででてくるので、正直混乱しますし、そのドラマひとつひとつがそんなに面白くない・・・。トム・ハンクスがCGで10代を演じていて、そこに全然違和感ないのはさすがのロバート・ゼメキスという感じでしたが、これやれちゃうと似た俳優を使って亡くなった人主演で映画撮れそうなんですよね。実際ワイルドスピードでポール・ウォーカーの弟がポール演じていますし。正直ブルース・リーの完全新作は観てみたいです。ブルース・リー対全盛期のジェット・リーとか。でも俳優協会が黙ってないでしょうね・・・。
とにかく、CGの技術にドラマが追いつけてないという感じでした。別に他の若い俳優がやれば済む話ですし。
世界が違って見えてくるーーゼメキスの実験的超意欲作!
映画を観る目的はなんだろう。感動するため、楽しみのため、明日からまた働く活力を得るため……。
さまざまあると思うけれど、観終わったときに、観る前と自分自身の在り方が変わってしまい、同じ世界が違って見える——そんな映画はいい映画だと思う。
そしてこの映画は、まさにそんな作品だった。
西新井の映画館を出て、新興のマンション群と散り始めた桜並木が、映画館に入る前と違って見えた。桜が散り、青く葉を茂らせ、また枯れて、満開の時期がもう何年も繰り返している。新興マンション群ができる前、もっと遠い過去の武蔵野の原野だった頃までもが同時に感じられるような感覚。
中沢新一の『アースダイバー』的な視点といったらいいか、あるいは不遜ながら、神的な視点。「いま、ここ」というのは、長い時間の「いま」の積み重ねによって「ここ」ができている、というような——普段とは違う認知を体験させてくれる映画だった。
事前の評価は、ロバート・ゼメキスの最新作としては考えられないほど低く、映画館も公開したばかりなのに空いていた。
それも、無理はない。この映画は、通常の映画や物語の文法を無視している。カメラ位置を固定し、その一つの視点から見えた数千年間の光景を編集する——これがおそらくゼメキスのアイデアの出発点だろう。そして、そのルール通りに、映画は徹底して作られている。
普通、映画とはカメラが主人公を追い続け、観客はその人物に感情移入して、共にヒヤヒヤし、何らかの達成を手に入れることでカタルシスを得る。
ところが本作は固定カメラだ。主要登場人物として、トム・ハンクスとロビン・ライトが演じる夫婦がいる。だが彼らも、いわゆる「主人公」らしくはない。20世紀を生きた、ごく普通の、真面目に、しかし流されるように生きた夫婦だ。特別なヒーロー的要素はない。
だからゼメキスの過去作の、『フォレスト・ガンプ』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のようなカタルシスを期待すると、それは得られない映画かもしれない。それがこの厳しい評価の理由なのかもしれない。
だが同時に、本作はそれら2作でも展開された、ゼメキスの時間への関心を、さらに先鋭的に形にした作品とも言える。
過去と未来、長い時間の積み重ねによって作られる運命のようなもの。それを今作では、「主人公視点」を極限までそぎ落とし、「時間そのもの」を主役に据えることで表現しようとしたのだろう。
通常の映画の文法を踏み外しているから、期待するカタルシスはない。その代わりに、全く異なる時間の流れを俯瞰するような視点を、観客に体験させてくれる作品になっている。
そしてその視点で人間の人生を眺めると、本当に短く儚い。ヒーローズ・ジャーニーのような輝かしい達成とは縁遠い、市井の一個人として生き、死んでいく。記憶されることもなく、大切な人とのつながりも儚く失われ、手元には何も残らない。
でも、そんな人生が儚くても、とても美しい営みであることを感じさせてくれる。
これは、ロバート・ゼメキスの超意欲的挑戦作だ。普通ではない映画体験をするために、ぜひ観てほしいと思った。僕もまた観るだろう。
memories of here
米国の劣等感をコントにして笑えないコメディ‼️❓
貴重な映像体験
驚くほど
スクリーンの使い方は新しい
アメリカ近代史をなぞりながら、同一アングルで時代時代の有り様を描い...
定点観測
あるアメリカの街の家族の出来事(過去から現在まで)を定点観測のように固定アングルで描く話。グラフィックノベルが原作らしく、コマ割りのようなカットがあり、挑戦的。
なんか評価は芳しく無いが、私は嫌いではないです。アメリカの良き時代の中流家庭が中心の話。特別な事は全く起きないが、各時代の家族の生と死、や普通の営みが淡々と描かれていて、なんだか愛おしくなりました。二時間ならだらけたかもしれないけど、90分が丁度良かったかも。
盛り上がりに欠けるとか、カメラアングルとかあるかもしれないが、私はそれはそれで今回の趣旨に合っていて良かったかなあ、と思う。
CGは若いトム・ハンクスになってる!すごい。それとポール・ベタニー父ちゃん好きです。
全103件中、61~80件目を表示