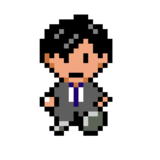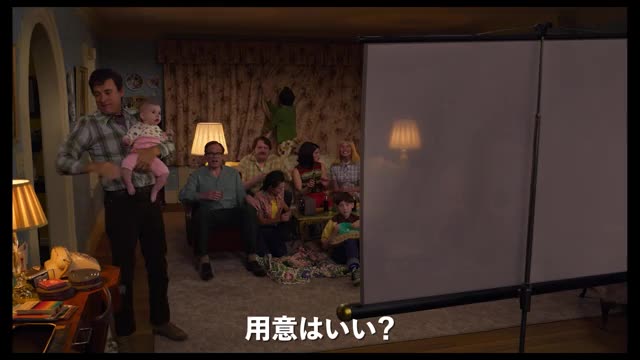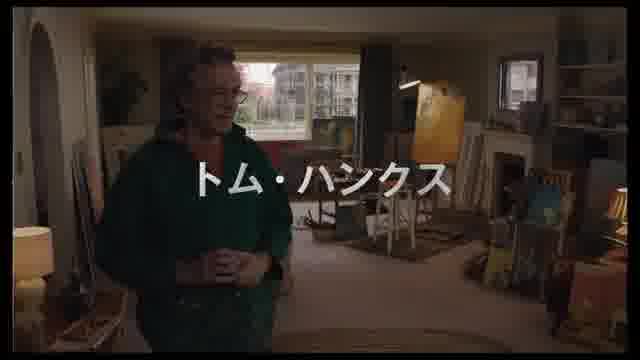HERE 時を越えてのレビュー・感想・評価
全140件中、1~20件目を表示
試みのオモシロさと、切っても切り離せない表現の限界
ゼメキスという監督は映像面でのチャレンジに常に意欲的で、映像的なギミックと物語のベストなバランスを追求しているところがある。ときにそのバランスは崩れてしまうのだが、それでもゼメキスが試みていることが刺激的だったり面白かったりする。
本作も、同じ構図のひとつの絵の中にさまざまな時代を織り込むという原作のスタイルを、いかに映像に落とし込むがゼメキスにとっての最優先事項であったのではないか。そしゼメキスは、ほぼ映画の全編を同ポジションの据え置きカメラ(あくまでも、というテイでやっているだけだが)に貫くという、諸刃の剣のようなことを敢えてやっている。
ひとつの定点から長いスパンの時間の流れと、そこに生きていた人たちの人生を映し出すというアプローチは珍しくはないが、ここまで徹底した例は非常にレアだと思う。その手法によって醸し出される情感や感慨は確かに立ち上ってくるのだが、同時に足かせになっていることも確かで、原作にはなかった家族のエモーショナルな物語を持ち込んだ以上、エモーションを減じてしまっているように思える箇所が多いことには首を傾げてしまった。
具体的に言うなら、やっぱりクローズアップもカメラ位置を変えることもできないもどかしさの方が、試みのおもしろさより大きいんだよなあ。俳優陣がいい芝居をしていればこそ、もっと芝居に集中したくなるんだよなあ。
PCのGUIと複数ウインドウから着想した1989年の原作漫画の前衛性は失われ、「ここ」に縛られる不自由さが残った
ロバート・ゼメキスは大成してからも開拓精神を失わない稀有な映画監督で、当代の最新技術を導入した映像で観客を驚かせ続けてきた。2019年日本公開作「マーウェン」の映画評を担当した際は、『「永遠に美しく…」「フォレスト・ガンプ 一期一会」で90年代ハリウッドのCG視覚効果による映像革命を、ジェームズ・キャメロンやスティーブン・スピルバーグとともに牽引したロバート・ゼメキス監督』と書いた。だが、興行的・批評的ともに成功した傑作群を高打率で世に送り出してきたスピルバーグとキャメロンに比べ、ゼメキスの場合はその実験精神が空回りして幅広い評価や支持を得られなかった作品も多い。残念ながら「HERE 時を越えて」も微妙な出来に留まっている。
原作は米国人漫画家リチャード・マグワイアが1989年に6ページの短編漫画として発表し、2014年には304ページのグラフィックノベルとして出版した「Here」。マグワイアはインタビューで、1980年代にMacintoshやウインドウズPCによって普及したGUI(グラフィック・ユーザー・インターフェイス)とマルチウインドウから、1つのコマの中に別の時代を映す小さな“窓”を描くことを着想したと語っていた。
GUIが普及する前はテキストベースのコマンドを打ち込んで処理を実行させるインターフェースだったから、マウスでファイルをつかんで別のフォルダに移動させるといった操作は直感的だったし、デスクトップ上にテキストを扱うウインドウや画像を表示するウインドウなどを複数同時に並べられるのも便利で画期的だった。1980年代にコンピュータの分野で起きていた革命を漫画表現に応用したという点で、マグワイアの「Here」は確かに当時前衛的だっただろう。
映画「HERE 時を越えて」も、マグワイアのコンセプトを踏襲し、全体のフレーム(親画面)の中に別の時代を映す小さな窓(子画面)を複数出現させ、子画面が伸長して親画面になるなどしてさまざまな時代を行ったり来たりする。カメラはほぼ全編で定点観測のスタイルにこだわり、キャラクターを別の角度からとらえることもなければ、クローズアップして表情に寄っていくこともない(俳優がカメラに近づいてアップになることはあるが)。
このスタイルにこだわった映像を観続けているうちに、映画鑑賞とは自分が同じ席(ここ)に座ってスクリーンを眺める行為だということを改めて思い知らされる気がしてきた。従来の映画、作品の世界に没入できるタイプの映画なら、自分の物理的な居場所から解き放たれ、カメラが移動したりカットでシーンが変わったりするたび、海でも山でも外国でも瞬時に移動した気分になれる。だが本作の、スクリーン上に展開するさまざまな時代の映像を定点から見続けるというスタイルが、いかに窮屈で不自由なことか。その意味で、作品世界に没入して今の居場所(さらに言えば“今の自分”)を忘れさせてくれる自由さがあるからこそ、映画鑑賞は素晴らしいのだということを、本作から反面教師のように教わった気がする。
あらゆる手法を経験し尽くしたゼメキスが挑む時空を超えた定点観察映画
私たちが暮らすこの場所、この住居はいかなる歴史を重ねて、いま現在へと至り、未来へと続いていくのか。一見、物語にも満たない取り止めもない視点に思えるが、すでにあらゆるタイプの映画を具現化済みなゼメキス監督にとってこれくらいのチャレンジングな切り口でないと挑む価値はないのだろう。とは言え、目の前に展開するのは「定点観察カメラ前で織りなされる、時代を超越した複数の登場人物の群像劇」という言葉でいくら説明しても伝わらないシロモノだ。万人受けするとは言い難い。中にはピンとこなかったり、つまらないと感じる人もいて当然。が、慣れ親しんだ不動産の売却や、新たな物件の購入などを経験した人にとっては他人事と言えない内容かと思う。時空を超えたり、CGだったり、実写との融合だったりと、ゼメキスならではの一つの映像内に同時共存する幾つもの要素のタペストリーを見つめつつ、今ここに立つ喜びを噛みしめたくなる一作である。
よく貫徹したな
ある存在からの目線
退屈な人生、それでも我々は生きていかなければならない
トムハンクス主演、ロバートゼメキス監督というフォレストガンプコンビの新作ということで、まあまあ映画の奇跡もりもりのほっこりファンタジーみせられるのかな、くらいで油断してたら、最後気がついたら泣いてました。
一見、気をてらったように見える映像や、歴史を飛び越えた様々な家族の悲喜交々、生と死や成長さえ、特段の意味を持たせず、観客に余計な感情を抱かせないように演出されており、これが退屈とさえ思わせる(ように作られていて)、びっくりするほど「何も起こらない」ことこそ、それが人生なんだと突きつけられます。
バックトゥザフューチャー、フォレストガンプのようなエンタメ性はあえて排除して、この作品を作ったゼメキス監督の凄みにしびれました。
これもまた、配信ではなく劇場で観ていただけますと最高の作品かと思います。
人々の移り変わりの儚さ、寂しさ…
カメラアングルの面白さ
原作小説があるとの事。このストーリーを映画化すると考えた時に、カメラを固定にするというこの発想がまず面白い。確かに同じ場所に住む何百年もの時を経て物語を紡ぐときに定点観測にするというのはいいアイディアでもあるが、カメラアングルの面白さやカット割り編集などの映画ならではの良さが損なわれてしまうのではないかと心配になるところ…が、そこはロバート・ゼメキス監督。定点観測ならではの良さを上手く作り、それはそれで見た事が無い映画になっていて面白い。ちゃんとこんな映画見た事なかったと思えるような作品になっている。そして、時間もちょうどいい塩梅で飽きずに最後まで楽しめる。
最後までみたらメッセージも見えてくるし、感動もした。そしてロバート・ゼメキスらしさも感じられる作品に仕上がっていた。
とても不思議な映画体験が出来て良かった1本🎥
自縄自縛か
普通なのに変で面白い
鉄拳のマンガみたい
定点カメラで歴史が変わるという内容を長編にしたのは評価できる。
家族の人間模様は切なかった。
●ただホームという概念でテーマを通すなら恐竜やインディアンは蛇足だと思える。
家が建ち始めたところから映画が始まって、ある家のその場所と移り変わる家族の喜怒哀楽に絞った方が良いように思えた。
●逆に言えば場所と歴史というテーマであったなら、恐竜やインディアン、建国などのエピソードが足りない。
地球史や人類史という視点で描くなら。
●内容が先読み出来てしまうのは残念だがそうでしかない。
もう少しウィットを考えるなら、日本で言えば柱のキズが誰かの身長、誰か前の住人の名前、塗りつぶしていたペンキが剥げて、歴史が見えるなど移り変わりの中でも連続する心情を描いてもいいと思った。
普遍のテーマを正面から描いていたのは良かった。
目が楽しい映画
その場所の歴史を描く事で表現されることは
定点カメラでその場所を映し続けている、というイメージだったが、実際には違う。題材となっている時期をそれぞれ行ったり来たりを繰り返す、つまり意図をもってこの場所の歴史の断片を、意味ある順序で描いていると感じた。それは完全に撮り手のセンス。押しつけがましくなく、切り取られた時間。話の散りばめ方をどのように決定して脚本を書かれたのか、不自然さもなく流れる組曲のような作品に仕上がっていて、制作者の力量に感心する。オムニバスでもない、これまで見たことがない、観客の想像力を穏やかに導く作品。
人生が詰まっとったー。 時空のスパン長すぎ?とも思ったけど 宇宙の...
あたたかく、さみしい
・100年くらいの歴史がありそうな家で暮らした家族模様の話だった。恐竜のいる時代からかいっと驚いたけど、確かに地面はずっと過去からあるんだよなと思った。冒頭から様々な時代のワイプと家庭がありましたという感じが泣きそうになった。カメラが固定で画面の変化がほとんどない状態を色々なワイプで時空を超えた演出で見飽きることがなくて凄かった。
・舞台となったような歴史が深い家ってどれぐらいあるんだろうと思った。多いのか、そんなにないのか。
・普通の家族が普通に暮らしている様子を撮りためたものを編集した映画みたいな感じだった。日常で起こる範囲のトラブルが続いていくのが、ドキュメントみたいに見えてきて実際にいるアメリカの家族の記録のような気もした。
・奥さんが始終、家を建てて出ようと言って拒絶した末に家を出ていった。その後、リチャードが後悔を懺悔するシーンがあった。動かなければ心配がなくなると思ったというのがぐっと来た。守るための行動で相手を傷つけている事が辛かった。
・発明家の夫婦が異常に明るくて面白かった。何となく、悪徳業者に騙されてるんじゃないかと思って観ていた。成功したのかどうかわからないままに終わった気がする。どうだったんだろう。墜落で亡くなったのかと思った父親がインフルエンザだったり、笑いの要素もあって良かった。
・家政婦の人が多分、コロナに感染して亡くなっていた。数十年してこの映画を観た時、においを感じなくなる病気って何?って思う人いるんだろうなっていう演出だったのでそう思った。
・黒人の青年が両親から警察に会った時の話を重々しく説明していて、考えたことがなかったけれど確かにそういう話をしっかりしておかないといけないんだなと思った。
・子供の誕生から団らんなどのシーンはとてもあたたかった。その後、子供が大きくなって病気や死別、離婚など年齢を重ねていけばいくほどさみしくなっていって、切なくなった。けれど、人生って感じがした。
発想は面白いんだけど
発想は面白く、最後は「じわっ」とした。
とはいえ、あっちにいったりこっちにいったりして、つながりを追うのが大変。
つながっていないところもあるし。
私だったら、時系列的に組み立てるけどなぁ。
確かにそこにいた
土地の神様目線
アメリカのある場所、そこに建てられた一軒の家とその土地に纏わる関わる人たちの営みを悠久の時を超えた定点視点で描いた壮大なドラマ。
完全な土地の神様目線でストーリは描かれる。レンガ建築物が標準的な社会かつ都市開発から取り残された地域が条件。土地が狭く災害が多い木造建築中心の日本において自宅の百年存続には奇跡的かつ相当な維持費用が掛かる。日本人に共感を得にくいテーマだ。日本なら土地の神様は、今頃駐車場かワンルームマンションの壁の中かとか妄想。
ストーリは「わが人生に悔いなし、ご苦労様」系、普通の家庭を描いたので、話の山も大した事はない。104分の尺を持たせたのは、監督及びチームの映画製作の技量の高さだろう。トム・ハンクスはインタビューで「真剣に遊んだ作品にはパワーがある」と、一理あるが一昔前なら膨大な手間が必要で、これを撮る熱量に感心するが、映像技術の発展が著しい現代で説得力は低く、パワーより編集の妙だけを感じた。
残念ながら共感も懐古も感じられなかったというのが正直なところ。
映画作りを極めたチームの遺言作になるかもしれない作品がこれで良いのですか、と上から目線にて失礼します。
全140件中、1~20件目を表示