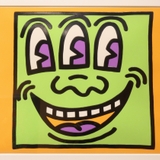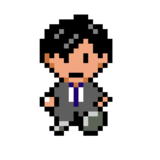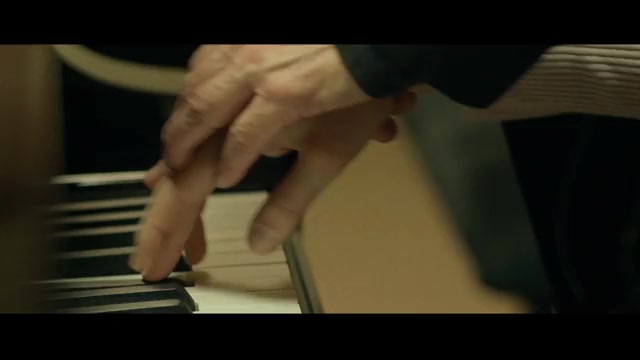ピアノフォルテのレビュー・感想・評価
全26件中、1~20件目を表示
エボニー・アンド・アイボリー
まずはクラシック音楽にうとい者の感想ということで、ご容赦願いたい。
肝心の演奏シーンが思いのほか少なかった。各人のエピソードが断片的にスケッチされ、時系列もあちこちして散漫な印象。指導者からの有形無形の圧力が尋常でなく、気が塞ぐ。
取材対象の6人は選考結果とは無関係に選ばれているので、競技者が絞られていく過程が、天下一武道会のような醍醐味に欠ける。特にどの人物にも思い入れは生まれず、淡々と見終わった。
個人的にはジャズピアノの方がずっと血が騒ぐので。
ドラマ仕立てのドキュメンタリー
不思議な感じはあったがドキュメンタリーでありながらカメラアングル、ショット、インサート、BGMなどはとても映画的。ドラマ的と言っても良い。友人が言っていたが緊張感を撮っているが緊張感は伝わって来ない・・そう言う撮り方なんだと。本来は観客に緊張感を伝えるように撮るのがドキュメンタリーなのだが、本作品は敢えてそうしたのか、意図せずそうなったのか、その本質は不明のままだが、良くも悪くもエンターテイメントになっている。きっと作者(監督)は映画として見られることを望んだのではないか?作者はキッと記録映画にはしたくなかったのであろう。それゆえ見せられるのは演奏の迫力(余り記憶に残らない・・キッとプロが見たらすごく印象に残るかもなのだが)ではなく、どろどろした師弟関係や、演者の天才せいではなくプレッシャーに押しつぶされそうな人間性など、音楽ドキュメンタリーとは違う方向にベクトルが持って行かれている。ちょっとフィギアスケートのリンクサイドを思い出してしまった。フォーカスされた6人にも何らかの意図が感じられたし、それによってこの『ショパンコンクール』なるものがある程度定義づけられた。楽器を生業とするもの、音楽を聴くだけのもの、この狭間にこの作品を成立させんとする意欲は強く感じた作品であった。
演奏よりも人となり?
2021年の第18回ショパンコンクールを追ったドキュメンタリー。
出場者の中から6人に焦点を当てて撮影。
コンクールは本来5年に一度ですが、2020年開催予定だったものがコロナ禍で1年延期。
マスクをしている人が画面に沢山映っているのはコロナの余韻を感じさせます。
ラプンツェルのような長い金髪が目立つエヴァ、中国の小皇帝といった感じのハオ・ラオ、ヨガ好きのアレックス、アレックスといつも一緒にいる気のいいレオノーラ、自然体でざっくばらんな語り口が魅力的なミシェル、カメラ映えを気にするマルティン、それぞれキャラが立っています。
ステージ上の演奏シーンは思ったより少なく、彼らのプライベート(実家でくつろぐ様子や練習風景、師匠との会話など)にカメラがかなり斬り込んでいたのが新鮮でした。
アスリートのようにジムで身体を鍛え、基礎練習を欠かさないエヴァの様子はいかにもロシアっぽい。師匠には絶対服従で、フィギュアスケートやバレエの世界と重なる。
中国のハオ・ラオの様子は対象的で、彼の教師はまるで母親のように世話を焼き、常に励ます。トイレに行かなくていいの?とか、着替えたら?などなど、見てるこちらが引いてしまうくらいかいがいしい。
アレックスとレオノーラは予選を勝ち抜くたびに祝杯をあげて楽しそう。(さすが陽気なイタリア人)
ミシェルはいちばん醒めていて、コンクールにチャレンジするのは経済的に安定するためだとバッサリ言い切る。ショパンコンクールだけが唯一、優勝者が名を残せるコンクールだと。
マルティンは容姿がショパンに似ていて(本人も意識している)、優勝する気満々で挑んでいたがまさかの途中棄権。ポーランド人だけに地元から期待されるプレッシャーに耐えかねたのでしょうか。そのあたりが深く突っ込まれなかったのがやや残念。
毎回審査に時間がかかるのもこのコンクールの特徴で、夜のステージでファイナルの協奏曲を弾き終えた後、数時間の協議を経て順位が決定。
長い待ち時間の間、ファイナリストたちが客席で写真撮影に興じる姿が一瞬映りましたが、普通の若者に見えて微笑ましかったです。
ここにたどり着くまでに並々ならぬ努力があり、プレッシャーに耐えてきたことが示された後の…ラストに幼少期のコンテスタント達がひたむきにピアノを弾く映像には涙。
ピアノコンクール好きも、そうでない方にもオススメしたいです。
ここから先はとあるピアノファンの戯言…↓
私は当時このコンクールをYouTubeの配信でほぼリアルタイムで視聴していましたが、界隈ではとある日本人出場者の話題で持ちきりで純粋に楽しめなかった記憶があります。
その日本人ピアニストが人気なのは演奏が魅力的なのはもちろんですが、SNS等で彼らの人となりがよく知られているということが大きい。
今作の6人も、このような舞台裏を知って演奏を聴くのと、知らないで聴くのではかなり印象が異なるだろうなと思ってしまいました。
私は(当時は何とも思わなかった)エヴァとハオ・ラオにすっかり感情移入してしまい、結果を知っているのにも関わらず彼らが入賞できなかったことにがっかりしてしまいました。
ドキュメンタリー、どこを切り取ってどう編集するかで見ている人の印象を操作できる、なかなか恐ろしい代物ですね。
今作は誰か特定の人物や組織に肩入れするでもなく、比較的公平な目線で撮られてはいましたが。
プロジェクトなんちゃら、や情○大陸のようなアゲアゲドキュメンタリーは眉唾モノだなと改めて思いました。
ハオのせんせい👍
音楽版「ひゃくえむ。」
10月3日の1次予選から、ファイナル発表の10月20日(日本時間2...
10月3日の1次予選から、ファイナル発表の10月20日(日本時間21日早朝)まで、ショパン・コンクールは、すべてオンラインで公開されているので、フルに見た。
三次予選まで現地ワルシャワの劇場に通い、帰国便の機内で映画『ピアノフォルテ』を観て、思い返して再びワルシャワに戻ってファイナルまで見届けた——そんなYouTuberの話を聞き、上映館を探して超スモール館の港南台シネサロンへ。
本作は、前回(4年前)のショパン・コンクールを予備予選からFinalまでの数人にフォーカスしたドキュメンタリー。前回2位入賞の反田 恭平と4位の小林 愛実(今は夫婦!)も一瞬映り込む。
予定調和だと感じる人もいるだろうが、そもそも予定調和になり得ないコンペティションの過程を追うカメラの眼は終始やさしく、勝敗や物語化に踏み込みすぎない。
上映館を探して観に行く価値はあると思う。
※現時点では配信は未だ無い(はず)。
ピアニッシモとフォルテッシモの間のどこか。
ちょうど一昨日に第19回ショパン国際ピアノコンクールが終わった。入賞者ならびにファイナリストは下記の通り。
1位 エリック・ルー(アメリカ)
2位 ケヴィン・チェン(カナダ)
3位 ワン・ズトン(中国)
4位 桑原志織(日本)
4位 ティエンヤオ・リュー(中国)
5位 ヴィンセント・オン(マレーシア)
5位 ピョートル・アレクセヴィッチ(ポーランド)
6位 ウィリアム・ヤン(アメリカ)
F 遠藤美優(日本)
F デヴィッド・フリクリ(ジョージア)
F ティエンヨウ・リ(中国)
2回連続のファイナリストはいなかったわけである。遠藤さんは前回は本選には進めず、でも今回はファイナリストになった。立派である(この映画でも予選のポスターにちらりと顔が出ている)
映画の話をすると、ショパンコンクールのドキュメンタリーというと審査員側や運営側も取り上げて、と考えがちだが、本作品は出場者だけ。清々しいほどシンプルな作りである。
ただ、早く脱落する人、本戦手前まで進む人、本戦に行く人、それぞれを取材できていて映画が成り立つわけで、全員本戦に行けませんでしたでは困る。トータル何人追いかけていたのか分からないけど、うち4人は本戦に進んだわけで、なかなかの目利きといっても良いかもしれない。(マルティンが棄権したのは想定外だったみたいだけど)
もちろん、ドキュメンタリーなのであまり意図的な筋はつくっていないけど、なんとなく、エヴァとラオを対比するような構造になっているような気はする。
この二人は17歳で同い年。かたやモスクワ音楽院所属のばちばちロシアピアニズムの継承者という感じなのに対して、一方はごく普通の高校生で団地の台所の脇に置いてあるアップライトピアノで練習していたりする。
ロシアピアニズムのメソッドでいうと、正しい音というものはピアニッシモとフォルテッシモの間の何処かに「必ず」存在する。それを厳しいマンツーマンのコーチングで身につければ表現だの情念だのもついてくる。ところが、今や、YouTubeなんかで良い演奏は共有される時代となった。それがこの映画でいうとラオ・ハオの善戦に表れているということなのだろう。
ちなみに先行レビューにある「ピアノフォルテ」というタイトルは勝者を表す、という解釈だが少し違う。fとPには別に上下関係はない(技術的には全く違うものだか)ピアノフォルテは大きな音を出せるようになった近代ピアノをそれまでのピアノと区別するため付いた名称である。わざわざこの名称をタイトルにしたのは1台でオーケストラに匹敵するデカい音を出せるこの楽器を弾きこなし、たくさんの聴衆(YouTubeで12万人!)を魅了する全能感がタイトルに込められているから。
作品の時点から五年たった。今回のコンクールではファイナリストは2名を除きすべて東洋系が占める結果となった。中国でのピアノ人口は3000万人という。時代は変わったということなのだろう。
「ピアノフォルテ」の意味
・ショパン国際ピアノコンクールのドキュメンタリー
・参加者に密着して、予選から本戦までを追う
・小説「蜂蜜と遠雷」を彷彿とさせる
・お国柄により、コンクールへの向き合い方が違うのが面白い
・ロシアのエヴァはスパルタ教育を受ける
・中国のハオは家庭的
・その他の出場者からも希望と葛藤が入り混じるコンクール独特の雰囲気が伝わってくる
・勝者と敗者のコントラストも残酷
・てっきり扱いが厚かったエヴァかハオが優勝するのかと思ったら、両名とも本戦で入賞すらできなかったのは驚き。
・それなら2位になった反田恭平を追っかけて欲しかったと思うのは日本人だからw
・多分、監督は敗者に焦点を当てたかったのだろう。結果として勝者になった参加者も追いかけてたはず
・題名の「ピアノフォルテ」は、強い音(フォルテ)も弱い音(ピアノ)も出せるピアノの本来の名前。勝者と敗者を意味していると思われる
・出場者の織りなすリアルな物語に感動したのは、それぞれが全身全霊を打ち込んでいる真実の物語だったから。これはスポーツでもピアノでも同じ
根性なしの自分には刺さる
最近ちょっとクラシックの公演に行きだした初心者です
もう最初の一音からスゲ~、って思ったけどこのコンクールに出る人はみんなこのスゲ~をやってるんですよね…スゲ~…
私も好きこそものの上手なれ、な仕事をしてますが、頂点を目指すとか、高みを目指す努力ができない人なので、この毎日の鍛錬にはほんと感服しかありません…
レビュー読んでるとちょこちょこ出てくる不満事項についてですが、
カナダの優勝者含めスペインや日本の入選者は個人的な映像使用拒否だったんでしょうね
You Tubeなどで演奏やインタビューは見られるので、別にこの映画でそこに不満を持つことはないのではないかな
ほぼロシアと中国のティーンエイジャーの二人がメインなんだけど、見事に正反対なのが興味深かった
いやーロシアの先生、めっちゃ怖い!どっかもっと褒めてあげて!って泣きたくなるくらいダメ出ししかしない…
中国の男の子は先生とほっこりほのぼの可愛かった
ポーランドの子は開催国だしプレッシャーに押しつぶされちゃったのか、猫とのやりとりが可愛かったので残念だったけど、これからも止めずに弾き続けてるといいな
名前も出てこなかったけど、予選通過せずも帰国前に空港のピアノ弾いちゃう子とか、ミスったー!って反省会してる子とかもね
そしてイタリア勢は三人三様だけどそれぞれ演奏が大好きなのが伝わってきて和んだ
見終わって映画館出る手前に2位のアレクサンダーの日本公演のチラシが!
彼はほんとに1人独特だったので、行ってしまおうかしら
そして現在進行系の今年のショパンコンクールの予選結果(10/133次通過)に、アジア系の台頭すげーな、とええー?!という気持ちになりました!
文句なし!ここまでショパン国際ピアノコンクールの舞台裏を密着するとは
文句なし!素晴らしかった。5年に1度ショパンの出身国ポーランドのワルシャワで開催されるショパン国際ピアノコンクールを若きピアニストに密着したドキュメントだが、よくぞここまで密着した内容。予選〜最終日まで舞台裏を知る事ができて観ごたえがあった。彼らのピアノへの想いがスクリーンから物凄く伝わった。もう一度観たくなるドキュメント。今、ちょうどショパン国際ピアノコンクールがポーランドで開催中。観ごたえがありおすすめします。
それぞれの正念場。誰と、どのように迎えるのか?
5年に一度開催される、ショパン国際ピアノコンクール。その出場者6人を追ったドキュメンタリーである。
プレッシャーに押し潰されそうになりながらも、ファイナリストだけが演奏できるコンチェルトでは、みんな自分の音楽に没入して、気持ちよさそうだった。
指導者の在り方も様々で、スパルタ式、お母さん型、冷静型、など多種多様。
どれがベストかはわからないが、それぞれ一定の結果を出してきたということは、その人に合った指導法なのだろう。
ショパンコンクールで独特なのは、ピアノのブランドが選べること。
2021年に1位のブルース・リウが話題となり、CDを取り寄せて、演奏を聞いたことがある。音がキラキラしていて、「2位の音とは全然違う、さすがだ」と感心していたのだが、どうやらFAZIOLIのおかげでもあるようだ。
反田恭平と同率2位のアレクサンダー・ガジェヴは、Sigeru KAWAIという、KAWAIの最高級ピアノを選んでいた。自分に合っていて、しかもコンクール映えする楽器の選択も、勝利の鍵を握る要素の一つだろう。
最後に、6人の子どもころの映像(栴檀は双葉より芳し?)と、その後の情報が流れたのは、興味深かった。
感動した
ショパン国際ピアノコンクール
5年に一度の世界大会、日本人が入賞したとかニュースで聞く。
2021年大会のコンクールの予選、2次予選、3次予選、本選とどんどん絞られていく過程を、何人かのピアニストを追ったドキュメンタリーなだけに、すごい緊張感も伝わって感動した。
あれだけの努力とプレッシャーの中、幼い頃からずっと時間を費やして練習しても本番で実力が発揮できるとは限らず、まだ17才の子が出ているのを見ると親の気持ちになって力が入ってしまう。
この年は2位に日本人の反田さんが入られたけど、予選から本選まで追っていなくて残念。
どのピアノで演奏するかを選ぶ際に優勝候補の方が「KAWAIがいい」って言ってくれたら、なんか日本人として嬉しい。
5年に一度だけど、まだまだ次がある。頑張って!って応援したくなる映画でした。
今開催のショパンコンクールも楽しみ
ちょっと断片的な編集だけど青春群像で登場する若者らとショパンコンクールに親しみが湧きます。反田さんら日本の方の演奏シーンが無いのは残念でしたが。ラストの出演者の幼少フィルムがエモかった。
知らない世界を知れたのは良かったが
ショパンの出身国ポーランドの首都ワルシャワで、5年に1度開催されてるショパン国際ピアノコンクールは、出場するだけで名誉なことで、入賞すればその後の成功が約束されるため、世界中の若きピアニストたちがその頂点を目指している。
本作では、反田恭平さんと小林愛実さんという2人の日本人が入賞を果たした2021年・第18回大会の一次予選、二次予選、三次予選、本線の全4回、21日間の舞台裏を追い、コロナ禍で1年延期となった大会に臨む6人の出場者を取材。ポーランドのマルチン、ロシアのエヴァ、中国のハオ、イタリアのアレックス、レオノーラ、ミシェルなど6人が、それぞれ葛藤や苦悩を抱えながら競技に挑む姿を、映し出したドキュメンタリー。
予備審査を通過した87人が一次予選に挑み、46人が二次予選に進み、23人が三次予選へ、そして12人が本線へと、予選の都度約半分が振り落とされる過酷な大会だったことがわかった。
なぜ87人の中からこの6人が選ばれたのかはわからないが、取材拒否した人ももちろん居たのだろうと思う。
現に、反田恭平さんや小林愛実さんの取材は行われてないし、演奏風景さえ映らなかった。
本戦の結果発表は12人の中からまず5位の発表があり、4位、3位、2位、優勝者まで順番に発表された。小林愛実さんは4位になったのに表彰式の映像にも映らず、これは意図的に拒否されたんだろうと思えた。どんな様子だったか見たかったのに残念だった。
ポーランド人マルチンの途中棄権には驚いた。体調不良と言ってたが、プレッシャーが半端ないのだろうと感じた。
ハオの先生が2000年の大会に挑戦しようとしてたのに諦めた話が現実的だった。それくらい厳しいものなのだということなのだろう。
ロシアのエヴァの先生はケチをつけてばかり。フィギュアスケートやバレエでもそうだったが、多くの生徒の中から教えてやってるんだという態度がロシアの教師の伝統なのかも。凄く感じ悪かった。エヴァは17歳と若くて綺麗なのに笑顔がなくて顔が怖かった。
本線には進めなかったが、ミシェルが楽しそうで良かった。
ただし、優勝者ブルース・リウ、2位の反田さんの演奏がどんなだったのか作品の中で紹介しても良いのでは、と思ったし、全く聴けなかったのは残念だった。
16歳から30歳までがこのコンクールの参加資格らしく、パオとエヴァは2025の大会にも挑戦するようなので、今年の大会の様子もフォローしてみようと思う。
【”若き野心の努力の過程と耐圧と結果。”今作は優勝すればピアニストの道が拓けるショパン国際ピアノコンクール出場者達の姿を追った”さあ、明日から頑張ろう!”と言う気持ちになるドキュメンタリーである。】
ー 今作では、世界最高峰のショパン国際ピアノコンクールの若き出場者達数名の、一次、二次、最終選考会に挑む姿と共に、出番が来るまでの焦燥、苛立ち、自信喪失、無理やりの過剰な自信過多で自らを鼓舞する姿が、映し出されていく。ー
■特に印象的なのは、
1.ロシアの40以上の表彰実績がある、メンタルがタフそうな、けれども指導者の高齢女性の叱咤が物凄いエヴァである。
プレッシャーに強い筈の彼女が最後に流した涙は、幼い頃から努力を重ねて来た者にしか流せない、貴重なモノだと思うのである。
2.ポーランドのイケメン青年、マルティンが耐圧の為か体調を崩し、棄権するシーンは”辛いだろうな”と思いながら観ていたのだが、エンドロールのテロップを観て救われたな。
3.我が道を行くイタリア人のアレックスが一番、冷静に大会に臨んでいたように見えたな。
4.中国人のハオは、失礼ながら大きな団地に住んでいて、経済的には恵まれていない感があったが、ショパン国際ピアノコンクールには出れなかった母の強い支えの元、頑張る姿からは、元気を貰ったな。
<彼らの演奏を聴く、多くの聴衆たちが涙を拭いながら観ているシーンも、彼らの未来を拓くために懸命にピアノを弾く姿から出るオーラに触発されたモノである事は間違いがないであろう。
今作は優勝すればピアニストの道が拓けるショパン国際ピアノコンクール出場者達の姿を追った”さあ、明日から頑張ろう!”と言う気持ちになるドキュメンタリーなのである。>
ショパン国際ピアノコンクールという名の戦場
「ピアノフォルテ」角川シネマ有楽町で鑑賞した。2週前に観たBrian Enoのドキュメンタリー”Eno”上映前にみた予告映像が忘れられずに観たが、見て良かった作品。
世界的ピアニストを輩出してきた、世界最古で最高峰の舞台、ショパン国際ピアノコンクールに挑む若きピアニストたちに迫ったドキュメンタリー映画。
ショパン国際ピアノコンクールとは、ポーランドの首都ワルシャワで、5年に1度開催される大会で、審査は1次から本選まで全4回、21日間にわたって行われる模様を時系列順に追う構成。出場するだけで名誉なだけでなく、入賞すればその後の成功が約束されるコンクールであり2021年のコンクールを題材にした作品。
これは結構ヒリヒリした肌触りの感触であり、一人ひとりの人間模様、生き様、こだわり等々が生々しく画面に滲み出てくるリアリティ。コンクールという名の戦場、闘いでは勝者はたった1人という現実。
とてつもない緊張に負けてしまう者もいれば、その緊張を力に変えて真の実力を発揮できるものだけが生き残れる生存競争。クラシック音楽の世界も本当に大変…。
イタリア出身で眼鏡の天才肌風のアレックスが、「コンクールなんて誰も望んでない。音楽で競うなんて」の言葉が心に残る。個人的には全員優勝🏆で良いと思うが、甲乙がつけられないほど熾烈な競争は本当に切ない…。
ロシア出身の17歳のエヴァはブロンドの長い髪と美貌と煌めく才能を持ってても、コンクールでは優勝できず、ひっそりトイレで泣くシーンは辛過ぎる。
「カメラの前で泣いたら駄目よ!」と注意するコーチの女性も印象的。(この女性コーチがめっちゃ厳しかったね…)
エンドロールで流れる、コンクール出場者たちの幼少時のピアノ発表会の映像も彼らの輝かしい未来を予見される。その街や国でトップレベルだったはずの才能が、ワルシャワでぶつかり合い、そしてそのほとんどが砕け散るのは見てて辛かった。
好きで始めた音楽🎵なのに、決して終わりのない辛い練習、厳しい評価、評判を乗り越えながら突き進む音楽人生、ピアニストという生き方は幸せなのだろうか。
世界はYAMAHA音楽教室に気づいてない🎹
2021年のショパンコンクールのドキュメンタリー。
5年に一回のピアノのオリンピックなので、この映画の次が2025年10月3日から始まったので、映画のあと5年後の結果をまさに今、競ってるってことで、こちらの結果も楽しめるのかなと思います。
感想としては、まあ想像以上でも想像以下でもなかった。カメラが追うのは90名弱のうち、6人。ロシア女子と中国男子がともに17歳で指導法など対象的。
この大会に出てくるレベルで、もうピアノ演奏においては神に近いレベルと思うが、結局のところ、神経伝達と筋肉の反射の話で、反復して脳にも身体にも覚えさせることしかないんだということがよくわかる。
でもそうやって積み上げた精密な機械のような演奏は、17歳の寝癖がとれないような男の子が弾いたとしても、コンクールの観客としてくるような音楽にうるさいおじいさんに近い年齢の人にも泣くほどの感動を与える。
日本人の視点からは、出場者が自分のピアノを選ぶシーンで、スタンウェイなどの銘器にまじって、ヤマハ、カワイが候補に入ってることが印象に残った。
物足りなかったのは、あれだけの日本人が本選に進出してることを描かないこと。勝手な推測だが、このクラスに出てくる日本人の演奏家のほとんどが幼児期にYAMAHA音楽教室を通ってるのではないかと思う。実際、YAMAHA音楽教室は、クラシックのみならず、ポップス、ジャズなどジャンルを超えて、音楽でメシを食えるようになるという、世界に稀にみる音楽カリキュラムを実践している。
そろそろ世界がYAMAHAのすごさに気がつくんじゃないか?日本の小学校教育、高校野球のドキュメンタリーを撮った山崎エマ監督がショパンコンクールのドキュメンタリーを撮ったのを観てみたい。
今年は84名の予選出場者のうち、日本からの参加者は13名。結果が楽しみだ。
鳥肌が立つ演奏が何回も
自分が知らない世界を体験できるというのも映画の良さだと思う。
この映画でも大いにそのような体験ができた。
21日間、緊張を保ち続けなければならない過酷さ、直前になって棄権する気持ち、このコンクールだけに生活のすべてを捧げて来たにも関わらず、入賞できなかった落胆。
平々凡々の人生を歩んでいる自分にも僅かではあるが、その気持ちがいかばかりであるか、わかる。
実際には想像の数億倍の精神的ダメージがあるに違いない。
芸術というのは、良くも悪くも数値化できない部分を含んでいる。
だからこそ、スポーツのオリンピックよりも過酷だとも感じる。
制作の仕方に影響されているのか、ハオ君に肩入れしてしまう自分がいる。
音楽というのは、音の正確さとか、人生の経験値が醸し出す表現力とかを超えたその人しか紡ぎ出せない音色みたいなものがあって、私はそこに惹かれる。
彼にはそれがあるような気がする。
全26件中、1~20件目を表示