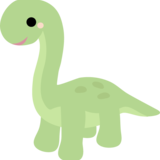ノー・アザー・ランド 故郷は他にないのレビュー・感想・評価
全108件中、21~40件目を表示
恐怖に駆られているのはどちらか。
映像を観ていると、恐怖に駆られているのは、パレスチナの人々ではなく、軍や武装した入植者の方であることがよくわかる。自分たちのしていることは国際法違反であることを自覚し、人道上の後ろめたさもあるからこそ、武力や詭弁のような国内法を盾に、破壊活動や言論統制を進めて、時には実際に発砲もするのだ。
本当に哀れなのはどちらか。
ガザ侵攻前のイスラエルのパレスチナへの戦争犯罪については、アジアンドキュメンタリーズの「ガザ 自由への闘い」が無料で視聴できるので、ぜひこちらもご覧いただきたい。
単品購入という形にはなるが、そのサイトには、「医学生ガザへ行く」もある。在りし日の美しいガザの街並みと、そこに暮らす人々が、当たり前だが、とても人間らしく生きている様子が伝わってくる。
パレスチナで、恐怖に駆られた狂信者たちの被害に遭っているのは、単なる数ではなく、固有名詞を持った一人一人の人間であることを忘れないようにしたいと強く思った。
そして、どちらの国家や民族を支持するとか、右だ左だという二者択一に陥ることなく、真に公正公平と社会正義が実現する世界の方向を見据え、自分のできることをしたい。
【”シオニズムの壁は越えられないのか!”ヨルダン川西岸のパレスチナ人居住地区の青年が、イスラエル人青年と共にイスラエル軍により破壊されて行く故郷の姿を4年に渡り記録した値千金のドキュメンタリー作品。】
■2019年。バゼルが暮らすヨルダン川西岸のパレスチナ人民居住区に、イスラエル軍が軍事訓練施設建設を口実に、パレスチナ人私有地をブルドーザーで破壊し始める。
激しく抵抗するパレスチナ人達だが、銃を持つイスラエル軍に家を壊され、洞窟に家財一式を持って避難する。
バゼルはその様子をスマホで撮影し、ネットで配信する。その状況を知りイスラエル人ジャーナリスト、ユーバールがやって来て、取材や編集に協力するのである。パレスチナ人の一部から非難されつつも。
彼らの抗議の声やイスラエル軍の非人道的な行為は世界に発信されるが、イスラエル軍の破壊行動は過激になって行き、家だけではなく学校を壊し、ナント生命線の井戸までコンクリートで塗り固めるのである。人道違反である事は、明らかである。
◆感想
・このドキュメンタリー映画の価値は、イスラエル軍の非人道的な蛮行を世界に知らしめた事と、制作にイスラエル人が加わっている事である事は、論を待たない。
彼らの行為は、正に命懸けで世界にパレスチナ人居住区で何が起きているのかを伝えたモノであり、そこにはシオニズム、反シオニズムの壁はない。微かなる希望がそこから感じられるのである。
・それにしても、イスラエルのネタニエフ達政治家は且つて、ユダヤの民がナチスドイツにされた非道なることを忘れたのであろうか。この映画で描かれている事は、且つてユダヤの民がナチスドイツにされた事を、そのままアラブの民にしている事だからである。
現代社会に蔓延る全体主義、自国ファースト思想の浸透であろうか。住民一人に発砲するイスラエル軍の姿と、息子を銃撃され下半身不随になった事を嘆く母の姿が哀しい。
・映画の中では、バゼルとユーバールの会話も映される。バゼルは”法学の学位を取ったのに、イスラエルの建設現場の仕事しかない。”と嘆く。又、ユーバールは”パレスチナ人の自由なしに我々の安全はない。”と言う名言をさり気無く口にするシーンも映される。先見性の或るユーバールや、登場しないが共同監督をしたラヘル・ショールの様な思想を持つ政治家を、イスラエル政府の要衝ポストに置いてくれないかな。良識あるイスラエル人に是非とも行動を起こして貰いたいモノである。ご存じのように、イスラエル人の中には、ネタ二エフの行為を批判している人が多数居る事は、信用できる新聞が報じている。
それで思い出したが、共同監督のハムダン・パラルが暴行され、イスラエル軍に一時拘束されたニュースが流れた時はイスラエルもそこまで堕ちたか、と思ったが解放されて良かったよ。
・けれども、ユーバールの”パレスチナ人の自由なしに我々の安全はない。”という言葉が現実になった23年10月のイスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃には、暗澹たる気持ちになった事を想い出す。
序に言えば、自分に有利な情報のみ真に受けて、衝動的に発言、行動するアメリカのオレンジ色の顔の、頭が空っぽの男は少し黙っていて欲しいのだけどな。事態を悪化させているだけなのだから。
<千年以上続く宗教問題が根底にあるので、そう簡単には解決しなだろう事は十二分に分かってはいるのだが、ユダヤの民もアラブの民も、シオニズム、反シオニズムの壁を越えての融和を模索する気はないのだろうか。
”怒りは怒りを来す。”と言う言葉を知っているのだろうか、と思ってしまった作品である。
だが、この作品は、命の危険がある中で製作、公開した若い世代の4人の映像作家兼活動家の存在に微かなる希望を感じさせてくれる作品でもあると私は思うのであり、そこにこの作品の値千金の価値があると思うのである。
何時か、全てのユダヤの民とアラブの民が、今作のバゼルとユーバールのような関係になる事を望むモノである。>
<2025年4月6日 刈谷日劇にて観賞>
今後はどこの国でも同様のことが起こる可能性がある
Wikipediaでマサーフェル・ヤッタを調べると現地の言葉で「何もない」というのが地名の由来だそうだ。そんな何もない土地でも古くから人が住んで生活している。逆に、軍や入植者は何もない土地に何を期待して追い出そうとするのだろう。と思っていたら、土地目当てではなく、単にそこに住む人たちの生活を破壊するのが目的だったという。ひどい話。
パレスチナ人とイスラエル人、2人ずつの共同監督のドキュメンタリー。家屋をブルドーザで押しつぶすイスラエル軍の軍人たちはサングラスで表情が見えないが、どんな心境だったのだろう。やめてくれと懇願するパレスチナ人に向けて、カメラの前でも平気で発砲するのも衝撃だ。理解できない。撮る方にイスラエル人が入っているのなら、軍側のコメントも欲しかった。
しかし、どんな事情があろうとも、子供たちの眼前で小学校の建物を破壊する道理はないだろう。
追い出された住民たちはどこへ行くのだろう。都市部へ移住させ、今度はその都市丸ごと別の理由をつけて爆撃するつもりでは、とガザの惨状を見て考えてしまう。
自分の生まれた故郷は忘れられないものだよね。そうだろ?
逞しく、勇気溢れる姿に感動
21世紀の現代においても、
はるか昔の植民地と変わらず、
武力で先住者を追い出し、土地を強奪することが
日常的に繰り返されている現実に対して、
そしてテクノロジーは著しく進歩しても、
人間自身がまったく進歩していないことに対して、暗澹たる気持ちになった。
仮に古代の歴史とか、法律とか追い出す側に何か理由があるにしても、
長く同じ地に住み、平和に暮らし家族の歴史を紡ぎあげてきた先住者に対して
敬意をもって近しい目線、態度で接することが人としての最低限だと思うが、
そうできないのは、差別とか偏見とかが根底にあるんだろうなと想像する。
頻繁に武器を目の前に突きつけられる不安に晒される日々でも、
ひたすら悲観的に落ち込むことなく、
家族みんなの集まる食卓には、会話に笑いもあるし、
厳しい現実に悩みながらも、将来や家族について思いを馳せる
若者の強く逞しい姿にはほんとうに勇気づけられ、救われる思いがした。
命をかけて現実を伝え、そして様々に考える機会を与えてくれたことに感謝。
不法入植という「絶望」の実態
本作は、中東の地で続くパレスチナ問題を映し出したドキュメンタリーである。ユダヤ人とパレスチナ人が共同で制作し、ユダヤ人の中にもパレスチナ人への仕打ちに憤る人々がいることがわかる。映像は淡々と事実を映し出し、視聴者に直接的な説明を与えず、感じ取ることを求めている。
◇土地収用の実態
ヨルダン川西岸における入植地の接収は国連決議に反し、国際法にも違反している。正式な国家として成立していない状況を利用し、パレスチナ人の土地が奪われ続けている。映画では、住民の抵抗に対する発砲、住居の破壊、井戸の封鎖、夜間の家宅捜索など、数々の暴挙が映し出される。
◇ユダヤ人ジャーナリストとパレスチナ人
パレスチナ人コミュニティに溶け込み、事実を伝え続けるユダヤ人ジャーナリストの存在が印象的である。彼は軍や入植者の行動に立ち向かいながらも、パレスチナ人と友情を築いていく。彼らの関係は、映画の中で唯一希望を感じさせる瞬間である。
◇日常の抑圧
ガザ地区のみならず、西岸地区においても、パレスチナ人の日常は制限されている。経済活動や移動の自由が奪われ、監視と圧力が続く。入植地の拡大により、土地を失った人々が強制的に移住させられる現実も描かれている。
◇移民政策と入植者
中東の地では、移民の受け入れが積極的に行われている。近年のロシア・ウクライナからの移民増加により、さらに多くの土地が奪われている現実がある。土地を追われるパレスチナ人の苦悩が、この映画を通じて浮き彫りになる。
◇長期化する闘争は子孫が継承
パレスチナ人は、世代を超えて土地を守るための闘争を続けている。短期的な抵抗が無力であっても、彼らは長期戦を覚悟している。怒りと悲しみを抱えながらも、土地への愛着を胸に、未来への希望をつなぎ続けている。
本作は、単なる過去の記録ではなく、今もなお続く現実を映し出している。パレスチナ人の声に耳を傾け、抑圧の歴史を記憶し続けることが、我々に求められているのかもしれない。
両方の歴史をいちから学ぶ必要がある
ただただ胸が痛む
私達日本人に、この作品に星をつける権利があるのだろうか
正義とは、一体何?
人間が持つ、根本的な矛盾を目の当たりにする。
遠い海の向こうの事は関係無いと思ってる日本人が観るべき作品。
本年のアカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した本作。
紛争中のガザ地区の話では無いが、この作品の舞台はガザ地区よりはまだ良いと言われている“ヨルダン川西岸地区”のドキュメンタリー。同じ“人間”がかくも非人道的な事を行なっているのかと思うと胸が張り裂ける。
そこに人権などない。
そして、海の向こうの出来事に、ほとんど触れる事も無い日本の報道機関やジャーナリズム、毎日使うスマホの情報は人々の思考にあわせた都合の良い情報ばかり。
知らぬ間に、何者かに支配されている我々に“民主主義”の“正義”を語る資格はあるのだろうか?
ヨルダン川西岸地区という通り、川の対岸はヨルダン王国。中東は「危険」という先入観があるかもしれないが、ヨルダンは比較的安全な国と言われている。外務省の渡航危険レベルでは“1”十分注意となっているが、エジプトやモロッコもレベル“1”、地域によってはより危険な地区もあり、中東の中では比較的治安は良いとされている。実際10年ほど前に映画「インディージョーンズ」でも有名なペトラ遺跡に行きたくてガイドブックを購入したが、「とても治安が良い。一般家庭に鍵が付いていない家も多く、道に迷ったらどこからともなく人が集まって、あーだこーだと教えてくれる」なんて嘘か本当かわからない様な情報が載っていた。
そんな、ヨルダンの対岸に位置するパレスチナ人の土地。
Wikipedia(適切な出典では無い)には、ユダヤ人入植地について「イスラエル入植地はアラブ人を追放する事を目的とした物ではなく、実際に行ってもいない。また、入植地はヨルダン川西岸地区の3%程度の面積である」と発表しているそうだが、そんな方便が嘘八百な事は容易に想像できる。
何故イスラエルの人々はそんな非人道的な事をするんだろう、何故?
日本人がイスラエルに“イメージ”するのは、恐らく“ユダヤ人”の国、そして“ユダヤ人”と言えば、第二次世界大戦で抑圧と虐殺をされた民族、そう思うのは私だけでは無いと思う。
しかし、この作品に登場するイスラエル兵士や入植者達の姿にはそんなイメージは結び付かない、彼らの行為は全く共感できないし、何故この様な事をするのか、理解もできない。
海の向こうにいる日本人には、まるでウクライナで非人道的なジェノサイドを行なっているロシア人兵士と同じに見える。
そして、そんな非人道的な行為を支援しているのが“アメリカ”だという事もわかっている。
何故「力による現状変更」を、日本の民主主義同盟国でもあるアメリカが支援するのか?
正義とは何なのかがわからなくなる。
日本国憲法第十四条
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
法治国家における“法”とは、公正で公平な社会を築く基礎であり、国民の自由と権利を守る民主主義の根幹だ。
ただ、法律にも矛盾が無い訳では無い。
人を殺す事は“悪い事”、「そんな事は当たり前」と思うだろうが、戦争で“敵”兵士を殺す事はある意味“良い事”英雄視される事だってあり得る。
昨年公開された映画「オッペンハイマー」に映し出された原子力爆弾をとってみても、日本人にとっては“悪”な存在だが、アメリカ人にとっては“善”な存在だ。
21世紀になっても、世界のどこかで殺戮が繰り返されている。「人を殺してはいけない」という“概念”は、決して人間の本能では無いのだ。
そんな、人間の中に当たり前の様にまかり通っている“矛盾”を、改めて痛感させられた。
今日ドラッグストアでチョコレートを買おうとして躊躇した。有名メーカーの手頃で美味しいチョコレート。
以前、カカオ原産国の農場で、人身売買で買われた子供がカカオ農場で働かされていることが問題になった。そして、我々が身近に享受しているささやかな喜びも、遠い目の見えないところでは全く違う真実があるのかもしれないと初めて知った。
原産国の児童労働は未だ改善されていない。
日本の有名メーカーの、子供等を笑顔にさせるお菓子、なのにそのお菓子の向こうに何があるのか、なんて考えて買う事も無いだろう。
我々には知らない事が沢山ある。目の前に見えている事が全てではない。
ただ大切なことはある。
それは、“真実を見極める”事。
断片的でもよい、常に事実を見つめそれらの行為が人類にとって正しい事なのか、正しくない事なのか。
その先にある真実とはなんなのか。
人間が“真実”とはなんなのか見つめる事を放棄した時、人間は滅びのカウントダウンを始めるかもしれない。
この95分の映像の“事実に”触れる事は、真実に辿り着くための重要な一歩かもしれない。
3月26日BBCの報道で、映画「ノー・アザー・ランド」の共同監督でパレスチナ人のハムダーン・バラールさんが、イスラエル人入植者に暴行された後に軍に連行され消息不明になっていた。と報道があった。米アカデミー賞でオスカーを掲げていたのがついこの間なのに、
ヨルダン川西岸の入植地の警察署で「恣意的に」拘束され、イスラエル兵から暴行を受けた、イスラエル人入植者たちが村を襲撃したとき、入植者たちはバラールさんの頭を「サッカーボールのように」蹴った、軍に拘束された後も目隠しをされ、イスラエルの兵士らが交代で見張りに来るたびにバラールさんを蹴ったり棒で殴ったりしたとの証言もAP通信に述べている。
日本の地上波報道機関でこのニュースに触れているニュースは聞いたことが無い。残念ながらそれが事実。
“真実”がどこにあるのか、この95分のドキュメンタリー映像を、その目で見て、確かめて欲しい。
パレスチナ人の不満はわかるが・・・
破壊される故郷を撮影するパレスチナ人青年が2019年夏から2023年10月までの4年間にわたり動画を記録したドキュメンタリー。
ヨルダン川西岸マサーフェル・ヤッタで生まれ育ったバーセル・アドラーは、イスラエル軍による占領が進む故郷の様子を幼い頃から撮影し、世界へ向けて発信してきた。次第にイスラエル軍の破壊行為は過激さを増し、ガザのハマスが2023年10月にイスラエルへ攻撃した事により、ヨルダン川西岸のマザーフェル・ヤッタにも影響があり、撮影が続けられなくなった、という話。
不条理な占領行為というのはパレスチナ人からみた言い分であり、1900年から住んでいたと言ってたが、紀元前10世紀頃にはその地に古代イスラエルが有ったのだし、1948年の現イスラエル建国によりユダヤ人はやっと約束の地に戻って来れた訳で、その後も領土を巡る争いは続き現在に至る、という事だろう。
ユダヤ人は約束の地を追われ、現イスラエル建国まで長い間住む所を持てなかったのだから、いつから住んでいた、というのも言い出したらどこまで遡るのか、と収拾がつかない気がする。
不法占拠と言えば、日本の北方領土を今だに占領し続けてるソ連からのロシアや、今もウクライナで酷い事をしてる同じくロシアなんて、あんなもんじゃない。
マリウポリの20日間、などはもっと悲惨だった。
住民を無差別に殺し、人々を車に積んで自国の別の場所に運び、強制労働させ、抗議が有ったら釈放と称して送り返す。
そんな事に比べたらまだゆるい感じがした。
生まれた土地を離れたく無いという気持ちは良く伝わったが、もっと酷い侵略者は他にいくらでもいると思う。
嘆くだけでは、、、
あまりの現実に理解が追いつかない。
アカデミー賞をはじめ世界中で高く評価されても、パレスチナの状況は悪化するばかりだ。長年、多くの人が声を上げ、今日も世界中でデモが行われている。それでも現実は変わらない。イスラエルの正義を語る声はほとんど聞かれないのに、この事態が容認され続けていることに違和感を覚える。
同時に、イスラエルの安全保障への脅威や、一部の過激なパレスチナ人によるテロ行為が状況をさらに悪化させている現実もある。暴力の応酬が、和平への道を遠ざけている。
映画を観ても、「パレスチナ人は迫害されているよな」という記憶だけが残り、私たちは今日も日常を生きている。
世界中が怒っている。けれど、その怒りは現実を動かさない。
この映画の称賛が、免罪符になってはいけない。
自分もまた、「分かったつもり」になっていないか――そんな問いが残る。
解決には、構造そのものを問い直す必要がある。
それでも、信頼される指導者が現れ、国家としてのビジョンを描けたなら――そこに希望はある。
国家とは象徴ではない。経済、防衛、統治、外交。現実的なビジョンと、それを導くリーダーシップが不可欠なのだと思う。
見捨ててないよ
学校をブルドーザーで壊し、発電機を奪い、取り返そうとした人を撃ち、井戸を埋め、大工道具も奪い…。
イスラエルや入植者の酷さはSNSでよく知っていたので驚きはなかった。SNSだと入植者の子供までもがパレスチナ人を迫害していて怒りがわく。
あんな風に簡単に人が撃たれ、誰も罰せられない世界があるなんて。それが同じ現代に起きてる。
バーゼルとユバルにいつしか芽生える友情めいたもの。パレスチナ人とイスラエル人、立場の違いが浮き彫りになる。交わされる言葉、沈黙。
時には怒りが抑えられなくなって、バーセルが無口になるシーンもあった。いつか自由に行き来できるようになればとユバルに言われても、バーセルはうまく思い描くことができないようだった。
ユバルがアラビア語を覚えたことでいろいろなことを知ったと言っていたので、ヘブライ語だと情報に偏りがあるのだろう。それにしても、イスラエル兵や入植者はどんな気持ちであんな酷いことをしているのか、そちらのインタビューもあってもよかったかも。聞くに耐えない言葉だとしても。
私からみると、パレスチナ人もイスラエル人も見た目では見分けはつかない。よく似ているように思う。彼らが破壊し、追い立てているものはなんなのだろうか?恐れは何も生まないのだと思う。
希望があるとすれば、今日の映画館にたくさんの人がいたこと、このドキュメンタリーがアカデミー賞をとったこと。世界は見捨ててないよと伝えたい。
70年以上にわたるイスラエルの侵略とパレスチナの苦難を多くの人に知ってもらえたらと思う。どっちもどっちではないし、暴力の連鎖ではない。イスラエルによる侵略とパレスチナによる抵抗なのだと。
世界平和は永遠に来ないのか
映画を観たばかりで起きた、この映画のパレスチナ人監督へのイスラエル兵による暴行、拘束と釈放のニュース。
イスラエルパレスチナ問題は複雑過ぎて意見する事はできないが、仕事で毎日イスラエル製機会を動かし、あちらのエンジニアもたまに来日来社してくれるが、そんなイスラエルに対する俺の感想は「理解できない」。分からないとしか言えない国。
映画は西岸地区でのイスラエル兵によるパレスチナ人迫害を克明に映し出して行く。
平日にも関わらず、都内の映画館は満席に近かったが、日本人がパレスチナ問題に関心を寄せるのは正直難しい。
イスラエルの後ろには西側諸国、パレスチナの後ろにはアラブ諸国、ロシア、中国がいる。この対立が第三次世界大戦につながれば世界が滅びる。その可能性は決して低くない。
今必見の一本
こんな現実があるなんて
日本人でパレスチナの現状を積極的に学ぼうとしない人にとっては
パレスチナで起きていることはイスラム国やアルカイダのように、テロとの戦いだと思ってしまうかもしれない。
だが、それは違う。
これはイスラエルという国家による、パレスチナ市民への侵略なのだ。
入植者のにやにや笑いには本当に背筋が凍る思いだ。
自分の立場が上だと感じると、人はこんなにも残酷になれる。
昔から暮らしていた場所で、勝手に法律が作られ、家や小学校が破壊される。
そんな不正義が現実にあるなんて、とても信じたくない。
遥か遠くに住んでいる私たちでさえそう思うのに、当事者たちの絶望感はどれだけ深いのか。
それこそがイスラエル政府の狙うところなのだろう。
だが、重要なことは、私たちが唱えなければならないのは反ユダヤ主義ではなく、
反イスラエルであるということである。
監督の一人はユダヤ人であり、イスラエル政府の不正義に反対を表明しているのだ。
森を見て木を見た気になってはいけない。
再現映像なのか実際の映像なのか判断が難しい部分がある。
正直、淡々と進むので集中できない場面もあった。
自分の甘っちょろさを恥じ入るばかりである。
絶望感フルだけど…
マサーフェル・ヤッタの普通の人々
圧倒的な非対称性
イスラエルとパレスチナ、民法と軍法、重機と取り壊される家、武器と丸腰のデモ、どこにでも行けるユヴァルと西岸に閉じ込められたバーセル、スクリーンのこちらと向こう、この圧倒的な非対称性に打ちのめされた。
軍時訓練=社会防衛という名の下に、国家がマイノリティの住居を破壊する。(それは映画内で明かされていたように、マイノリティを弱らせる事こそが真の目的)
このあからさまなレイシズムに対するパレスチナ人の命がけの抗議を、ルールだから、法律で認められているからとニヤニヤしながら踏みにじるシオニストたち。
差別ではなく区別、法律を守っているだけと言いながら、反差別規範をかいくぐってマイノリティを痛めつけるこの行為は、沖縄の基地問題など、世界各地の植民地主義的な場所で共通に行われている。
デモでもスタンディングでも署名でもBDSでも、何かしら自分にできる植民地主義に抗う行動を起こす事でしか、この映画に刻みつけられた凄まじい胸糞の悪さを解消することはできない。
全108件中、21~40件目を表示