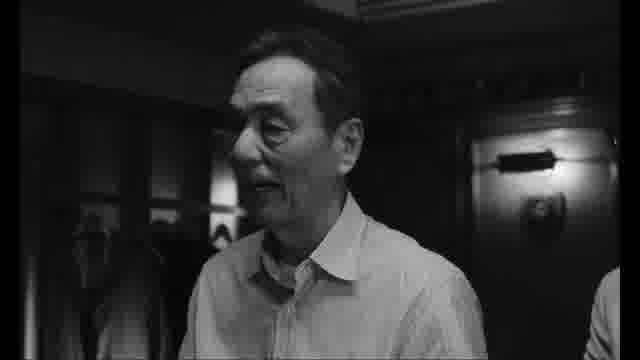敵のレビュー・感想・評価
全102件中、1~20件目を表示
「敵」は誰ものもとにもやってくる
儀助が見た敵とは何だったのか?
老いそのものか、または穏やかな老いを妨げる何かか。
映画化を知ってから原作を読んだが、「これ、どうやって映画にするんだろう?」というのが正直な感想だった。
まず、前半は儀助の日常描写、というより生活習慣の説明が、微に入り細に入りなされる。食事のこと、知己や親族のこと、家の間取り、預貯金、性欲、体調、野菜、諸々。映画と違って会話劇ではなくほとんど儀助のモノローグで、ひとつのテーマにつき7〜8ページの分量の章立てで淡白な日記のような文章が延々と続く。
確かに儀助という老人の解像度は4Kレベルに高まるのだが、話がわかりやすく動かない。ちょうど中盤にある「敵」の章あたりからようやく起伏が出てくるが、幻と現実のあわいをさまようように物語は展開してゆく。
この分じゃ映画はとっつきにくい仕上がりなのかな、という不安がよぎったが、意外と見やすかった。
原作で言葉を尽くして説明されていた儀助の生活上のこだわりが、ほぼ映像表現に置き換えられたことで随分すっきりした。言葉がなくても原作に近い印象が伝わってくるところは映像の力だ。
序盤の、丁寧に暮らす儀助の淡々とした日常描写は「PERFECT DAYS」を思わせる心地よいリズムがある(ただし生活費は全然違っていて、原作によれば儀助はこだわりや習慣のために毎月40〜50万出費している)。彼の食べる朝昼の食事がどれも美味しそう。
演じた長塚京三は儀助に近い79歳、パリのソルボンヌ大学で学んだ経歴を持つ。181cmの長身で、足が長くすらりとした立ち姿がインテリ設定に合う。儀助ははまり役ではないだろうか。
そんな彼が2回目の内視鏡検査(の妄想)で縛られて四つん這いになり、そのお尻に内視鏡カメラがちゅちゅっと吸い込まれるシーンは笑ってしまった。その後度々現れる妄想シーンも、いい塩梅のユーモアがあって楽しい。
そんなユーモアの向こうに透けて見えるのは、一見理性と知見で余生を御しているように見える儀助の人間臭い部分、あえて不穏当な言葉で言えば無様な部分だ。
彼はフランス近代演劇史の教授という経歴からくるインテリらしいプライドを持つ反面、自分を慕う教え子靖子に性的妄想を抱いたり、バーで出会った歩美に易々と金を渡したりと俗っぽい煩悩も捨てきれずにいる。普段はプライドによって抑え込まれている煩悩が、彼の妄想の中で顕在化する。筒井康隆によると、この妄想は認知症など病的なものではなく、あくまで儀助が"夢と妄想の人"であることに依るのだそうだ。
妄想に現れる亡き妻や現世の人々とのやり取りは、儀助の秘めた願望や後悔なのだろう。妻との入浴や、「フランス旅行に行けばよかった」という後悔の告白。終電までの時間で靖子を抱こうとするのも心のどこかにあった欲望だ。
旅行雑誌への寄稿を打ち切った出版社の社員犬丸の妄想での扱いは散々だ。打ち切り通告の席で、儀助のフランス語の返しを理解しなかった犬丸を、彼は内心嫌悪したのだろう。妄想の中で寄稿の継続を依頼しにきた犬丸は、鍋の肉を食べ尽くす傍若無人な人間として振る舞う。そして終いには儀助の知性を理解する靖子に殴り殺され、椛島の掘った井戸に放り込まれる(笑)。
そんな儀助も、最後は隣家の臭いおじさんと通りすがりの犬(名前がバルザック笑)の飼い主と共に、見えない「敵」に撃ち殺される。ここ以降は映画オリジナルで、ちょっとホラーチックなラストカットが秀逸。
筒井康隆は映画化にあたって、64歳の時に原作小説を書いたことについて「年をとるのが怖かったからでしょうね」とコメントしている。
その怖さの源を想像してみる。取り返しのつかない後悔を抱えることか。社会での役割を失ってゆくことか。年の功で日常をコントロールしつつ穏やかな余生を過ごしたいのに、不如意な欲望から逃れられないことか。
結局誰にとっても、現世の煩いや執着を手放して穏やかな死を迎えることは、かなりハードルの高いことなのだろう。物語中盤で病床に伏した湯島も、妻の前では寝たふりをしつつ、「敵」の影に恐怖しながら死んでいった。
今際の際まで惑い続け、意のままにならないものを抱えたまま終わってゆくのが大半の人間の人生なのかもしれない。
それがむしろ当たり前なのだと思っていっそ受け入れれば、死に方に対するハードルが少しだけ下がるような気がする。結局は、今を生きることに集中するしかない。
筒井御大のように理性的に恐怖と向き合う勇気のない私は、そのように開き直ってみたりする。
77歳の元大学教授に襲いかかる敵の正体は幻覚か、それとも。。。
妻に先立たれた77歳の元大学教授の儀助が、東京都内の山手にある古い日本家屋で慎ましく、日々のルーティンを守りながら暮らしている。とは言え、彼が焼く魚は美味そうだし、たてるコーヒーの香りがこちら側にも届きそうだ。何より、彼は枯れていない。時折訪れる教え子に密かな欲望を抱いたりしている。
ある日、儀助のパソコンに突然"敵がやってくる"というメッセージが届いて以来、彼の意識は一気に混濁していく。それは現実か、幻か。そして、敵襲来以前の日常はどうだったのか。儀助の混乱はそのまま観客にも伝染し、多くの人が感じる老醜の残酷という聞いたような結末に収まらない、衝撃のラストへと突き進んでいく。それは、筒井康隆の原作にもなかった映画オリジナルのアイディアだとか。観客を混乱させて、さらに異次元へと誘い込む脚本と演出に思わず息を呑んだ。
筒井原作に綴られた儀助の人物像はユーモラスで、やたら男性性器や性欲にまつわる記述が登場する。77歳でそんな?と思うわけだが、映画ではそんな主人公を長塚京三が演じることで、さもありなんと思わせる。何しろ長塚=儀助はエロくてかっこよくて、知的なのだ。気がつくと女性に覆い被さっているような、前のめりで痩せた身体にも妙な危うさがあり、それさえ魅力になっている。観ていて疑問に感じたところを後で誰かと話なくなる、対話に飢えた新春のシネフィル向き。
レビューが多くて驚く
孤独な老後にこれまでの行いややってこなかった事が自身を苛んでくるのかしら、本人と世間とのギャップにこんなに振り回されて…なんともな哀愁。
正直よくわからなかったけど共感される方が沢山いるって事が怖いねぇ
我々一人一人にも迫る“敵”
長塚京三氏を久々に見た気がする。
以前は映画にドラマ引っ張りだこだったが、近年はお歳を召して仕事量をセーブしているのか、露出が少なくなった印象。
本作は12年ぶりの主演映画。個人的に映画で最後に見掛けて印象的だったのは2014年の『ぼくたちの家族』。
ちょいちょい出てはいるが、この名優も静かにフェードアウトかなと思ったら、今年80歳になって自身の代表作やハマり役と言っていい作品に巡り会うとは…。
長塚氏が以前インタビューで語ったという“人生100年時代”。
本当に人生まだまだ先、何があるか分からない。
元大学教授で、フランス文学を教えていた儀助77歳。
長塚氏も昔、パリ留学の経験あり。吉田大八監督も当て書きしたという。
職は10年前にリタイア。祖父の代から続く古い日本家屋で隠居生活。妻には20年前に先立たれ、子供はおらず、一人暮らし。
職はリタイアしたが、時々講演や出版社から依頼された執筆を。
毎日決まった時間に起き、質素な食事や晩酌をし、パソコンに向かって依頼された原稿を書き…。買い物や日々使う文具もこだわり、徹底管理。毎日の営みやルーティンは『PERFECT DAYS』の平山さんのよう。
たまに数少ない友人や教え子が訪ねてくる。行きつけのバーに飲みに行ったり、自宅で手料理を振る舞ったり。
自由気ままな一人暮らし。ちょっと憧れる。
見るからに真面目そうな儀助。そんなイメージも長塚氏にぴったり。
性格も生き方も高潔かと思いきや、案外そうでもない。
近所で犬のフンでトラブル。途端に体臭を気にし、身体を洗う。
時折訪ねてくる教え子の靖子。大学在籍時から親交あり。美人で、最近離婚したという靖子。堅物に見えて、ちょっと下心ありの儀助。妄想の中で靖子と…。まあ、無理もない。夏、ランチやディナー、お酒も入って…。その相手が瀧内公美なら、男なら誰だってドキマギするって! それにしても本当に魅力的な女優さん。映画などではシリアス&クールな印象だが、たまにバラエティーに出ると明るくケラケラと笑い、そのギャップに萌えてもうた…。
行きつけのバーで、マスターの姪の歩美と知り合う。大学生でフランス文学専攻。フランス文学についての話やアドバイスはとにかく、若い娘(ブレイク&フレッシュの河合優実)と会うのが楽しみに。学費で困っている歩美。儀助は貯金を彼女に。それ以来歩美と音信不通に。まあ、そういう事。
身体は老いてもまだまだ気持ちはあり。それ故自分の愚かな部分も露見。悲哀やユーモアもあり、これも長塚氏のイメージに合う。
ショックではあるが、騙された事に不思議と腹が立たない。
なるべくしてなり、末路が早まっただけ。
端から長生きなど考えてもいない儀助。
貯金と一日使ったお金を計算し、後どのくらいで底を尽きるか。尽きる直前になったら葬式代くらい残して、自死を決めている。
遺言も書いてある。
騙し取られたのは自分の不甲斐なさ。そういう運命。“その時”が早まっただけだ。
さて、いよいよ自死しようとした時…
いや、ヘンな予兆は少し前からあった。
一通のメール。送り主は“敵”。
“敵”が来る。
ネット上でも“敵”についてあれこれと。
“敵”は日本に近付いている。
“敵”は南の方からやって来る。
“敵”はすでにもう来ている。あなたの近くにまで…。
何かの悪質メール…? 比喩…? デマ…?
何故かこれが妙に気になる儀助。
それからというもの、儀助の完璧だった生活が崩れ、次々奇妙な事が…。
靖子から誘い。ハッと気付いて起きると一人ベットの上。
病床の友人。ハッと気付くと…同じ。
近所でまた犬のフンのトラブル。何処からか飛んで来る銃弾。ハッと気付くと…同じ。
死んだ筈の妻が…。ハッと気付くと同じだが、これだけは夢でもこのままでいたかった。
妻、靖子、新担当編集のあり得ないシチュエーションで夕食。
これが現実ではないのは分かる。なのに、どれも妙にリアリティーがある。
どれが幻想か、どれが現か。何処から幻想だったのか、今現なのか。
端から儀助の妄想だったのかもしれない。
その狭間が曖昧…を通り越して、分からなくなってくる。
儀助の深層心理か、何の迷宮か、そもそもが分からなくなってくる。
それを印象的にする白黒映像。見る者を惑わし引き込む幻想的でありながら、美しい。
吉田大八の演出は、日常、ユーモア、シュール、サスペンス、哲学的などを織り交ぜバラエティー豊か。フィルモグラフィーの中でも異色作ながらしっかりと自分の作品に。『桐島、部活やめるってよ』『紙の月』などと並び、ベスト演出の一本。
長塚京三のハマり名演は言うまでもなく。今年の主演男優賞は吉沢亮で決まり!…と思ったが、大ベテランが立ち塞がる。
筒井康隆の同名小説が原作。幻想とリアリズム、哲学やナンセンスなど幅広いSF作家の御大の一人。
本作もいずれのジャンルにハマる。難解ではあるが、全く分からない/つまらない/飽きる事はなく、不思議と引き込まれた。
その一つに、“敵”の考察。
“敵”とは何だったのか…?
劇中では明確に描かれてはいない。
見る側が解釈。人それぞれ見方があると思う。
私的にはまず、死や老いと感じた。それは間違いなく込められているだろう。
平和ボケの日本に迫る危機警鐘。“北の方”だからあの国か、戦争の火種か。
コロナなどまた新たな未知の脅威かもしれない。
ひょっとしたらもっと個人の内面やパーソナルな事かも。年甲斐もない欲求や思い上がりや醜態への戒め。
“敵”ははっきりとしたライバル存在ではなく、何かのメタファー。答えはない。だから考察のしがいがあり、それがなかなか面白くもあった。
儀助は死去。
遺言に従って家や遺した書物などの事で関係者や唯一の親族の甥が集う。
物置で双眼鏡を見つける甥。覗いて家の方を見ると…
儀助の姿が。
ほんの一瞬だが、遠方を見渡している儀助。
亡き今もこの家に留まり、迫り来る“敵”に対しているのか、迎えようとしているのか、警鐘しようとしているのか。
我々の近くに、人それぞれの“敵”が迫り、或いはもう来ているのかもしれない。
最恐のホラー映画
「敵」が支配する世界にとって、私こそが「敵」
施設に入っている父に会うのは半年ぶりだった。
半年前とそれほど変わらぬ見た目に安堵するも、すぐにその感情は畏怖となり、落胆へと変わっていった。
目の前に座っている父の穏やかな立ち振る舞いとは正反対に、つぶらな目は泳ぎ続け、誰かに助けを求めているように見えた。
きっと父が施設の外の人に会うのも半年ぶりなのだろう。
彼にとって日常に存在するのは、施設のスタッフだけであり、目の前に座る私は初めて会う見知らぬ人でしかないのだろう。
「敵」の侵食によって父は世界から排除され、施設に入ることで自分の人生を「立ち止まらせる」ことを強要された。
半年が経ち、「敵」に支配された父から見た私は、残念ながら「敵」でしかないのだろう。
穏やかな性格のおかげで敵意を剥き出しにされないだけ喜ぶべきか。
与えられたわずか15分という短い面会時間が永遠に感じて、途中から息苦しくなっていった。
15分を待たずに、私たちは面会を終え、父は施設のスタッフの介護で自分の部屋へと戻っていった。
スタッフの姿を見つけた時の父の安堵の表情を見た私は、非常に複雑な思いを抱えたまま、スタッフに一礼してその場を去った。
この静かな施設の中は「敵」が支配していた。
この中では、私自体が彼らにとっての「敵」なのだ。
筒井康隆さん原作の映画「敵」。
これまでに、「時をかける少女」や「パプリカ」「七瀬ふたたび」など、数多く映像化されてきた筒井康隆作品の印象はエンタテインメント性の高いSF小説。
しかし、この作品は少し趣が異なる。
原作の発行は1998年。
作者はおそらく還暦後に書きまとめ、断筆解除後に単行本として発表された。
主人公・渡辺儀助は75歳。
大学教授を辞して10年、悠々自適の余生を過ごす教養人。
フランス文学研究の権威として、時折依頼のある講演や稀にある執筆依頼の他は、規則正しい生活を重ね、誰もが羨む丁寧な暮らしを続けていた。
講演依頼を受ける基準は「謝礼が10万円である」ということ。
それ以下ならもっとオファーがあるはずだが、自分を安売りしないというポリシーで10万円以下なら即断りを入れる姿勢を崩さない。
三度の食事を大切にし、手間をかけて旬を盛り込んだ自分のためだけの食事を作る。
食後に挽き立ての豆で淹れた美味いコーヒーをゆっくりと飲み、夕食にはそれなりに贅沢な赤ワインをじっくりと嗜む。
人生の折り返しを過ぎた大人の男性から見れば、きっと憧れの老後生活の最上級のモデルケースのひとつだろう。
この映画を見るまでは。
自ら「立ち止まる」と決めた時、「敵」は静かに近づいてくる
人生を賭けて研究し続けたフランス文学への造詣によって、主人公・儀助はフランス文学の権威となり、大学教授にまでのぼりつめた。
そこでは自分を尊敬する弟子たちが常に集い、自分の一挙手一投足に賞賛の声が湧き、憧憬の眼差しが途切れることはなかった。
中には、引退した今でも彼を慕い、老人の一人暮らしの庵を訪ねる教え子たちもいた。
恩返しの思いで彼に執筆を依頼し続ける出版社勤めの教え子もいた。
けれど、かつて大学の教壇に立って熱弁を振るっていた頃の賑わいは、もう自分を囲むことはない。
恩返しの気持ちだけでは、大学教授の視点が抜けきらない原稿を畑違いの雑誌に掲載し続ける熱は続かない。
周囲は生き続けていた。動き続けていた。
しかし、儀助だけが動きを止め、過去に生きていた。
そして、そのことに彼だけが気づいていなかった。
生きるために変わり続け、動き続けている周囲の人たちの流れの中で、「立ち止まる」と決めた主人公だけが交わることなく、自然と傍に追いやられていった。
私たちにとっての「敵」は、果たして本当の「敵」なのか?
「敵」とは何か?
それは「立ち止まる」と決めた人を襲う「孤独」という名の疎外感。
「自分らしく生きる」と決めた者に訪れる「世の中から忘れられる」という喪失感。
「自分は変わっていない」にもかかわらず、周囲の反応がどんどん変わっていくことへの苛立ちや怒り。
ただ立ち止まっているだけなのに、どんどん世の中から取り残されていく驚きや違和感。
教え子たちが慕っていたのは、じつは自分個人ではなく、「大学教授」という肩書きや地位の方だったということに気づけたとしても、もう「敵」は心身を蝕んでしまったあと。
主人公が見ている日常は、現実世界のものなのか、彼の夢想・妄想なのか。
「敵」に侵食されてしまった後では、それを判別すべは本人でさえもう持ち得ない。
「敵」とは何か?
少なくとも、「敵」となりうるものが誰の心の中にも潜んでいるということは間違いない。
私に微笑むあの人は、本当に実在するのだろうか?
主人公・儀助は、自ら進んで「立ち止まる」ことを選択した。
本人はそう考えていたが、実際は流れ続ける社会から弾き出されただけだった。
そのことに気づいた時、儀助は遺書を書き、自死を選ぼうとする。
しかし、「敵」に完全に支配された状態では、もう自らの意思で何かを選択し、実行することさえ難しい。
今生きているのか、夢の中なのかさえ、本人には判別ができないのだから。
彼は妄想の中を生き、妄想の中で死ぬ。
この映画を見た50代以上は、きっと映画の中の光景にリアリティを感じ、恐怖に慄くはずだ。
果たして今、自分が感じていることは現実なのか? 妄想なのか?
親しくしてくれている友人は実在するのか?
いつも愛想を振りまいてくれる行きつけの喫茶店のバイトの子は、本当は自分に向けて笑ってなどいないのではないか?
毎年届く年賀状は、ただ機械的に郵送されているだけではないか?
届くメールは全て「敵」からのメッセージなのではないか?
父を介護するスタッフは、とても親切で優しい人に見えた。
父が住む「立ち止まった」世界でも、同じように見えているといいなと心から願った。
老いる…ということ
…おもしろい視点で見られる
妻に先立たれ一人で暮らす
真面目で几帳面な元大学教授の日常
全編モノクロ
料理は彩りは無いのですが
美味しそうに食べる姿や
食べる音で美味しさがわかる
食後豆から挽いた珈琲で
充実したひとときを楽しむ
途中から"敵"の存在が何度も出てくる
はじめはよく分からなかった
一人で暮らす生活で
老いからの"孤独"や"寂しさ"から
現実だと思っていた事が夢だったと
…可笑しな夢を見る
何度も何度も(最後の頃は悪夢)
現実かのような夢
記憶が遡っているかのような夢
最後は母の胎内にいるかの様な戦中の夢
季節は夏から冬の出来事
春になったらまた皆と会いたい
と最期のことばが切なく聞こえる
相続は従兄弟の槙男に託される
託された槙男は双眼鏡で伯父の姿を…
そして槙男の姿はない
ラストの意味がわからなかった
ミステリ(謎)な感じで終わる
所々笑える所もあり面白しろさもある
長塚京三さんをあてがきされた様な作品
リアルな感じが素晴らしい
他のキャストの皆さんもとてもよかった
目を覆いたくなる前半のプライドと痩せ我慢の痛々しさ。なぜか愛らしい後半の暴走ダメ爺さんぶり。
久しぶりに見る長塚京三。
落ち窪んだ目元、深くなった目尻の皺、
伸びきった喉元のシルエットは、すっかり老人のものだ。
モノクロ映像の深い陰影が、それを際立たせる。
「私、部長の背中見てるの好きなんです」
部下の女性の言葉に小躍りしていた
サントリーオールドのCMの長塚京三は
はるか遠い日のものだ。
仕事は遠のき、人付き合いも限られていくのに、
ブライトは高く、食欲も性欲もまだまだある。
人生の残高を計算しては心細くなるのに、
後輩に説教がましく人生の閉じ方を語ったりしてしまう。
ひとり自分のために美食をつくっては、
女性に振る舞って褒められる自分を妄想している。
しかし妄想は妄想。現実は変わり映えしない。
ひときわ強めの効果音が、老いの現実を容赦なく刻みつけていく。
この映画を観るひと(つまりぼく)が、
老いへの不穏な気配を感じていれば(つまりぼく)、
映画の前半は思い当たることばかり(つまりぼく)だ。
物語は動き出す。
元教授の大好きな(ぼくも好きだ)可愛い子ちゃんとの
甘い日々はガラガラと音を立てて崩れる。
自分を教授に引き戻してくれる教え子たちとのささやかな現実も、
妄想がじわじわと染みこんできて暴走し始める。
振り回され、混乱し、慌てたり、怖がったり、謝ったり。
だがしかし、教授はなぜか遥かに生き生きとしている。
何度も推敲した遺言書は、最後は万年筆で清書だ。
自分らしい知性に溢れている。
敵との戦いに自ら飛び込んで、最期を迎えたそのあとは、
懐かしいみんなと会える。
さあ、ぼくの遺書を聞いてくれ。
よくできてるだろ?
長塚さんは、前半のカッコ良いところが、痛々しくて見ていられず、
後半のカッコ悪いところが、人間的でいいやつっぽくて、よかった。
自分はどう老いたいのか、考えずにはいられなかった。
死ぬときはあんな感じ
長塚京三、瀧内公美、黒沢あすか、河合優実、すばらしい。
あと何年という計算をするところが、身につまされます。
なくなる時は、たぶん、現実と夢が混在してきて、わからなくなっていくのだと思い至り、あんな感じで死んでいくんだなという、身につまされる映画でした。
老いとは自身を構成しているものがどんどんほどけていく過程
事前の情報で何となくイメージが出来ていたけど、大体そのとおりの映画でした。
長塚京三さんは77歳になったのですね。
この映画では老体を色々と出している。裸体とか。
ヒロイン的な女性が3人。亡くなった妻の黒沢あすかさん、教え子の瀧内公美さん、知り合った仏文学生の河合優実さん。
瀧内さんは、とても良い。
河合さんは、ハマり役だとは思う。
老いとは、自分自身を構成しているものが、どんどんとほどけていく過程なり、ということを再認識しました。
そういう事を書ける筒井康隆さんは、やっぱり凄いです。
「敵」とは
元大学教授の渡辺儀助は連れ合いを亡くしてすでに二十年。一人暮らしがすっかり板についていて家事全般をそつなくこなしている。特に料理へのこだわりが強く毎度食卓に並べられる食事は充実していた。
悠々自適な暮らし、年金と少しばかりの原稿料で食いつないでいるが食と酒にはこだわりがあり摂生をする気もなく今の生活スタイルを変えるつもりもない。このままの生活が維持できなくなればその時がXデーだとばかりに限りある残りの人生を満喫したいという。
そんな彼の気ままな余生が徐々に侵食され始める。それはパソコンにいつも一方的送られてくるメールからだった。いつもの迷惑メールだとして無視してきた彼だがある時ふと目に付く文言が。
「敵」と書かれたそのメール、いつもの怪しげな迷惑メールとは違う文言ながらもやはり彼は無視し続けた。
儀助の周囲には彼を魅了する二人の女性の存在が。元教え子の鷹司靖子、行きつけの文壇バーには女子大生の菅井歩美。なにかと彼女らは彼の自尊心をくすぐり誘惑してくる。いやそれは彼の妄想に過ぎないのかもしれない。
そんな彼の下心を見透かしたかのようにあるいは彼の抱く罪悪感が妻信子の亡霊を見せるのか。あるいはこの家にはかつての住人たちの霊が住みついているのだろうか。彼は何かと妻の亡霊に翻弄される。
そして迫りつつある「敵」の存在。それは北からやって来るという。北の国の独裁体制から解放されたその住民たちが難民となって押し寄せてくるというまことしやかなネット上のデマにより作り上げられた妄想なのであろうか。
たちまちあたりは戦場のような騒乱に包まれる。それは儀助が母の胎に宿っていたころの戦時中の空襲を思わせた。
そこに漂うのは死の恐怖。「敵」はゆっくり近づいてくるのではない、それは突然現れる。「敵」とはなんなのか、それは「死」そのものではないのか。
敵とは、その正体とは。それはけして人間が逃れられないもの、自分自身の死を言うのではないだろうか。儀助は自分の死を常に意識していた。自分の今の生活を維持できなくなる日が来れば潔く死のうと。あえて自分の生を引き延ばすための節約もせず食べたいものを食べ、飲みたい酒も飲む。そうして時が来れば命を絶とうと。
愛する妻を亡くしもはやこの世に未練はない。死が向こうから来るのを待つのではなく自分から死を受け入れてやろうと。そう考えて余生を過ごしてきた。しかしいざ過ごしてみると誘惑も多い。周りには思わせぶりな美女たち、思わず下心も芽生えてしまう、そんな自分の罪悪感が妻を呼び覚ます。
この年齢になり人生をすべて見極めたつもりだった。いまさら死を恐れることなどないと。しかしやはり死への不安や恐怖は拭えない。Xデーが来たら潔く自死すると決めていた儀助、しかしそれが来ることがいつかはおぼろげにわかっていても、それはいつか来るものでありそれがすぐにでも訪れるとは思っていなかった。健康診断を避けてきたのも自分の死を直視させられるのを避けたかったからにほかならない。
しかし下心から女子大生歩美への援助で貯えの金を渡してしまい、ことのほかXデーが目の前に来てしまった。まさかこんなにも早く。常に死を意識していながらもしかしそれはまだまだ遠い先のことだと高をくくっていた。死はゆっくりと近づいてくるものだと、しかしそれは突然やってきてしまった。
いくら長い人生を生きてきて経験を積んでも死だけは経験できない。死は未知の領域だ。儀助は覚悟していたようでその実、覚悟なんてできてはいなかった。
いったんは首を吊ろうとする儀助だが、それも尻をついてのもの。彼の死ぬことへのためらいがそこからも見て取れる。
友人にも死の期限付きで生活すれば人生が充実するなどと語りながら、やはりその不安は払拭できてはいなかった。そんな彼の潜在的な死への不安や恐怖が「敵」となり、メールを通してじわじわと彼にその予兆を知らしめ、ある時突然襲いかかったのかもしれない。
死という名の敵。生きる上では常に対峙すべきもの。生を望めば望むほど死という敵の存在が大きくなる。生に執着すればするほど死の不安と恐怖は大きくなって彼に強大な敵となって襲い掛かってくる。
受け入れようが受け入れまいがやがて死は必ず訪れる。そして儀助にも死が訪れる。「敵」は受け入れたとたんそれは「敵」ではなくなる。死を受け入れることはそれは死の不安や恐怖からの解放を意味する。
そうして死から解放された彼の魂は安住のこの地、この住み慣れた家に宿ったのかもしれない。それを知った彼の甥はおいそれとはこの家を売り渡すことはできないであろう。
相続手続きがなされる主を失った邸宅で儀助の甥が彼の双眼鏡を何気に覗くと二階の窓際に佇む儀助の姿があった。
独り身で悠々自適な生活を送り続けていた主人公、しかしそこには常に老いと死がつきまとう。そんな老いと死への不安や恐怖が「敵」という形となって彼をじわじわと追い詰めていった。
高齢となれば連れ合いは必ず先に逝く。孤独な老後の暮らしで誰もが味わう死への不安や恐怖を筒井文学特有の語り口で見事に映像化した。
十代の頃夢中になって読み漁った筒井文学の世界がそのまま再現されたような作品だった。一見平凡な日常が徐々に非日常に侵食されてゆく様、スラップスティックな笑い、悪夢のようなシュールリアリスティックな現象。
筒井氏はむかし村上龍氏との対談で非現実なことを描くには現実的な描写がしっかりと描かれてないといけないと述べていた通り、本作は前半はごく普通の日常がリアルに描かれ後半から超現実的な現象が描かれて見る者を悪夢へといざなう。まさに筒井氏の十八番と言える作風を見事に映画という映像表現に落とし込んだ監督の筒井康隆愛がにじみ出た作品だった。
筒井文学ファンなら本作を存分に楽しめたことと思う。と言っても私自身筒井文学から離れてかなりの時間がたつ。父親と同い年の筒井氏がいまだ健在なのがうれしい、早速原作本を注文した。なんせ80年代までしか氏の作品は読んでいない。ベストセラーになった文学部唯野教授でさえ読んでいない。これから読ましていただこう。
ちなみに私が好きなのは七瀬三部作、俗物図鑑、大いなる助走、乗越駅の刑罰、などなど数え上げたらきりがない。誰か有名な作家が言ってた、青春期の読書は恋愛と同じだと。まさに青春時代夢中になって読み漁った筒井文学は私にとって恋愛だった。
男性の秘めたることをバラしちゃいけないと思ってしまう映画
筒井康隆原作、長塚京三が主演。「桐島部活~」の吉田大八が脚本監督。東京国際映画祭グランプリ。
モノクロで丁寧に作られている。初老の域に入った男性にとって、けっこうドキっとする映画。
前半は、一人暮らしをとても丁寧にテンポよく描く。ちょっと気が緩んできたら、後半はホラーのような「時をかける少女」のような掴みどころのない展開。それが、老人の独り身の老いてゆく怖さに繋がっている。
ラストの中島歩には笑った。この人いろんなのにちょい役で、場面をさらってゆく(Netflix「阿修羅のごとく」とか)。売れてるね、この人。
瀧内公美も不倫とか夫を誘惑といえば、彼女が選ばれる(「阿修羅のごとく」)。で、それが実にハマる。河合優実もなかなか可愛い。と男性の下心をくすぐる(中島歩はちがうけど)。
まあ、世の男性で、心当たりがある人は、なんとも居心地の悪い映画だと思う。
その意味ではよく出来た映画。
(そんな男性の秘めたることをバラしちゃいけないと思ってしまう映画)
妄想
老人男性が日常の妄想という敵に
追い込まれていくストーリー。
自分の老いに向き合う姿は滑稽でもあり
切なさも感じる。
自分自身と向き合い考えて、女性に対して
後ろめたさと醜態を死ぬギリギリまで
感じてる男性も多いのでは。
特に、ある年齢の男性に観て欲しい。
現実と虚構
前半は現実。
後半は夢の話。
ポイントは「なぜ、今夜はこの夢を見たのか?」という問い。
そしてラストシーンに必要なのは、「そもそも、これは現実なの?」という問い。
敵は誰なのか?そして、味方は誰だったのか?
この映画からは「今、あなたの周りに見えてるモノはホンモノですか?」と問われてる。
そんな映画だと、私は受け取りました。
敵は…
敵は我が身の、「妄想」って、ことね…。
そして、その「妄想」は、恐れと願望があいまって、老人特有の痴呆も絡み当て増幅ざれていくといことね…。
確かに怖い。
まさに痴呆症の人の思考についていかれないように、映画にもついていけない部分があった…。
結果、我々も「人様の恥ずかしく面白い生活」覗いている。
妻に先立たれて独り暮らしをする、引退した仏文学の教授の静かなる生活を丹念に静かに描く前半。
インテリで品のある人物だけに、起床してからの、朝食の支度、食事、身嗜み、清掃など、静謐に粛々とこなす様に、どこか不自然な印象も持ちながらも、独居暮らしのそこはかとなく垣間見られる哀愁に、誰もがいずれやってくる自分の未来を重ねて見てしまうだろう。
その普遍的でヤマもない前半を経て、中盤から虚構と現実な入り混じる展開となっていき、「敵」と呼ばれる未確認な存在と、隠喩を交えながらの物語が紡がれていく。
まーぶっちゃけ、後半から虚構と現実の区別が掴めなくなって、ちょいとお手上げ状態。このあたり、いっそのこと考察系ブログを確認してから鑑賞したほうが面白いかもです。
とりあえずわかったことは、インテリ系老人の隠キャはかなり痛いってことだ。
マジか…老後のために陽キャに転向するかー。
筒井康隆ワールドへの真摯な挑戦が可能にする没入感
老醜を晒すくらいなら己の命を絶つと意気込む元大学教授、
その均整の取れた生活は「敵」の到来を告げるメールと共に徐々に瓦解していく。
夏から秋、そして冬へと時の移り変わりを追うモノクロームの映像に
実感豊かな音を乗せて送られる主人公の末期の日々、その恐ろしいまでの実感に圧倒される。
不安、痴情、後悔、そして恍惚……打ち寄せる波にも似た感情は泡沫の夢へと溶けていき、
徐々にルーチンを保てず荒廃していく実生活に観客は主人公の老いを否応なく納得させられる。
そして孤独に震え春を待ち侘びる老翁の背に喚起させられる疑念、
「夏の輝かしき日々も既に忘我の人の妄想に過ぎなかったのでは?」……
その答えを得る者はいない。主人公も、観客も。
筒井康隆作品の本領とも言える世界観をかくも表現しきる熱演と構成に
ただただ敬服と言うほかない。
うーん‥‥?
長塚京三さん、久しぶりでした。
以前は良くドラマに出てましたね。
スクリーンで観るととってもカッコ良かったです。
なんだか不思議な映画でした。退屈を感じる事も無く終始引き込まれました。
しかしながら、理解不能‥?
うーん‥この映画で"敵“と京三さんの幻覚の伝えるモノとは‥?
理解しようとするが、出来ず。
最後のシーンで槙男さんが幻覚っぽいのを見ていたが繰り返すって事?
うーん‥‥‥
げんなりする
主人公の長塚京三が完全に認知症でつらい。うちも母が軽度の認知症で物忘れが激しいのだけど、まだ被害妄想などはないので助かっている。バーの娘の老人たらしっぷりが怖い。それこそ敵ではないだろうか。300万円とられたのは現実なのだろうか。現実と幻覚の境目があいまいに表現されているので何がなんだかよく分からない。
丁寧な自炊が描かれるが炭水化物がグルテンばかりだ。最近実験的にグルテンをオフにする食生活をしているので気になった。
年をとってもいいことなんか何もない。うちはまだ子どもがいるから助かっているが、もし子どもがいなかったら希望など何もなく、先細っていくばかりだ。
大学教授ということで最初から偉そうで、そんな彼がどんどんみっともなくなっていくのが面白い。遺書まで偉そうだった。
自分で意味づけができる作品
予告でとても気になったので見てみました。
予告で予想していた通りの内容で自分としてはとても良かったと思います。
前半の長塚京三さんが朝起きてごはん作って食べて歯磨きしてコーヒーの豆を挽いてコーヒーを飲む、スーパーで買い物をする、昼飯や夕食を作るというこのルーティンをセリフもなくモノクロ映像で淡々と映し出すところはなんだか不思議にずっと見ていられるものでした。長塚さんがすごく細くて背が高い感じがなんとなく松重豊さんに通じるものがあり飯を淡々と食う姿が孤独のグルメの吾郎さんにも見えたり、その出てくる飯がなんだかすごく美味しそうに見えたり飯テロ要素もある作品です。
そんな中、徐々に切り替わっていき、いつのまにか見ているこちらも飲み込まれている後半の世界観については見る側の想像力が求められると感じました。
あくまで私が感じたいくつかの点を書かせていただきますが「敵」という存在を意識し出して非現実な夢を見るようになってくくだりは、あのゆっくり流れていくような毎日が夏休みな感じの生活の中で先生は日常に何かしらの刺激を求めていたのではないだろうかと思います。その心境の現れがあの夢なのかなと。一見、真面目そうに見えるが作中の様子や会話で見えてくる先生の変態性がありました。あの年の老人の独居の人にしては老いを感じないような几帳面さ、近所を双眼鏡で覗きをしたりする面、真摯に振る舞いながら女の子や教え子の女性に下心を持つ面、そう思っていながら紳士ぶるけど実は想像しながら1人でしていることを夢で白状してみたり。
このような感じからあの非現実さは先生の中に何かしらの刺激を求めていたのだろうなと思いました。
もう一つ考えられるのは認知でボケが入ってきてその妄想を映し出していたのか。作中でも非現実な世界がクライマックスを迎えて、そこから日常に戻ったらすぐポックリ逝っちゃったので。
あとは犬のうんこのじいさん、あの人も認知が入ってきていてボケていて自分でうんこをあそこにしてそれをあの女性のせいだと思い込んでいたのかなとか思いました。
ラストシーンの双眼鏡に映っていたのは誰なのかマジでなんなのかはわかりませんでしたが
とにかく後半は意味がわからない分、様々な考察ができるような作品になっていると思います。
私もこの作品を見た他の方がどのように感じたのかを少し見てみたいと思います。
全102件中、1~20件目を表示