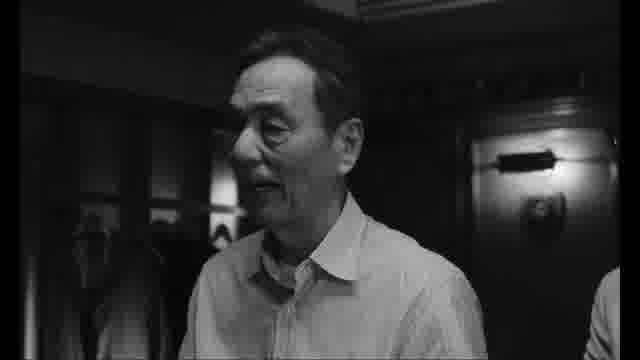敵のレビュー・感想・評価
全367件中、141~160件目を表示
リアルとドリームの境界が…
時間軸がシンクロするので、今はリアル❔それとも… 字幕で観たということもあって疲れた😖💦
アカハラや女子大生への一方的な金銭供与(回収不可能)等々、歳をとっても…未々あの歳ではないが、身につまされる思いでしたが…😣
離婚前の編集長に迫られたら僕も…😆
いかにも筒井康隆…
妻には先立たれ、10年以上前に大学を退職し、昔ながらの日本家屋で、丁寧に食事を作り家事をこなし時々原稿を書いたり講演をしたりする、恐らく昭和の頃から変わっていないであろう日々のルーティーンを一人で静かにこなしているフランス演劇を専門とする仏文学者の渡辺儀助。原稿執筆中に時折り届くメールは「5百万円が当選しました」のような詐欺メールばかり。そんなある日、「敵が北からやって来る」というメールが届く……。
儀助は時として現実離れした夢にうなされながら目覚める。上映開始1時間ほと経過した映画の後半になればなるほど、その夢は激しくなっていき、現実と幻想の境目が曖昧になっていくが、そんなシュールレアルな幻想を真に受けていても仕方がない。そもそも、やって来るはずの「敵」とは、いったい何者なのか?
劇中で敵の姿が明示的に描かれることはない。しかし、映画の、そして人生の、時間の進行とともに誰しもに忍び寄ってくる「敵」とは何か?と考えてみると、さほど難しい謎掛けでもないだろう。
「こちらの世界にいる人類や友人よりも、あちらの世界にいる知り合いの方が圧倒的に多い年齢になると死を恐れなくなる」といういう話をどこかで聞いたことがある。
誰にでも訪れる「老い」を敵対視するのか、それともそれを味方につけて楽しみに過ごすのかによって、人生の質も変わって来るのだろう。
ちなみに、全編白黒なのだが、これも余計な情報が遮断され、逆に集中しやすいのかも。
ホラーでもなくて
これは、絶対に原作を読む!
混沌モノクロ夢と現実まさに筒井康隆
期待値がかなり高かったけど期待を裏切ららず!品の良い元大学教授の素敵な暮らしぶりに途中まで「長塚京三は素敵。いつ筒井康隆っぽさでてくるのか?」と思いながら鑑賞。途中から夢と現実が交差し始め混沌の中ふと現実が顔を出す感じに。いやどこまで現実?妄想?北から来る敵って?ネット民?妄想ワールドに行ってしまった。筒井康隆✕吉田大八成功してると思いました
タイトルなし(ネタバレ)
評判通りモノクロ版孤独のグルメだったが、自炊してる分より孤独感が増してるのですが端正な分、後半のカップうどんやあんパンで錯綜してる感じがより強く感じられた。
これはネタバレになるかも↓
筒井康隆原作のイメージより屋敷(家)に取り憑かれた『シャイニング』のような話だと思った。(最後双眼鏡でみたものとか)
恐るもの
白黒映画なのに
だから?なのか
食べ物が美味しそう✨
焼き鳥が一番食べたくなりました
最初みていて、パーフェクトデイズ的な感じかと思っていたら
平山さん役所さん的な?
全然違くて
自死を決めて生活をする
元大学教授
お金にゆとりがある時の生活から
行きつけBARオーナーの姪
健気な哀れな彼女にほぼ全財産をあげてしまう
これは現実出来事と私は捉えた
困窮しはじめてから、現実なのか
夢なのか
わからない展開
生きているのか、死んでいるのか
わからない展開が続く
敵は死だったのかなと解釈
主役は長塚さんじゃないとだめだと思いました。というか長塚さんだからとてもよい
夢じゃ、夢じゃ、夢でござる。いや、夢ではない。
1月31日(金)
1月にインフルエンザと虚血性腸炎で2度入退院を繰り返した高齢の母を見舞う。元気になって良かった。帰りにユナイテッドシネマ浦和で「敵」を。
祖父の代からの一軒家に住むフランス文学の教授だった渡辺儀助(長塚京三)は、20年程前に妻を亡くし、一人暮らしで買い物、料理、掃除、洗濯をこなし、コーヒー豆を挽いてコーヒーをいれて、仏文学に関する講演や原稿を書いて生活している。
昔の教え子(瀧内公美)が訪ねて来たり、友人とバーに飲みに行ったりもする。
貯金の残高からあと何年こんな生活が出来るかを計算して、その日を目指して生きている。
そんな中、あなたに500万円当選しましたとかスパムメールが来る中に、「敵がやってくる」というのがある。
そこから生活のリズムが狂い初める。
バーのオーナーの娘(河合優実)に金を騙し取られたり、亡くなった妻と一緒に入浴したり、昔の教え子とあわやの関係になったりと虚々実々の世界が展開される。
不条理なのは筒井康隆ワールド。
どこまでが真実で、どこまでが虚構なのか夢なのか。
夏、秋、冬とストーリーは進み、
「春になればまたみんなと会える」と言うのが儀助の最後の台詞だった。
「なれば?」冬には誰とも会っていないのか。するとあれは全てが幻覚、幻想、妄想か。春の儀助の葬式、本作のそれまでの登場人物は誰一人出席していない。
そもそも本作は、最初から全てが儀助の幻想だったのではないか。
「ファーザー」のレビューにも書いたが、認知症になると料理が出来なくなる。昔出来ていた事が出来なくなるのだ。
あれだけ手際良く調理していた儀助が冬には料理をせずパンをかじっていた。
しかし、美しいモノクロームの世界の瀧内公美の艶めかしさはどうだ。
儀助でなくても性欲を刺激されるのは間違いない。
いや、私が70過ぎたエロジジイだから言うのではなく、人間は70歳になっても性欲は衰えない。少なくとも精神的には。肉体が付いてくるかは別の問題だ。
辛いキムチを食べ過ぎて大腸炎で下血し、内視鏡検査を受けた儀助は医師に言われる。腸の機能は加齢で落ちているのだと。
(先週、母が虚血性腸炎で入院し大腸の内視鏡の画像を見せられたばかりなのだ)
やって来る本当の「敵」は、老いか、孤独か、死か。
老境に至りても、ひとは醜くて面白い。
筒井康隆は関西圏のテレビで鷹揚としゃべるおじいちゃんという印象しかない。
小説は読んだことない。時をかける少女とかの原作者だってことは知ってる。
吉田大八の脚本・監督ってことに惹かれて観た。
多分、ある種の認知のズレが始まった老人の、混乱から死への季節の描写なんだろなー。
かっこよく死に時を探しているけど、40くらいの教え子に欲望を抱き(瀧内公美さんがすごくいろっぽくてよい)夢精するし、20そこそこの小娘に鼻の下を伸ばしてお金を取られ、20年前に死んだ妻のコートに面影を求め、隣人の加齢臭に自分も臭くないかめっちゃ気にして石鹸をこすりつけ、金はとられるし絶望して自死しようとするのに、訳のわからんものに襲われたら抗ってしまうし、みっともなくて性も生もどっちも全然達観できてないやんってところが、生々しくて面白かった。
長塚京三さんの演じた、老境に至りてなおみみっちいプライドや欲望に拘泥する、普遍的でチャーミングな人物像がとてもよかった。だいぶ年とらはったなー、説得力ある画だけど演じるのに勇気いるよななど思った。
辛いレーメンでおなか壊して、大腸のカメラ検査の2回目で、女性医師に四つん這いにされて、下着おろされてはずかしいのに恥ずかしいと言えず、黒いホース状の何かが尻から吸い込まれる描写がおっかしくて、がんばって無音で爆笑した。
あと、犬の糞を放置するなとキレる隣人が、敵?に打たれて糞を尻でつぶしてしんじゃう描写と、犬の糞放置の犯人にされる女性の飼っている犬の名前がバルザックで、そんなところにまでフランス文学風味を…なども面白かった。
フードコーディネーターは飯島奈美さんだったよう。
社会の勝者であった人に
モノクロ画面については、モノクロ作品をたくさん観ているし(なんなら映画はモノクロの方が多い)、先に知っていたのもあり、そういう手法なんだな、程度だった。
画面に映る家電等が最先端なので、モノクロと映っているものとの間の軋みも味わいとなる。
そもそも妻を大分前に亡くしているのに家電が新しい、ということは自分で選別して購入する能力がある男性であることを表している。
庭掃除、料理、洗濯、廊下掃除(掃除機でははなく箒)の場面はあったが、しばしば登場する調理にまつわる台所の掃除はどうしたんだ、と思っていたら夜中にやっていた。
そのように主人公となる渡辺儀助は「丁寧なくらし」をしている。
フランス文学の教授職を退官して、貯蓄と年金、講演料や原稿料で生活している。
(ちなみにネット情報によると長塚京三氏はパリ大学に在籍していたことがあるそうな)
貯蓄があることも、退職したあとに小遣いというには十分すぎる(と思われる)収入があることも、社会の勝者であった彼を描き出している。
そういった下敷きの上に、老いによる孤独、隔絶感、閉塞感から芽生えた現実と妄想が降り積もってゆく。
最初は、雪が黒い地面に落ちて静かに溶けてゆくように、儀助という人間の中に吸い込まれて消えてゆくが、次第に、彼を浸食し、凌駕してゆく。
一応、女性として年金受給年齢まで日本で生きてきたものとしては、教え子の女性も夜間飛行というバーの女子学生もあざとさが目立つが、こういう罠に嵌ることにすら潜在的な願望を抱く男性は少なくないのかもしれない。
認知症になったらどうしよう、と悩む高齢者は多いが、病気と名付けられずとも、生命を授けられたものはすべからく老いて死んで行く。(どの程度の老いかはばらばらだが)
そういった事実を覚悟する意味で、社会の勝者として生きてきた方に観ていただきたい、と思った次第である。
まあ、それでも「オレ(だけ)は大丈夫」という人はいるけれど。
儀助の最後の姿から亡くなるまでの数ヶ月は描かれていない。
それは救いなのか恐怖なのか。
全く関係ないけれど、「猫と庄造と二人のをんな」を観てみようかな、と思った。
〝煩悩〟なんて都合のいい言い換えです
昨日のことです。
ナポリの窯でピザを持ち帰り購入し、自宅で冷え冷えのビールをグビッ!!昔から辛いのが好きなので、当然のようにTabascoをワンピースあたり3〜4滴大粒でかけました。案の定〜中略〜なわけです。病院へ行くほどではないのですが、若い頃に比べると、辛いものに対しての大腸の耐性(機能?)がすっかり弱くなっていることを痛感するばかりです。
シワとか肌のツヤとか人から言われなくても分かるような、加齢による変化についてはさしてショックは受けません。
けれど、20代〜40代、人によっては50代60代までは気にも留めなかったようなこと、それもまさか加齢で衰えるとは想像もしてなかった部分で衰えを自覚することになるという経験は結構ショックです。
歳を取る、というのは身体のあちこちで生じる〝まさかこんなところが!〟という加齢による変化(要は衰えのこと)に慣れていくことなのです。
なのに〝性欲〟(それを煩悩なんて呼ぶのは男にとって都合のいい言い換えでしかない!!)だけは、歳を重ねても衰えを感じない。機能は肉体的なものなのに、それが想像力から発するものだなんて極めて大脳的。その矛盾ってどういうこと?
知的作業を生業(なりわい)としているものにとってそのショックは簡単に整理できないから、自分の内面の課題ではなく、いちどきに襲って来る、自力で対処しようのない〝敵〟のようにも見えるのではないでしょうか。
原作者 筒井康隆さんの、テレパシー能力を持つ七瀬が主人公のシリーズでは、出てくる男はひとりの例外を除き、すべて女を見れば裸とセックスを想像しているように描かれています。
もちろんそれは作品全体から見れば部分的なものであり、主題ではないはずですが、男の一面としては絶対に切り離せない欲望のひとつです。
これぞ映画。悪くはない後味を噛みしめて余韻に浸る。
とても丁寧な暮らしをする主人公の姿に「PERFECT DAYS」を思い出しました。食も住もテキトーな私は憧れはしてもとても真似はできませんね。
でもその几帳面な日常ルーティンさえも、結末を知ってから思い返すと、別の意味があったんだろうなと気づいたり。
現実と妄想の境目が次第に無くなっていく不思議な作品で、モノクロ映像の鮮やかさが印象的。
長塚京三さんも、彼を取り巻く3人の女性も、まさにハマり役でキャスティングもお見事です。
レビー小体型の症状で幻視の出る肉親を近くで見てきたから、主人公に見える見知らぬ男や襲いかかる敵たちがとてもリアルに感じました。
老いも死も避けられないという現実。
筒井康隆原作なのでそれさえもSF的に飛びこえて映像にしてしまった吉田大八監督の手腕が光っていました。
久々の筒井康隆ワールドを堪能
原作は読んでいないので、初めから『敵』とは何かを考えながら観ていた。ま、死だったり老いだったりだろうなと単純に想像していた。
同居している91歳の私の母親は認知症ではないが、ここのところ睡眠時間がやたら長く、何かに対して怒鳴っているような叫んでいる様な大声の寝言が多くなった。物忘れも酷くなってきて、そんな事聞いてない、私がいい忘れたからって人のせいにするななど理不尽な事を言ったりする頻度も増えて来た。
この映画で私の母の頭の中を垣間見た気がする。きっと母も、過去の記憶や、長い人生の経験からくる理想、恐怖などの妄想と現実の混乱の中で日々の生活を送っているに違いない。何度も出て行こうと思ったが、雨の日に縁側に一人ぽつんと座っているシーンを観て、最後の日まで一緒に居てあげようと改めて思った。
敵とYシャツと私
2025年2本目は、敵。
序盤は憧れるほど丁寧な生活が描かれる。
焼き鳥を串打ちし、すぐ混ぜる冷麺もきっちりと盛り付ける。
何気ない日常描写でありながら、退屈はしない。
敵が現れてからは生活が一変し、パジャマで過ごし、菓子パンやインスタント麺のズボラ生活。
この対比が素晴らしいと思いました。
どこからどこまでが現実なのか、だんだん境界線が曖昧になっていく感じがとても良かったです。
画面がモノクロなこともこの映画にとってプラスに働いていると思います。
理性vs本能
敵は
老いですか?独居は少し寂しいですが、ある意味憧れの生活を送れているフランス文学の元教授ですが、段々と老いが迫ってきます。これは仕方ないですかね。できるだけ人に迷惑をかけない様にしたいものです。
観る人によってそれぞれ違う「敵」
中学生の時、筒井康隆の「狂気の沙汰も金次第」を読んでからファンになって、筒井康隆作品はほとんど読破しました。多くの作品を作り出している大御所ですが、すでに映画化されている「時をかける少女」や「俗物図鑑」みたいな解りやすいSF作品と、「虚構船団」や「文学部唯野教授」みたいな少々難解な純文学作品とに二分されます。今回の作品は後者ですね。
原作はもちろん読んだのですが、解りやすいSF作品とは異なり読むのに物凄く時間がかかったのを思い出しました。で、映画版なのですが、全編モノクロ(というか淡いセピア色?)で構成されていて、原作の雰囲気を上手く反映させていました。以前から教師役が上手な長塚京三を元フランス文学教授の主人公に据えて、エッセイやイラストにも造詣が深い松尾貴史を主人公の友達のデザイナー役、「ナミビアの砂漠」でも難解な役を演じきった河合優実を小狡い女子大生役に起用するなど、とても解りやすい作品に仕上がっていました。
全367件中、141~160件目を表示