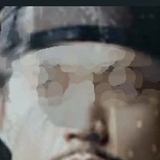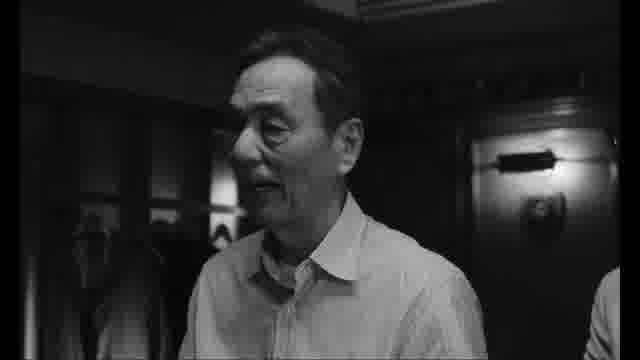敵のレビュー・感想・評価
全366件中、21~40件目を表示
モノクロの焼き魚が美味しそう
フランス文学の元大学教授。妻には先立たれ、都内の古い日本家屋にひとり暮らす。早起き、自炊、掃除、雑誌連載の仕事、友人との晩酌、教え子たちの訪問。静かで潔い生活を選択したはずの男に不穏な何かが迫る。
歳を取ったらこんな生活は悪くないなと思わせる、文学的隠居生活の描写が次第に崩れ始める。映画全体のペース配分が絶妙に良い感じで、これから起こることに期待膨らむ。
物語に何かが起こって欲しいという期待と、美しい生活が壊される不安が織り混ざり、またモノクロの効果もあって新鮮な後味が残る。
焼き魚が美味しそう。
最後は、うーん、文学的というか、筒井康隆ぽいというか、夢と現実が混ざり合った結末と言えば良いのか、説明し難い。
役者が皆さんお上手。
我々一人一人にも迫る“敵”
長塚京三氏を久々に見た気がする。
以前は映画にドラマ引っ張りだこだったが、近年はお歳を召して仕事量をセーブしているのか、露出が少なくなった印象。
本作は12年ぶりの主演映画。個人的に映画で最後に見掛けて印象的だったのは2014年の『ぼくたちの家族』。
ちょいちょい出てはいるが、この名優も静かにフェードアウトかなと思ったら、今年80歳になって自身の代表作やハマり役と言っていい作品に巡り会うとは…。
長塚氏が以前インタビューで語ったという“人生100年時代”。
本当に人生まだまだ先、何があるか分からない。
元大学教授で、フランス文学を教えていた儀助77歳。
長塚氏も昔、パリ留学の経験あり。吉田大八監督も当て書きしたという。
職は10年前にリタイア。祖父の代から続く古い日本家屋で隠居生活。妻には20年前に先立たれ、子供はおらず、一人暮らし。
職はリタイアしたが、時々講演や出版社から依頼された執筆を。
毎日決まった時間に起き、質素な食事や晩酌をし、パソコンに向かって依頼された原稿を書き…。買い物や日々使う文具もこだわり、徹底管理。毎日の営みやルーティンは『PERFECT DAYS』の平山さんのよう。
たまに数少ない友人や教え子が訪ねてくる。行きつけのバーに飲みに行ったり、自宅で手料理を振る舞ったり。
自由気ままな一人暮らし。ちょっと憧れる。
見るからに真面目そうな儀助。そんなイメージも長塚氏にぴったり。
性格も生き方も高潔かと思いきや、案外そうでもない。
近所で犬のフンでトラブル。途端に体臭を気にし、身体を洗う。
時折訪ねてくる教え子の靖子。大学在籍時から親交あり。美人で、最近離婚したという靖子。堅物に見えて、ちょっと下心ありの儀助。妄想の中で靖子と…。まあ、無理もない。夏、ランチやディナー、お酒も入って…。その相手が瀧内公美なら、男なら誰だってドキマギするって! それにしても本当に魅力的な女優さん。映画などではシリアス&クールな印象だが、たまにバラエティーに出ると明るくケラケラと笑い、そのギャップに萌えてもうた…。
行きつけのバーで、マスターの姪の歩美と知り合う。大学生でフランス文学専攻。フランス文学についての話やアドバイスはとにかく、若い娘(ブレイク&フレッシュの河合優実)と会うのが楽しみに。学費で困っている歩美。儀助は貯金を彼女に。それ以来歩美と音信不通に。まあ、そういう事。
身体は老いてもまだまだ気持ちはあり。それ故自分の愚かな部分も露見。悲哀やユーモアもあり、これも長塚氏のイメージに合う。
ショックではあるが、騙された事に不思議と腹が立たない。
なるべくしてなり、末路が早まっただけ。
端から長生きなど考えてもいない儀助。
貯金と一日使ったお金を計算し、後どのくらいで底を尽きるか。尽きる直前になったら葬式代くらい残して、自死を決めている。
遺言も書いてある。
騙し取られたのは自分の不甲斐なさ。そういう運命。“その時”が早まっただけだ。
さて、いよいよ自死しようとした時…
いや、ヘンな予兆は少し前からあった。
一通のメール。送り主は“敵”。
“敵”が来る。
ネット上でも“敵”についてあれこれと。
“敵”は日本に近付いている。
“敵”は南の方からやって来る。
“敵”はすでにもう来ている。あなたの近くにまで…。
何かの悪質メール…? 比喩…? デマ…?
何故かこれが妙に気になる儀助。
それからというもの、儀助の完璧だった生活が崩れ、次々奇妙な事が…。
靖子から誘い。ハッと気付いて起きると一人ベットの上。
病床の友人。ハッと気付くと…同じ。
近所でまた犬のフンのトラブル。何処からか飛んで来る銃弾。ハッと気付くと…同じ。
死んだ筈の妻が…。ハッと気付くと同じだが、これだけは夢でもこのままでいたかった。
妻、靖子、新担当編集のあり得ないシチュエーションで夕食。
これが現実ではないのは分かる。なのに、どれも妙にリアリティーがある。
どれが幻想か、どれが現か。何処から幻想だったのか、今現なのか。
端から儀助の妄想だったのかもしれない。
その狭間が曖昧…を通り越して、分からなくなってくる。
儀助の深層心理か、何の迷宮か、そもそもが分からなくなってくる。
それを印象的にする白黒映像。見る者を惑わし引き込む幻想的でありながら、美しい。
吉田大八の演出は、日常、ユーモア、シュール、サスペンス、哲学的などを織り交ぜバラエティー豊か。フィルモグラフィーの中でも異色作ながらしっかりと自分の作品に。『桐島、部活やめるってよ』『紙の月』などと並び、ベスト演出の一本。
長塚京三のハマり名演は言うまでもなく。今年の主演男優賞は吉沢亮で決まり!…と思ったが、大ベテランが立ち塞がる。
筒井康隆の同名小説が原作。幻想とリアリズム、哲学やナンセンスなど幅広いSF作家の御大の一人。
本作もいずれのジャンルにハマる。難解ではあるが、全く分からない/つまらない/飽きる事はなく、不思議と引き込まれた。
その一つに、“敵”の考察。
“敵”とは何だったのか…?
劇中では明確に描かれてはいない。
見る側が解釈。人それぞれ見方があると思う。
私的にはまず、死や老いと感じた。それは間違いなく込められているだろう。
平和ボケの日本に迫る危機警鐘。“北の方”だからあの国か、戦争の火種か。
コロナなどまた新たな未知の脅威かもしれない。
ひょっとしたらもっと個人の内面やパーソナルな事かも。年甲斐もない欲求や思い上がりや醜態への戒め。
“敵”ははっきりとしたライバル存在ではなく、何かのメタファー。答えはない。だから考察のしがいがあり、それがなかなか面白くもあった。
儀助は死去。
遺言に従って家や遺した書物などの事で関係者や唯一の親族の甥が集う。
物置で双眼鏡を見つける甥。覗いて家の方を見ると…
儀助の姿が。
ほんの一瞬だが、遠方を見渡している儀助。
亡き今もこの家に留まり、迫り来る“敵”に対しているのか、迎えようとしているのか、警鐘しようとしているのか。
我々の近くに、人それぞれの“敵”が迫り、或いはもう来ているのかもしれない。
妄想は人間を貶める「敵」
彼はフランス文学では著名な教授だった。モリエールら劇作家が専門。
プライドと名誉だけで生きてきた。
出入りの女性編集者にうつつをぬかす一方、亡き妻をパリに連れて行ったことは一度もなかった。
彼は庭が広い平屋の一軒家で一人暮らし。何を思ったのか、プライドと名誉と過去を封印しようと試みる。
完璧な自炊ぶり、モノクロの映像に、彼自作の料理が美味しそうに並べられる。
「残高に見合わない長生きは悲惨だ」が彼の口癖。
そう、彼は完璧に自分の老後を演出しようとする。
だが、人間完璧に生きようとすればするほど、どこかがほころびる。
それは妄想らしきもので具現化される。もしかしたら、幻想は人間の美しさを擁護する「味方」で、妄想は人間を貶める「敵」なのかもしれない。
モノクロの映像に、元教授が辿ってきた負の側面が漏れ出る。
そこを暴き出す、黒沢さやか、瀧内公実、河合優実の女優陣が、美しくも怖い。
元大学教授が身の丈に合った隠居生活を送っているな、という印象で微笑...
最恐のホラー映画
「敵」が支配する世界にとって、私こそが「敵」
施設に入っている父に会うのは半年ぶりだった。
半年前とそれほど変わらぬ見た目に安堵するも、すぐにその感情は畏怖となり、落胆へと変わっていった。
目の前に座っている父の穏やかな立ち振る舞いとは正反対に、つぶらな目は泳ぎ続け、誰かに助けを求めているように見えた。
きっと父が施設の外の人に会うのも半年ぶりなのだろう。
彼にとって日常に存在するのは、施設のスタッフだけであり、目の前に座る私は初めて会う見知らぬ人でしかないのだろう。
「敵」の侵食によって父は世界から排除され、施設に入ることで自分の人生を「立ち止まらせる」ことを強要された。
半年が経ち、「敵」に支配された父から見た私は、残念ながら「敵」でしかないのだろう。
穏やかな性格のおかげで敵意を剥き出しにされないだけ喜ぶべきか。
与えられたわずか15分という短い面会時間が永遠に感じて、途中から息苦しくなっていった。
15分を待たずに、私たちは面会を終え、父は施設のスタッフの介護で自分の部屋へと戻っていった。
スタッフの姿を見つけた時の父の安堵の表情を見た私は、非常に複雑な思いを抱えたまま、スタッフに一礼してその場を去った。
この静かな施設の中は「敵」が支配していた。
この中では、私自体が彼らにとっての「敵」なのだ。
筒井康隆さん原作の映画「敵」。
これまでに、「時をかける少女」や「パプリカ」「七瀬ふたたび」など、数多く映像化されてきた筒井康隆作品の印象はエンタテインメント性の高いSF小説。
しかし、この作品は少し趣が異なる。
原作の発行は1998年。
作者はおそらく還暦後に書きまとめ、断筆解除後に単行本として発表された。
主人公・渡辺儀助は75歳。
大学教授を辞して10年、悠々自適の余生を過ごす教養人。
フランス文学研究の権威として、時折依頼のある講演や稀にある執筆依頼の他は、規則正しい生活を重ね、誰もが羨む丁寧な暮らしを続けていた。
講演依頼を受ける基準は「謝礼が10万円である」ということ。
それ以下ならもっとオファーがあるはずだが、自分を安売りしないというポリシーで10万円以下なら即断りを入れる姿勢を崩さない。
三度の食事を大切にし、手間をかけて旬を盛り込んだ自分のためだけの食事を作る。
食後に挽き立ての豆で淹れた美味いコーヒーをゆっくりと飲み、夕食にはそれなりに贅沢な赤ワインをじっくりと嗜む。
人生の折り返しを過ぎた大人の男性から見れば、きっと憧れの老後生活の最上級のモデルケースのひとつだろう。
この映画を見るまでは。
自ら「立ち止まる」と決めた時、「敵」は静かに近づいてくる
人生を賭けて研究し続けたフランス文学への造詣によって、主人公・儀助はフランス文学の権威となり、大学教授にまでのぼりつめた。
そこでは自分を尊敬する弟子たちが常に集い、自分の一挙手一投足に賞賛の声が湧き、憧憬の眼差しが途切れることはなかった。
中には、引退した今でも彼を慕い、老人の一人暮らしの庵を訪ねる教え子たちもいた。
恩返しの思いで彼に執筆を依頼し続ける出版社勤めの教え子もいた。
けれど、かつて大学の教壇に立って熱弁を振るっていた頃の賑わいは、もう自分を囲むことはない。
恩返しの気持ちだけでは、大学教授の視点が抜けきらない原稿を畑違いの雑誌に掲載し続ける熱は続かない。
周囲は生き続けていた。動き続けていた。
しかし、儀助だけが動きを止め、過去に生きていた。
そして、そのことに彼だけが気づいていなかった。
生きるために変わり続け、動き続けている周囲の人たちの流れの中で、「立ち止まる」と決めた主人公だけが交わることなく、自然と傍に追いやられていった。
私たちにとっての「敵」は、果たして本当の「敵」なのか?
「敵」とは何か?
それは「立ち止まる」と決めた人を襲う「孤独」という名の疎外感。
「自分らしく生きる」と決めた者に訪れる「世の中から忘れられる」という喪失感。
「自分は変わっていない」にもかかわらず、周囲の反応がどんどん変わっていくことへの苛立ちや怒り。
ただ立ち止まっているだけなのに、どんどん世の中から取り残されていく驚きや違和感。
教え子たちが慕っていたのは、じつは自分個人ではなく、「大学教授」という肩書きや地位の方だったということに気づけたとしても、もう「敵」は心身を蝕んでしまったあと。
主人公が見ている日常は、現実世界のものなのか、彼の夢想・妄想なのか。
「敵」に侵食されてしまった後では、それを判別すべは本人でさえもう持ち得ない。
「敵」とは何か?
少なくとも、「敵」となりうるものが誰の心の中にも潜んでいるということは間違いない。
私に微笑むあの人は、本当に実在するのだろうか?
主人公・儀助は、自ら進んで「立ち止まる」ことを選択した。
本人はそう考えていたが、実際は流れ続ける社会から弾き出されただけだった。
そのことに気づいた時、儀助は遺書を書き、自死を選ぼうとする。
しかし、「敵」に完全に支配された状態では、もう自らの意思で何かを選択し、実行することさえ難しい。
今生きているのか、夢の中なのかさえ、本人には判別ができないのだから。
彼は妄想の中を生き、妄想の中で死ぬ。
この映画を見た50代以上は、きっと映画の中の光景にリアリティを感じ、恐怖に慄くはずだ。
果たして今、自分が感じていることは現実なのか? 妄想なのか?
親しくしてくれている友人は実在するのか?
いつも愛想を振りまいてくれる行きつけの喫茶店のバイトの子は、本当は自分に向けて笑ってなどいないのではないか?
毎年届く年賀状は、ただ機械的に郵送されているだけではないか?
届くメールは全て「敵」からのメッセージなのではないか?
父を介護するスタッフは、とても親切で優しい人に見えた。
父が住む「立ち止まった」世界でも、同じように見えているといいなと心から願った。
けり
吉田大八「敵」原作は知らなくて“敵”はネットで真実のメタファーなの...
死ぬ日を逆算して生きるけれど、
死ぬ日(X-da y)を逆算して生きていた渡辺儀助の、
完璧なルーティンを砕く【敵】とは❓
まるで役所広司の「PERFECT DAYS」を思わせる
毎朝のルーティーン。
原作(筒井康隆の同名小説)は儀助の日記形式で
書かれてると言う。
ただ役所広司の朝より、倍速で気忙しい。
追われるように手際は良いのだけれど、
余裕やゆとりがない。
しかしモノクロでも料理は旨そうで、伝わってくる。
ひとり焼き鳥は生真面目な儀助も、実に楽しそうだった。
長塚京三は言う、
吉田大八監督は原作を映画界に入る前の1998年には読んでいて、
いつか映画化しようと考えていた。
コロナ禍で予定がバタバタと消えて無粋を託っていた時、
ふと今こそ映画化しようと思ったそうだ。
主役は“長塚さん以外には考えていない“
長塚いわく、“私が歳をとるまで待っていたのではないだろうか?“
そう思うほど、何も考えなくて良くて、
ト書の通りに“歩き“、ト書の通りに“話した“
それだけで渡辺儀助になれた。
“私は何もしていません“
死を超越したような、死をコントロール出来ると考えてる前半。
迫り来るX-davを余裕たっぷりと待ち受けている・・・
ところがどうだ!!
後半はコントロールするどころか、無様に《敵》に怯え、
老いに侵食されていく。
老いへの優越から、ごく当たり前の弱い年寄りに
成り下がる・・・のではなく・・・
《死》も《敵》も《老い》も
見下すことなど不可能なのだ。
さまざまな出来事。
3人の女
瀧内公美、河合優実、黒沢あすか、
彼女たちは存在したのだろうか?
夢と妄想の産物ではあるまいか?
それにしても色っぽくて、しっぽりした瀧内公美、
小悪魔的に、殺し文句を連発して、大金を巻き上げる(?)河合優実、
20年以上前に死んだ妻の黒沢あすかまで現れる。
先生(儀助)は大学のフランス文学の元教授で、
瀧内公美は元教え子、
“今なら、セクハラ・・・ですよねー”
と言いながら、足繁く訪れて先生の手料理でワインのお相手をする、
眼福のような慎み深いしっとりした美しさ‼︎
瀧内公美も河合優実も超人気女優、
二人は幾つの引き出しを持っているのか?
役柄によってまるで別人に化ける演技巧者、
仏文の学生・河合優実は、プルーストやサン・テグジュペリ、
マルグリット・デュラス、などを持ち出して儀助を翻弄する。
“こんな会話に儀助は飢えていた・・・“
“知性で優位に立ちたい男のプライドをくすぐり捲る河合優実・・・
脚本も良いが三人の女が実に魅力的。
フランス文学の教授なのに、
“一回もフランスに連れて行ってくれなかった“
と恨み言を言う妻の黒沢あすか、
“実は会話に自信が無くてねー“
生きている間には一度もなかった、
同じ湯船につかり、向かい合う、
亡き妻と愛人(?)と旅雑誌の編集者、儀助の四人で囲むお鍋料理、
ちょっと滑稽で苦くて甘いシーン。
儀助は認知症・・・ではないと思います。
あくまでも夢と妄想が入り混じり、
《敵》に怯え、最後には《敵の襲来》に果敢に立ち向かう、
本当に長塚京三は適役でした。
ソルボンヌ大学を6年掛けて卒業した経歴。
実年齢とほぼ同じ79歳、
息子は有名・人気劇作家で演出家の長塚圭史で、
(KAAT神奈川芸術劇場の芸術監督)
その妻は常盤貴子、
長塚京三の遺伝子は社交的で優れた息子に引き継がれた。
心に刻まれる素晴らしい映画だと思います。
ラストの台詞
「この雨が上がったら春が来る、みんなに会いたいなぁ」
のところで、長塚京三さんは、涙ぐんでしまった、そうです。
阿川佐和子にそう話すのでした。
老いる…ということ
…おもしろい視点で見られる
妻に先立たれ一人で暮らす
真面目で几帳面な元大学教授の日常
全編モノクロ
料理は彩りは無いのですが
美味しそうに食べる姿や
食べる音で美味しさがわかる
食後豆から挽いた珈琲で
充実したひとときを楽しむ
途中から"敵"の存在が何度も出てくる
はじめはよく分からなかった
一人で暮らす生活で
老いからの"孤独"や"寂しさ"から
現実だと思っていた事が夢だったと
…可笑しな夢を見る
何度も何度も(最後の頃は悪夢)
現実かのような夢
記憶が遡っているかのような夢
最後は母の胎内にいるかの様な戦中の夢
季節は夏から冬の出来事
春になったらまた皆と会いたい
と最期のことばが切なく聞こえる
相続は従兄弟の槙男に託される
託された槙男は双眼鏡で伯父の姿を…
そして槙男の姿はない
ラストの意味がわからなかった
ミステリ(謎)な感じで終わる
所々笑える所もあり面白しろさもある
長塚京三さんをあてがきされた様な作品
リアルな感じが素晴らしい
他のキャストの皆さんもとてもよかった
まぁ〜…(本文に続く…)
目を覆いたくなる前半のプライドと痩せ我慢の痛々しさ。なぜか愛らしい後半の暴走ダメ爺さんぶり。
久しぶりに見る長塚京三。
落ち窪んだ目元、深くなった目尻の皺、
伸びきった喉元のシルエットは、すっかり老人のものだ。
モノクロ映像の深い陰影が、それを際立たせる。
「私、部長の背中見てるの好きなんです」
部下の女性の言葉に小躍りしていた
サントリーオールドのCMの長塚京三は
はるか遠い日のものだ。
仕事は遠のき、人付き合いも限られていくのに、
ブライトは高く、食欲も性欲もまだまだある。
人生の残高を計算しては心細くなるのに、
後輩に説教がましく人生の閉じ方を語ったりしてしまう。
ひとり自分のために美食をつくっては、
女性に振る舞って褒められる自分を妄想している。
しかし妄想は妄想。現実は変わり映えしない。
ひときわ強めの効果音が、老いの現実を容赦なく刻みつけていく。
この映画を観るひと(つまりぼく)が、
老いへの不穏な気配を感じていれば(つまりぼく)、
映画の前半は思い当たることばかり(つまりぼく)だ。
物語は動き出す。
元教授の大好きな(ぼくも好きだ)可愛い子ちゃんとの
甘い日々はガラガラと音を立てて崩れる。
自分を教授に引き戻してくれる教え子たちとのささやかな現実も、
妄想がじわじわと染みこんできて暴走し始める。
振り回され、混乱し、慌てたり、怖がったり、謝ったり。
だがしかし、教授はなぜか遥かに生き生きとしている。
何度も推敲した遺言書は、最後は万年筆で清書だ。
自分らしい知性に溢れている。
敵との戦いに自ら飛び込んで、最期を迎えたそのあとは、
懐かしいみんなと会える。
さあ、ぼくの遺書を聞いてくれ。
よくできてるだろ?
長塚さんは、前半のカッコ良いところが、痛々しくて見ていられず、
後半のカッコ悪いところが、人間的でいいやつっぽくて、よかった。
自分はどう老いたいのか、考えずにはいられなかった。
奇妙な展開と人生の終末期が見事にマッチした映画
質素だけれど、家事を自然体でこなす現実的な日常風景の前半と
幻想と現実がわからなくなる主人公の混乱が
観ている私たちも追体験していくような感じで
非常にリアル。
観終わった後も、現実と幻想に思いを馳せた。
それにしても、ご飯をとても美味しそうに食べる長塚京三さんがカワイくて魅力的、とても御年80歳とは思えなかった。
死ぬときはあんな感じ
長塚京三、瀧内公美、黒沢あすか、河合優実、すばらしい。
あと何年という計算をするところが、身につまされます。
なくなる時は、たぶん、現実と夢が混在してきて、わからなくなっていくのだと思い至り、あんな感じで死んでいくんだなという、身につまされる映画でした。
飯テロ→現実の崩壊
原作未読、前情報ナシで鑑賞しました。
文化系インテリじいちゃんの質素な日常に、虚構(妄想?)がいりまじり、境界があいまいになっていき…というおはなし
いや、こういう話とは思っていなかった。
つらかった。
アンソニー・ホプキンスの「ファーザー」のときもこういう感覚に陥って、号泣しながら観た。
敵。
老いなのか、死なのか、認知の歪みからくる漠然とした恐怖なのか。
わたしは認知症のメタファーと思ったし、監督もそのように考えているみたいだけど、筒井康隆氏は否定しているそうな。
こういう自我や認知が崩れていく話は恐ろしくて見ていられない…年とったら違う感想になるんだろうか。
白黒なのにご飯がとても美味しそうでお腹がすきました。
長塚さんも見事でした。一人でいるとき、靖子がきたとき、奥さんの幻に話しかけるとき、女子大生と会話するとき、それぞれ違った顔で。
瀧内公美さんがエローい!!!上品なのに、、
かわいいなあ。
あの色気はどうやったら出るんですかね?
あの女子大生は実在していたんだろうか。お金騙し取られたのは事実?(だからXデーが早まった?)
靖子があんなに美しく魅力的なのは、儀助の主観がはいってる?
もはやどこまでが客観的事実だったのかわからない
あと、ラストシーンの意味がよくわからなかったな
儀助がお家につく幽霊になってしまったかのようだった
追記
演出がホラー映画に似ているから
あんなに居心地が悪かったのかもしれない
3日経ったらだいぶ馴染んできて、原作を読みだした。
(原作の儀助は更にプライド高いしきもちわるい)
最初から儀助はオバケ(死後)だったのでは
でも流石にそれでは可哀想すぎるな、などと考える
余韻に浸れる作品
途中からよく分からなくなった
敵はいきなりやってくる
長塚京三さんのようになりたい。
長文のレビューが多いですね
全366件中、21~40件目を表示