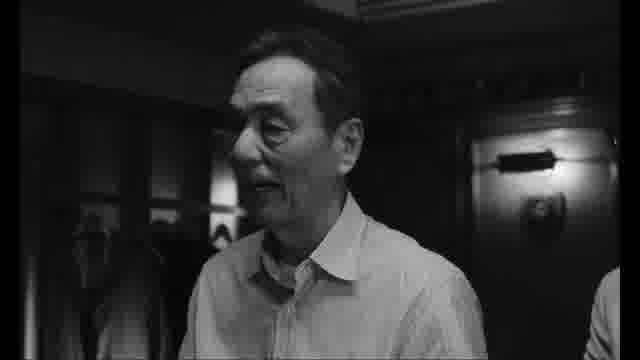「モノクロながら、鮮やかな色彩を感じさせる一個人の老後生活」敵 緋里阿 純さんの映画レビュー(感想・評価)
モノクロながら、鮮やかな色彩を感じさせる一個人の老後生活
『時をかける少女』『パプリカ』の日本文学界の巨匠・筒井康隆による同名小説を『桐島、部活やめるってよ』の吉田大八監督が映像化。生い先短い老人の慎ましやかな生活と、自制していた欲望が次第に表出していく様を、モノクロの映像で鮮やかに描き出す。
主人公の元大学教授・渡辺儀助を、ベテラン俳優であり儀助と同じくフランスと強い縁のある長塚京三が演じる。
妻に先立たれ、余生を都内の山の手にある古い日本家屋で過ごしている元大学教授・渡辺儀助は、年金と講演や執筆の仕事で得た預貯金を切り崩しながら、“来るXデイ”に向けて過ごしていた。それは、「毎月の支出からいつ預貯金がゼロになるかを割り出し、ゼロになった時に自殺する」というものだった。
日々の食事を全て手作りし、僅かな友人やかつての教え子、行きつけのバーで出会ったフランス文学を専攻する女子大生と過ごす。時に自らの加齢臭を気にしたり、身体の不調に悩まされながらも、季節は過ぎて行った。
そんな中、突如自宅のパソコンに送られてきた「敵が来る」というメッセージを皮切りに、次第に儀助は現実と妄想の狭間に飲み込まれてゆくー。
タイトルにある「敵」についての意味を探る時、ともすれば我々は、現在の世界情勢と結び付けて考えてしまうかもしれない。しかし、原作が発行されたのは1998年。本作で描かれる「敵」とは、全て儀助の中、それを見守る我々観客一人一人の中にある問題である。その事にアテンションするように、作中ではカトウシンスケ演じる新米編集者の犬丸が「ロシア問題か…」と呟いた際、すかさず靖子が「先生はメタファーの話をされているのよ」と訂正する。
現在31歳である私が思うに、本作で描かれている「敵」の正体とは、月並みだが“死”であり、“孤独”であり、何より“自分自身”に他ならなかったのではないかと思う。
預貯金から割り出した「あとどのくらい生きられるか」という計算に裏打ちされた“死”に対する覚悟も、ラストでは脆くも瓦解する。
外見では常に余裕を持ち、穏やかな姿勢で元教え子の鷹司靖子(瀧内公美)や女子大生の菅井歩美(河合優実)と接しながらも、密かに靖子への劣情を抱き、亡き妻である信子(黒沢あすか)の幻影を追って遺品のコートをクローゼットから引っ張り出して書斎のハンガーに掛ける。歩美の大学の授業料を負担すると申し出て、まんまと預貯金から300万円も失ってしまう。知人の湯島に語った「不思議と腹が立たない」という台詞にも、僅かな見栄があったのかもしれない。
トランクケースに溜まり行く、独りでは使い切れない程の量の石鹸は、儀助が妻を亡くしてから積み上げてきた“孤独”なのではないか。妄想の中で難民に向けて「好きなだけお持ち下さい」と自宅の塀の前にそれを置く様は、妻に先立たれ、友を失い、若い女に騙されて預貯金を無くした事で、自らの理性と自制心が限界を迎えてしまった儀助の「誰かこの孤独を消し去ってくれ!」という静かな叫びだったようにも思えるのだ。
だからこそ、儀助は自宅の庭に振り続ける冬の雨を前にして、「この雨があがれば春になる。春になればきっと、また皆に逢える」と、心の中で呟く。静謐で厳かな雰囲気を漂わせていた儀助の生活の下には、孤独と虚栄心に塗れたごく普通の老人、どうしようもない「人間」、「男」という性別の生き物の本質があったのではないか。
しかし、パンフレットを読むと、主演の長塚京三氏は更に深い領域まで渡辺儀助という人物を捉えている事が分かる。それは、フランス演劇・文学という高尚でインテリジェンスな分野に人生を費やして来た事から来る傲慢さ。妻の信子に注ぎ切れなかった愛情と侮り(「夫婦揃って貧乏暮らしをするなんて、君は耐えられなかったはずだから、先に逝ってくれて良かった」と口にする様や、フランス文学・演劇を専門としながら、一度たりともフランス旅行に行かなかった事)。性欲を自制心と虚栄心によって律する中で密かに、しかし確かに抱いていた下心。儀助が向き合う「敵」の正体とは、つまり彼がこれまでの人生で蔑ろにしてきたもの、それらからの“復讐”なのだと。
この事を受けて、私の中では心理学者のユングが遺した【向き合わなかった問題は、いずれ運命として出会うことになる。】という言葉が思い起こされた。
他にも、“老い”や“恐怖”といった様々な「敵」を、観客一人一人が想像するだろう。その正体が何であるかが明確に語られない以上、それぞれがそれぞれの「敵」を想定して鑑賞し、考察して行く他ないのだから。
しかし、こうした内容やポスタービジュアルが与えるシリアスな印象とは裏腹に、本作は意外にも儀助の人間的・男性的な滑稽さをコミカルな表現で描き出す様も目立ち、それが魅力の一つとなっていた。
靖子を想って無精し、翌朝無様に下着を洗う姿や、痔の検査で内視鏡を挿れられる際、まるで掃除機のコードのように内視鏡が勢いよく入って行く様などは、場内からクスクスと笑い声が漏れていた。
また、信子が儀助に「この人(靖子)の事を考えて。勃起して。一人でしてたんでしょ?」と問い詰めるシーンでは、「…した。でも、想像の中だけだ!」と返す儀助に「想像するのが1番悪いのよ!」と激昂する姿が面白かった。
モノクロながら、その彩りの豊かさを感じさせてきた数々の料理シーン・食事シーンは、本作の最大の魅力だろう。本作は一個人の老後の私生活を描くと同時に、優れた飯テロ作品でもあったと思う。
物語冒頭から、起床した儀助は米を研ぎ、電気コンロで鮭を焼く。自ら豆を挽いて食後のコーヒーを嗜むのがルーティン。
湯島からの土産の手造りハムは、ハムエッグにして手際よく蒸し焼きにする。
たまの晩酌では、焼酎のお供に焼き鳥を自作する。レバーは血抜きし、葱間を作って焼き上げる。
朝食の白米を少し余らせて、塩昆布でサッとお茶漬けにする手際が美しかった。
好物の麺類は、素麺や冷麺を楽しむ。この冷麺の為に、拘りを持って買ってきた辛口のキムチが、翌朝痔を発症する原因となってしまうのだが。茹で卵を四つ切りにし、白胡麻を挽く手際の鮮やかさからは何とも悲惨な末路。
しかし、そんな食材や栄養に気を遣った食生活も、「敵」を前にして次第に現実と妄想の区別が付かなくなってからは、最終的には簡単なカップ蕎麦になってしまう。こうした食に対する姿勢の落差にも、抗いようのない“老い”を感じさせる。
渡辺儀助役の長塚京三氏の演技力には、今更賞賛を贈るまでもないだろうが、監督がキャストを想定して脚本の初稿を書き上げたと語るだけあって、儀助という人物のリアリティのある説得力は素晴らしい。時に滑稽な姿さえ晒してしまう振り幅の豊かさも、長塚氏が積み上げてきたキャリアの賜物だろう。
鷹司靖子役の瀧内公美の美しさは、モノクロの世界に於いて抜群の存在感を放っていた。本人も「モノクロ映えする」と言われた事があるというだけあって、妖艶さと成熟した大人の女性さを兼ね備えた靖子役はハマり役だったと思う。