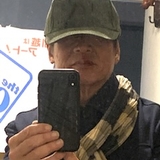「原作は「信用できない語り手」の悦子が一人称で語る(騙る?)小説 映画は母の語りを聞いて回顧録を編む悦子の娘ニキの視点が加わるメタ構造 モダンホラーと文芸作品の両面を持つ傑作」遠い山なみの光 Freddie3vさんの映画レビュー(感想・評価)
原作は「信用できない語り手」の悦子が一人称で語る(騙る?)小説 映画は母の語りを聞いて回顧録を編む悦子の娘ニキの視点が加わるメタ構造 モダンホラーと文芸作品の両面を持つ傑作
原作は1982年発表の日系英国人のノーベル文学賞作家カズオ•イシグロの長篇デビュー作『遠い山なみの光』(原題: “A Pale View of Hills”)です。この小説は1980年代初頭の英国に住む悦子という長崎出身の日本人女性が1950年代前半のある年の夏を回顧して書いたという形式で「わたし」(悦子)の一人称で語られます。
登場人物は悦子(映画では広瀬すずが演じています。’80年代の悦子は吉田羊)とその周囲にいる人々、夫の二郎(松下洸平)、二郎の父親で悦子からみると義父にあたる「緒方さん」(映画では三浦友和が演じています。二郎との結婚前から交流があるようで一時期は悦子の養父みたいな存在であったみたいなことが小説では示唆されますが、背景はよくわかりません。映画では小説より少しだけ具体的になります)、古くからの知り合いでうどん屋さんを経営している藤原さん(柴田理恵)、緒方さんのかつての教え子で今は緒方さんに批判的な松田重夫(渡辺大知)、そして、悦子にとってはその夏に知り合った新たな友人である佐知子(二階堂ふみ)、佐知子の幼い娘 万里子(鈴木碧桜)。一夏の間の(映画では1952年と表示される)、悦子とこれらの人たちとの直接的、間接的な交流が淡々と描かれます。
そして、80年代パートには悦子の娘ニキ(カミラ•アイコ)が登場します。原作小説は悦子の一人称語りなので視点が悦子から動くことはありませんが、映画のほうでは、ライター志望のニキが母親の語りをもとに自分の英国人の父親と結婚して英国にやって来た母親の回顧録を書こうとしているという設定が新たに加わり、80年代パートはニキの視点で描かれていると思われます。また、ニキには日本生まれで悦子といっしょに英国に渡ってきた景子という姉がいたのですが、自死してもういません。50年代パートで語られる夏は悦子が未来の景子を妊娠していた時期です(この景子という名は、50年代には既に亡くなっていた緒方さんの妻、すなわち、悦子の義母の名前からとったと原作小説にはありました)。
さて、50年代パートですが、登場人物それぞれのその夏の様子のみが描かれているだけの感じで、それ以降の彼ら、彼女らの消息がまったく描かれていません。また、それまでの各人の背景についてもあいまいな感じです。特に原作小説のほうは余白がたっぷりととってある感じですが、映画のほうでは原作のままでは映像作品として成り立たないからなのか、多少は具体的になっています(それでも原作小説ほどではないにしろ、余白たっぷりです)。
小中学校レベルの図形の問題を解くときに「補助線」というのを使うことがよくあります。的確な補助線を一本引くと難しいと思われた問題がたちどころに解けてしまう…… この映画は、ちょっと掴みどころのない印象のあるカズオ•イシグロの “A Pale View of Hills” いう小説に対して「文学的補助線」を引こうとしているようなところがあります。ただ、幾何の問題なら解答はひとつで補助線一本でめでたく正解に到達してカタルシスを感じるということになるのですが、こっちのほうは、その補助線によって新たなものが見えてきたと感じるかもしれませんが、余計なお世話だと思う原作読者もいるだろうし、補助線のおかげで逆に謎が深まったということもあるかもしれません。原作既読者からしてみると評価が別れる映画かもしれないと感じました。
私が原作小説を読んだときに感じたこの小説のいちばんの魅力はカズオ•イシグロの書く会話の面白さでした。例えば、悦子と佐知子の会話。現状を肯定し、緒方さんの示すような古めの価値観も支持して今いる現状の中に幸せを見い出そうとする悦子に対して、プライドが高く現状に満足せず、海外に出てゆくことで新たな一歩を踏み出し、幸せを掴もうとする佐知子…… 映画のほうで少し残念だったのは悦子のほうが方言を使っていて、それがノイズに感じられたことです。小説のほうでは悦子も佐知子もたぶん当時の育ちのいい日本人女性が話していたであろう標準的でニュートラルな日本語で話しています。考えてみれば、原作は英語で書かれているわけで、訳者の小野寺健氏(故人。1931年生まれで悦子とほぼ同世代と思われます)の訳が十分な成果をあげていると感じます。他に緒方さんと二郎の父子の会話、緒方さんと悦子の会話あたりも含めて会話は全般的に小説のほうに魅力を感じました。
原作と映画の決定的な違いは、30年後の悦子が語る50年代パートの悦子と佐知子に関して、小説では微妙な違和感を示すだけにとどめているのに対して、映画では悦子と佐知子が実はひとりの人間であることを映像で示すところまで踏み込んでいることです。それを終盤に「伏線回収」するために悦子と佐知子の演出があざとくなっている印象を持ちました。特に佐知子は終盤に悦子に「回収」されてしまうため、映画ではだんだんと精彩を欠いてゆくように演出されている感じで、小説の佐知子のほうが魅力的だと思いました。ということで、先述した「補助線」でもっとも重要な線は悦子がニキに語る30年前の長崎での出来事に潜んだ大きな嘘を暴いてしまうというこの線だと思いますが、この補助線は引いてもよかったのでしょうか。
あと、終戦後80年の節目の年に上映されたからかもしれませんが、「戦争」とか「原爆」とかいうキーワードにこだわり過ぎている感があるのも気になりました。原作小説にはない、二郎の傷痍軍人設定や悦子が夫にする被曝の有無に関する質問などは屋上屋を架すような感じです。カズオ•イシグロの伝えたかったテーマはもっと普遍的で幅広いものだ思います。私が特に印象に残った登場人物にうどん屋を経営している藤原さんがいます(映画では柴田理恵が演じてました)。彼女は軍人の奥様かなんかで裕福な暮らしをしていたのが、戦争に自分と長男以外の家族全員を奪われ、うどん屋を始めたのです。もうこれだけで戦争と戦後のリアリティを感じることができます。プライドの高い緒方さんや佐知子からの「上から目線」を感じながらもプライドをかなぐり捨てて前向きにうどん屋を続ける藤原さんの姿は、新しい女性の生き方を示しているようで実は男頼りの佐知子に対するアンチテーゼのようになっていますし、終戦で価値観が大転換した後、うだうだと観念的な言い合いをしている緒方さんと松田重夫のような男たちとも対照的です。このあたりの登場人物の配置の仕方はさすがカズオ•イシグロだと思いました。
といったところで、ここで原作のほうではなく映画のほうの美点を挙げたいと思います。私はニキをライターにして、そのニキが母親の回顧録を書く目的で母親の長崎時代の話を聞くというメタ構造にしてニキの視点を入れたところだと思います。原作小説にももちろんニキは登場しますが、悦子の一人称で書かれた小説なので悦子の目から見たニキになります。この映画の80年代パートは、ニキ、それも50年代の悦子がそうだったように新しい命を胎内に宿している状態のニキが母の話を聞いて回顧録を書くのです。ニキは母の話が不自然だったり、錯綜していたり、矛盾点を含んでいたりするのに気づきます。
そして、「ママ、ケイコの死はママにとっていくら悔やんでも悔やみきれないことで墓場まで持ってゆくような後悔の念なのでしょう。ママは自分の選択のせいでこうなったとして、過去が直視できないのね。私はママは悪くないと思う。そんな嘘はやめてもっと楽になって前を向きましょう。ママはこれまでもこれからも私のロールモデルよ」そう、あの悦子の嘘を暴く補助線はニキが引いたのです…… とすれば腑に落ちると私は感じました。まあでも、ニキがどんな回顧録を書くかは定かではありません。悦子が信用できない語り手であったようにニキも信用できない語り手になる可能性もあります。この作品はミステリ味はありますがミステリではないので、一連の出来事の背景が分かり、真実にたどり着いてカタルシスを味わう、なんてこともありません。結局、謎は謎のままでこの不条理劇は幕を閉じます。
ミステリではないと書きましたが、ホラー風味はあります。川の向こう側というのは「死」のメタファーなんでしょうか。そうすると川は「三途の川」ということになります(ちょっと古典的)。可哀そうな子猫たちは三途の川を渡ってしまいました。ロープは「束縛」のメタファーなのかな。親の子に対する束縛、夫の妻に対する束縛、師の弟子に対する束縛……
まあ結局、身も蓋もない言い方をすると、謎は謎のまま、観客をケムに巻いたまま物語は終わるのですが、そこはそれ、ノーベル文学賞作家カズオ•イシグロ原作の作品ですから、文芸作品ぽいテーマを見つけておきたいです。人は時としていくら悔やんでも悔やみきれない後悔の念を持つことになって真っ暗闇の中にいるような気分になることがある。でもその真っ暗闇の中でも丘の向こうに淡い光が差しかけているので、それを頼りに前に進もう、といったあたりのことでしょうか。”A Pale View of Hills” というタイトルにも、そんなメッセージが込められているように感じました。
原作既読者としては、映画化がけっこう難しい小説ではないかと思っていましたが、映画を観て不満点もあるけど、よくできてるなと感心しました。鑑賞後に原作小説を再読してみましたが、前にも増して味わい深かったです。ということで、レビューが小説と映画の合わせ技みたいになって長くなりましたが、実まだまだ書きたいことがたくさんあって自分でもびっくりしています。長文、失礼しました。
共感ありがとうございます。
この映画にはモヤモヤしていましたが、理由が言語化できませんでした。
こちらのレビューで腑に落ちた気分です。
石川慶監督は、「アーク」しか観てないのですが、やはりモヤモヤしてしまいました。
原作小説を映画にする場合の、どこに「補助線」を引くかが、観る人の何に引っかかるか、分かれるところかもしれませんね。
こんばんは、やはり映画は原作本と違って目の前の映像の印象が強いぶん自由な想像がしにくい、そしてナレーションを多くとれないため視聴者の状況理解が不十分なのは仕方ない気がします。
映画レビューが良い悪いの両極端なのも、映画表現の難しさか…
原作未読ですが映画との違いの解説、ありがとうございました♪
こんにちは^ ^
レビューにイイネ有難う御座います☆
深過ぎるレビューに目から鱗でしたorz
川がメタファー…で長女が舟に横になっていましたね‼︎いろいろ気付けました、
有難う御座います♪♪
Freddie3vさん
カズオ・イシグロ作品への愛に溢れたレビューですね 📙
数学の『 補助線 』の例えはとても分かり易くなるほど、と感じ入りました。
原作を未だ読んでいませんが、本作を思い浮かべながら読んでみたいと思います。登場人物が本作のキャストの皆さんとして脳内処理されますが ☺️
女優陣の皆さんの熱演が、より作品を輝かせていましたね。鑑賞者に思考させてしまう、という意味でもとても魅力ある作品だと感じました。
共感ありがとうございました。
解釈の自由度が高いということは、意外に映画化しやすいのかもしれません。イシグロは大の映画マニアらしいので戦略的に映画監督をひきよせているのかも……
共感ありがとうございました。Freddie3vさんのレビューがまさに補助線となって、より一層この映画の余韻が深まりました。ありがとうございました。
「原作小説の方が余白たっぷり」とおっしゃっているのを読んで、きっとそうだろうなと思っていたので、スッと胸に落ちました。読んでみたくなりました。
恐るべきは、今作を20代で執筆したカズオ・イシグロですね。
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。