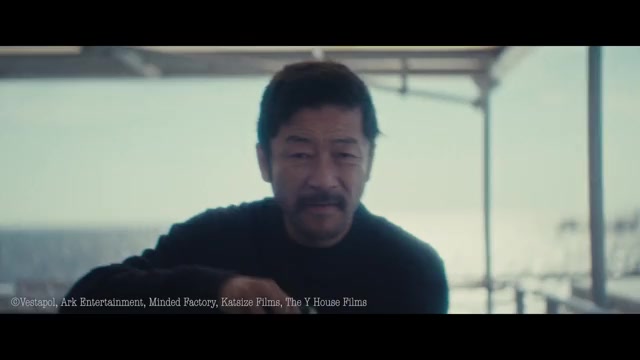レイブンズのレビュー・感想・評価
全64件中、1~20件目を表示
難しいニュアンスとバランスを見事なまでに妖しく成立させている
英国人監督が日本人写真家についての映画を撮る。そこには無数の超えるべき壁があったに違いないが、結果として、一瞬にも永遠にも等しい幻想的かつ生々しい生き物の記録へ結実した。主人公の生き様を体現する浅野の演技はどんな状況にも流れるように身を任せ、その中にほのかな可笑しみをにじませる。言ってしまうと2時間、似たようなぶっ飛んだ演技が続くわけだが、しかしこの人の表現の引き出しの豊富さには舌を巻く。観ているだけで飽きさせないし、ぶっ飛んだ中に確かな感情の揺らめきが感じられるのだ。そんな主人公と対峙し、彼を照らす月のような存在の瀧内もこれまた秀逸。加えて古舘、池松が確かな存在感で彩り、さらに特殊造形によって具現化されたカラスの化身の訪問と英語による語りかけが、この映画の唯一無二の幻想性を高めていく。これら全てにおいて難しいニュアンスとバランスを見事に妖しく成立させたギル監督の情熱と表現性を評価したい。
浅野忠信、世界へのさらなる飛躍を予感させる渾身作
本作については当サイトの新作評論枠に寄稿したので、ここでは補足的な事柄をいくつか書いてみたい。
まず俳優・浅野忠信の魅力が英国出身のマーク・ギル監督によって存分に引き出された一本と言える。評論で触れたように監督は「殺し屋1」を観て以来の浅野のファンであり、クールな外見と内に秘めた狂気などのような相反する二面性を活かして、矛盾を抱えた写真家・深瀬昌久の人物像をヴィヴィッドに造形しているし、浅野本人のアーティストとしてのセンスも役作りに有効だったろう。
評を執筆する前のリサーチで英文記事にいくつか当たったが、“「SHOGUN 将軍」のタダノブ・アサノが主演”という紹介が多いのにやや意外な思いもした。というのも、浅野は「マイティ・ソー」でハリウッド進出を果たしたほか、マーティン・スコセッシ監督作「沈黙 サイレンス」など外国製作や合作の映画にも多数参加してきたので、すでに国際的な俳優として認知されていると(日本にいる映画ファンとしては)思ってしまうけれど、ゴールデングローブ賞の助演男優賞を受賞した「SHOGUN」がまだ枕に必要なくらいの認知度なのか、と。とはいえ、GG賞とエミー賞で「SHOGUN」が席巻したことは出演者らの今後のキャリアの大きな足掛かりになるだろうし、さらに浅野は「レイブンズ」(日・英・仏・スペイン・ベルギーの合作)での熱演も評価されて、国際的なプロジェクトからのオファーが一層増えるだろうと予感させる。
外国人監督が撮った日本の映画として、日本の人物や文化・社会の描写に違和感のない真っ当な作品に仕上がった点も評価したい。ギル監督が深瀬の写真の権利関係をクリアしたことをはじめ、鰐部洋子やバーの店主・南海(なみ)ら存命の関係者に直接会いコミュニケーションを取れたことも、登場人物らと物語の真実味に大いに貢献しただろう。監督のデビュー作「イングランド・イズ・マイン モリッシー、はじまりの物語」では、実はモリッシーが在籍したバンド、ザ・スミスの楽曲を使用する権利が得られず、モリッシーがバンドを組むまでの若き日々に限定して描くという苦肉の策をとらざるをえなかった。その点でも、ギル監督はこの2作目でようやくやりたいことを思いっきりやれただろうし、彼にとってもまた飛躍の一作になるはずだ。
Through the Raven’s Eye
Fukase was one troubled soul who found his way to being one of the most influential photographers of our fashionable era. Befriending an imaginary crow that's as horrowing and adorable as Donnie Darko's campy bunny costume, Asano naturally leads Ravens as a pseudo-psychological headtrip into the pangs of strict uprbinging and eventual entrepreneurship. A European production organically Japanese.
アーティストの極、日常生活者の極とカラス
浅野忠信と瀧内久美のW主演。さすがの演技力に賞賛!!
U-NEXTでポイント交換で視聴しました。
アーティストって辛いなと実感。
映画感想文を読んでみてください。
【映画批評】
アーティストは、放っておくと自己の表現を突き詰めるためにいつか人間破綻してしまうのではなかろうか。それをつなぎとめるのはパートナーの存在であり、自分が信じる何かがうまくバランスを維持し人間生活をおくっているのではないか。
深瀬はアーティストになる、日常をまっとうにおくる人になる、この両極を持っていた。その両極で自己葛藤しているのがカラスとの会話だ。自己葛藤を映像化するのは難しい。それゆえ作り手は巨大なカラスを登場させ深瀬のアーティストの極を前面に押し出していく。そして深瀬はアーティストの道を歩む。
ある日深瀬は魅力的な女性、洋子と出会い恋に落ち結婚する。洋子をモデルにした写真を撮りまくる深瀬はまさに女神をえたアーティストとしていきいきとしていた。しかし洋子はアーティスト深瀬を愛したのではなく、一人の男を愛した。深瀬に日常生活をおくる人生を要求し、アーティストの狂気を愛せなかった。
深瀬は洋子をえたことでアーティストの極と人間生活をおくる極がうまくバランスをとって生きていた。二人が破綻したことによって深瀬はまさに破滅していく。一方の極を完全に失ったからだ。
洋子と別れた深瀬はアーティストの極にふれて偉大なアーティストになったのか。否である。洋子という女神が去ったため深瀬は両極のバランスを完全に失ってしまったのだ。深瀬は洋子と別れてから二回の個展を開催した。しかしそこにある写真はすべて深瀬のカラスとしての残りかすだ。深瀬はもはや深遠なアートは撮れない。洋子がいないからだ。つまり深瀬は洋子と別れてから事実上死んでいた。
ラストシーン、洋子が深瀬の見舞いに来て病院を出てから歩く洋子の表情をカメラはずっとおう。洋子の表情は後悔の一念しかなかったのではなかろうか。自分がアーティスト深瀬を理解しパートナーとなっていれば。でもそれでは自分をコントロールできない。そんな洋子の心の葛藤が表情からにじみでていた。深瀬と洋子が出会い愛し合った幸福と不幸が、まさに二人の両極の描写が切なくて胸をうつ。
芸術と死に取り憑かれた男
「深瀬は静かだけれど、狂人だった」知る人は口を揃えてそう言った。
私が一番知りたかったことは、イギリス人のマーク・ギル監督が、
日本人にもあまり知られていない写真家・深瀬昌久の生涯を知り、
妻・洋子とのラブストーリをどうやって知り、
こんなに綿密な脚本が書けたのか?でした。
謎はギル監督本人が語っている。
以前から日本の写真家に興味があり、森山大道、荒木経惟、深瀬昌久を
知っていた。
そして2015年に英国のガーディアン紙に深瀬の記事が載った。
さらに2016年「ブリティッシュ・ジャーナルofフォトグラフィ」が
深瀬の『RAVENS』の中の「鴉」の写真を過去25年で最も
重要な写真に選んだ。
そしてその紹介記事を読むと深瀬昌久と妻・洋子の波乱に満ちた
濃密な愛の歴史に深く興味を惹かれたそうだ。
深瀬には『殺し屋1』の浅野忠信しか思いつかないほど深瀬に
合っていると思いオファーをすると2016年のうちに快諾を得た。
他に「深瀬アーカイブ」のスタッフよりも情報を得たそうだ。
ここで浅野忠信は言う。
もう日本では浅野忠信を主役にした映画は殆ど企画されない。
その現実を考えたし「主役には主役にしか表現できないことがある」
彼は思う存分に役作りする主役に飢えていたのだ。
深瀬昌久(1934年~2012年)
篠山紀信(1940年~2024)アフロヘアー、そして妻が南沙織。
荒木経惟(1940年〜)・・・天才アラーキーを自称、
森山大道(1938年〜)海外でも評価が高く、
多くの賞を受賞している。
岩合光昭(1950年〜)動物写真家で国民的人気があり
猫の写真に定評あり。
現代日本を代表する写真家は、横山・荒木・篠山紀信、岩合、
有名で知っているのはこの4人だと思っていました。
そう言うわけでマスコミに登場しない、
記事も載らない、
写真も見たことがない深瀬昌久は、
聞いたことがありませんでした。
(彼は1992年にバーの階段を落下して脳挫傷を負い、
重度の障がい者となる。
ただただ20年、特別養護老人ホームで生き延びていた・・・
・・・本人に自覚がなくて本当に良かった・・・)
北海道の名寄市の写真館・深瀬の長男に生まれて、重圧の強い父親の
深瀬助造(古舘寛治)を説き伏せて上京して日大芸術学部を卒業。
写真の技術は父親から徒弟制度で5歳からスパルタ式で習った。
映画の中でも、子供の頃、暗室に閉じ込められた・・・とあるのは、
父親に反抗して折檻されたのでしょう。
昌久は父親への愛憎が強く(肉親に愛と共に、憎しみとまで行かなくても、
恨み辛みのない子供は、まずいませんから、)
生涯頭が上がらなかった。
深瀬昌久の写真集を年代順にあげると、
1、遊戯(1971年・・・ユニークな視点と実験的なスタイルが特徴。
2、洋子(1978年・・・妻・洋子を被写体にした代表作。
★★
1974年渡米・・・ニューヨークに呼ばれて近代美術館で展覧会・・・
・・・脚光を浴びるものの、はしゃぐ妻・洋子を苦々しい顔で
シニカルにみつめる昌久。
ニューヨークの帰路・・・二人の気持ちの齟齬は甚だしくなり、
遂に洋子はそのまま出ていく。
★幸せは居心地悪く、“ぶち壊さなければ気が済まないクソバカ“
と、洋子は言う。
洋子が去り自殺癖は激しく、助手の正田(池松壮亮)に
手伝わせて首吊りを図りものの、正田は当然止めてしまう。
もともと独り言が多かったと言う深瀬、
★☆この映画のもう一つのユニークな仕掛け。
深瀬の分身である大きなカラスが、英語を話す。
深瀬の心の声なのに、
説教をしたり理論武装をして、深瀬をとっちめたりする。
そのカラスのヨミちゃんには、CGを使わずに、
ホセ・ルイス・フェラー
という日本の滞在経験を持つ舞台俳優が低いドスの効いた声で語る。
★このファンタジー設定は賛否があるそうだが、私は好き。
英語を話すカラスとの対話を聞くと、さらなる深瀬の心の闇
日常的に起こる双極性障害の傾向が明らかになるのだ。
★★☆
洋子の去った痛手からやっと立ち直り、猫に傾倒して被写体にする。
トラ猫のサスケとモモエを写した
1979年「猫の麦わら帽子」を刊行
1979年には「鴉1979年」の写真展も開催している。
1985年には10年ぶりに故郷・名寄の深瀬写真館で
「家族」で制作再開。
1986年-写真集“鴉」を刊行
1987年父・助造が死去。
道北の名寄市は過疎化と高齢化が進み、札幌まで車で3時間。
七五三や結婚写真は都会で撮影するようになったのだろう。
助造は写真館の前途に悲観して自殺。
1988年「父の記憶」を銀座ニコンサロンで開催。
1989年、深瀬写真館が廃業、
妻・洋子役の瀧内公美。
髪型や化粧で変幻自在に変わる女優。
衣装を着ても性格まで変えられる魔性そして優しさ。
強過ぎる個性の者のぶつかり合いが凄まじい夫婦だったが、
深瀬は不器用な愛し方しかできなかった。
ラストで本人と洋子さん、そして作品が次々と紹介される。
私は「家族写真」が一番好き。
10人なら10人全員にライトが当たり、全員が幸せそうに、
満足そうに笑っている。
コスプレした「浅田家!」も好きだけれど、
「深瀬家」も素敵な家族、みんなが良い顔をしている。
フランス・日本・ベルギー・の4カ国合作。
まるで私小説のような和風な趣と英語を話す大きなカラス。
逆輸入された深瀬昌久は、マイク・ギル監督により
墓場から復活を遂げた。
死んでから有名になった芸術家・・・
きっと本望だろう。
最後に、
《仮説》
深瀬は・・鴉は自分だ‼︎
と言うが、
《鴉は、父親、だったのではあるまいか?》
モーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」を見たとき
思った。
父親が死んで、亡霊になって現れる。
モーツァルトは死期が近いのだが、その父親の亡霊が、
モーツァルトを地獄へ引き摺り込む。
鴉のように黒いマントを着て震え上がるほど怖くて、
モーツァルトも「死神」のように怯える。
有名なオーケストラ曲の怖いこと、
私には《鴉と父親》が重なるのだ‼︎
鴉の名は“ヨミちゃん“
黄泉の国、からの使者だった気がする。
そしてバー南海の階段で深瀬の背中を蹴ったのは、
“鴉“だったと、そう思う。
興味深い人生
不勉強ながら、この人の事を知りませんでした。鑑賞後に調べたらかなり有名な方で…映画になるくらいだからそりゃそうかとも思ったけど…とにかく変わって人と思って見てたけど、幼少期の環境を考えたらそうなるかとも思ったりもする。冒頭から出てくるカラスが物語の途中で時々出てきて主人公に問いかけをするが、それが面白い☺️この映画のアクセントにもなってるし、深瀬のターニングポイントにもなってるし、我々観客の思考を誘導する…色々と考えさせられる。彼はネガティブな考えや被害妄想的な所も多くて自業自得とも思ったりもするが、ある意味可哀想な人でもあるが、考え方は人それぞれなのでそーゆーもんかとも思ったり、とにかく人生について色々と考えてしまった。特に正解もない話だし、いいとか悪いとかそーゆー話でもないが、この映画を見た事により色々と学びはあったので、みて良かったと思う😗自分の中にもカラスはいるのだろうか…
【”ピクチャーズ・オブ・ユー。そして、あの烏は俺だ。”今作は支配的な父に写真を教えられた男が写真家として名を上げるも、被写体の妻には写真でしか愛を伝えられなかった不器用で哀しき姿を描いた作品である。】
■北海道の実家の父(古館寛治)が営む写真館を継ぐ事を拒否し、上京した深瀬(浅野忠信)は、写真家を目指しながら酒を喰らって彷徨う日々を送る。
そして、洋子(瀧内公美)と出会い、その黒髪が際立つ美しさと目力の強さと気性の激しさに惹かれ結婚する。洋子は深瀬の写真の主題となり、二人は革新的な作品を生み出し、写真界で認められて行く。
だが、能楽師になる夢を持つ洋子と深瀬の関係は徐々にすれ違って行くのである。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・今作では随所に登場する烏の形をした男が、深瀬に話しかける。だが、他の人には烏は見えず、深瀬が独り言を言っているように見えるのである。深瀬の心の闇を烏は代弁しているのである。故に深瀬は劇中で屡々”あの烏は俺だ・・。”と呟くのである。
・深瀬が毎日、定時にきっちりと通うボロイアパートの2階にあるスナック南海。あんな素敵なママ(高岡早紀)がいるなら禁酒が解けたら通いたいモノだが、深瀬は大体朝まで飲んで泥酔し、”俺が死ぬとしたら、あの階段から落ちた時だ。”などと口走っているのである。
・今作では、矢張り深瀬を演じた浅野忠信の、父との確執の中で魅せる狂気性を帯びた演技や、瀧内公美の長き美しい黒髪に彩られた意志の強そうな眼が印象的な顔が、抜群である。優れたる俳優は凄いモノだと、素直に思ってしまうのである。
■今作では、フライヤーにも記載してあるが、元ミュージシャンのマーク・ギル監督の選曲が光る。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの名曲”毛皮のヴィーナス”や、”ユア・ミラー”が洋子との関係性を描く中で効果的に使われているのである。
・自らの過ちで洋子と別れた深瀬は、数々の賞を得ながらも彷徨う日々を送り、若き日に言っていた通りに、泥酔しスナック南海の急な階段を転げ落ち、脳を損傷してしまうのである。
<ラストシーンは切ないし、グッと来てしまう。病院の椅子に座り黙って外を見ている深瀬の元を訪れる白髪が出来始めた洋子。彼女は優し気に話しかけるが、深瀬は既に答えられない。
このシーンで流れるのが、”ザ・キュアー”の名曲”Pictures of You”なのである。
”僕の君の写真。僕が君の写真以上に望んでいたのは、世界には何もないんだよ・・。”
この曲は大変な好きな曲でもあるのだが、余りにも哀しい深瀬の姿と重なると、思わず嗚咽が出そうになってしまったのである。
今作は、旧弊的で支配的な父に写真を教えられた男が写真家として名を上げるも、被写体の妻には写真でしか愛を伝えられなかった不器用な男の哀しき姿を描いた作品なのである。>
<2025年5月25日 刈谷日劇にて観賞>
「最初のレビュー瀧内公美さん」
ある写真家の一生。
全くノーマークでしたが、雑誌で写真家の映画である事を知りラストだったので急いで鑑賞しました。
深瀬昌久って写真家は初めて知りました。昭和の伝説の写真家のようです。
写真館の家に生まれて家業を継ぐよう厳格な父に育てられ、耐えきれず家を飛び出して東京で酒、女、ドラッグに溺れていきます。破天荒で狂ったような一生が故に大胆でグロテスクな写真を撮れたのは十分に理解できました。酒、ドラッグのおかげで自分では意識はしていないが、常識には囚われないぶっ飛んだ写真が撮れたこともあったでしょう。
私も写真を趣味としていますが、せこせこデスクワークをしている身ではとても撮れない写真です。なので彼の一生だけでなく、もう少し写真の事を掘り下げるシーンが欲しかったところです。
自宅の団地の窓から、はにかむ奥さんを定点観測的に撮っていくシーンが印象的で彼女に出逢わなければ、彼はもっと早死にしていたと思います。
やはりそれなりの芸術家は狂人か変人である要素が必要ですね。
凡人である私は静かにネイチャー写真を撮る事にします。(泣)
カラスはオレかぁ、、、。
荒木をモデルにした映画かと思ってた。
深瀬の事は不勉強で知りませんでした、すいません。
でも劇中に出てくる写真は見た事有るのが色々、、特にカラス。深瀬の中のもう1人の深瀬としてカラスマン(ちゃんと瞬きしたり指の造作もレベル高い)は登場する、ちょっとダークなファンタジー的な作りですが芸術への真剣さ故崩壊していく様はかなり生々しく描かれていると思いました。奥様の濃厚なキャラも瀧内さんががっつり取り組んでてよい恋愛映画とも言えると思います。作りの良さと構成の巧みさは海外の監督だからかなぁ、、、。
英名レイヴン=和名オオガラス(ワタリガラス)Corvus coraxという種類で、日本は北海道の北の方にしか居ないのです。その辺のカラスとは違うのよ。
大切な人を手放す愚か者
写真家・深瀬昌久を知る
北海道の高校を卒業した深瀬昌久は、父の写真館を継がずに上京し、美しい強い女性・洋子と結婚した。洋子は深瀬の写真のモデルとなり、革新的な作品を生みだした。しかし、深瀬の心の闇から彼女に傷害事件を起こし離婚されてしまった。その後、酒に酔い、階段から落ちて脳挫傷となり、2度と写真を撮ることは無かった彼の半生を描いた事実を基にしたファンタジー作品。
深瀬昌久の事を全く知らず、鑑賞前にぐぐって一応彼の生涯を把握してから鑑賞した。
レイブンズってカラスの事らしいが、英語を話すカラスが出てきて哲学的な事を言ってたが、なんのこっちゃ?だった。
あれはファンタジーだったのはわかるが、カラスの所だけがファンタジーなのか?洋子と離婚後新しい女性と再婚してる筈だが、そこは描かれてなかった。
で、深瀬昌久という写真家がこんな人というのはわかったが、凄いとは全く思えずさっぱり興味持てなかった。
狂気を見せた浅野忠信は上手かったんだろうけど。
洋子役の瀧内公美も存在感有った。
カラス役の 声による圧倒的な演技
ふらっと映画館に入って、これ観てみようかな、という軽い気持ちで鑑賞しましたが、観て良かったです。写真家・深瀬昌久さんのことも、そのミューズであった妻 洋子さんのことも何も知りませんでしたが、深瀬昌久さんが写真館を営む父親との間で抱え続けた葛藤や、心の闇が生み出したカラスと対話する様子などが巧みに描かれていました。
妻の洋子から「カメラの後ろに隠れないで、人の目で私を見て」と言われても、何をどうしたら良いのか分からず、戸惑い、どこか踏み出せない深瀬昌久の様子を浅野忠信さんが、眩しいばかりの奔放さで深瀬昌久のミューズであり続けた妻 洋子を瀧内公美さんが、時にぶつかり合いながら苦悩を共に生きた夫婦をよく演じていました。個人的に瀧内公美さんは、1人で立っていても、傍に男性がいる(男性に腕や身体?が絡んでいる)かのように感じてしまう不思議な女優さんなのですが(って、こんな事を書いたらご本人に失礼ですよね。この場でだけこっそりと自分からみた印象を打ち明けておきます)、女の情とか情念を表現する役によく合うように感じました(光る君へ、でもそういう役だったかな)。
この映画で驚いたのは、カラスの声を担当された、ホセ・ルイス・フェラーさんという方。無知なのですが、舞台俳優の方でしょうか?深瀬昌久に内省を促すカラスの存在は、この作品では不可欠に感じますが、映像には、CGではなく、人間より一回り大きいカラスのロボット?のような姿で現れます(着ぐるみではないんじゃないかな)。このカラスのキャラクターは、日本の天狗とか、能楽などにヒントを得て設けたもので、監督にとって一つの挑戦だったそうですが、カラスの声(英語で深瀬昌久に語り掛けます)が、ものすごく説得力があってストーリーに引き込まれます。シリアスな場面に着ぐるみのようなものが出てきたら、もしかしたら少しコミカルにみえてしまうかもしれないと思うのですが、カラスの語り口の重厚感と説得力が凄かったです。声による演技の凄さを初めて知りました!
父の記憶が…
深瀬昌久の名は、写真集「父の記憶」を人に見せてもらって知った。その当時で写真集は絶版だったし、写真家がゴールデン街の階段で転落し、再起不能となり、新作が出るのは絶望的なことも知った。そういう前情報が、写真を見るのにフィルターをかけたかもしれないが、事情を知らずとも「父の記憶」は切なくて泣ける写真集だった。深瀬家の家族の歴史と、父への思いが胸を打つ…それが…あんな独善的で暴力的なお父さん!? あまりのギャップに呆然。まあ、この映画は伝記じゃないからね、これが事実というわけではないよね。
まあ、私にとっては深瀬昌久は「父の記憶」のイメージだけど、英国人監督にはもっと前の写真集「洋子」や「鴉」のイメージなのだろう。「レイブンズ」のタイトルもカラスだし、カラスが主人公の語り相手だし。このしゃべるカラスってのが、好みの別れるところかもしれないが、私はけっこう好きかな。カラスくんのおかげで、実在の人物を描いていても、どこか架空の出来事めいて見える。これは、日本人が深瀬を描くより、外国人の監督の方が、いい距離感なのかもしれない。洋子さんも、イギリス人だから映画化を許可したのでは、と推測する。そして、写真使用の許諾も取ったのはグッジョブだ。長らく深瀬の写真集は入手できなかったが、最近再販されたので、映画きっかけで売れるといいね。「父の記憶」も、私の記憶がおぼろげなので、また見たい。
洋子の登場シーン、フレームに現れてピントがバチっと合った瞬間にシビれたー。あの登場の仕方、うますぎる。瀧内公美の目が強くて、とてもいい。蠱惑的で、享楽的で、自己主張のはっきりしている洋子。でも、自由を欲しつつ、枠がないと少し不安、という感じがした。若い洋子は芸術家のミューズを楽しんでいたが、芸術家の不安定さを支えるには、自身も不安定だったのかな。でも、歳相応に成長変化したので、深瀬を最後まで見守れたのかも。
浅野忠信は写真家の役をやるの3度目じゃない? 縁があるのね。とはいえ、「地雷を踏んだらサヨウナラ」も観てないんだけど。ひとつ気になったのは、左目が閉じ気味なことかな。右利きなら右目がファインダー、左目は開けたまま被写体の状況を確認しながら、シャッターを押すというワザができると、とてもプロっぽい。次にオファーが来たら、ぜひ使ってくださいませ。浅野忠信のこの映画の一押しシーン…久しぶりに再会した洋子に再婚したと言われ、喜びからがっかり、持ち直すが視線泳ぐ、ここの表情の変化が最高にチャーミングだった。
エンドロールのthe cureは、まるでこの映画のために作られたかのようにぴったり。これだけでおしゃれ度が爆上がり。そして、不遇な最期と見られがちの深瀬を、こんなキラキラしたサウンドで彩ると、人がどう思おうと、本人は精一杯楽しんで生きたんだと、全肯定しているようで、とてもポジティブな締め方だった。
40にして成せなかったダメ男を名優:浅野忠信さんが好演技(高演技)で魅せてくれました
著名な写真家をモデルにした映画なので、観ました。
日大芸術学部卒業の異色写真家の深瀬昌久さんは、モノトーンの象徴として、カラスの写真を撮り続け「鴉《Ravens》カラス」と言う写真集を出版し、著名になったが、
映画の中では、洋子を自分が独占した被写体として写真を撮り続けた事を、成功への階梯として焦点を当てている。
その中で、深瀬昌久さんを読み説く"切り口"として、カラスを使ってはいるが、彼を表現するには、それだけでよいのであろうか?
登場する"江戸川乱歩"風カラスと、被写体としてのカラスの同期的な結びつけとを、本人と被写体である洋子との真逆に位置する関係性として
いまひとつ描ききれていなかったのに、食滞感を残した。
深瀬昌久さんは、自分と被写体とが"主客未分"となる関係を重んじた為に、被写体であった妻:洋子との関係が 上手くいかなくなると
被写体を烏に換える。
カラスをシュールに撮り続けても、自分との距離感が埋まらない事を感じ
被写体を猫、そして自分自身に次々と換えていく事に成る。
人間には見る事ができない‘’紫外線‘’が見える生物は数多く存在する。
カラスもその中の1種で、カラスの羽根には、人間には見えない"個体差が有る模様"が入っています。
その事を大学で学んだ深瀬昌久さんは
人間には見えない模様を、あえてモノトーンで撮り続けましたが、
心の葛藤として、”カラスが自分"なのか、"カラスが父親"なのかを、”カメラ”と言う共通した宿命を持った親子関係をも交えて、彼自身でも整理しきれなかった多々の関係を、もっと鮮明に打ち出す脚本にした方が、
彼のモノトーン写真に拘った事が、心の葛藤として、表現できて、深瀬昌久さんがカラスに執着した葛藤とも重なり、素晴らしいATG映画(アート・シアター・ギルド)的な仕上がりになったと考えます。
写真家をテーマにした映画だけに、光と影の撮り入れ方や、オレンジと青の照明の明暗の使い方が、絶妙に優れていました。
ちなみに、彼が写真家としていた愛機は、コンタックスRTS、ニコン F2・F3であり、洋子をマンションから望遠レンズを使って撮影していた"スナップ写真"には、ふたりの関係性がとても良く現れています。
本筋には、関係してこなかったが、要所要所に重要な位置を占めていた母から貰ったカメラは、最新鋭のカメラではなく、ドイツ・Kodak や Zeiss(Carl Zeiss)、 Agfa といった蛇腹沈胴式機械カメラでもなく、当時では古くても まだ高額であった Konica Pear であり、本作中には、ミノルタSR-1他名機が何台も"顔出し興行"をしてくるが、これは単にカメラマニアを喜ばす為のサービスカットです。
白黒写真は、赤灯下の暗室でないと、現像できないのですが、本作スタッフは
その知識がなく、2シーンとも非暗室での現像場面を本作に組み入れてしまったのは、写真家の映画としては失笑でした。
最近の戦場カメラマン映画なら「シビル・ウォー アメリカ最後の日」を観るとよいが、この作品も白黒フィルムの現像が良く理解できていない デジタル映像世代映画ではあります。
追記) 深瀬昌久さんにとっての"カラス"とは、写真と言う"宿命"です。
カメラマニアから見た視点 小道具の時代考証ミスだけが・・・惜しい・・・
映画も好きですが、それ以上に写真カメラが好きで、敬愛する深瀬昌久が題材の作品という事で期待して鑑賞しました。
構成、映像、演技いずれもしっかりとした文句のない作品で、カメラマンの生涯として重要な小道具の写真機も実際に深瀬がそれぞれの時代に持ってものだったのでよく調べているなと思いました。ただ1点だけの時代考証のミスを除いては・・・
冒頭に近い場面に主人公正久が結婚前のモデル洋子のポートレートを撮っていたシーン。時代は1960年後半~1970年代初めのはずです。撮影しているカメラは彼が当時使っていたミノルタSR-1で、よく調べてるなと思ったのですが、カメラストラップのミノルタのロゴマークが当時に存在していなかった1980年以降のものでした。時代的にありえない組み合わせで、少しカメラに詳しい人ならば誰でもわかるミスでした。
この一瞬だけならばよかったのですが、そのカメラが写るシーンが何度も何度も出てきましたし、おまけに映画ポスターにもわずかですが、そのロゴが写ってしまっています。なので冒頭のこのシーンがどうしても自分の中で引っかかってしまって、かなり映画のストーリーに没入できない自分がいました。
ご存じない方には全然問題ないシーンで、普通の映画なら私自身もご愛敬でOKなのですが、仮にも日本が誇る写真家の深瀬昌久を描いた作品です。これはしっかりしてほしかった。言い換えれば小道具はじめスタッフの中にはこのことを指摘する人がいなかったんだなあ、写真をやっている人がいなかったんだなあ・・と感じました。
その他には小西六パール、PENTAX SP オリンパスXAなどの名機が次々と出てきて見ごたえがありましたし、深瀬の有名な作品も沢山見れました。特にクレジットに出てきた作品は映画を圧倒するクオリティでしたし、鴉が舞うラストシーンと音楽は過去に見た作品の中でもかなり印象に残りました。他には文句をつけるところがない映画だったので、返す返すもあの設定は残念でした・・・
全64件中、1~20件目を表示